�S���X�[�b�Ɛ���n��u���o�̐S���w�v��ǂ��
���z�N����
�p��V��
�艿�V�W�O�~(�ŕʁj

�Q�O�P�S�N�U���Q�T���i���j
�����̃A�L���X�F�͉����H
���{�𒾖v������̂͊ȒP���I
| �w���{�𒾖v������̂͊ȒP���I�x�ƌ����ƁA�s�ސT�Ȃ��Ƃ������ȁI�Ƃ���������邩������Ȃ��B�������A����͎����ł���B �w��́A�ǂ�����Γ��{��ׂ��邩�H�x�ł���B �@���݁A���{�̌��q�͔��d���͑S����54��݂���B���̂��ׂĂ����A�ғ����~���Ă���B�ғ�����~���Ă��錴�q�͔��d���͈��S���Ǝv���邪�A���͔��� �傫�Ȋ댯�����͂��ł���B �@�����̓E�����R�����g���A�E�������q�j���j�����������ďo�鋐��ȔM�G�l���M�[�Ő��������A���C�Ń^�[�r�����A���d�@���d�C�ݏo���Ă���B ���C�Ń^�[�r�����A���d���邱�Ƃ͉Η͔��d�ƑS���ς�肪�Ȃ��B �Η͔��d���͔M���Ƃ��ĉ��ΔR���ł���ΒY�A�Ζ��A�V�R�K�X�Ȃǂ��{�C���[�ŔR�₵�ĔR�ĔM�ŏ��C��B���ΔR���͒n���̑��Âɉh�������A���̑�ʂ̎��[���ώ����A�Y�����f�ɂȂ������m�B ���ꂪ�R�₷�ƁA�_�f�ƌ������A���Ɠ�_���Y�f�ɕς��B���̍ۂɔM���o���B���̔M�𗘗p���Ă���B������R���̋������~�߂�A�R�Ă��X�g�b�v���ĉ��x��������A���d���͈��S�ɒ�~����B ����ɑ��A�����͂ǂ����H �Η͔��d���̃{�C���[�ɑ������镔�������q�F�ł���A�ƂĂ��Ȃ��������|�S���̗e��i�S�̌��݂�30cm�ȏ�j�̒��ɃE�����R���_�����\�{��������Ă���B �]�k�����A���̍|�S���̘F�S�͓��{���|���ƌ�����Ђ��Ɛ�I�ɑ����Ă���B���{���|���͐펞���͑�C�̖C�g���Ă�����ЂŁA�������|�S���̃��m��Z�p�ł͉E�ɏo����̂͂Ȃ��B�܂��ɑf���炵�����m�Â���̉�Ђł���B �{�_�ɖ߂�ƁA�E�����̓y���b�g��ɉ��H����A�W���R�j���E���ƌĂ������Ǔ��Ɏ��[����A���ꂪ�R���_�ƌĂ��B���̃E�����R���_����́A��ɒ����q���o�Ă���B���̒����q�����鐔�ɂȂ�Ɨׂ̃E�������q�����������ƂŁA�E�������q�j�����A�V���������q����яo���B���Ƃ��Ə����o�Ă��������q�̐����l�Y�~�Z���ɑ����A�h���h�����𑝂��B �@������̔��M�ʂɂȂ�����Ԃ��ՊE��ԂŁA����ȏ�ɂȂ�Ȃ��悤�ɐ��䂷��B����ɏ]���ăE�������q�͌��q�j�����v���g�j���E���₻�̑��̌��q�ɕς��B������w�j����x�ƌĂ�ł���B���̍ۂɁA�����킸���̏d���i���ʁj������B ���̌��������ʂ�����ȔM�G�l���M�[�ƂȂ�B���̍ہA��������G�l���M�[�̗ʂ� �A�C���V���^�C���̑��ΐ����_�Ŏ����ꂽ�B �@�@���M�ʁ��i���ʂ����������j�~�i�����j�̂Q�� �ƌ����ƂĂ��Ȃ��傫���M�ʂƂȂ�B �@�����́A�R�~�i�P�O�j�W��m/�b�@������A���̂Q��ɂȂ�̂ŁA�E�����̌��q�j����ł킸�����ʂ������Ă��A�������甭������G�l���M�[�͋���Ȃ��̂ɂȂ�B �@�R���_�̃E��������͏�ɂ���ʂ̒����q���o�Ă���B���̒����q�̐��𑝂₳�Ȃ���A�傫�ȔM���Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B���R����M���o�Ă��邾���ł���B �@���q�͔��d�����Ɏg��Ȃ��A���͎g���I�����A���͓_���̂��ߌ��q�F������o���ꂽ�R���_���A�����Ŗ������ꂽ�v�[���̒��ɒЂ��ĕۊǂ��Ă���B �@���ɒЂ��Ă����ƁA�����q�͐��ɋz�����ꂽ��A��яo�����x���x���Ȃ�̂ŁA���̔R���_�̃E�������q�����������₽�����͂��キ�Ȃ�A�j�����������N���Ȃ��B �@�����琅�����傫���͏㏸���Ȃ��B�E���������ƂȂ�����ԂŊǗ����ł���B �@�E�������q�͌��q�ʂ��Q�R�T�Ƃ����傫�Ȍ��q�ŁA�傫�Ȍ��q�͊�{�I�Ɍ��q�j���N���₷���B�E�����͂��̓T�^�ŁA���R�E�ɉ����Ă��A�E�����z��E�����z�ł͎��R�̏�ԂŊj�������킸�����X�ɕ��Ă���B���̍ۂɏo�����M�͂���͑傫�ȔM�ʂł͂Ȃ��B�����琅�ɐZ���āA���������z�����Ă����Α��v�ł���B �@�������A�ꂽ�сA���̔R���ۊǃv�[���̐����Ȃ��Ȃ�ƁA�E�����R���_������o����钆���q�����ڋ߂��̃E�������q��A�ׂ̔R���_�̃E�������q���������̂ŁA�����q�̐��������Ă䂫�A�M���Ȃ��Ă䂭�B �@��������A������₷�����Ȃ���A�h���h���M���オ�葱���A�R���_�̍ޗ��̗Z�_�ł���1700�x���A�R���_���n�������B �@�R���ۊǃv�[���͏㕔���I�[�v���ȍ\���ŁA���q�F�Ƃ����ƂĂ��Ȃ��������S�̘F�S�ƁA���̎��͂𐔂��̕������R���N���[�g�̌��q�F�̈͂����S���Ȃ���ԂŔR���_���n���o���i�����g�_�E�����N����j�Ɩc��ȕ��˔\����Ԃɕ��o�����B �@������ꌴ�q�͔��d���̑�4���@�����͈�Ԋ�Ȃ���Ԃ������B �@���f�����łP�A�Q�A�R�A�S���@�̌����͑傫���j�ꂽ���A4���@�͓����A����_���̂��߁A���q�F�i�F�S�j����R���_������āA�������̔R���ۊǃv�[���Ɉڂ��Ă����B �@���̃v�[�����n�k�␅�f�����łЂт�����A�����R��o�āA�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă�����A���k��т͍��Z�x�̕��˔\�����Œ����ԁA�l�͋߂Â��Ȃ��A�Z�߂Ȃ��ɂȂ�Ƃ��낾�����B�����A�����ł����Z�x�ɉ������ꂽ��������Ȃ��B �@�K���ɂ��A���̕ۊǃv�[���͒n�k�̗h��ɂ��ς��A���f�����̏Ռ��ɂ��ς��āA�����R��Ȃ������̂ŁA���낤���čň��̎��Ԃ͉���ł����B ����͑S���w�_�l�̂�����x�ƌ��������Ȃ��B �@�����A���̃v�[���ɑ傫�ȂЂт�����A�����R��o�āA����⋋���Ă��Ԃɍ���Ȃ��ƌ������ԂɂȂ��Ă�����A��̑ł��悤���Ȃ���ԂɂȂ��Ă����B ���Ƃ��ς��Ă��ꂽ�̂��I�B �@������w���{�̋Z�p�̗D�G����A���S���̍����x�ƌ����ɂ́A���ɕs�ސT�Ř����ȑԓx���Ǝv���B���������n�k�̗h�ꂪ�傫��������A���f�����̉e���������Ɛ[���� ����A�v�[���̐����Ȃ��Ȃ����\���͏\������B ���āA�{����w�����̃A�L���X�F�͉����x�����A����́A�w���{�𒾖v������̂͊ȒP���I�x�Ƃ����B ���{�ɂ�54��̌���������A�C���^�[�l�b�g�ł����ݒn���ڍׂɌ��J����Ă���B �@���{�Ɛ푈���鑊�荑�͔�s�@��R�͂Ȃǂ͕s�v���ƌ�����B��R�̌����̌����ɏƏ����߂āA���P�b�g�C��ł����߂A�����͐���s�\�Ɋׂ�B�����̃V�X�e��������Η�p���s�\�ɂȂ�B �@�����肱�킢�̂́A�㕔�����S�ɉ������Ă��錴�������̔R���ۊǃv�[���ɏƏ��Ăă~�T�C���U��������邱�ƁB �@�v�[���̐����Ȃ��Ȃ�A�����Ԍ�ɂ̓����g�_�E�����N���čL��ȓy�n�ɍ��Z�x�̕��˔\�i���ː������j���U���B �@�����ɂ͑�ʂ̔R���_�������Ă���B �P���100��KW�ȏ�̔��d�����錴�����������݂���B �@�S�r�A�g����10���n�����������A�����͂P��łP�O�O���n�́A�S�r�A�g����10�{�ȏ�̃G�l���M�[�ݏo���Ă���B �������������ȋ���Ȑݔ���54��������Ă��邱�Ƃ��ǂ��l����������H �@���Ƃ�d�͉�Ђ͌����̈��S���̍�����ɑi���āA�ĉғ��������������Ă���B�V�X�e���̈��S���́A�m���ɐl�m�ō��߂邱�Ƃ��ł���B �������R�X�g�̐�����̂ŁA���S�Ȉ��S�͂��蓾�Ȃ��B �@�������A�����A�V�X�e���̈��S���m�ۂł����Ƃ��Ă��A�e���U���ȂǁA�l�דI�ȍU���ɂ��炳�ꂽ�ꍇ�A���S�͂ǂ��S�ۂł���̂��낤���H �@���A�W�A�n��͉��ƂȂ������ȗl����悵�Ă����B �������i�h�́A���̖��ɂ��Ăǂ��l���Ă���̂��낤���H �w����Ȃ��Ƃ͎��̒m�������Ƃł͂Ȃ��I�x�ł͍ς܂���Ȃ��B |
�U���Q�R���i���j
�C�^���A�̌��@���푈������搂��Ă��܂��B
| �@���{�͈��{���t������ɏW�c�I���q���s�g�ƁA����ɍŋ߂͏W�c���S�ۏ�܂œ��݂����������āA���Ԃ𑛂����Ă��܂��B �@���{�����@ ��X���͐��E�Ɍւ�w�푈�����x�m�ɉ̂��グ���ق��̍��ɂ͂Ȃ����̂��ƍ��܂Ŏv���Ă��܂����B �@���܁A���@���߂��c�_�̓I�ɂȂ�A�V����e���r�����グ���Ă��܂��B �����ŁA�C�^���A�̌��@�ł��w�푈�����x��搂��Ă��邱�Ƃ����߂Ēm��܂����B ���̂��Ƃɂ��āA���������ڂ������ׂĂ݂܂����B �@��̑��A��Q�����E���Ŕs�퍑�ƂȂ����h�C�c��C�^���A�A���{�͑傫�ȋ]�����܂����B���ɓ��{�͐l�ގj�㏉�߂ĕ���Ƃ��ĂQ���̌��q���e�̓������A���ɔߎS�Ȕ�Q��ւ�܂����B����͔�l���I�ȕ���ŁA���̌�̐푈�ɑ���傫�ȑ������ɂȂ�܂����B �@�����āA���{�͏I���A���a���@�𐧒肵�A��X���ɖ��m�Ɂw�푈�����x��搂������܂����B �@���{�����@�@��X���̏́A �@1.���{�����́A���`�ƒ�������Ƃ��鍑�ە��a�𐽎��Ɋ��A�����̔������@�@��푈�ƁA���͂ɂ��Њd���͕��͂̍s�g�́A���ە��������������i�Ƃ��ā@�@�@�́A�i�v�ɂ�����������B �@2.�O���̖ړI��B���邽�߁A���C��R���̑��̐�͂́A�����ێ����Ȃ��B �@�@���̌�팠�́A�����F�߂Ȃ��B �@���̏́A�i���������A���ɖ������Ǝv���B �@���w�Z����ɋ�����ꂽ�ƋL�����Ă��邪�A���w�Z���w�N��������������Ȃ��B ���̏�f���ɓǂ߂A���{�l�Ȃ�A�w���͂ɂ��Њd���͕��͂̍s�g�́A���ە��������������i�Ƃ��ẮA�i�v�ɂ�����������B�x�ƌ��������͂ǂ��l���Ă��W�c�I���q����W�c���S�ۏ�̂��߂̕��͍s�g�͑�����Ȃ��B �@�C�^���A�ł͌��@�P�P���Łw�푈�����x���߂Ă������Ƃ����߂Ēm�����B ���̏����Ă݂悤�B �@�C�^���A�����@�@��11���i�푈�̐�������э��ە��a�̑��i�j �@�C�^���A�́A���l���̎��R�ɑ���U���̎�i�Ƃ��Ă̐푈�y�э��ە��������������i�Ƃ��Ă̐푈���������B ���ƊԂ̕��a�Ɛ��`��ۏႷ��̐��ɕK�v�Ȃ�A���̍��X�Ɠ����̏����̉��ŁA�匠�̐����ɓ��ӂ���B���̖ړI�������ۑg�D�𑣐i���x������B �������{�����@�ƃj���A���X���Ⴄ�悤�Ɏv�����A�푈������搂��Ă��邱�Ƃ͎������B �������A���̃C�^���A���{�͑����ɑ��A�l���I����╜���x���Ȃǂƌ������R�ŁA���@���߂��g�債�A�����ւ̔h�����J��Ԃ��Ă����B �@����ɂ��A���a��`�̗��O�͕ώ����A���ʂƂ��đ����̐�n�Ŏ�҂������]���ɂȂ��Đ펀���Ă���B�����҂͂���ɑ����ɂ̂ڂ�B �@���A���@���߂�ς��āA�W�c�I���q���̍s�g�̂��߂ɕ���g�p���ł���A�܂������n�ɏo��������Ƃ������ƂɂȂ�A���@��搂��Ă���w���͂ɂ��Њd���͕��͂̍s�g�́A���ە��������������i�Ƃ��ẮA�i�v�ɂ�����������B�x�Ƃ������ڂɔ�����s�ׂƌ�����B �@���ɍs���A�킢������Ό��@���������������B ���X�ƁA�w���ە������������邽�߂Ɍ�팠��F�߁A�����ʂ��Đ��E���a�Ɋ�^����x���炢�̕\���ɕς���Ȃ�A�܂�������₷���B �@���@�����̂܂܂ɂ��āA���͍s�g�ɎQ������̂́A������W�c�I���q����W�c���S�ۏ�Ƃ��������t�����Ă��F�߂��Ȃ��B �@�����āA���A�c�_����Ă���W�c�I���q���̍s�g��A�W�c���S�ۏ�̍s�ׂ��s���Ȃ�A�K�����q���ɐ펀�҂╉���҂��o��B���̏ꍇ�A�w�푈�����x��搂��Ă��錻���@���ŁA�s�K�ɂ��Đ��Ŏ����q���́w���̎��Ȃ̂��H�x�@�܂����w�펀�x�Ƃ͌����Ȃ��͂����B�w�푈�͂��Ȃ��x��搂��Ă���̂�����E�E�B �@�Q�R���̒����V�������g�b�v�ɁA�ŐV�̓��t�x�������f�ڂ���Ă���B���{���t�͍��܂ō����x�������L�[�v���Ă������A����̒����ɂ��ƁA43���i�O���49%�j�Ƒ傫���ቺ�����B���e������ƁA�W�c�I���q���̍s�g�e�F�ɂ��Ă͋c�_�s���ƌ����Ă���l��78%�ɏ��B�@�������S�����̂Ƃ��肾�Ǝv���B �@�悭�c�_��[�߁A���̏�ŁA�����@�ɕs������߂���e������Γ��X�ƍ����I�c�_�����āA��������Ȃ炷������B �@���t�̊t�c����ŁA�����������̍����ɂ�����邱�Ƃ����߂�ׂ����e�ł͂Ȃ��B �@���{����́A�Ȃ�����Ȃɋ}���ŏW�c�I���q���̍s�g�e�F���������̂��H �@����͈�߂ɂ��A���{����̐����M���Ƃ��āA�@�o�ς̗��Ē����A�A�W�c�I���q���s�g�e�F�������@�ƌ���2�̑傫�Ȗ���i�M���j�������Ă���ƌ����Ă���B���̓����������A���{����͖{�]�ƌ����H �@������̔w�i�́A�������ł���A�����J���琷��ɓ��{���W�c�I���q���̍s�g��A���A���S�ۏ��c�Ō��c���ꂽ�ꍇ�ɂ͏W�c���S�ۏ�ɎQ������悤�v������Ă��邩�炾�Ǝv���B �@���̓��e�͑����Ƃ̌����i�O���Č��j������\�ʂɂ͏o���Ȃ����Ƃł���B �ꗬ�V�����e���r�ł������Ă����������Ƃ͌���Ȃ��B �@�v�͈��{����͎�������肽�����ƂƁA�������A�����J����̗v���̓���d�Ȃ��āA�e���V�������オ���Ă���Ƃ������Ƃ��Ɖ��߂��Ă���B �@�������A���߂ĕ����������Ƃ́A�C�^���A���w�푈�����x�����@�ŋK�肵�Ă���Ƃ��������ł���B �@�ŋ߁A�ǂ������E�͕s����ȕ����ɓ˂��i��ł���悤�Ɋ�����B ��펞��́A�A�����J�ƃ\���B�G�g�A�M�̓��卑�����������A�wBalance of terror�x�ƌĂꂽ���������������B �@���q���e�␅�f���e�ۗ̕L���������A�嗤�Ԓe���eICBM��n���i�[�ɂɉB���āA�݂��ɑΛ����������B���̊j�푈�̋��|�̃o�����X�̏�ɁA���Ƃ��������ێ�����Ă������ゾ�����B ���̌�A�\�A�����A���V�A�ɂȂ��āA�A�����J�����E�̌x�@�ƌ����鎞��ɂȂ����B�����āA���F�g�i���푈�A�p�ݐ푈�A�A�t�K���푈�Ƒ������A���F�g�i���푈�̍����푈�̎d�����傫���ς���Ă����B ���ʐ��Đ키�Ƃ�����p����A�Q�����킪��̂ɂȂ��Ă����B����ɉ����Ė��O�����m���敪�����Ȃ��Ƃ����Q������͕��m�ɂƂ��Ă͔��ɐ��_�I�ɔ���B �����Ȃ̂��A�G�Ȃ̂�����ʂł��Ȃ��B������딚��E�C���J��Ԃ����B ��������Ζ��O�͂܂��܂����g���āA��������B �ŋ߂͂���������p�̕ω��ɉ����A�@���̏@�h�Ԃ̐킢���ڗ����Ă����B���ɃC�X�������͏@�h�Ԃ̑����ŁA�C�X�������k���m���E�C���J��Ԃ��Ă���B ���݂��ɉƂ��Ă������A�����j���A���܂ŋC�Â��Ă�����Y������j�Ă���B�����������Ӗ��Ȑ킢�������𒆐S�ɑ����Ă���B �@�����ҊԂɂ́A�키���߂̑�`������̂��낤���A���E���a��l�ވ��ƌ��������ōl����ƁA�����ɐ푈����Ƃ�����`�͌����Ȃ��B �ނȂ����E�C�������J��Ԃ���邾���ł���B �@�����������ɓ��{����э������Ƃ��Ă���B ��U�A���Ԃɓ���ƁA���肩��͓G�Ƃ݂Ȃ����B���{�͕��a�ȍ����������A���肩��G���Ƃ݂Ȃ����A���{�̊e�n�Ŕ��j��e���U�����N���Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��B �����������Ђ��o�債�āA�W�c�I���q���̍s�g��A�W�c���S�ۏ�ւ̎Q�������ӂ��Ă���̂��낤���B �@�ƂĂ������͎v���Ȃ��I�I |
�U���Q�P���i�y�j
�W�c�I���q���ƏW�c���S�ۏ�͉����Ⴄ�̂��H
| ��ςȂ��Ƃ��N�������ȗ\��������B�U���P�T���ɂ����������A���{�����͐���͂� ���@��ς��邱�ƂȂ��A���@�̉��߂�ς��邱�ƂŁA�I���A����Ă������@�X���̍l������ ��C�ɕς��悤�Ƃ��Ă���B����Ɍ����}���Ƃ������邩�ǂ����H�@�ǂ��� �낤���Ȃ��Ă��Ă���B ���@��ς��āA���̃X�^���X����j��ς��邱�Ƃ͔��ł͂Ȃ��B�������A���@�ƌ������̍����̍l���������߂̕ύX�ŁA�s����ς��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�A�����N���邩�����ɂ͕�����Ȃ��B���̐����̎v���܂܂ƂȂ�B �W�c�I���q�����A�W�c���S�ۏ����肽����A�܂����s���@��ς��邱�Ƃɒ��肵�č����̐M��₤���Ƃ���n�߂�ׂ����B�������t�ɂȂ��Ă��܂���B���{����B �ʓ|�Ȃ��Ƃ͌�ɂ��āA�Ƃɂ�������悤�ɂ������Ƃ����v�f�����������Ă���B �����V�������ɂ��ƁA �W�c�I���q���Ƃ́A���ڂȊW�ɂ��鑼�����U�����ꂽ�ꍇ�A�Ƃ��ɔ������錠���B���܂ł̓��t�́A���{�͏W�c�I���q���͎����Ă��邪�A�s�g�͌��@�㋖����Ȃ��Ƃ������߂ɂȂ��Ă����B �W�c���S�ۏ��Ƃ́A�N���Ȃǂ��������ɁA���A�����������A���S�ۏ�ψ���c�Ɋ�Â������ЌR�Ȃǂ��������A���ق������邱�ƁB ���̍����ɂ�����邱�Ƃ�ّ��ɁA����̉�����Ƀo�^�o�^�̏�ԂŌ��߂�̂́A�܂������ǎ�������Ƃ͌����Ȃ��B |
6��15���i���j
���{�����A�����ّ��ł͂���܂��H
| ������������Ȃ��Ă��܂��B������^�}�Ɩ�}�̑Η��ł͂Ȃ��A�^�}���̎����}�� �����}�����X���~���Ă���悤�ł��B�ۑ�͈��{�������ϔN�̎v���ł���W�c�I���q���s�g�̗e�F��������̉�����Ɋt�c���肵�����Ƃ��������v���ł��B ���̑P���͂��낢��Ȕw�i�⍑�ێ������܂��̂ŁA��T�ɗǂ������͌����Ȃ��Ǝv���܂��B�T�d�ɔ��f���Ȃ���Ȃ�Ȃ��d�v�Ȃ��Ƃł��B ����E���i�����m�푈�j���I�����A���E�����a�ɂȂ�܂����B���̎���߂�ꂽ���{�����@�͑�9���ŁA���E�Ɍւ�푈������搂������܂����B���a���畽���ɂȂ肷�ł�26�N�A�I���70�N�ɂȂ낤�Ƃ��Ă��܂��B ���̊ԁA�x�g�i���푈�A�C�����C���N�푈�A�A�t�K�j�X�^���̓���ȂǁA�A�����J��[���b�p�����͑����̏o�����ɑ��ĕ��m�𑗂�A����l���̎�҂̖����]���ɂ��Ă��܂����B���̖��̏�Ɍ��݂̐��E�̕��a���ۂ���Ă��邩�ƌ����ƁA�K�����������ł͂Ȃ��悤�ȋC�����܂��B�卑�̍��v�f�����푈�������Ă���悤�ȋC�����܂��B���̂��Ƃ̐���͂��Ă����A�W�c�I���q���̍s�g��e�F����Ƃ���������ɂ������e���t�c���肵�A�s�g���ł��鏀�����������Ƃ������Ƃł��B �@ �@���{�̌��@�͕��a���@�Ő��E�Ɍւ����̂ł����B�������A�ŋ߁A�����̌o�ϐ�����؍���k���N�̓��������Ă���ƁA�����P�ɂ킪�������a���@�̂��ƂŁA��������Ă���o���͂��Ȃ��Ƃ������Ƃł��Ƃ��ς܂Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���悤�ɂ��v���܂��B �������������q�ɂȂ��āA�����Ă��䖝�ł���Ƃ������Ƃ͗��h��������܂��A �l�ƍ��Ƃ͗��ꂪ�Ⴂ�܂��B �@����������̒��ŁA���{�����͔O��̏W�c�I���q���̍s�g�e�F��i�߂����Ƃ��������ӎu���\������A�����}�ɍU�ߊ���Ă���Ƃ����p�������܂��B ���a��`��W�Ԃ��Ă�������}��������ԁA�ǂ�����������Ƃ邩��ϋ���������܂��B�����œO�ꂵ�Ĕ�����ΘA���^�}��E���邱�Ƃ��Ӗ����܂��B�ǂ��������}�͕�����ɂ������߂ŁA���{�����̏W�c�I���q�̍s�g�e�F�����ݍ��ނ悤�ł��B �v�͐����^�}����������蒅���A�^�}�̂��܂����Ɋ���Ă��܂����̂ł��傤�B �@���̌��@�͂��̍��̊�{�̍l�����𖾕����������̂ł��B ����͖��Ԋ�Ɓi��Ёj�ł́A�А���o�c���O��o�c��{���j�Ƃ������̂ŁA��Ђ��Ƃɂ��̐ݗ��̎�|���܂Ƃߏグ�����̂ł��B ���̌o�c���O��ς���ɂ́A��Ђ̑�����₤�d�v�ȈӋ`������܂��B �����K�V������́A�o�c���O�ɔ�����Ȃ�A��Ђ�ׂ��Ă��悢�Ƃ܂Ō����܂����B �����d��̌o�c���O�͍j�̂Ƃ��Ē�߂��Ă��܂��B ���̏ꍇ�͌��@�ŁA����9���ɐ푈������搂��Ă���̂ł��B �W�c�I���q���̍s�g������A�����������荑�ɂ���Ă��鎞�͏����邱�ƂɂȂ�܂��B����̐���͕ʂƂ��āA�푈�͕����ł͂���܂���A�l�Ɛl�̎E�������ł��B�݂��Ɏ��������̌������i���`�j�������Đ킢�܂��B ���ꂪ�̓y���ł�������A�@����̎v�z�M���ł�������A�����Ԃ̑����ł������肵�܂��B ����͂���Ƃ��āA�킢�̏�ɏo�����āA�킢�ɉ��S����Ƃ������Ƃ́A�K���펀�҂��o�܂��B�A�����J�͑����̂��߂ɐ���l�̎�҂������Ȃ��Ă���̂ł��B ���{�̎��q���͍K�����܂Ŏ��̂ŖS���Ȃ������͕ʂƂ��āA�푈�Ő���Ď��Ƃ������Ƃ͑���ȍ~����܂���B �������A���̏W�c�I���q���̍s�g�����邱�Ƃ͐��ɏo�����邱�Ƃł�����A�K�����҂��o�܂��B���q�����͍��܂ł̗���ƑS����������̂ɂȂ�܂��B �l�̖���������ɂ͂���Ȃ�̑�`�������Ȃ���Ȃ�܂���B ����͍��̕��j�Ƃ��ċK�肵�Ă��錛�@��������Ɛ������āA���{�͂��������ꍇ�͂����키�A���������푈�͂��Ȃ��Ɩ��m�ɂ���ׂ��ł��B���̏�Ő��ɏo������K�R��������A����͓��{�̈АM�Ɩ��_�ɂ����Đ키���Ƃ��K�v�ł��傤�B ���̋c�_�́A���@9���ŋK�肵�Ă���푈�������Ȃ�������ɂ��A���߂�ς��ēs���̂����悤�ɑΉ��ł���悤�ɂ���Ƃ������Ƃł��B ����͑�ϊ댯�ł��B�Ƒ��Ȃ����ł��B ���X���X�ƍ����S�̂ŋc�_���āA���@��ς���Ȃ炱���ς���Ƃ������ӂ����ĉ�����������Ǝv���܂��B ���a���@�����̂܂܂ɂ��āA���߂�ς��ēG�ƌ������Ƃ����̂͊�Ȃ��Ďd���Ȃ��v���܂��B����̎g�p�͐��������A���������ꍇ�͕�����g���Ă������Ȃǂƌ����������K��͈Ӗ�������܂���B�����ł��܂���B �Ȃ��Ȃ���͎E�������̏ꂾ����ł��B�����ɕ����̗����͂���܂���B���������邩�A������E���Ȃ��Ǝ������E������Ȃ̂ł��B ���̋c�_���Ă���Ɗ���_�ŁA���ꂢ���Ƃł��B �����������炢�搶���͐��ɍs���Ȃ��̂ŁA�����̓s���̂����c�_����������̂ł����A���ꂪ��x���܂�A����̎��q�����͖��������邱�ƂɂȂ�܂��B �{���ɍ��܂ł̕��j�ƈႤ���ɓ��ݍ��ފ댯�Ɨׂ荇�킹��s�ׂ������̑��_�Ƃ��ċc�_���Ȃ��Ō��߂Ă������̂ł��傤���H ���e�̎^�ۂ͂Ƃ������Ƃ��āA�i�ߕ��ɋ������Ƙ�����������ł���悤�Ɏv���܂��B�����}�͂����ƌ����ɂȂ�ׂ��ł��傤�B �����獡�A����ň������đ命���������Ă���Ƃ͂����A����w�i�ɂ��������Ȑi�ߕ��͎^�����ł��܂���B ��}�̖���}�͍��������Ă���̂��A�S�������܂���B���̑���}���悭������܂���B ���{���W�c�I���q���̍s�g�e�F�A���@��������肽���̂Ȃ�A�������肻�������菇�߂����̂ł��B�������̂��Ƃɂ��Ĕ����Ă���킯�ł͂���܂���B ���ȍ����I�c�_�͔����āA�ّ��Ɏ���i�߂悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃɔ����Ă���̂ł��B |
3��30���i���j
�������ȗ\�Z���s�m���}�H
| �@3��26���������Ǝv���܂����A�����V���ɂ������ȋL�����f�ڂ���Ă��܂�����B �w�\�Z���s�A�ٗ�̃m���}�v�Ƃ����^�C�g���ł��B ����́w�㔼��6���A�������Ƒ��ߌi�C��ƂȂ��Ă��܂��B �@�ȉ��A�{�����Љ�܂��B �@���{��20���ɐ�������2014�N�x�����\�Z�̎��Ƃ𑬂��i�߂邽�߁u9�����܂ł�6���ȏ�̌_����I����v�Ȃǂ̗\�Z���s�̖ڕW��݂���B���z�ł́A6�����܂ł�4���ȏ���g�����Ƃ�ڕW�ɂ���B���N�x��\�Z�ƕ����đO�|���ŗ\�Z���g���A4���̏���ő��Ō�̌i�C�̗������݂������_�����B�����ɂ����\����B �@���l�ڕW�̑ΏۂƂȂ�̂́A�V�N�x�\�Z���z�̑��z95��9�牭�~�̂����A�������Ƃ𒆐S�Ƃ�����12���~�B�����̂�e�Ȓ��̊����ʂ������Ƃ��ڕW�ɉ����āA�����܂łɌ_����I������A�⏕���̎x���������߂��肳����B �@��N����1���قǑ����X�s�[�h�ŗ\�Z���g����Ƃ����B���ƌ������ɐl����A�����ی��A�����̂ɔz��n����t�łȂǂ͖ڕW�̑ΏۊO�ɂ���B �@���{�����͍��N4���ɏ���ł�8���Ɉ����グ�邱�Ƃ����߂����A15�N10���ɗ\�肵�Ă���P�O���ւ̍đ��ł́A���N4���`9���̌i�C�̏����ɂ߂Ĕ��f���邱�Ƃɂ��Ă���B2���ɐ����������N�x��\�Z���A���z5��5�牭�~�̌o�ϑ���̂�����3��4�牭�~���ɂ��āA6�����܂ł�7���ȏ�A9�����܂ł�9���̌_��Ȃǂ��I����ڕW���߂Ă���B �@���Ō�̌i�C���x���邽�߁A���{�͍��N�x���14�N�x�����\�Z���킹�Ė�7���~�̌������Ɨ\�Z���������A���ƊE�̐l��s����w�i�ɁA���Ƃ̒S���肪���܂�Ȃ��u���D�s���v���S���ő������ł���B�������Ƃ���ƁA���Ō�̌i�C������Ȃ邽�߁A�����\�Z�ł͈ٗ�̐��l�ڕW�����邱�Ƃɂ����B �Ƃ����L���ɂȂ��Ă���B �@���̐ŋ����i�C��̂��߁A�������Ƃɂ���Ԃ���Ԏg���Đi�߂悤�Ƃ��Ă��邪�A����ɂ����̎M�����܂Ō��ƊE�̓������i���Ă������߁A����ł��Ȃ��قnj��ƊE���ׂ��Ă���悤���B���z�̐������ł��Ȃ��Ȃ��Ă���B �@���̎؋���100���~�ɂȂ낤�Ƃ��Ă��邳�Ȃ��ɁA����ɂ���Ԃ���ԂƋ������āA����������g���I�Ƃ����v���܂ł��Či�C�Ȃ���Ȃ�Ȃ��͉̂����Ԉ���Ă���悤�Ɏv���B �@ �@����������������̂Ȃ�A�����Ƒ��ɗL���Ȏg����������͂��B ���Ƃ��A���q�p���[�������ƈ����o���āA�Љ�v���ɖ𗧂Ă悤�Ƃ����ڕW������B����ł͘J���������������Ă��܂������ƂƁA�����ɕK�v�ȋ��������邱�ƁA�܂����q�̘J���ӗ~�E�Љ�v���ӗ~�Ȃǂ����܂�A�O�����ȏ��q�����������ƂȂǂŁA���q�̘J���ӗ~�͍��܂��Ă���B �@����A���q�͎q��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ɂ���l����R����B���������l�ɑ��A�ۈ�{�݂���S���ėa������c���a����A�����a����{�݂̌��݁A�ۈ�v���̊m�ۂȂǂɎv���������������A��C�ɑҋ@�c���E��������������悤�ɂ���A�ۈ牀��{�݂̌��݂Ȃǂɗ\�Z�̎��s���L���ɂł���B �@�������A���̌��Ԃ�ɏ��q�̘J���p���[������I�ɍ��܂�A���Y�����オ��A�Ŏ�����������B �@���̂悤�ȃ`�}�`�}�����\�Z�łȂ��A��C�ɍ���10�{�Ƃ����悤�ȗ\�Z�̎��s���K�v���Ǝv���B �@���H���݂́A�k�C���ň���ɐ��䂵���ʂ�Ȃ��悤�ȍ������H�����݂���Ƃ����S�����ʂȌ��������͍���A����Ă͂Ȃ�Ȃ��B �@�����}�̋c���͓��������l�������̂�����A�����̌��v�ɍ��E���ꂸ�ɁA�����ƍ����ɓ������ׂ������l���Ăق������̂��B |
3��18���i�j
�r�s�`�o�זE�ő����ł��܂��ˁI
| �@���̂Ƃ���A���A�V����e���r�̃j���[�X�ŁA�r�s�`�o�זE�̂��Ƃ���Ă��܂��B ���ꂾ���A�傫�����グ��ꂽ�g�b�v�j���[�X����������A���̌������ʂ̍����������ƁA���҂◎�_���傫���͓̂�����O�ł��B �@����������ȏ�ɁA�����҂Ƃ��Ă̗ϗ��ς̂悤�Ȉ�ԑ�ȋ��菊�����ꂽ���Ƃɑ��鉽�Ƃ������Ȃ����E�ȁA�Ȋ����͏��������ł��傩�H �܂����̂������N�����̂ł��傤���H�@�܂��A�͂����肵����Ԃł͂Ȃ��悤�ł����E�E�E�B �@�ǔF���������čČ��ł���ĂыP���������ʂɂȂ���Ǝv���܂����A�{���Ɉ�x�͐����������̂łȂ���A�Č��͂ł��܂���B �@�g�����W�X�^�������V���b�N���[���m��3���́A�����̗��_������ɉ𖾂���Ă������A�������J��Ԃ��ăg�����W�X�^��p�i�d���̑������ہj�����܂����B�������A�����͕s�Ǖi����ŁA�Ȃ��Ȃ�����ɗǕi�邱�Ƃ��ł��Ȃ������Ƃ������Ƃł��B����ł��A���_����������A�������J��Ԃ����ƂŁA����Ɉ��肵�ăg�����W�X�^�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B���_���Z�p�Ɉڂ�u�Ԃ�������܂���B �@�������A�Ȋw�̗��_���������Ƃ�����O�Ȃ���A������������J��Ԃ��Ă��A���ʂ͓����Ȃ��Ǝv���܂��B �@�����A���ە������ۂɂr�s�`�o�זE�̐���Ɉ�x�͐������Ă����̂Ȃ�A�Č������ɂ����čČ����邱�Ƃ��ł���͂��ŁA���������Ƃ��ؖ�����܂��B �@�܂������������҂������āA���̃j���[�X����X���ڂ��Ă��܂��B �@�����ł����Ăق����Ƃ����C�����ň�t�ł��B |
3��16��(���j
�Ȃ��A���{��Ƃ͕������̂��H�@
���̗v����m��ċN�ł��邩��
| �����i�ɑ��鋭���v���Ƃ́A �@�u���{��Ƃ͋Z�p������̂ɂȂ����ĂȂ��̂��v�Ƃ悭�����邪�A���̖₢�̓s���g������Ă���B�ЂƂ̏��i�𐢂ɑ���o���Ƃ��ɂ́A�Z�p����ʂ�̑O�ɁA���i�̃R���Z�v�g�����݂��܂��B����́A�u����ȕ֗��ȋ@�\����������������V���i���J�����悤�v�Ƃ����v����������A�u���ꂪ����ΐ������y�����Ȃ�v�Ƃ������������肵�܂��B �@�Z�p�͂��̎v�����������邽�߂̎�i�Ƃ��đ�Ȃ̂ł����āA���[�U���S���Ȃ��A���ł��炦�Ȃ��Z�p���������s���Ă��A���̏��i�͎Љ�ɍL��������A�����킯�ł͂���܂���B��������A�w���[�U���l�������Ȃ������A����ǂ��A���ڂ낰�Ȃ��炠�����炢���Ȃ��I�x�Ǝv�����̂��\�z���A���i�����Ă����p������Ȃ̂ł��B �@�������������ߒ��ŁA�������Ђɕs������Z�p���������瑼�Ђƒ�g������A�D�G�ȃG���W�j�A���W�߂��肷��Ȃǂ��āA�����₤����͂�����ł�����܂��B �u���̏��i�Ő��̒���ς������v�Ƃ����ŏ��́w�M���v���x���Ȃ���Ή����n�܂�܂���B �����̓��{��ƂɌ����Ă���̂́A���́w�M���v���x�B����������u���i�ɑ��鈤��v�̋����ł��B �@���������ƋP���Ă����Ђɂ́A�K���u���i�ւ̔M���v���E����v���g�D�Ɉ��Ă��܂��B����́A�o�c�g�b�v�ɂ��������Ƃ������܂��B�o�c�g�b�v���A���i�ɑ��Ăǂꂾ���[���w�M���v���E����x�������Ă��邩�ł��B�@�w����x�Ƃ́w�[���S�x�ƌ����邩������܂���B �@���Ƃ��A�A�b�v�����X�e�B�[�u�E�W���u�Y�́A�u�݂�ȁAiPod�������̂��߂ɍ�����B �����̂��߁A���邢�͎����̗F������Ƒ��̂��߂ɓw�͂���Ȃ�K�������܂����肵�Ȃ��v�Ǝ��g�̓`�L�i�E�H���^�[�E�A�C�U�b�N�\�����A�u�k�Ёj�ŏq�ׂĂ��܂��B �@ �@�������~�������̂肽���̂�����A���ꂪ�ł���܂őË��͂��Ȃ��Ƃ����ԓx���т��B iPod��SONY��Panasonic����s���Ĕ̔����Ă����|�[�^�u�����y�v���[�����A�㔭�ł���Ȃ��猩���ɋt�]���đ听�����A���E���ŃI�o�P���i�ɐ��������B �@�A�b�v�����|�[�^�u�����y�v���[���́uiPod�v�����i��������ɁA���C�o���̃}�C�N���\�t�g���R���i�u�Y�[���v�����܂������A�Y�[���̔̔��͒�������܂܁A����iPod�̉����������ɂ͎���܂���ł����B�A�b�v�����}�C�N���\�t�g�ɏ������̂͋Z�p�̗D��ł͂���܂���B�u�Z�p�ɂ��Ă͓����悤�Ȃ��̂ł����A�������i�����낤�Ƃ����v���ɑ傫�ȍ����������Ƃ������Ƃł��B���ꂪ����I�������v�ƃW���u�Y����͌����Ă��܂��B �@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E �@���l�̂��ƂŁA�����̑̌����v���N�����ƁA�����Ԃ�̘b�ɂȂ�܂����ASONY���E�H�[�N�}�������܂����B�����Ƃ��Ă͒����^�E���^�ŁA�d�r�œ��삷�����I�ȏ��i�ł����B �܂��ɔ�Ԃ悤�ɔ���܂����B�J�Z�b�g�e�[�v�̑傫���ɂ܂Ƃ߂�ꂽ���̏��i�͎��ɍ��܂ł̃J�Z�b�g�e�[�v�f�b�L�̊T�O��ł��j���Ă��܂����B �@���̏��i�ɂ͑�_�Ȋ���肪�s���Ă��܂����B����̓J�Z�b�g�e�[�v�ɘ^������@�\���Ȃ��āA�Đ��@�\�����Ƃ������ł����B �@�w���������āA���y��������x�Ƃ����R���Z�v�g�ɓ����������i�ł����B�^���@�\���Ȃ������߁A���J�j�Y���͔����ȗ����ł��A�e�[�v���s���\��������x�����邱�Ƃ��ł��A���J�j�Y���̐v���y�ɂȂ�܂��B�������A�J�Z�b�g�e�[�v�̑傫���Ƀ��J�j�Y����[�߂邱�Ƃ͑S���]���Ȃ��������z�̓]���������̂ł����B �@ �@�����A�J�Z�b�g�f�b�L�s���SONY��Panasonic��2�����Ă��܂������A�E�H�[�N�}�����o�����ƂŁA�����Ƃ����Ԃ�SONY���傫�ȃV�F�A�����܂����B����ɑΉ�����Panasonic�A�^���@���ƕ��̎��ƕ����͖�N�ɂȂ�A�w�����E�H�[�N�}���R���i���o���I�x�Ƃ������j���J���w�ɂ����܂����B�����ŏo�Ă������i���A�ʏ́w�q�f�b�L�x�ƎГ��œǂ��̂ł����B�J�Z�b�g���J�j�Y���͂����v���Đ����ł���悤�ȊȒP�Ȃ��̂ł͂���܂���B �@�E�H�[�N�}���͑����A�S���V�������z�ŃJ�Z�b�g���J�̐v�����A�\���i�����������Đ����������̂������Ǝv���܂��B��ϗǂ��ł������i�ł����B�G�Ȃ��炠���ς�I�Ǝv���܂����B ����APanasonic�́w�q�f�b�L�x�́A�J�Z�b�g�f�b�L�Ɏg�����ʂ̃��J�j�Y�������̂܂����Ȕ��ɓ��ꂽ�����̏��i�ŁA���A�v���ƑS���E�H�[�N�}���Ƃ͏��i�R���Z�v�g���Ⴄ���̂ŁA�E�H�[�N�}���̑R���i�Ƃ͉��������̂ł����B�q�f�b�L�͎����������Ƃ��ł��Ȃ��i���ł����B �@ �@�����A�����̓X�e���I���ƕ��ŏ��i�������Ă����W�ŁA���̎��قǏ��i�Â���ŁA�w�R���Z�v�g���厖���ȁI�x�Ƃ������Ƃ��v���m�炳�ꂽ���Ƃ͂���܂���ł����B �@���̌�A�Г��Ŗ{�i�I�ȃE�H�[�N�}���R���i���ł��A�����SONY�ɒǂ������Ƃ��ł��܂������A���̃W�������́w�E�H�[�N�}���x�Ƃ����l�[�~���O���蒅���Ă��܂��܂����B �@�����d��͈ȑO�A�w�}�l���d��x�ƌ���ꂽ���オ����܂����B�������A����ł����i�͏�ɏ�ʂ̃V�F�A���Ƃ�A����グ��NO1�Ƃ������̂���������A���v���\���o�Ă��܂����B�}�l���d�펞��̕����ނ���ǂ������̂ł��B �@���[�U(����ҁj������Ă������́A���ł�����������̂邱�Ƃ����[�J�̎g���ł��̂ŁA����Ă�����̂�^���č���āA��ʔ̔����邱�Ƃ��ł��鎞��ł����B����������ƁA�w���m�s���̎���x�������̂ł��B �@���݂͋t�Ɂw���m�]��̎���x�ł��B���[�U���~�������̂���Ȃ��ƌ�����������܂���B���[�U���~�������̂����i�R���Z�v�g�Ƃ��Ă܂Ƃ߂����A�����O�ꂵ�Ė����グ���Ƃ����Ȃ��ƁA�q�b�g���i�ɂ͂Ȃ�܂���B �@�ŋ߁A�A�b�v����iPod�AiPad�A,iPhone�Ɨ��đ����ɃI�o�P���i��A�����Ă��܂����A����͓V�˂������X�e�B�[�u�E�W���u�Y����������ł��B�ނ͎c�O�Ȃ��Ƃɂ��̐�������܂����B �@ �@������ATechnics�Ƃ����u�����h�������d��ɂ���܂����B���́A�Ɉꕔ�̏��i�ɂ����g���Ă��Ȃ��Ǝv���܂����A10���N�O�܂ł͐��E����Hi-Fi�I�[�f�B�I���i�̃u�����h�Ƃ��Ċ�����Ĉꐢ���r�������������܂����B �@����Technics���\���鏤�i�́A���X�̖��@�ƌ�������̂�����܂����A���Ƀ^�[���e�[�u���ŁA�A�i���O���R�[�h�����t����ۂɎg���v���[���ł��B����͏]���A�^�[���e�[�u���ƌ������[�^�Ɍ𗬃C���_�N�V�������[�^�[�i�U���d���@�j���g���A�x���g�ʼn�]���𗎂Ƃ���33��]��LP���R�[�h�ɍ��킹�Ă��܂����B���̃��[�^�͉�]���̕ϓ����傫���A�x���g�̓S���łł��Ă��܂����̂ŁA�g���Ă�����ɐL�т܂��B���̃��[�^���^�[���e�[�u���̎��ɒ������āA�d�q��H�Ő��䂵���_�C���N�g�E�h���C�u���[�^���J�����A����𐢊E���œ��ڂ����v���[�������܂����B���ꂪ���ɃZ���Z�[�V���i���ȏo�����ő傢�Ƀu�����h���l�����߂܂����B���̌�A���X�Ƃ��̋Z�p���g���V���i���o���A�R�X�g�_�E�����āATechnics�@SL-1200�V���[�Y�͉���20�N�ɂ킽�鏤�i�Ƃ��āA�����O�����܂��܂����B �����A�b�����܂������A���[�U�Ɋ��鏤�i�͂��̎���ł��A���܂Ōo���Ă��O�����邱�Ƃ��Ȃ��g���܂��B�t�ɂ����łȂ����i�͈ꎞ����Ă��A�����ԉɏI���܂��B �@�ŋ߂̃f�W�^�����i����{�p���͓������Ƃł����A���̈ڂ�ς��̌������͈ȑO�ɔ�ׂ�ƁA�����̊��������܂��B����Ɍo�c�҂③��肪�ǂ��Ή��ł��邩�H�ł��B �@������x�A�b�����ɖ߂��܂��B �@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E ���Ă̓��{��Ƃł́A���i�ւ̈�����ӂ�Ă��܂����B �@�z���_�̌��G���W�j�A�ł��鏬�юO�Y������A�w�z���_�@�C�m�x�[�V�����̐_���x�i���oBP�Ёj�̒��ŁA���̂悤�ȃG�s�\�[�h���I���Ă��܂��B�Ⴂ����A�Z�p�Ҍ��C�������āA���N��̒���7�`8�l�ƃO���[�v�Řb�����������邱�ƂɂȂ�A���̂Ƃ��A��i����^����ꂽ�e�[�}���Ȃ�Ɓu���Ƃ͉����v�Ƃ������̂����������ł��B�Ȃ�Ŏ����ԂÂ���Ɍg���l���A���ɂ��Ęb������Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂��A�ŏ��͊F�A�킯���킩��Ȃ��Ƃ�����������������ł��B�c�_�ɉ������̂́A�N�����u���ԁv�Ƃ������t���v�������Ƃ��������ł��B ���ȁA�����A������......�B���ꂾ���łȂ��J������M�^�[�����@�ƌ��������������܂��B �ł��①�ɂ͈��ɂƂ͌���Ȃ��B�������i�ł��w���x�����Ă҂����肭�郂�m�Ƃ��Ȃ����m������Ƃ������Ƃ����������ƁB���̏ꍇ���w���x�Ƃ́A�g���l�̐[���v���ł��B ���Ƃ��A�①�ɂ͗�₷�Ƃ����@�\�����A���i�Ƃ��ė��h�ɖ�ڂ��ʂ��������Ƃ� �Ȃ�܂����A�����Ԃ͓����Ώ\���Ƃ����킯�ł͂���܂���B �G���W���̃T�E���h��������A�����̐S�n�悳��������A�C���e���A�̎�����������A���l�� �S��܊���h���Ԃ�悤�ȏ�I�ȉ��l���������āA���߂āu�����N���}�v���Ƃ����܂��B �����������Ƃ��A�Ⴂ�G���W�j�A�����͂��̌��C�Ŋw�ƁA���т���͏����Ă��܂��B�}���������z���_�Ƃ������[�J�͎ԑ���Łu���v�̑�������o�����̂ł��B���ꂪ�w�z���_�h���[���x���Ǝv���܂��B �@���́A�ȑO�̓��{�̃G���N�g���j�N�X��Ƃɂ́u���i�ւ̈���v�����Ă��܂����B�����������ƁA�\�j�[�E�R���s���[�^�G���^�e�C�������g�iSCE�j�̋v��ǖ،�����ł��B�u�v���C�X�e�[�V�����v�Ƃ�������I�ȃQ�[���@������A�����̃\�t�g��摜�̔������A���I���Łu�Q�[���͎q�ǂ��̂�������v�Ƃ�������܂ł̊T�O��ς��Ă��܂��܂����B �W���u�Y����Ƃ����ʂ��邱�Ƃł����A���i�ւ̈������O��ɋ����l�͂���䂦�ɂ��܂��܂ȃG�s�\�[�h���c�����̂ł��B����Ƃ��A���i�̕s��������N����܂������A�N���[��������l�����ɑ��ċv��ǖ���́A�u�d�l�ɍ��킹�Ă��炤�����Ȃ��B�L���Ȍ��z�Ƃ������������Ƀh�A�̈ʒu�����������ƕ��������l�͂��Ȃ��B����Ɠ������Ƃ��v�ƌ����������Ƃ����܂��B����ԈႦ��A�ڋq�y���̖\���Ǝ~�߂�ꂩ�˂Ȃ����t�ł����A����̐��i�ɑ���[���v�����ꂪ�Ïk����Ă���Z���t�ł��B�����܂Ŏ��А��i�Ɏ��M�����Ă�o�c�҂��A���܂ǂ̂��炢����ł��傤���H �\�j�[�ł́A�n�Ǝ҂̐��c���v�������T�Y������A���i�ɂ�����蔲�����l�����ł����B���c����̎���ɢ�E�H�[�N�}����Ƃ����I�o�P���i���o�ꂵ���̂́A�uiPod�v���������A�b�v���Ɠ������A�����̃\�j�[�Ƃ�����Ƃɂ����y��������l��������������ł��傤�B ���Ƃ��ƌ|�p�Ƃ̑�ꂳ����A���i�̍ו��ɓO�ꂵ�Ă���������Ƃ����܂��B�V���i�̌�����c�ŁA�����r�f�I�J�����̃��b�N�A�b�v�i�͌^�j����Ă��ꂽ�Ƃ��A��ꂳ��͂��̃f�U�C�����C�ɓ��炸�A�{��̂��܂肻�̃��b�N�A�b�v����蓊�����Ƃ����܂��B ����ȏ����q�ǂ����݂Ă��邱����肪�A�\�j�[�̐��i����������A�����������A���ɂ�SONY�u�����h�̊m���ɂ��Ȃ������̂��Ǝv���܂��B �������A�c�O�Ȃ���A�������������������A���i�ւ̈���́A���{��Ƃ̂Ȃ����珙�X�ɔ���Ă����悤�Ɏv���܂��B�g�D�����������āA�Z���I�Ȕ��㍂�◘�v�Ƃ������������F���ǂ������͂��߂܂����B����������ƕ��y����������m������ƁA�̂̐������������{���̂��̂Â��肪�ł���g�D�ɖ߂�̂͗e�Ղł͂���܂���B �����ASCE���\�j�[����Ɨ����A�����̓V�˂ł���v��ǖ���̎v���ǂ���̌o�c���ł��Ă�����A��������u��2�̃\�j�[�v���a��������������܂���B�������A�\�j�[�̌o�c�w�ɂƂ��āA����̗���ł�����SCE����������Ƃ͎v�������Ȃ��������Ƃł��傤�B�v��ǖ���ɂƂ��Ă��A���{�ɂƂ��Ă��A�c�O�Ȃ��Ƃ������Ǝv���܂��B ���X�s�[�h�o�c�\�\�����ЂƂ̏����p�^�[�� �@����܂Łu����o�c�v�ɂ��ď����Ă��܂������A�����ЂƂ����̃p�^�[��������܂��B ����́u�X�s�[�h�o�c�v�ł��B���̃G���N�g���j�N�X�EIT�s��ɂ����鏟���p�^�[���͂���2�������Ǝv���܂��B ���{�ɂ�����X�s�[�h�o�c�̑�\�I��́A�\�t�g�o���N�̑����`�В��ł��傤�B �������2012�N�̏H��1���~���鋐�z�𓊂��āA�A�����J�ő�3�ʂ̌g�ѓd�b��Ђ̃X�v�����g�E�l�N�X�e���̔��������f���܂����B�ނ́A�`�����X�ƌ���A�u���Ɍ��f���ėh�炮���Ƃ�����܂���B ���{�Ń{�[�_�t�H���E�W���p�������Čg�ю��ƂɎQ������Ƃ����A�����̐l�� �u�؋����傫�����āA�\�t�g�o���N�͂�����j�]����v�ƌ����܂������A�����̒�z������������ �ł��o���Ȃǂ��Č����ɐ������܂����B�g�b�v�����ɑ傫�ȃ��X�N���Ƃ��āA���₭���f���邱�ƂŁA�r�W�l�X�ɂȂ��Ă����B���{�̑��Ƃ̌o�c�҂ɂ͂ƂĂ��}�l�ł��Ȃ��X�s�[�h���f�ŁA�Ј��̎m�C��傢�ɍ��߂�̂��A�����̌o�c��@�ł��B ���{��Ƃ�ǂ��z�����؍����[�J�[�̐����̔閧���X�s�[�h�o�c�ɂ���Ǝv���܂��B�A�b�v��������o�c�̑�\�Ƃ���A���̏h�G�̃T���X���d�q���X�s�[�h�o�c�̐����Ⴞ�Ƃ�����ł��傤�B �؍���Ƃ̓����́A�g�b�v��������M�����A�������o���Ă����v���W�F�N�g�������Ɣ��f������M�����Ȃ������ł���𐋍s���Ă����B���̂��Ƃ������ɂƂ��đ傫�ȃ��`�x�[�V�����ɂȂ�A����̃v���W�F�N�g�̐����Ɍ�����簐i���Ă����B ����A���{��Ƃ̌o�c�̃X�s�[�h�͐M�����Ȃ��قǒx���B���{��Ƃ̃~�h���w�͂��̓��̃v���ł���A�傫�ȊԈႢ�͂��Ȃ��B�Ƃ��낪�A�o�c�̃g�b�v�w�����_���o���a��A�������������v�������l���Ă��A�����Œ���Ă��܂��B�{�l�����̂��C���Ȃ��Ȃ������ɂȂ��āA�悤�₭�S�[�T�C�����o��悤�Ɏv����B�Ƃɂ����A�ӎv���肪�x���B ���T���X���̃W�����} ���{�̃T�����[�}���o�c�҂ɂ́A�Ƃ��Ă��}�l�̂ł��Ȃ��X�s�[�h���Ŏ������āA�����Ȃ��Ă����̂��A�A�W�A�ʉ݊�@�ň��ނ����T���X�����Ǝv���܂��B�������A���̃T���X���ɂ����p���Ȃ��킯�ł͂��肹��B���ē��{�̑����d�@���[�J�[���o���������Ƃł����A���i�̃��C���A�b�v���g���肷�������ʁA����Ԃ̗��v�������[���ɂȂ��Ă��܂����B��ԕ�����₷���̂́A�ŏI���i�ƕ��i�̗��v�����ł��B ���Ƃ��A�X�}�z�s��ŁA�T���X���̓A�b�v���Ƃ��̂������A�����i�ׂ��i�s���ł����A�T���X���̔����̕���ɂƂ��ăA�b�v���͑�Ȃ����ӗl�ł��B�������A�E��ň��肵�āA����ʼn��荇���悤�ȊW�̓A�b�v�����T���X�������ЂƂ݂Ȃ��x�������傫���Ȃ�ɂ�āA�ێ������������̂ɂȂ��Ă����܂��B �A�b�v���́A���ƃ��o�C��DRAM�̒��B�ɂ��Ă͖��炩�ɃT���X���ւ̈ˑ������炵�A�G���s�[�_�Ƃ̊W���d��������j�ɑǂ���Ă��܂��B�����������Ƃ́ADRAM�����łȂ��R���_�N�^�[��f�B�X�v���C�̂悤�ȑ��̓d�q���i�ł��N����ł��傤�B�A�b�v���ȊO�̋@�탁�[�J�[���A���C�o���ł�����T���X���ւ̈ˑ��͋C�����̂������̂ł͂���܂���B ���́A�T���X�����g���A���̃W�����}�ɋC�Â��Ă��܂��B���܂��琔�N�O�ɂ́A�����̎��Ƃ��X�s���I�t���āA�ŏI���i����Ɣ����̕�������{�W�̂Ȃ��Ɨ�������Ƒ̂ɂ��悤�Ƃ����������������悤�ł��B�������A�����܂ł̌��f�͂ł����ɁA���Ɏ����Ă��܂��B�܂��A�T���X���̋Ɛѕ]���͔��Ɍ������A�N���ƂɋƐтɂ���ă{�[�i�X�̎x�����啝�ɕς��܂��B�����̕��ϋΑ��N����4.4�N���ƕ����Ă��܂��B ���̂��Ƃ�����A�����I�ɕ������l����͂������Ă��邨���ꂪ����Ǝv���܂��B �@�@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E �@����܂ŏ��ҁA�T���X���̃X�s�[�h�o�c������ǂ��Ȃ��Ă������A���ڂ������B �w���ҕK���͔ՐƂ��v����T���X���ɂ��N���邩�H�x�ł���B �@�����āA�T���X���̎�����(��_�j�������o�����ƂŁA���{���[�J�ɂ��ċN�̃`�����X�����o���Ăق����B |
3��14���i���j
�T���X���͂Ȃ����������̂��H
�g�� �ǎO ���̃R�������
�T���X���̖��i���x����3�̃C�m�x�[�V�����Ƃ́A �u�g���^�̃J���o�������v�ɏے��������{�̂��̂Â���ɑ��A���܂��ɓ��{�̍H��̐��Y���͍����A���{�͔��Ɍ����I�ɂ��̂Â�������Ă���Ǝv������ł���l�������B���{��Ƃ̐��Y���͒Ⴂ�I �����Y���Ƃ́A �C���v�b�g�i�J���͂⎑�{�j�ɑ��āA�ǂꂾ���A�E�g�v�b�g�i���v��t�����l�j�ݏo�������ł���B���Ȃ킿�A���͕��̏o�͂ŁA�o��/���͂������B �u���Y���������v�Ƃ����̂́A�������R�X�g�i�J���͂⎑�{�j�ɑ��āA��葽���̗��v��t�����l�����ݏo����Ă����Ԃ������B �@�����̓��{��Ƃ��A�������G�Ђ��i��悤�ȃR�X�g�팸�w�͂��d�ˁA�l���팸�ɂ܂Ŏ�����Ă���B�ɂ�����炸�A���v���Ȃǎ��v�������ۓI�Ɍ��ĒႢ�܂܂Ȃ̂́A�w�͂̕������Ԉ���Ă��邩��ƌ�����B �@���q���g�傷��A���Ȃ킿�u�����ɑ����̃A�E�g�v�b�g�ݏo�����v�Ƃ������Ƃ��ɁA���Y����ɂ���������A�b�v��}������A�R�X�g�����肬��܂ō�����肵�Ă��A���̌��ʂɂ͌��E������B���C�o����Ƃ������悤�Ȃ��������Ă�������Ȃ�A����ŏ��Ă邩������Ȃ����f�W�^�����̎���ɂȂ�A���܂�w���Y������̊T�O�x���̂��̂��ω����ė��Ă���B���傫�Ȍ��ʂ邽�߂ɁA�]���̉�������ɂ͂Ȃ��A��_�ȃA�v���[�`���K�v�ɂȂ��Ă���B ���N�����������T���X����3PI�^�� ����܂ŁA��@�ɒ��ʂ����T���X�������{�̌�ǂ����~�߁A�O���[�o�������������������߁A�]���̂��������ׂĕς���قǂ̑�_�ȉ��v��f�s�����B ���ꂪ�A�l�ވ琬�i�p�[�\�i���E�C�m�x�[�V�����j�A���i�J���i�v���_�N�g�E�C�m�x�[�V�����j�A�J���E���Y�v���Z�X�i�v���Z�X�E�C�m�x�[�V�����j��3�̃C�m�x�[�V�����i�u3PI�v�j�Ƃ�������́B �@�T���X���O���[�v�𗦂��闛��꤁i�C�E�S���q�j��́A�O���[�o�����ƃf�W�^�����Ƃ������E�̕ω���q���Ɋ������A�w���{�̕��܂˂𑱂��Ă����̂ł͐����c��Ȃ��x�Ƃ���������@������A1993�N�A�u�ȂƎq���ȊO�͑S�Ď�芷����v�Ƃ������t�ɏے������u�t�����N�t���g�錾�i�V�o�c�j�v�\���A����v�ɒ��肵���B �u3PI�^���v�͂�����Ďn�܂������̂����A���̌�A�O���C�����o�āA97�N���Ɋ؍����P����IMF��@�ȍ~�A�{�i�I�Ɍ��ʂ�\�����ƂɂȂ�B IMF��@�ő��S�̐��ˍۂɗ������ꂽ�T���X���́A�]���̓��{�̂��̂Â���̂�������͂����茈�ʂ��A�܂������[���̏�Ԃ��炷�ׂĂ��������āA���{��Ƃ��܂��s��Ƃ��Č��Ă��Ȃ������V�����s��Ɋ��H�����o�����ƂƂȂ����B ���̍ہA�V�����̏���҂̑��푽�l�ȃj�[�Y�ɑΉ����A�ቿ�i�ł��m���ɗ��v���グ�邱�Ƃ��\�ɂ��������͂�3PI�ł���B ���f�W�^���f�[�^�����p�����u�h�g�����v�ŊJ�����Ԃ�Z�k �v���Z�X�E�C�m�x�[�V�����́A���i�J����Y�Ȃǂɂ����邷�ׂẴv���Z�X���������I�ɂ��Ă������Ƃ�ړI�ɐi�߂�ꂽ�B�v���Z�X�E�C�m�x�[�V�����͂܂��A���Ə����Ƃɂ�炾�������i�R�[�h�̓���ƕW�������s���A����ƕ��s���Đv��J���Ɋւ��S���̈ꌳ�Ǘ��V�X�e���iPDM�GProduct Data Management�j���\�z�B ���̏�ŁACAD/CAM�ƌĂ��R���s���[�^�[�x���ɂ��v�E�����V�X�e���������BCAD�̓R���s���[�^�[�x���ɂ��v��Ƃ��s�����ƁACAM�̓R���s���[�^�[�x���Ő������邱�ƂŁACAD/CAM�͂���2�������V�X�e���̑��̂ł���B ��f�W�^�������A�Г��ɏ����W��n�u�����邱�Ƃ��\�ɂȂ������ƂŁA�����ڕW�Ɍ������ē����Ă���l�������A�ʁX�ɍs���Ă����Ƃ����s�I�ɐi�߂���悤�ɂȂ����B��̐��i���̕����ɕ������A�����̐v�҂����s���č�Ƃ�i�߂Ă����`�[���v��A���i���A�f�U�C���A�v�A�����A�i���Ǘ��A�c�ƁA�A�t�^�[�T�[�r�X�ȂǁA�قȂ镔��̐l�����������ɊJ����i�߂�R���J�����g�G���W�j�A�����O�Ƃ�������@��PDM�����邱�Ƃŏ��߂ĉ\�ɂȂ���̂��B �����������̂Â���́u���Ă������v�Ɓu�h�g�����v�̈Ⴂ�ɗႦ�邱�Ƃ��ł���B ���Ɏh�������Ă����͒ʏ�A���A�l�M�A�Q�Ԗڂ̒�����Ƃ����ӂ��ɁA��̂ق����珇�ԂɐH�ׂĂ����B���l�ɂ��Ă̏��i�J���́A���i��恨�f�U�C�����@�\�v���\���v�����Y�ւƍ�Ƃ�������Ői�߂��Ă����B �v���Z�X�E�C�m�x�[�V�������ʂ��������ƂŁA���ꂪ�h�g�����ւƕς�����B����ނ��̋���ނ��M�ɐ�������Ă���h�g�ł́A�}�O�����悩�C�J���悩�ƐH�ׂ鏇�������߂��Ă���킯�ł͂Ȃ��A�����̐l�������ɁA���ꂼ��D���ȂƂ��납��H�ׂ���B���i��悪�����Ă��邤���Ƀf�U�C�����n�߁A�f�U�C���̍Œ��ɋ@�\�v�A�\���v���n�߂�Ƃ����J�����@���f�W�^���f�[�^�����Ƃ肷�邱�Ƃʼn\�ɂȂ�A�Z���Ԃɂ�葽���̎�ނ̐��i�ݏo�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B ���ł��K�v�Ȏ��ɕK�v�ȃf�[�^�����o���A���L�ł��邩�炱�����ꂪ�ł����B ���{��Ƃ͂�������J�����X�^�[�g������A���������Ă��Ō�܂œ˂����邪�A�T���X���ł́A���v�̉��U���R�X�g�̑����Ƃ������ω�������A�r���œP�ނ��邱�Ƃ��ł���B ���Ă������̓A�i���O����̂��̂Â���ł���A�h�g�����̓f�W�^������̂��̂Â��肾�B���҂ł͂��̃X�s�[�h��_��ɑ傫�ȍ������܂��̂͌����܂ł��Ȃ��B ���u�����鉻�v����u�����鉻�v�� �T���X����PDM��i�������Ă����ߒ��ŁA�Г��̊e�����͂������A�C�O�̎�������ЊO�̕��i���[�J�[�ɂ�����܂ŁA���i�Ɍg��邷�ׂĂ̐l���K�v�ȂƂ��ɕK�v�ȏ������ׂČ�����悤�ɂ����B���Ƃ��A�M���ł���O���̕��i���[�J�[�ł���A�����Ȏ�����O�ɏ������邱�Ƃ��ł���悤�ɂ������ƂŁA�v�}�̊�����҂����ɏ�����i�߂���悤�ɂȂ�A�J�����Ԃ̑啝�ȒZ�k�ɂȂ������B ����ɃT���X���́u�����鉻�v�ɂƂǂ܂炸�A�K�v�ɉ����āu�����鉻�v���邱�Ƃ��S�������B���߂�������O���t�ɂ�����A�����̃f�[�^�̊֘A�������o�������肵�āA����ɂƂ��Ă��L�v�Ȃ��̂ɂȂ�悤���H���邱�ƂŁA����܂ł̎��Ԃ�Z�k����ƂƂ��ɁA�l�ɂ�锻�f�̂�������炵�A����̐��x���グ�邱�Ƃ��ł��邩�炾�B ���{�́w�f�W�^�����̂Â��聁�v���Ȃǂ��f�W�^�������邱�Ɓx�Ƃ����F���ł����Ƃ������B�f�W�^�����̂Â���̖{���Ƃ́A�{�����̂悤�ɑg�D�̂�����⓭�����̕ϊv�������Ȃ̂��B ���n��ɐ��ʂ����l�ނ��琬���A�V�����̎��v�@ 3PI�̍����ł���p�[�\�i���E�C�m�x�[�V�����ł͎Ј��̈ӎ����v�ƁA�O���[�o������ɑΉ��ł���l�ނ̈琬��}�����B�Ȃ��ł��傫�Ȗ������ʂ������̂��A�u�n����Ɛ��x�v���B���̐��x�ł͑Ώێ҂��u�l�͊J���@�v�Ƃ����l�ވ琬�@�ւ�3�J���ԃJ���d���ɂ��A���̍��̌��t�͂������A������K���Ȃǂ��@�����ށB���{��Ƃ͂��܂��p��Ώd�����A�����Ŋw�Ԃ͎̂�ɐV�����̌��t�ŁA�C���h�ł���A���n��̃q���Y�[���^�~���ꂾ�B���{��̃N���X�ł́A�����Ԃ⒃���A�J���I�P���̋��t�����āA�����ɂ́A�̕����\�̕���̖͌^�܂ł������B �l�͊J���@�ŏW�����������͎��n���C�Ƃ��Ĕh����̍��ɔ��N����1�N�ԁA�؍݂�����B�����[���̂́A�ނ�͂��̑؍݊��Ԓ��͉��ЂƂC����ттȂ����Ƃ��B���n�������⒓�݈�����ؗ���Ȃ��Ƃ������[����������Ă���A�ɒ[�Șb�A�����p�`���R�X�ɒʂ��Ă������B �������Č��n�̎Љ�ɗn�����݁A�Ǝ��̐l����[�g���\�z�����u�n����Ɓv�́A�����ɔh�����ꂽ��A����g�����h�����������L���b�`���āA�n��̃j�[�Y�ɍ��v�������i�����X�Ɋ�悵�Ă������B ��������D�ʂɉ^�ׂ�V�X�e���\�z �u�p�[�\�i���E�C�m�x�[�V�����v��u�v���Z�X�E�C�m�x�[�V�����v�ɉ����āA3�ڂ́u�v���_�N�g�E�C�m�x�[�V�����v������B���̉��v�ŃT���X���́A���o�[�X�E�G���W�j�A�����O�̎�@����g���A���������ɂ̓W���K�C���������@�A�C���h�����ɂ͂�����T���[�������@�A�Ƃ�������ɁA�n�悲�Ƃ̗v���@�\�i�j�[�Y�j�������ɉ��������i�̊J���͂����߂Ă������B �K�v�̂Ȃ��@�\���S���l�ߍ��݁A���E���ɓ������i����܂����Ƃ������{��ƂƂ͑ΏƓI�ȓ���i���̂��B ���̂悤�ɂ��ăT���X���́A�f�W�^�������ő���ɗ��p���A�e������҂̑��푽�l�ȃj�[�Y�ɉ��������i���������v���ɒł���d�g�݂����肠���A������ɁA�V�����̎s���Ȍ������B �]���̂������̂��̂��������ċ�����D�ʂɉ^�ԃV�X�e�����\�z�������ƂŁA�O���[�o�������̏��҂ɂȂ邱�Ƃ��ł����̂��B ���������T���X���̃C�m�x�[�V�����ɂ��āA�u�����V�����Z�p�ݏo���Ă��Ȃ��ł͂Ȃ����v�Ɣ��_����l������B���{�ł́u�C�m�x�[�V�����v���u�Z�p�v�V�v�ƂƂ炦���Ă��邽�߂��B �����{���_���ɂ���3�̌�� �@�C�m�x�[�V���� �@�����̋Z�p��g�ݍ��킹�āA����҂ɐV�������l����邱�Ƃ��A�{���͗��h�ȃC�m�x�[�V�������B �@�t�ɂ����ƁA������V�����Z�p���J�����Ă��s��Ɏ�����Ȃ���A�C�m�x�[�V�����Ƃ͂����Ȃ��B �A�u�}�[�P�e�B���O�v �@�u�s�꒲���v�Ɩ�邱�Ƃ��������A�T���X���ł́u�s�ꔭ�@�v�u�s��n���v�Ƃ����Ӗ��ɂƂ炦�Ă��āA���̂��߂ɑ吨�́u�n����Ɓv���琬���Ă���B �B�u�R���v���C�A���X�v �@�u�@�ߏ���v�ł͂Ȃ��A�u����̕ω��ɓK�����邽�߂ɁA�]���̂�����ς���v���ƂƉ��߂��ׂ����B �@3PI�^���́u�Љ�̃p���_�C���ω��ɒǏ]�����T���X�����̃R���v���C�A���X�v�Ƃ݂邱�Ƃ��ł���B �@ ���{��Ƃ͈�x�A�����������z�����{���猩�����Ă݂Ă͂ǂ����낤�� |
2��18���i�j
���{�l�̓A�i���O�l�Ԃ��H
| ���{�l�ƊO���l �w���{�l�̓A�i���O�l�ԁA�O���l�̓f�W�^���l�Ԃ��I�x�Ƃ����ƁA�Ƃ��҂ȕ\���ɕ������邩������܂���B ����͋ɒ[�Ɍ����̘b�ŁA�t�ɓ��{�l�ɂ��f�W�^���l�Ԃ��A�O���l�ɂ��A�i���O�l�Ԃ����܂��B�������A���̓I�Ɍ���A���{�l�̓A�i���O�l�Ԃ��I�@�Ƃ������Ƃł��B �w�������������̂��H�@�����ς蕪�����I�x�Ƃ���������邩������܂���B�v�͂����������Ƃł��B ���{�l�͗L�j�ȗ��A�A�W�A�̓��̒[�̓��ɏZ��ł��܂����B������O�G�ɏP��邱�Ƃ��Ȃ��A����N���̊ԁA���₩�ɐ������d�˂Ă��܂����B �������g���ċL�^�i�h�L�������g�j�Ƃ��āA�Î��L����{���I���c����Ă���1500�N�قǂɂȂ�܂��B���̕����͒�����������Ă��������ł����A�������A�����W���ăJ�^�J�i��A�Ђ炪�Ȃ����A�Ǝ��̕�����z���A�����ɍ�����̂��ꂽ�Ƃ������Ƃ͂���܂���B�����͒�������i�����Ƃ��ē����Ă��܂����B ���{���P��������{�l����Q��ւ����̂͌����̖����炢�ŁA���̌�A��̑����m�푈�łł����B ���{�l�͐l���^�킸�A���������w�a�����đ����x�Ƃ����S���������Ă��܂��B ������A���߂��Ƃ⌈�ߎ��ɂ����Ă��A�����𒅂��A�����ȓ������o�����Ƃ����߂������A�����T����l�������B����͓��{�l���O���l�Ƒ傫���Ⴄ�C�����Ǝv���B ���[���b�p�l�͊e�����������Ȃ̂ŁA�Ñ�M���V���A���[�}�鍑���ォ��ߑ�ɂ�����܂ŁA�e�n�̏����ʁi�e���j��D�������A�E�C���J��Ԃ��ꂽ���j�������Ă����B���[���b�p�͂ǂ̍��ł��A���������X�Ɠ���ւ��A�푈�ŏ��������̂��V�������ʂɂ��A�j�ꂽ���̂͗e�͂Ȃ��E�Q��Ǖ����ꂽ�B�̓y���e���ҁi�����j�̗͂ōL���Ȃ�����A���܂�������J��Ԃ��Ă����B���ׂ̒����ł��A���N�ł��������Ƃ��������B ���E���ŗB����{�������A�w�V�c�x�Ƃ���������Ղ���1000�N�ȏ�������Ă����B���̂��Ƃ́A���E�̗��j��Ŕ��ɒ��������Ƃł���B �����i�����j���͂́A��������̓����A���q����̌��A���y���R�̑����A�D�c�A�L�b�A�����č]�ˎ���̓���Ƒ����A�����̑吭��҂ɂȂ���B�����͋M���A���m�Ƒ����Ă��A���ʁi�V�c�j�͉��X�Ƒ����Ă����B������̂��āw������n�̓V�c����x�ƌĂ�ł���B ���{�ȊO�̏����́A���A�܂��͉��ʂ�����ւ��A�O�̉��͎E�Q��Ǖ�����ė��j����r�₦��B ����A�M�������A���Ɛ����̗��ŁA���X�ƓV�c�Ƃ��琔�S�N�ɂ킽�萶�������Ă����B���̂��Ƃ����E�j�̒��ŁA���{�����̓Ǝ��̕����ł���B ���{�ł́A�����c�_����ꍇ�ł��A���ʐ��Ď^���A�����Ȃ����Ƃ������B�܂��A���{��́w�����܂��A�͌Ёx�Ƃ����\���������B���̈�Ⴊ�w�������܂��x�Ƃ������t�ŁA�w�ϋɓI�Ɏ^���łȂ����A���ɔ��ł��Ȃ��A�܂��A���̓��ɉ���������܂��傤�x�Ƃ����悤�Ȏ��Ɏg����B �{���̈Ӗ��́A�w�������܂��x�Ƃ������Ƃ́A�w�������ƒ��ׂē������o���܂��x�Ƃ����O�����̈Ӗ��̂͂��B �����Ƃ��l���w�������܂��x�Ƃ������́w����͎��s���܂���x�Ƃ����ے��Ɏg����悤���B ���{�l�́w�������͂����蒅����̂͂悭�Ȃ��x�Ƃ����[�w�S���������Ă���B���̂��A���Ȃ��̂����ʒ��F�ɂ��ĒI�グ���āA���̂����Ɏ��R�ƌ��_���o��܂Œu���Ă������Ƃ����X�^���X�ł���B ���炭�҂ĂA���R�ƌ��_�⌋�ʂ��o��A���̎��ɂ������ƌ��߂�����Ƃ����悤�Ȋ��o�������Ă���l�����ɑ����B����A�D�_�s�f�ł���B ����̓A�i���O�I�Ȋ��o�ŁA�����̕ω����Ȃ���ōl���Ă���B �O���l�͔������͂����茈�����A�͂����茾���̂����ʂł���B����̓f�W�^���I�ȍl�����ŁA�����𔒂����Ŏd�������čl����B�w����Ă������ƁA����Ă͂����Ȃ����Ɓx �w��邱�ƁA���Ȃ����Ɓx�w���l�ɖ��f�����������ƁA�����łȂ����Ɓx���͂�����ԓx�⌾�t�ŕ\���B������O���l�͎����������Ȃ��Ǝv���A��Ɏӂ�Ȃ��B�ӂ邱�Ƃ͎����̔��F�߂邱�ƂɂȂ�B���F�߂�ƁA�������s���v�̗���ɂȂ邱�Ƃ����j��ʂ��Đg�ɒ����Ă����̂��낤�B �gExcuce me�h�Ƃ������t�͂悭�g����B���{��ł́w������Ǝ��炵�܂��x�Ƃ����Ӗ����Ǝv�����A����ɑ��đΓ��ȗ���œ`���錾�������B �@ ����ɑ��āA�gI�fm�@sorry�h�Ƃ����̂́A����ɉ����܂������Ƃ������Ƃ��w���炵�܂����A���߂�Ȃ����x�Ƃ������ƂŁA�����̔��߂���F�߁A�w���݂܂���x�Ə����ӂ�悤�Ȏ��ɂ�������Ȃ����t�Ŏg�������Ă���B ���{�l�͉����ɂ��āw������݂܂���x�Ƃ悭�����B ���Ƃ��A�G���x�[�^�ɏ��Ƃ��A�gExcuce me�h�Ƃ������A�gI'm sorry�h�Ƃ͌����Č���Ȃ��B���{�l�Ȃ�w���݂܂���x�Ƃ����B�����ɔȂ��A�����ӂ邱�Ƃ��Ȃ��ꍇ�ł��w���݂܂���x�Ƃ����B ���������������́A�������g��������O���l���炷��ƁA�w���{�l�͕ς�����l�킾�x�Ǝv���炵���B �����𔒍��Ō������邱�Ƃ�����A�ł��邾�����₩�ɁA�w�a�������đ����x�Ƃ��Ă������������{�ł���B�v�͔����̊ԂɊD�F�Ƃ������ԐF�����܂��g���Ȃ���A�݂��̓G����ْ�����a�炰�A���₩�Ȑ����𑗂��Ă����ƌ�����B ���ꂪ�ł����̂́A���{�����N�ɂ킽��G���鑊��A�U�߂Ă��鑊�肪���Ȃ���������ł���B�����̏����ȕ����͂��������A�����l������Ƃɂ��閯���Ԃ̐푈�͂Ȃ������B�@����ł��A�G����悤�Ȍ������Η��͂��܂�Ȃ������B ���������Ӗ��ŁA�A�i���O�l�Ԃ͓��{�l�ɂ������Ȃ����A�J���r�㍑���i���̏Z���ɂ͓��{�l�ȏ�ɃA�i���O�l�Ԃ����邩������Ȃ��B �������A���オ�ς��O���[�o���A�{�[�_���X����ɂȂ�A���E����ɂȂ���錻�݁A���E�̂�����X�^���_�[�h���h���h�����{�ɓ����Ă���B ���O���Ɠ��{���̊Ԃɒn���I�ɂ͊C�����݂��A�u����͑��݂��邪�A�q��@��D���̗A����i�����B���A�C���^�[�l�b�g�AIT�̓����ŕ����I�Ȋu������Ȃ����Ă��܂����B���{�͈ˑR�Ƃ��ē����ł��邪�A�Ǘ��������ł͂Ȃ��Ȃ����B ���{�l�̃A�C�f���e�B�e�B�[�������A�i���O�l�ԓI�v�f�͎���ɐF�����𔖂����Ă���B�f�W�A�i�i�f�W�^��-�A�i���O�j�l�Ԃ������Ă�����B �r�W�l�X�͍��ۉ����A�O���l���咣���锒���_���ɑ��āA�w����@�I���������l���悤�A����������Ƃ����Ă��Ȃ����H�x�ȂǗI���ɉۑ���l���A���_��摗�肵�A�w���̓��Ɍ��ʂ��o�Ă���A��������Č��_���o�����x�Ƃ������܂ł̓��{�I�ȍl������s���ł͂ǂ�ǂ�u���Ă��ڂ��H���B �؍��T���X����LG�d�q�����{�̂��ƌ|�������Ɠd�E�d�q�Y�Ƃ��쒀�������Ƃ̓g�b�v�̌��f�̑����Ƒf�����s���ɂ��B ����A���{�l�����������Ă���A�i���O�l�ԓI�l������w���{�l�C���x�����ۋ����łǂ������D�ʐ����ł��邩�y���݂��B �w���{�̏펯�͐��E�̔�펯�v�@�ƌ����Ă������A�w���{�̏펯�͐��E�̏펯�x�ɂȂ�������邩�B �@����̓f�W�^�����s���l�܂������A���Ȃ킿���E�̏펯�������s���Ȃ��Ȃ������ɁA�A�i���O�̗ǂ��A���Ȃ킿���{�̏펯���Ĕ�������邩������Ȃ�����ł���B |
�Q���P�T���i�y�j
���{�̍���p�����āA
�u���E�ō������̈��S��ŐR��������̂ŁE�E�E�v
| �@���A�J����Ă���ʏ퍑��̗\�Z�ψ���̃e���r���p�����Ă���ƁA��}�̌����ĉғ��̎���ɑ��āA���{�A���{�����A�Ζ،o�Y��b�⎩���}�������悭�g�����t�ł��邪�A������a���������܂��H �@���E�ō������̈��S��ŁA����~���Ă���S���̌����������R�����āA���i�������̂���ғ�������Ƃ�������ɂȂ��Ă����B �@���ɒ����d�͂��l�������͓���C�n�k�̐k���n�̒��S���ɑ��݂���̂ŁA���������ғ����~��\������A�����d�͂����d��~���A�Ôg��Ȃǂ̈��S����{���āA�ĉғ��̐\���������Ƃ������Ȃ��ꂽ�B �@�É�����O��s�ɂ���A��n�k���N���A�x�m�R�������āA��ʂ̕������n�◬�Œn�`���ς�����Ƃ��Ă����̌����͑��v�Ȃ̂��H �@�����A���̂��N����A���ː������͓��ɔ�U���A������֓��n��ɂ͐l���Z�߂Ȃ��Ȃ邾�낤�B �@�����͈��S�łȂ���Ȃ�Ȃ����Ƃ͒N�ł��������Ă���B�������S��S�����邽�߂ɂǂ����邩�ł���B�����A���ꂪ�[���ł��Ȃ���A�Z���⍑���̗���������ꂸ�A���܂ł��ĉғ��͂ł��Ȃ��B �@�������͐��牭�~�Ƃ����ƂĂ��Ȃ������������Ă���B���̋��͉ғ����Ȃ���A�����̃��_�i���ɋ��j�ɂȂ�B�d�͉�Ђ͈ꍏ�������ĉғ����������B�������A���q�͈��S�ψ����Ƃ������̐R���ɍ��i���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@ �@���܂ł��A���ׂĂ̌����͌��q�͈��S�R�����č��i���Ă����B �������A������ꌴ���́A�����{��k�Ђ̒Ôg�ɂ����Ȃ��j��Ă��܂����B�����ŁA���{�͐��E�ꌵ�������S�R��������肵�A����ɏ]���ĐR�����邱�ƂƂ����B �@�����ő�Ȃ��Ƃ́A���t�̂���ɂ��܂�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B �@�V���S��͌������Ȃ�A���E�ō��̈��S��ł��邱�Ƃ͓��ɔے肵�Ȃ��B���E�ō��̈��S��Ƃ́A���̍��̈��S��Ƃ̔�r�ł����āA���̊�ŐR�������i����A���{�Ƃ����n�k���A�ΎR���ł����S���ǂ����ł���B ����������ƁA���{�͐��E��̒n�k���̈�ł���A�S�y���ΎR�ł���B ���������������E���̂ǂ��ɂ���̂��H �@�v�́A�n�k���A�ΎR���̓��{�́A�����������ꂪ�Ȃ����̈��S��Ɣ�r���āA���E�ō��̈��S��ƌ����Ă��A����͈��S��ۏႷ����̂ł͂Ȃ��B �v�͔�r�_�ł���A��r�I�A�����̈��S��ɑ��Č������Ώ������Ă���Ƃ͂�����B������n�k��ΎR�̕���Ôg�ɑ��Ĉ��S���Ƃ͒N��������Ȃ��B �@ �@����X�ƍ���̋c�_�̒��ŁA���{�^�}�͌������Ă���B���̉ɑ��āA��}�͂���ȏ�̒Nj����ł��Ă��Ȃ��B �@�����͔�r�_��m���_�Ői�߂Ă͂Ȃ�Ȃ��B �@����͎��̂��N����ƁA���d�������Ă����w�z��O�́E�E�E�x�Ƃ������ƂɂȂ���B�z��͐�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�������A�l�m�͖����A���ۏႷ��p���Ȃ��B�p���Ȃ��Ȃ�A�����͉ғ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B �@���������ƁA�Ȋw�Z�p�͂��ׂđz����̐����ŕ�����i�߂Ă���B���ׂĂ̍H�Ɛ��i�A�C���t���Ȃǐv��ƌ����z��l�Őv����B �@ �@��s�@�����āA�Q�d�A�R�d�̈��S������Ă��邪�A���R�̐ۗ��ł���d�͂ɋt�炤���Ƃ��ł��Ȃ��B��s�@�����S�ɔ�s�ł���̂́A�d�͂ƕ��͂��o�����X���Ă���Ƃ��������ɂ����āA���S�����藧���Ă���B �@ �@�������A�F�S�̒��Ɍ��q�j�R���������߂��āA�j��������Ƃ��������ɂ����Ăł���B���̏��������ꂽ���A���q�̓G�l���M�[�͂ƂĂ��Ȃ���Q���܂��U�炷���ƂɂȂ�B �@��s�@�͎��̂��N����ƒė�����B�ė����Ă�����҂ƁA�ė��n�_�ɐl���Z��ł���Δ�Q�ɂ������A��Q�͂��͈̔͂ɂƂǂ܂�B �����������Ɣ�s�@�̈Ⴂ�ł���B �@ �@���{�����Ζ،o�Y��b���悭�����w���E�ō��̈��S��ŐR������x��������v�A���S���Ƃ����_���͊ԈႢ�ł͂Ȃ����������͂Ȃ��B �@ �@�ΎR�A�n�k�A�Ôg�̓��{�ł̍��y�̏�ŁA�T�S�����̌������ĉғ����āA���̓V�Ђɂ�鎖�̂��N�����ۂ͓��{�͍ċN�s�\�ɂȂ邾�낤�B �@ �@�����̍����˔\�p�������������I�グ��Ԃɂ���B�j�̃S�~�������Ă���鍑�͂Ȃ��B�����ŏ��u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂷ����S�ɉ���N�A�����N�ۊǂ���ݔ��ȂǕۏ�ł���͂��͂Ȃ��B �@ �@�C�O���s���ċC�Â����Ƃ́A�����ł͈ꕔ�̒n�k���������āA�n�k��m��Ȃ��A�o���������Ƃ��Ȃ��Ƃ����l�����ɑ����B�t�ɓ��{�l�͒n�k�Ɋ�������ɂȂ��Ă���B����ق����{�̒n���ɂ͒n�k�̑��������Ă����B ������������ȍ��ł��邱�Ƃ����o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��������A���E�ō��̈��S�������������t�������Ɂw���Ӗ��x�ł��邩��������͂����I�I |
�P���R�O��(�j
�S���X�[�b�Ɛ���n��u���o�̐S���w�v��ǂ��
���z�N����
�p��V��
�艿�V�W�O�~(�ŕʁj

| �@���z�搶���w�S���t�b�ƌy���Ȃ�u�u�Ԃ̐S���w�v�x�Ɉ��������āA�����V���[�Y�� �w�S���X�[�b�Ɛ���n��u���o�̐S���w�v�x��ǂ�ł݂��B������͎v���Ă����ȏ�ɓ���ŁA�ǂ݉����̂ɋ�J�����B�Ƃ������킩��h���������B �@��͂�A�S���w�Ɠ��̌��t�̎g����������A����������̓��ň�x�A�����̐�����ɐ����Ԃ��Ƃ����Ȃ�K�v�ɂȂ�B ���z�搶�͕�����₷���A�b�̓W�J�̒��ł���������Ƃ����Ȃ���A����i�߂Ă���Ă��邪�A����ł��܂������ŁA�����͂ǂ����������炢���̂��ȁH�Ƃ����t���[�Y����������A�����ɓ˂�������ƁA�Ȃ��Ȃ��O�ɐi�߂Ȃ��B�����炠�܂�C�ɂ�������������Ƃ������R����B�ł����Ƃ��Ō�܂Œ��߂��ɓǂݏI�����B �@�������O�����s���l�܂�A�����s���ƂƂ��ɐ����Â炳�������Ă��܂��B�ǂ����Ă��S���Â��Ȃ肪���ł����A����₩�ŐS�n�������o�͎��͂̐l���^���Ă��������Ƃ����v�����݂����Ă��܂��B�����̐S���R���g���[������͎̂������g�ł��B �@�����āA�S�n�������o�͎��O�ł���o�����Ƃ��ł����̂ł��B���̎�i�Ƃ��āA�S������Ă����悤�Ȃ���₩�ȋC���A�g�̂̒����畦���N����悤���u�������o�v��̌����A�C���v�b�g���Ă����̂ł��B �@���̂��߂ɂ́A�ǂ���������̂��B�Ⴆ�߂��ɂ��邨����_�ЂȂǁA�����̐S�����������ꏊ�ɏo�����A�����̎��Ԃł����̂Ő^���ɋF���Ă݂Ă��������B�S�����ݓn��A�y���Ȃ�悤�Ȋ��o���g�̂��ݍ��ނ͂��ł��B�@ �@�܂��A�����̐S���������j�^�����O�ł����悤�ɂȂ�ƁA�s���Ȋ���ɐS���x�z�����O�ɁA�s���Ȋ���N���N���肻�����Ɠǂݎ�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B����ƁA�l�K�e�B�u�Ȋ���萶�������ȂƂ��ɁA���O�ɗ}���邱�Ƃ��ł����悤�ɂȂ��Ă���̂ł��B�S���s����ꂵ�݁E�Y�݂Ɏx�z���ꂸ�A�O�����ȋC������������ɂ͂ǂ���������̂���`���Ă����܂��B �@ �@���́F�����̕s����@�����߂ɁA�ǂ���������̂��H �@���́F�����Â炳�̍���ɂ������ �@��O�́F�Ȃ������S�͑u�₩�ł����Ȃ��̂��H �@��l�́F�S�n�������o�͎��O�ł���o�����Ƃ��ł��� �@��́F�u�₩��������o���x�[�X�����u���Ӂv �@��Z�́F�S������n�������o���L�[�v����ɂ� �@�掵�́F�u�������o�v���l�����y�ɂ��Ă���� �ƂȂ��Ă���B �@�������镶�͂ɖЎq�̌��t���Љ��Ă���B �w�����������l�Ԃł���Ȃ���A�̑�Ȑl�ɂȂ�����A�܂�Ȃ��l�ɂȂ����肷��̂͂ǂ������킯���x�Ɩ��ꂽ���̓����́H �@�w�l�Ԃ̑̂ɂ͑傫�ȑ̂Ə����ȑ̂̋�ʂ�����B�傫�ȑ́A���Ȃ킿�l�Ԃ��{�������Ă���ǐS�ɏ]���Đ�����Γ��̍����l���ɂȂ�A����ڂ̗~�]�̂܂܂ɏ]���Đ�����A�܂�Ȃ��l�ԂɂȂ�x�ƁB �@����������Ƃ������Ƃ�S�ۂɂ��Ȃ��ƕs���ł��܂�Ȃ����{�l �w������ɂ����Ƃ���Ă������͖₢�ɑ��Ĉ�̐���������A��������߂邱�Ƃ������Ă����B�����Đ���������Ƃ������S����S�ۂƂ��Ĉꐶ�����l����K�����w�K�̂�����Ƃ��Đg�ɟ��݂��Ă��܂��Ă���B ������A�Љ�l�ɂȂ��Ĉ�ԍ��邱�Ƃ́A�w�������Ȃ��x�ɒu����邱�Ƃ��Ƃ������Ƃł��B�D�����قLj�̓�����l��萳�m�ɁA����������P�������Ă����l������A�w�������Ȃ��x�܂��́w���������������āA����I�ׂ����̂��x�Ƃ����ɒu�����ƌ˘f���Ă��܂��B��������Ǝ����̓��ӋZ�A�������m���Ă�������ɗ���B�������A�����ɉۂ����Ă���͑S���t�ŁA�������������̓��ӋZ���ʗp���Ȃ������ɒu����Ă���̂ł��B�E�E�E�E�B �@���i�͌��C�Ȃ̂ɁA��Ђɍs���ƗJ�T�ɂȂ�Ƃ����w�V�^���x�Ƃ����l�͎����̒��q���R���g���[���ł��Ă��Ȃ��l�ł��傤���H �V���������K�����g�ɕt���ɂ����Ƃ��A�Z�������Đ����s���Ō��ӊ��������Ȃ��Ƃ��A�E������������Ď��т��ς߂Ȃ��Ƃ��A�����Ȍ����������l�����܂����A���X�ɂ��Ď����̐S�Ƃ̑Θb�E�Ή����g�ɂ��Ă��Ȃ��l�قǁA�₽��Z�����A�Z�����ƌ����Ă����ł��B������ÂɐU��Ԃ�Ƃ����ԂԂ�Q��Ă��邱�Ƃ�����܂��H�E�E�E�E �{���ɖZ�����l�قǁA�Z�����A�Z�����Ƃ��܂茾���܂���ˁB �@�Ƃ����悤�Ȓ��q�ŏ�����Ă��܂��̂ŁA�����̂�����͐���ǂ�ł݂ĉ������B �@���݂̓��{�Љ�̕NJ��̒��ŁA�����������߂̏���Ⳃ̂悤�Ȋ��������܂��B |
�P���Q�S���i���j
�S���t�b�ƌy���Ȃ�u�u�Ԃ̐S���w�v��ǂ��
���z�N����
�p��V��
�艿�V�W�O�~�i�ŕʁj

| �@�����A�����Ȃ��璆�g��NHK���W�I�i�������j���悭�������A�w���y�j�ق��ƃ^�C���x�Ƃ��������A�i�̓Ɠ��̂�����ׂ�ɖ��������B �P���P�W���i�y�j���j�̕������Ă���ƁA��ϋ����[�����e�̘b������܂����̂ŁA���Љ��B �@�S���w�҂����z�N���搶�̑Βk�̍ĕ����������̂ł����A�v���Ԃ�ɑ�ς킩��₷���S�̖��ɂ��Ă��b����Ă��܂����B �@���������A���z�搶��NHK�e���r���w���\���̚��x�̃R�����e�[�^������Ă��܂��B �S���w�Ƃ����ƁA�Ƃ����ɂ����A����Ǝv���܂�������b�������S���w�҂���R�����܂��B���������搶�������̂ł��B �@�������A���傹��A�S���Ƃ͐S���e�[�}�ł�����A�f���ɓǂ݉����Ƃ�������l���邱�Ƃ��Ȃ��Ǝv���܂��B �@���z�搶��NHK���W�I�̑Βk�ŁA��ς킩��₷���A�g�߂ȗ�������Ȃ��炨�b������Ă��܂����̂ŁA�搶�̏������{��ǂ�ł݂����Ȃ�A�ƂɋA���Ă����p�\�R���𗧂��グ�A�C���^�[�l�b�g�ɂȂ��Aamazon���J���Ė��z�搶�̖{���Q���������܂����B �@���̈�����A�����̃^�C�g���̖{�ŁA�w�S���t�b�ƌy���Ȃ�u�u�Ԃ̐S���w�v�x�ł��B ��������͓����悤�ȃ^�C�g���ŁA�w�S���X�[�b�Ɛ���n��u���o�̐S���w�v�x�ł��B �@�S���w�͂Ȃ�����̂��H�@�����l���Ă݂����Ǝv���܂��B ��́A��w����ɋ��玑�i����낤�Ǝv���A�����͒��w�P���A���Z�Q���Ƃ��������N�ŁA�Ȗڂ͐��w�Ɨ��ȁi�����j�ƍH�ƉȂ̋����Ƌ����擾���܂����B ���̂��߂ɁA�u�����S���w�v�Ɓu�N�S���w�v�̍u������u�������Ƃ�����܂��B�����ŏ��߂āA�S���w�ɐڂ����̂ł����A���̌�A�����d��̖����̎Ј����C������ɁA�}�l�W�����g���C�Ƃ��āA���l���̐S���w�҂�S���ɂ��Ęb�����Ă��������u�����J�Â��A���������̘b���@�����܂����B �@�����������ƂŁA�S���w�ɂ��Ă͋����̂��镪��ƂȂ�܂������A����Ƃɂ��Ă���搶���͑�ςȋ�J������ȁH�Ƃ�����ۂ������Ă��܂����B �@����͐S�Ƃ������̂����`�ŏ�ɗh�ꓮ���Ă��邩����݂ǂ��낪�Ȃ�����ł��B ����ł͈���ڂ́w�S���t�b�ƌy���Ȃ�u�Ԃ̐S���w�x�ɂ��āI�I �@�搶�̒����́u�܂������v�����肷��Ȃ�A�w�{��Ȃǂ̊���₻��ɔ����v�l�́A�S�̌Œ肵���\���������痝�����Ă��A���ۂɑ����邱�Ƃ�����B�܂��A�X�̐l�Ԃ̐��������̒��Ő��N�������܂��܂ȃG�s�\�[�f�B�b�N�ȑ̌��͂��������邱�Ƃ��A�����ɑ���j��I�Ȋ���𐧌䂷�邱�Ƃ̏d�v�ȑb�ɂ͂Ȃ蓾�邪�A������������������ł́A��͂���ʓI�ȑΏ��@�ɂ͎���Ȃ��̂ł���B�x�Ƃ����悤�ɏ�����Ă��܂��B���̂Ƃ��肾�Ǝv���܂��B �@���̕��͂𗝉��ł���A���̖{��ǂݑ����A�ǂݏI��邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂������̕\���������ł��Ȃ���A��͂�S���w���w�Ԃ͓̂����������Ȃ��Ǝv���B �@ �@����ɐ搶�́A�w�����v�l�͂����A���̂��̏u�Ԃɐ��N�������Ă��邩��ɑ��Ȃ�Ȃ��B���̂��Ƃ̗Տ��I�ȈӋ`�́A�����狭�����Ă��������邱�Ƃ��Ȃ��قǏd�v�Ȃ��Ɓx�ƌ����Ă���B �@�����āA��͂�A�w����Ӗ��A�\�z�ʂ�A������ǂ݂₷����ނ̃n�E�c�[�{�Ƃ͂��Ȃ����قɂ�����ƂȂ����B�u�Ԃ���u�ԂցA���ɂ����܂����X�s�[�h�Ő₦���ω��������Ă����X�̐S�̏��ł��邾���킩��₷���������邱�Ƃ͎�������B�x�ƌ���ł���B �@ �@�搶�ɂ����܂��\�����邱�Ƃ�������ƂȂ̂��Ƃ������Ƃ�������܂��B ��͂�A�S�͗Z�ʖ��V�ɕω��������閳�`�̂��̂Ȃ̂ŁA�݂͂悤���Ȃ��A�͂u�Ԃɂ��łɑ��̂Ƃ���֕ω����Ă��邩�炾�Ǝv���B������w��I�ɗ��t������A�������悤�Ƃ���A�ǂ����Ă������≹���ɂ��\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�������A�P�O�O���A�S�𐳂����\���ł���p�͂Ȃ��B������S���w�҂͂����ȃp�^�[���⎖��������Ȃ���S�̐^���ɔ��낤�Ƌ�J����̂ł��낤�Ǝv���B �@��������ǂޕ��Ƃ��Ă��A�����w�͂��W�����Ȃ��ƁA�搶�̌����Ƃ��邱�Ƃ������ł��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B �@�ł��A���z�搶�͂������₷���������Ă����̂ŁA����̐S���w�����Ƃ��ǂ݉������Ƃ��ł���B �@�ڎ������Љ��B ���́@�NJ�����������́u������́v ���́@�S������Ă���Ǝv�������A���Ɍ�����Ȃ����߂� ��O�́@�l�ɂƂ��ē������ƁA���������Ƃ� ��l�́@�������炢�Љ���������߂� �ƂȂ��Ă��܂��B ��ϋ����̂��镶�͂��ꕔ���Љ�܂��ƁA �w�����܂ŕs���Y����̂́A�������g�̓��ʂł���B�������A���Ԃł́A���ꂩ�����ɂȂ�����A���E�A���邢�͎��E����������ƁA���̌����������O�I�v���ɊҌ����悤�Ƃ������ł��B�x �w�������Ƃ͉����H�@����͂ЂƂɂ͎����������Ă��鉿�l�ςւ̎����ł��B���̎����̋�����ɂ��āA��łɉ䂪����˂��i�����Ƃ���̂��������̑ԓx�ł��B����ɑ��A�����Ɩ{���I�ȈӖ��ŁA�������������Ă���l�́A�Œ�T�O�Ɏ�����Ƃ������A�ނ���A�������邱�Ƃ���ɒNj�������A�T�������肵�Ă���l�̂��Ƃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���������^���ȑԓx�ƒP�Ȃ��łȂ������Ƃ́A�ʂ̂��̂ł���C�����܂��B �@�������̂�����́A���ЁA��x�{��ǂ�ł݂ĉ������B ���\���̂�����e�ł��B |
1��18���i�y�j
�u�A�����J�͓��{�o�ς̕�����m���Ă���v��ǂ��
�l�c�G��i���t�Q�^�j��
�u�k��
�艿1600�~�i�ŕʁj
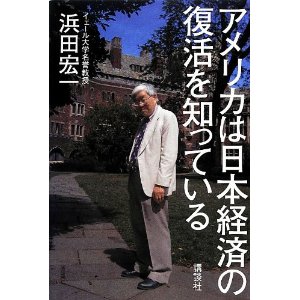
| �@���A�o�ϕ���Ńm�[�x���܂Ɉ�ԋ߂��ƌ����Ă���l�c�G�ꎁ�̖{�� �O��̖{�u�A�x�m�~�N�X��TPP���n����{�v�Ɉ��������ēǂB�O��̖{�̓nj㊴�͉��ɏ����Ă��邪���e�I�ɂ�Q&A�ŏ�����ĊȌ��������̂ł����ɓǂݏI�����B �@����̂��̖{�́A���e�������A���\�ǂ݂�����������A�����ɂ͂Ȃ��Ȃ�������̂������B �@�l�c�搶��1936�N���܂�Ƃ������Ƃł�����A�V�O�Ό㔼�ɂȂ���B ��ς����C�Ŋ���Ă���B�o�ϊw�̗��ꂩ�炵�āu���t���v�ƌ�����l�����̕��ł��B �@�o�ϊw�͑f�l�̏����ɂ́A�����Ȍo�ϗp�ꂪ�o�Ă���Ƃ����ŗ����~�܂邪�A����͋C�ɂ����ɓǂݒʂ����B �@��ɓǂw�A�x�m�~�N�X��TPP���n����{�x�̓��e�Əd�Ȃ��Ă��镔�����������邪�A�ȒP�ɗv��A���̎���ꂽ10�N�Ƃ�20�N�Ƃ���������{�̌o�ϒ���͎Y�ƊE�̓w�͕s�������邱�ƂȂ���A�l�c�搶�Ɍ��킹��ƁA����̖���ɂ������N�����ꂽ���̂��ƒf�߂��Ă���B �@2008�N�ɋN�������A�����J�̃T�u�v���C�����[���[�Ƃ��郊�[�}���E�u���U�[�X�̔j����ŁA���������[�}���V���b�N���N���A�A�����J�̋��Z�@�ւ��@�\���Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ƃ�����@�ɒ��ʂ������A���̌�A�A�����J��C�M���X�A���̑����[���͒�����s��������ʏ�̗ʂ̌��Ⴂ�ɔ��s���A��@���������B �@����A����͒ʏ�A�܂��͓����{��k�Ђ̕�����Ȃǂ��l�����Ă��A�ʏ�̐��{���x�����A�~�s���Ȃ������B �@���ꂪ���ƂŁA�בփ��[�g�͋ɒ[�ȉ~���ɐ��ڂ��A70�~��㔼�܂ō������A�蒅���āA�A�o�Y�ƁA�Ƃ�킯���{�o�ς���������Ă����d�@�ƊE�A�����ԋƊE�͋ꋫ�Ɋׂ����B���ɔ����̊e�Ђ�Ɠd���[�J�͐Ԏ��ɓ]�����A��_�ȃ��X�g����]�V�Ȃ����ꂽ�B�����ԎY�Ƃ����l�ŁA�H��̊C�O�ړ]���i�B �@���������́w����̂Ƃ��Ă������Z����̊ԈႢ���x�ƌ������w�E���Ă���B ����̏펯�͊C�O�̔�펯�Ƃ܂Ō����Ă���B �@����Ɍ��킹��A�������ʂɔ��s����Ήݕ����l��������A�C���t���𑣂��A���̌��ʁA�肪�t�����Ȃ��u�n�C�p�[�C���t���v�ɂȂ�̂��|���Ƃ����_�@�̂悤���B����͈�ʋ��ʂ��Ă��邵�A�ԈႢ�ł͂Ȃ��B�N�ł�������B �@����ŁA����͓��{�̌o�ς̂��������������ȂƋ��ɒS���Ă���͂��ł���B ����(���{��s���j�̔��s���ƐӔC��S���Ă���̂ŁA�T�d�ɂȂ炴��Ȃ������̂�������Ȃ��B �@�������A�l�c�搶�̈ӌ��́A�C�O�A�A�����J��C�M���X�̒�����s����ʂ̎�������C�ɔ��s���āA�C���t���ɗU�����ă��[�}���V���b�N�̌��ǂ�H���~�߂��̂�����A���{�����l�ɂ��邱�Ƃňבփ��[�g���ێ��ł��A���̂悤�ȃf�t���Ōo�ς��k�����A��Ƃ⍑�����ꂵ�ނ��Ƃ��N���Ȃ������ƌ����Ă���B �@�ǂ����A���{�̌o�ϊw�҂�A�o�ϕ]�_�Ƃ�A�o�σW���[�i���Y���Ȃǂ́A����̊�F�����Ȃ��甭����s�������Ă�������������B �@���ꂼ��̐l�͎����̗����A�o����A������������̂ŁA����ɏ|�˂��āA���O����A���ꂪ��������Ȃ��Ȃ�̂�|�����Ă����B�N�ł����������킢���̂ł���B �@�l�c�搶�̓A�����J�̃C�F�[����w�ɋ߂āA�C�O������{���Âɒ��߂��闧��ɂ���B���������l�͐����������������A���������f���ł���B �@�����K�V���n�Ǝ҂����������Ă������ƂɁw�f���ȐS�ɂȂ�܂��傤�x�Ƃ������������邪�A�l�Ԃ̐g���肳�i���ȕېg�j���琶���镨���̐^�����������悤�ɂȂ��Ă͂�����Ƃ������߂̌��t�ł���B �@������A�w�Ԉ���������ɓ��{��U�����悤�x�Ƃ͌����Ďv���Ă��Ȃ��B ��ʂ̎������s�ŁA�בփ��[�g�̉~�����~���ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����l���A�����đ�ʂ̎������s�ň����N�������\��������n�C�p�[�C���t���̋���A���������v�����O���ł͂���Ă������Ⴂ�̉ݕ����s�ɑ����{�͑Ή����Ȃ������B �@���̌��ʁA���܂Ńf�t���͎~�܂炸�A�בփ��[�g���傫���~���ɐ��ڂ����̂��B �@���̈��{�����́A3�{�̖��ݒ肵�A���M���A���g��ł���B����͕l�c�搶�̍l������������Ă���B�܂�����̑��ق��X�R�����B����̊�{�I�ȍl������������𐳂����B �@�בփ��[�g��70�~�㔼�̒��~������}���ɉ~���ɂȂ�A����104-5�~�O��𐄈ڂ��Ă���B�P�h��100�~�O��ł���A���{�̊e��Ƃ͏\���Ή����邱�Ƃ��ł���̂ŁA�A�o�Y�Ƃ͊��C���o�Ă����B�H��̊C�O���獑���ړ]������悤�ɂȂ����B������������̌ٗp�����i�����B���ʂƂ��āA���̂Ƃ���̌i�C��A���{�̌i�C���f�͏㏸�ɓ]�������Ƃ������Ă���B �@���̂Ƃ���A�l�c�搶�̂��������ɓ����Ă���B �@���コ��Ɍi�C���ǂ��Ȃ邱�Ƃ����҂��Ă���B ���ЁA���̖{��ǂ�ł݂ĉ������B�ł��Ȃ��Ȃ���������܂���I�I |
�P���P�Q���i���j
�u�A�x�m�~�N�X��TPP���n����{�v��ǂ��
�l�c�G��i���t�Q�^�j��
�u�k��
�艿�P�S�O�O�~�i�ŕʁj
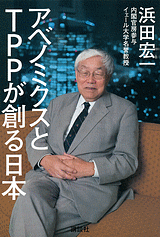
�����́HGDP�́H�����́H��`�����X����������!!
�S�O��Q&A�Œm��Q�O�P�T�N�̓��{
| �@���̖{��Q&A�̌`�ŁA�b���W�J���Ă���̂ŁA��ϓǂ݂₷���B �������Ȍ��œǂ�ł��Č�������Ȃ��B����̈ꕔ���グ��ƁA �@Q�F�Ȃ��A���{�o�ςɂ͋��Z�ɘa���K�v�Ȃ̂��H �@Q:�A�x�m�~�N�X�ł͂��l�̎�����������̂��H �@Q�F���Z�ɘa�Ńn�C�p�[�E�C���t�����N����̂��H �@Q�F�l����������������f�t���ɂȂ����̂��H �@Q�F��_�ȋ��Z������s�����A�����J�ł͉����N�������H �@Q�F�C���t���E�^�[�Q�b�g�ʼn����ς��̂��H �@Q�F�؍���TPP�ɎQ�����Ȃ��{���̗��R�Ƃ́H �@Q�F���{�o�ςɂ͂ǂ̂悤�Ȗ������҂��Ă���̂��H �@Q�FTPP�͓��{�_�Ƃ��ǂ��ς���̂��H �@Q�FTPP�œ��{��Ƃ͊O���ɏ�������̂��H �@Q�FTPP�œ��{�o�ς̋ߖ����͂ǂ��Ȃ�̂��H �ȂǂȂ� �@�l�c����̍l�����́u���t���h�v�ƌĂԂ炵���A���܂ł̓��{��s�▯��}��������̐����A�o�ϕ]�_�Ƃ̍l�����Ƃ͑傫���Ⴄ�B �@���{�o�ς̒���́A�w����⋌�������Ƃ��Ă����o�ϐ���̌�肾�x�ƌ������w�E���Ă���B �@Panasonic��V���[�v��Sony���T���X����LG�d�q�ɕ������̂��A�~���̗e�F�ō��ۋ����͂��ቺ�������Ƃ��v�����I�Ƃ��Ă���B �@ �@���܂ŁA��������Ă����̂́A���{�͋��z�̍����Ԏ��łP�O�O�O���~�ɏ��؋����ςݏオ���Ă���B��������Z�ɘa������o���͍T���Ȃ���A�n�C�p�[�C���t���Ɋׂ�����j����Ƃ������̂������B �@���������͒ʉݐ��������A��s�݂͑��a��ɓO���Ă����B���ʂ͑��Ƃ��瓊������]�T���Ȃ��A������Ƃ͎����J��ɍs���l�܂�|�Y���p�������B �@�l�����ɂ����Ă��������オ�炸�A�ނ��뉺���邱�ƂŁA����ɏ��������f�t���X�p�C�����Ɋׂ��Ă����B �@ �@���̌�����Q�O�P�Q�N�N���ɔ�����������{���t�ł́A���Z����̑�]����}�����B���ꂪ���ɂ����w�A�x�m�~�N�X�x�œ��e�͂R�̖�琬�藧���Ă���B�@�ȒP�Ɍ����ƁA �@�@��_�ȋ��Z�ɘa �@�A�@���I�ȍ������� �@�B�K���ɘa�ɂ�鐬���헪 �@�܂��A��_�ȋ��Z�ɘa�����s�����B ����́A���܂ł̓��₪�Ƃ��Ă������o���̋��Z�ɘa�ł͂Ȃ��A�v�������ی��̂Ȃ����Z�ɘa�Ƃ�����@�ŁA�w�K�v�Ȃ����o���܂���x�Ƃ������M�ł������B �@���܂ł́A�w�n�C�p�[�C���t�����N����I�x�Ƃ��������ł���̓^�u�[�ł������B ������t�ɋ��s�����B �@ �@���̂P�O���N�ԁA���{�̓f�t���ɋꂵ��ł����̂ŁA���܂łƂ͑S���Ⴄ�����̐����ł��Ȃ���f�t���E�p�̕����]�����ł��Ȃ����Ƃ͕������Ă����B ����ł���̓^�u�[������Ă����B �@ �@�l�c����̌������́A���������A���̓��{�̃f�t���̓A�����J�̃��[�}���V���b�N�������ł������B���̐k���n�̃A�����J�͂��łɃ��[�}���V���b�N�O�̌i�C�ɉ��Ă���B���[���b�p�����l�ɉ��i��ł���B �@�w�Ȃ����{�����P�O�N�ȏ���s���������Ă���̂��H�x�Ƃ����^�₪�c��B ����͓���̌o�ϐ��Ԉ���Ă������炾�I�ƒf�߂��Ă���B �@ �@�A�����J�́A�o�ϑ�Ƃ��Ēʏ�̂R�{�ɏ��ʉݗʂ𑝂₵�A�h���������s��ɏo�����B���[���b�p���l�ɑ��₵���B���̌��ʁA���{���������Z�������߂𑱂����̂ŁA�~�����i�݁A�A�o�Y�Ƃ��傫�ȒɎ�������ނ����B �@�����ԎY�Ƃ�A�Ɠd�Y�ƊE���ꂵ�Ƃ����\�}���w�E����B �@������A�A�x�m�~�N�X�́w�ی��̂Ȃ����Z�ɘa���s���x�w�K�v�ȑ�������ł��x�Ƃ������Z�ɘa������Ƃ邱�ƂŁA�~������~���ɗU�������B����ɐ���������B �P�h�����V�O�~��̒��~������A�P�h���P�O�T�~�O��̉~���ɕς�����B����͂Q���ȏ�̈ב֎��x���P�ɂȂ�B �@ �@���܂Ō����Ă����P�O�O�O���~�ɏ�鍑�̎؋�������Ȃ���A���Z�ɘa������Ύ؋����ςݏオ��A���̌��ʁA�n�C�p�[�C���t���ɂȂ�肪�t�����Ȃ��Ȃ�Ƃ����l�����Ƃ͑S���t�ł���B �@���݂̏̓f�t����E������悤�Ɋ����邪�A�܂��E�o�����Ƃ͌����Ȃ��B��͂�A�������オ��Ȃ���A��X�����̎����ɂ͂Ȃ�Ȃ��B �@������̉ۑ�ATPP�ɂ��Ă��{���͂Q�ڂ̃e�[�}�Ƃ��Ď��グ�Ă���B ������A���{�����͍��܂łƂ͈�������g�݂����悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃł���B �@����͔_�Ɛ��I ���{�̔_�ƁA�R���͊O���Y�̈����R���ɑR���邽�߂V�V�W���i��W�{�j�̊ł������Ă���B����ŗA����H���~�߂Ă����B �@�������ATPP��i�߂邽�߂ɂ͗�O�Ȃ��œP�p���O��ƂȂ�B���{�̔_�ƁA���̑�\���R���_�ƁB�œP�p��������ǂ���ɗ����s���Ȃ��Ȃ�B����ł�����A��p�������Ȃ��A�Ȃǔ_���̉ߑa����A�k������n���g�債�Ă���B �@ �@TPP�ɎQ�����邱�Ƃ́A���{�����ӂƂ���A�o�ʼn҂�����͑傢�ɉ҂��ŁA�R���_�Ƃɂ͏����⏞���Đ����ۏႷ��Ƃ���������Ƃ�����Ƃ����l�������B�@�@����ł����ۓI�Ɏア�_�ƕ��������ȏ�ی삷��Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�ア����͐������ł���悤�ɕۏႷ��B �@�������������]���Ɏ��g�����Ƃ��Ă��邪�A�_����_���iJA)�Ȃǂ͊������v�̕����ɂȂ���̂ő唽�Ή^����W�J���Ă���B �@ �@��R�̖�ł��鐬���헪�́A�ނ���_�Ƃ����̍ہA���ގY�Ƃ��琬���Y�Ƃɓ]�������悤�Ƃ����l�����ł���B���{�̔_�Y�i�͖����悭�A���h�����悭�A�i���������Ƃ��������]�����C�O�œ��Ă���B���������̕����i�͍����B �@�������C�O�̕x�T�w�ɂƂ��Ă͂������̂₨���������̂�H�ׂ����Ƃ����j�[�Y�������B�\�����@������B �@�����Ȃ�A�ʓI�ɂ͑����͂Ȃ����A�t�����l�̍����_�Y�i���A�o�ł���`�����X���g�傷��BTPP�͍H�Ɛ��i����ł͂Ȃ��A�_�Y�i�ɂ��Ă��A�o���g��ł���`�����X�Ȃ̂ł���B �Ƃ����b�ɂȂ��Ă���B �@����ȏ�̏ڂ������e�́A���Ж{����ǂ�Œ��������B �A�x�m�~�N�X���v�f�ʂ�ɓW�J���A���{�o�ς��D�]���A�Ăь��C�ȓ��{�ɂȂ��Ăق������̂��B |
20140101
�މ�V�N
| �@�V�N���߂łƂ��������܂��B �@ �@���N�͌ߔN�i���܂ǂ��j�ł��B �@�n�͑������邱�Ƃ��ł��܂��B�x�n�Ƃ������܂��B �܂��A���܂ꂽ�Ă̎e�n��1���Ԃقǂŗ����オ��A���̌シ���������Ƃ��ł��܂��B �@����͑��H�����̏K���ŁA���܂ꂽ�Ă̎e�n�͊O�G�ɏP����`�����X�������̂ŁA���������̐g����邽�ߗ����オ��A�삯��悤�ɂȂ����̂ł��傤�B �����A���M�������悤�ɗ����オ�邱�Ƃ��ł��܂��B �@�܂��A�w���������܂����x�Ƃ������ƂŁA���������A����N�ƌ����܂��B �@ �@�������A�v��⌈�ӂ��Ȃ���A�����������������܂���B ������1��10���ɂȂ�A�̐l�H���w1�N�̌v�͌��U�ɂ���x�Ƃ������Ƃł����A1�����܂łɂ́A��N�̌v���������Ɨ��ĂĎ��g�ނ��Ƃ���ł��B �@���������v��𗧂ĂĎ��g�ސl�ƁA�N���A�̂�ׂ��߂����l�Ƃł́A���N������Ή_�D�̍��ƂȂ邱�Ƃł��傤�B �@ �@���̍��N�̌v��́A���̐��N�Ԏ��g��ł����d�C��C�Z�p�Ҏ��i�ł���w�d��3��x�ɍ��i���邱�Ƃł��B �V�O�ɂȂ��Ă��܂��牽�����悤�Ǝv���Ă���̂��H�Ǝ��⎩�����܂����A��肩�������Ƃ�r���ŃM�u�A�b�v�������Ȃ��̂ł��B �@���̎��i�����͊�b�i�d���C�w�j�Ƌ@�B�Ɠd�͂Ɩ@�K�̂S�Ȗڂł��B �Ȗڍ��i�͂S�Ȗڂ��ׂĂ��I���܂������A�R�N�Ԃ̗L�����ԓ��ɂS�Ȗڂɍ��i���Ȃ���Ȃ�܂���B��������܂��g�ݍ������ƂɎ��s���A���N�͖@�K�݂̂������̂ł����A����Ɏ��s���A��N�͖@�K�Ɗ�b�̂Q�ȖڎāA�@�K�����i���܂������A��b�Ɏ��s���܂����B���܂܂Ŗ@�K�ɍ��i�������Ƃ��Ȃ������̂ł����A��N���߂č��i�ł��܂����B �@���N�͍ēx�A�w��b�x�ƁA�w�@�B�x�Ɓw�d�́x�̂R�Ȗڂ��Ȃ���Ȃ�܂���B ���̐��N�ԁA�����߂�������Ă���悤�Ȋ�������܂��B �@ �@�L���͂�v�Z�X�s�[�h���Ƌ��ɗ���̂�g�������Ċ����Ă�������ł��B�Ⴂ���Ȃ炷���Ɋo������A�v�Z�ł������Ƃ��Ȃ��Ȃ�����Ȃ�i�݂܂���B �����������v���ł����A���N�͔N�v����������[�߂悤�Ǝv���Ă��܂��B �@���ꂪ���̍��N�̖ڕW�ł��B �@���̂������́A��l�̖��v�w�Ƒ�3�l���W���A�����͉Ɠ��Ɠ�l�̂Ђ����肵���䂪�Ƃ���ςɂ��₩�ł����B �@3���͑��̊�]�ŁA�z���_�̗鎭�T�[�L�b�g�ɍs���A��������̏�蕨�ɏ��܂����B�ƌ����Ă������̓J�����ƃr�f�I�B��ɏW�����܂����̂ŁA��蕨�ɂ͏���Ă��܂��E�E�E�B �@12���̔��Ƀt�B�b�g�R������Ɠ͂��܂����B����ƂƂ����̂͂R�����҂��ł�������B�Ԃ̃y�[�W�ɏ��������܂������A�V�����w�t�B�b�g�R�x�ŗ鎭�T�[�L�b�g�ɖ��v�w�Ǝ�3�l�Ƒ���l�̂S�l��Ԃōs���܂����B �@���s�����͉����łQ�O�O�������炢�ł��B�R���25.5����/L�ł����B �@��Ԑl�����������ɔR������̂ɖ������Ă��܂��B �@�ŋ߂̎Ԃ́A�N���X���X�Ƃ������t������悤�ɁA�t�B�b�g�N���X��100���~��̎Ԃł��A���܂ł�200���~��N���X�̎ԂƂ����ς�Ȃ������A�O�ρA���S�n�A�Â����A�����ɂȂ��Ă��āA��ϖ������Ă��܂��B �@���̑O�̎Ԃ́w�t�B�b�g�Q�n�C�u���b�h�x�ŁA2�N7�����������܂���ł����B���̎Ԃ��悭�ł����Ԃ��Ǝv���܂����A�n�C�u���b�h�Ƃ����ʂł͊����x�����܂����ŁA�R������܂����ł����B�������H�̑��s�ōō��R�21����/L�����X�ł����B �@�v���E�X��A�N�A�ɔ�ׂ�ƁA���Ⴟ���n�C�u���b�h�Ԃł����Ȃ������Ǝv���܂��B ����́w�V�^�E�t�B�b�g�R�x�́A�{�i�I�ȃn�C�u���b�h�ԂɎd�オ���Ă��܂��B �@�v���E�X��A�N�A����_�͏o���̗ǂ��ł��B����o���̓��[�^�Łw�q���C�[���x�Ƃ������[�^�����������܂��B���̌�A�G���W����������܂��B�����S�O�`�U�OK���łĂ����s���̓��[�^�ő���܂��B �@ �@�ȑO�A�F�B�̃v���E�X�Ɏ��悳���Ă��炢�܂������A�o���������������܂����B�������邢�̂ł��B���̓_�A����́w�t�B�b�g�R�x�̓n�C�u���b�h�炵����ʁH�o���ŁA�������������Ƃł��B�������܂���B����ł��ĔR������̂ł��B �@�����A�g���^�̎Ԃ́w����x���悭�ł��Ă��āA���ɓ����̍����ł͂҂���ł������A����́w�t�B�b�g�R�x�͓����ʂł��V�[�g�n��A�_�b�V���{�[�h�̎���̓����ނ�������������܂��B �@���Ƀh�A�[�̓h�V���Ƃ��������A�d�ʊ��ƁA�܂�ۂ̃h�V���Ƃ����������Ƃ������Ȃ����������������܂��B�����ԕ��݂̊����ł��B �@�A�蓹�A163�����ňꕔ�a������܂����B���̎��A�i�r���������O��ċ��������ē����܂��̂ŁA���̂Ƃ���ɑ���ƁA�a�ؒn��̂R�����قǐ�ɏo�āA�������A�a������ł��܂����B �@���̃z���_�����i�r���C���^�[�i�r�V�X�e���ƌĂԕ������̗p���Ă��܂��B �i�r�͍��܂�GPS�d�g����M���āA���݈ʒu�ƍs�����\�����邱�Ƃł����B �@�V�����C���^�[�i�r�V�X�e���͓��H�����펞��M���āA�a���Ă���ꍇ�́A������T���@�\�����Ă��܂��B �@�P�Ȃ铹�H�n�}����̃i�r����A���s���̓��H������肵�Ȃ���A�ł��K���铹�H���ē�������悤�ɕς���Ă��܂��B����ɁA�Ԃ��玞�X���X�̓��H���M����A�b�v���b�N�@�\���t���Ă��܂��̂ŁA�C���^�[�i�r�������ԓ��m�̊ԂŁA�œK�ȑ��s���ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B���̃f�[�^�̓z���_�̃T�[�o�ɏ펞�~�ς���A�������r�b�O�f�[�^�Ƃ��ďW�ς���A�����ȖʂŊ��p�����悤�ɂȂ��Ă��܂��B�@����ɂ͂т����肵�܂����B �@����́w�t�B�b�g�R�x�ɂ͎v������8�C���`����̂��̂ɂ��܂����B���܂ł͂V�C���`�������̂ŁA�����ɂ��������̂ł����A�W�C���`�͂�͂�傫���āA��ό��₷���A�n�}�̕\�������邭�A�V��ɂ͏�����܂��B�吳���ł����B �i�r�̃��[�J��Panasonic���ł��B �@�ŋ߁A�V�j�A�����Ƃ������x�������ȂƂ���ł���A���̊Y���҂ɂȂ�܂����B�鎭�̓��ꌔ�������œ���܂��B�������A�N����ؖ����鉽���̒����߂��܂��B����Ȃ킯�ŁA�������͓��₩�ȂЂƎ����߂����܂����B �@�l�ɂ��A���̏�Ԃ��w���䕗������Ă��āE�E�E�x�Ƃ����l�����܂��B �@���N���A��N�A���C�ɁA���N�ʼn߂��������Ǝv���܂��B �@�{�N���ǂ����A���t���������������B |