2016年12月13日(火)
高速増殖炉と軽水炉の違いは?
危険性はないのか?
2016年12月10日(土)
高速増殖炉もんじゅのパブリックコメント
| 政府(自民党)は原発の再稼働を着々と進めている。12月9日付朝日新聞朝刊によると、福島原発の事故の後片付け(事故処理)に21.5兆円というとてつもない巨額の費用がかかるとされている。当初想定の2倍に上る。この費用は福島第一原発の事故の廃炉費用と、被害者賠償費と、汚染費用、中間貯蔵施設費の合計金額である。 20兆円がいかに巨額であるかは、下の11月29日の記事で紹介した。今後、この費用はもっと膨らむ可能性を秘めている。 そういう未曽有の原発事故を経験しながら、まだ恐れを知らずに『高速増殖炉もんじゅ』の開発について諦めきれないようだ。 「高速増殖原型炉もんじゅの安全確保の考え方」の国際レビュー報告書(パブコメ) 日本原子力研究開発機構 高速炉研究開発部門もんじゅ運営計画・研究開発センター (2015 年9 月24 日受理) 東京電力福島第一原子力発電所における重大事故から得られた教訓に鑑み、日本原子力研究開発機構が設置した「もんじゅ安全対策ピアレビュー委員会」は、高速炉特有の安全特性を考慮して、報告書「高速増殖原型炉もんじゅの安全確保の考え方」を2014 年7月に作成発行した。 同報告書につき、独立した客観的な立場からの公正な評価を得るべく、5か国及び1国際機関の高速炉安全性に関する主導的専門家によるレビューを実施した。各小節につき国際レビューにより得られたコメントを収集・整理し、それに基づいてレビュー会議の議論や個別のフィードバックを経て、最終的な結果をまとめた。 その結果「もんじゅ」の重大事故の発生防止と影響緩和に関する基本的考え方は、高速 炉特有の安全特性を考慮すれば適切であり、また、国際的な共通認識にも一致している ことが確認できた。 2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震とそれに引き続く東京電力福島第一原子力発電所での重大事故(以下、東京電力福島事故)以来、我が国のほぼ全ての原子力発電所は運転を停止している。全原子力施設は、東京電力福島事故を教訓として策定された新規制基準に基づき、新設された原子力規制委員会(以下、NRA)による許認可手続きを経なければならないとされている。 2013 年7 月に施行された実用発電用原子炉である軽水炉に対する新規制基準では、重大事故と自然ハザード等に対して、新たな厳しい要求が課されている。 この実用軽水炉に対する基準と同時に、NRA は研究開発段階発電用原子炉である高速増殖原型炉もんじゅに対する規制基準を施行した。 この研究開発段階発電用原子炉に対する規制基準は、今後NRAにおいて安全審査を行うまでに、パブリックコメントによる意見も含め改めて検討し基準を見直すこととされている。 これを受けて、日本原子力研究開発機構(JAEA)は、科学的および技術的知見・洞察を踏まえて重大事故を考慮した「もんじゅ」の安全確保の考え方を自ら独自に確立すべく、「もんじゅ安全対策ピアレビュー委員会」を設置した。 同委員会は、高速炉技術および安全性研究に精通した専門家により構成した。 同委員会は公開報告書1)「高速増殖原型炉もんじゅの安全確保の考え方」(以下、原報告書を作成発行し、2014年7月にNRAへ提出した。 この原報告書について独立したより客観的な立場からの公正な評価と記載された「もんじゅ」の安全確保の考え方や要求事項が国際的な共通認識に適合しているかどうかの確認を得るため国内及び国際的な高速炉安全性の専門家に同時併行してレビューを依頼した。本報告書では、その内でも国際レビューの実施と結果について報告する。 本レビューは、各国の高速炉安全性に関する主導的な専門家に委託して実施した。 付録1 に示すように、中国、仏国、韓国、ロシア、米国、及びEU(欧州連合)から計9名の 専門家を選任しており、いずれも各国の高速炉計画に於いて高速炉安全設計・評価に責任ある立場の方や国際的組織を代表する方々である。 全員が、例えば第4世代原子力システム国際フォーラム(GIF)や国際原子力機関(IAEA) のような国際協力プログラムにおける重要メンバーとして活躍している 全レビュー者が合意に達したレビューまとめの最終版を、国際レビューの結果として本章に示す。既述の通り、本レビューは公開報告書「高速増殖原型炉もんじゅの安全確保の 考え方」の第4章と第7章を対象として、9名の国際的専門家へレビュー用に事前送付して実施した。 レビュー結果は、コメントや意見と共に収集整理し、更にレビュー会議での議論を踏まえて改訂した。以下、レビューの結果を、原報告書の元の章番号、節番号、表題(イタリックで記載)を参照しまとめた。 3.1 原報告書第4章について 4.2.1 炉心の著しい損傷防止 (1) プラントの内部事象から選定される事故シーケンスグループプラントの内部事象に起因する事故シーケンスが「もんじゅ」の設計上の特徴に特有のシーケンスも含め、網羅的PRAと決定論的評価に基づいて系統的に特定されている。 よって、事故シーケンスグループの選定方法と選定結果は、適切なものと判断する。 これらは、例えばIAEA が整備した一連の安全基準のような最新の国際標準にも基本的に 適合するものである。 (2) 地震・津波来襲から選定される事故シーケンスグループ 外部事象に起因する事故シーケンスグループが、地震及び津波に関するイベントツリ-7ー 分析の結果に基づき、適切に特定されている。全交流電源喪失(以下、SBO)シナリオを 過酷外部ハザードの代表的事象進展の帰結として選定することは、全ての主要な外部起因事象に対処するためには妥当なものである。本レビューの対象外ではあるが、公開報告書の他の章に記載の考え方によれば、地震と津波以外の外部ハザードについても、同様に検討することとされている。 (3) ナトリウム冷却高速炉の特徴を踏まえて論点となり得る事象についての検討 局所事故や気泡炉心通過、或いはナトリウム漏洩や他のナトリウム反応事象は、SFR (sodium-cooled fast reactor)に固有の事故起因事象候補として重要であり、これらは事故の発生防止と影響緩和のための安全設計と共に、設計基準事故(DBA)の範疇で網羅的に扱われる。ここでは重大事故を念頭に置いており、例えば集合体入口瞬時完全閉塞(TIB)のような、どちらかと言えば重大な局所事故の取扱いが論点となる。 しかしながら、極度に仮想的な特性や極めて低い発生頻度に照らしてみると、このような事象を重大事故として位置づけることは不適切であると考えられる。 したがって、TIB 事象は事故シーケンスグループからは実質的に除外できるものと判断され、この考え方は世界共通で採用されている最新のSFR 安全アプローチとも一致する。 各種局所事故シーケンスを代表し包絡する安全評価のために、TIB 事象を非機構論的、且つ決定論的な方法で、BDBA(設計基準外事故)の範疇に含める、と言うアプローチも あり得るかも知れないが、「もんじゅ」の場合、発生確率が無視できる程度に小さく、 その影響は炉心流量喪失時原子炉停止機能喪失(ULOF)事故に代表される全炉心事故に十分包絡されるので、事故シーケンスグループとしては選定する必要はない。 4.2.2 使用済燃料貯蔵槽内の燃料損傷防止 (1) 炉外燃料貯蔵槽(EVST) EVST に関する事故シーケンスグループ選定の考え方と選定結果は、「もんじゅ」の設計上の特徴を踏まえており妥当である。すなわち、EVST 崩壊熱除去系の多重性と多様性を持たせた設計や、その妥当性を実証する事故解析結果を踏まえて同グループが選定されている。燃料移送中や取扱中の潜在的事象や臨界事故についても配慮されている。 (2) 燃料池 燃料池に関する事故シーケンスグループ選定の考え方と選定結果も、燃料池に移送される使用済み燃料の崩壊熱レベルは十分に低いため十分な猶予時間がある、と言う「もんじゅ」の設計上の特徴を踏まえており妥当である。 4.2.3 運転停止中原子炉内の燃料損傷防止 選定された事故シーケンスグループは、「もんじゅ」運転停止中の多種多様な事故を包含している。また、既往の設計対応は、それらシーケンスにおける燃料損傷を回避するに十分なものと判断する。 上記の文章は、もんじゅを何とか動かしたいという立場の側からまとめたもので、難しい内容に見えるが、要は世界のこの道の専門家や識者から意見を聞いた。 そしてもんじゅの設計から考慮すると、東日本大震災による福島原発事故と比較しても、もんじゅは大丈夫だというシナリオになっている。 果たしてそう言い切れるのだろうか? |
2016年11月29日(火)
福島原発事故対策費20兆円が意味するものは?
| 最近、耳にするようになった福島第一原発の廃炉費用が20兆円という話。 考えてみると、日本の国家予算が28年度一般会計で96.7兆円、約100兆円規模です。 その内訳は、税金等の歳入は58兆円しかありません。残りは公債、すなわち国の借金で34兆円賄っています。残りは約4兆円はその他の歳入となっています。 福島原発の後片付けの費用が当初2兆円ぐらいと言われていたのが、5兆円になり、10兆円になり、今や20兆円とも言われています。 この金額がいかに巨額かということは、日本の国家予算の20%以上にも上る数字です。 通常、100万KW級原子力発電所1基建設するのに約5,000億円かかると言われます。 20兆円もあれば何と、原発が40基も建設できる費用です。 日本の原発は全部で確か57基?だったと思いますので、福島第一原発の1,2,3号機の後片付けのためにいかに巨額の費用が掛かるかという実態を皆さん余り気にしていないようです。 さらに、20兆円は現状のラフな見積りだと思いますので、まだまだこれからドンドン増える可能性もあります。まず減ることはないでしょう。 原発を片付ける作業は、放射線被爆という非常に危険な作業がつきものですから、念入りに十分な被爆防護対策をしながら作業しなければなりません。それでも被爆することは避けられないので、作業員には被爆手当(危険作業手当)を支給します。作業員は被爆を覚悟で働いているです。 何とか事故処理を終息したいという願望ですが、40年かかるとも言われています。20兆円をかけて後片付けが済んだとしても福島原発は片付いたというワケではありません。 デブリというウラン燃料がドロドロに解けた残骸を分厚い金属製の容器に入れるまでの作業だと思います。どういうふうに入れるか、まだその作業の内容や工程が決まっていない状況です。もし、うまい方法が見つかって、容器にデブリが収納できたとして、それをどこに保管するのでしょう? 今回の東日本大地震が起きるまで、通常通り稼働している日本の57基?の原発の燃えカス(放射性廃棄物)の処理や保管方法や保管場所が決まらないので、燃料棒は各原子力発電所内の建屋内のプール(水槽)に漬けている状態です。 小泉元総理はこれを『トイレのないマンションに住んでいるようなものだ!』と言いました。言い得て妙の言葉です。 原発のウランはジルコニュウムという金属でできた合金の棒に入れていますが、この燃料棒からは常に強い放射線(α線、β線、γ線)が出続けています。 水はこの放射線を吸収し弱める働きがあるためプールに水を入れて、その中に燃料棒を浸して核分裂が進まないようにして保管しています。 このプールの水がなくなると、燃料棒から出る放射線が互いのウラン原子の核分裂を促し、核分裂が起き始め、その結果、発熱が激しくなります。ですから燃料棒を保管するプールの水は絶対なくならないように維持する必要があるのです。 福島原発事故で一番恐れたことは、1,2,3号機ではなく4号機だったのです。 4号機は定期点検中で、炉心から燃料棒を取出して保管プールの中に入れた状態でした。もし、このプールが地震でヒビが入り、水漏れして燃料棒が水につからない状態になれば、核分裂反応が進んで臨界状態になれば、何の囲いもない状態で猛烈な放射能が空気中に放出され、間違いなく東日本一帯は人が住めない状態になるところでした。東京ですら危険な状態になったと思われます。 幸いなことに4号機のプールの水漏れはなくて大事故になりませんでした。 今は、1,2,3号機の炉心冷却に失敗し、水素爆発により原子炉がメルトダウンしたことばかり伝えられていますが、原子炉は30cmもある分厚い鋼鉄製の炉心(圧力容器)と、その周りを数mの分厚いコンクリート(原子炉収納容器)で囲っています。 それでも核分裂による数千度の高温になったウラン燃料は30cmの鋼鉄製の圧力容器を溶かし、その底から灼熱のウラン燃料が溶け落ち、数mのコンクリートも溶かしたのです。これがメルトダウンという状態です。何とか数十cmぐらいのところで留まったということです。 もしこの数mの厚みのコンクリートの壁が溶けてしまい、その底から地中にデブリが溶け出たとすれば、今のような状態で収まらなかったのです。 必死に海水を消防車でくみ上げて、放水し続けて冷やした結果、何とか灼熱の燃料が冷えて固まったのです。 しかし、原子炉の内部は燃料棒が溶け落ちてしまっているので、正常な原子炉の格納容器の片付け作業のようには参りません。 原子炉内部は放射線量が非常に強くて、人間が近寄ることができませんので、ロボットを使い遠隔操作で何とか溶け落ちたデブリを処理しようと取り組んでいます。今はそういう方法で何とかしようと懸命に技術開発している段階です。こういう事故の状況は世界でも初めてのことですから、作業が前になかなか進まないのです。 強烈な放射線にさらされると電子回路が壊れてしまい、電子カメラも画像が乱れます。この猛烈な放射線に耐えるロボットの開発からしなければなりません。 それが何を意味するかです。それは膨大な開発費用と時間が必要だということです。技術の戦いです。そして最後は、人間が作業しなければならないのです。 それが今、20兆円の片づけ費と言われ出したのですが、これで収まるかどうか全くわかりません。 20兆円で後片付が出来たとして、そのデブリをどこに置くのでしょう。 通常の原子炉の燃えカスの燃料棒でさえ置き場所がなく、仕方なく各原発の所内のプールに保管しているのが実態です。 政府、自民党は原発をベースロード電源と位置づけしました。これは原発は燃料を一度炉心に入れると、通常1年間は何もしなくても、昼夜一定の発電が出来ますので、発電事業側の立場からすれば非常に都合がいいわけです。だから、全国の電力量の30%程度を原発の電力で賄おうと考えているのです。 今、すでに57基の原発があり、そこには燃料のウランがプールに眠っているのです。それを使わない手はないだろう!というのが、再稼働推進派の人たちの考え方です。 のど元は未だ過ぎていませんが、もう過ぎたかのように、福島原発の事後処理に手を焼いていながら、その姿を見ていながら、「世界一厳しい安全基準で審査し合格した原発は稼働を始める」と言う方針を打ち出しました。 原発は危険がなく稼働できるものなら、これは一つの考え方ですが、今回起きたような事故が再び絶対に起きないとは言い切れません。 なぜなら、日本は国土が太平洋プレート・北米プレート・ユーラシアプレートという3つのプレートが交錯する位置にあります。このプレートの境界線では常に巨大地殻変動のエネルギーが発生し、巨大地震や火山噴火がつきものです。  上図は地球のプレートの交錯地点で、地熱が高く地震が多い場所を赤線で示しています。 南北アメリカの太平洋岸、東南アジア、日本、地中海沿岸、アイスランド等はまさに火山国であり、地震国です。 このように日本はプレートが交錯する国土であることをまず理解しなければなりません。 生まれて死ぬまで、人生で地震を知らない人が多い中で、我々日本人は地震に慣れ過ぎています。慣れると怖さが和らぎます。しかし、地球規模の巨大地震は必ず訪れる地理的条件の国土に住んでいることを忘れてはならないのです。 人間の力は自然界の力に及ばないことは昔からよく言われています。 現在の最先端科学をもってしても、自然現象を克服することは不可能なのです。 人間は、知恵や技術の進歩で自然現象を乗り越え、それを制御できたかのような錯覚を持つようになりました。 そして、人間が自然の力に負けた時は、『想定外の出来事だ』という言い訳をするのです。 所詮、人間が自然に対抗できるのは人間が想定できる範囲のレベルに対してのことです。それを忘れては、人間は滅びるしかないと思います。 |
2016年10月5日(水)
『世界史の大転換』を読んで
佐藤 優
宮家 邦彦
常識が通じない時代の読み方
PHP新書
820円(税別)
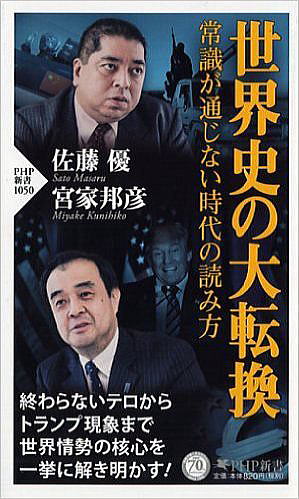
| 最近、書店に並ぶ書物のタイトルを見ると、『大転換』という文字がいやに目につく。それだけ、我々は、世界情勢が大きく変わろうとしている中に置かれているのだろう。 アメリカ大統領選が11月に迫ってきた。クリントンと話題のトランプ氏が争っている。共和党のトランプ氏の発言や行動をテレビで見ると、今までのアメリカの大統領でなかった激しく、少々下品とも思える振る舞いが誰の目にも明らかだ。こういう人物が成熟した民主主義国家アメリカ大統領として、最後まで残ったという事実は、大国アメリカ社会も今までにない様変わりし、苦悩している証拠だと思う。 イギリスがEUから抜けるという話も具体的になった。そもそもEUはヨーロッパ経済圏を構築し、大きな枠組みで経済の活力化を進め、将来は国家連合のような柔らかな統一を図ろうとして取り組んできた。そのEUもイギリスの脱落や、ギリシャの国家財政の破綻寸前で、今までの流れが大きく変わろうとしている。さらにスペインのカタロニア地方(バルセロナ中心)が国家として独立を企てる動きもある。 アジアでは中国が中華思想の下に、東に、南に、西に、と領土拡大の動きを露わにしている。中国はアヘン戦争でイギリスに負け、その後、日清戦争で負け、列強の餌食になった屈辱の時代を経て、今、リベンジを企てているような動きが見える。 こういう世界の動きは最近、急激に高まり目立ってきた。 そこには何が要因としてあるのだろうか? 社会の動きや変化が起きるためには、何か必ず要因がある。 現在、起きている『世界の大転換』の背後にある要因は何か?を本書はひも解いている。しかし、政治、宗教、経済、文化、人種、民族、歴史などいろんな要素が絡んで起きている現象なので、複雑怪奇な話になり、なかなか読み応えがある。 9月27日の『量子コンピュータ』の記事や内容は、物理的な話で難解だったが、今回の話は、世界の動きが対象なので断片的には理解しやすい。しかし、その断片が統合され、複雑に絡み合い、各国の動きに方向性を与えていると言えるので、読み解くのはなかなか難しい。 政治や経済はそういう複雑な動きの中で、自国の利益を最大化しようという取り組みだと言える。国益の最大化である。 本書の組み立てを紹介すると、 第一章:ポスト冷戦の終わり、甦るナショナリズム 第二章:ISを排除しても中東は安定しない 第三章:中央アジアは「第4次グレートゲーム」の主戦場 第四章:「国境のない欧州」という理想はテロで崩れるか 第五章:トランプ現象に襲われたアメリカの光と闇 第六章:中国こそが「戦後レジュームへの挑戦者」だ 終章 :「ダークサイド」に堕ちるなかれ、日本 となっている。 一言で世界情勢を言い表すならば、『世界がグローバル経済になり、金や人が自由に世界を駆け回り、経済の枠組みが国単位から世界が舞台になったこと。 それにより、世界中の金が利益を求めて駆け巡り、その結果、富める部分と、そうでない部分(本書ではダークサイドと表現している)に分化してきた。これは一国内でも言えるし、世界を視野にしても言える。強いものはますます強くなり、弱者は置いてきぼりを食う時代に入った。 日本の強さは、中間層がしっかりしていたことだが、現状は従来の中間層が弱者層(ダークサイド)に陥落する動きが見え、経済を支える循環が崩れてきている。 日本は国内需要がGDPの60%程度あり、そういう意味ではまだまだ経済力はある。 国内需要と、貿易を両立させることで、安定的な経済発展ができる素地がある。 中国は人口が日本の10倍(12億人)もあるが、貧富の差は激しく、GDPに対する国内需要率は低い。韓国も国内需要率は極端に低い。韓国は貿易に頼って経済発展を遂げてきた。一時はウォン安で、半導体やテレビなどサムスンやLG電子に代表される電子産業が急速に成長した。これは日本が70円台、80円台の超円高の時代に韓国はウォン安を活かして、貿易を急拡大し、あっという間に主客が逆転した。その韓国は最近、ウォンが高くなり成長率に陰りが見える。 さて、日本は、これからどうすればいいのか? それが本書の最終章で述べられている。 興味がそそられる部分だ! |
2016年9月27日(火)
『量子コンピュータが本当にすごい』を読んで
竹内 薫 著
PHP新書
840円(税別)
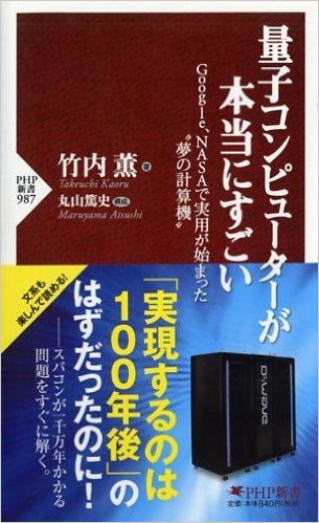
| 量子コンピュータという聞きなれない言葉がある。コンピュータと言えば、パソコンやスーパーコンピュータ(スパコン)という言葉が思い浮かぶ。 量子コンピュータと、今までのスパコンとは、全く構造や動作が異なるもので、量子コンピュータは、日本のスパコン『京』が1千万年かかる問題(計算)をすぐに解くことができる夢のコンピュータである。 日本のスパコン『京』は計算速度が1京分の1秒という速さで、当時は世界最速であった。その消費電力は約3万戸分、1.2万KWである。 民主党の業務仕分け会議で、当時の蓮舫議員が「なぜ世界一でないといけないのでしょうか?」という名セリフを残したスパコンの開発費の件ですが、京は1120億円の巨額の費用がかかっています。 さて、量子コンピュータが実現するのは100年後と言われてきたが、初期の量子コンピュータが既に商品化されました。 大学で学生時代に量子力学を学んだことがある。量子力学は講義を受けても全く理解できなかったのを覚えている。ただ、量子という言葉だけが頭に残っていた。 現在のコンピュータは、日常使う10進法(1,2,3,4,5,・・・9)と違って、2進法(0、1)を使っている。正しくは16進法(1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F )を使っている。これは2進法では、桁上げが激しく起きるので、16進法の方が扱いやすいからということ。 2進法は、簡単に言えば、「ある」場合は1、「ない」場合は0として表示する。これを電気的に置き換えて、例えば1の場合は5ボルト、0の場合は0ボルトというように電圧がかかるか、ゼロかに置き換える。これを論理回路(AND回路やOR回路やNOT回路など)の電子回路で構成し半導体集積回路で、いろんな計算や記憶や命令を出す回路構成にして、コンピュータとして構築している。 半導体の集積度が非常に大きくなり、それにつれて性能が向上し、現在の高速、高性能なコンピュータになった。パソコンですら計算速度は今まで考えられなかったような速度になっている。 しかし、世の中はそれすら満足できなくなっている。 機器や商品などに組み込まれるソフトウェアの設計途上で、いろんな不具合(バグ)がつきものだが、それを洗い出す(デバックする)のに膨大な人手がかかる。 スマホの開発ですら何百人のソフト屋さんが働いている。 それが航空機となると、どれくらいの人手がかかるのか?分からないが、人手と時間をかけなければならない。それをコンピュータで検証できれば、非常に早く結果が出せる。人出でやれば数か月もかかる作業を、数日間で終われるということだ。今後はもっと早くなる。 速くて00年後と思われてきた量子コンピュータが現実にもう商品化されている。 世界初の量子コンピュータは、2011年にカナダのD-Wave Systems社が開発し、 『D-Wave』として1000万ドルで商品化した。1号機はロッキード社が契約し、2012年にはMK2を出し、2013年には、NASAやGoogle などが採用した。 従来のスパコンをはるかに凌ぐ『量子コンピュータ』がそこまで迫っている。 もう一つ、量子コンピュータの優れた点は、電力消費が少ないこと。 日本の理化学研究所のスパコン『京』は一般家庭の3万戸分の電気を消費するが、量子コンピュータは僅かな消費電力で稼働する。 コンピュータの成り立ちから説明が始まり、今までのコンピュータの歴史や構成の話があり、今話題のセキュリティ、秘密保護の開設にも触れ、最後に量子コンピュータ『D-Wave』の解説と続くが、難しい内容である。 本書は、タイトルに『文系も楽しんで読める!』と注釈が書いているので、気軽に買って読んだが、なかなか難解だった。 興味のある方は是非、一読してみて下さい。 |
2016年9月18日(日)
『ハーバードで一番人気の国・日本』を読んで
佐藤智恵 著
PHP新書
800円(税別)
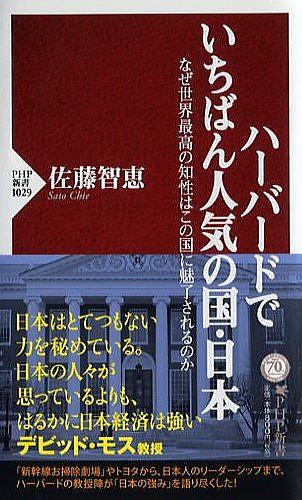
| この失われた20年、日本はバブル崩壊後、経済が低迷し、なかなか脱することが出来ず、もがき続けている。アメリカや欧州諸国が好況を取り戻す中、日本だけが底を這う低迷状態から浮上しない。そういう経済環境下で、アベノミクスによる経済刺激策が第一弾に続き、第二弾が打ち出されているが、景気の実態は相変わらず混迷したままになっている。 一時は、“Japan is NO.1”とまで言われた経済大国日本、『なぜこういう状態になってしまったのか?』と日本は自信喪失に陥っているようだ。 この本はそういう状況の日本が、世界一と言えるハーバード大学大学院ビジネススクールで教授陣や学生や受講する企業経営者などから絶賛を浴びているという姿を紹介している。 もっと、日本や日本人は自信を持ち、日本人の優れた点を知り、弱点を修正すれば、日本は再び世界を席巻する力を持っていることを示唆している。 本書のまえがきから、一部を紹介させて頂きますと、次のような内容です。 世界最高峰の学舎がハーバード大学であることに異論を持つ人はいないはず。 そのハーバード大学大学院ビジネススクールで、一番人気のある国が日本ということを知らない人は多い。この本はハーバード大学経営大学院の教授陣に直接取材し、『ハーバードはなぜ日本に学ぶのか』の核心に触れている。 日本企業の卓越した戦略、日本史の教訓、すごい日本人のリーダシップなど日本の強みを赤裸々につづっている。 それは、これから日本が世界をどうリードするかを考えるヒントを示唆している。 アメリカの大学が殆どそうであるように、ハーバード大学は一方的に講義で教えるのではなく、議論形式で学習を進めている。その際に使われる題材(ケース)は各教授陣が世界各国から取材して集め、それがテキストになっている。 その題材として、ある特定の国や企業の事例が20ページ程度にまとめている。 各題材(テーマ)の主人公は、国の大統領や会社のCEO、役員などさまざまだが、彼らが重要な決断をする前の状況が説明されている。 その題材に日本発のたくさんの事例が使われている。 受講者の学生や、民間企業経営者に一番人気がある題材として日本のいろんな出来事が取り上げられている。 ハーバード大学大学院ビジネススクールの学生は年間250本、卒業までの2年間で約500本の事例を学ぶことになっている。その内、必修科目で学ぶ日本の事例はトヨタ自動車、楽天、全日空、本田技研、日本航空、アベノミクスの6本だ。 その中で、何十年も引き続いて教材として取り上げられ、教えられているのが、トヨタ自動車と本田技研の2つのケースである。 ハーバードの教員も学生も日本に魅せられ、日本にたくさんの人が研修に来る。 ハーバード大学大学院ビジネススクールはマサチュセッツ州にあり、自他ともに認める世界最高学府である。大統領からグローバル企業のCEOまで、多数のリーダを輩出している。 2年制で、1学年900名、2学年合わせて1800名の学生が学んでいる。 その多くは各国の要人の子女、富裕層の子女である。彼らは卒業後、自国に帰って、政財界で要職に就き、世界に大きな影響をもたらす人材となる。 ハーバードのビジネススクールでは、どんな授業が人気を集め、何を日本から学ぼうとしているのかを本書は詳しく実例を挙げて説明している。 日本にいれば気づかないが、ハーバードでは日本が世界に大きな影響を与えてきた国であることが分かる。 本書のトップに出てくる題材は、JR東日本テクノハートTESSEI(テッセイ)の記事。 JR東日本が運行する新幹線(東北・上越・北陸・山形・秋田)の車内清掃業務を請け負っている会社TESSEIについての紹介である。 それは『新幹線お掃除劇場』で有名になった会社。 具体的には下記のHPをご覧ください。 https://www.youtube.com/watch?v=Ck6ISYMel6Y https://www.youtube.com/watch?v=CLf2WtXojZ4 https://www.youtube.com/watch?v=-Ak6uWp4ATk ホームに入線してきた新幹線が引き返して運行する際、7分間で車内の清掃を完ぺきに終える決まりになっている。椅子のリクライニングを戻す、椅子の方向を変更する、頭のシートの交換、室内の清掃、トイレの清掃、ごみ箱の入替など実にたくさんの作業を1車両一人で担当し、7分間で完璧に終えることになっている。 しかも、これを笑顔で作業し、終了すれば一斉に車外に出て、乗車する客に笑顔で『お待たせしました』という言葉をかける。全員が生き生きとこの作業をこなす。 こういう姿を見て、外国人は信じられない!感激と驚きの衝撃を受ける。 それは、掃除婦は3Kの仕事で、下層の人たちの仕事として見られている海外では、この仕事に対する真剣さと、心からの笑顔が信じられないのだ。 数千年の歴史を経て築いてきた日本人独特の思考や価値観や人間性、日本人気質は他のどの国の人々も持ち合わせているものではない。 しかし、TESSEIの従業員はここまでできるようになったのは、それなりの背景があることを学ぶ。 松下幸之助創業者が、『企業は世のため、人のために尽くすことが第一目的であり、利益は社会から頂く報酬で、利益そのものが企業活動の目的ではない』と明確に言い切っている。これが松下電器(Panasonic)の企業理念である。 欧米諸国の企業は、『事業活動は収益、利益を上げることが目的で、利益のない企業は社会悪、淘汰されるべきもの』という概念とは基本的に相いれない。 企業の存在する立ち位置が大きく異なる。日本の企業は、松下幸之助創業者が明示している企業の社会的貢献を謳っているところが殆どである。 もう一つ日本と外国企業の大きな違いは、日本企業は『人を大切にする』が、欧米企業は『人は金で買う』というスタンスになっている。 経営者であろうと、労働者であろうと、人=金という考え方が根強い。これは働く側からすれば、『もらう金の分だけ働けばいい』という気持ちにつながる。 日本人は勤勉で誠実な国民性だから、給料いかんにかかわらず良く働く。それが高い生産性につながり、世界の先進国の仲間入りを果たし、経済大国になった大きな要因だ。それ以外にも日本には、外国の国民が持ち合わせていない独自の考え方や伝統や文化を持っている。それらを外国人や、ハーバード大学の教員が知ると、ますます日本の良さが理解され、驚き、感激することになる。 その詳しい内容は、本書を読んでみてほしい。 ただ、すべての面で『日本人が世界中で一番すぐれているか』と言えば、日本人の弱点もある。それは一言で言えば、日本は島国であり、『島国根性』だと思う。 最近は少し変わって来たが、日本人同士は、日本語だけで通じる『阿吽の呼吸』や『ツーカーで通じ合う』ものがある。世界を相手にする場合は、この考え方を捨てなければならない。 主張すべきはしっかり主張し、相手に明確に意思を伝えることが大切だ。そのためには語学力、特に英会話力が問われる。 日本人は英語力が低い。なかなかうまくならない。それは日本人が恵まれた日本という一国の中で、何不自由なく生活ができるので、外国語(英語)を学ぶことに真剣になれないことが原因だ。 自分が変わることに対しても、しり込みする性格が強い。良い部分はしっかり継承し残して行き、グローバル化の中で変わらければうまくゆかない部分はしっかり変えて対応することが今後の日本人に求められる。 そういう意味では若者はもっと海外に出て、違った環境を経験し、日本人の優れた部分を海外に広め、逆に海外の優れた部分を取り込むという柔軟さが必要になる。そうなれば、再び世界の中心に立って、活躍できる日本が再生できる。 というような、内容でまとめられている。 ぜひ、ご一読を!!お勧めします。 |