「失敗の本質」を読んで
日本軍の組織論的研究
中公文庫
定価 本体762円(税別)
戸部良一、寺本義也、鎌田伸一、杉之尾孝生、村井友秀、野中郁次郎 著
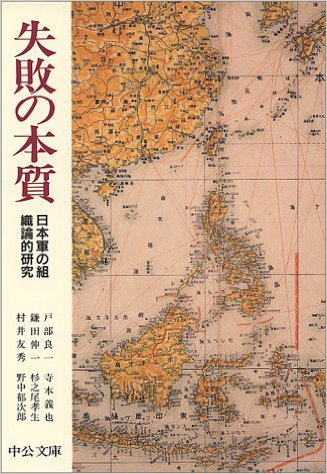
2017年4月9日(日)
「失敗の本質」を読んで
日本軍の組織論的研究
中公文庫
定価 本体762円(税別)
戸部良一、寺本義也、鎌田伸一、杉之尾孝生、村井友秀、野中郁次郎 著
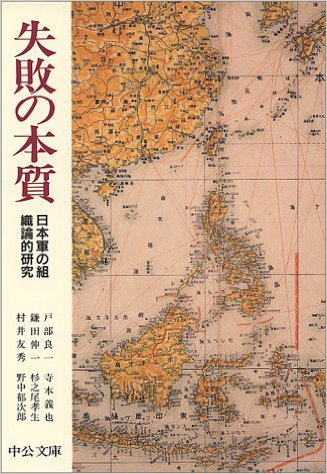
| 今、話題の本になっている「失敗の本質」は、太平洋戦争で日本はなぜ敗けたのか」という点について、大東亜戦争史上の失敗に示された日本軍の組織特性を探ることで、敗戦という悲惨な経験の上に築かれた平和と繁栄を享受してきたわれわれの世代にとってきわめて大きな意味を持つ。 まず、失敗の事例研究として、代表的な戦いについて書かれている。 ①ノモンハン事件 ②ミッドウェイ作戦 ③ガダルカナル作戦 ④インパール作戦 ⑤レイテ海戦 ⑥沖縄戦 と、ハワイ真珠湾攻撃以降、対連合国軍、また対米軍との戦いを通じて双方の戦力や指揮命令や戦略や戦術や戦果など、勝敗にかかわるいろんな条件を分析して詳述されている。 戦争本は沢山書店に並んでいる。『ミッドウェイ海戦』などは以前に読んだことがあるが、単にアメリカの国力や工業力の大きさが日本を圧倒していたという要因だけではなく、戦略や戦術や、軍のマネジメントや、指揮官のリーダシップや、技術開発力や人材の活かし方など日米の違いが大きくクローズアップされている。 日本人は過去の成功体験をもとに、確立した組織や指揮命令や規律などを構築し、それをかたくなに守って来た。一方で、失敗体験は、反省し活かさないで闇に葬ってしまった。戦争は局面、局面で時事刻々変化するもので、硬直した戦法では対応ができない。 悲惨な敗戦とい経験をしながら、現在の日本はそれを本当に生かしているだろうか? 組織論では、相変わらず官庁の縦割り組織が維持されているが、平時は善しとして、非常時は統合された指揮命令系統が強みを発揮する。 東日本大震災等で、災害対応に当たる役所がバラバラに動き、なかなか被災住民への対応がうまくゆかないのも同様だ。 各官庁を横断的にまとめて、責任者の下で強い権限を発揮できる体制が必要になる。非常時に、陸軍だ、海軍だということに拘っていては戦果が上がらない。 逆にその弱点を敵につかれることになる。 また、近代戦では情報が非常に重要になることも述べられている。 以前、会社の上位職は情報をたくさん握っていることで存在価値があった時代もある。今はネット社会になり、各自が情報を瞬時に掴むことができる。 そういう意味では、太平洋戦争当時と今は比べようもないが、相変わらず日本人気質という面で、旧態然とした特性が生き残っている面もある。 そういう見方で、本書を読むと、古くて新しいたくさんのことを学ぶことができる。 『アメリカは勝つべくして勝ったし、日本は負けるべくして負けた』と言える。 それを現在の日本社会に置き換えて、何か元気のない企業活動を見ると、本書が示唆するものを感じる。 本書によると、破綻する組織の特徴は、 ①トップからの指示があいまい、 ②大きな声は論理に勝る、 ③データの解析がおそろしくご都合主義、 ④「新しいか」よりも[前例があるか」が重要、 ⑤大きなプロジェクトほど責任者がいなくなる |
2017年4月5日(水)
『国家は破綻する』を読んで途中までの感想
「日本は例外」にはならない!
藤巻 健史(ふじまき たけし) 著
幻冬舎
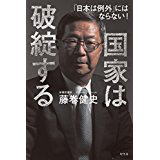
定価1200円+税
| 出口のない量的緩和により、万策尽きた日銀。これから日本が直面することとは? 今がマネーを守る最後のチャンス! 状況証拠がこんなにそろっているのに「日本は大丈夫」と言えるのですか? これだけ各界の識者が警告しても、暴走し続ける日銀と政府。この先に何が起こるかは歴史とマーケットが如実に語る。 以上が、著者の帯等に書かれている警告文だ。藤巻氏は現在、日本維新の会所属の参議院議員(全国比例区)として国会で活躍中の方だ。大学を卒業後、銀行に就職、その後、MBAを取得され、モルガンスタンレに移り、為替ディーラとして活躍された方で経済通の方。 その広い識見を活かして書かれた著書であるが、工学部出身の小生には経済のからくりがとっつきにくいのであるが、辛抱して303ページの本書を読み終えた。この本はもう一度読み直さなければ理解できない部分が多い。 著者が訴えていることは、上のタイトルのとおりで、このままアベノミクス政策を続ければ近い将来、必ず日本は国家財政破綻するということである。その時、国民の一人として、どう対応するのが賢明か、その解は円をドルに換えて置くことだ! と教えてくれている。 もう少し、立ち入った詳細内容は後日、まとめてみたい。そのためには、再度熟読しなければならないと思っている。 そんなことを考えていると、今日、ネット上で、東洋経済オンラインの記事が載っていたので、これなら分かり易いので紹介したい。 下のURLを読んで頂ければ詳しいことは分かるが、簡単にまとめて紹介する。 http://toyokeizai.net/articles/-/166068 この記事はいつまで公開されているかは分からないので、興味のある方は早くアクセスして読んで下さい。 記事の概要は、下記のとおり 日本の一般会計は、97.4兆円で、5年連続増加し過去最大になった。 主な歳出の内訳は下記のとおり。 日本は超高齢化社会を迎え、医療費や介護費が増加している。 この社会福祉費が最も多くて、32.7兆円(30%)を占める。 次が、国債費で23.5兆円(25%)を占める。 この巨額の金は、過去の国債の利払いや、期限がきた国債の返還の費用である。 いわゆる借金の利息払いと、期限が来た借金し払い分が国家予算の1/4もある。 次が地方交付税15.5兆円(16%)で。補助金として配られる。 次が、公共事業費5.9兆円。 次が、文科振興費5.3兆円 次が、防衛費で5.1兆円、 防衛費の伸び率は最大になっている。 問題は、アベノミクスをこの5年間やってきたのに、税収が一向に増えないことだ!。 アベノミクスは経済成長を促し、経済を活性化し、経済規模を拡大することで、税収を増やそうという政策であった。 そのために日銀と組んで、異次元の金融緩和や、マイナス金利まで導入して経済に刺激を与え続けてきたが思ったように経済活動が活発化しないで低迷が続いている。 2017年は57.7兆円どまりで、前年よりわずかに1080億円増収だった。 2016年の予想では、3.1兆円の増収を見込んでいた。 政府は2017年の税外収入を5.3兆円、外国為替資金特別会計を8683億円を繰入れ、2017年予算は新規国債を34.4兆円に抑えた。 これは2016年に比べ、633億円減で、公債依存度は35%となっている。 安倍政権は2010年は公債依存度が48%だったから、アベノミクスでここまで財政が改善したと誇っている。 (注)公債依存度とは、公債発行額÷一般会計 騙されてはいけない! 一般の家計で言えば、へそくりを使って借金を穴埋めしただけで、何も家計が良くなったわけではない。数字を付け替えたごまかしの手法だ! 世界各国の情勢を見ると、アメリカはトランプ大統領が就任して、『強いアメリカを造るために何でもする』という分かり易い政策を立て取り組みが始まった。 ヨーロッパEUは、ここにきて、マイナス金利から金融緩和を縮小する方向で動こうとしている。 日本だけが、相変わらず同じ低金利金融政策を続けている。 黒田日銀総裁の任期はあと1年で終わる。当面はマイナス金利を継続するそうだ。 マイナス金利の意味が分からなくて、銀行に金を預けたら利子がつくのではなく、預金から利子を引かれるという風に思っていたが、そうではないことが、藤巻さんの本を読んで分かった。 要は、①日銀がじゃぶじゃぶお金を市場につぎ込むことがいつまで続けられるのか、 ②長期金利は本当にコントロールできるのか この2点に失敗すれば、日本経済はデフォルトになり、ハイパーインフレに陥るという怖い話だ。 その辺は、次の機会に書いてみたい。 今日は、ここまで。 |
2017年4月2日(日)
GEとWHの腐れ縁?
| 19世紀末から20世紀にかけアメリカの電機メーカとして活動し、世界の電気業界を牽引してきたのが、GE(ゼネラルエレクトリック)とWH(ウェスチングハウス)である。 GEは発明王エジソンが造った会社で、1878年に設立し、1892年にトムソン・ヒューストンカンパニーという会社と合併してできた。  その後、電気事業を拡大し、白熱電球、アイロン、ラジオ、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、トースター、等の家電商品や、電気機関車、ジェットエンジン、MRIなど産業、医療機器分野に進出し、次々と新技術を開発・製造して巨大メーカに成長し世界に君臨してきた。 その後、電気事業を拡大し、白熱電球、アイロン、ラジオ、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、トースター、等の家電商品や、電気機関車、ジェットエンジン、MRIなど産業、医療機器分野に進出し、次々と新技術を開発・製造して巨大メーカに成長し世界に君臨してきた。 一方、WHは1886年から1999年にかけ総合電機メーカとして発展してきた。創業はジョージ・ウェスチングハウスで、ウィリアムズ・スタンリーやニコラス・テスラという優れた技術者らにより、エジソンが提唱した直流送電に対し、交流送電技術の開発を進め、1893年に送電システムとして、交流方式でGE (エジソン)に勝利した。 現在は当たり前の三相交流送電方式を開拓し、電力事業として確立した。鉄道や、発電変電所、ラジオ、テレビ放送局、1950年には加圧水型原子炉(PWR)を開発し、原子力発電分野で実績を上げた。 しかし、その後は衰退の道を歩み始め、1980年頃から中核事業の売却、分離が行われ、1997年、放送局以外の大半の電機事業を売却した。社名をWHからCBSコーポレーションと改め、1999年にCBSはバイアコムに売却されてWHは消滅した。 原子力事業部門は英国核燃料会社(BNFL)に売却された後、東芝が引き継いだ。 1893年に交流送電に勝利したのち、1894年には三相誘導モータを開発し、各企業の動力源として活用され出した。1895年にはナイアガラ滝に水力発電所を建設。 WHは重電、発電、送電に強みを発揮してきた名門企業であった。 発明王エジソンが『交流による送電は危険極まりない』と持論を主張したが、交流送電による効率の良さを証明したWHに負け、交流発電や送電が世の中のインフラのディファクトスタンダードになった。これは交流が電圧の上げ下げを変圧器で簡単に行えることで、長距離送電による電力ロスを下げられること、変圧器の変換効率が高く、電力損失をあまり気にしないで済むことがあげられる。 その直流・交流の戦いに勝ったWHだったが、その後の事業展開ではGEに負けた。 GEは名経営者に恵まれ、特に1060年入社のジャック・ウェルチは経営手腕を発揮し、事業の立て直し、強化を図り、伝説の経営者として称賛された。彼は儲からない事業のリストラやダウンサイジングを徹底して行い、合併、買収によるM&Aや、事業の国際化を目指した。将来にわたり付加価値が取れる事業を伸ばした。 中でも、電機メーカから航空機エンジン用ジェットエンジン部門は急速に力を付けた。 ボーイングやエアバスなどの航空機製造メーカとコラボして、高効率・低騒音・低燃費のジェットエンジンを開発し、世界を飛び回る航空機に取付けたエンジンの稼働状況をリアルタイムで全機をモニター・ディスプレイに表示し、安全や修理・サービス体制などを構築した。 また、医療機器分野では、CTやMRIという画像検査医療機器を開発し、常に先端技術の開発、実用化に力を入れた。 同じ業態に留まらないで、社会の動向に合わせ事業を変化させてきたことが、名門を力強く支えている。 WHは逆に、儲からない事業を次々と売却して、新しい事業を生みさせなかったことが体力の低下につながり、経営の維持ができなくなり、次々に身売りして消滅した。 ここにアメリカの二大電機メーカの盛衰の歴史を学ぶことができる。 最近話題になっている東芝の場合と相通じるような気がしてならない。 東芝は、原子力発電事業に深入りしすぎた? 運悪く東日本大震災の津波で、福島第一原発爆発事故の後、世界の原発の安全基準の見直しがされ、その結果、設計基準にかかわる大幅な変更や、工事の安全性確保など原発建設費用が大きく上昇した。加えて、安全基準の見直しの結果、工事の進捗が遅れ、その賠償問題が表面化した。 その費用のねん出のため、儲かっていた事業のMRIやCT医療機器事業をキヤノンに売却し、また稼ぎ頭の虎の子の半導体事業の過半株を売却せざるを得ない状況に陥った。 その状況を見ていると、WHと組んだ日本の名門、東芝がWHの悪しき足跡を踏みながら歩いているような印象を受ける。早く立ち直って、元気な『東芝』に立ち返ってほしい。 |
2017年4月2日(日)
PONANZA(電脳)が佐藤名人を破り、先勝する!
| 今朝のニュースによると、電脳(PONANZA)が、将棋の佐藤天彦名人を破り、まず一勝した。数年前から、電脳(コンピュータ)が将棋や、囲碁や、チェスなどの名人と対戦し勝敗を競っているが、勝ったり負けたりを繰り返し、名人に追い付いてきた。 将棋は囲碁に比べ、指し手の組み合わせが少ないので、コンピュータ(電脳)としてはプログラミングがしやすいそうだ。今回は日光東照宮で4月1日、対局戦があり、電脳が勝った。次回は5月20日姫路城で行われる。その結果に興味が湧いてきた。  最近の電脳(コンピュータ)が急速に強くなった。そのわけは、過去の対局データから勝ち方を蓄積して、常にもっともよい指し手を探し出すことができるようになった。 最近の電脳(コンピュータ)が急速に強くなった。そのわけは、過去の対局データから勝ち方を蓄積して、常にもっともよい指し手を探し出すことができるようになった。プログラミング次第と言えそうだが、人間の脳の思考をいかに電脳に移植するかだと思う。 その方法として、最近、「ディープラーニング」という考え方が注目されるようになった。 コンピュータの計算速度が飛躍的に上がり、大量のデータを蓄積し、その中から解を導くことになるが、対局の場面、場面が刻々と変わる中で、最適解を見つけることは容易ではない。 しかし、コンピュータは全く疲れを知らないし、不安や、びくつくこともなく、人間的に言えば常に平常心で対戦できるという優れた能力がある。 今まで電脳(コンピュータ)が名人に勝てなかったのは、新しい手や未知の手に対して、対応力が劣っていたからだろう。 電脳が将棋や囲碁やチェスの名人と対戦で勝った、負けたを繰り返すことで、勝つ手を学習する力をつけたと言える。これは大変な意義を持つ。 コンピュータが人類にとって、もっと有益な存在となることが分かってきた。 今までのコンピュータは、データの処理作業を速く正確にするという点に力を発揮した。 これからは、新しいことを考える領域まで、コンピュータが活躍する場が開けてきたと言える。 その一例が、新薬の開発に活用すること。 最近の新薬は、新しい技術開発により、いろんな化学物質や分子構造の組み換えなど全く新しい考え方で製薬や創薬が実現しつつある。 薬は自然界にある有機物質の抽出により造られた漢方薬などと、化学物質の合成により造られたものがある。いずれにしても、その分子構造の組み合わせが無限にあり、どういう分子をどう組み合わせるかで、効能が大きく変わる。 一方で、病気の原因が細菌性のもの、遺伝子的なもの、免疫的なものなど次第に明らかになってきた。そうなると、薬の使われ方も変わってくる。 無限の物質(分子)の組み合わせの中から、病気に合わせて最適な薬を合成するには、人間脳で考えるには限界がある。そこで電脳の活躍する場が期待されている。 薬は間違うと、副作用で害になる。いかに病気に対して有効で、薬害のない薬を速く開発するかが製薬会社の使命であり、企業競争になっている。 電脳戦はコンピュータと人間脳の戦いの場であるが、そこで育成された電脳の成果は全く別の場で生かされることを期待したい。 将棋の名人は、特別な頭脳を持った人だけが成れる特殊な世界である。そういう超人的な頭脳を持った少数の人間に対して、電脳はそれ以上の能力を持ち、しかもいくらでも製造できる。そうなると、将棋や囲碁の名人戦は意味が無くなるかもしれない。 そう考えると、常に電脳が勝つという日が来るのだろうか? 何人かの名人が電脳戦を戦い、感想を述べていることは、勝ったり負けたりの繰り返しになると。それは、人間脳は電脳の弱点を見抜く力を持っているから、相手の弱点を突くことができるからだと言われている。 電脳は無限の中から最適解を見つけることができるようになるから、常勝できると。。 果たして、どちらの力が勝るか、もうしばらく様子を見てみないと分からない。 両者、闘いながら、互いに進化することが一番素晴らしい結果を生み出すと思う。 いずれにしても、すでに電脳が学習する力をつけ出したことは事実である。人間脳の学習する能力をはるかに上回ることも考えられる。 そうなると、この世はどういう姿に進化するのだろうか? 切手サイズの一つのシリコンチップ上に、200億個以上のトランジスタを集積できる時代になった。これは物理的な製造技術の問題であるが、その集積された回路が、人間の頭脳の脳細胞や神経系統の如く、つながり機能するようになれば、電脳はまさに人工脳と言われるにふさわしい部品になる。 何か、楽しいようで、恐ろしい気もする昨今の電脳の進化の話です。 |