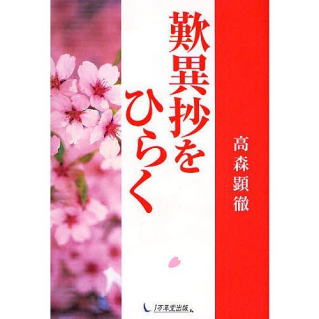お盆も過ぎて猛暑も峠を越えたのか、朝夕はめっきり涼しい日がやってきました。
これからも、まだ暑い日もあるでしょうが、季節は着実に秋に向かっています。
「台風の当たり年」という言い方が昔ありましたが、今年の台風の発生数と進路は従来と全然違うようで、気象庁も戸惑っているようです。
台風20号は紀伊水道に突っ込んできそうな予想になっています。私どもアマチュア無線家にとって、高い位置にアンテナを上げるので、雷と台風(強風)が一番怖い存在です。20号が無事に通過することを祈っています。
秋と言えば、昔は『読書の秋』という言葉がありました。また、『秋の夜長』や『灯火親しむ候』というノスタルジックさを感じる言葉がありましたが、昨今のスマホ時代は、年中何でもありという感じで、人々が異次元の生活しているように感じます。
我が家の近くに『平和台霊園』という広い墓地があり、お盆、春秋のお彼岸にはたくさんの墓参りの人で賑わい、その時はガードマンが出て周辺の交通整理をしています。
しかし、今年のお盆の墓参りの人は例年より減ったな?という感じを受けました。
これは、ご近所を見ても分かりますが、年々歳を重ねていますので、以前のように動ける方が減ってきたのが実態です。自分の体が動く内は、先祖を供養する墓参りを欠かさなかった家も、自分の体が動けなくなったらお仕舞です。
知り合いに墓苑管理者(墓守)をされている方が居ます。最近のお墓事情を聴いてみると、なるほどと思いました。
誰も参らないで、周囲に雑草が茂り、荒れ放題で放置された墓が年々増加して困っているということです。
そこで、ネットで少し調べてみると、墓に関する法律について、分かり易く書かれた記事がありますので紹介します。
*********************************************************
お墓は「墓地」にしか作れない
お墓に関しては、「墓地、埋葬等に関する法律」という法律があります。略して、墓埋法と言います。墓埋法は、お墓は「墓地」にしか作ってはいけないと定めています。
つまり、たとえ自分の土地であっても、自宅の庭や裏山にお墓を作ることはできません。もし「墓地」でないところに墓石を建てて、その地下に遺骨を埋めてしまうと、墓埋法違反になります。
「墓地」というのは、お墓が集まっている区域のことです。「◯◯霊園」とか、「◯◯墓地」などをイメージしていただけばよいと思います。
「墓地」の経営には、都道府県知事の許可が必要です。現在は、公益法人や宗教法人(お寺など)でなければ「墓地」の経営を許可しないことになっています。個人や会社では、「墓地」を作ることはできません。
お墓が勝手に撤去されてしまうことがある
世間ではお墓を建てる土地を手に入れることを、「お墓を買う」と言うことがあります。「買う」という言葉には、所有権を手に入れるというイメージがありますが、「お墓を買う」と言うのは、「お墓の敷地の使用権を買う」という意味です。お墓を買った人は、土地の使用権を取得するに過ぎません。お墓の敷地の所有権は引き続き、「墓地」を経営している寺院や霊園が保有し続けることになります。
多くの場合、お墓を買う時には、永代供養料を支払います。
永代供養料を支払っておけば、未来永劫、お墓をその土地に置いてもらえるようなイメージがありますが、これも違います。
永代供養というのは、文字通り、魂の供養をいつまでも行うという意味です。
お墓の存続とは無関係です。
理屈では、魂の供養はお墓がなくても行えます。
そこで、墓地の経営者は一定の手続を踏むことで、誰も面倒をみる人のいなくなったお墓(無縁墓)の使用権を消滅させることができます。
その場合、お墓に収められている遺骨は、共同墓地に移動し合祀されます。
そのうえで墓石等を撤去して整地し、別の人のお墓の敷地として再利用することになります。
人は次々亡くなります。古いお墓を整理しなければ、この世界は、いずれお墓だらけになってしまいます。無縁墓を整理するのは、致し方ないことといえます。
長期間、管理料を支払わないと無縁墓と判断される可能性がありますので、注意が必要です。
お墓の敷地に抵当権が設定された場合の対処法
前述のようにお墓の敷地は、「墓地」の経営者の所有物です。そのため、「墓地」の経営者が自身の借入金の担保にお墓の敷地に抵当権を設定することも可能です。
その場合、「墓地」の経営者が借入金の返済を怠れば、抵当権が実行されて競売にかけられて、第三者が競落するという事態になることもあり得ます。
たとえ競売にかけられて第三者が所有権を取得したとしても、お墓を撤去する必要はありません。お墓の敷地の使用権は、借地権や地上権と同じように、新しい土地所有者に対しても、「自分は権利者である」と主張できる権利とされています。
お墓の敷地の所有権が第三者に移った場合であっても、今まで通り、お墓を維持することができます。
お墓の所有権の承継者は慣習で決まる
お墓は、相続財産とは別の「祭祀財産」とされています。「祭祀財産」は、預金・不動産等の他の財産とは異なり、法定相続分によって分配するのではなく、慣習によって誰が承継するかを決めるとされています。慣習は、地域や世代によって異なるでしょうが、長男あるいは長子が承継することが多いと思われます。
お墓は、税法上も特別な扱いがされており、相続税はかからないとされています。
*************************************************************
上記のように、墓苑管理者(寺院や公益法人)は、無縁墓の増加に対して、市町村役場に書類を出して、一定期間公示後、墓の撤去を行うことが出来ます。こういう処分が最近、急に増えてきたそうです。
『墓石を撤去した跡地をどう活用するか?』 が墓地管理者の課題です。
墓地の空き地に、合祀墓を作り、そこに納骨するというのです。もちろん有料です。
もう一つは、夫婦墓というかたちで、小さな墓石に名前を刻み、20年から30年の有期限で、夫婦の墓を作りますが、期限が過ぎると、合祀墓に骨を移して、その夫婦墓の場所に、別の新しい夫婦墓をつくるという合理的な考え方です。
この場合の夫婦墓は30万円程度で安く造れます。永代供養を付けると、その分は加算されます。これなら、墓に数百万円もかけることがないので、金銭的にも楽です。
墓じまいの跡地に、事務所を建てて、法事や仏事に安く賃貸するようです。
最近は一人身(単身生活者の人が亡くなると、誰も供養する人が居ないので、市役所が僧侶に依頼して、この事務所で死者の供養をするそうです。そういう人が最近、増えていると聞きました。
そういう話を聞くと、何か時代の流れを感じます。
檀家や檀那寺、離壇料、墓じまい、合祀(ごうし)、共同墓地、永代供養、お布施、墓の引越し、というような今まであまり耳にしなかった言葉が随分身近になってきました。家族葬もその一つです。
亡くなった親や親族の供養のための仏事は、どういう意味があるのでしょう。
そこで、本論なんですが、タイトルの「歎異抄をひらく」では、親鸞聖人はどういうふうに述べられているのか興味があるところです。
歎異抄と言えば、知らない人が居ないくらい有名なくだり、『善人なおもって、往生を遂ぐ(とぐ)。いわんや悪人をや』があります。これは、『善人でさえ、浄土へ生まれ変わることができるのだから、まして悪人はなおさら往生できる』という意味です。
この意味の解釈が間違って伝えられていることが多く、悪人はなおさら往生できると言われるのだから、悪いことをし放題という時期があったそうです。
これは弥陀の真解釈を誤っているのです。
何故、善人より悪人なのか?について、本書は前半で詳しく述べています。
もう一つ、読んでみて、びっくりした点があります。
何と、親鸞聖人は『葬式・年忌法要は死者のためにならない』と言い切っています。
(歎異抄;第5章) 『親鸞は父母の孝養のためとて念仏、一辺にても申したること未だ候わず』と書かれています。
親鸞は亡き父や母の追善供養のために、念仏一遍、いまだかつて称えたことがないと言われているのです。
『葬式や年忌法要などの儀式が死人を幸せにする』という考えは、世の常識になっているようです。
インドでも釈迦の弟子が、釈迦に「死人のまわりで有難い経文を唱えると、善いところへ生まれ変わるというのは本当でしょうか」と尋ねている。
黙って釈迦は小石を拾い近くの池に投げた。沈んでゆく石を指さして、「あの池の周りを『石よ浮かび上がれ、浮かび上がれ』と、唱えながら回れば、石は浮いてくると思うか」と反問された。
石は自分の重さで沈んでいったのである。そんなことで石が浮かび上がるはずはなかろう。
人は自身の行為(業)により死後の報いが定まるのだから、他人がどんな経文を読もうとも、死人の果報が変わるわけがない、と説かれた。
読経で死者が救われるという考えは、本来、仏教になかったのである。
釈迦は生涯、80歳まで、教えを説かれたのは生きた人間であり、常に苦悩の心田を耕す教法だった。
死者のための葬式や仏寺を執行されたことは一度もなかったと言われる。
そのような世俗的、形式的な儀礼を避けて、真の転迷開悟を教示されたのが仏教である。
このくだりを読んで、私は仏教に対する考え方が大きく変わった。
皆さんはどうお考えでしょうか?
『歎異抄をひらく』は、分かり易く表現されている本ですが、『歎異抄』が非常に奥深く難解なため、一度では理解しがたいことが多い。これからも2回、3回と重ねて読むことで、少し心田が開けるかもしれない。
非常に深淵な教理を示されているように思う。
ぜひ、ご一読を!!
|
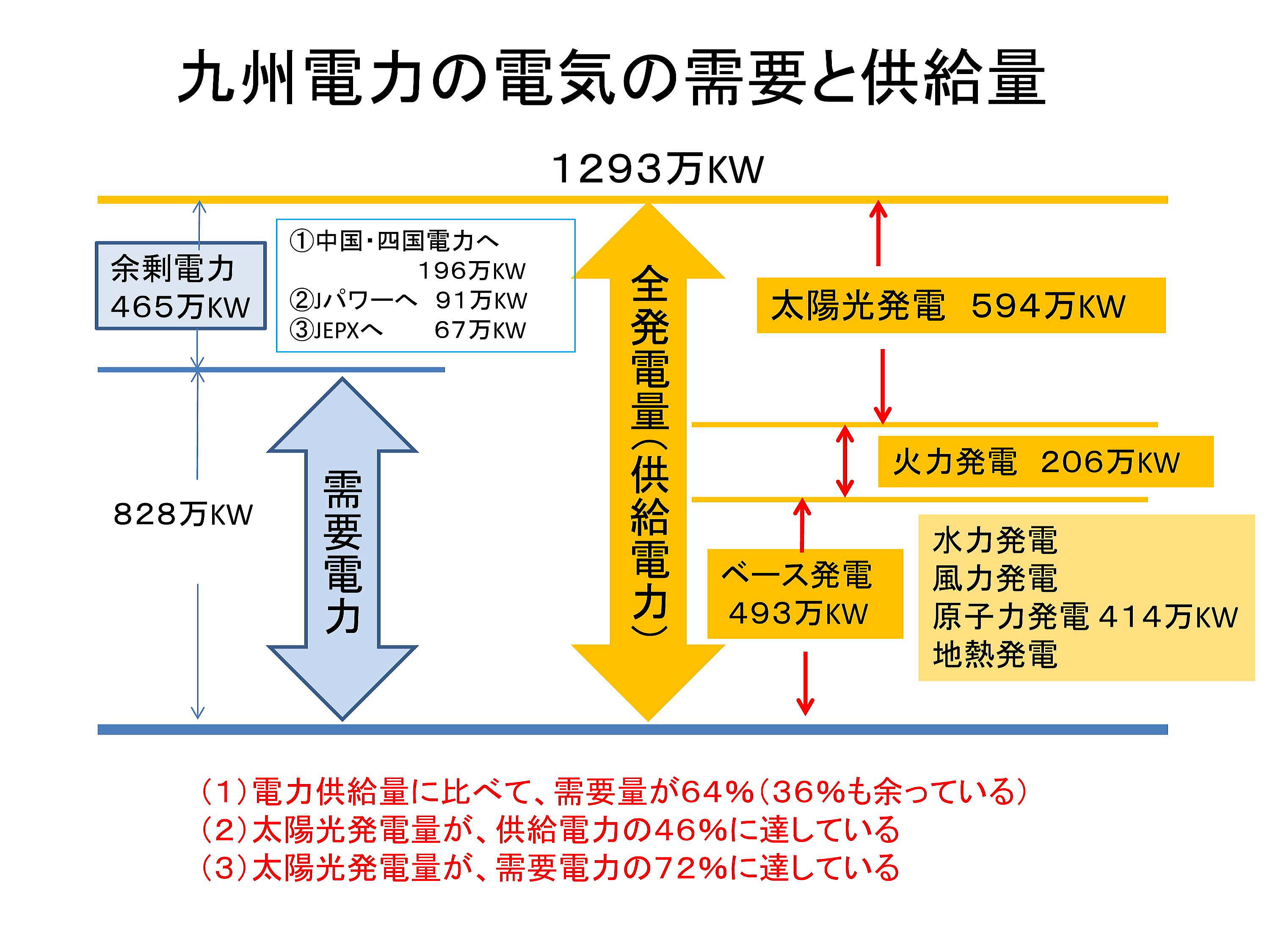
 2018.10.4
2018.10.4
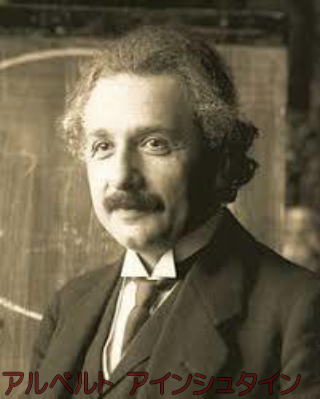 この公式は、光速不変を元にして成り立っている。この宇宙に存在するあらゆる速度は相対的であるが唯一の例外は「絶対速度」をもつのが光だとしている。 光速 C=秒速30万kmだという。
この公式は、光速不変を元にして成り立っている。この宇宙に存在するあらゆる速度は相対的であるが唯一の例外は「絶対速度」をもつのが光だとしている。 光速 C=秒速30万kmだという。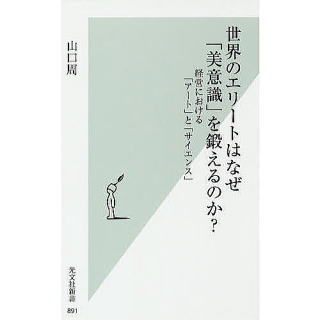

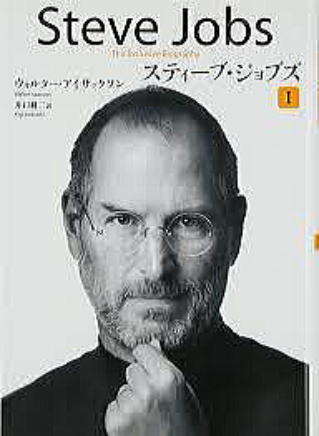 Steve Jobsとはどういう人なのか?
Steve Jobsとはどういう人なのか?  それは英国で生まれたダイソンの羽根のない扇風機(左)と、サイクロン掃除機(下)だ。
それは英国で生まれたダイソンの羽根のない扇風機(左)と、サイクロン掃除機(下)だ。