iPS細胞が医療をここまで変える
実用化への熾烈な世界戦争
山中伸弥 著
京都大学 iPS細胞研究所
PHP新書 出版
定価 820円(税別)
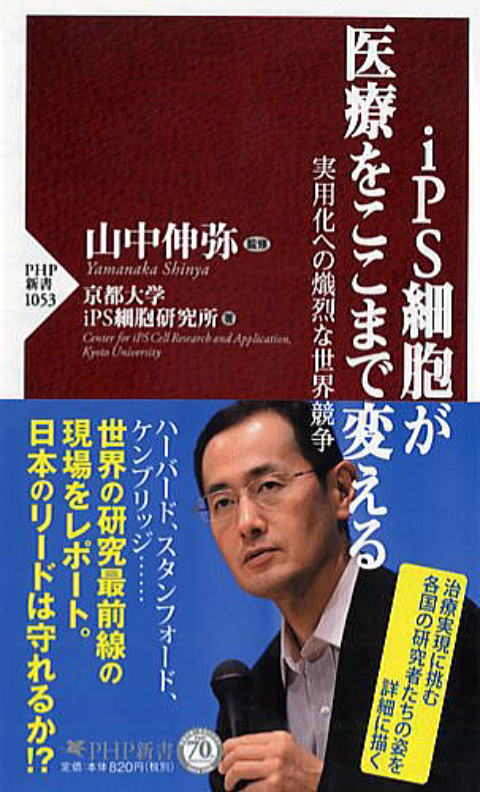
2016年12月16日(金)
iPS細胞が医療をここまで変える
実用化への熾烈な世界戦争
山中伸弥 著
京都大学 iPS細胞研究所
PHP新書 出版
定価 820円(税別)
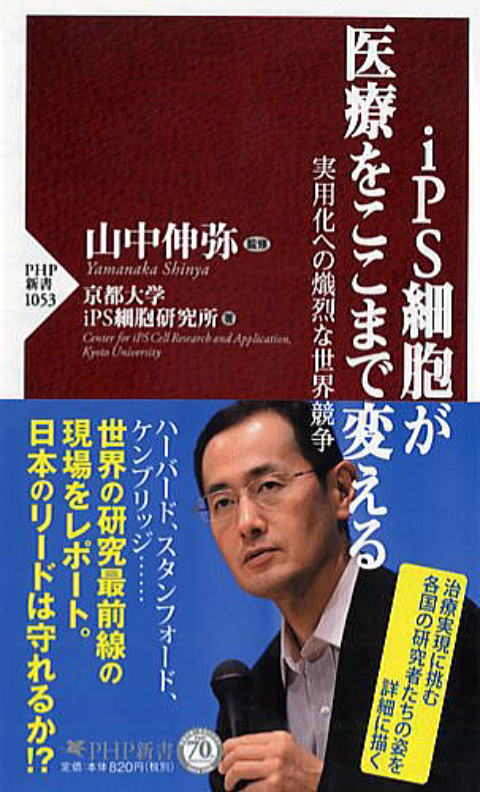
| iPS細胞を発見し、2012年に「ノーベル生理学・医学賞」を受賞した。 受賞の理由は成熟細胞が初期化され、多能性を持つことを発見した」 表紙の内容紹介の文では、次のようになっている。 山中伸弥教授がマウスiPS細胞の作製成功を発表したのは2006年のことだった。 それからiPS細胞を用いた再生医療や創薬研究は加速度的に進んでいる。 これまで日本がリードしてきたが、世界各国の追い上げも急だ。 この本は、世界各国でiPS細胞関連の研究をしている著名な研究者を訪ね、ルポ形式で研究最前線をレポートする。 また代表的な疾患について、iPS細胞を用いた最先端研究の進捗状況を紹介し、iPS医療実現への道のりを探る。世界的な大競争の中、日本はリードを守れるのか?“夢の医療”の実現への希望と課題を浮かび上がらせる。 そして、裏表紙には、海外の科学者や研究支援者の“生の姿”を描きつつ、医療に向けたiPS細胞研究の「いま」を明らかにする。 「加速度的に進展するiPS細胞研究ーそこにあるのは、単純な国同士の競争ではない。時には新たな成果をいかに早く世に出すか、お互いを高め合いながら競い合い、時には国をまたいで手を組み一緒に研究を進めてゆくのだ。 病気やけがで苦しむ患者さんを一日でも早く治すため、そしてまだ見ぬ生命の謎を解き明かすため、研究者たちの挑戦は続いていく」となっている。 序章は、iPS細胞とはどのようなものか そもそもiPS細胞とは何か? iPS細胞の可能性と課題? 第1章 iPS細胞研究最前線 第2章 熾烈さを増す世界的な研究競争(アメリカ編) 第3章 熾烈さを増す世界的な研究競争(ヨーロッパ・アジア編) 第4章 iPS細胞での治療が期待される主要疾患 となっている。 iPS細胞とは、一口で言うと、体中のどんな細胞にも変化できる万能細胞である。 2006年8月に、京都大学の山中伸弥教授らのグループが、「マウスの皮膚の細胞に4つの因子を加えると、体中のどんな細胞にでも変化できるiPS細胞ができた」という論文を発表した。 当時はあまりにも簡単な方法であったので、他の研究者は半信半疑であった。しかし、海外の他の研究グループが再現性を確認したこともあり、次第に広く認められるようになった。 翌年、2007年には、ヒトで同様にしてiPS細胞が作製できることが発表され、これにより一気にiPS細胞は医療応用に向けて、世界中の研究者から注目されることになった。そして、2012年には、ノーベル賞を受賞した。 iPS細胞とは、英語名の「induced pluripotent stem cell」の頭文字を取ったもの。日本語では「人工多能性幹細胞」という。 山中教授は広く世界的に使ってもらえる親しみやすい名前にしようと、当時流行していたアップルのiPodに似せて最初の「i」を小文字にした。その思惑は見事に当たり、世界中の研究者が「iPS」という言葉を使うようになった。 発表された当時は、すでに発表されていたES細胞(胚性幹細胞)が日本で、“万能細胞”と呼ばれていたことから、新聞等で新聞等では新型万能細胞という呼ばれ方もしていたが、今ではすっかり市民権を得て「iPS」という言葉が新聞の見出しにも使われるようになった。「万能細胞」というのは正式名称ではなく、「多能性」という言葉の方が適切だ。 細胞は、それぞれの部位毎に役割が決まっている。 生き物は、全て細胞の組み合わせで出来ている。これは植物でも動物でもみんなそうで、細胞は生命の基本単位ともいえる。 細胞の中には、体の設計図である遺伝子が中に収納されている「核」。タンパク質を作る工場である「小胞体」、エネルギーを作り出す「ミトコンドリア」などさまざまな細胞小器官が含まれている。 生物の中には、細胞1つだけで自立して生きている単細胞生物というものもあるが、人間の体は60兆個とも言われる細胞でできている。さまざまな種類がある。 例えば、皮膚や、脳の神経、体を動かす筋肉、心臓の筋肉、アルコールを分解する肝臓など、それぞれの細胞でできているが、これらは全て異なる細胞である。 こういう細胞はいったんその役割が決まると、他の細胞に変化することはできない。通常は細胞がその役割を代わることはない。 しかし、役割が決まる前の細胞であれば、他の細胞に変化することはある。 人間の体は、200種類以上の細胞からできていると言われている。この細胞は元をたどれば、たった1個の細胞である受精卵がスタートとなっている。受精卵が分裂し、数を増やしていく中で、次第に役割分担をしてゆき、最終的に200種類以上の細胞へと分かれるのだ。この過程を「分化」という。 iPS細胞を作ることは、皮膚などのように既に分化して役割の決まってしまった細胞を人工的に受精卵に近い、役割がまだ決まっていない状態に戻すことともいえる。 受精卵に近い状態に戻せば、つまり細胞を「初期化」すれば、その細胞を再び分化させて、必要な細胞を作ることができる。そうして新しい分化させて作り出した細胞を医療に使えるのではないかと考えられている。 細胞分裂をして自分自身の数を際限なく増やすことができ、さらに分裂したあとに他の種類の細胞に分化する能力を持つ細胞を「幹細胞」という。ちょうど、木の幹のように枝分かれする元となるので、「幹細胞」と呼ばれている。この幹細胞があるからこそ、体中で様々な細胞が生まれるのである。幹細胞にはいくつかの種類がある。 造血幹細胞、神経幹細胞、間葉系幹細胞、骨格筋幹細胞などいくつかの種類がある。造血幹細胞も体性幹細胞の一種である。 すべての細胞に分化できる受精卵は「全能性」を持つと言われる。また「多能性」とは、全能性ではないがさまざまな細胞になることができることを意味している。 iPS細胞は、とても受精卵に近い状態ではあるが、厳密には受精卵とは異なる。 受精卵は胎盤と胎児を作るが、iPS細胞に胎盤を作る能力はない。この特徴をもって、「全能性幹細胞」ではなく、「多能性幹細胞」と呼ばれている。 iPS細胞は、今ではマウスやヒトなど、いくつかの種類の動物の細胞から作られている。しかし、他の動物ではなかなかできないケースもある。 ちなみに、植物は古くから刺激を与えると全能性を持った細胞に変化させることができると知られており、iPS細胞のように因子を入れる必要はない。 iPS細胞の可能性と課題については、iPS細胞で何ができるかで、大きく2つの医療応用の可能性がある。 1つは再生医療、もう一つは薬の開発である。 再生医療はイメージしやすい。たとえば、肝臓が悪くなった患者さんの肝臓を新しい肝臓と取り換える移植手術が行われている。しかし、そう簡単に移植できる肝臓が手に入らない。iPS細胞で肝臓を造り、それを移植することができれば多くの患者を助けられる。しかし、現状では立体的な構造を作るのは難しい。 もう一つは創薬研究である。 iPS細胞を使って、さまざまな難病などの薬を開発してゆくことである。 患者の細胞を採取して、その細胞をiPS細胞に変化させると、病気の情報を持ったままのiPS細胞を作ることができる。このiPS細胞から病気の原因となる細胞を作ると、患者さんの体内で起きている現象を実験用の培養皿の中で再現できる可能性がある。これにより病気のメカニズムを調べたり、さまざまな薬の候補物質をこの細胞に振りかけて効果をみることで、有効な候補物質を見つけ出すことができる。 これまではマウスを使った実験をしてきたが、マウスとヒトでは病気に対するメカニズムが異なることもある。iPS細胞はヒトの細胞を使い、また無限に増やすことができ、またほぼすべての種類の細胞が造れるので、大量の種類の薬の効果を調べるような実験も出来る。 当初、2006年当時はマウスの皮膚から取り出した繊維芽細胞に4つの遺伝子をレトロウィルスというウィルスを使って細胞内に運び込み、iPS細胞を作っていた。 この方法は、レトロウィルスが細胞に感染して、細胞内の遺伝子にレトロウィルスが持っている遺伝子を導入するという性質を利用していた。しかし、遺伝子を入れる場所は選べないので、運悪くもともと細胞が持っていた大切な遺伝子を傷つけてしまうこともあった。遺伝子が傷ついた細胞をマウスに移植すると、がんが発生してしまうこともあった。 この時の印象が悪く「iPS細胞=がん化のリスクが高い」というイメージが着いてしまっているが、現在のiPS細胞を作る方法はかなり進んでいる。 たとえば、遺伝子の導入の方法は、レトロウィルスからエピソーマルプラスミドに変更された。プラスミドを使う方法であれば基本的に細胞内の元々あった遺伝子とは関係なく、初期化に必要な因子を導入できる。もともとあった遺伝子を傷つける確率は低くなる。当初はがんに深くかかわっていた遺伝子として知られている遺伝子を使っていたが、後には構造が似ているが、がん化しにくいと考えられている遺伝子に置き換えている。 その他、いくつかの改良を加えて、今では6つの因子を導入するなどして、iPS細胞を作っている。完全にがん化のリスクをゼロにすることは不可能であるが、iPS細胞を使ったからと言って、がん化のリスクが高いとは言えない程度まで低くなっている。 実際に移植に使う細胞では遺伝子の検査をするなどして安全性の検証を行うことが重要になっている。 iPS細胞は「万能細胞」と呼ばれたこともあり、この細胞さえ使えば何でも治せると思われていることもあるが、実際はそれほど簡単ではない。 治療に用いるためには、iPS細胞から治療に必要な細胞へと分化させてから、移植をするという作業になる。 iPS細胞には増殖する能力や、あらゆる細胞になる能力があるため、iPS細胞をそのまま移植してしまうと、体の中で勝手に望まない細胞が増えてしまうことになる。 分化させた細胞を移植する際に移植する細胞の中にiPS細胞のままのものが残らないようにする工夫がいる。 非常に期待されているiPS細胞であるが、実はまだ実際に誰かを治したと言った成果は出ていない。iPS細胞を用いた治療は現段階ではまだ未来の治療法なのだ。 それでも、着実に研究は進み、患者さんに使える技術に近づきつつあると言える。 詳しい内容は、是非、本書を読んで頂きたい。 iPS細胞について、平易に分かりやすく書かれているので、スーッと読める。 そして、同意された方は、山中先生の研究を一層加速するため、資金提供をお願いしたい。研究開発は多額の費用が掛かる。安倍政府はやっと60億円程度のiPS細胞医療応用研究費として計上するというニュースを聞いたが、研究費はいくらあっても足りない。山中先生はマラソン大会で走ったりして、皆さんから寄付(ドネーション) を募り苦労されている。 日本初のiPS細胞技術を世界中の難病に苦しむ人々に役立つよう、一刻も早く成果が出ることを期待します。 山中伸弥教授の講演会(2015年11月14日)はここをクリックしてください。 |