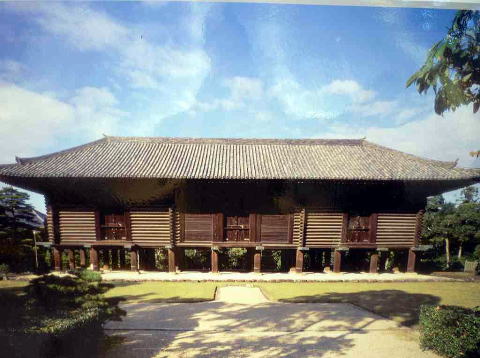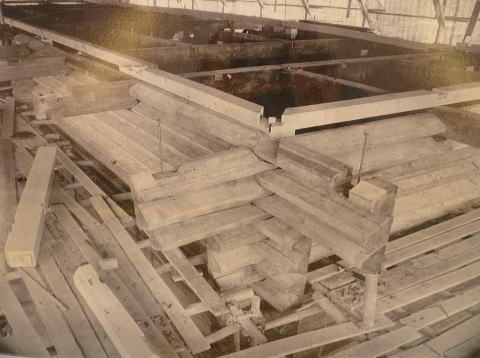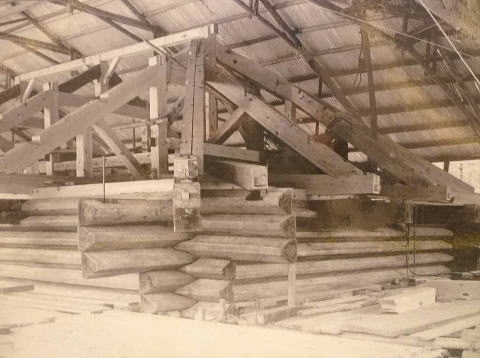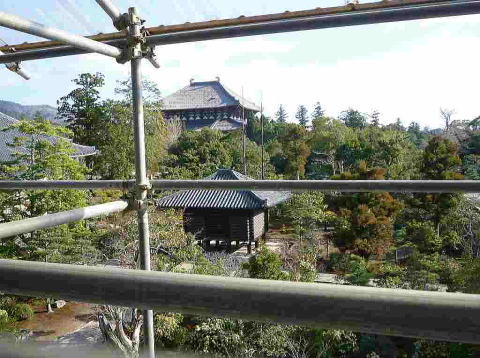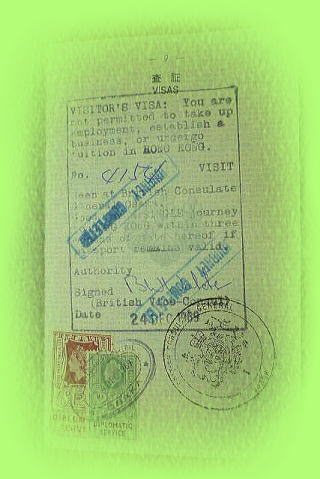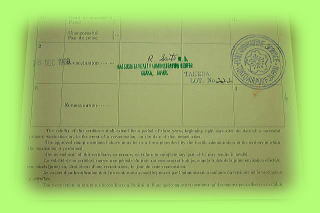11��11���A�w���E�o�c�ƐS�̉�x����Â���u����A���̓��̃��[�K�E���C�����z�e���ŊJ�Â���A500�l���������̏�Ԃł��b������܂����B
�@�R���L��搶�́A��w�E�����w����̃m�[�x����҂ŁA���݂͋��s��w�����AiPS�זE�����������Ƃ��ē���撣���Ă����܂��B
�@�uiPS�זE���Ђ炭�V������w�v�Ƃ����e�[�}�ł��b������܂����B�����̐�����������b���n�܂�A�Ȃ���҂��u�����̂��ɂ��ĐG��A���`�O�Ȉ�ɂȂ������A��p������ŁA���͂���u����܂Ȃ��v�ƌ����Ă����Ƃ����G�s�\�[�h�̔�I������A�J����킹�܂����B�_�ˑ�w��w���𑲋Ƃ��A���s����w��w�@�����ȂŔ��m�ߒ����I����A�č��O���b�h�X�g�[����������3�N�ԗ��w�B�A����A���{�̈�Ì���ł��܂������킸�ɗ�������ł����Ƃ���A�ޗǐ�[�Ȋw�Z�p��w��w�@��`�q���猤���Z���^�[�̏������Ƃ��Č}�����A�����ŗD�G�ŗL�\��3���̃T�|�[�g�����o�[�i����j�Ɍb�܂�AiPS�זE���Ɏ���B
�@�����āA�m�[�x����܁A���s��w�Đ���Ȋw�����������AiPS�זE�����������ɂȂ�B
�@�č����w���́A������킸ES�זE�̌����ɖv�������B
�S���̋�������A�u�L��A�ꐶ��������Ă��邱�Ƃ͔F�߂邪�A�Ȃ��N�͂���ȂɊ撣��̂��H�v�ƕ����ꂽ�B���̖₢�ɑ��āu���ʂ��o���āA�L���ɂȂ肽���A�����������������A�����d����ɒ��������v�ƌ����悤�Ȃ��Ƃ��������B����Ɛ搶���A�u�������Ȃ��Ƃ����A�����Ƒ�Ȃ��Ƃ�����v�ƌ���ꂽ�B����́u�u�v���I�v�ƁB
�@
�@�u�v�͍��A�r�K�X�K�����Ő��E�𑛂����Ă���B���̂u�v�Ƃ͈Ӗ����Ⴄ�B�����ł܂���ꂩ�������o���B
�@�u�u�v�Ƃ́A�d���������ő�Ȃ��Ƃ́A�u���������������������@�v����������I�v�ƌ���ꂽ�B���̂��߂ɂ��������̂��Ƃ����u�����������m�ɂ��āA���g�܂Ȃ���Ζ{���̐��ʂɂȂ���Ȃ��ƒ��������B������悭�l���Ă݂āA�u�Ȃ�قǂ������I�A�����͂d�r�זE���������Ă��邪�A������ǂ������ړI�Ŏ��g��ł���̂��H�v���ēx�l�������Ă݂��B
���ꂩ��A�d���ɑ���ԓx���ς�����悤�ȋC������Ƃ������b�ł������B
�@�u�����������A���A�m�g�j��̓h���}�ŁA�w�Ԃ���x������Ă���B���Ƀh���}�ł͎����g�c���A�������ɔ��ŏ������w�u���x�ƌ������t���v�������B
�@�]�˖����ɁA���{���͑�R�̎u�m���W���I�ɔy�o�����������ŁA���݂̖L���ȓ��{���ł����B���̓y��Â���́A�������疾���ېV�ɂ����Ă̎Ⴂ�u�m�����̂��������Ǝv���B
�@
�@�R���L��搶�̌����ŁA���Ɍ������Ă����l�Y�~�̎������d�r�זE�����邱�Ƃ��ł��Ă����B�d�r�זE�͑̂̂ǂ̍זE�ɂ��ω��ł��閜�\�זE�ł��邱�Ƃ��������Ă����B�������A�d�r�זE�́A�l�Y�~�i�}�E�X�j�Ő����ł������ƁA�}�E�X�̎��Ɍ�����Ƃ������̂ł������B
�@����ł́A�l�Ԃ̈�ÂƂ��Ďg�����Ƃ͂ł��Ȃ���Ԃł������B
�@
�@���Ƃ����āA���ł͂Ȃ��̂̔畆�Ȃǂ̕��ʂ̍זE�ŁA���\�זE���ł��Ȃ����Ɛ��E���̌����҂����g��ł����B���̒��ŁA�R���L��搶�̃O���[�v�����ɐ��������B
�@�����A�A�b�v�������o���������s���Ă����̂ŁA���o�r�������킴�Ə������Ŗ��������B
�@���{�l�͐V���������ۂɖ��O��t����̂�����ŁA���̓��ɊO���l�̃O���[�v���ʂ̖��O��t���āA���ꂪ���ۓI�ɗL���ɂȂ�悤�Ȃ��Ƃ��悭�����Ă����̂ŁA�����ɂ͏\�����ӂ��ĐT�d�ɍl�����Ƃ����b���������B
�@
�@�������o�r�זE���g�����ƂŁA���܂Œ���Ȃ������a�C��A�����ő����������ʂ̍Đ��Ȃǂ��\�ɂȂ�B�܂��A����זE�Ɛ���זE�̈Ⴂ�Ȃǂ�����ׂ邱�Ƃ��ł���B
�@
�@���߂ł́A�Ԗ��̉����ϐ��ǂ̏����ɖ{�l�̂��o�r�זE��|�{���āA���ߍ��ގ�p�𗝉��w�������Ŏ��{���A�悢���ʂ��o���Ă���B
�@�܂��A�p�[�L���\���a�̊��҂ɁA�]�̉��[���ɂ��镔�ʂɂ��o�r�זE�����邱�ƂŁA�̂̓����������邱�Ƃ����҂��Ă���B���̎�p�͔]�̉��[���ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ�����Z�p���v�邪�A�߁X���{����鏀�������Ă���B
�@�̑��A�X���Ȃǂ̑���̍Đ��ɂ����킪�n�܂��Ă���B
�@�搶�����A�����Ă��邱�Ƃ́A��R�̌�����̂˂�o���Ƃ������Ƃł������B
�����琔�\���~�̌������������Ă��邪�A���o�r�זE�������ɂ�400���߂��̃X�^�b�t�������Ă���B���̓��A����̐E���i���ƌ������j��1�����x�������Ȃ��B
�@�c��̑啔���́A1�N�A2�N�A3�N�A������5�N�Ԍ_��̌_���ҁA�܂��͔h���X�^�b�t�Ƃ��Čق��Ă���B���̗D�G�Ȍ_���ҒB�����ꂼ��̗���Ŋ撣���Č�����O�i�����Ă���B���̐l�����̋�����d���̂��A�R���L��搶�̍ő�̎d���݂����ɂȂ��Ă���B
�@�搶�̓}���\���ɏo�Ē��ڂ��W�߂Ă��邪�A��x�o�ꂷ��ƁA1500���~���x�̗�������炦��B���������܋��܂ŁA�X�^�b�t�̐l����ɏ[�Ăĉ��Ƃ����̂��ł���B
�Ƃ��낪�A�����ɂ��Ă͊������݂����ȍl�������������āA���炤�������炳���̂ɂ͑傫�Ȓ�R������B���̊��������ǂ����z���āA�\�Z�̍Ĕz�����ł��邩�����{�̖����̔��W�����肷��ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B
�@�搶����A���̉��ɂ��W�܂�̊�Ƃ̂s�n�o�̊F����ɁA�����ł��������肢�������Ƃ����؎��Ȃ��b���������B�č��ł͍��Ɨ\�Z�����{��葽�����A����ȏ�Ɋe��Ƃ���̊�t�i�h�l�[�V�����j�����ɑ��z�ɏ��A����ŏ���Ȏ����̌��Ō������i�߂��Ă��邻�����B
�@�����ŁA���{�����A���{�\�Z�̊���U������������������Ē�����A���S���~�Ȃ�P�o�ł���B���݂ł͂��o�r�זE�������̔N�ԍ��Ɨ\�Z��60���~���x�����Ȃ��B�������P�^���₵�āA���Ȃ��Ƃ��Q�O�O���~���炢�ɂ���A�����@�ނ̍X�V��A�@�ނ̑��݂�A�����҂̑�����A�����҂̐����̈���Ɏ����邱�Ƃ��ł��A���̌��ʁA�������傫���O�i�ł���B
�����āA���̕���œ��{�͐��E�̃g�b�v�����i�[�Ƃ��đ��葱���邱�Ƃ�����Ǝv���B
�@���{�̉ߋ��̉h���A�w�i���������@�����@�m���D�P�x�ƌ���ꂽ�����ƒ��S�̎���́A�Ƃ��ɉ߂�����A���������E�̐����H��ɂȂ����B����͎���̗���ł���B
�@
�@���{��V�����h�点��ɂ͍��܂łƈ�������o�r�זE�Ȃǂ̐�[��Â�A��[�Z�p����ɏd�_�I�ɗ\�Z��U������錩���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��������Ǝv���B
�@���̂܂܂̏�Ԃł́A��l������̂f�c�o���ǂ�ǂ��葱����B���{�͑傫�ȕt�����l�̏��i��Z�p���ǂ����Đ��ݏo�����A�ǂ̕���ŕt�����l�ݏo���̂����l���āA�����ɏd�_�������邱�Ƃ�����B���܂łǂ���A���ՂȂ��z��ł͂���n�ɂȂ�B
�@���䌧�ɂ��鍂�����B�F�u����v�͉ғ�����~���Ă���B���̒�~�̏�Ԃł��ێ���ɔN�ԓ�S���\���~�������Ă���B�֘A�̔�p�͂���ɖc���ł���B���̖��ɂ������Ȃ��S���̖��ʌ����B���q�͋K������̓c���ψ������A���{���q�͊J���@�\�̊Ǘ��ł͂��߂��Ƃ������_�ȏȂɒ�o�����B���{���q�͊J���@�\�ɑ��������͑��݂��Ȃ��B
�@������������ɁA���܂ł�����������ꂸ�\�Z�̐��ꗬ�����ł��鍑�͖͂����Ȃ��Ă���͂��B
�@���o�r�זE�������ɔN�ԏ��Ȃ��Ă�200���~����A�f���炵�����ʂ��o����B���Ȃ��Ă��J�����������A�Đ���Â��傫���O�i���A�����̕a�C�ɕa�ސl�������~����B
�����������_�ŁA���������u���������������L���A�����ɂ��̂�\�����Ƃ����ꂩ���ɂȂ�Ǝv���B
�@
�@��ʂ̖��ʌ�����������ŁA�s�����v��b�F�͖��b���撣���Ă����̂ŁA���̘b�����[���ő������B�܂��A�Ԏ����Ȃ����A���Ă�����ĉ����̓��������҂���B
�@
|
�@2015�N�X��17�i�j
���a���S�@�Ă��������H�@���̌�̓����́H
�@���͒x���܂ŁA���S�ψ���̕������e���r�ɉf����Ă����B���{�����ƁA���J�h�q��b�Ɗݓc�O����b������ō����đҋ@���Ă����B�莝���������Ȃ̂��A�ݓc�O����b�͎��X�A�X�}�z�����Ă����E�E�E�B
�@�w���@�ᔽ�@�āx�Ƌ���Ă��邱�́w���a���S�@�āx�����A�����ʂ���{����镽�a���S�@�ĂȂ�A�命���̍����͂������Ď^�����ׂ����̂��B
�@���{���{���ɁA���{���̍��ƁA�����̈��S�̂��߂ɕK�v�Ȗ@�Ă��ƍl���Ă���̂Ȃ�A���̔��̑����ɑ��ẮA�`�������܂����̂�������Ȃ��B��肭�������ł��Ă��Ȃ��Ƃ�������B
�@
�@���{�Ɋ�@������A�������ɖ@�Ă����Ȃ���A���Ƃ̑����Ɋ�Q���y�ڂ��A��ςȂ��ƂɂȂ�Ƃ������Ƃł���A�N�������Ȃ����A���}����B
������������A�����������t�ʼn���ƍ���ق����B
�@
�@�������A���A���������ł��Ȃ��B
�ŋ߁A���A�W�A�n��͈ȑO�Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ��悤�Ȋ�@�I�ɍ����|�����Ă���Ƃ����������B���̋�̓I�ȓ��e�́A�����Ɩk���N�̓����ɂ���B
�ŋ߂̋c�_�ŁA�����Ɩk���N�Ƃ����������o���ꂾ�����B
�@���̓�J���͂���ɋ߂����̂����邩������Ȃ��B�������A�����ɔނ炪���{�ɍU�߂Ă���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�����́A��t�������ӊC��ł̍s����A�X��ʖ����n�ɌR���{�݂��s��̌��݂ȂǁA���܂łȂ��g��H����˂������Ă���B����͎������B�������A���ꂪ���ړI���ق��ƂȂ���̂��낤���H
�@�������m�ɑ��Ă͈����A�����s�ׂ��Ƃ͂�����\�����A���E�̏펯�ɑi���邱�ƁB
���������Ƃ��\�����Ȃ��ŁA������R���͂��������āA����ɗ}�~�͂�^���鎖����Ԃ��I�@�Ƃ����X�g�[���[�őΏ�����Ȃ�A�ی��̂Ȃ��R���͋��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B
�@������U�O�N�قǑO�A���w���̍��A�w�Z�ŗL��V���Ђ̈̂��l�i�m���_���ψ��̕����������j�������āA���ɃX���X���Ɛ��E�n�}�������ɏ����ꂽ�B
�@�����āA���ł��o���Ă��邪�A�u���ܐ��E�̕��a�͂Ȃ�ŕۂ���Ă��邩�킩��܂����H�v�ƌ�����������ꂽ�B���w���ɑ��鎿��ł���B
�@���̓����́A�wBalance�@of terror �x���ƌ���ꂽ�B
�āE�I�����q���e��A���f���e�̎������d�˂āA�݂��Ɉُ�ȌR���͂��g�債�A���̎����ɒn����j�ł�����ɏ\���ȗʂ̌����␅���𗼍��ŕۗL����Ă������ゾ�����B�@���E���a�́w���|�̋ύt�x�ŕۂ���Ă���̂��Ƃ������Ƃł������B
�@���̗����ŁA�w�ڂɂ͖ڂ��x�Ƃ����R���͂őR���邱�Ƃ͂Ȃ�̉v�����܂Ȃ��B
�������A�}�~�͂Ƃ����͎͂��Ƃ��ėL�������m��Ȃ��B
����́A�݂̌R���͂�m��A�푈���Ă��݂��ɑ傫�ȏ������Ƃ��킩��̂ŁA����Ȃ疳�v�Ȑ푈�͂�߂悤�Ƃ������Ƃ��B
�@�����A�Е������荑�ɏ���R���͂�ۗL���Ă���Ƃ���A�U�ߍ��ނ̂��H
����́A���̂Q�P���I�̐��E�̗ǎ��������Ȃ��Ǝv���B
�@�Q�O���I�����̐��E���鍑��`�v�z���ʂ�������Ȃ�A�����̗̓y�g���o�ϗ͊g���ڎw���āA�U�߂�Ƃ����\�}���������B���{���ߋ��ɂ����������オ�������B
�������A���A����������Ȃ��Ƃ����ۓI�ɋ�����鎞��ł͂Ȃ��B
�@���݂��l�ł��邪�A���������{�̋Z�p��A�o�ό𗬂Ȃ����Ă͂���čs���Ȃ��B
�@�����i�Áj�����q����ɓ��{�ɂQ��U�߂Ă������Ƃ�����B�w�����̖��x�ł���B
��������_���i�䕗�j�������r��āA�قƂ�ǂ̌R�͂����v���A���{�͏��������B
�@
�@���������ߋ��̗��j�I�Ȏ��b�ƌ���͑S���Ⴄ�B
���݂��Ɍo�ϓI�ɂ͐[�����т��A�l�I�𗬂�����ɍs���Ă��錻��ŁA��t�������ȂǂŊ�@�ӎ���A���t���A����ɑΏ����邽�߂ɕ��a���S�@�Ə̂��āA�W�c�I���q���̍s�g��F�߂�Ƃ������e�͍s���߂��ȏ�̉����ł��Ȃ��B
�@
�@�A�����J�����Ĉ��S�ۏ���̓������Ƃ��āA���{�Ɂw�R���I�ȃp���[�i�R���́j�������̕��S������x�Ƃ����X�g�[���[�͗����ł��Ȃ��ł��Ȃ��B
�@
�@����͂���Ƃ��āA���{�͐��E�ɔ�ނȂ����{�����@�Ő푈�����ƕ��a��`��搂��Ă���B���̕��a���@�����݂���ȏ�A���ē������S�ۏ�̑̐���A���͂̈��S�ۏႪ�ǂ����낤�Ƃ��A�������ƂƂ��Č��@�����{���̍����ł���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�w���{�����@�����ۓI�ȏ펯���炸��Ă��Ă���x�ƌ����邩������Ȃ��B
���̏ꍇ�͂܂����@�ɂ��āA���Ԃ������Ă悭�����I�ȋc�_���A���̏�Ō��_���l��Ηǂ��B���̏ꍇ�͏\���c�_��s��������ŁA�������[��I���ŁA���@�����𑈓_�ɂ��A�������Ō��߂�����B���̒i�K�ނ��Ƃ����߂���B
�@����̃S�^�S�^�̗v���́A����t�ł�����{���t���˂������Ă��鎖�ɂ���B
����͑���{���t�����|�I�����̋c�Ȃ����Ƃɑ��鎩�掩�^�̌��ʂ��B����������ƁA�������炠����M�����Ƃ����v���オ�肾�B
�@�����}���A�ȑO�̖���}�̎����H�@���n���̂̂܂��������ɑ��A�o���L���Ȑl�ނ𑵂��������}�ɑ��A�傫�Ȋ��҂������ē��[�������Ƃ͎������B�������A����Ƃ��ܘb��̕��a���S�@�āA���̂��̒��́w�W�c�I���q���x�ɂ��č������F�߂��Ƃ����_���͑S���Ȃ��B���{����́A���̓_��傫�����Ⴂ���Ă���B
����A�������Ă��Ȃ���A�����̎�`�咣��ʂ��������߂ɁA���������X�g�[����簐i���Ă���̂����m��Ȃ��B�{�l�����킩��Ȃ��_���B
�@
�@����ɂ��Ă����a�̓}�������͂��̌����}�܂ł�����ɏ���Ă��܂��Ă��邱�Ƃ��B�����}�͗^�}�̊Â��`���z���Ă��܂��āA�{���̓}�̌��_��Y��Ă��܂����̂ł͂Ȃ����B���̏؋��ɁA��̂̑n���w������}�Ɉ�a����\���Ă���B
�@������̈ψ����A����O�ŏW����J������A���@�w�҂⎯�҂⌳���t�@���ǒ����Ȃǂ̍u����A�L����A�����̃f���s�i�����Ă���ƁA������̂��߂ɂ���̂��Ǝv����قǁA�l�����ɑ傫�Ȋu�����������B
�@
�@�����}�́A���{����̂������H�ő叟�������̂ŁA���{����ɓ����オ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂��낤���B��Ȃ��b���B
�@�����Ȉӌ��������������}�c�����A���͈��{����ɋt��킸�A�ق��Ă����ق�������ƍl���Ă���̂��낤�B
�L�\�Ȑl�����������}�c�����S���A���{����̍l���Ɠ������Ƃ͓���l�����Ȃ��B
�@�ނ�́A�펯�⎯�����[���������l�B���Ǝv���B���̎����}�c������N�����_���Ȃ��Ƃ���ɁA���{�̐����̍���ɕs����������B
�@
�@���a�̎���A�����m�푈�Ɏ��������̐����̗���ɒʂ�����̂�����̂ł͂Ȃ����Ƃ�������B����͓��{�l���̊m�����\���ł��Ă��Ȃ����ɋN������Ǝv���B
�@���ď����́A�l�E�l�̎���̊m���͔��ɋ����B��l�ł������ł���B
�@���{�l�͐������q�́w�a���ȂāA�����Ƃ���x�Ƃ����a�l�̈�`�q�������Ɏp����Ă���B����͈������Ƃł͂Ȃ��B
�@���ď�����������������̂ɑ��āA���{�͌×�����_�k�����ł������̂ŁA�݂�Ȃœn��Ε|���Ȃ��I�Ȕ��z���������Ƃ������Ƃ��B
�@�����������{�����̓������������Ȃ���A���E�ɒʂ���f���炵����������Ă䂩�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���ď����Ɠ����̉��l�ς������Ď��ɏ�����Ƃ��������A�O���[�o��������̓��{�̎{��ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���B
�@�ȉ��A�{���̒����V���̎А������Љ��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@************************************************************
�@�u�ጛ���@�v�̌��ց\���@�����@�łȂ�����̂��@�@2015�N9��17���i�j�t
�@���܂鍑���̔��̒��A���S�ۏ�֘A�@�Ă��߂���^��}�̍U�h�͍ŏI�ǖʂ��}�����B�^�}�͂����܂ł��T���ɐ���������\�����B
�����t���u���@���������Ȃ���ł��Ȃ��v�Ɩ������Ă������@���߂��A���{���t���W�c�I���q���̍s�g��F�߂�t�c����������͍̂�N�V���B�ȗ��A���@�w�҂⌳���t�@���ǒ�����̐��Ƃ����̂����������J��Ԃ��w�E���Ă����B
�����������ǂ�������
���̌���ł��A�ጛ���@�R���������ō��ق̒����߂��R���Ɏ��̎��̌��t���B�u�]���̌��@���߂��A�X���̋K�͂Ƃ��č����Ɖ����Ă���B�W�c�I���q�����s�g�������̂Ȃ�A�X������������̂��ł���A���U�@���v���͂�ō��ق̔��f��҂܂ł��Ȃ��B�W�c�I���q���ɂ�����闧�@�͈ጛ���ƍl������Ȃ��B
�@�Ȃ��A�W�c�I���q�����s�g�ł���悤�ɂ��Ȃ���A�����̐�������Y����邱�Ƃ�
�ł��Ȃ��̂��B
�@���̍��{�I�Ȗ₢�ɁA���{�͓��{�l��������Ċ̖͂h��⒆���z�����Y�C���̋@���|�C�������o�������A���̐����͐R�c�̉ߒ��Ŕj�]�i�͂���j�����B
����ł������͖@�����ւƂЂ��������B����́A���{���t�����@�d���i�삷��`������炸�A�����}������}�Ȃǂ������ǔF���邱�Ƃ��Ӗ�����B
�@�����Ƃ̓y���h�邪���s�ׂ��ƌ��킴��Ȃ��B
���{���������ǂ��Ă�������U��Ԃ��Ă݂悤�B�Q�O�P�Q�N���ɐ������A�������{���́A�X������������ɁA�܂����@�����葱�����ɂ߂�X�U���������������B�Ƃ��낪���_�̗����������Ȃ��Ƃ݂�ƁA�X���̉��ߕύX�ւƓ]������B�L���҂ɉ����̐����₤�K�v�̂Ȃ��u�����v�ł���B
�^����Ɏg�����̂��A�ጛ���@��h�����{���֖̊�ł���A�W�c�I���q���͍s�g�ł��Ȃ��Ƃ̈�����������Ă������t�@���ǂ̒�������������Č�コ����ւ��肾�B
�@���ǂ̐V���ȑ̐��̂��ƁA�����͏W�c�I���q���́u����e�F�v��ł��o�����B�����Ƃ����̂́A�T�X�N�̍��쎖���ō��ٔ����ƂV�Q�N�̐��{�������B
���@�̎x�z��������
�@�����A����ٔ��ł͓��{�̏W�c�I���q���͖���Ă��Ȃ��B�V�Q�N�����͏W�c�I���q���̍s�g�͋�����Ȃ��Ƃ̌��_���B�u����v�ł��낤�ƂȂ��낤�ƁA�W�c�I���q�����s�g�ł���Ƃ��鐭�{�̗����͋��ʂ�Ȃ��B
�@���̖�����}�炸�����t�����̂��u�@�I���萫�͊W�Ȃ��v�Ƃ̎⍲���̌��t�������B���̂��������ɂ�����A�{��̐�������̊O�ɂ��傫���L�������͓̂��R�ł���B
���{�́u���S�ۏ���̕ω��v�𗝗R�ɁA���ē������������ė}�~�͂����߁A�����̈��S�����ƌJ��Ԃ��Ă����B�����������S�ۏ�_�ɂ��Ȃ����l�����邾�낤�B
����A���q�����o��������Ƃ����傫�ȍ��ƌ��͂̍s�g�ɂ������ẮA���{�͋ɂ߂�
�}���I�ł���ׂ����B�ǂ�ȂɈ��S�ۏ�����ς�����Ƃ��Ă��A���@�ƈ�̂ƂȂ��Ē��N�蒅���Ă������߂��A����t������ɐ����̌��_�ɕς��Ă������R�ɂ͌����ĂȂ�Ȃ��B
����Ȃ��Ƃ��������Ȃ�A�Љ�I�A�o�ϓI�Ȋ��̕ω��𗝗R�ɁA�\���̎��R��
�@�̉��̕����𐭕{���������Ă����ƂȂ��Ă����������Ȃ��B
�R���I�ȗv�������@���D�悳��邱�ƂɂȂ�A���@�̋K�͐��͂Ȃ��Ȃ�B
�܂�A���@�����@�łȂ��Ȃ��Ă��܂��B
��������`��₢����
�@����́A���D��Ō��ɂ���u�@�̎x�z�v����̈�E�ł���B���q�����C�O�ł̊������L���邱�Ƃ����}���鍑�����邾�낤�B�����A�����ڂŌ���A���{���{�ւ̐M�����ނ��ށB
�@�ٔ�������ጛ���Ɣ��f����郊�X�N��w������������Ƃ邱�Ƃ��A���S�ۏᐭ��Ƃ��ē��Ƃ��v���Ȃ��B
�́u�Ă܂łɐ��A������v�Ƃ̕ċc��ł̖��ЂƂ܂��ʂ������ƂɂȂ肻�����B
����ŁA�@���ǒ����̌��Ɏn�܂邱�̂Q�N�Ԃ�ʂ��Ė��炩�ɂȂ����̂́A���Ƃ�����c���̐��̂����ł́u�ꋭ�v�̐����ł��A���@�̔�����������Ƃ���ɂ͖c��ȃG�l���M�[��v����Ƃ������Ƃ��B
���@�́A���ꂾ���d���B
���@�w�҂�ٌ�m�̗L�u���A�@�{�s��Ɉጛ�i�ׂ��N�������������Ă���B�ٔ���ʂ��Ĉጛ����i�������A�u�����I��������Ɓv�ɂ͂����Ȃ��̂��ړI���Ƃ����B
���@���Ȃ�������ɂ�����{�����̎p���ɂ���āA���͂����@�Ŕ��闧����`�̈Ӌ`�������ɍL�܂����̂́A�ɂƂ��Ă͔���Ȃ��Ƃł͂Ȃ����B
���߂Ė₢���������B���@�Ƃ͉����A���@�ƌ��͂Ƃ̊W�͂ǂ�����ׂ��Ȃ̂��B
�@���������Ă��A�c�_���I���ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�@*****************************************************************
�@�ȏ�ł��B
�����͗��j�I�ȓ��ɂȂ邩������܂���B
����́A�V�O�N�����Ă������{�̕��a���S�ɑ���l�����͑傫���ς����ł��B
���ꂩ��̓��{�́A�s���S�ȍ��ɂȂ邩������܂���B
|
2015�N8��15���i�y�j
�I��L�O�����}���A����̈��������̒k�b
�q�S���r
�@�I��70�N���}����ɂ�����A��̑��ւ̓��̂�A���̕��݁A20���I�Ƃ���������A�������͐S�Â��ɐU��Ԃ�A���̗��j�̋��P�̒�����A�����ւ̒m�b���w�Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl���܂��B
�@100�N�ȏ�O�̐��E�ɂ́A���m�����𒆐S�Ƃ������X�̍L��ȐA���n���L�����Ă��܂����B���|�I�ȋZ�p�D�ʂ�w�i�ɁA�A���n�x�z�̔g�́A�\�㐢�I�A�A�W�A�ɂ������܂����B���̊�@�����A���{�ɂƂ��ċߑ㉻�̌����͂ƂȂ������Ƃ͊ԈႢ����܂���B
�A�W�A�ōŏ��ɗ���������ł����āA�Ɨ�����蔲���܂����B
�@���I�푈�́A�A���n�x�z�̂��Ƃɂ����������̃A�W�A��A�t���J�̐l�X��E�C�Â��܂����B
�@���E����������ꎟ���E�����o�āA���������̓������L����A����܂ł̐A���n���Ƀu���[�L��������܂����B���̐푈�́A1000���l���̐펀�҂��o���A�ߎS�Ȑ푈�ł���܂����B�l�X�́u���a�v�������肢���ۘA����n�݂��A�s����ݏo���܂����B�푈���̂���@������A�V���ȍ��ێЉ�̒��������܂�܂����B
�@�����́A���{�������݂𑵁i����j���܂����B
�������A���E���Q���������A���ď������A���n�o�ς��������o�ς̃u���b�N����i�߂�ƁA���{�o�ς͑傫�ȑŌ����܂����B
�@���̒��œ��{�͌Ǘ�����[�߁A�O��I�A�o�ϓI�ȍs���l�܂��͂̍s�g�ɂ���ĉ������悤�Ǝ��݂܂����B�����̐����V�X�e���́A���̎��~�߂��肦�Ȃ������B�������āA���{�͐��E�̑吨���������Ă����܂����B
�@���B���ρA�����č��ۘA������̒E�ށB���{�́A����ɁA���ێЉ�s��ȋ]���̏�ɒz�����Ƃ����u�V�������ے����v�ւ́u����ҁv�ƂȂ��Ă������B�i�ނׂ��j�H�����A�푈�ւ̓���i��ōs���܂����B
�@
�@������70�N�O�A���{�́A�s�킵�܂����B
���70�N�ɂ�����A�����O�ɝˁi�����j�ꂽ���ׂĂ̐l�X�̖��̑O�ɐ[�����i�����ׁj�𐂂�A�ɐɂ̔O��\���ƂƂ��ɉi���i���������j�̈����̐�������܂��B��̑��ł́A300���]�̓��E�̖��������܂����B�c���̍s�������Ă��A�Ƒ��̍K�����肢�Ȃ���A��w�ɎU�������X�B�I���A�����́A���邢�͎ܔM�i���Ⴍ�˂j�́A�����ً��̒n�ɂ����āA�Q����a�ɋꂵ�݁A�S���Ȃ�ꂽ���X�B�L���Ⓑ��ł̌��������A�������͂��ߊe�s�s�ł̔����A����ɂ�����n���Ȃǂɂ���āA��������̎s��̐l�X�����c�ɂ��]���ƂȂ�܂����B
�@������������X�ł��A���������҂����̖������m�ꂸ�����܂����B
�����A����A�W�A�A�����m�̓��X�ȂǁA���ƂȂ����n��ł́A�퓬�݂̂Ȃ炸�A�H�Ɠ�Ȃǂɂ��A�����̖�烁i�ނ��j�̖����ꂵ�݁A�]���ƂȂ�܂����B���̉A�ɂ́A�[�����_�Ƒ�����������ꂽ�����������������Ƃ��Y��Ă͂Ȃ�܂���B���̍߂��Ȃ��l�X�ɁA�v��m��Ȃ����Q�Ƌ�ɂ��䂪�����^���������B
�@���j�Ƃ͎��Ɏ��Ԃ��̂��Ȃ���i����j�Ȃ��̂ł��B��l�ЂƂ�ɂ��ꂼ��̐l��������A��������A������Ƒ����������B���̓��R�̎��������݂��߂鎞�A���Ȃ��A���t�������A���������f���̔O���ւ����܂���B
�@����قǂ܂ł̑����]���̏�ɁA���݂̕��a������B
���ꂪ�����{�̌��_�ł���܂��B
�@
�@��x�Ɛ푈�̎S�Ђ��J��Ԃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���ρA�N���A�푈�B�����Ȃ镐�͂̈Њd��s�g���A���ە��������������i�Ƃ��ẮA������x�Ɨp���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@�A���n�x�z����i���Ɍ��ʁi���ׂj���A���ׂĂ̖����̎����̌��������d����鐢�E�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�@��̑��ւ̐[������̔O�Ƌ��ɁA�䂪���͂��������܂����B���R�Ŗ���I�ȍ���n��グ�A�@�̎x�z���d�A�Ђ�����s��̐������������Ă܂���܂����B70�N�Ԃɋy�ԕ��a���ƂƂ��Ă̕��݂ɁA�������͐Â��Ȍւ������Ȃ���A���̕s���̕��j�����ꂩ����т��Ă܂���܂��B
�@�䂪���́A��̑��ɂ�����s���ɂ��āA�J��Ԃ��A�ɐȔ��ȂƐS����̂��l�i��j�т̋C������\�����Ă��܂����B���̎v�������ۂ̍s���Ŏ������߁A�C���h�l�V�A�A�t�B���s���͂��ߓ���A�W�A�̍��X�A��p�A�؍��A�����ȂǁA�אl�ł���A�W�A�̐l�X������ł������̗��j�����ɍ��݁A����т��āA���̕��a�Ɣɉh�̂��߂ɗ͂�s�����Ă��܂����B
�@�������������t�̗���́A������h�邬�Ȃ����̂ł���܂��B�����A�������������Ȃ�w�͂�s�������Ƃ��A�Ƒ������������X�̔߂��݁A��Ђɂ���ēh�Y�̋ꂵ�݂𖡂�����l�X�̐h�i��j���L���́A���ꂩ��������Ė����邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B
�@�ł�����A�������́A�S�ɗ��i�Ƃǁj�߂Ȃ���Ȃ�܂���B���A600���l��������g���҂��A�A�W�A�����m�̊e�n���疳���A�҂ł��A���{�Č��̌����͂ƂȂ����������B
�����ɒu������ɂ��ꂽ�O��l�߂����{�l�̎q�ǂ��������A�����������A�Ăёc���̓y�ނ��Ƃ��ł����������B�č���p���A�I�����_�A���B�Ȃǂ̌��ߗ��̊F���A���N�ɂ킽����{��K��݂��̐펀�҂̂��߂Ɉԗ�𑱂��Ă���Ă��鎖�����B
�푈�̋�ɂ����i�ȁj�ߐs�����������l�̊F�����A���{�R�ɂ���đς����ɂ������ߗ��̊F���A����قNJ��e�ł��邽�߂ɂ͂ǂ�قǂ̐S�̊���������A�����قǂ̓w�͂��K�v�ł��������B
���̂��ƂɁA�������͎v����v���Ȃ���Ȃ�܂���B���e�̐S�ɂ���āA���{�́A���A���ێЉ�ɕ��A���邱�Ƃ��ł��܂����B���70�N�̂��̋@�ɂ�����A�䂪���́A�a���̂��߂ɗ͂�s�����Ă������������ׂĂ̍��X�A���ׂĂ̕��X�ɁA�S����̊��ӂ̋C������\�������Ǝv���܂��B
�@���{�ł́A��㐶�܂�̐��オ�A����A�l���̔������Ă��܂��B���̐푈�ɂ͉���ւ��̂Ȃ��������̎q�⑷�A�����Ă��̐�̐���̎q�ǂ������ɎӍ߂𑱂���h����w���킹�Ă͂Ȃ�܂���B
�@�������A����ł��Ȃ��A���������{�l�͐�����āA�ߋ��̗��j�ɐ^���ʂ����������Ȃ���Ȃ�܂���B�����ȋC�����ʼnߋ����p���A�����ւƈ����n���ӔC������܂��B�������̐e�A���̂܂��e�̐��オ�A���̏Ă��쌴�A�n�����̂ǂ��̒��ŁA�����Ȃ����Ƃ��ł����B�����āA���݂̎������̐���A����Ɏ��̐���ւƁA�������Ȃ��ł������Ƃ��ł���B����́A��l�����̂���܂ʓw�͂Ƌ��ɁA�G�Ƃ�������i����j�ɐ�����č��A���B�A���B�������͂��߁A�{���ɂ�������̍��X����A���Q�i���イ�j���z���āA�P�ӂƎx���̎肪�����ׂ̂�ꂽ�������ł���܂��B
�@���̂��Ƃ��A�������́A�����ւƌ��p���ł����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���j�̋��P��[�����ɍ��݁A���ǂ��������Ă����A�A�W�A�A�����Đ��E�̕��a�Ɣɉh�ɗ͂�s�����B���̑傫�ȐӔC������܂��B
�@�������́A����̍s���l�܂��͂ɂ���đŊJ���悤�Ƃ����ߋ����A���̋��ɍ��ݑ����܂��B�����炱���A�䂪���͂����Ȃ镴�����A�@�̎x�z�d���A�͂̍s�g�ł͂Ȃ��A���a�I�E�O��I�ɉ������ׂ��ł���B���̌������A���ꂩ����������A���E�̍��X�ɂ����������Ă܂���܂��B�B��̐푈�픚���Ƃ��āA�j����̕s�g�U�Ƌ��ɂ̔p���ڎw���A���ێЉ�ł��̐ӔC���ʂ����Ă܂���܂��B
�@�������́A20���I�ɂ����āA�펞���A�����̏��������̑����▼�_���[��������ꂽ�ߋ������̋��ɍ��ݑ����܂��B�����炱���A�䂪���́A�����������������̐S�ɁA��Ɋ��Y�����ł��肽���B21���I�����A�����̐l�����������邱�Ƃ̂Ȃ����I�Ƃ��邽�ߐ��E�����[�h���Ă܂���܂��B
�@�������́A�o�ς̃u���b�N���������̉����Ă��ߋ������̋��ɍ��ݑ����܂��B
�����炱���A�䂪���͂����Ȃ鍑�̜��Ӂi�����j�ɂ����E����Ȃ��A���R�ŁA�����ŁA�J���ꂽ���یo�σV�X�e���W�����A�r�㍑�x�����������A���E�̍X�Ȃ�ɉh�������i����j���Ă܂���܂��B�ɉh�����A���a�̑b�ł��B
�\�͂̉����Ƃ��Ȃ�n���ɗ����������A���E�̂�����l�X�ɁA��ÂƋ���A�����̋@�����邽�߁A��w�A�͂�s�����Ă܂���܂��B
�@�������́A���ے����ւ̒���҂ƂȂ��Ă��܂����ߋ������̋��ɍ��ݑ����܂��B
�����炱���A�䂪���͎��R�A�����`�A�l���Ƃ�������{�I���l��h�邬�Ȃ����̂Ƃ��Č������A���̉��l�����L���鍑�X�Ǝ���g���āA�u�ϋɓI���a��`�v�̊��������f���A���E�̕��a�Ɣɉh�ɂ���܂ňȏ�ɍv�����Ă܂���܂��B
�@�I��80�N�A90�N�A����ɂ�100�N�Ɍ����āA���̂悤�ȓ��{�������̊F�l�Ƌ��ɑn��グ�Ă����B���̌��ӂł���܂��B
|
�@���낢��b��ɂȂ��Ă������{�����70�N�k�b������A�[�����\���ꂽ�B���A�V�O�N�̐ߖڂɓ�����A�����̍l������\���������Ƃ������Ƃ��Ǝv���B
������؍���4�̃L�[���[�h�������Ă��邩�ǂ������m���߂����Ȃnj����Ă����悤�����A���������ꎚ�ꎚ�̕����ɍS���Ă���悤�ł͂��܂��䂩�Ȃ��Ǝv���B
���ƍ��̊O���݂̗͌��v��\������A�Փ˂���͓̂�����O�̂��ƁB���̏�ŁA�O���[�o���ȏ펯�������Č݂��ɐڂ��������Ƃ�����Ǝv���B
���荑�̌����Ȃ��A���荑�̋@�����Ȃǂ��邱�Ƃ͂����Ă̂ق����B
�݂��Ɏ咣���������A�ǂ����ŗ����������A�����������n�����W�ŊO���͍s���ė~�����B
��̃I�����W�F�ɕς������́A�����C�ɂȂ����_�ł��B
����ŁA���A�Q�c�@�ŏW���R�c���Ă���w���a���S�@���x������B�c�_���Ă���ƁA�ۂǂ����ł̎��q���̑Ή����b�������Ă���B
�W�c�I���q������������ƁA���q���͍��܂ł����S�ɂȂ�Ƃ����킯�̂킩��ʂ��Ƃ������Ă��邪�A���ɉ������Ƃ��A�푈�Ɏg������e��A���Ƃ��^�Ԗ��������鎩�q���ɓG���͂ǂ������ԓx����邩�͎������Ǝv���B�ł���Ε��Ƃ߂肽���Ƃ����ꍇ�����邾�낤�B�����Ȃ���̏ꏊ�͐��ɉ�����B
�푈�ɍ��@����@���Ȃ��B���ɂ͖����`���A�l�����Ȃ��B��������ď����Ȃ���ΎE����邾���B������������ȏ�ɂ����āA����ŐR�c���Ă�����e�́A�����܂ŕ����i���a�ȏ�ԁj�ł̗����ł̉��߂ɂ���Ă���B
�@�푈�͍��Ǝ匠�����߂�A���q���̔h���Ɍq����A���łȂ��ꏊ�ɑ���o�����Ƃ����Ă��A�����͂����ɂȂ邩�S��������Ȃ��B
�@��̒k�b�́A���a��`���A���{����������܂łǂ�����g��ł䂫�܂��Ƃ����悤�ȈӖ��Ɏ���B����͌��\�Ȃ��Ƃ����A����ɂ��ẮA�悭�ǂݕԂ��ƁA�����i�D�lj߂��܂��B�@�����Ɛ^���ȁA�S����̔��Ȃ̎d���⍡��̎��g�݂̕\�����ł���͂��B�Ƃ肠����4�̕����荞�̂ŁA�����Ɗ؍��͂ǂ��o��ł��傤�H |
�@2015�N�W��11���i�j
�����A����������ĉғ�/�ՊE�ɓ��B�H
�����������̂ɒ���Ȃ����{�l�ُ͈�Ȑl��H
�@�e���r��V���ɂ��ƁA��B�d�͊Ǔ��̐���������A���E�ꌵ�������S��ɍ��v���Ă���Ƃ������ƂŁA�ғ����X�^�[�g�����B�X�^�[�g�����ƌ����Ă��A���d���J�n�����킯�ł͂Ȃ��B
�@��(�����j���������q�F�ɃE�����R���_��}�����A�R���_�̎���ɒ����q���z������z�E�f�iB�j�ŏo��������_�����āA�j�������N���Ȃ��悤�ɂ��Ă���B���q�F���ĉғ�����ꍇ�́A���̐���_�������グ��ƁA�R���_�̃E��������o�钆���q�����ׂ̔R���_�̃E�������q�ɏՓ˂���B���̒����q�̑��x���K���Ȓl�̎��ɁA�Փ˂��ꂽ�E�������q�����A��̒����q���o���B�ŏ���1�̒����q���Q�ɂȂ�A�S�ɂȂ�A�P�U�ɂȂ�A�E�E�E�Ƃ��̐��𑝂₷�B�����q�̐������̒l�ɒB���āA�A���I�Ɋj���N�����ԂɂȂ�ƁA�ՊE��ԂɂȂ����Ƃ����B
�@���̏�Ԃ́A�E�������q�j���������N���A���̍ۂ̌��q�j�̎��ʌ����ɂ�锭�M�Ŏ��͂̐������߁A�����̐��Ə��C�ɕς���B
�@���̓����́A�j�����M�����o�����ƂƁA������̓����́A�����q�̔�яo�����x��x�����铭��������B���͌����ނ̓��������Ă���B������͕��ː����Ղ�Օ��ނƂ��Ă������Ă���B
�@
�@�ՊE��ԂɒB�������q�F���獂���̐��A���C�����o���ă^�[�r�����A�Η͔��d���Ɠ��l�ɓd�C���N�������Ƃ��o����B�Η͔��d���͐Ζ��i�d���j��ΒY��V�R�K�X��R�₷���ƂŁA�R�ĔM�������{�C���[�ō����̐����C�ɕς��āA�^�[�r�����B
�@�����̏ꍇ�́A�Η͔��d���̂悤�ɐ��͍����ɂ͂��Ȃ��B�Η͔��d���̃{�C���[���̐��̉��x�͂U�O�O�x���炢�܂ō����Ȃ�B�����͂��������Q�O�O�x��Ŏg���B
�@��������̍��̗l�q�́A�ՊE��ԂɒB�����Ƃ������Ƃ�����A���炭���̏�ԂŌ��q�F�̈��S�����m�F���AOK�Ȃ炢�悢��A�^�[�r���ɐ��A���C���z�����A��ʂ̊C���ŏ��C�𐅂ɕς���ƁA�}���ɑ̐ς����k����̂ŁA���̍ۂ̖җ�ȃ^�[�r�����̋C���ω��ŁA�^�[�r���̉H���ɃG�l���M�[��^���A�^�[�r������]����B
���̍ۂ̏��C�̎��G�l���M�[�̂��Ƃ́A�E�����̌��q�j����̎��ʌ����ɂ��c��Ȕ��M�ɂ��B
�@�����̍ĉғ������Ă��闝�R�́A��x�ՊE��ԂɒB�������q�F�͎��̂ŋً}�ɒ�~�����鏈�u�����Ă��A�c��ȃG�l���M�[���o���Ă���E�����R���̊j�����͋}�Ɏ~�܂�Ȃ��̂ŁA��₵������K�v������B�ʏ�͂Q�S���Ԓ��x��₵�Ă��̌����₵�����鑀�삪����B�Η͔��d���͎~�߂�ۂ͔R���̃o���u��߂�����B
�@
�@�����A�����̌����ŁA���q�F���ً}��~�����Ƃ��Ă��A��₵�����邱�Ƃ��ł��Ȃ���ΘF�S���J���Ă���ԂɂȂ�A�R���_���n���ă����g�_�E������B
�F���̉��x�͂Q�O�O�O�x�߂��ɂȂ�A��������̂̓h���h���ɗn���Ă��܂��B
���̍ۂ̔��M�ʂ����͂̂��̂��D���M�ʂƃo�����X����܂ŗn��������B
�@���������͂܂��ɂ���������ԂɂȂ��Ă��܂����B�����ĉ��Ƃ��O������̕����ɐ��ŘF�S�ɐ�������A����ɔR������₳��āA���肵���B
���ł��A�����������炩�̌����ŘR��ĂȂ��Ȃ�A�܂��j���n�܂�A���x���㏸����\��������B
�@���q�F�͉����N���Ă��A�ً}��~�����ۂɏ\�����ŗ�₷���Ƃ��ł��Ȃ���A�����̓�̕����N����B������A���S��͂����������Ƃ�O����Ɍ��߂đΉ����Ă���B
�@��₷���߂ɂ́A�������ݏグ�ĘF�S�ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̂��߂ɂ͑������͂������Ă��Ȃ��Ɛ��������ł��Ȃ��B�F�S�͍�����Ԃ�����A�������܂̂悤�Ɉ��͂������Ȃ��Ă���B���̓����̈��͈ȏ�̈��͂������������p�C�v�Œ�������K�v������B�����Đ����z�����邱�Ƃł���B
�@�F�S�̐��͍������˔\���܂�ł���̂ŁA�F�S�̈��͂������邽�߂ɉ������Ƒ�ʂ̕��˔\����C���ɕ��o�����B
�@���܂ł́A���˔\�Ǘ����Ƃ�����ŁA�����킸�����˔\�R��ɂ��C���g���Ă����B���̉e���ŁA������ꌴ���͘F�S�̈��͂������鏈�u���x�ꂽ�B�����A�����Ƒ����F�S�̊J�������Ă����Ȃ�A��C���ɕ��ː��R��͋N�������A����̂悤�Ȕ����ő�ʂ̕��ː��R��͖h�����͂����B
�@�������������̎��̂̔��ȓ_�͏[����������Đ��E��̈��S��ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ́A���x�ȋZ�p���x����L������{�ł��邩�炫�����ƑΉ����Ă���Ǝv���B
�@�������A����͂����܂őz�肵���͈͓��̑Ή��ł���B�z��O�̎��̂�V�Ђ͓����悭�N����̂ł���B
�@�����̋K���ψ����̓c������������Ă��邪�A�w���E�ꌵ�������S���������̂ŁA����ɍ��i���������͏[�����S����ۂ��Ă���ƌ�����B�������A��Έ��S���Ƃ����Ƃ���͌����Ȃ��B�x�Ƃ����{�����I���Ă���B
�@����ڂ�����A�e�n�̌����̈��S������ɍ��v���Ă��邩�ǂ����`�F�b�N���}���ł��邪�A���E�ΎR�n�}������ƁA���{�͉ΎR�ŁA�S�����ΎR�ɑ�������悤�Ȉt���Ă���B�ΎR�ɂ��n�k�A�n�k�ɂ��ΎR�̕��Ƃ������邾�낤���A���{�͐��E�L���̒n�k���ł���A�ΎR���Ȃ̂ł���B
�����^��Ɏv�����Ƃ́A���E��n�k�������ΎR���������{�ŁA���E�ꌵ������ɍ��i���������͐��E����S�ƌ�����̂��낤���H
���̊W�������������Ȃ�����A���S�ł��Ȃ��B�����N����w�z��O�x�̂ł����ƂŁA�Еt����̂ł���B
�@�����ł�����A�����ł��Ă��Ȃ����肪����B����͊j�̃S�~�̏����ł���B
�������ғ�������ƁA�����x���̕��ː����������܂��B����N���ۊǂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����҂��B������e���͒I�グ���Č��������A����ɐV���������낤�Ɩ�N�ɂȂ��Ă���B�����������ɂ��܂��\���������A�w�����̓g�C���̂Ȃ��}���V�����ɏZ�ނ悤�Ȃ��́x�ƌ����Ă���B�p����������I�グ���āA�Ƃɂ����d�͂��N�������Ƃ���
���̂����b���B
�@���q�͔��d�͑��̔��d�V�X�e���������Ƃ������Z�ŁA�������Ă����B���������̃R�X�g�ɔp���������̔�p�͓����Ă��Ȃ��B�����A��������A����Ɏ��̂̑Ή��̏����R�X�g����悹����A�Η͔��d���R�X�g���オ��͂����B
�@�������d�͉�Ђ́A�����̂Ƃ���Ɋ��Ɋ������������錴��������A�X�ɓ������E�����R���܂Ŏ茳�Ɋ��ɂ���B�����Ă���̂ɁA�������Ȃ��ł���B���ǂ�������ԂɂȂ��Ă����B
�@�����������ɁA�S���̌����͍ĉғ��Ɍ����ĉ�������悤�ɓ����o���͂��B
�@���̓������낤���Ȃ��Ă���̂ŁA����ɑΉ����邽�ߏW�c�I���q���̍s�g���ł���悤���S�@�������������Ƃɖ�N�ɂȂ��Ă���B���l�Ɍ���������͖�N�ɂȂ��čĉғ���簐i���邾�낤�B
�@�ǂ��͕����̎��̂����āA�����̔p�������߂ē����Ă���B���{�͎��̂��N�����đ傫�Ȕ�Q���o���A�ĉғ���i�߂悤�Ƃ��Ă���B
�@���̕������ӎv���肷��v�l�̈Ⴂ�͂ǂ��ɂ���̂��낤���H
�@�����A�����Ƃ���Ƃ���݂ɂȂ��Ă��邱�ƂƁA�����Ƃ������̕|����������ƕ����Ă��Ȃ����炾�Ǝv���B�����Ƃ������Ă��Ȃ��Ƃ͌���Ȃ��B�����Ƃ������̘b�����肪�����͈��S�ŃN���[���ȃG�l���M�[�ł���Ƃ����Ȋw�҂�W�҂��狳������ƁA�{���̎p���������Ă��܂��B
�@�������������f���A�ӎv���肪�ł��鐭���ƂƐ��}�����{�̐��������鎞��ɂȂ��ė~�������̂��B
�@ |
2015�N�W���V���i���j
�����ς��Ȃ��I
���̖ҏ��ł��A�d�͂ɗ]�T������̂͂Ȃ��H
2015�N�W��8���i�y�j�ꕔ�NjL
����A���L�̕����f�ڂ��܂������A�W���W���́w�����V���x�����ɓ��l�Ȏ�|��
�L�����f�ڂ���Ă��܂����B�@�N���l���邱�Ƃ͓������Ȃ��I�Ɗ����܂����B
�����V���̓��e��ǂ�ŁA����A�f�ڂ������e�������������ĒNjL���܂����B |
���̉Ă͖ҏ��������Ă��܂��B
�@
�@NHK�̃j���[�X�����Ă���ƁA�䕗��n�k�̍ۂɏo����ʌx���̃u���[��ʂ��A
�w�M���ǒ��Ӂx�Ƃ��Ď��X����܂��B ���ꂭ�炢�A���N�̉Ăُ͈퍂���������Ă���Ƃ������Ƃł����A�ߔN�A�Ă̋C�����R�T�x���z����̂�������O�ɂȂ��Ă��܂����B
�@
�@�q���̍��A�a�̎R�i�L�c�̓c�Ɂj�ł��������͂R�O�x���������������炢�ŁA�^�Ăł��R�O�x�O�ゾ�����ƋL�����Ă��܂��B���́A���̍����R�x����T�x���炢���C�����オ���Ă���悤�ȋC�����܂��B
�@��X�́A��������͂̊������X�ɕω�����ƁA���̕ω��������Ȃ��Ƃ������Ȃ�����܂��B�悭�������w��Ŋ^�x�ł��B�C�Â������͂�ŏオ���Ă����Ƃ������Ƃł����A���̏����͂T�O�N�قǑO�ɂ͍l�����Ȃ�������Ԃ��Ǝv���܂��B
�@
�@�X�C�X�A���v�X�̕X�͂�����ɗn���āA�X�͂̒������h���h���Z���Ȃ�A�ȑO�A���n�ɍs�������́A�w���̂܂܂ł͑S���̕X�͂��n���ĂȂ��Ȃ邩���m��Ȃ��x�Ƃ����b�ł����B���n�K�C�h����w10�N�O�͂��̕ӂ͕X�͂������̂ł���x�Ƃ����b���āA���̏ꏊ�͍��A����̓��ɂȂ��Ă��܂����B���g���͒n���S�̖̂��ł��B
�@
�@NHK�́A�j���[�X�Łw�M���ǂɒ��Ӂx�ƌĂт����Ă��܂��B�����āA�w�K�ɃG�A�R�����g���܂��傤�x�ƌ����Ă��܂��B
�@
�@���N�̉ẮA���d�͂����w�ő�d�͎g�p���������ɂȂ�\�z�Ȃ̂ŁA�ߓd�ɋ��͂��Ă��������x�Ƃ����d�C�g�p�ɑ���x�����܂���B�C���^�[�l�b�g��ɂ́A�d�͎��v�̎��ԓI�Ȑ��ڂ��f������Ă��܂��B
���d�͂̃z�[���y�[�W�͉��L�̂Ƃ���
�@�@http://www.kepco.co.jp/corporate/energy/supply/denkiyoho/
�@
�@���Z�싅���n�܂�A���炭�͓d�͎��v���s�[�N�ɂȂ�܂����A�����i�W���V���j�̓d�͎��v���͂X�O����\�z���Ă��܂��B�܂��P�O���ȏ�̗]�T������Ƃ������Ƃł��B
�@�ő�d�͎g�p�����X�O�����z���Ɓw��⌵�����x�A�X�T�����z���Ɓw�������x�Ƃ����\���ɂȂ�܂��B
�@���N�̓s�[�N���łX�V�����炢�܂Ŕ������Ǝv���܂��B���ɂX�T���ȏ�ɂȂ�܂��ƁA�ǂ����̔��d����ϓd�����̏Ⴕ���ꍇ�A�d�͌n�����_�E�����邱�ƂɂȂ�A�L��̑��d�Ƃ������ԂɂȂ肩�˂܂���B
�@�d�͌n���͋����ʂɑ��Ď��v�ʂ��I�[�o�[����ƁA�d�͐ݔ���ی삵�A�d�͌n���̈���E�����ۂ��߁A�I�[�o�[���������������I�ɐؒf����悤�Ȏd�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B
����������ԂɂȂ�A�L�͈͂̒�d�ɂȂ�ꍇ������܂��B������s�[�N�J�b�g�ƌĂ�ł��܂��B
�@
�@�d�C���Ɩ@�ł́A�d�͎����������w�W�Ƃ��āA���v���Ƃ����\�����g���܂����A
�@�@���v�����i�ő���v�d�́��ݔ��e�ʁj�~�P�O�O�@�m��]
�@����ɑ��āA�V����e���r�ȂǕŎg�p����Ă���p��́A�d�͎g�p���ŁA
�@�@�ő�g�p�����i�ő���v�d�́��ő募���d�́j�~100�@�m��]
�Ƃ����\���ł��B
���v�����A�g�p���������悤�Ȃ��̂ł����A�ݔ��e�ʂ������Ă��A�ݔ����̏Ⴕ�Ă�����A�����e�i���X����������A����������������肵�āA�d�C�̋������ł��Ȃ��ꍇ������܂��̂ŁA�K�������ݔ��e�ʁ������ʁ@�ł͂���܂���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̂S���Ԃ̓d�͎����W
| ���t |
�ő募���d��
�i�ő唭�d���j |
�ő���v�d��
�i�g�p�s�[�N���j |
�g�p���i���j |
| 8/8 �i�\�z�j |
�Q�C�W�V�V��KW |
�Q�C�Q�T�O��KW |
�V�W.0�� |
| 8/7 |
�Q�C�V�W�Q��KW |
�Q�C�T�R�O��KW |
90.9�� |
| 8/6 |
�Q�C�W�T�S��KW |
�Q�C�S�U�V��KW |
86.4�� |
| 8/5 |
�Q�C�W�U�S��KW |
�Q�C�T�T�P��KW |
89.1�� |
�@�@
�@��\�̂Ƃ���A���̉Ă͍�N��菋���悤�Ɋ����܂����A����ł��d�͗]�T�͑傫�����P����Ă��܂��B
�@���q�͔��d���͈�ӏ����ғ������Ă��Ȃ��ɂ�������炸�A�d�͎��v�ɑΉ��ł��Ă���̂ł��B�@�Ȃ��ł��傤�H
�@
�@���d�̕�����ꌴ�����̈ȗ��A�S���̌��q�͔��d���͊��S�ɒ�~���Ă��܂��B���d�͍͂�����10�d�͉�В��ŁA��Ԍ�������������A�����ˑ��̏�Ԃł�������A��N�܂Łw��������~���Ă���̂ŁA�d�͋������s���I�x�ƌ�����~�̐��ɂ��Ă��܂����B�@�Ƃ��낪�A���N�͂��������b�������Ƃ�����܂���B
�@
�@���̗��R�͂���������Ǝv���܂��B
�@�@�d�C�̎g�p���̑Ή�
�@�@�@�d�C���������v�Ƃ̐ߓd�ӎ��̍��܂��A�ȓd�͉Ɠd��A�ȓd�͋@�킪
�@�@�@�����Ă������ƁB����͈�ʉƒ��Y�ƊE�����l�ł��B
�@�@�@�d�͎g�p�ʂ��Q�O�P�O�N�k�БO���P���V�疜�`�W�疜KW���������A�k�Ќ��
�@�@�@�P���T�疜KW�ƁA�P�O�������Ȃ��Ȃ��Ă���̂ł��B
�@�@�@�Q�O�O�O��KW����ƁA�����͖�Q�O��s�v�Ƃ������Ƃł��B
�@�@�@��̓I�ɂ́A
�@�@�@�@�@�Ɩ���LED�����i��ł��邱�ƁB
�@�@�@�@�@�@LED�͓������邳�ł��A�d�͏���A�d����1/10�A�u������1/3�ɉ�����B
�@�@�@�@�A�N�[���r�Y�ȂǂŁA�I�t�B�X�̗�[�ݒ艷�x���グ�Đߓd���Ă��邱�ƁB
�@�@�@�@�B��ʉƒ�ł́A�①�ɁA�G�A�R���A���̑��A�Ɠd���i�̏ȃG�l���i�����y���Ă������ƁB
�@�@�@�d�͂̑����v�����܂ł̂悤�ɁA�h���h���L�т�ł͂Ȃ��Ȃ��ė��܂����B
�@�@�@�@�k�БO�i�Q�O�P�O�N�j�ɔ�ׂāA�P�O�����d�͎g�p�������Ă���̂ł��B
�@�A�d�C�̋������̑Ή�
�@�@�@�@��~���̉Η͔��d�����ғ������Ă��邱��
�@�@�@�@���d�͊Ǔ��̌����̈����Â��Η͔��d���i�d���R���j����C���Ȃ���ғ������Ă���B
�@�@�@�@�@�Ⴆ�A�a�̎R�����̌�V�Η͔��d���A�C��Η͔��d���ȂljΗ͔��d�����ғ������Ă���B
�@�@�@�@�A���Ƃ͍������̎��Ɣ��d�ݔ������݂��A���O�d�C���g���悤�ɂȂ��Ă������ƁB
�@�@�@�@�@�]��������d�͉�Ђɔ����Ă��܂��B
�@�@�@�B���z�����d���傫����^���Ă��邱��
�@�@�@�@�@�Đ��\�G�l���M�[���搧�x�iFIT�j�ɂ��A���K�\�[�����d����ƒ�̉����ɐݒu�������z�����d
�@�@�@�@�@�ɂ��A�Q�O�P�O�N�ɂ͂Q�W�O��KW�ł��������A�Q�O�P�S�N�͂Q�V�O�O��KW�ɒB���Ă��܂��B��P�O�{�ɂȂ�܂��B
�@�@�@�@�@����́A�������P��łU�O��KW�`�P�Q�O��KW�Ȃ̂ŕ��ςP�O�O��KW�Ƃ��āA�����Q�V��ɑ������܂��B
�@�@�@�@�@�������A���z�����d�͓d�C���ʏ���钋�ԂɈ�Ԕ��d�ʂ�������̂ŁA�g�p�̃s�[�N�ɂ��܂�
�@�@�@�@�@���d���ł��܂��B���̂悤�ɏ��Ȃ����ς����Ă��A�����P�O����ɑ������܂��B
�Ȃǂ��������܂��B
�@�����̑Ή��ŁA���q�͔��d�����ғ������Ȃ��Ă��A���v�s�[�N���̓d�͗]�T��
�P�O���ȏ������Ƃ������Ƃł��B
�@���N�͗]�T�����R�������Ȃ��Ƃ����������ŁA�d�͋����̊�@�����A�����̍ĉғ��𑣂����悤�ȋC�����܂������A���N�͏����l�q���ς���Ă��܂����B
�@
�@�������A�����̍ĉғ��́A�e�d�͉�Ђ̔O��ł��B
���z�̓������������q�͔��d�ݔ�������A�����ɂ͔R���E�������ۊǂ���Ă����ԂŒ�~���Ă���̂ł�����A�d�͉�Ђ��炷��Ε�̎�������ł��B
�ꍏ�������ĉғ����������Ƃ����̂��{���ł��B���̂��Ƃ͗����ł��܂��B
��������܂菔�Ɍ����o���Ȃ�������܂�Ă��܂����B
���̗��R�͂Q�ł��B
�@��́A�����̈��S���ɑ���s�M�������܂��ė������Ƃɂ����ӏZ���̍ĉғ����Ή^���B�ĉғ��ɂ͋ߗZ���̍��ӂ��K�v�ł��B
�@������́A�d�͂̎��R���̓����ł��B
�@�܂��A�����̍ĉғ��Ɍ����A�����}���{���㉟�����A���q�͋K���ψ���w���E�ꌵ�������S������A���̌�������ɂ�茟�����邩��A�����ɍ��i���������͐��E����S���I������ĉғ����Ă�낵���x�Ƃ����_���Ői�߂Ă��܂��B
�������A����������Ȃ��Ȃ��N���A�ł��Ȃ��̂ŁA�������i���x��Ă��܂��B
�@���̌����ɍ��i������B�d�͂̐���������W�����{�ɍĉғ�����ƌ����Ă��܂����A��������������ɁA���X�ƌ������i�A�ĉғ����n�܂邩���m��܂���B
���E�ꌵ��������N���A�ł���A�����͈��S�ƌ�����̂ł��傤���H
�@�n�k��ΎR���̎��R���ۂ́A�l�ނ̌��݂̒m�\�⍂�x�ȉȊw�E�m���������Ă��Ă��A���S�ȗ\�m���ł��Ȃ��ł��܂��B
�@����ɍ��A�Q�c�@�Łw�W�c�I���q�A���a���S�@�x��R�c���Ă��܂����A���{�����͓��{�̎��ӎ��Ԃ̏ω��ɂ���@�E���X�N�����܂��Ă���̂ŁA�w���{���ƁE��������邽�߂̖@�āx�Ƃ������Ƃō���������܂����Ă��܂��B
�@�����A���荑�i�G���j�����{���U������ꍇ�A�s�s����_�����A�����Ƀ~�T�C���̏Ə������킹�邱�Ƃ���ԑ�Ō���^����L���ȑΏۂɂȂ�܂��B
����ɑ���Ή����ł��Ă���̂��ł��B�@
�@
�@�n���K�͂̎��R���ۂ𐳊m�ɗ\�m�ł��Ȃ��̂Ǝ������Ⴄ�b�ł����A�l�דI�ȍU���̊댯���͂ǂ����悤������܂���B���S�h�q�͕s�\�ł��傤�B
�@�~�T�C���U���ɑ��ẮA�~�T�C���őΉ�����Ƃ������Ƃł����A�ł�����������͂��ł��B�~�T�C���������ɏW�����������A�����͑ς����Ȃ��ł��傤�B�����Đ���s�\�ɂȂ�A���˔\���T���U�炳���̂ł��B
�@
�@���������S���ǂ����f���鍪���́A���R�ЊQ�̔��������P�O�O�O�N�Ɉ�x�Ƃ��A�����N�O�ɒf�w���Y�����Ƃ������Ȋw�I���������ɂ���m���Ōv�Z���āA�X�Ɉ��S�����|���Ĉ��S������A����ɂ�茟�������Ĉ��S���ǂ������f���܂��B
�@���̈��S��ȏ�̎��R���ۂ���������A������w�z��O�̂ł����Ɓx�Ƃ��ď���������Ȃ��̂ł��B
�@�����郂�m�i���i�A�ݔ��A�@�B�A�S�āj�̐v�E�����͂��������m���ƈ��S���̌��ɂ���ė��܂����B�����ȊO�̂��̂́A���̕��@�Ŕ[�����ł��܂��B
�@�Ⴆ�A��s�@�͗g�͂Əd�͂̃o�����X�������ƁA�K���ė����܂��B���d�̈��S����{�����S�������Ă��A�ė����͕̂K���N���܂��B�������A�����Ă���Q�͌���I�ł��B
�@�����͉����̌����Ŏ��̂��N����ƁA���̔�Q�͐l�Ԃ̑����\�ɂ��A�L�͈͂ɓn��A�����������Ԃɂ킽��܂��B�l�Ԃ̗͂ł͎肪�����Ȃ��Ȃ�܂��B
���ꂪ���q�͂̐��E�̂ł����Ƃł��B
�@
�@�������������̕�����댯����m��Ȃ���A���Ƃ��������Ɩ�N�ɂȂ��Ă��܂��B
�����ėǎ�������ӏZ���̕s���͍��܂����ł��B
�@������̗v���͓d�͎��Ɩ@�����ɂ��d�͂̎��R��������܂��B
�@���܂ŁA�d�C���Ɩ@�œ��{�͂X�d�͉��+����̂P�O�d�͉�Ђɂ��n��Ɛ萧������Ă��܂����̂ŁA�Z��ł���ꏊ�ɂ��ǂ̓d�͉�Ђƌ_�邩�͎����ƌ��߂��Ă����B�d�C�͋K�����Ƃ������킯�ł��B
�@����̓d�C���Ɩ@�̉����ŁA�d�C�̔����͎��R������A�ǂ̓d�͉�Ђ���ł�������悤�ɂȂ�܂��B�����Ȃ�ƁA�d�͉�Ђ͈����Ĉ��肵���d�C���������Ȃ���A���v�҂͑��̓d�͉�ЂɌ_��ύX���邱�ƂɂȂ�܂��B������A�w�����̍ĉғ����Ȃ���Γd�͕s�����I�x�Ƃ����P���ȋ����H�͒ʂ��Ȃ��Ȃ�킯�ł��B
�@���āA�d�C�����d�͂��瑼�̓d�͉�ЂɌ_��ύX����ꍇ�A�w�d�C���ǂ����Ď�̂��H�x�Ƃ����^��������܂��B
�@�K�\�����Ȃ�ʂ̃K�\�����X�^���h�ɍs�������̂ł����A�d�C��K�X�͓d����K�X�ǂ��K�v�ł��B�Ⴆ�A���܂ł̊��d�͂ƈႤ�d�͉�Ђƌ_��ꍇ�A�w��d�̓d����\�蒼���̂��H�x�Ƃ����^�₪����܂����A�d���͍��܂łǂ���ŁA���d����z�d���͕ς��܂���B
�@���̓d�͉�Ђ͔��d�ݔ������݂��āA���̓d�͂����d�͂̑��d�ԂɂȂ��ł���̂ł��B�����łǂꂾ���̓d�͂𑗂����̂��f�[�^��c�����܂��B
�@���v�ꏊ�i�e�ƒ��H��Ȃǁj�̓d�͌v�͐V�����_���d�͉�Ђ̃��[�^�ɕt���ւ��邱�ƂɂȂ�܂��B�����Ă��̎g�p����V�����_���d�͉�ЂɎx�����Ƃ��������ł��B
�@�b������܂������A���N�̉Ă̓d�͗]�T�͏\�������Ƃ������Ƃł��B
�����ȉ䖝�����Ȃ��ŁA�������͓K�ɃG�A�R�����g���A�M���ǂɂȂ�Ȃ��悤�Ɍ݂��ɒ��ӂ��܂��傤�B |
�@�@�@
2015�N�V��29���i���j
�w���a���S�@�āx�̍���R�c������
�@�u���̑�����S�����A��������邽�߂̐�ڂ̂Ȃ����S�ۏ�@�Ă��V��16���ɏO�c�@��ʉ߂��܂����B�@�O�c�@�̖@�ĐR���ψ���̗l�q���e���r���p��A�C���^�[�l�b�g���p��j�R�j�R���撆�p�����Ă���� �A�c�_�����ݍ��킸�A��}�̓˂����݂ɑ��āA���{����ꗬ�́w�E�E�E�ł������܂��āx�w�E�E��������E�E�E�x�w���c�_���E�E�E�x�ȂǁA���t�̕ςȒ��J�p��̑��p��A�w��ʘ_��\�d�グ��ƁE�E�E�x�w����Ɏ��ɑ��Đ\���グ���Ȃ��E�E�x�Ƃ������\���ŁA�̂�肭���Ǝ�������킵�āA�������������Ă���̂��A�悭������Ȃ������B�����āA�V��16���ɋ��s�̌����s�����B
�@�O�c�@�͗^�}�����|�I�Ȑ����m�ۂ��Ă���̂ŁA������ł����s�̌��͂ł���B
�@�������A������������������̂́A�����}�͌��X�A�Љ�}�n�̂悤�Ȑ��͂������͂����A���͎����}�ɎC����A�^�}�Ƃ��ĊÂ��`���z���Ă���B����̏O�c�@�ł̍̌����@�ĂɎ^�������B
�@
�@���a���S�@�ẮA�`���Ɍf�����Ƃ���A�u���̑�����S�����A��������邽�߂̐�ڂ̂Ȃ����S�ۏ�@�āv�Ƃ����\���ɂȂ��Ă���B
�@����͕����ɂ����Ă��Y�펖�̕\���ł���B�����A�펞�ɂȂ�ƁA�E�������̐��ŁA���܍���ŐR�c���Ă�����ł͎��q���̊����͂ł��Ȃ��Ƃ����A���̂悤�Ȑ��������ǂ����Ăł���̂��ł���B
�@�N���l���Ă��A���ł͎E�������̏ꂾ����A���{�̎��q���͂��������K���ŎQ�����Ă��邩����{�̎��q���ɂ͍U���������Ȃ��Ƃ����悤�ȗ����͑S��������Ȃ��B
�@������A�����̗��_�ŁA�����玩�q���͍���̖@�Ă��ʂ�A�ȑO�����S�ɂȂ�Ƃ����悤�Ȕn�������b�����X�ƍ���łȂ���Ă���B
�@
�@���{�̎��ӂ̏��ŋߋ}���ɕς���Ă��Ă���B�����͌R���g�����āA�ǂ�ǂ��t��������ӊC��ɐi�o���Ă���B�k���N�̍s���̌������Ȃ��B�e���e�~�T�C���˂��ē������̊C�ɂ��Ă��Ȃǂƌ����Ă���B
�@������A�ʓI���q���i���q�������œ��{�����j�ł͑Ή����ł��Ȃ��̂ŁA�W�c�I���q�����s�g�ł���悤�ɖ@�������A�@�Ă����Ƃ�������̍s���ɏo���B
�@���Ƃً͋}��v����̂ŁA���{����͑����@�Ă�����ŏ��F���ʉ߂��������ƌ����Ă���B�������A���̂U��18���ɏ������悤�ɁA���@�Ƃ��ꗂ⌛�@�ᔽ���Ƃ��������w���҂⌛�@�w�҂�A�����t�R�c���A�@���ǒ����܂ŁA���̓��e�͌��@�ᔽ���ƌ����o���n���ɂȂ����B���{����͓��S�A�傫���h��Ă��邱�ƂƎv���B
�@��������̋��Ђ�����A�������菜�����߂̊O����A���q���̐�͂�������������B���������Ή������A�����Ǝ��Ԃ������āA�����̍��ӌ`����}��A�܂�
�@���̊�{�ł��錛�@�������s�������B���̏�ł��܋c�_���Ă��镽�a���S�@�ĂX�ƍ���ɍĒ�o����Ƃ������Ƃł���A���͂Ȃ��B
�@�������A�������������I�c�_������A���a�ɂȂꂽ���{�����͐푈�ɎQ�����邱�Ƃ�������@�Ăɂ͒N���^�����Ȃ����낤�B
�@������A����̂悤�ɖ������A���@�̉��߂�P���Ȃ��Ăł��A���a�H���S�@�ĂƂ�����Ȗ��O�̖@�ĂƂ��āA�ʂ��������̂��낤�B
�@���{����Ƃ��ẮA�����ǂ݊ԈႦ���I�I
�@�����āA�Q�c�@�ł̐R�c���������n�܂��Ă���B
�Q�c�@�ł́A�O�c�@�Ə����j���A���X���Ⴂ�A���@�ᔽ��A�@�Ă̕s��������W�c�I���q���̖��_�ȂǁA�����[���@�艺�������_�ɂȂ��Ă���B
�@����͎Q�c�@�̑��݂��������������B
|
2015�N6��18���i�j
�푈�ƕ��a
�@���a���S�ۏ�@�Ă�����ŕ��c���������Ă���B�W�c�I���q�������@�ᔽ���ǂ����H
�ȂǁA�c�_���������A�b���Ă�������ɂ����B
�@�w�����킩��ɂ����̂��H�x�Ƃ����ƁA���߂̎d�������ɂ��낢�날�邩�炾�B
�@���@�͕�����₷�����{��ŏ�����Ă���B�������ɂȂ�̂́A���@��X���ł���B
���̏́A�ȉ��̂Q�ł���B
- ���{�����́A���`�ƒ�������Ƃ��鍑�ە��a�𐽎��Ɋ��A�����̔��������푈�ƁA���͂ɂ���Њd���͕��͂̍s�g�́A���ە��������������i�Ƃ��ẮA�i�v�ɂ�����������B
- �O���̖ړI��B���邽�߁A���C��R���̑�������́A�����ێ����Ȃ��B������팠�́A�����F�߂Ȃ��B
�ƂȂ��Ă���B��X�̏��w�A���w����ɂ͓��{�����@�͐��E�Ɋ����镽�a���@���Ƌ������Ă����B
�@�Q���ڂ����C��R���̑��̐�͂́A�����ێ����Ȃ��ƋK�肵�Ă��邪���q���͑��݂���B���q���͐�͂ł͂Ȃ��̂��H�@���q�̂��߂̐�͂��Ȃ�����͎��Ȃ��B������s���悭���@�����߂��āA���h�̂��߂ɂ͎��q���������A���q���͐�͂ł͂Ȃ��Ƃ��Ă����B�����Ɋ�{�I�Ȍ��@���߂̂���������������B����ɁA���@�����m����팠�͔F�߂Ȃ��Ə����Ă���B
�@���q���͓��{����������U�߂�ꂽ�ꍇ�ɁA���y�э�������邽�߂ɐ키�g�D�ł���B�����đ����ɏo�����Đ키���߂ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��B
�@���̒N�����[���ł�����߂��A���ς��悤�Ƃ��Ă��邩��A������������������̂��I
�@���@�͈ꌩ�A���m�Ɂw�푈�����Ɛ�͂������Ȃ��x���Ƃ��K�肵�Ă���悤�Ɍ����邪�A�ǂݍ��ݕ��ɂ��A�����悤�ɂ����߂ł���ƌ����������B������A���������āA���{�����͖�̂킩��Ȃ��w���a���S�ۏ�@�āx���o���A�O�c�@��ʂ������Ƃ��Ă���B
�@�������A�b���Ă���ƁA�����Β����قlj�����a����������B����A���@�w�҂��A���̕��a���S�ۏ�@�Ă͌��@�ᔽ���Ǝa�����B
�@�����������̊�@����悤�Ȏ��Ԃɂ́A�W�c�I���q���Ƃ���������ɂ������t�ŕ\�����ꂽ�l�����̂��ƂɁA���q�����o���ł���Ƃ������ƂɂȂ�炵���B
�@����́A���{���������璼�ڐӂ߂�ꂽ�ꍇ�Ȃ�A�����邪�A�����łȂ����������U�߂�ꂽ�ۂɂ��A�������̈���Ƃ��āA���ڐ퓬�n��ȊO�̏ꏊ�Ȃ�o�����Ă䂭�Ƃ��������B
�@���ڐ퓬�n��ł��낤�ƁA����x���ł��낤�ƁA�G���炷��Γ��{���푈���荑�Ƃ����ʒu�Â��ɂȂ�͓̂��R�̂͂��B���������ƒ��ځA�h���p�`����Ă��鍑�͂�������A���̍��ɕ���╨����A�����A��͕⋋�����Ă�����{�����̂܂܌��߂������Ƃ͂Ȃ��B
�@���������̗���Ȃ�N�ł������ł��邱�ƁB��������ڐ퓬�n��ӊO��������S���Ƃ��������́A�푈�Ƃ�����@�ȍs�ׂ��Ɠ��l�ɍl���Ă����ɉ߂��Ȃ��B
�@������A�W�c�I���q���⎩�q���̏o���̊�������������̂Ȃ�A���@��ς��邱�Ƃ���n�߂Ȃ��Ɛ�����������Ȃ��Ȃ�B
�@���@�ł́A���Ȃ��ƌ����Ă����Ȃ���A���C�Ő푈�s�ׂɎQ������Ƃ������Ƃł́A���@�̈Ӌ`��������Ȃ�������ɂ����B���ꂪ��ԋ��낵�����ƂɂȂ���B
�@���{�͗����N�卑������A���@�������鍑�̍s���̌��_�ɂȂ���Ȃ�Ȃ��B���@�w�҂��ጛ���ƌ����Ă�����̂��A�w����͊w��I�ȍl�����ł��傤�I�x�Ɛ�̂Ă���{�����͉���ژ_��ł���̂��|���Ȃ�܂��B�����}�̑S���͂��������l�����ł͂Ȃ��͂��I
�@������A���ɑ�Ȃ��Ƃ�����܂��B
�@����́A���F�g�i���푈����n�܂����푈�́A�S�ăQ�����킾�Ƃ������Ƃł��B
�����푈�A���I�푈�A��ꎟ���E���A����E���i�����m�푈�j���́A���ƍ����݂��ɍ��Ђ������Đ�����푈�ł��B�^��������A�����f���Đ��X���X�Ɛ키�푈�ł����B
������A�^��������̐^�������Ƃ��������̐푈�ł����B�傫�ȋ]���������̂͐푈�̏�ł����A�����ɂ͌����Ƃ������̂�����܂����B
�@���m�͕����𒅗p���A��ʖ��Ԑl�Ƃ͈Ⴄ�����ŁA�g���������Ă��܂����B
�@�����̃Q������̓o���o���̋ǒn��ł���A�Z���ƕ��m�̌��������t�����A�Z�����˔@�A���m�ɕς������A���[�̏�p�Ԃ����������肷�鉽�ł�����̐푈�ł��B
�@
�@���������푈�ɎQ������ƁA�����瑕�������x�����A�ݔ�����������ۑS���ėՂ�ł��A���肪�N���킩��Ȃ��̂ŁA�s�ӑł��ł���邱�ƂɂȂ�܂��B�܂Ƃ��ɐ���Ď��ʂƂ����ł͂Ȃ��̂ł��B
�@
�@�A�����J�Ȃǂ͐V����J���ɋ��z�̍��h��𓊂��Ă��܂������A����͂܂��Ƃ��Ȑ푈��O��ɂ��Ă��܂��B�Q������ł͂����������x�ȐV���킪���ʓI�Ɏg���܂���B
������E�����߂̕���́A���肪���m�ɂȂ��Ă��Ȃ��ƍU���ł��Ȃ��̂ł��B
�@��ʂ̕����i�����j�ƁA�Q�������m�͓���H�@���������ł��Ȃ��̂ł��B
�������A���̒��ɕ��ꍞ��ŁA����ł��镺�m���ˑR�U�����Ă���̂ł��B�s�ӑł��ł��B
����ŁA��������̕ĕ������F�g�i���푈�łȂ��Ȃ�܂����B����͔ߌ��ł��B
���������푈�����ݍs���Ă���푈�ł��B
�@IS(�C�X���~�b�N�X�e�C�g�j�A�C�����A�C���N�A�����A�G�W�v�g�A�V���A�A�E�N���C�i�A�p�L�X�^���ȂǍL�͈͂Ő���s����ł��B�قƂ�ǂ��C�X���������ł��B
�@�����������݂̍��ׂƂ����s�����Ԃ̒��ɁA�W�c�I���q���̂��ƂɁA�݂𐳂������q�����A���肪�ł��Ă���܂őł��Ȃ��Ƃ��A���q�̂��߂̏o�����Ƃ��A�����猾���Ă��A����͉��ł�����̏W�c�ł��B�Q�����Ȃ̂ł��B
�@��x�A���̒��ɑ��ݓ����A���{������̕W�I�ɂȂ�ł��傤�B
�@�W�c�I���q���A���a���S�Ȃnj��t�ł��Y��ł����A���Ԃ̓h���h���̉������E�ł��B
|
2015�N5��22���i���j
�l�Ԃ̓�̔]�Ƃ́H
�@�������́A������ڕW�ɓ��X�����Ă���B�@���Ɂw���������m���ȖڕW�͎����Ă��Ȃ��x�Ƃ����l�������Ǝv�����A���������l�ł��A�w�������~�����x�Ƃ��A�w�������������x�Ƃ��A�w�ǂ������ӂ��ɂ��肽���x�Ƃ��A�u�ǂ������ӂ��ɂȂ肽���x�Ƃ��������R�Ƃ����~�]�͒N�ł������Ă���B
�@�����Ɛg�߂Ȍ�����������A�w�^�o�R���z�������x�A�w�X�����ȑ̌^�ɂ������x�Ƃ��A�w���������܂������x�Ƃ��A�w���鎑�i����肽���x�Ƃ��A�w�S���t�������Ə�肭�Ȃ肽���x�Ƃ��A�w�Ԃ��~�����x�Ƃ��A�w�����������x�Ƃ��A�w�����������̂�����ӂ��H�ׂ����x�Ƃ��A�����ȗ~�]������B
����͂����ē�����O�̂��ƁB
�@
�@�������A����ŁA���̗~�]�ɔ����邱�Ƃ��]�̒��Ŕ������Ă���B�����Ƃ���������́B
�������̔]�͈�����Ȃ����A�������̐S�͓����B
����������Ǝ������̐S�̒��ɂ́A��̎��Ȃ����݂���B
�@
�@����̎��Ȃ́A�l���̏Փ��̂܂܍s�����āA�ڐ�̗~�]�������Ƃ���B��������̎��Ȃ́A���Ȃ̏Փ���}���āA�~�]��扄���A�����I�ȖڕW�ɏ]���čs������B
�@�w���������N�b�L�[���H�ׂ����A�H�ׂ����Ă��܂�Ȃ��x�A�Ƃ����~�]�ƁA�w���������x�Ƃ����~�]�����߂������B�����Ď����̐S�̒��őΗ�����B
�@���̒����I�ȖڕW��B�����邽�߂ɂ́A�Փ��I�ȗ~�]���˂������邵���Ȃ��B
�������A���̏Փ��I�ȗ~�]�̗U�f�ɕ����Ă��܂����Ƃ������B����͓��Ɉ����킯�ł͂Ȃ��B
�u�ł���Ȃ͉̂����I�v�Ƃ������Ƃ��B
�@���������߂Ă䂫�����Ƃ����v���͒N�ł��`�����̂��B
�Ⴆ�A��Ј��Ȃ�A��C�ɂȂ肽���A�ے��ɂȂ肽���A�����ɂȂ肽���Ƃ����z���������ē��R���B
�������A����ł��̎v����j�Q����Փ��I�~�]�������o���B
�@�V�т����A���R�Ȏ��Ԃ��~�����A�y�������A�Ƃ����Ȃ��Ƃ���������B
�@�����ŁA�w���ȁx�Ƃ������t������̂������m���낤���H
�Ȃɏ��Ƃ����Ӗ������A����͌����ɓ�̎����ɑ��āA����ׂ��������Ɍ������Đi�ނɂ́A�����j�Q���鎩���ɏ����Ƃ��Ƃ������Ƃ�\���Ă���B
�@�w�Ȃɏ����Ƃ́A���Ŋ������̓G�ɏ��̂ɏ���x�Ƃ������t���قǁA�Ȃɏ����Ƃ͓���Ƃ������B
�@�����ŁA�w���ȁx�͏Փ��I�~�]���˂������邵���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B�ǂ�����ΌȂɏ��Ă�̂��H
�ʔ������������B
�@����́A�����̏Փ��I�~�]�ɑ��āA���m�ȁA�������Ȃ�����������Ƃ悢�炵���B
���撣���Ă��Ȃ��ƕ����i�܂Ȃ����ɁA�V�т����A��������Ƃ����ア���������ꂽ�Ƃ��́w�Ȃ܂����́x�����ꂽ�ȁI�@�Ƃ��A���َq��H�ׂ����Ɖ䖝�ł��Ȃ��Ƃ��́A�w�N�b�L�[�����X�^�[�x�����ꂽ�ȁI�Ǝ����Ɍ����������āA�����X�^�[�o�X�^�[������I�@�����̎コ���͂��ƋC�Â��A
������J��Ԃ���������ɁA����ɏՓ��I�s���Ɍ����킹��ア�������������Ă����炵���B
�@�u�炵���v�Ƃ������̂́A�������ꂩ����H���Ă݂悤�Ǝv���Ă��邩��E�E�E�B
�@�����d��̑n�ƎҁA�����K�V�������悭����ꂽ�u�f���ȐS�ɂȂ�܂��傤�v�Ƃ������t������B
��������Ԃ��ĉ]���A�f���ȐS�ɂȂ�Ȃ�����A��ɂ�������E�̖��ɂ��Ď����Ɍ������������̂��Ǝv���B
�@�������A�l�Ԃ������Ă����̎����A���̈������菜�����Ƃ͂ł��Ȃ��B
�����A���ꂪ�ł����Ƃ�����A�����N����̂��H
�@�Փ��I�Ȏ����͌��n�I�Ȕ]�ɍ��܂ꂽ�l�Ԃ̓����I�Ȉ�`�q���琶�܂�Ă���炵���B�����炱�̏Փ��I�ȗ~�]�����S�ɂȂ�����Ƒ�ςȂ��ƂɂȂ�B
�@����͈�w�I�ɏؖ�����Ă���B�Ⴆ�A�]�̑����ɂ��A���n�I�Ȗ{�\�������ǂ镔�����Ȃ��Ȃ�ƁA�����ɑ��鋰��A�~�]�A���N�A�K���̊��o�⎩���S���Ȃ��Ȃ�B
�@�����A�ςȘb�����A�~�]�͌���Ȃ��傫���Ȃ�A�Z�b�N�X�ɑ��Ă��A�N�ނȂ��ɋ��߂�悤�ɂȂ�炵���B�e��Z��ɑ��Ă��B
�@���̓�̔]�͐l�Ԃ��������B���̓����͏Փ��I�Ȕ]���������Ȃ��B
�l�ԈȊO�̓����́A�����̎p��F���ł��A�����̊댯�͊�����B������P����Ɠ�������A�U������B�������A�l�ԈȊO�̓����͎����̐S�̒�������A�܂��͒m�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
��X�́A�����������̍s�������Ȃ���A����ł����̂��A���ɂ������@�͂Ȃ����A��Ɏ��⎩�����J��Ԃ��Ȃ���s���ł���B
�@�^�o�R�͌��N�ɗǂ��Ȃ����Ƃ͕������Ă���B�������A�z�������B
�w�^�o�R�����X�^�[�x���v���o���A�։��X�^�[�g�ł��܂����H
|
2015�N5��13���i���j
������a���������܂��H
�@�ߍ��A�V����e���r�����Ċ����邱�Ƃ́H�@�A�x�m�~�N�X�Ƃ������t�����܂蕷�����Ȃ��Ȃ������ƁB
���A���{���g�����܂茾��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���悤�Ɋ�����B
�����āA�w�i�C�͉A���ɂ���x�ƌ����Ă��܂����A�m���ɁA���鐔���ⓝ�v�I�ɂ͗ǂ��Ȃ��Ă���͎̂����ł����A�����̎����Ƃ��ĈȑO�ƕς��Ȃ��B�ނ���A�������Ă���悤�ł�����B
�@�ꕔ�̑��Ƃ������~���̉��b���āA�ō��v���X�V�ȂljX������`����Ă��܂��B
������ƁA�A�x�m�~�N�X�Ɋ��҂����ƁA����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�@
�@�ȑO�̂悤�ɁA�w�i�C�͎R�J���J��Ԃ����x�Ƃ����z�^�̍l�����͒ʂ��Ȃ��悤�ȋC�����܂��B����́A���E������̑傫�Șg�g�݂̒��ɓ����Ă��܂������Ƃ��傫�ȗv���ł��傤�B�����̍������ŁA�o�ϐ������ʂ������Ƃ��Ă��A����̓O���[�o���o�ς̑傫�Ȃ��˂�ɍ��E����Ė|�M����܂��B���{�͓��{�����̌i�C��ł͂����ǂ����悤���Ȃ��Ȃ��Ă���Ǝv���܂��B
�@
�@�A�x�m�~�N�X�́A�َ����Ƃ܂ŕ\�����������Z�ɘa�ɂ��A�v�������~����U�����A�A�o�����������A�A�o��L�����Ƃ���_�����傫���Ǝv���܂����A�v�����悤�ɗA�o���L�т܂���B
�@����͍H�ꂪ�C�O�Ɉړ]���Ă��܂��Ă��邩��A���݂�1�h��120�~�O��̉~���ɂȂ��Ă��A�����̐����Ƃ��ȑO�̂悤�ɍ����Ő��Y������̂��Ȃ��A����䂦�ٗp���傫�����P���Ȃ��āA�o�ϊ�����������悷�邱�Ƃ��Ȃ�����ł��B
�@���̓T�^�Ⴊ�����ԎY�Ƃł��B�̂́A�������Y���啔���ŁA�����Ő��������Ԃ�A�o���܂����̂ŁA�~���ɂȂ�ƁA�A�o���傫���L�т܂����B����ɂ��A��������Ђ����b���邱�Ƃ��ł��܂����B�������A���݂͂��̉~���ł��A�����̐��Y�ʂ͍����̔̔��ʂɌ������������������Ȃ��H��̑̐��ł�����A�~���̃`�����X���������Ă��A�����̐����Ƃ��v�����قNJ��C�Â����Ƃ��]�߂܂���B
�@�~���ɂȂ�ƁA�C�O���Y�������i�̌��n���i�͓����ł��A�h�����~�ɑւ��Ď������ގ��́A�ב֍��v�œ��{�Ɏ����A��~�������܂��B
�@�Ⴆ�A�P���h���̎Ԃ��A�����J�Ő��Y�̔������Ƃ��܂��B���̎Ԃ̗��v��1���ŁA1��h���������Ƃ��܂��B������~���Z�ŁA1�h����80�~��120�~�Ƃł́A�@���v������1���̔��������ɁA8���~�ɂȂ邩�A12���~�ɂȂ邩�ł��B���n���i�͓����ł��A�~�Ɋ�����ۂɁA�~���ł͂�������̉~�������A�邱�Ƃ��ł��܂��B���ꂾ���ׂ���������Ƃ������Ƃł��B
�@�g���^��z���_����Y�����Ԃ́A�Ԃ̎��v�n�̋߂��ɊC�O���Y�𑝂₵�ė��܂����B�~���Ńh�����Ă̔̔������Ă��邽�߁A��L�̂悤�Ɉב֍��v���͗��v�Ƃ��đ傫���ςݏオ��܂��B
�@�g���^�����Ԃ͉��Ɖc�Ɨ��v���ߋ��ō���2��7000���~������܂����B���̓��A1��4000���~�����v�����Ƃ������Ƃł��B�ł�������v�̎��͂́A���̍��z���A���Ȃ킿1��3000���~�ƂȂ�܂��B
1�~�̉~���ŁA400���~�ׂ��銨��ɂȂ邻���ł��B
����́A�O���[�o����Ƃ̘b�ł��B
�@������50���ЂƂ��A60���ЂƂ������鍑���̒�����Ƃɂ͓��ɉ��b������܂���B�ނ���A�~���Ō��ޗ��̎d���ꉿ�i���l�オ�肵�A�x������������X���ɂȂ�܂��B
�@���������ӂ��Ɍ��Ă���ƁA�A�x�m�~�N�X�̌��ʂ͓������҂����悤�ȊÂ����̂ł͂Ȃ��悤�ł��B���҂����A�x�m�~�N�X�Ƃ�������̌��ʂ��������������Ȃ��Ă���悤�ȋC�����܂��B�����������Ƃ��v�����ǂ���������܂��A�ŋ߁A���܂�w�A�x�m�~�N�X�x�Ƒ������Ă邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ����悤�ł��B
�@���A���ڂ���Ă��邱�Ƃ́A���@�����ƁA����ɐ旧���ۑ̐��̖��ł��B
���Ĉ��ۑ̐��ɂ��āA���{���I�o�}�哝�̂Ɖ�k���A�X�ɃA�����J��@�A���@�c��ɂ����ē��{�l�ŏ��߂ĉ����������Ƃ����܂����B���{����͂��������s���͍��܂łɂȂ��������Ǝv���܂����A�ǂ������{�̎��q���̊����͈͂��g�債�A�ϋɓI�h�q�Ƃ��A�Ӗ����킩��Ȃ��A�܂��͂ǂ����f���ėǂ��̂��������������\���ŁA�h���h�����E�ɐϋɓI�ɏo�����čs�������Ƃ����v�f�������܂��B���܂ł͎��q�����C�O�ɏo������ۂɂ́A�����Ȕ��肪�����āA�\���Ȋ������ł��Ȃ������Ƃ������Ȃ̂��ƂɁA���������C�O�ł̕����n��ł��A����x�����ł���Ƃ�������@�������āA�]���̖@�����������A�����Ƒ������݂̌R���������ł��鍑�ɂ������悤�ł��B
����́A���q���Ƃ������e�����R���ł��B
���q���Ƃ������t�ɂ́A���Ƃ����Ӗ������������͂��ł��B�W�c���S�ۏ�Ƃ����h�q�Ƃ��悭�Ӗ����킩��Ȃ����t���g���āA����ɈӖ��Â����āA�h���h�����q���̍ی��Ȃ��C�O�h�����ł���悤�ɂȂ�Ƃ����킯�ł��B
�����}�Ƃ̘A�����t�ŗ^�}���c���A���ӂ��ꂽ�Ƃ����j���[�X�����܂����B
���E�͏�ɕω����A�����Ă��܂��̂ŁA���{������ɑΉ����Ă䂩�Ȃ���Ȃ�܂���B�������A������Ă��邱�Ƃ͗]��ɂ��ߑ����Ȃ��A�}�������ł͂Ȃ��ł��傤���H
�����ɂ́A�}���ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂƁA�\�����Ԃ������č����̍��ӂ��`�����Ă�����g�ނ��Ƃ�����܂��B����E���⑾���m�푈�̋��P�Ƃ͈�̉��������̂ł��傤�B
�l�́w�A���߂���A�M����Y���x�ƌ�����������܂����A���70�N�Ƃ����N�����߂��A�푈�̌����オ����ɖS���Ȃ鎞�����}���A�푈�̔ߎS����Y�ꂩ���Ă���悤�ȋC�����܂��B
�푈���悻���̂悤�ɁA�y�X���������Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B
�������A�������U�߂Ă���ƂȂ�ƁA���̉̕��͖h���Ȃ���Ȃ�܂���B���������~�j�}��������ݒ肵�Ď��g�ނ��Ƃ���ł��傤�B
�������A���͂��̃��C�������ɑ傫�������Ă��܂��Ă���悤�Ɏv���܂��B
�@���{�̌��@�́A��9���́w�푈�̕����x��搂��Ă��܂����A���̂悤�Ȑ����Ȍ��@���f�������͐��E�ɂ���܂���B���̌��@�𖢗��i���A�ւ��葱����̂��A����̓����̂悤�Ɍ��@���������A�L���ɂ͐푈���ł��鍑�ɕς��Ă䂭�̂��H�@���A���ˍۂɔ����Ă����悤�ȋC�����܂��B
�@�ǂ������ꍇ�ɁA���q�����o���̂��A���̘_�c�����낢��Ƃ����悤�ł����A���̓��e�����ɕ�����ɂ����Ȃ��Ă��܂��B�N�����������f�ł���̂��ł��B���G����Ȗ@���������āA�ǂ���ɂ����߂ł���悤�ȓ��e�Ɏd�グ�āA���{�̓s���ɂ���Ăǂ���ɂ����f�ł���Ƃ������̂��Ǝv���܂��B����͑�ϊ댯�Ȃ��Ƃł��B
����̒����V���@�[�����f���q�ɏ�����Ă��镶���Љ�܂��B
�@��ڂ��~�����@�Ƒ肵��
�@���a�Ɛ푈�Ƃ́A
�@���q���ƕČR�Ƃ́A
�@��������u���ԁv�́A
�@���@9���̓��ƊO�Ƃ́A
�@�퓬�n��ƌ���x���Ƃ́A
�@���a�ƐϋɓI���a��`�Ƃ́A
�@10�{�ꊇ�̈��ۖ@�������ẮA
�@���V�ԕԊ҂ƐV��n���݂Ƃ́A
�@�A�x�m�~�N�X�ƕx�������Ƃ́A
�@���{�̑����ƒ����̑|�C�Ƃ́A
�@�č��Ǝv�f�Ɠ��{�̒Ǐ]�Ƃ́A
�@�̊�]�ƍ����̊�]�Ƃ́A
�@��x�݂��A�������邽�߂́A
�@���A���{�����́A���q���̋����ƊC�O�h�������₷�����邱�ƂɔM���グ�Ă���B����ŕ����������̂́A���S�ɃA���_�[�R�����g�[���ɂ���ƌ��������B�����āA�����̍ĉғ��ɑ�ϔM�S�Ɏ��g��ł����B����͓d�͂̈��苟���Ƃ�����`�����̂��Ƃɐi�߂��Ă���B����ŁA�����������̂̌�A�Đ��G�l���M�[�ւ̓]���Ƃ����傫�Ȗ���͎���ɂ��ڂ݂���B����͕��͂⑾�z�����d�͕s���肾����Ƃ������R�ɂ��B�m���ɕ��͕͂����~�߂Δ��d���Ȃ��B���z�����d�͓܂�J��A��͑S�����d���Ȃ��B�����畗�͂⑾�z�����d�̓_�����Ƃ����l�����͋Z�p�̐i����j�Q����B�����ł͂Ȃ��āA���z���́A���͔��d�̕s���肳���ǂ����č������邩�H���̖���ɑ�������o�����ƂɁA�Ȋw�̑傫�Ȑi�������܂��B���̉��͋���ȗe�ʂ̓d�r�����m��Ȃ��B
�@�h�C�c�͕����������̂����āA�����Ɍ����[���ɓ��ݐ����B
�������̓��{�͂��Ƃ����낤�ɂ܂��܂������ĉғ��ɓ˂��i��ł���B
���{�̌��������U����Ă���B�w���{�͐��E�ň�Ԍ��������S������A����ɑ��茵�����R�����č��i���������ɂ��Ă͉ғ�������x�ƌ����Ă���B
�@���q���̊C�O�h����A�ϋɓI���S�ۏ��A�ϋɓI���a��`�A�Ȃlj����Ȃ�������Ȃ����t������ĕ��ׂāA���q�����R�������āA���E�̕��a�ɍv�����悤�Ƃ���B
����ɂ͑�ϔM�S�Ȑ��{�����A�����ĉғ��ɂ��ẮA�w�҂⌴�q�͈ψ���ɔC���āA��������{�����Ɠ���������悤�ȃ����o�[�ł���Ă���B
�����̈��S���́A�������K����ňȑO���̓n�[�h�I�ɁA�����I�ɂ͈��S���͏オ�������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�������A�V�X�e���s�ǂ�A�@��̕s�ǂ�i�C�̕s�Ǔ��n�[�h�̕s�ǂ������Ő[���Ȏ��ԁi�V�r�A�A�N�V�f���g�j�Ɋׂ����ꍇ�ɂǂ��Ή����邩���`���Ă��Ȃ��B
��������ԐS�z����̂́A�������e���ɑ_��ꂽ�ꍇ�ǂ����邩�ł���B����A���E�̌����̓e���̐�D�̑Ώە��ɂȂ�ƒf������B
���R�E�̒n�k��ΎR�͖҈Ђ�U�邤�B����͂���ő�ςȋ��ق��B
�������A���R�E�͐l�m�ł�����x�̗\�����ł���B�\������A�w�z��O�̂��Ɓx�Ƃ���������ɂȂ�B�������A�l�דI�ȃe���s�ׂ́A�\�������Ȃ��B
���{�C���ɂ͌����̌Q�ꂪ����ł���B������_���āA�����͂���~�T�C���˂���āA�����̐S������䎺�����U������A�j��Ă������̓V�r�A�A�N�V�f���g�Ɋׂ邱�ƂȂ����S�ɒ�~�ł��邾�낤���H
����̖h�͂���������������A���������o�����肵�Ȃ���Α��v���B
�����ƂȂ肪�Ύ��ɂȂ��Ă��h�Εǂ��������肵�Ă��邩��A�ޏĂ͂Ȃ��B
���ꂾ�����������A���v���ƌ����Ă���悤�Ȃ��́B
�ׂɁA�����������Ȑl���Z��ł��āA������ꂽ��ǂ����H
�K�\�����ⓔ����������āA�������Ă��A��Α��v���H
�Ƃ͔R���Ă��A���Ē����ςނ��A�����͕����Ōo���������Ă���悤�ɁA���\�N�����܂�Ȃ��B
�������Ȃ��̂ł���B
�@���A���{�e�n�̉ΎR���������������Ă���B���h�A�����A��ԎR�A�����A�����ȂǑS���̉ΎR�₻��ɘA�Ȃ�Ƃ���Œn�k�ϓ���ΎR���n�k���p�����Ă���B
�@
�@�܂��A���E�Ń}�O�j�`���[�h�X�ȏ�̋���n�k���N�����n���5�N�ȓ��ɉΎR�������Ă���B
�����{��k�Ђ̓}�O�j�`���[�h���X�D�Q�Ƃ����l�ł���A���E�̋���n�k�Ƃ��̌�̉ΎR���̃f�[�^���炷��A���{�̂ǂ����̉ΎR���啬���Ă��S�����������͂Ȃ���Ԃɂ���B
�@�����������{�ŁA�܂��A����Ȃ��Ō������ĉғ������悤�Ƃ����_�o�������ł��Ȃ��B
�l�Ԃ̔\�͂�m�b�͎��R�E�̗͂̑O�ł͔���Ȃ��́B���̕|�����������������Ǝv���B
�@�l�Ԃ͂P�V�A�P�W���I�ȍ~�A�}���ȉȊw�̔��W���s���Ă����B
���q�̐��E�A���q�̐��E�A�X�Ɍ��q�j�A�d�q�ȂǗʎq�͊w��d���C�w�Ƃ����r�����Ȃ�������Ԃ�����q�ōl���A�����Ŋm���߁A���_���\�z���A��������ɐl�Ԃ̐�������ɐs�����Ă����B
�@�������A���q�̐��E�A���Ɋj�̕���Ƃ������ۂɍs�����������A���̓r�����Ȃ�����ȃG�l���M�[�������B���ꂪ�]��ɂ����傷�������߁A�܂��l�����͕̂���Ɏg�p���邱�Ƃ������B����͈�C�ɃG�l���M�[����o�������قǁA�E���͂������A�D�͂ȕ���ƂȂ�B���ꂪ���q���e�ł���B������X�ɐi�߂��̂��A�������N���܂Ɏg���������������B��������ς���Ȃ�A���q�j����ɂ�錴���ƁA���q�j�Z���ɂ�鐅�����B
�@�����āA���q�͂̕��a���p�Ƃ��āA���܂ꂽ�̂��~����ƌ���ꂽ���q�͔��d�ł������B�������A���q�j����Ƃ������Ƃ́A���R�E�ɂȂ��V�������낵�����ː������ݏo���B�����Ă���̔p����������ۊǂ��S���i�܂Ȃ���ԂŁA�l�Ԃ͗ǂ��Ƃ���肾�����Ă���̂ł���B
�@�n�k���A���{�̂ǂ��ɂ��A���S�N�A����N�Ƃ����N���ۏł��Ȃ��ۊǏꏊ�ƁA�ۊǑq�ɂ铯�ӂ͓����Ȃ��B�v�̓g�C���̂Ȃ��}���V�����ɏZ�܂��Ă���̂ł���B���̂��Ƃɂ͑S���G�ꂸ�ɁA���킸�ɁA�����̃R�X�g�͈�Ԉ����i��P�O�~�j�Ƃ���������������B���̃R�X�g�ɔp�����ۊǔ�p��������Ί��ɂȂ�̂��낤���H�@�����Ă��̕ۊǏꏊ�͍����S�����܂�Ȃ���Ԃ��B
����͐��E�������l�ȏɂ���B
���@�����A���q���̊����̖@���̕ύX�ȂǁA��ϐϋɓI�ɐi�߂悤�Ƃ��Ă������ŁA�����̍ĉғ��ɑ��ẮA�Ƃ����ς́w���E�ꌵ�������S��ɑ����ĐR������̂ő��v�x�Ƃ������Ɋ�Ȃ���ԂŐi�߂Ă���B
�����������ƂɁA��a���������܂��H
|
2015�N�S���Q�T���i�y�j
���R��Ƀh���C�u���܂���
�@����A�v���Ԃ�ɁA���ԃt�B�b�g�n�C�u���b�h�ŁA�����R�T�O�����قǑ����ė��܂����B
���[�g�́A���H�͑��A�����o�C�p�X�A���_�������珬�qIC�܂ō������H�𑖂�A���������ʓ��H�𑖂�A���s���Ԃ͂Q���ԂR�O�����炢�B
�@���R��̓V��t�̊ό����ς܂��āA�鉺�����U�A���H���Ƃ�A�߂��̗L�y�����̍���A�@���Ȃlj������U�܂����B���{�̊ό��n�̓��ꗿ�͍����̂ŁA�������邩�ǂ����A��������S�O���܂����A����͍������������Ċό����܂����B
�@�A�H�̓R�[�X��ς��āA���É���O�H�A�����㎩���ԓ��Ŏl���s�A�鎭��ʂ�A�����Q�T�����A�i���㎩���ԓ��j�ŋA���Ă��܂����B
�����̔R��́A���[�^�\���l�ŁA�Q�W����/L�ɂȂ�܂����B
�@�������H�͂W�O��������P�O�O����/���ő���܂����B���ɏa�͂Ȃ����K�ɑ���܂����B
�@���^���ɂ����R����o�����Ǝv�������A�X�^���h�ɗ�����炸�ɋA��܂����B
�@����͍��܂ōō��̔R��o�܂����B
����́A�C�����オ���Ă������ƂƁA���̎Ԃ��S���s�������U�O�O�OK�����ɂȂ�A�G���W����J�̂Ȃ��݂��ǂ��Ȃ�A���C������A�R��ǂ��Ȃ������̂Ǝv���B
����ɂ��Ă��ŋ߂̎Ԃ̔R��̗ǂ��ɂ͊��S����B
�@���̐V�^�t�B�b�g�n�C�u���b�h�́A�w�����Ă���T�R�[��������A���Ԃő啪�@����A�z���_�͒ɂ��ڂɂ������B�����͑S�����R�[���͋C�ɂ��Ă��Ȃ��B
�����A�������ڂ��Ă��āA�����̎ԂƏ����U�镑�����Ⴄ�ȂƂ�����a�����Q�A�R�_����A������f�B�[���ɘb�����܂����B���̓��e���A���R�[���̑Ώۂ̂ЂƂɂȂ��āA���P����ėǂ��Ȃ����̂ŁA�z���_�ɂ͍v���ł����Ǝv���Ă���B���̐V�^�t�B�b�g�n�C�u���b�h�͑�ϗǂ��Ǝv���B
������u���[�L���O��n���h�����O��Â������͑f���炵���ǂ��o���Ă���B�Ƃɂ�������Ĕ��Ȃ��̂������B
�@�����i23���j�A�z���_�W�F�b�g���H�c��`�ɔ����B�V�l���̏��^�W�F�b�g�ŁA�l�i�͂T���S�疜�~���������B�����������^�@�̓A�����J��[���b�p�̃g�b�v�r�W�l�X�}�����������Ɨp�Ƃ��Ďg�p���A�e�n���щ���Ă���B
�@
�@�ڂ������̂́A�嗃�̏�ɃW�F�b�g�G���W����ςނƂ�����z�V�O�̔��z���t�����A�������L���A������s���ł��A�R��ǂ��Ƃ����v��ʈ�ΎO���̌��ʂ������o���Ă���B
�S�����܂łɂȂ��`�ŁA�������z���_���������s�@�͈Ⴄ�Ƃ�����ۂ����B
�`�͉��̎ʐ^�̂Ƃ���B���{�ɏ���s���Ă����@�̂͐Ԃɓh������Ă����B
 �@�@ �@�@
�@�b�͎����Ԃɖ߂邪�A�ŋ߁A�����ԃ��[�J�̊J�������͌���ɂȂ��Ă���B
�܂��A�g���^�͐��E�����R���d�r���u�~���C�v�������B
 ����͐��f��R���Ƃ���̂ŁA�����Ă��S���r�C�K�X�͏o�Ȃ��B�g���^�̓[���G�~�b�V������搂��Ă���B�R���̐��f����C���̎_�f�ƌ������Đ����ł���B���̍ۂɓd�C����������d�g�݁B�������A�u���f�K�X���ǂ����đ���̂��H�v�ł���B ����͐��f��R���Ƃ���̂ŁA�����Ă��S���r�C�K�X�͏o�Ȃ��B�g���^�̓[���G�~�b�V������搂��Ă���B�R���̐��f����C���̎_�f�ƌ������Đ����ł���B���̍ۂɓd�C����������d�g�݁B�������A�u���f�K�X���ǂ����đ���̂��H�v�ł���B
�@���́A�V�R�K�X��LNG�����Đ��f����邪�A���̍ۂɔr�C���Ƃ��ĒY�_�K�X���o��̂ŁA�g���^��搂��Ă���[���G�~�b�V�����Ƃ͌����Ȃ��B����͎��͂܂₩�����I�B
�@
�@����ɁA����ł͐��f�K�X�X�^���h���w�ǂȂ��̂ŁA�X�^���h���ł��Ȃ��ƃK�X�̏[�U���ł��Ȃ��B���Ȃ킿�Ԃ����Ȃ��B���̂Ƃ���A���f�X�^���h�̐����A�g���҂��Ƃ������B
�@���f�K�X�X�^���h�͐ݔ������ɐ����~���K�v�ƂȂ�炵���A�e���ɂł���ɂ͑������Ԃ������邾�낤�B�����Ȃ�Ƃ����������E�ɐ�삯�ĊJ�������i�������u�~���C�v������Ȃ��̂ŁA�g���^�͐�ʁA�R���d�r�Ɋւ�����������J���A�e���[�J�����R�Ɏg����悤�ɂ����B������������̃��[�J�����X�ƔR���d�r�Ԃ����āA���f�K�X�X�^���h�����y���邱�Ƃ�_�����[�u���B
�@���̓_�A�n�C�u���b�h�Ԃ̓v���E�X���㖼���ɂȂ�قǎs���Ȋ������B�����ďo�����A�N�A���o�J���ꂵ�Ă���B
�@
�@�z���_�͌y�̃X�|�[�cS�U�U�O�̔����ŁA�b�肪�������Ă���B����̊J���ӔC�҂��Q�U�̎ᑢ�Ƃ������ƂŁA��w�ڂ������Ă���B
�@�z���_���V�^�t�B�b�g�n�C�u���b�h�̃��R�[�����Ђƒi�����Ĉȍ~�A��p�����ɐV�Ԃ̓������s���A���F�[���A�O���[�X�A�W�F�C�h�A�E�E�E�Ƒ����B
�@�����Ă��ŋߔ����������͂̃n�C�G���h�ԁA���W�F���h�͂R���[�^�n�C�u���b�h�̐V�V�X�e����ς�ł���B�A�R�[�h�͂Q���[�^�����ŁA���̑��̎Ԃ͂P���[�^�n�C�u���b�h�V�X�e���ŁA�Ԃ̃N���X�ɉ����ĂR�̈قȂ�n�C�u���b�h�V�X�e�����J�����ē��ڂ��Ă���B
�@����ɑ��A������������Ō��C�Ȃ̂��}�c�_���B�}�c�_�̓n�C�u���b�h�̓g���^���甃������Ă���������Ă���B
�@�}�c�_�̖{���́A�X�J�C�A�N�e�B�u�Ƃ������������V�G���W���ƃg�����X�~�b�V�����V�X�e���A��R��E�������G���W���̊J���ɗ]�O���Ȃ��B�}�c�_�ɂ��ƁA�G���W�����̂̍��������͂܂��܂��ł���Ƃ����B����łS�O�����z���Ƃ���܂ŗ��Ă���B����̓K�\�����������Ă���u�M�G�l���M�[�̉������@�B�o�͂ɕς�邩�v�Ƃ��������̖�肾�B�P�O�O���ɋ߂��قǁA�����������B
�@�}�c�_�͊�z�V�O�̔��z�Ŏ��g�݁A�K�\�����G���W���͍����k��ō���������}��A�W�[�[���G���W���͋t�ɐ��E��ሳ�k��i���܂ł̃W�[�[���G���W����1/20�`1/25���炢�̈��k����}�c�_��1/14�ƒሳ�k��Ŏ����j�ŁA�W�[�[���G���W���̌��_�Ƃ���Ă��������A�U���A�r�C�K�X�̖������������B�W�[�[���G���W���͌��X�A�������Ńg���N���傫���A�D�ꂽ������L���Ă���B���_�����������Αf���炵���G���W���ɂȂ�B�}�c�_�͑傫�����z�ɋ߂Â����B
�@���Y�����[�t��EV��̔����Ă��邪�A���[�d�ő���鋗�����܂��Q�O�OK�����炢�ŒZ���A����̂悤�ȃh���C�u�ɏo������ƁA�ǂ����̃T�[�r�X�G���A���A���ԏ�ŏ[�d���Ȃ��瑖��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�܂��܂����p�I�Ƃ͌����Ȃ��B���߂ĂT�O�O��������邱�ƂƁA�[�d���Ԃ�15�����x�Ŗ��[�d�ł���悤�ɂȂ�AEV�͖{���ɋ߂Â���������Ȃ��B
���������Ԃ̋Z�p�̐i���̃g�����h�����Ă���Ɩʔ����B
�@�����͋v���Ԃ�ɁA���Ԃ̐V�^�t�B�b�g�n�C�u���b�h�ŏo�����ėV��ł��܂����B |
2015�N3��6���i���j
�����͂Ȃ��댯�Ȃ̂��H
���S�Ȍ����͂Ȃ��̂��H
�@�����{��k�Ђɂ���Ôg�ŁA������ꌴ������p�s�\�Ɋׂ�A�唚�����̂��N�������B �K���A�E�����R���̓����g�_�E���������̘̂F�S���̂��̂̔����͂Ȃ�Ƃ�������ꂽ�B
�@�����A�F�S�������A�܂��͗�p�����������x��Ă�����A���͊u�ǂƌ����镪�����R���N���[�g�e����E�����R����2000�x�߂��ɂȂ�R���N���[�g��n�����ĊO���ɗ��o���Ă����Ƃ��낾�����B�����Ȃ��A���̃R���N���[�g�u�ǂƃE�����R���̗l�q���ǂ��Ȃ��Ă���̂����������Ă��Ȃ��B
�@���E�̌��q�͔��d�����̂ŗL���Ȃ��̂́A�A�����J�A�X���[�}�C�����̌������́A�\�A����̃`�F���m�u�C�������̔������̂��B�X���[�}�C�������R���_�������g�_�E���������A�F�S�̒��ŗ��܂����B
�@
�@�`�F���m�u�C���͌��q�F���̂��̂����������̂ŁA��������L��ȓy�n�ɕ��ː���������U���Ă��܂����B�����A���ꂪ���{�ŋN���Ă�����A���y���������{�ł͑�ςȂ��Ƃ������B
�`�F���m�u�C�������͓��{�̌����Ǝd�g�݂��Ⴂ�A���ŗ�₷�^�C�v�ł͂Ȃ��B
�@���{�̌����͑S�Đ��⎮�ŁA�������^�Ɖ������^�̂Q��ނ�����B
���͕��ː��i�����q���j���Ղ铭��������̂ŁA�w��Έ��S���x�ƌ����Ă����B�������A����͐���ɗ�₹���Ԃ̂Ƃ��̘b�ł���B
�@�����A�`�F���m�u�C���Ɠ��l�ɘF�S�������N���Ă�����A���k�n���S��͂������A�A�������܂ߊ֓��n���܂ŕ��˔\�������i�݁A����ƑS��������ɂȂ��Ă����B���˔\�����͌��Ⴂ�ɑ傫���Ȃ�A���{�̔������Z�߂Ȃ��Ȃ��Ă�����������Ȃ��B����d�ŁA�K�^�Ƃ��������悤���Ȃ����A���̋���ōL��Ȕ�Q���瓦���ꂽ�B
�@
�@�w�A��������ΔM����Y���x�Ƃ��w�l�̉\��75���x�Ƃ�������������B
�������A�������̂́A�ʏ�̎��̂ƈႢ�A���܂ł̐l�̊��o��y���ɒ����鉽����ɂ��n���Q�������炷�B
�@���̓_���������̂̋��낵���Ɩ��ł���B
�@���āA��X�͓d�C������邱�ƂŁA�����I�ʼn��K�Ȑ����𑗂邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B
�d�C���Ȃ��Ȃ�ƁA�������ł��Ȃ��قǐg�߂ɕ֗��Ɏg���Ă���B
�@�����ŁA�����͓d�C�G�l���M�[�̃x�[�X���[�h�d���Ƃ����ʒu�Â��ŁA���ς�炸�ĉғ��Ɍ����ē˂��i��ł���B���{���n�k���łȂ��������Y�_�K�X��r�o���Ȃ��N���[���G�l���M�[�Ƃ��Ĉʒu�Â��邱�Ƃ��d���Ȃ��Ǝv���B�������A�g�C���̂Ȃ��}���V�����ɏZ�ݑ�����Ə�����������ꂽ�ɕς��͂Ȃ��B
�@���͓��{�����E���ň�ԑ�������n�k���ł���Ƃ����������B���E�n�}�ɒn�k�̉⋐��n�k��Ԃ��F�Ń}�[�L���O����A���{�͐^���Ԃ����̏�Ԃ��B
���E���ɂ͉ߋ��ɒn�k���Ȃ��Ƃ����n�悪��������B
�@���E��̒n�k���ł���Ȃ��炪������ғ�������B���̍ۂɐ��E�ꌵ�������S��ŊǗ����邩����v���Ƃ����_�����B
�@���E��̌��������S��Ȃ�A���E��̒n�k���ň��S���Ƃ����^�₾�B
�@������A�w���q�́x�ɂ͑S���Ⴄ��̕���������B
��́A���݁A���p���Ă���E�����R�����g�����@�B����̓E�������q�̌��q�j������N�������āA���̍ۂɐ�����w���ʌ����x�Ƃ������ۂɂ�鋐��Ȕ��M�����o���ď��C�������^�[�r�������d������@�ł���B
�@�E�����R���̓E���j�E���Ƃ������f�ł��邪�A�E�����ɂ͂Q�R�T�ƂQ�R�W�Ƃ���2��ނ�����B��Ϗd�����f�ł���B��������ς���ƁA��ό��q�j���傫���ƌ�����B
�@�S���̌��q�̒��ŁA��ԏ����Ȍ��f�͐��f�ł���A���Ƀw���E���A���`���E���A�x�����E���E�E�E�E�E�Ǝ���ɏd�����f�ɂȂ�B�y�������Ȍ��f�͈��肵�Ă��邪�A�傫�Ȍ��f�ł���E�������q�͒����q�i�A���t�@���j�����q�j�ɓ�����ƌ��q�j�����A��̑S���ʂ̌��q�ɕʂ��B���̎��Ɍ��̈�̃E�������q�̏d�����A��̌��q�ɕ����ꂽ�ۂɁA�ɂ��킸���y���Ȃ�B���̂��Ƃ��w���ʌ����x�ƌĂԁB���̂����킸���y���Ȃ镪������ȃG�l���M�[������B
�@�@�@�@�@�@�����G�l���M�[�i���M�ʁj���i���ʌ������̏d���j�~�i�����̂Q���j
���������ڂ��������܂��ƁA
�@�@�@�@�@�@���M�ʁi�L���W���[���j�����ʌ����mkg]�~�i�R�~�P�O�̂W���j�̂Q��
�@�����ŁA�d�v�Ȃ̂́A�����̂Q��Ƃ����ƂĂ��Ȃ��傫�Ȑ������I
�@�����́A�R�~�P�O�̂W��m��/�b]�Ƃ�������Ȑ����ł��邱�Ƃ��B
���̂Q�悾����A�X�~�P�O�̂P�U���ƂȂ�B�C�������Ȃ�悤�ȋ���Ȑ����ł���B
�@���̋���Ȕ��M�𗘗p�����̂����݂̌������B
������A�E�����R������x�F�S�ɑ}������A�P�N�Ԃ��̂܂܂łP�O�O���L�����b�g�Ƃ����悤�ȋ���ȓd�C�d���邱�Ƃ��ł���B
�@
�@�����ŏd�v�Ȃ��Ƃ́A�E�����̓E�����z�R����@��o�����A�E�����z�̓E�����ܗL�ʂ��Ⴍ�A�d�ʂ̂O.�����ł���B��������Z�k����2-�R���̒�Z�k�E������A�R���_�Ƃ���B
�@�@�@�@�@���q���e�̓E������80���ȏ�̍��Z�k�E�����ɐ������A����ň��k���邱�Ƃň�u�Ɍ��q�j������s���B
�@�E�����͓V�R�E�����ł��͂��ɕ��ː����o���A���R�E�Ō��q�j�����Ă���B
����͂����킸���Ȃ̂Ŕ����I�Ȕ��M�ɂȂ�Ȃ��B���̂悤�ɃE�����͂��Ƃ��Ɗj���Ă��錴�q���Ƃ������Ƃ��I�B������C�}�W�i���[�E�I���i�������Ȃ���Ԃł����M��������Ƃ����Ӗ��j�Ƃ����B����������ƁA�E�����͏�ɗ�₵�����Ȃ��ƁA���M�������镨�����Ƃ������Ƃ��B������A��₷���Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�����ɂȂ�A�����͊댯�Ȃ̂ł��B
�@����ɑ��āA���q�͂𗘗p��������ЂƂ̕��@������܂��B���q�j�����Ɛ^�t�����q�j�Z���Ƃ����Z�p�ł��B����͂܂��Z�p�J���r��ł���A���p���̖ڏ��͗����Ă��܂���B���q�j�����݂̌����Ɏg���Ă���̂ɑ��āA���q�j�Z���͏����Ȍ��q�����q�j�Z�������邱�ƂŔ�������M�����o���B
�@�@���f���q�i�ʏ�̐��f�ł͂Ȃ��A��d���f�A�O�d���f�ƌĂ�铯�ʑ́j���j�Z�������āA�w���E�������̂ł����A���̌��q�j�Z���������N�����ɂ͊O����c��ȃG�l���M�[��^���Ȃ���Ȃ�܂���B�������A���̉ߒ��ŁA���ꎖ�̂��N���Ă��A�O�����������G�l���M�[���~�߂�ƁA�j�Z�������͎~�܂�܂��B
�@���X�͐��f���q�ł�����A�R��o�Ă��傫�Ȕ�Q�ɂȂ�܂���B�ł�����A���q�j�Z���̓C�}�W�i���[�E�I�t�ƌ����܂��B
���̊j�Z���͔��ɍ�����Ԃ�ۂ��Ă��Ȃ��Ɣ������i�݂܂���B����Ɣ��������������邱�Ƃ������������ɓ���̂ŁA���݂ł͂܂������i�K�ł��B�������A�l�m�͕s�\���\�ɂ��Ă��܂����̂ŁA�߂������A�j�Z�����q�F�����������Ǝv���܂��B
�@�����A�j�Z���Z�p�����p������A�댯�Ȍ������ғ�������K�v���Ȃ��Ȃ�܂��B
�j�Z���͐��f���g���̂ŁA�n����ɖ����ɑ��݂��܂��B
���̊j�Z���ɐ�������A���S�Ȑl�ނ͖����̃G�l���M�[�邱�Ƃ��o����̂ł��B
�@�b����������Ȃ����̂ŁA�����͂��̕ӂŏI���܂��B
�@���E��̒n�k���E�ΎR���̓��{���A���E�ꌵ�������S��E�ۈ�������A���̌�������Ō������Ǘ����邩��A�ĉғ����Ă����v���I�Ƃ����_���͐��藧�Ǝv���܂����H
�@�ǂ����āA�ۏ��ł���̂ł��傤�H
�@�n����A�ǂ��ł��������ł���A���{�����E�ꌵ�������S������A����ɑ���Ǘ����邩����v�ƌ����邩���m��܂���B
�@�������A���{�͐��E��A�n�k��ΎR���������Ȃ̂ł��B�n�k�U�m��Ȃ��l�͐��E�ɂ������܂��B�����������Ɠ��{�͊����S���Ⴂ�܂��B
�@�u����̘O�t�v�Ƃ������t������܂����A�܂��ɓ��{�Ɍ�������邱�Ƃ́A����̘O�t�����ɓ������b�ł��B����͓�����Ȃ����{�̏h���ł��B���̏�ɑ��錴���������Ɋ��Ȃ��̂ɂ��Ă��A��Ղ������ƘO�t���ۂĂȂ��ł��傤�B
�@���̎��A�O�t�Ȃ����Ă��A���Ē��������̂ł����A�����͕�����ꌴ���ŋ�J���Ă���Ƃ���ł��B����͕s�K���̍K���������̂ł��B�F�S�n�Z�A�F�S�������N���Ă�����A���{�̍��y�̔����i�������j���Z�߂Ȃ��Ȃ��Ă����Ƃ��l�����܂��B�������A�������_���ɂȂ��Ă����ł��傤�B
�@�w�A��������ΔM���Y���I�x���Ƃ͂����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B
���������Ӗ��ŁA����̕���n�ق̍ĉғ����~�ߔ����͓������̂��Ǝv���܂��B |
�Q�O�P�T�N�R��3���i�j
�v���E�X�̑S�����R�[�����\�@�P�X�O����
�@�g���^�����Ԃ̓x�X�g�Z���[�@�v���E�X�̑S�����R�[����͂��o�܂����B
�@���{�̔������X�X,�V�O�O�O����A�C�O�̔������X�O����ŁA���s�i�O����ځj�̎ԂŁA�Q�O�O�X�N�R��23������Q�O�P�S�N�Q���T�܂ł̐��Y�i�S���Ƃ������Ƃł��B
�@���R�[���̗��R�́A�n�C�u���b�h�V�X�e���̃o�b�e���[�d���i�Q�O�P�D�P�{���g�j���U�T�O�{���g�ɏ�������d�q��H�Ɏg���Ă���IGBT�iInsulated Gate Bipolar Transistor�j�Ƃ��������̕��i�����M�̃X�g���X�ʼn���Ƃ������̂ł��B
����IGBT�Ƃ������i�͓d�Ԃ̑��x�������d�p��H�̐���ɂ��g���Ă��܂��B
�ȃG�l�̐�D�̂悤�ȕ��i�ł��B
�@���R�[�����e�́A����v���O���������������邱�ƂŁA���ׂ̂��������ς���Ƃ������Ƃł����A���ɔM��IGBT�����Ă���ꍇ�͕��i�����Ƃ������ƂɂȂ�悤�ł��B
�@
�@���̏����V�X�e���̓p���[�R���g���[�����j�b�g���Ɏ��߂��Ă��āA���[�^�̃h���C�u�p�̍��d���E��d���̔����A������s���Ă��܂��B�����ɃG�A�R���쓮�p�P�Q�{���g�����d�������������Ă��܂��B
�@�g���^�̃n�C�u���b�h�V�X�e���͂Q�̃��[�^���g���Â����\���ɂȂ��Ă��܂��B��͔��d�@�A������͋쓮�p���[�^�ł��B�����Ƃ��i�v���Ό𗬓������[�^�ŁA�쓮�p���[�^�͍ō��o�͂��U�O��W�i�W�Q�n�́j�A�ő�g���N�͂Q�O�VN/m(�Q�P�D�P�������E���j�Ƃ������͂Ȃ��̂ł��B
�@���̃V�X�e���������ɑ�e�ʁi��n�́j���𗝉�����ׂɁA��������Đ������܂��ƁA�Z��p�̃G�A�R���͂��������Q�n�͂���R�n�͒��x�̂��̂��啔���ł��B���̂Q�O�{�O��̗e�ʂ����郂�[�^��ς�ł��܂��B
�@�߂��̓d���Ɏ��t�����Ă���g�����X������ƁA�Q�O�Ƃ��R�O�Ƃ��������������܂��B
����͂�W��\�����Ă��܂��B�v���E�X�̂U�OKW�Ƃ������[�^�͓d���̂R�OKW�̕ψ�����Q��ς�ł���̂Ɠ����ł��B���Ȃ݂ɁA�d���̂R�OKW�̃g�����X����e�ƒ�ɔz�d���Ă��܂����A��˓����蕽�ςŖ�RKW�Ƃ����v�Z�ł�����A�P�O�����̓d�C���������܂��B
�@�ł�����v���E�X�ɐς�ł��郂�[�^�͂Q�O�����̓d�͂������A���������傫�ȃp���[�̃��[�^�ł��B
�@���̃��[�^���쓮����d�C�́A�v���E�X�ł̓j�b�P�����f�d�r���狟������܂����A�j�b�P�����f�d�r�͈����P�D�Q�{���g�ł�����A�U��ڑ��������́i�V�D�Q�{���g�j���P�u���b�N�Ƃ��āA������X�ɂQ�W����ڑ����ĂQ�O�P�{���g�Ă��܂��B
�@���̓d����IGBT�ŃX�C�b�`���O���ď������A�U�T�OV�܂œd�������ߋ쓮���[�^�ɂȂ��܂��B
�@
�@�Ȃ��A����ȍ����d���ɂ���K�v������̂����ȒP�ɐ������܂��B
���[�^�ɓd���𗬂���Ɖ�]�g���N�����܂����A�R�C���ɔ�������͂́AF=BIL�Ƃ��������Ŏ������悤�ɁA�͓͂d���@I�ɔ�Ⴕ�܂��B�Ƃ��낪���̓d���̓��[�^����]���n�߂�Ƃ��Ɉ�ԑ傫�ȓd��������܂����A���[�^�͑������ƁA���[�^���ɓd���𗬂��Ȃ��悤�ɋt�N�d�͂��������A����ȏ�d��������Ȃ��Ȃ�܂��B����d���ň��ɂȂ�܂��B����ȏ�ɓd���𗬂����Ƃ���ƁA���[�^�ɉ�����d�������߂Ȃ���Ȃ�܂���B
�@
�@�����ŁA�v���E�X�͑�ꐢ��A���A�����Č��݂̑�O����Ɛ����ǂ����ƂɁA����ɍ����d���������A���[�^�̉�]�͂����߂�悤�ɉ��ǂ��A���[�^�̔n�̓A�b�v��}���Ă��܂����B
�@
�@���̌��ʁA������H�Ɏg���Ă���IGBT�Ƃ��������̑f�q�ɂ͍��d���E��d����������f�q�̔��M���傫���Ȃ�A����̂悤�Ȏ��ԂɂȂ������̂ł��B
�@�ǂ������^�]�̎��Ƀ��[�^�ɉ��{���g�������邩�́A����v���O�����ŃR���g���[�����܂��̂ŁA����̃��R�[�������̐���v���O���������������邱�Ƃő�悤�ł��B
�@
�@���̐V�^�v���E�X�́A���悢��A�P���b�^�[�łS�OK�������邻���ł��B
�ȔR����͗��܂�Ƃ����m��Ȃ��قlj��P���i��ł��܂��B
�@�����ǂ�����ΔR��ǂ��Ȃ邩�́A�s�v�ȃG�l���M�[�i���_�j���Ȃ����邱�Ƃł��B
����������グ�Ă݂܂��ƁA
�@�@�ԑ̂��y������F
�@�@�@�����͍|�Ȃǂ��g���A�S�𔖂����ċ��x��ۂB
�@�@�@�����𑽗p����B
�@�A���M���镔�������Ȃ�����FIGBT�͑�d���������̂ő傫�ȔM�����܂��B
�@�@�@���݂̔����̍ޗ���Si(�V���R���j�ł����A�����SiC�i�Y���V���R���j�ɕς���ƁA
�@�@�@���M�ʂ�1/3�Ɍ���܂��B���̕��A���M������K�\�����̃��_���Ȃ��Ȃ�܂��B
�@�@�@SiC�́A�ȃG�l�Œ��ڂ���A������Ɍ�������Ă���ޗ��ł��B
�@�B���C�����������܂��F
�@�@�@�^�C���͐ڒn�ʐρi���j�������A���a��傫�����܂��B
�@�@�@���ꂩ��̎Ԃ́A�^�C���̕��������Ȃ�A�a���傫���Ȃ�ł��傤�B�̂̃J�u�g���H
�@�@�@���̑��A�G���W����J����̖��C�����炷�H�v�����܂��B
�@�@�@��͊w���������āA���s���̕��ɂ�镉�ׂ����炵�܂��B
�@���������H�v�����ςݏd�ˁA�܂��܂��R��͉��P�ł���]�n������܂��B
�����A�P���b�^�[�łT�O�������炢�͑����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����͏���ȑz���ł����A�����A�Z�p�̐i���Ŏ�������ł��傤�B
�@�ł��A������ȃG�l�Ƃ����Ă��A�Ԗ{���̉^�]�̊y�����A�������A�n���h�����O�Ȃǂ�
�傫���]���ɂȂ�ƁA�h���C�r���O�̊y���݂�A�������낳���Ȃ��Ȃ�܂��ˁB
|
2015�N�Q��25���i���j
����,�E�O�C�X�̏������܂���
�@���t���߂��āA�J�����߂��āA���悢��t�������܂ŗ��܂����B�䂪�Ƃ̒�̓썂�~��
�炫�n�߂܂����B
�@�����A6��50���̃o�X�ɏ�邽�߉Ƃ��o��ƁA���肭���ł������E�O�C�X�����Ă��܂����B ���N���߂ĕ����܂����B�܂��܂��A�w�z�[�z�P���x�Ƃ͖��Ȃ��悤�ŁA�w�z�[�E�P�L���x�Ƃ����������Ȃ������ɕ������܂�����B
�@�������A�E�O�C�X�̖�������������ƁA���������t�ł��B
�Ƃ��낪�A�쐯��o�X�₩��ےÂ̎R���݂��S�������܂���B�������Ă��܂��B��͔��܂�ł������A�������ۂł��B
�@�����[���̖����q�̖`���ɁA�w�t�͂����ڂ��x ���� �t�͂����ڂ��B�₤�₤�����Ȃ�䂭�R�ہA����������āA������ ����_�ׂ̍����Ȃт�����E�E�E�E�Ƃ���܂����A�t�͖閾���̍�����ԕ���L���Ă�낵���Ƃ������Ƃ炵���̂ł����A�����������}���`�b�N�ȕ\���͍���A�Ȃ�̂��Ƃ͂���܂���B�t���Ȃ�Č����Ă���ꍇ�ł͂���܂���B�����ł��B
�@�t�͋G�ߕ������������̂ŁA�����������オ���āA���{�܂Ŕ��ł���Ƃ����킯�ł��B
�@�����ŁA���������̂��Ƃ��C�ɂȂ�̂ł����A�����Ɗ؍��͓��C�ݐ��ɉ����āA��R�̌��������݂��ғ������Ă��܂��B
�@�ȑO�ɂ��������悤�ɁA�����͑�ʂ̊C���ŏ��C���₷���ƂŁA�^�[�r���������グ�悤�Ƃ��܂��̂ŁA�ǂ����Ă��C�ݐ��Ɍ��݂���܂��B���{�������ł��B
�@�����̉��n�A�`�x�b�g����S���t�߂̉����������オ���āA���{�܂œ͂��̂ł�����A�����̌���������A���̂��N�������ꍇ�ɂ́A�ԈႢ�Ȃ����˔\�������オ��A�����{�y����Q����͓̂��{��������܂���B���낵���b�ɂȂ�܂��B
�@���̒����́A�H�Ɖ��̐i�W�ŁA�܂��܂��d�͕s���Ƃ������Ƃł��̂ŁA��ʂ̓d�C�G�l���M�[���������邽�ߌ������݂��v�悵�Ă��邻���ł��B
�w�~�߂Ă���x�Ƃ͌����Ȃ��̂ŁA���߂āA���S��͖��S�������ė~�������̂ł��B
�@��C�ɂ䂯�Ε�����܂����A��������̍������H�̍��ˋ����ł��Ă��܂��B���̒�������A�����Ƃ��܂���B
�@���蔢�̂悤�ȍׂ��������\���[�g���̍����ɗї����Ă��āA���̏�ɍ������H�����݂��Ă��܂��B
�@��_�W�H��k�Ђł́A�V�����⍂�����H�̋������|��܂����B���{�̂������肵�����ˋ������|�ꂽ�̂ł��B�����̍������H�͌����ڂ��{���ɂЎア���̂ł��B
�@�n�k���Ȃ��Ƃ������ƂŁA�����ꌚ�݂��ꂽ���̂��Ǝv���܂��B�����̍������H��V�����͒n�k���N���ĉ��Ă��A���������̔�Q�ł�����A�Ǐ��Ɍ����܂��B
�@�������A�������������H�Ɠ����l���ŁA�n�k�����܂łȂ�����������v�Ƃ����Ў�Ȍ��݂��Ȃ���Ă���ƂȂ�Θb���Ⴂ�܂��B�����A�n�k���N����ΔߎS�ȏ�ԂɊׂ邱�ƊԈႢ�Ȃ��ł��B���{�͂��̂��������˔\�ʼn�������邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�t�͏��I�t�����I�@�Ȃ�ėI���Ȃ��Ƃ�������Ԃ͌��\�ł����E�E�E�B
�@�t�����݂Ȃ���A�v���͌����Ɍ��т��܂��B |
2015�N2��19���i�j
�}�b����ƃ��^�̖{���̎ʐ^
�@�w������x�ȗ��̑�l�C���Ă���NHK�̘A�����h���w�}�b�T���x�B���悢��A������I�Ղɍ����|�����Ă��܂��B
�@���̘b�́A�h�L�������^���[���̏����ŁA���̓j�b�J�E�B�X�L�[��n�Ƃ����}�b���ƒ|�ߐ��F����ƍȃ��^����̕���ł��B
�@����A�����ɍs�����Ƃ��A�n���S���V�{�w�߂��̃��C�����p�[�N�z�e�����̏��葋�ɁA�{���̎ʐ^���W������Ă��܂����̂ŁA�f�W�J���ŎB���Ă��܂����B
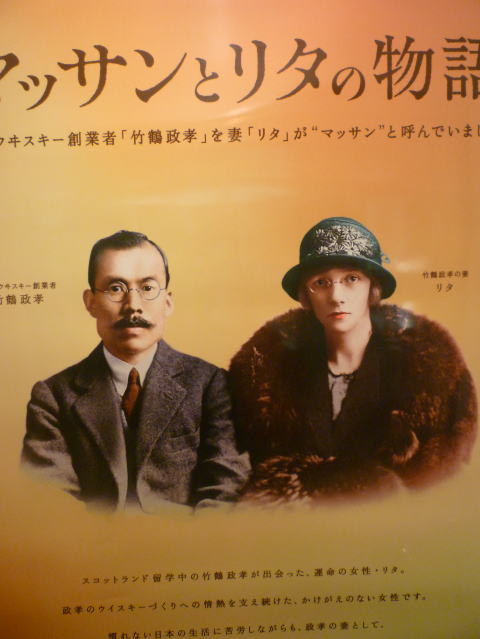 �@�@ �@�@
�@�X�R�b�g�����h�ɃE�B�X�L�[�Â�����w�тɍs�����}�b�T�������^����ɏo��A��l�͗��Ɋׂ�A���^���}�b�T���Ɣ��ɁA�͂����{�ɗ��āA���U����{�ʼn߂������B�����͑D�łQ������v��������B���͔�s�@�łP�Q�C�R���Ԃōs�����ł��邪�A�����̓C�M���X���猩�����{�͋ɓ��iFar
East�j�ƌĂ�ł����B�n���̉ʂĂ̍��Ƃ����C���[�W�������Ǝv���B�����������J�̍��A���{�ɂ���Ă������^����̈��̐[���ƁA�c�̋����������܂��B�������l���ȂƁB
�@���^����́A�P�W�X�U�N�i�吳�Q�X�N�P�Q���P�S���j�A�X�R�b�g�����h�A�O���X�S�[�n���ɐ��܂�A�����A���ی���������������ɁA���͂̔���������P�X�Q�O�N�Ɍ���
�@�v�̃E�B�X�L�[���̖��������邽�߂ɓ����̌��������B
�@�v���w�}�b����x�ƌĂ�ł����B�P�X�U�P�N�i���a�R�U�N�j1���P�S���A�U�S�ʼni���B
�@
�@�T���g���[�̎R��ƁA�j�b�J�̗]�s�͓��{�̃E�B�X�L�[�̂ӂ邳�ƂɂȂ��Ă���B
�]�s�́w�}�b�T�����ʁx�ŁA�������܁A����킢�̂悤�ł��B |
2015�N2��14���i�y�j
���������ĉ����낤�H
�i�I�[�f�B�I�k�`�B�j
�@����A���~�c�̃O�����t�����g����Panasonic�Z���^�[�A�n���P�K�ɂ���Technics��
�V���[���[���ŋv���Ԃ�ɖ{�i�I�ȉ������Ă�������B���ɏ������Ƃ���B
�@�����̎��̕������i�����j���ƂƂ��ɐ����Ă��鎖�����o���āA�ŋ߂͂��܂�Hi-Fi�I�[�f�B�I�ɋ����������Ȃ��悤�ɓw�́H���Ă����B���̐��E�͋Â肾���ƌ��肪�Ȃ��B���ł̂悤�Ȃ��̂ŁA�ǂ����ʼn����������̂�����ƁA�������������Ȃ�����A�����̂��̂ɂ������Ȃ�B�@����ł����I�@����Ŗ����I�Ƃ����킯�ɂ͂䂩�Ȃ��B
�@�I�[�f�B�I�}�j�A�Ƃ͂����������̂��Ǝv���B�I�[�f�B�I�Ɍ��炸�}�j�A�Ƃ͂��������l�킾�B�T���猩�Ă��Ĕn���Ȃ��ƂɎ���o���A�J�l���g�����̂��I�ƌ����邪�{�l�͎����Đ^�����B���ꂪ�}�j�A�ł���B
�@�I�[�f�B�I�}�j�A���A�����̂����Ă���I�[�f�B�I�V�X�e���ɏ�ɉ����s��������Ă��āA�ǂ��ɂ����Ă���ɖ����ł��鉹�ɂ������A�����Ƃ������ɂ������Ǝv�������Ă���l�킾�I
�@���鎞���܂ŁA�����������������Ԃɓ����Ă����B�ƌ�����肻�ꂪ�d���ł��������B
�u���E���ǃe���r�����S�ɐ��̒�������������Ă��܂����B�u���E���ǃe���r�͂P�T�D�V�TKH���̉����e���r�̒������ɏo�Ă����̂ŁA���̉�����������l�́A�������\���ɕ�����������Ƃ����ڈ��ɂȂ��Ă����B�w�L�[���x�Ƃ������Ɠ��̉��ŁA���ɂ����B����̓u���E���ǃe���r�̉�ʂ𑖍�����M�����ŁA���������͂U�OH���A���������͐��������M���Ƃ����M�������R��ĕ����������̂��B
�@
�@�ŋ߂̉t���e���r��v���Y�}�e���r�ł́A���̉��͑S���o�Ă��Ȃ��̂ŁA�����̎��̕������̃`�F�b�N�Ɏg���Ȃ��Ȃ����B
�@�����̎��̗ŁA�P�T�D�V�TKH���͋������݂ł͂P�OKH�����[���������Ă��Ȃ��悤�ȋC������B����A�l�ԃh�b�N�Łw�E�̎��̍����̕������������Ă��܂��x�ƌ���ꂽ�̂ŁA�߂��̎��@�ȂŒ��͌��������B���̌��ʂ͍��E�Ƃ��N����ɍ����̕������������Ă���Ƃ����O���t�����������������B���퐶���������ł͓��ɕ������Ŗ��͂Ȃ����A���������N��ɂȂ������Ǝ��o���Ă���B
�@
�@�Ƃ��낪�A�v���Ԃ�ɐ�ɏ������~�c��Technics�������ŁA�����s��̃n�C���]�I�[�f�B�I�����Ă��炢�A�w���������o�Ă���ȁI�x�Ƃ����������v���Ԃ�Ɋo�����B
�@����ɂ��Ă��A���̃V�X�e���͂T�O���~�A�T�O�O���~�Ɩ@�O�H�Ȓl�i�ł���B�ƂĂ������ɂ͎肪�o�Ȃ��B�������A���̒��ɂ͊���Ȑl����������B����������������B�I�[�f�B�I�}�j�A�Ȃ�T�O���~��T�O�O���~�͑債�������ł͂Ȃ��B
�@�I�[�f�B�I�̂��߂Ȃ�A�Ƃ����Ē����A�܂��͎������𐔐疜�~�����ĉ���������A���ւ����肷��l����������B���������Ђƈ���̐l�������A�I�[�f�B�I�����������Ă䂭�B
�@���̕ӂ��I�[�f�B�I�̖ʔ����ł���B�����l�t������ƁA�����ۂ����ɂ����������Ȃ��B
�w�T�O�O���~�ł��x�Ƃ����A�w�������I�@��͂肢�������o�Ă���ȁI�x�Ƃ������ƂɂȂ�B
����������l�ƁA�t�Ɂw�������ǁA���܂莩���D�݂ł͂Ȃ��ȁI�x�Ƃ����l������B
�@���Ƃ͂����������̂��I
�@���y�����ǂ����Œ����Ƃ������Ƃ́A�Ⴆ�I�[�P�X�g���̉��t�ŁA������Ԃ���s�A�j�V���ɂȂ�A�t�H���e�V���̍ő剹�ʂ܂ŁA�S���c�Ȃ��Đ��ł��鑕�u�����z�I���I
�@������Ԃ̎��ɁA�I�[�f�B�I���u����U�[�b�Ƃ����m�C�Y��A�u�[���Ƃ��������ɂ킸���ł���������悤�ł͗ǂ�HI-Fi���u�Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ��B
�@
�@�����̎��͂����܂ł������łȂ���Ȃ�Ȃ��B
���̃`�F�b�N�̎d���́A�������͐M�������Ȃ���ԁi���M���̏�ԁj�ŁA�A���v�̃{�����[�����ǂ�ǂ�グ�āA�ő�܂ʼn�A�X�s�[�J����S�����������������Ȃ���A���Ȃ��̑��u�͑f���炵���ƌ�����B�قƂ�ǂ̑��u�i�I�[�f�B�I�V�X�e���j�́A�{�����[�����ő�ɂ���ƁA�K���X�s�[�J����킸���ł��U�[�Ƃ��A�u�[���Ƃ��������o�Ă���B���ɂ̓{�����[�����i�肫���Ă��A�X�s�[�J����T�[���Ƃ��u�[���Ƃ���������������ꍇ������B����ł͂������u�Ƃ͌����Ȃ��B�@����̓I�[�f�B�I�V�X�e���A���ɃA���v�̃`�F�b�N�ɗL�����I
�@���M����Ԃł́A�����܂Ŗ����ł��邱�ƁI�@���ꂪ���z�ł���B
�@
�@�����āA�ő剹�ʂ̃t�H���e�V���̐M���������Ă��Ă��A�c�܂��ɗ]�T�������čĐ��ł���Αf���炵���B�قƂ�ǂ̃V�X�e���͍ő剹�ʎ��ɘc�ށI�@���ӂ��ɂȂ�B
�@
�@���������ʂł̓n�C���]�I�[�f�B�I�͗��z�I�ȓ����i�f���j��L���Ă���B�ȑO��LP���R�[�h�ł͐�Ώo���Ȃ��������z�I�ȍĐ������Ƃ��ȒP�ɍČ��ł���悤�ɂȂ����B�f�W�^���Z�p�͕s�\���\�ɂ��Ă��ꂽ�B�f���炵�����Ƃ��I
�@���̓����͐l�Ԃ̎��̓������͂邩�ɒ����Ă���B�Q�OH���`�X�OKH���܂Ŋ��S�ɍČ�����B����̓n�C���]�̃\�[�X�i�����j�̂��ƂŁA���̑f���炵�����������邽�߂ɂ́A�A���v��X�s�[�J�̎��͂������B�������A���z�I�ȉ������o���������Ƃ͑傫�ȑO�i���B
�@�n�C���]�̑f���炵�������Ă��A���܂肢���Ɗ����Ȃ��Ȃ�A���Ȃ��̎��̐����ƌ���ꂩ�˂Ȃ��B
�@�V�X�e���͋Z�p�I�ɂ͊����ɋ߂Â�����B�B
�������A�{���ɂ��������ǂ����́A�܂��܂����m�̗̈悪��������B
�@���������ł́A�Ⴆ����z�[���ŃI�[�P�X�g�����t�����^����ہA�ǂ������}�C�N���g�����A�}�C�N���ǂ��ɐ����t���邩�A�z�[���̉��������ő傫�����^���ꂽ�M�����ς��B
�@�}�C�N�ɓ��鉹�́A���t����y�킩�璼�ړ`��鉹�i���ډ��j������A�z�[���̕ǂ�V��ɔ��˂��ē`����ė��鉹�i�Ԑډ��j������B���g�͕��G�ɔ��˂��J��Ԃ��ē`����ė���B�������������̉��̍����g�Ƃ��ă}�C�N�͉���d�C�M���ɕς���B
�@�Ƃ������Ƃ́A�z�[���̓V���ǂŔ��ˁA�z������������A�}�C�N�̂������ŃI�[�P�X�g���̉��t�������ƑS���������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B
�@�w�����t�x�ŕ��������͑f���炵���������邩������Ȃ����A�t�ɁA�����t���A�n�C���]��CD�̕����ǂ��Ǝv���l�����邩������Ȃ��B�ǂ��炪�������͕ʂƂ��āA���҂͑S�������ł͂Ȃ��Ƃ������ƁB
�@���̂��Ƃ͎���⎎�����ʼn��y�����A�X�s�[�J����o�鉹�����ڎ��ɓ͂����ƕ����̓V���ǂɔ��˂��Ă���͂�������������ĕ�������B���̊W���ǂ��Ȃ��Ă��邩�ŁA�S���������y�\�[�X���Đ����Ă������ꏊ��A�����ɂ���đ傫���ς��B
�@������A���[�J����X�̎������ŕ����ėǂ���������C�ɓ���A���̃V�X�e�����A���������Œ����ƁA�w����I����Ȃ͂�����Ȃ������A���̎��͂����ƃN���A�Ȃ����������Ă����̂ɁI�x�Ƃ����悤�Ȃ��ƂɂȂ�B�@�������A���̋t�̏ꍇ������B
�@���Ƃ͂����������̂��I
�@���̓_�A�e���r�́A�ǂ��Ō��悤���Y��Ȃ��̂��Y�킾���A�������͉̂����B����ꏊ���ς���Ă��A�����Ă��A�]���͂��܂�ς��Ȃ��B���ʔ����ȐF�┧�F�̉��Ȃǂ̕\���������B
�@�̐l���킭�A�w�S���͈ꌩ�ɔ@�����x�Ƃ͂����������Ƃ�������Ȃ��B
���邱�ƁA���Ȃ킿���o�́A���o���P�O�O�{�\�͂��s���̂ł���B�ꌩ����A��ΓI�Ȏ����Ƃ��ĔF�������B�������A���̐��E�́A���鎞�ɂ͂����Ǝv���Ă��A����Ŗ����ł��Ȃ��Ȃ�B���[�J�����ϕ]���������V���i���o���B�悭����Ă���B���������j���[�X���`���Ǝ����̎����Ă���V�X�e���ɕs����������B�����ĐV���i���ɂ䂭�B�Ȃ�قǂ����Ɗ�����ƁA�������Ă������Ă������Ȃ��B�}�j�A�Ƃ͂����������̂��B
������I�[�f�B�I�Ƃ������i�ɂ̓��}�������܂��B���}���Ƃ͋�z�̐��E���B
�@���[�J�͂����Ƀ��}����������邩�A���}����~�����Ă邩�A���}���邩�A���傫�ȈӖ������B�����痝�l�߂ł��̂Â�������Ă��A���̃��}����������Ȃ����i���ł͐������Ȃ��B
�@����Ӗ��Ŗ��ȏ��i�ł���A�܂�����Ӗ��ł͉��Ƃ������Ȃ���肪���̂��鏤�i���I
|
2015�N2��10���i�j
�I�[�f�B�I�̓��}���̐��E���I
�i�I�[�f�B�I�k�`�A�j
�@�Q���W���ɁA�wTechnics���������H�x�̋L�����������B
�@Technics�u�����h����������A�����̂悤�ɁATechnics���i�̊J���ɖ�30���N�Ԃ��g����Ă����҂ɂƂ��ẮA��ώ₵���v�������Ă����B
�@
�@�������A����ŁATechnics�Ƃ����u�����h�Ɏv�������߂ē����Ă����҂ɂƂ��ẮA�w���������Ȃ��̂Â���x�ŁATechnics�u�����h���i�����̒��ɍēo�ꂷ�邱�Ƃɂ͋����������Ƃ����v���������������B
�@������A�w�V����Technics���i�͂ǂ������d�オ��ɂȂ��Ă���̂��H�x�@�������̖ڂƎ��Ŋm�F�����������BTechnics�@OB�Ƃ��āA�����������Ƃ𖢂��ɂ�������Ă���̂́A���ꂾ�����̃u�����h�������Ă������炾�Ǝv���B
�@���̓x�A�~�cPanasonic�Z���^�[�@�n����K�̃e�N�j�N�X�������Ŏ����̋@����B
�@
�@���Ƃ��ƁA�I�[�f�B�I�̐��E�́A�����K���i�ƑS���Ⴄ�����̏��i���B
�@�����]�_�ƂƂ������قȐ搶�����������āA�e�Ђ̐V���i��]�����A�I�[�f�B�I�G���ɂ��̋L���������Ă����B���͂��̐����������Ă���Ǝv���B�����̐搶�����A���A��������A���̕��������s���R�ɂȂ��Ă���N��B
�@
�@�����́A�V���i���ł���ƁA�搶��Ɏf���A�������Ē����A�����]�������炢�A�ǂ��L�����G���ɏ����Ă��炤���Ƃ��A��`�Ƃ��Ĕ̔��Ɋ�^�����B�e�Ђ͋����āA�]�_�Ɛ搶�����������オ�������BTechnics�͑��̋������d��Y�Ƃ̏��i�Ȃ̂ŁA�搶�����Z��ł��铌���ߍx�ɑ��ɂ��ʂ������̂��B��C�̒S�������𓌋��ɒ��݂����Ή������B
�@
�@���̗ǂ��������A���������ŕ]���ł���̂Ȃ�A�J���҂ɂƂ��Ă͊y�Ȏd���ł���B
�������A�ǂ̏��i�i�Ⴆ�Ύ����ԁj�������ł��邪�A���ɃI�[�f�B�I���i�͌v����ő��������������ŕ\���ł��Ȃ�����������B���������͊�{�ɂȂ邪�A����ȏ�Ɏ��ŕ����������ŕ]�����ς��B�@�����ɒ�m��ʃI�[�f�B�I�̒k�`������B
�@��������ς���Ȃ�A�I�[�f�B�I�ɂ͐[�����}�����������BHi-Fi�I�[�f�B�I�̓��}���̐��E�ł������B
�@
�@A���Ƃ��������]�_�Ƃ��悭�d�オ���Ă���Ƃ����]�������Ă��������Ă��AB���Ƃ����]�_�Ƃ͂�����ƒ���ɉ����R�����AC���Ƃ������͒���͂��ꂢ�ɕ\������Ă��邪�A����̐L�тɌ�����ȁI�Ƃ��A�P�����R�����Ƃ��A���o�I�Ȍ��t���g���Č�����������H�ƌ����Ύ���ɂȂ邪�A���������L����������Ă����B
�@���[�J�͂���ɔ��_���邱�Ƃ��n�����Ă���H�@�Ǝv���Ȃ��炨�t���������Ă����B
�@
�@�Z�p�҂�Ȋw�҂͕������������ǂ���ŁA�܂��͑����𗊂�ɉ���������B
�@�X�s�[�J�̊J���͖������Ƃ�������Ȕ����������������ŁA�X�s�[�J��炵�A�Q�OH������Q�OKH���܂ł̐M�����o���āA�X�s�[�J�̑O�ɑ���p�}�C�N��u���A�}�C�N�̐M�����O���t�ɋL�^����B�����Z�p�҂Ȃ�N���m���Ă���B&K�i�u�����[�G���j�Ƃ����f���}�[�N���̑������g���A�X�s�[�J�̓����𑪒肵�ẮA�X�s�[�J�L���r�l�b�g�i���j��X�s�[�J���̂̐U����_���p�[�Ƃ������i��A����A�ቹ�p�̃E�[�n�A�����p�̃X�R�[�J�A�����p�̃c�C�^�[�Ƃ����X�s�[�J�̓������ő�����������ߊe�X�s�[�J�ɐM����U�蕪����l�b�g���[�N�Ƃ����R�C���ƃR���f���T�[�łł�����H�萔��ς��Ȃ���A�Đ����g�������R�ɂȂ�悤�ɉ��P���d�˂��B
�@�Đ����g�����Q�OH������20�j�g���܂ŁA���S�ɕ��R�ȓ����̂��͍̂��Ȃ��B�����ɂ���ɋ߂Â��邩�ł��邪�A�������ꂪ�ł����Ƃ��āA�������ʼn��y���Ă݂āA������������Ƃ͌���Ȃ��B
�@
�@���̕ӂ����������Ǝ��ۂ̎����ł͑傫���Ⴄ�����̓���ƌ�����B
�������A���Ȃ��Ƃ��������Ńt���b�g�ȓ����ɋ߂Â��Ă����Ȃ���������ɂ͋߂Â��Ȃ��B��������ς���ƁA�������̕K�v�������������̕��������ł���A�\�������͎��ۂɎ������ʼn��y���Ă݂āA���������o�邱�Ƃ��B���̗����������ł��Ȃ���A�܂��܂��������ȏ�Ԃƌ������ɂȂ�B
�@�X�s�[�J�̊J���҂͂������������⑪��⎎������X�J��Ԃ��ď��i���Ă����B
���̊J���̐i�ߕ��͌��݂ł���{�I�ɂ͕ς��Ȃ��Ǝv���B
�@�Ƃ��낪�A�ŋ߁A�傫���ς���������́A�����ł���\�[�X�̕������B
�R�O�N�قǑO��LP���R�[�h�A����ɁA���̂R�O�N�O��SP���R�[�h�̎���ł������B����CD�̎���ł���B����CD���ł��Ă����R�O�N���o�����B
�@�I�[�f�B�I�̉����i�\�[�X�j�͂ǂ������킯���A�R�O�N�T�C�N���ŁA�V���������ɓ���ւ���Ă����B���̓x�ɉ����̓���������I�ɗǂ��Ȃ��Ă����B
�@�ǂꂾ���悭�Ȃ������Ƃ����ƁA�������ς�閈�ɁA��30�{����100�{���x���P���Ă���B
�@SP�̓��R�[�h��������ƕ����邪�A�U�[�E�U�[�Ƃ����G���i�m�C�Y�j�ƂƂ��ɉ��y�A�̐����������Ă���B�M�����ƃm�C�Y���ׂ�ƁA�M�������m�C�Y�i�U�[�U�[�Ƃ����G���j�ɑ��Đ��{���x�Ƃ����㕨�������B�������^������Ă��鉹�̎��g���ш�͋����āA������������H�����x�ł������B
�@
�@���ꂪLP���R�[�h�ɂȂ��āA�M���ƃm�C�Y�̔�iSN��Ƃ����j��30�{���x�ɂȂ����B�G�������y�̐M�����ɑ���1/30�ȉ��ɂȂ����̂ł���B�������A�^������Ă��鉹�̎��g���͂Q�OH������Q�O��H���ȏ�ɍL�������B�f���炵�����ōĐ��ł���悤�ɂȂ����B�������ALP���R�[�h�͎�舵���𒍈ӂ��Ȃ��ƁA����������A�����t����ƁA���R�[�h�̍a�ɏ���S�~�����܂�A���ꂪ�v�c�v�c�Ƃ����G���ɂȂ�����A�Ђ��݉��Ƃ��ĕ�������B
�������R�O�����Ƃ����傫���ł���B�܂��A�ቹ���\���o���ƁA�U������荞�݃n�E�����O�i�{�E�{�[�Ƃ������j���o��B
�@�����������_�����������ASP�ɔ�ׂ�Ɣ���I�ȉ���������ꂽ�B
�@���ꂪ�X��CD�ɑ������B
CD��LP�͑S���ʕ��ŁACD�̓f�W�^���M���ŋL�^���Ă���B
SP��LP���A�A�i���O�M���ŋL�^���Ă���̂ŁA�{���̍������ዾ�ōa������ƁA���y�M���̔g�`�����̂܂܍��܂�Ă��邱�Ƃ�������B
�@�}�C�N�ŏE�����d�C�M�������̂܂܃��R�[�h�̍a�ɍ��ݍ����̂������B
�@
�@CD�̓f�W�^���M��������A�P�Q�����̃f�B�X�N�ɉ����̌��̏W���Ƃ��ċL�^����Ă���B���̌��Ƀ��[�U�����āA���ˌ������o���A���̐M�����f�W�^��-�A�i���O�ϊ��iDA�ϊ��j���Č��̉��y�M���ɖ߂��B
�@�}�C�N�̐M���i�A�i���O�M���j���f�W�^���M���ɕϊ��iAD�ϊ��j���ACD�����ACD�����t����ƁADA�ϊ����Č��̃}�C�N�ŏE�����M���A���Ȃ킿���y�M���ɖ߂�̂ł���B
�@
�@�P�Q������CD�̔i�f�B�X�N�j�ɍ��܂�Ă��鉚�E���̌��́A�b�q������̃O���E���h�̂P�����̍����ɕC�G����傫���ł���B
�@�������������̉��E���̌`��f���炵�����y���Č��ł���悤�ɂȂ����B���ꂪ�f�W�^���Z�p�̑f���炵�����Ȃ��B
�@
�@���̌��ʁACD�ł�LP���R�[�h�Ɣ�r����100�{�i�m�C�Y���M���ɑ��ĕS���̈�j�Ƃ�������������ꂽ�B���̎G���ƐM�����̔�ł́A1/3000�ȏ�̉��P�ɂȂ�B
�@�قƂ�ǎG���͎��ɕ������Ȃ��Ȃ����B�����āA�^���E�Đ��ł��鉹�̎��g���͂Q�OH������Q��Hz�܂ŁA�l�Ԃ̉����g���ш�͊��S�ɍČ��ł���悤�ɂȂ����B
�@����Ŋ������Ǝv���Ă����B
�Ƃ��낪�ŋ߁A����CD�̉����d���Ƃ��A�M�X�M�X���ĕ�������Ƃ��A�����݂��Ȃ��Ƃ��A�����Ȉӌ����o�Ă����B
�@�����č����݂��A���E���ł�LP���R�[�h�̈��p�҂��������邱�Ƃ������ł���B���ɊC�O�A���[���b�p�ł�LP���R�[�h�̈��p�҂���������Ƃ����b�ł���B�����ALP���R�[�h�ɓ��ʂȈ���������̂��낤�B
�@������CD�ɁA�����ۑ肪�c��̂��H�@�Ƃ������Ƃł��낢��͍����Ă����Ƃ���A�w�l�Ԃ̎��͖{���������Ȃ��͂��̂Q�OKH���ȏ�̎��g�����A�̂⎨�Ŋ����Ă���x�Ƃ��������������悤�ɂȂ��Ă����B
�@����͂��������l�B������Ƃ������ƂŁA�S�����������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��̂Œ��ӂ��ė~�����B
�@�����������ɍ������z�����߂�l���������Ă����������Ȃ����A�Z�p�̐i���͂�������������n�܂�B
�@�����āA���A�wTechnics�͕��������H�x�̋L���ɂ��������Ƃ���A�n�C���]�E�I�[�f�B�I�Ƃ������L�ш�̃\�[�X�����܂�Ă����B�n�C���]�Ƃ́A�u�n�C�E���]�����[�V�����x�̗��ŁA�w���𑜓x�x�Ƃ����Ӗ����B
�@�n�C���]�E�I�[�f�B�I�́A�Đ����g���ш�́A�Q�OH������X�OKH���܂ŐL�тĂ���B�܂��ASN��͎��ɐ��\�����̂P�ɂȂ�A�S���m�C�Y�͕������Ȃ��B��������͉̂��y�݂̂Ƃ������ƂɂȂ����B����͂܂��ɗ��z�̉��y�\�[�X�̏o���ł���B
�@
�@�n�C���]�E�I�[�f�B�I���ɂ́A�C���^�[�l�b�g�̃n�C���]��������Ă���T�C�g�ɃA�N�Z�X���A�_�Ē��������Ȃ��_�E�����[�h����B�����͉ۋ����Ŏx�����B��Ȑ��S�~�Ƃ������Ƃ��B�N�ł��_�E�����[�h�͂ł���B
�@
�@�����ŁA�n�C���]�E�I�[�f�B�I���V�X�e�����Ƃɐݒu���Ă��ACD���ǂꂾ�������������邩�ۏ̌���ł͂Ȃ��B
�@�����A���͕������iTPO�G���ԁA�ꏊ�A�C���A�̒��ȂǗl�X�ȗv���j�Ɉ����đ傫���ς��B�܂�A���������ǂ����́A�����Ȋ����������Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�n�C���]�����́A�������ł���Ƃ����ۏ͂���B���������ꂪ�����Ď������������Ǝv�����A�����ł��邩�ǂ����͕ʖ�肾�Ƃ������ƁB
�@���h�Ȏ������������Ă���l�́A���z�I�Ȋ��ɋ߂��l���ƌ�����B�������A�����̏Z���ł͎������������Ƃ͕��ʂ̐l�ł͖������Ƃ�����B����Ȃ��y�Ƀn�C���]�E�I�[�f�B�I���y���ނɂ͂ǂ�����������ƃ��[�J�͍l����B
�����ō��A���h�o�V�J�����ȂǗʔ̓X�ɂ䂯�A��ʂ̃w�b�h�t�H���������Ă���B�悭����ƁA�n�C���]�Ή����i�Ƃ������Ă���^�O���Ԃ牺�����Ă���B���������w�b�h�t�H���͈����Ă������~�A�������͉̂��\���~��������̂�����B
�@���Ȃ݂ɂP�T���~�̃w�b�h�t�H���Ŏ������Ă݂����A�Q���~�̃��m�ɔ�ׂ�ƁA����̍L�����������B�\�[�X�̓n�C���]�������B��y�Ƀn�C���]���y���ގ�i�Ƃ��Ĕ����Ă���̂��B��y�ƌ����Ă��A�����~���琔�\���~������B
�@���āA�{���̂����������߂āA�O�����t�����g����Technics�������ɗ���������B
�����ŕ��������y�̈�ۂ́A���܂ŕ��������Ƃ��Ȃ��f���炵�����������Ƃ�����ۂ��������B
�@���ꂪ�n�C���]�������A���ꂪ�V����Technics�̉����Ɗ��S�����B
���̈�ۂ͏��������������ƂŁA�ق��̐l���ǂ����������������ǂ����͕�����Ȃ��B
�@Technics�ɍD�ӓI�Ȑl�ŁA���i�̕�����҂��]��ł���l�͑����f���炵�������Ɗ����������낤�B�������A�ȑO����A���`�e�N�j�N�X�̐l�͂������������Ɏ�������ǂ����͕�����Ȃ��B
Technics������
 ���i�́A�����Ȍv�������g���A�ŐV�̋Z�p��n�C�e�N�ޗ��荞��ŊJ�����Ă���Ǝv���B���������͑f���炵�����̂��Ǝv���B ���i�́A�����Ȍv�������g���A�ŐV�̋Z�p��n�C�e�N�ޗ��荞��ŊJ�����Ă���Ǝv���B���������͑f���炵�����̂��Ǝv���B
�������A�����Ă݂āA�ǂ�������ۂ��邩�ǂ����́A���̐l�̏����ɂ��قȂ�B
�@���̐��E�Ƃ͂����������̂��I�@�E�]�͂��̎��A���̎��Ŋ��������ς��B
�@������ATechnics������A�傫����A������邽�߂ɂ́A����������{���ł͂Ȃ��ATechnics�Ƃ����u�����h�헪������B
�@Technics�ƕ��������ŁA�f���炵�����������鏤�i���Ƃ�����ۂ�^����A�i���̐���ϓI�Ȃ��́j���Ƃɐ����ł���A���E�̈ꗬ�i�ɂȂ�邾�낤�B
�@���i�͑f���炵�����̂��I
|
2015�N2��8���i���j
Technics�͕��������H
�i�I�[�f�B�I�k�`�@�j
�@�w�܂Ƃ���Hi-Fi�I�[�f�B�I�́A���E����������������x�Ǝv���Ă������A�ŋ߁A�e���[�J��
���A�������Ď��g�ݎn�߂��B
�@�~�c���h�o�V�J�����R�K�̃I�[�f�B�I�����ɍs���ƁA�ȑO��HI-Fi���[�J�������i�����j���\���ď��i��̔������Ă���B����ɏ��ʐς��L���Ȃ��ė����B�������A�ȑO�̂悤�Ȋ��C�͂Ȃ����A�I�[�f�B�I���D�҂͑��ς�炸���������݂��Ă��邱�Ƃ��������B
�@
�@Pioneer�ASansui�AKenwood�Ƃ����I�[�f�B�I��O�Ƃ��W�R�ƋP���Ă������a�T�O�N�O��A�Ɠd���[�J�ł��鏼���d��́ATechnics�u�����h�ő傫�Ȓn�ʂ�z���Ă����B
�@Technics�͍����͂������A���ɊC�O�A�Ƃ�킯���[���b�p�ő傫�ȃV�F�A�������Ă����B
�@
�@CD�̏o���ƂƂ��ɁA������Hi-Fi�I�[�f�B�I���[�J�́A����Ɏs�ꂩ������Ă������B
�@���܂ł̃A�i���O�I�[�f�B�I���i�����ł��Ă��܂����̂��B
�@�{���Ȃ�ACD�Ƃ�������Ă��Ȃ����������ꂽ�̂�����AHi-Fi�I�[�f�B�I�͂܂��܂��傫����������Ǝv��ꂽ���A���ꂪ�傫�Ȍ�Z�ł������B
�@
�@CD�͈�ʉƒ�ɓ���f�W�^���@��Ƃ��čŏ��̏��i�ł������B�f�W�^���@��͘r���v�����������A�T��~�̎��v�ƂT���~�̎��v�ŁA�덷���قƂ�Ǖς��Ȃ��B�����P�T�b�Ƃ������\�͂قƂ�ǒl�i�ɂ�����炸�����ł���B���ꂪ�f�W�^�����i�̓������I
�@
�@CD���f�W�^�����v�Ɠ��l�A�T��~�̃v���[���ł��A�P�O���~�̃v���[���ł��Đ������قƂ�Ǖς��Ȃ��B������}���ɒቿ�i���i�����AHi-Fi�I�[�f�B�I�Ƃ�������́A�R���f�B�e�B�A���Ȃ킿���폤�i�ɑ����Ă��܂����B
�@�����āA�{���ɂ����������߂郆�[�U�͉��������̂��A���i���Ȃ��悤�ȏ�ԂɂȂ��Ă��܂��Ă����B�������A�C�O�̏����ȃI�[�f�B�I���[�J�ׁ͍X�Ɩ���ۂ��Ă���Ă����B���{�ɂ������������[�J�͐��А����c���Ă���B
�@CD�͂P�X�W�Q�N�ɔ������ꂽ�̂ŁA������R�R�N���̂ɂȂ�B�R�O�N�]��o���āAHI-Fi�I�[�f�B�I���Â��ȃu�[�����N�����Ă���B�Ƃ͌����Ă��A�ȑO�̂悤�ɁA��҂��M�����ĉ��y�ɖv�������Ԃł͂Ȃ��B���a�̎���͑�R�̉̎��A�O���[�v�T�E���Y��A�x���`���[�Y�A�r�[�g���Y�A�܂��N���V�b�N���y�ȂLj��Ă����B
�@���͌���e���Ȃ��B����͌o�ς̒�������ɂ����̂��낤�I�@�w���͉��y�ɕ�����ĉ߂�����ł͂Ȃ��x�Ƃ������Ƃ�������Ȃ��B
�@��҂͍���ɃX�}�z�������A�E��̎w���ɓ������A��ʂɒ������Ă���B�����҂����łȂ��A���\�N�z�̐l�����l�Ȍ��i���悭����B�d�ԓ��ł͂V�O���ȏ�̏�q���X�}�z�����Ă���B�قƂ�ǂ̐l�͂��킢���Ȃ��Q�[���ɋ����Ă���B
�@�����̑����f����ڂŒǂ������āA���_�o���h�����A���]���h������B
�@�h���̋����f���i�摜�j�Ɋ��ꂽ�l�́A���y�̉E�]�̐��E�Ƃَ͈����̗̈悩���m��Ȃ��B�{���̂������A���y�����Ă��A�ǂ��������������邾�낤���H
�@�������A���̒��͈ڂ�ς��B
�@CD��LP���R�[�h�ɔ�ׂđf���炵�������������Ă����B����͍Đ��ł�����g�����l�̉����g���i�Q�OHz����Q�OKH���j�������ɍĐ��ł�����̂ł������B�@�c��m�C�Y���x���͂قƂ�ǂȂ��B�܂����̋���i�_�C�i�~�b�N�����W�j�̍Č������f���炵���B
�@����ɏd�ቹ���Đ����Ă��n�E�����O���Ȃ��B���������f���炵������������������I�ȏ��i�ł������B
�@������A�e�������[�J�͂���CD�Ƃ����f���炵�����i���g���A�����Ɩ{���̉��̒Nj������������葱���邱�Ƃ���������B���ꂪ�f�W�^���̕|���ŁA�R���f�B�e�B���i�̕��ɑǂ���Ă��܂����B������Hi-Fi�I�[�f�B�I�͑傫�Ȏs�ꂪ�����������B
�@�ꕔ�A�����ȋK�͂̉������[�J�ׁ͍X�Ǝ��Ƃ��Ȃ��Ő����c���Ă����B
�@�������A�ŋ߁A�gCD�̉��͍d���A�M�X�M�X���Ă���h�Ƃ����悤�Ȉӌ����o����Ă����B�t�ɁA�hLP���R�[�h�̉��͂܂�₩�ŁA���������͋C������h�Ƃ����Ă����B�����������猾���ACD��LP���R�[�h�̔�ł͂Ȃ���������̂��I�B
�@�������A�ŋ߂̕����́A�w�l�Ԃ̎��͉����g���ш���Đ��ł���Ί������x�Ƃ����l������A�w�����g���ш�O�̒����g�̗̈�̍Đ������y�̕��͋C�������o���x�Ƃ����l����������l�������Ȃ��Ă���B���̌������͐��������ǂ���������Ȃ��B
�@
�@�������A�o�C�I������e���ƁA�Q��Hz�ȏ�̍������y�킩��o�Ă��邱�Ƃ͊m�����B�o�C�I�����ɂ�����炸�A�e�y��͂Q��Hz�ȏ�̍������o���Ă���B
�@CD�͂��̂Q��Hz�ȏ�̉��̓t�B���^�[�Ŋ��S�ɃJ�b�g���āACD�̒��ɂ͐M���Ƃ��ē����Ă��Ȃ��B
LP���R�[�h�ɂ́A�Q��Hz�ȏ�̉��y�M���͓����Ă���B
�@CD���������ꂽ�����̋Z�p�I�Ȍo�܂ŁA����͂Q��Hz�ɂ���ƌ��߂��B����͂Q��Hz�ȏ�̉���^���A�Đ�����ɂ�CD���傫�ȏ��ʂ�������ꕨ�A���Ȃ킿DVD�₻�̑��̂�荂�x�ȋZ�p���K�v�ł������BCD�͈�ԑ����J�����ꂽ���̂�����A�����̋Z�p���x���ł͖����ł������B
�@���ꂪ�A���ADVD���ł��ACD�̂U�{���x�̏��ʂ������P�Q�����̃f�B�X�N�ɋL�^�ł���悤�ɂȂ�A����Ƀu���[���C�Ȃ�DVD�̂T�{��������̂��ł����B
�f�W�^���Z�p�̐i���̎����ł���B�����M������f���M���̋L�^�ɓK������ʂɂȂ�A��ʉƒ�ɂ����荞�B
�@���������@�킪�ł��āA�n�C�r�W�����i�n�f�W�e���r�j�̘^���A�r�f�I�B�肵���摜���f�B�X�N�ɏĂ��āA�݂��Ɍ���������A�ۑ��ł���悤�ɂȂ����B
�@���̋Z�p�����y�̘^���A�Đ��Ɏg���ACD���t�H�[�}�b�g�Ő��������Q��Hz�̍�����̐M���ɂ�����炸�A�S��Hz�ł��W��Hz�ł��^���Đ����ł���B������X�[�p�[�I�[�f�B�I���ȒP�Ɏ����ł��鎞��ɂȂ����B
�@
�@�ŋ߁A�w�n�C���]�x�Ƃ������t�����s���Ă������A���ꂪ���̈Ӗ��ł���B
�n�C���]�����́A�C���^�[�l�b�g����_�E�����[�h���ăn�[�h�f�B�X�N�ȂǂɃR�s�[����B
������Đ����������ƂɂȂ�B����p�\�R���ȂǂŃf�W�^���M�����_�E�����[�h���Ă���A������Đ�����B
�@���̃n�C���]�I�[�f�B�I�ɍŋ߁A�I�[�f�B�I�e�Ђ����i�����n�߂Ă���B
�@�����ɗ��āATechnics���������A�n�C���]�I�[�f�B�I�@������i�����Đ�ʔ��\�����B
���i�́A���̂Ƃ���Q�V�X�e�������ł���B
�@�v���~�A���V�X�e���͂T�O���~���x�A
�@���t�@�����X�V�X�e���͂T�O�O�����x
�Ƃ������ƂŁA������ɂ��Ă����������z���i�ł���B
�ǂ��������i���̏ڂ������͉��L�̃z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ���Ă���̂Ō��ė~�����B
�@�@http://jp.technics.com/
�@�~�c�O�����t�����g���@��ف@�p�i�\�j�b�N�Z���^�[�@�n���P�K�Ɏ�����������̂ŁA���Ђ��̑f���炵�������Ă݂Ăق����B
�@�����́A�v���~�A���V�X�e���i�T�O���~�j�ŏ\���ȋC�������B
������̕����e�y��̒�ʂ��������肵�Ă����悤�Ɏv�����B
�@�������A�{���̓��t�@�����X�V�X�e���̒��̐L�т͑f���炵�������B��͂�X�s�[�J�͔����傫�Ȃ��̂łȂ��Ƃ�����肵���{���̒ቹ�͏o�Ȃ��ȁI�Ƃ������z�ł������B
�@��������ɂ͗\�K�v�Ƃ̂��Ƃł��̂ŁAURL����\���ʂɃA�N�Z�X���ĉ������B
|
2015�N1��7���i���j
�g���^�̌��f
�@�V�N���߂łƂ��������܂��B
�@���N�͖��N�Ƃ������ƂŁA�U��ڂ̔N�j�ɂȂ�܂��B
���N���͊F�l�ɁA��������̃A�N�Z�X���܂��āA���肪�Ƃ��������܂����B
�{�N����낵�����肢���܂��B
 ����̒����V��TOP�L���ŁA�g���^��FCV�i�R���d�r�ԁj�Ɋւ���֘A������S�� ����̒����V��TOP�L���ŁA�g���^��FCV�i�R���d�r�ԁj�Ɋւ���֘A������S��
�����J������Ƃ����L�����f�ڂ���Ă��܂����B����͑f���炵�����Ƃ��Ǝv���܂��B
�g���^�В��̎v���������f���Ǝv���܂��B
�@�g���^�ƃz���_������FCV�ł͐�s���Ă��܂����A���̎����ԃ��[�J�͒ǐ��ł��Ă��܂���B���ɑ��z�̊J���R�X�g��������S���V�����Z�p����ł��B
���̌Ղ̎q�̋Z�p���ŊJ������Ƃ������Ƃ͉p�f�ȊO�̉����̂ł͂���܂���B
�@��́A�����K�V���������W�I�̓������ŊJ�������Ƃ�����b������܂��B����ɂ�肽������̓d�C���[�J�����W�I�̊J���E�����ɎQ�����āA���W�I�̔̔����傢�ɐL�т��Ƃ������Ƃł����B����������Ƃ��Ă͑�p�f�������̂ł��B
����̊J���̋L����ǂ�ŁA����Ɠ����悤�ȏՌ����܂����B
�@�g���^�̓����̖����J����2020�N�܂ł̗L�����ŁA�R���d�r�{�̂̊֘A������1970���A����V�X�e���֘A������3350���ȂǁA�S����5680���ɋy�Ԃ����ł��B
�@����ɁA���f�K�X�����֘A�ƁA�K�X�X�^���h�֘A��70���قǗL��A����͖������Ŗ����J������ƌ����Ă��܂��B
���̏Ռ��I�ȃj���[�X�͍������烉�X�x�K�X�R���x���V�����Z���^�[�ŊJ�Â����CES
�i�R���V���[�}�E�G���N�g���j�N�X�E�V���[�j�ł����\����A��j���[�X�ɂȂ�ł��傤�B
�@���̊J�����ԓ��ɁA���̎����ԃ��[�J��FCV�ւ̎Q���𑣂��āAFCV�s��𑁂������グ�A�����g�傳���悤�Ƃ������̂ŁA����̓g���^��FCV�헪���̂��̂ł��B
�@FCV�̓n�C�u���b�h�ԂƈႢ�A�K�\�����G���W����ς�ł��܂���B�n�C�u���b�h�Ԃ͕����ʂ�A�K�\�����G���W���Ɠd�r�̗������g���A�G���W���ƃ��[�^�̂����Ƃ��������ĎԂ𑖂点��Ƃ������̂ł��BEV�͓d�r�Ń��[�^�݂̂��쓮�͂Ƃ��ĎԂ𑖂点�܂��BEV�͌��݁A�d�r�̎��͂��ǂ��Ȃ����Ƃ͌����A�Ԃ������点��ɂ́A�܂��܂��e�ʕs���ł��B�����Ƃ�������d�r��ςނ��A�d�r�������̗e�ʂ��グ�邩���Ȃ���A�{���̈Ӗ��̎��p�ԂƂ��Ă͎g���Â炢�ł��B
�@��������̓d�r��ς߂Η����ł͉������܂����A�Ԃɐς߂�d�r�̒u���ꏊ��d�ʂɌ��肪����܂��B�܂��R�X�g���o�J�ɂȂ�܂���B
�@�d�r�̈������̏[�d�ʂ�����2�{�A�R�{�ɂł���A���̕����s�������L�т܂��A�܂��͓��������Ȃ�d�r���A1/3�ɂł��܂����A���E���Ń��`���E���C�I���d�r�̗e�ʂ��A�b�v���錤���J��������ɐi�߂��Ă��܂��B�߂������A�����Ƒ�e�ʂ̓d�r����������鎞�オ�K������Ǝv���܂����A����ł�EV�͈�x�[�d���đ���鋗���͓��Y���[�t�ŁA�Q�Q�W�����ƂȂ��Ă��܂��B���ۂ̑��s�ł͂����ƒZ���ł��傤�BEV�ł�����̖��͏[�d�ɗv���鎞�Ԃł��BEV�X�^���h�̍����[�d�ݔ��ł͖�30���قǂŋ�i���S���d�j�̏�Ԃ��疞�[�d�ł��܂����A�ƒ�̂Q�O�OV�i�P���j�d������ł��ƁA�W���Ԃ������邻���ł��B��Ԃɐ[��d�͌_�Ĉ����d�C��ŏ[�d����Ƃ����g�p�@�ɂȂ�ł��傤�B�Ƃ������Ƃ͌����EV�͋ߏ��������x�̎g�����ɓK���Ă��܂����A�ԂŒ������h���C�u�Ƃ����킯�ɂ͕s�������܂Ƃ��܂��B
�@�����ЂƂ̌��_�́A�~�̊��������̒g�[��A�Ă̗�[���g���ƁA���s�������啝�ɒZ���Ȃ�܂��B�����v����M���v�������Ȃ���A�Ԃɏ��Ƃ������Ƃɑς����Ȃ��ł��傤�B
�@���̓_�AFCV��EV�̖����������Ă��܂��B
���f�X�^���h�����A�S���ɔz���ł���A��x�A���f�^���ɂ���ƁA�V�O�OK���قǑ���邻���ł�����A�K�\�����Ԃ�n�C�u���b�h�Ԃƕς��܂���B
�@�܂��A���^���ɂ��鎞�Ԃ͂Q���O��Ƃ������ƂŁA������K�\�����Ɠ��l�ł��B���̓X�^���h���������ł��̂ŁA�ǂ��ł��Ƃ����킯�ɂ͎Q��܂���B�s��n���珇�����������ł��傤�B
�@���f�X�^���h�����݂���̂ɉ����~�Ƃ������������邻���ł�����A���f�X�^���h�����݂���ɂ�FCV�̑䐔�������Ȃ��ƃy�C�ł��܂���B
�@FCV�͐��f�X�^���h���Ȃ��ƎԂ�����Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����悩�A�{���悩�Ƃ����W�����}��Ԃł��B
�@����𑁂���������ɂ́AFCV�ɎQ�悷�郁�[�J�̐��𑝂₵�āAFCV�̔̔��䐔�𑝂₷���Ƃł��B�g���^��FCV�w�~���C�x�����ł͑䐔�������܂��̂ŁA�Q�O�Q�O�N�܂ł�FCV�����p�I�Ȏ����ԂƂ��ĔF�m�����헪���l���āA����̓����̊J���Ɏ������Ǝv���܂��B
�@FCV�����ɂ̎Ԃ��ǂ����ł����AEV�ɂ��傫�ȃ`�����X������܂��B
�@����͐V�����d�r�̊J�����i��ŁA�d�r�̗e�ʂ����̃��`���E���C�I���d�r�̐��{�̏[�d���ł���A�ނ���FCV���EV�����ꂩ��̎����Ԃ̖{���ɂȂ肦�܂��B
�d�r����Ȃ̂ł��B
�@EV�͎����ԂƂ��Ă͈�ԃV���v���ȍ\���ŁA�K�\�����G���W����ςގԂƈႢ�A���i�_����1/10���炢�ɂȂ�܂��B���i�����Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���ɂ������Ƃł����A���i�������͌��I�Ɉ��������\��������Ƃ������Ƃł��B
�@���̏����͂ǂ����Ƃ����܂��ƁA���Ȃ�����̉\���������ƌ����܂��B
���`���E���C�I���d�r�́A���`���E���Ƃ��������̒��ōł��C�I��������₷���i�����x�̍����j���q�ł�����A���`���E���͊�{�I�ɔ��ɓd�r�Ƃ��Ă̔\�͂͗D��Ă��܂��B�A���A���q�������Ă���\�͂��܂��\�����������邱�Ƃ��ł��Ă��܂���B����͗]��ɂ��������������̂ŁA�������`���E���̏�Ԃł͈��S��g���܂���B�����Ń��`���E���̍����̂悤�Ȍ`�œd�r�������Ă��܂��B���̍ޗ��̊J���������e�Ђōs���Ă���i�K�ł��B
�@���Y���[�t�ɂ�Panasonic�̉~���`���`���E���C�I���d�r��ɂ�������Ȃ��Ŏg���Ă��܂��B����ł͊e�Ђ̓d�r�̎��͎͂�����������̏�Ԃł��B�č��̃x���`����Ƃł���e�X����EV��Panasonic�`�����E���C�I���d�r���ʂɐς�łT�O�O�����قǑ���邻���ł��B
�@���܁A�킽�����g���Ă���z���_�A�V�^�t�B�b�g��GS���A�T�o�b�e���[�ƃz���_�̍��ى�Ђł���u���[�G�i�W�[�Ђ������������`���E���C�I���d�r�𓋍ڂ��Ă��܂��B
�ꎞ�A�b��ɂȂ�܂����{�[�C���O�V�W�V�ɍq��@�Ƃ��ď��߂ē��ڂ����d�r�́A��������A�T�n�̃��`���E���C�I���d�r�ł����B���ꂪ����f���ėL���ɂȂ�܂����B
���S��������H�ɂ���Ă����┚�����N����\��������܂��B
�@���`���E���͊����Œn����̖��������ʂ����܂肠��܂���B�܂�����ꏊ��������A��A�����J�Ɍ����Ă��܂��̂ŁA�ʎY���Ă��l�i��������ɂ����Ƃ����ۑ肪���܂Ƃ��܂��B
�@EV����ʂɕ��y���邽�߂̏����͓�ł��B
��͈�x���[�d����ƁA���s�\�������V�O�O�������炢���邱��
��ڂ́A�d�r�̒l�i��������A�Ԏ��͈̂����Ȃ邱�ƁA�Ԃ��Q�O�O�`�R�O�O���~���炢�Ŕ����邱�ƁB
�̓�̏���������܂��B
��ڂ͓d�r���\�̖��ł��B
��ڂ͓d�r�̍ޗ������`���E���ƈႤ�ޗ��ŁA�d�r�̐��\�����̃��`�����C�I���d�r�����e�ʂ��傫�����̂��ł��邱�Ƃł��B
�@���A���������Ă��Ă���ޗ��̓��`���E���ɕς��A�}�O�l�V���E�����g���d�r�ł��B�}�O�l�V���E���͊C���ɖL�x�Ɋ܂܂�Ă��܂��̂ŁA��r�I�����A������ł����o���܂��B�������}�O�l�V���E���͌��q���i���q�j���\�������ԊO�����d�q�̐��j���Q�ŁA���`���E���̂P�ɔ�דd�C�ʂ��{�ɂȂ�܂��B�e�ʂ��{�ɂȂ�\���������Ă��܂��B���̃}�O�l�V���E���d�r�����p�������AEV��FCV�ɏ��Ă鋆�ɂ̖����J�[�ƂȂ�͂��ł��B
�@�A���A���̍ۂ͏[�d���邽�߂̓d�C���ǂ����ē��邩�Ƃ����ۑ肪����܂��B
���q�͔��d�͌�Ɣ�肽���ł�����A���͔��d��A���z�����d��A�n�M���d�Ȃǂł����A����ɐV�����G�l���M�[���Ƃ��āA�R�̎G��R���ɉΗ͔��d����Ƃ��A�~�W���R�i���V�j��r�ő�ʂɔ|�{�������̎悷��Ƃ��A�����ȃA�C�f�A������悤�ł��B
������ɂ��Ă��A���ꂩ��̎ԎЉ�͑傫���l�ς�肵�Ă䂭�Ǝv���܂��B
�V�N���X�ɁA�g���^���Ռ��I�Ȕ��\�������Ƃ����j���[�X�ɂ��Ăł����B
�@ �@�@ �@�@
�@���N�́A�z���_�̃r�W�l�X�W�F�b�g�@�i����j����������܂��B�����S�����ł��傤�B
�S���ɎO�H�d�H�Ƃ��J�����̍��Y�W�F�b�g���q�@MRJ�i�E��j������s���邻���ł��B
�@�������N���N���܂���ˁB |
2014�N11��19���i���j
�A�x�m�~�N�X�̑�R�̖�͉��������̂��H
�@����A��V���߂��Ɉ��{�������L�҉���A���t���U�A���I���\���܂����B���A�^�}��300�c�ȂɒB���鋐��^�}���`�����Ă����ԂŁA��������ς������ȏ�̈��ׂ͂Ȃ��A���ł��ł��鈳�|�I�Ȑ��͂�L���Ă���B
�@
�@���̎����}��������U��I�����邱�Ƃ́A�펯�ł͍l�����Ȃ��Ǝv���Ă����B�I�����āA���ȏ�ɋc�Ȃ𑝂₷�K�v���Ȃ����A���̋c�Ȃŏ\�ł���B
�@����Ȃ̂Ɂw���́A�N���̖Z���������ɁA700���~���̍���i�ŋ��j���₷���I�����s���̂��H�x����̉��U�͑S�������ł��Ȃ��B
�@���̂��Ƃ͂����ȂƂ���ő�����Ă���B
�@����A�L�҉�ň��{�������ǂ������b�����邩���ڂ��Ă������A�v�́A����ł��P�O���ɏグ��̂���N���扄�����Ƃ����߂����Ƃɑ��āA�����̓��ӂ������邩�H��₢�����Ƃ������Ƃ��B���̘b�ɁA��a����������B
�@
�@�������̒��ŁA�������炱�̑��I���̃X���[�K���Ƃ��āw��\�Ȃ����āA�ېłȂ��x�Ƃ����b���������B�S���������������̂�����ɕ�����Ȃ��Ȃ����B���{����͓����ǂ�����̂��A����Ƃ��A������̓��ɗ���͂��Ȃ��̂��H
�@���Ƃ����u��\�Ȃ����ĉېłȂ��v�̓A�����J�Ɨ��푈���̃X���[�K����1�B
�C�M���X�̂�����18���I�����A�ږ������͐ł��ۂ��������ŁA����̑�\���C�M���X�c��ɑI�o���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B����ɔ������A�C�M���X����Ɨ����悤�Ƃ���^���̒��Ő���ɏ�����ꂽ�̂��u��\�Ȃ����ĉېłȂ��v�Ƃ����X���[�K�����B�ږ����炷��A�u�c��̑�\��F�߂Ȃ��̂ɉېł�������ȁv�Ƃ������Ƃ��B�@����Ȃ�悭�����ł���b���I
�@����ł��グ�邱�Ƃɑ��A�����̈ӌ������߂̑I��������Ƃ������ƂȂ痝���ł���B����͋t�ŁA�ŗ����A�b�v���邱�Ƃ�扄�����Ƃɑ��đ��I�����������Ƃ������Ƃł���B
�@
�@�����͏���ł��グ�邱�Ƃɂ͊�{�I�ɏグ�Ă��炢�����Ȃ��Ƃ������ꂾ�B
�Љ���̈ێ���q��Ďx���ȂǁA���ꂩ����̂����錜�ĂɑΉ����邽�߁A����ł��グ��Ƃ������Ƃł���B���������ړI�łƂ��ĂW�����P�O���ɂ���Ƃ����b�ɁA�����������ƂȂ�d���Ȃ��Ȃ��I�Ƃ�����������Ǝv���B
�@����̉��U�A���I���͂��������Ӗ������ł͂Ȃ��A�w����ł��グ��̂�扄������x���Ƃɑ��č����̓��ӂ����Ƃ������ƁB�扄��������A�����̔��͓��ɂȂ��B���{�����߂�����b���I
�@�����700���~�̑���i�ŋ��j�ʌ������鑍�I�����s�����Ƃɑ��A�����ق��̕��ς����v�f������A���̂��߂̑��I�����ƌ��킴��Ȃ��B
�@���{�����̌��͎҂Ƃ��Ă̒n�Ղ��X�Ɍł߂����Ƃ����v�f���A�����̉����A�A�x�m�~�N�X�̎��s�B�����A����̗l�X�ȓ���ۑ�ɑ��A�����}���̔��Δh��}����ׂ��A��l�̑�b�̕s�ˎ��B�����A���X�̉ۑ�����̓��ɓE�ݎ���Ă����A�V�����������č\�z�������A�����̓��t�x���������Ƃ����Ȃ����̊ԂɑI�����āA�����̐M�C���Ƃ������т���肽���̂��낤�B
�@�A�x�m�~�N�X�ɂ��āA����̋L�҉�ł́A�i�C�A�ٗp�̉��P�A�����̏㏸�A��Ɨ��v�̊g��A�����̏㏸�Ȃǂ��グ�āA���̐��ʂ����������B
�@�m���ɁA�b���ꂽ���ڂ͉��P�A�܂��͗lj����Ă���B
�@�������A�����̍��ڂ͍����̋ɂ��ꕔ�̐l�ɉv�������炷���̂ŁA�t�ɑ命���̐l�͈������Ă���̂ł͂Ȃ����H
�@�A�x�m�~�N�X�Œ��~������~���֗U���ɐ��������ƌ���ꂽ�B�m���ɂV�U�~�O�サ�Ă����~���́A�P�P�T�~�O��̉~���ɂȂ����B
�@�]���ł���A���̃��[�g�Ȃ�A�o�Y�Ƃ̑�\�������d�C�⎩���ԂȂǂ̓��{�����ӂƂ��Ă����A�o�Y�Ƃ͗A�o����傫���L���͂����B
�@�Ƃ��낪���̉~���ɂ��ւ�炸�A�A�o���v�����قǑ傫���L�тĂ��Ȃ��B�t�ɗA�����錴�ޗ��̉��i�͏オ��A���ɒ�����Ƃ��g�������ނ��傫���㏸���Ă���B������Ƃ͐��i�╔�i����Ƃɔ[������B���̉��i�͗}�����Ă���̂ŁA������Ƃ͎��x���������A��w�ꂵ�����f���̏�ԂɂȂ��Ă���B
�@�����͑傫���㏸�������A���̉��b����l�͂ق�̈ꕔ�̐l�ŁA�命���̐l�͊W���Ȃ��B�����l����ƁA���̂܂ܐ������ێ���������ƁA�A�x�m�~�N�X�̕��̖ʂ��\�ʉ����A��ς܂������ƂɂȂ�B
�@�����Ȃ�O�Ɉ�x�A�A�x�m�~�N�X�̃��b�L��������Ȃ��O�ɁA��x���Z�b�g���Ă������Ƃ������Ƃ�������Ȃ��B
�@���Ƃ͊�ƌ��ł�~���ŗ��v���ߋ��ő�Ƃ�����Ђ��o�Ă����B�C�O���玝���A�鎖�Ǝ��v�������A�A�o�������A�ō��v���o���Ă���Ƃ��낪��R�o�Ă����B�������A������S���ł͂Ȃ��A�ꕔ�̑��Ƃł���B
�@�Ƃ���ŁA�A�x�m�~�N�X�͂R�{�̖�Ő��藧���Ă���ƌ����Ă���B
�ł���B
�@��{�ڂ̖�͑�_�ȋ��Z����B���₪����Ԃ���Ԏ����s���āA�����̉��l�������鐭������Ƃ������ƁB��������Ɖ~�̉��l��������A�f�t������C���t���̕����ɐU���B�f�t���E�p�̕��B
�@
�@��ڂ̖�͋@���I�ȍ�������B��K�͂����������i���y���Չ��j���s���B
�����{��k�Ђ̔�Вn�ōs���Ă����K�͂Ȍ������ƂȂǂ́A�[�l�R���ɂ��̂��������𓊂��A���ߗ��Ă�A�����グ�ȂǁA���k�̑f���炵���C�ݐ��̌i�F���ς���Ă��܂��悤�ȍH����i�߂Ă���B
�@���̓�i�Q�{�̖�j�͍��܂ł̕s����ł�����Ă�������Ƒ傫�ȈႢ�͂Ȃ��B��{�̖����_�ȋ��Z�����Ə����Ă��邪�A����̍��c���ق��َ����̋��Z�ɘa���ƌ����Ă���B����������Ԃ���Ԃǂ���łȂ��A���ꗬ����������Ȃ��B���̌��ʂ��A�~����U�����Ă���̂ł���B
�@���R�A����Ԃ���Ԕ��s���������̂��́A�����̍����Č��ɕ��S��������B
�@���ꂾ���̑�_�Ȑ����ł��Ă��Ă��A�i�C���ǂ��Ȃ����Ƃ����������Ȃ��B
�����͎g�����A���Ƃ������A�������A�i�C�͎v�����悤�ɉ��Ȃ��B
�@��������ȏ�A��̑ł��悤���Ȃ��Ƃ����̂����Ԃł͂Ȃ����H
�@����͓��{�����ɐ��n�������Љ�ɂȂ����Ƃ������Ƃ��Ǝv���B
��҂͂��������A�H���H���Ƃ���������ł��H�ׂ��邵�A�̂��܂��܂������ɂȂ�B���{�͂��������N��ł͂Ȃ��Ȃ������Ƃ��Ӗ�����B
�@��X�͍��̗͔̑N��ɉ������H�������A�N��ɉ������g���[�j���O���āA�ؓ����Ȍ��N�ȑ̎������グ�邱�Ƃ���ŁA���������{������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@����ɂ́A���܂œ��{�����W�r��łƂ��Ă������������A���Z�����A�������Ƃւ̓����ƈႤ���������Ȃ��ƃ_���Ȃ낤�B
�@����͎O�ڂ̖�ł��鐬����͂���ԏd�v�ł����B
�������A���ꂪ��ԓ�����Ƃ��B����A���{��A������A����ł����琬���헪�͂�������Ƃ������Ƃ����߂Ă��A���܂ł̂����ł͂����ʂ��Ȃ�����ɂȂ��Ă���B���̂��Ƃɑ����C�Â��K�v������B����Ɏ��g�ނ͖̂��Ԋ�Ƃł���B
�����哱�ŁA�w������A������x�Ƃ����Ă��A���Ԃ͕K�����������Ȃ��B
���������Ďx�����Ă��A�����͊m���ɏo�Ă䂭�����ʂɂȂ���Ȃ��B
��3�̖�A�����헪�𐬌��������̍�͉����H
�@���������ڂ��镪��́A�_�ƁA�ό��ƁA�G�l���M�[�Y�����グ�����B
�@
�@�܂��A�_���́A���{�̐H�ނ͐��E��ł��邱�Ƃ͊C�O���s����Ε�����B���{�̉ʕ��̔��������A���̗ǂ��A�����ڂ��Y�킳�A�傫���ȂǁA�ǂ���Ƃ��Ă��A���E�ꂾ�B������_���g�c�̈�ŁA���ɔ�ׂ��鍑�͂Ȃ��B����قǓ��{�̉ʕ��͑f���炵���B���܂ŗA�o�Ƃ����A�d�C���i�⎩���ԂȂǍH�Ɛ��i���肪�ڗ������B���̍\����ς��āA�_�Y���̗A�o�ɓ��ݐ�K�v������B
�@�_�Y�i�̗A�o�𐭕{������������Đi�߂Ă���Ƃ������Ƃ������Ƃ��Ȃ��B
�@�R���_�Ƃ̏����⏞���葛����āA�_�Ƃ̈�[��~�������Ă���n���c���̎p�������B�ꂷ��B
�@���{�����Ⴕ���o��̂Ȃ�A���������_�Y�i�̕���Ŏ��R�ɗA�o���ł���㉟������������B
�@���ꂪ�Ȃ��Ȃ�����B�_�Y���͑S�Đ��N�H���i�Ȃ̂ŁA���n���Ă����o�ׂ��A�A�����āA�C�O�̓X���ɕ��ׂ���܂ŁA�����z�B�ł���V�X�e����C���t�����\�z���邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�B
�@���O���i���{�����������j�͐H���i�ɂ͂����ȋK�����|�����Ă���̂ŁA����𐭕{���m�ł��݂����b�������A�����i���q�l�j�̂��߂ɂȂ邱�Ƃ����M�������Č㉟�����A�ۑ�̉��������邱�Ƃ���B
�@�Ƃ��낪�A�e�Ȓ��̌��v��꒣��ŁA�K����������Ȃ��Ȃ������Ȃ��B
��R�̖�𐬌������邽�߂ɂ́A�e�Ȓ��̋K����꒣���c����s�����Ȃ������ƂɎ��g�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@��}�A����}�͂��̂��Ƃɒ��ڂ���A�Ȃ��Ȃ��������g�݂��ł���̂����A�����̒�R���������B��������z���Ȃ��Ɠ��{�̏����͂Ȃ��Ǝv���B
�@�H�Ƃ̗͂�����ɋ�������K�v�͂���B���܂œ��{�͍H�ƍ��Ƃ��Đ��i��A�o���Ă����B�ʎY�i�̗A�o�͒����͂��ߔ��W�r�㍑�ɔC�������B���{�͊��ɁA��������C�O�ɍH��i�o���Ă���̂ŁA���n��Ђ̍H��ŗʎY�i�͍������B
�@���{�����ō�鐻�i�╔�i��ޗ��́A�t�����l�̍������́A�C�O�H��ł͐��Y�ł��Ȃ��悤�Ȃ��̂ɍi�邱�Ƃ�����B
�@�Ⴆ�A�������{�[�C���O����P���~�Ƃ�������Ȋz�������Y�f�@�ۂ̂悤�Ȃ��́B�|�S�̂P�O�{�̋����ł���Ȃ���A�y����1/4�Ƃ����n�C�e�N�@�ہB
��s�@�̓��̂Ȃǂɂ͑ł��ĕt���̍ޗ����B
�@���Ɋό��Y�Ƃ����Ȃ��Ƃ�5�{���炢�ɐL�����ƁB
�Q�O�P�S�N�x�͈ȑO�ɔ�ׂė�������ό��q�͑傫���L�т��B����1000���l���āA���N�x��1300���l�ɂȂ�Ɨ\�z����Ă���B��ό��\�Ȃ��Ƃ��B
�L�т����R�́A����A�W�A���痈�����₷���悤�ȃr�U�̔����̊ɘa��A�i���q��@LCC�����y�������Ƃ�A�H�c���̓w�͂�����B
�������A���E�e���̊ό��q�̐l��������ƁA2013�N�x�̏W�v������ƁA�P�ʂ��t�����X�łW�T�O�O���l�A�Q�ʂ��A�����J�łV�O�O�O���l�A�R�ʂ��X�y�C����6070���l�A4�ʂ�������5570���l�A5�ʂ��C�^���A��4800���l�ƂȂ��Ă���B���{�͂P�O�O�O���l���B�؍��ł���A1217���l��22�ʁA���{��27�ʂɊÂĂ���B
�@���{�����́A�o������l�������̂ɗ�������l�͏��Ȃ��̂��H
���{�ɂ͑f���炵���ό���������������B���j�I�����A����A�C�A�R�A���{�̕��i�͔���̂悤�Ȍi�F�ł���B�����đ����ɗ�邱�Ƃ͂Ȃ��B���܂Ő��{���ό��ɖ{�C�Ŏ��g��ł��Ȃ��������߂��B
�@�O���l���Ăъ邽�߂ɂ́A����Ȃ�̐ݔ��A�C���t����p�ӂ���K�v������B�ŋߑ啪�ǂ��Ȃ��Ă������A�܂��܂��s�\�����B
�@��������ԁA�C�ɂȂ��Ă���_�́A���{�̌i�F��䖳���ɂ��Ă���d���Ɠd�����B�ό��n�ł��������ꕔ�̒n��͒n���P�[�u���ɂ��āA���d�������������Ă���B�ߗׂł͋��s�̓����t�߂������Ȃ��Ă���B���ɂ������肵�Ď��͂̌i�F�������邵�A�������ʐ^���B�����ۂɓd�����f��Ȃ��̂ő�όi�ς��悭�Ȃ�B
�@������A�ό����Ɖ��P�E���i��Ƃ��āA���������d�����ɐU�������Ă��Ă���B���������Ă����A�O�����炽������̐l������ɑ�����B�C�O�ł͖��d�����͓�����O�ɂȂ��Ă���B�c�ɂ̔_�Ƃ�����ł���悤�ȏꏊ�́A�]���̂܂܂ł��ǂ����A�ό��n��l����R�W�܂�ꏊ�͎��}�A���d�����ɂ��ׂ����B���{�̓d���͓d�C�̑��z�d���i�������ƒሳ���j���㉺�ɒ��菄�炳��Ă���B����ɓd�b������P�[�u���⓯���P�[�u�������̉��ɓ\���Ă���̂ŁA�{���Ɍ��ꂵ���B
�������A�l�Ԃ͖��������i�F�����Ă���Ɖ��������Ȃ��B�C�O�̓s�s��ό��n�ɂ䂯�A�d���͂Ȃ��̂ł������肵���i�ςɂȂ��Ă���B����ɂ��������ꏊ�͊Ŕ⒣�莆���Ȃ��������B
�@���{�͂₽��ƊŔ𗧂Ă�ȁH������B�̂ڂ���⒣�莆��l�I���T�C����
���ʂ̊ŔȂǂŖ��ߐs�����ꂽ����������B������Ŕ��ǂꂾ����`�L���ɖ𗧂��Ă���̂��Ǝv���ƁA�Ȃ��Ă����܂蔄��ɉe���͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@���āA3�{�ڂ̖�̍Ō�̓G�l���M�[�Y�Ƃ��B
���{����͌����̍ĉғ���I���̌���ɓ���邾�낤�B�{���ɓ��{�Ō����������Ƃ����S���H����͒N���ۏ��悤���Ȃ���肾�B
�@���������邱�Ƃ́A���E�ꌵ�������S������A����Ō������č��i������̌����͍ĉғ����Ă��ǂ��A���{�̂��n�t��������Ƃ������ƁB
�@���̌������͐������悤�ɂ������邪�A���͐�Έ��S�̕ۏ͉����Ȃ��B
���E�ꌵ�������S���������B����͊���������Ƃ����Ӗ��ł͑S�����͂Ȃ��B���̒ʂ肾�B������������A���̌����������͒n�k���A�ΎR�����{�ō�����S���ƌ����A���S�ɔz�������ƌ����Ă��A���S���ƌ�����Ȃ��B
�@�����͐�Έ��S�łȂ���Γ������Ă̓_���ȃC���t�����B
��s�@�͕K��������B��s���x�Ŕ�������g�́i���́j�Ǝ��d���o�����X���Ă���̂ŁA���i�͗����邱�Ƃ͂Ȃ��B�������A�G���W�����~�܂�ΕK��������B�������A���ꂪ���Ȃ�A��s�@�ɏ��Ȃ�������B�����̑I�����ł��A���ȐӔC�ŏ������A���Ȃ�������I���ł���B
�@�����͉ғ��̑I���͍����̑��ӂ��K�v���B
���x�̑��I���ŁA�������{�����ĂA�S���̌����͎���ɍĉғ����n�߂�B
�����Ŕ���������ː��p�����̏���������܂��Ă��Ȃ��̂ɂł���B
�@���{�̈��S�ȃG�l���M�[�������{�̗D�ꂽ�Z�p�ŊJ�����A����𐢊E�ɔ��邱�Ƃ��l����A�V����3�{�ڂ̖�Ɉ�Ă邱�Ƃ��o����B
�@�����������Ƃ�����ɂ́A�����ƂƊ����ƁA�����������Ă���K���ɘa�𑁂����A�����̏c����g�D��ׂ��āA�V��������̐��{�A������K�v������B
�����}�Ɋ��҂����̂����A�S���_���������B
�@�����}�͋K���̐��̒��ɐ�����}������S�����҂ł��Ȃ��B
�ǂ����A�����������ړ_�ŁA���I���ɑi����}�����҂������B
|
2014�N11��12���i���j
���{�̖f�Վ��x�͂ǂ��Ȃ��Ă���́H
�@����A���N�㔼���i�S��-�X���j�̖f�Վ��x�����\�ɂȂ�܂����B
���{�͖f�����Ƃ��āA���܂܂Ŕ��W���Ă��܂����B�]�˂��疾���ېV�̍��Ɍf�����w�x�������E�B�Y���Ɓx��������ɁA�B�Y���Ƃ͖f�Ղ𑝂₷���ƂŊO�݂̊l����ڎw���܂����B
�@
�@�������A�����͌����̖a�эH��A�����ĖȉԂ̖a�эH�Ƃ��撣���āA�Q�n���̐��E��Y�ɂȂ����x�������H��ɑ�\�����w���{�̌��x�����������A�����J�ɗA�o���A�傫�ȗ��v���グ�܂����B���̌�A���S�Ȃǂ̏d�H�Ƃɗ͂����A����ɋ���������Ƃ�A���Ȃ��A��肪�����Ă��钆���Ⓦ��A�W�A�ւ̔h���Ɍq����܂����B
�@
�@�����āA�����m�푈�ɕ����A���a��`���f�����a�Y�Ƃ̖f�Ղ�ʂ��Đ��E���̌o�ϑ卑�ɂȂ�܂����B
�@
�@���̌�A�����̋}���Ȕ��W�ɂ��A�A�����J�A�����A���{�ƁA���E�����L���O��������܂������A���ς�炸���{�͐��E�̌o�ϑ卑�ł��鎖���͕ς��܂���B
�@
�@�������A�O���[�o�������i�݁A���E�o�ς���������A���Z�̎��R���Ő��E�̋��Z���l�b�g��Ō��ς���A�u���ɋ��z�̃J�l�����E�����삯����Ƃ����l�����Ȃ��悤�Ȏd�g�݂ɕς��܂����B
�@���m�̐����́w�f�W�^�����̂Â���x�Ƃ������t�������Ƃ���A���܂ł̂��̂Â���̐������ꂩ��傫���l�ς�肵�܂����B
�@���̑�\�I�Ȏ��������Љ�܂��B
�@������邽�߂ɂ́w���^�x���K�v�ł��B������20�N����30�N�قǑO�͋��^������Ƃ������Ǝ҂����܂����B�܂����i��@�B���̐v�҂��v���A�����v�}�ʂɏ����A�v�}�����^���ɓn���āA���^������͋��^�����ׂ̐}�ʂɏ��������܂����B��������^�}�ʂƌ����܂����B���^�Ƃ͋����̉�A���i�̕��i��������`�i�������̂ŁA���̂��߂̋��^���@��o���Ƃ�����Ƃ����܂����B
�@�����̍�Ƃ͐l�Ԃ���邱�Ƃł�����~�X�������̂ŁA�v�~�X��A���}�~�X��A���^�}�ʃ~�X��A���^�̍�ƃ~�X���A���^�������Ă������ȍH���Ń~�X�������邱�Ƃ���ł����B�����璍�ӂ��Ď��g��ł��A���������l�דI�ȃ~�X�̓[���ɂ͂Ȃ�܂���ł����B�~�X��Ƃ����тɁA�C������K�v�������A���̓s�x�A�����Ȏ��Ԃ�������܂����B
�@�V����������^���v�̎v���ǂ���ɏo���オ��A������g���Đ��`�i������i���ł���܂ŏ��Ȃ��Ă�1������1�����قǂ�����܂����B
�@
�@���ꂪ���A�ǂ��Ȃ��Ă��邩�Ɛ\���܂��ƁA�v�}�����ɏ����̂͊F���ł��B
�R���s���[�^���g���v��i�߂܂��B�����CAD�ƌĂ�ł��܂����A�R���s���[�^�͐v��A�ԈႢ������A�u���������������ł���v�ƁA�f�B�X�v���C��ɕ\�����o�āA�v�҂ɒm�点�Ă���܂��B
�@CAD�Őv�������^�}��CAE�ƌ�����v���O������ʂ����ƂŁA�o���オ��̕��i�����i�ɑg�ݗ��ĂĂĉ��Ȃ����A���������@�������Ă��邩�A�����Ȗʂ���V���~���[�V�����ł��܂��B
�@���^��O�Ƀ~�X��v��̖��_��������A�Ώ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�@���`�i�Ȃ�A���������^�ɗ������ލۂɗn�����������̗�����܂ŃV���~���[�V�����ł��܂��B����̗���ƌĂ�ł��܂����A���܂����i�⏤�i���o���オ�邩�ǂ������`�F�b�N�ł���̂ł��B���i�̊O�ςɎg�����i�Ȃ�A�\�ʂ����ꂢ�Ɏd�オ�邩�ǂ����܂ŕ�����܂��B�����������̂Â��肪�ł��鎞��ɂȂ�܂����B
�@���^����x����Ă݂āA���ۂɎg���ĕ��i�⏤�i������Ă݂āA�]�����āA����ɏC����������Ƃ�����肩���A�C���̎�Ԃ⎞�Ԃ��Ȃ��Ȃ�܂����B���R�A���̕��A�R�X�g��������܂��B
�@�������v�}�i���^�}�j�͑S�ăf�[�^������Ă��܂��̂ŁA�}�ʂƂ��Ď��Ƀv�����g�������̂ł͂Ȃ��A�f�W�^���M���ł��B
�@�ł�����A���̃f�[�^�̓C���^�[�l�b�g�œ��{����C�O�̂ǂ̍��̍H��ɂ��A���M�{�^��������Ώu���ɑ��邱�Ƃ��ł��܂��B���̃f�[�^����M�����C�O�̍H��́A���^�̐؍�@�Ƀf�[�^���C���v�b�g����Ύ����I�ɐ؍��Ƃ��n�܂�A���^�����܂Ŏ����łł���̂ł��B
�@�����������Y�@�B�V�X�e�����C�O�H��ɐݒu����Ă��邱�Ƃ��O��ł����A���{�̊�Ƃ͊C�O�i�o����ۂ́A���Y�@�B��H��Ŏg���@�B�������Ɏ����o���Ă��܂��B
�@�����Ȃ�A�l����������{�����ő���K�v�͂Ȃ��Ȃ�܂��B�H��͂ǂ�ǂ�C�O�ɃV�t�g���܂��B���ꂪ����̎p�ł��B
�@�@
�@�����Ȃ�A�~�h�����[�g���ϓ����Ă��A�����ȒP�ɍH����C�O���獑���Ɉړ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ�܂��B��x�ݔ����ړ]���܂��ƁA���ɖ߂��ɂ͂�����������܂����A�����m�E�n�E���ړ�����K�v������A�����ȒP�ɂ͎Q��܂���B
�@
�@���A�w�A�x�m�~�N�X���ʁH�x�ŁA�l�����Ȃ��悤�ȉ~���ɂȂ�A�ꎞ�V�O�~���������~������115�~�O��܂ʼn�����܂����B
�~����100�~�܂ł䂭�ƁA���{�ׂ͖���ƌ����Ă��܂����B�����ꂪ�����̎p�ɂȂ��Ă��܂����A�����Ă����悤�ɖf�Վ��x���ǂ��Ȃ�܂���B
�@
�@�C�O���s�́A���{�ɗ���ꍇ�͑�ϊ�������Ԃł��B�t�ɏo������ꍇ�͑�ς�����������܂����A�s�v�c�Ȃ��ƂɁA���{����o������C�O���s�̒l�i���v�������オ���Ă��܂���B
�@�����������̒��ŁA����̖f�Վ��x�͉��L�̂Ƃ���ł����B
| 2014�N�x����i�S���`�X���j |
| ���@�� |
���@�z |
�����z |
|
| �A�o�z |
36��1,668���~ |
1��8,959���~�� |
5.5���� |
| �A���z |
40��5,641���~ |
2��5,415���~�� |
6.7���� |
| �f�Վ��x |
4��3,974���~ |
�@�@6,456���~�� |
|
| �o����x |
2���@239���~ |
1��571���~�� |
|
�@��\�̂悤�ɖf�Տ�̎��x�́A�S���~�]��̐Ԏ��ł����B
����́A�Η͔��d�p��LNG��ΒY���̗A���̑�������ȗv���Ƃ���Ă��܂��B
�������ғ���~���Ă���̂ŁA�G�l���M�[�R�X�g��������A�f�Վ��x�͐Ԏ��ł���Ƃ������Ƃł��B������u�����������ĉғ������āA�f�Վ��x�̉��P��}�肽���v�Ƃ����_���������܂��B
�@�������A1�h�����P1�T�~�ɂ��~���ɂȂ�ƁA�{���Ȃ���{����̗A�o���傫���L�тȂ���Θb�����������Ȃ�܂��B�A���̌��ޗ��̃R�X�g�͓��R������܂����A���������A�o�̐L�т��Ȃ���Ȃ�܂��A�Q���~�サ���L�тĂ��Ȃ��̂ł��B
�@���̗��R���悭���͂���K�v������܂��ˁB
�@����́A�����ԎY�Ƃ�d�@�Y�Ƃƌ��������܂œ��{�̗A�o���x���Ă����劲�Y�Ƃ����ɊC�O�ɍH����ڂ������ʁA���{�����Ő�������ʂ������Ă��邽�߉~���ŗA�o���悤�ɂ������ō���ʂ����Ȃ��āA�A�o�ɐU������鏤�i�����������Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B
�@����A�o����x������ƁA2���~���x�̍����ɂȂ��Ă��܂��B���̌o����x�Ƃ́A�f�Վ��x�ɊC�O�ɐi�o�����H���X�܂Ȃǂ��炠���闘�v��m�E�n�E���Ȃǂ̎����A�蕪���������������x�ł��B
�@���{�͏�̂悤�ɗA�o�E�A���̌��ς���������ΐԎ��ɂȂ��Ă��܂����A�H���X�܂̊C�O�i�o��ړ]��i�߂����ʁA�C�O���Ə����e���ɖׂ����Ҍ����Ă���Ă���̂ł��B
�@���������Ӗ��ŁA�O���[�o�������i��ŁA�~�h�����[�g�̏㉺�̕ϓ������܂����������Ă���Ă���̂ł��B
�@���{��������l�������A��l�ׂ���Ƃ����l�����͗ǂ��Ȃ��Ǝv���܂��B���{�͔��W�r�㍑�ɍH������A�����Ō��n�̌ٗp���m�ۂ��A���̍��̌o�ϐ����𑣂��A���W�r�㍑�̌o�ςɍv�����A�e���ɂ��z�����𑗂����Ƃ���܂ŗ��Ă���Ƃ������Ƃł��B
�@�������ғ����Ă��Ȃ�����A������LNG�̗A������������݁A������G�l���M�[�R�X�g���オ���ĎY�ƊE���ꂵ���Ƃ����V�i���I�͊ԈႢ�ł͂���܂��A����ł͖f�Վ��x�̐Ԏ��������ɂ��Č����̍ĉғ��𑁂��������Ƃ����v�f�����������ł��B
�@�����ł͂Ȃ��A���������ł����A���{�͌������̂����P�ɂ��āA���E�ɐ�s����V�����G�l���M�[�̑n���A���ɂ₳�����n������邱�Ƃɗ��悵�Ď��g�݂܂��Ƃ����ڕW��N���ɑł��o���ׂ��ł��B�B���̎���̐����ł��o�����Ƃ��d�v�ł��B
�@�Y�ƊE�͍������邱�Ƃ���ł�����A�ǂ����Ă����߂̉ۑ�ɑΉ����悤�Ƃ��܂��B�����͎��̐V��������������������g�݂����������̂ł��B
�@�N���̉��U�A���I����������n�߂܂����B
�Ȃ��A���ܑ��I���Ȃ̂��A�悭�����ł��܂��A�����̓}����ԗL���ɐ킦��^�C�~���O���O�����ɑI�����邱�Ƃ��A�ނ�ɂ͈�ԏd�v�Ȃ��ƂȂ�ł��傤�ˁB
�@�����͂ǂ��ɍs���Ă��܂��Ă���̂ł��傤�H
���ɂ͓V�����Ƃ̂��߁A�����̂��߂ƃz���𐁂��l�����ł����E�E�E�E�B
|
2014�N11��8���i�y�j
�ɐ��R�̍g�t�����Ă��܂����B
�@����A���������܂ʼn��\��ځH���̒a�������}���A�V�C���ǂ������̂ŁA�v���Ԃ�Ɉɐ��R�̍g�t�����ɍs���܂����B
�@
�@�����O�ɁA�����V���Ɉɐ��R�i�W��1,377���j�̍g�t�̎ʐ^���f�ڂ���Ă��āA�Y��ɍg�t���Ă��܂����̂ŁA�w�������ȁH�x�Ǝv���A���ˋ����o�C�p�X�˖��_�����Ə��p���A�փ���IC�ō~��āA��ʓ��H���Q�������葖��ƁA�S��17�������ɐ��h���C�u�E�F�C�ɓ���܂��B�����͏t����H�܂ł̊ԁA�J�Ƃ��Ă��܂����A�ɐ��R�͐Ⴊ�[���ē~��͕�����܂��B
�@�ɐ��R�ɂ͂����Ԃŏo�����܂����A���̗L���h���C�u�E�F�C�͌��\�����������āA�R�O�X�O�~�i�����j���܂��B
�@
�@���āA������t�߂͂܂��g�t���n�܂��Ă��܂���ł����B�r���őҔ��ꏊ����������L��A�ԍ���U���Ă��܂����A15�ԁ`20�Ԃ��炢�܂ł̊Ԃ������ł����B
�@�R���̒��ԏꂩ�猩���낷�ƁA���ɓ~�i�F�Ŏ��̗t�͂Ȃ��A�V���Ԃł����B
�@���̒��ԏꂩ��R���܂ł̃n�C�L���O�R�[�X�͍��͕����l�����Ȃ��A���\���������āA�C����9���ł����̂ŁA�����̂͂�߂ĎԂ̒��Œ��H���Ƃ艺��n�߂܂����B
�@
�@�r���A���ӏ����ŎԂ��~�߂Ďʐ^���B��܂����̂ŁA�A�b�v���܂��B
���̎��A�Ȃ�Ɩ{���́w�L�c�l�x������܂����B�Ԃɋ߂Â��Ă��āA�����J���Ă������܂���B�悭�l�ɂȂ����L�c�l�łт����肵�܂����B
�@
�@���[�ɂ́w�N�}�ɒ��Ӂx�Ƃ����Ŕ�����A�ɐ��R�������������������������悤�ɂȂ����悤�ł��B
�@
�@�A��͎��Ԃ��������̂ŁA��ʓ��H�i�W�����j���Õt�߂܂ő���A�����o�C�p�X�ɏ���ċA���Ă��܂����B
�@
�@�g�t�̊��z�́H�H
�@�����ɍs�������ɂ́A�w�������g�t���Ȃ��I�x�Ƃ������������Y��ȍg�t�ł͂Ȃ������悤�Ɏv���܂��B
�@��N�H�A�J�i�_�̃��C�v���A���i�J�G�f�j�̍g�t�͐^���ԂŐF�N�₩�Ȑ��݂̂���g�t�ł����B
�@���������i�F�̏ꏊ�͑S���Ȃ��A���F�ƗƁA���X�ɏ��X�Ԃ��F�̃n�[�̖H��������x�ŁA�������A�g�t�͌͗t�̂悤�Ȓ��F���ۂ��F�����ŁA�Y��ɍg�t���Ă���Ƃ��������ł͂���܂���ł����B
�@�͂����茾���āA���܂肨�����߂ł��Ȃ��悤�Ȉ�ۂł����B�i�����ł��j�B
���ꂩ��ǂ��Y��ɍg�t���邩������܂��A����̒i�K�ł͂��������i�F�����Ă��܂����B
�@ �@�R������̒��] �@�R������̒��]
�@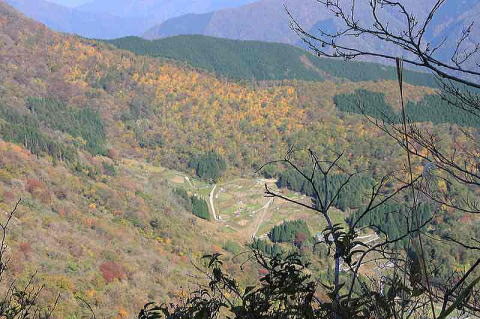 �@�r���̍g�t �@�r���̍g�t
�@ �@�X�X�L�ƍg�t �@�X�X�L�ƍg�t
�@ �@�r���̍L�� �@�r���̍L��
�@ �@�ό��o�X�Ƃ��ꂿ���� �@�ό��o�X�Ƃ��ꂿ����
�@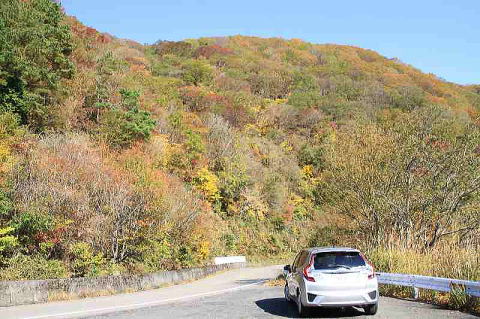 �@�}�C�J�[�ƍg�t �@�}�C�J�[�ƍg�t
�@ �@�@ �@�@
�@�@�@�@�@�@�삯���L�c�l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ԃ̉��ɗ��ĐH�ו����˂����Ă���
|
2014�N11��5���i���j
���̊ۂ̗����������ї��Ƃ��Ƃ��Ă��܂��B
�@YS-11���ޖ����ċv�����ł����A ���̌�A�u���W���̃G���u���G����A�J�i�_���̃{���o���f�B�A�Ƃ����v���y���@���������[�J����H����ł��܂��B
�@�@�݂肵���̗E�p�@�@YS-11_Aoki-11.jpg) �ŋ߁A��s�@�ɂ͊C�O���s����Ƃ��ȊO�͂قƂ�Ǐ��Ȃ��Ȃ�܂����̂ŁA�ڂ������Ƃ͕�����܂��A�v���y���@�͔�s���x���Ⴂ�̂ŁA�V��ɍ��E����āA�ӂ�ӂ�Ə㉺�ɗh��ċC���������Ȃ�悤�Ȃ��Ƃ��������̂��o���Ă��܂��B �ŋ߁A��s�@�ɂ͊C�O���s����Ƃ��ȊO�͂قƂ�Ǐ��Ȃ��Ȃ�܂����̂ŁA�ڂ������Ƃ͕�����܂��A�v���y���@�͔�s���x���Ⴂ�̂ŁA�V��ɍ��E����āA�ӂ�ӂ�Ə㉺�ɗh��ċC���������Ȃ�悤�Ȃ��Ƃ��������̂��o���Ă��܂��B
�@
�@YS-11�̃G���W���̓W�F�b�g�G���W���ł����B
�W�F�b�g�G���W���ɂ͂Q��ނ���A�r�C�K�X�Ń^�[�r�����A���̎��Ƀv���y�������t�����̂��^�[�{�v���b�v�W�F�b�g�G���W���ƌ�������́B���݂̃v���y���@�͂��̍\���̃G���W���𓋍ڂ��Ă��܂��B
�@
�@������̃W�F�b�g�G���W���͍����E�����R�ăK�X���㕔�ɐ����o�����ƂŐ��i�͂Ă��܂��B�^�[�{�t�@���W�F�b�g�G���W���ƌĂ�Ă��܂��B�z���_�̏��^�r�W�l�X�W�F�b�g�@���^�[�{�t�@���W�F�b�g�G���W���𓋍ڂ��Ă��܂��B�^�[�{�t�@���W�F�b�g�@�͍����Ŕ�ׂ�Ƃ������_������܂��B
�@
�@�Ƃ���ŁA�����q�����Ƃ𐭕{�̊̂����NEDO���㉟�����A�O�H�d�H�Ƃ���̂ɂȂ�A�x�m�d�H�ƁA���{�q��@�J������Ȃǂ̋��͂Ői�߂��Ă���̂��AMRJ(�O�H���[�W���i���W�F�b�g�j�ƌ����钆�����W�F�b�g���q�@�ł��B�@���Ȑ��͂V�O�`�X�O�ȁB
�@�@�X�}�[�g�ŐV��������̌`�Ɍ�����MRJ �n�u��`�ƃ��[�J����`�����ԘH���́A����ɉ���ƂȂ����������J��Ԃ��܂��̂ŁA���̓x�ɋ@�̂ɋ����Ռ��������A�\���I�ɂ��̏Ռ��ɑς��Ȃ���Ȃ�܂���B �n�u��`�ƃ��[�J����`�����ԘH���́A����ɉ���ƂȂ����������J��Ԃ��܂��̂ŁA���̓x�ɋ@�̂ɋ����Ռ��������A�\���I�ɂ��̏Ռ��ɑς��Ȃ���Ȃ�܂���B
�@MRJ�͓����A�@�̂��y�����邽�߂ɒY�f�@�ۑf�ނ��g���v�悾���������ł����A�ŏI�I�ɂ͎��т�����A���~�����Ɍ��܂����悤�ł��B
�@���{�̍q��@�Y�Ƃ̓A�����J�̃{�[�C���O�Ђ̐V�s�@B787�̋@�̂ɒY�f�@�ۂ̓��̂�A�o���Ă��܂��̂ŁA�Z�p�̖͂��͑S���Ȃ��Ǝv���܂��B
�@���Ȃ݂ɁA�z���_�̃r�W�l�X�W�F�b�g�͒Y�f�@�ۑf�ނ̂Ɏg���Ă��܂��B
���c�Ȃ͐V�����̂悤�ȃC���[�W�H�@MRJ
 �q��@�͎����ԂƓ��l�A�����ɋ@�̂��y�����邩����R��ɒ������܂��B����ƁA�G���W���̉��P�ł��BMRJ�͍������A�ȔR����ꂽ�v���b�g���z�C�b�g�j�[�i�J�i�_�j���̃W�F�b�g�G���W���𓋍ڂ���悤�ł��B �q��@�͎����ԂƓ��l�A�����ɋ@�̂��y�����邩����R��ɒ������܂��B����ƁA�G���W���̉��P�ł��BMRJ�͍������A�ȔR����ꂽ�v���b�g���z�C�b�g�j�[�i�J�i�_�j���̃W�F�b�g�G���W���𓋍ڂ���悤�ł��B
�@�����̏A�q�\�肩��J�����傫�����ꍞ��ŁA����A�����@������I�ڂ����Ƃ���ŁA����s�͗��N�ȍ~�ɂȂ�܂��B���̌�A�P�N��2�N�����Č^���F����擾���A�[���J�n����܂��B
�@������ɂ��Ă��A�z���_���^�r�W�l�X�W�F�b�g�@�ɑ����āAMRJ�����������������܂��B
�@�z���_�̕����ЂƑ�������������܂��B
�@�Ȃ����A��s�@�̎ʐ^��L��������ƃ��N���N���܂��ˁB
�������A�G�A�[�|�[�g�ʼnH�����x�߂��s�@������̂���D���ł��B
|
2014�N11���S���i�j
�z���_�����Ɨp�W�F�b�g�@�̐������n�߂܂����I
�@�z���_�̑n�ƎҁA�{�c�@��Y�������Ƃ��Č���Ă����w�����͋�ɉH���������x�Ƃ����肢�𗈏t�A�������܂��B
 ���̂悤�ȃE�B���O��G���u�������A�z���_�ɂ̓o�C�N�ŁA�x�����[����h���[�����Ƃ����q�b�g���i������܂������A���̃K�\�����^���N�̗����Ɏ��t���Ă����̂��L�����Ă��܂��B���̎�������A�{�c�@��Y���͑��ɉH�������������A���̊肢�����߂Ă����̂ł��B ���̂悤�ȃE�B���O��G���u�������A�z���_�ɂ̓o�C�N�ŁA�x�����[����h���[�����Ƃ����q�b�g���i������܂������A���̃K�\�����^���N�̗����Ɏ��t���Ă����̂��L�����Ă��܂��B���̎�������A�{�c�@��Y���͑��ɉH�������������A���̊肢�����߂Ă����̂ł��B
�z���_���Ɨp�r�W�l�X�W�F�b�g�@�͏��i�Ƃ��āA�A�����J�q��F���ǂ̌^���F���擾����A��������܂��B�����ɊJ�����i��ł��܂��B
�@���ɉ��@�����@�g���A�e�X�g��s�Ȃǂ��I���āA�������C���ɂ͔̔��p�̎��@���P�O�@�قǑg���ɓ����Ă��܂��B
�@���L��URL�Ƀz�[���y�[�W������܂��B
�@http://www.honda.co.jp/jet
 �Ȃ�ƁA���̘b��̃W�F�b�g�@�́A���̎ʐ^�̂悤�Ȍ`�ŁA���܂Ō������Ƃ��Ȃ��嗃�̏�ɃW�F�b�g�G���W�������t���Ă��܂��B �Ȃ�ƁA���̘b��̃W�F�b�g�@�́A���̎ʐ^�̂悤�Ȍ`�ŁA���܂Ō������Ƃ��Ȃ��嗃�̏�ɃW�F�b�g�G���W�������t���Ă��܂��B

 �@�@ �@�@
�@�@
�@���܂ŁA�q��@�̐v�ŁA�嗃�̏�ɃG���W����ςނ��Ƃ̓^�u�[�Ƃ���Ă��܂����B
�����ȕ��Q���N���A�ƊE�̏펯�ɂ͂���܂���ł����B���̎�̏��^�r�W�l�X�W�F�b�g�@�̓G���W�����@�̌㕔�̗����Ɏ��t����̂��펯�ł����B�ȑO�̃W�F�b�g���q�@�A�{�[�C���O�V�Q�V�̂悤�Ȋi�D�̂��̂��قƂ�ǂł����B ���̃^�u�[�ƌ���ꂽ�w�W�F�b�g�G���W�����嗃�̏�Ɏ��t�����x�Ƃ������z����萋���܂����B����ɂ͓����A�q��@�̋Z�p�ɏڂ����l��������}��A���̖͂Ҕ����������悤�ł����A���쓹�i�v���W�F�N�g���[�_�͖Ȗ��Ȍv�Z�����ƂɁA���x�ƂȂ�������ςݏd�˂����ʁA�����_�ɃG���W�������t����x�X�g�|�W�V�����i������X�C�[�g�X�|�b�g�ƌĂ�ł��܂��j�����A��C��R�̒ጸ��A����ɂ��R��̌����A���x�̑����ȂǁA���܂łɂȂ����X�̐��\���オ�ł��A����ɋ��x�������嗃�ɃG���W�������t���邱�ƂŁA�]���̂悤�ɋ��x���������邽�ߋ@�̌㕔�̕⋭���ނ��s�v�ɂȂ�A�q���i�i�L���r���j���R�O�����L���Ȃ�A���Ȃ̊Ԋu�����������܂����B�܂�������U�����������A���S�n����ϗǂ��Ȃ�܂����B�@���ʂ͗ǂ����Ɛs�����ɂȂ�܂����B ���̃^�u�[�ƌ���ꂽ�w�W�F�b�g�G���W�����嗃�̏�Ɏ��t�����x�Ƃ������z����萋���܂����B����ɂ͓����A�q��@�̋Z�p�ɏڂ����l��������}��A���̖͂Ҕ����������悤�ł����A���쓹�i�v���W�F�N�g���[�_�͖Ȗ��Ȍv�Z�����ƂɁA���x�ƂȂ�������ςݏd�˂����ʁA�����_�ɃG���W�������t����x�X�g�|�W�V�����i������X�C�[�g�X�|�b�g�ƌĂ�ł��܂��j�����A��C��R�̒ጸ��A����ɂ��R��̌����A���x�̑����ȂǁA���܂łɂȂ����X�̐��\���オ�ł��A����ɋ��x�������嗃�ɃG���W�������t���邱�ƂŁA�]���̂悤�ɋ��x���������邽�ߋ@�̌㕔�̕⋭���ނ��s�v�ɂȂ�A�q���i�i�L���r���j���R�O�����L���Ȃ�A���Ȃ̊Ԋu�����������܂����B�܂�������U�����������A���S�n����ϗǂ��Ȃ�܂����B�@���ʂ͗ǂ����Ɛs�����ɂȂ�܂����B
 �������A�z���_�̓W�F�b�g�G���W���܂Ŏ��ЂŊJ�������А��Y���܂��B�W�F�b�g�G���W���܂Ŏ��ЂŊJ���E���Y���邱�Ƃ́A�q��@�ƊE�ł͍l�����Ȃ����Ƃ̂悤�ł����A�z���_�̓G���W���ɂ��������A���̓�s�������ɃN���A���܂����B �������A�z���_�̓W�F�b�g�G���W���܂Ŏ��ЂŊJ�������А��Y���܂��B�W�F�b�g�G���W���܂Ŏ��ЂŊJ���E���Y���邱�Ƃ́A�q��@�ƊE�ł͍l�����Ȃ����Ƃ̂悤�ł����A�z���_�̓G���W���ɂ��������A���̓�s�������ɃN���A���܂����B
�@�@ ���ЊJ���̃W�F�b�g�G���W���@HF120 ���ЊJ���̃W�F�b�g�G���W���@HF120
���̃W�F�b�g�G���W���̔R��͏]���̓��^�@�ɔ��30������S�O�����ȃG�l�A�ᑛ�����������Ă��܂��B�z���_�͂��̎��ЊJ���A���Y�����ȃG�l�̍����\�G���W����ςނ��Ƃ͂������A�G���W�������𑼂̍q��@���[�J�ɂ��������Ĕ̔����܂��B���ɁA�Z�X�i�Ƃ̊ԂŌ����܂Ƃ܂��Ă��邻���ł��B
�@�p�C���b�g�͂P�`�Q���A����͂T�`�U���A���Ȑ��͂V�`�W���A��s�����͂Q�P�W�T�����A�ō������͂V�V�W����/���A��s�i�ō��j���x��13106���A���������͂W�O�V���A���������͂U�X�S���A��S�T�O���h���i�S���T�疜�~�j�Ƃ����l�i�ŁA���ɂP�O�O�@�قǎ��Ă��܂��B
�@�����҂͔�������������đ҂��Ă��邻���ł��B
�@���^���Ɨp�W�F�b�g�@�́A��ʂ̗��q�@��荂�����x���s����悤�ł��B��ʂ̗��q�@��1�������琸�X�P���Q�炍�܂łł����A���̔�s�@�͂P���R�炍�ł���s���ł��܂��B
�@�ԉ��̃z���_����s�@��Ƃ����Ƃ�ł��Ȃ��`�������W�ɑ��A�����Ɏ���܂ł̓��͕����ł͂Ȃ������͂��ł��B
�@�v���W�F�N�g���[�_�̓��삳��́A����H�w���q��H�w�ȑ��ƂŁA�P�X�W�U�N�A���ЂR�N�ڂŎЈ��T���ƃA�����J �~�V�V�b�s�[�B����ɔh������A�w�Ő�[�̍q��Z�p���w��ŗ����I�x�Ƃ��������đ���o���ꂽ�����ł����A���n�ł̓K���[�W�̂悤�ȏ����ŁA�ޗ��Ƀ��X��������Ƃ����閈���ŁA����̎���@������Ƃ����������ł��B
�@�����������Ƃ̌o���Ȃǂ��A�{�Ԃ̔�s�@���ɑ�ϖ��ɂ������ƌ����Ă��܂��B
�@�����ōq��@�J���̐_�l�H���I���E�g���x���ɏo��A���ꂪ�傫�ȃ`�����X�ɂȂ��������ł��B
�@���삳��́A���݁A�ăz���_�G�A�[�N���t�g�J���p�j�[�̎В��ŁA�]�ƈ��͂P�Q�O�O���̐w�e�ɂȂ��Ă��܂��B�q��@��F���D�̊v�V�I�v�J���ɍv�������l�ɑ������P���[��W�����\���������N��܂��A�܂��܂��O�r�m�m�Ƃ������݂ɂȂ��Ă��܂��B
�@���܂Ő��E�ŁA�q��@���[�J�������Ԃ����Ƃ������т͂���܂����A�����ԃ��[�J����s�@�����Ƃ����̂́A����̃z���_�����߂Ăł��B
�q��@�́A�s����ȋ����S�ɔ�s���邽�߁A���x�Ȑv�Z�p�����ƂɁA�c��Ȏ�����A�M�������s�e�X�g���J��Ԃ��č��i���Ȃ���Ȃ�܂���B
�@���̂��߂Ɏ��ԂƃR�X�g��������܂����A�ꎩ���ԉ�Ђ��n�Ǝ҂̑z�����������邽�߁A���d�Ƃ�������W�F�b�g�@�̊J���Ɏ��g�݁A�����܂Ŕ��N��ɔ����Ă��܂��B
�@�A�����J�̃r�W�l�X�W�F�b�g�̎��v�͑傫���A���ꂩ��̃z���_�W�F�b�g���y���݂ł��B
�@�����A�g���^�����Ԃ͎�����������Ă���ł��傤�ˁB
|
2014�N�P�P���R���i���j
�G�l���M�[�̒n�Y�n���͐i�ނ��H
�@���{�͒n���n���̖ڋʐ�������낢��͍����n�߂Ă��܂��B���̓��̈�Łw�G�l���M�[�̒n�Y�n���𐄐i���悤�x�Ƃ����b������܂��B�o�C�I�}�X��n�M���d�Ȃǒn��̎��������������d��M�̋������s�����Ƃ������̂ł��B�_���͑�ό��\�Ȃ��Ƃœ����ł��B
�@������n���n���̊j�Ɉʒu�Â��āA�����̎哱�̓d�͉�Ђ������x�����A�d�͂�K�X�̎��Ƃ����������悤�Ƃ��Ă��܂��B
�@
�@�d�C�ɂ��ẮA�Q�O�P�U�N4���A�d�͂̎��R���ɂ��A�d�͂̏������N�ł��ł��邱�ƂɂȂ�܂��B���݂͓d�C���Ɩ@�ŁA�S���i����d�͂������Ɓj10�Ђ̓d�͉�Ђ��n��Ɛ莖�Ƃ��s���Ă��܂��B���̒n��Ɛ�̋K�����O���āA���R�ɓd�͂����蔃���ł���悤�ɂ��悤�Ƃ�����̂ł��B
�@���{�ɏZ��ł���l�́A���܂ł͊��d�͂��炵���d�C���Ȃ������̂ł����A�Ⴆ�A�����d�͂̕���������A���d�ƌ_�ēd�C�̋������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B
�@�������A�d�C�͑��d����z�d���ɂȂ����Ă��Ȃ��Ǝg���܂���B���̑��z�d���͊e�d�͉�Ђ��Ǔ��Ɉ��������Ă��܂��̂ŁA���̓d����ʂ��ċ�������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�d���͍��܂łǂ���Ƃ������Ƃł��B
�@
�@���̏ꍇ�A�����ɂȂ��Ă����B�d�͂̂悤�ɁA���z�����d�̔��搧�x�ő�ʂ̐\�����o����A���d���e�ʂ��I�[�o�[���ēd�͋������s����ɂȂ�Ƃ������R�ŁA���㑾�z�����d�̐\����t�����Ȃ��Ƃ����悤�ȉ�Ђ��o�Ă��܂����B
�@���̏́A���z�����d�g�[�^���ŁA��B�d�͂̃s�[�N�d�͂�d����Ƃ������炢�̐\�����o����Ă��邻���ł��B
�@
�@���R�G�l���M�[�͊�{�I�ɕs���萫��L���Ă��܂��B���z�����d�́A���V�̎��ƉJ��܂�̎��̔��d�ʂ̍����傫���A�܂����R�A�����������d���܂���̂ŁA����̓��̔��d�ʂ̃s�[�N�l���傫���ϓ�����v�f������܂��B
�@����œd�͎g�p�ʂ̐��ڂ�����ƁA��������ԑ傫���Ȃ�܂��̂ŁA���z�����d�͂���Ӗ��ł͍����I�ł��B�G�ߐ����l���Ă��A�^�ẴW���W�����������̏����ŃG�A�R�����t���^�]����悤�ȏł́A���z�����d�͔��d�ʂ��ő�ɂȂ�܂��B����������I�ł��B
�@���l�ɕ��͔��d�����������Ȃ���ΑS�����d���܂���B���R�G�l���M�[�𗘗p����ꍇ�͔��d�����d�C����x�����̕��@�Œ~�ς��Ĕ��d�ʂ�������K�v������܂��B
����ɂ͑�^�̓d�͗p�̃��`�E���d�r��A�g�����d���̂悤�ȑ��u��ݔ����v��܂��B
�@�ǂ������킯���A���A�b��ɏオ���Ă���G�l���M�[�̒n�Y�n���ɂ͑��z�����d�╗�͔��d�Ƃ������t�����܂�o�Ă��܂���B��قǂ̃o�C�I�}�X��n�M���d���傫���N���[�Y�A�b�v����Ă��܂��B�n�M���d�͉���n�̋߂��̂��������ݏグ�āA���C�ł̓^�[�r�������d�����ł��B�o�C�I�}�X�͊Ԕ��ނ�|�؍ނ��o���āA�ыƂ̍Đ������˂��_���ŁA�؍ނ�R�₵�Ĕ��d���鏬�K�͂ȉΗ͔��d���ł��B
�@�n�������̂��n��d�͂ւ̏o�����Ƃ��Ēn���̔��s��F�߁A���̗����̔������������S����Ƃ����Ă��o�Ă��܂��B����Ɂu�d�͂̐��Ƃ��h�����܂���v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���悤�ł��B
�@�d�͏���n�̋߂��Ŕ��d���ł���A���d���ł̓d�̓��X�����Ȃ��Ȃ�A���d�����d�͂�L���Ɏg���܂��B
�@���q�͔��d���͈��S���ƌ����Ȃ���A��翂Ȑl�����ꂽ�C�ݐ��ŁA��������s�s���琔�S���������ꂽ�y�n�Ŕ��d���A���������d���ő����Ă��܂��B������d�������߂Ă��A�d���ɒ�R������܂��̂ŁA�d�����M�ɂȂ��Ď����܂��B���̑��d�̓d�̓��X�͂T�����ɂȂ�܂��B�������S�����S�Ȃ��̂ł���A�����p��H�c��`�߂��Ŕ��d����A���Ƀ��X�����Ȃ��ė��z�I�ł��B�������A�������Ȃ��Ƃ���ɁA��������S�Ƃ����Ă��A�����Ȉ��S�͂Ȃ��Ƃ������Ԃ��̌��ʂȂ̂ł��B
�@�������A�u���z�����d�̐\����t�𒆎~�����v�Ƃ�����d�̂悤�ɁA�d�͉�Ђ͎��Ђ̓d�͋����̈��艻�𗝗R�ɂǂ��܂Œn�Y�n���̓d�͂��t���邩�A���ꂩ�炪���ڂ��ׂ��Ƃ���ł��B
�@��͂�A�ꍏ���������{�̔w���ɂȂ钴�������d���l�b�g���[�N�����݂��A�����Ɋe�d�͉�Ђ̑��d�����Ȃ��ŁA�k�C�������B�܂ŋ���ȃl�b�g���[�N��������O�Z�N�^�[���ō\�z���邱�Ƃ��K�v�ł��傤�B��������A���͑S���I�Ɍ���ǂ����Ő����Ă���ł��傤���A�����������������ł��傤���A�V�C�\��̂Ƃ��萰��̒n�������A�܂̒n��������āA���d�ʂ���������������܂��B����ɓd�͗p�̒~�d�r���o�b�N�A�b�v����A���R�G�l���M�[�̕s���萫���J�o�[�ł��܂��B
�@������A�����}�������o���Ă��邱�ƂŁA�w�z�d���̒n�����x�ł��B��i���A���ɃA�����J��[���b�p�̓s�s�ł͓d������������܂���B�قƂ�ljƉ��ɔz�d���Ă���̂͒n���P�[�u���ɂ���čs���Ă��܂��B������w�z�d���̒n�����x�ƌĂт܂��B
�@�����̍H����p�͂�����܂����A�s�s�̔��ς�A���H�̌�ʈ��S�̗��ꂩ����A�d���������Ă��Ȃ��͔̂��ɓ��H���L���g���܂��B�d���͕K�����H�̋Ȃ���p�Ɍ����܂��̂ŁA�Ԃ̉^�]�ɂ͎ז��ȑ��݂ł��B
�����͂��́w�z�d���̒n�����x�ɂ͑�^���ł��B�ꍏ����������Ăق����C�����ł��B
�@�������A��C�ɒn�����z���͍H����̕��S�ʂŖ����ł��傤����A�܂��s�s���A����Ɋό��n�̓d�����Ȃ����A�i�ς𐮂��邱�Ƃ���ł��B
�@���{�ɂ͐��E��Y��A�L���Ȋό��n����������܂����A���������ꏊ��D��I�ɓd���A�d������蕥���A�X�b�L���Ƃ����i�ςɂ��ׂ����ƍl���Ă��܂��B
�@��������̓s�S���͈ꕔ�A�n���P�[�u���ɂȂ�A�d�����Ȃ��ꏊ������܂����A�{���ɂ�������Ƃ����i�ςɂȂ�܂��B
�@���s�s�̓����̕t�߂͓d�����Ȃ��āA��ϋC�����������i�ς�悵�Ă��܂��B
�d����d�����Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���ꂩ��O���l�ό��q�������钆�ŁA��ύD��ۂ�^���܂����A�ʐ^���B���Ă��A�d�����f��Ȃ��ʐ^�͑�ϑf���炵�����̂ł��B
�@
�@�����Ȍ��������̃A�C�e��������Ǝv���܂����A��Ԑ�ɓd���̓P���A�d���̒n���P�[�u�����Ɏ��g��łق����Ǝv���܂��B
�@������������ɓ����Ă��܂����A�����Q�R�N�x�łP�T���A�����Q�W�N�x�łP�W���ɂ����Ȃ�܂���B����ł͐�i�e���̒��Œu���Ă��ڂ�ł��B�N�ɏ��Ȃ��Ƃ��R�����炢��B������A�P�O�N�łR�O���ł�����A�c�ɂ������Γs�s���͉��Ƃ����d���ɂȂ肻���ł����E�E�E�E�B
���C�����邩�ǂ��������ł��ˁB
�ق��̌o�������Ă��A���������C���t���ɂ͋��������āA�O���l�ό��q���W�߂ĉ҂��I���������{���ł��Ăق������̂ł��ˁB
�@�G�l���M�[�̒n�Y�n���́A�܂��܂����ꂩ��d�͉�ЂƂ̂��߂������ŁA��q����Ǝv���܂��B�܂��́A���{�̔w���̒��������d���l�b�g���[�N�̌��݂��S�Ẳ��ɂȂ�ƍl���Ă��܂��B
�i�Q�l�j�@����URL�ɍ��y��ʏȂ̖��d������HP������܂��B
�@�@�@http://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/
|
2014�N10��21���i�j
�u�V�X���b�N�X�v�������m�ł����H
10��27���@�ꕔ���e�̏C���A�lj�
�V�X���b�N�X�Ѓz�[���y�[�W�@�@http://www.sysmex.co.jp/
TOA�Ѓz�[���y�[�W�@�@�@�@http://www.toa.co.jp/
�@�u �V�X���b�N�X�v�Ƃ�����Ђ�����܂����A���������Ƃ��Ȃ��l�������Ǝv���܂��B
���̉�Ђ́A�l�ԃh�b�N�⌒�N�f�f�̎��ɁA�̎悵�����t�͂��A�W���l�ɑ��Ď����̑���l��\�ɂ��āA�h�N�^�[����������܂��B���̌��t��A�Ȃǂ̕��͋@����Ă�����{�ň�ԁA���E�ł����w�̉�Ђł��B
�@
�@���̉�Ђ́A�u��������d�@�v�Ƃ����_�˂ɂ����Ђ̐V�K���ƂƂ��ăX�^�[�g�����q��Ђł����B���������d�@�́uTOA�v�ƎЖ��ύX���āA�w�Z��a�@��H���w�Ȃǂ̍\�������ݔ��A�ŋ߂̓Z�L�����e�B�J������f���V�X�e���ɗ͂����Ă����ЂŁA�Ɩ��p�����f���@��̐����A�̔��Ɉ�т��Ď��g��ł����Ђł��B
�@TOA�̋Ɨe�́A�]�ƈ����W�O�O����ŁA�N�Ԕ���͂S�Q�S���~�A�c�Ɨ��v�͂S�R���~�ŁA�P�X�S�X�N�ݗ��̉�Ђł��B
�@
�@���̓�������d�@���A�������ƈȊO�̒��Ƃ��āA�w�����V�K���Ƃ���낤�x�Ƃ������ƂŁA�A�����J�ɒ����ɍs�����ہA�������͂Ƃ�����Õ��͋@���m��A�w���ꂩ��͈�Õ��삪�L�т�x�ƌ����݁A�܂��A�e�Ђ������������Ȃ��������̐V�K���ƂɎ��g�݁A�����Ɋg�債�A����Ɨe�́A�U�C�V�U�W���A�N�Ԕ���P�C�W�S�T���~�A�c�Ɨ��v�R�Q�W���~�Ƃ������D�lj�Ђɐ������A�e��Ђł���TOA��傫���������Ђɐ������܂����B
�@�u�V�X���b�N�X�v�Ƃ����Ж��́A�}���\���̖���~�Y�L����̃X�|���T�[������Ă��܂����̂ŁA���q�}���\���̃e���r�ϐ킵�Ă���ƁA�������̃g���[�j���O�V���c��[Sysmex]�Ƃ������D���t���Ă����̂��o���Ă���������L��ł��傤�B
�@
�@����AIR�����Ƃ��āA����l��Ќ��w��s���܂��āA�����͒m�荇���̊���̕��̏Љ�œ��������Ă��炢�܂����B����́A�ŋߊ��������A�C�X�N�G�A�ƌĂ�Ă���Ő�[�H��̐��Y����������Ă��炢�܂����B
�@���Y���Ă���@��͌��N�f�f��A�l�ԃh�b�N�ŁA�a�@�ōs�����t�����A�A�����̋@��₻��Ɏg�p���鎎��A�\�t�g�E�F�A���J�����A�����E�̔��E�T�[�r�X���Ă����Ђł��B
�@
�@��Ì����ɂ́A�w���̌����x���w���̌����x������܂��B
�@���̌����Ƃ́A�a�@�ȂǂŁA�����g�Q����CT��MRI��S�d�}��]�g�����݃J�����A�咰�J�����A�����g�摜�f�f�ȂǁA�������a�@�ɍs���A�����ő̂̌���������̂ł��B
�@���̌����́AX������ː����ʌ��f���g���ĉ摜���B��MRI�APET�ȂǁA�댯���܂��̂ŁA�����@��͔��Ɍ��d�ȋK�i��R����ʉ߂��Ȃ���Ώo�ׂł��܂���B����͑�|����ȊJ����������Z�p��v���܂��̂ŁA���ł�A������A���Â�A�C�O���[�J�[�ł�GE��t�B���b�v�X�Ȃǂ��肪���Ă��܂��B
�@����ɑ��āA���̌����Ƃ́A���t��A�Ȃǂ��̎悵�āA�����@��ɂ����đ��肷����̂ł��B��a�@�͎��O�ł��̌��t���͊��A�����@�Ȃǂ����L���Ă��܂����A����҂Ȃǂł͍̌���̔A�������̂͂���ɂ��Ă��錟���@�ւɑ���A�����Ō������Č��ʂ���Ă��炤�悤�ȕ��@������Ă��܂��B
�@�V�X���b�N�X���A��҂����̌����@��𒆐S�Ɏ��g��ł����Ђł��B
�@�Ж��̗R���́A�wSYStematical +MEdics +�����̉\���iX�j�x�̑��ꂾ�����ł��B
�n�Ƃ͂P�X�U�W�N�Ƃ������Ƃł�����A�n�ƂS�U�N�ɂȂ�܂��B
�@
�@�Ɨe�̊g��ƂƂ��ɁA��ɕ��Ɍ����ɍH��⌤������T�[�r�X�T�|�[�g����Ȃǂ����݂��A���߂ł͉��Ð�s���A�C�X�N�G�A�Ƃ������O�̍H������݂��A�����𒆐S�ɐ����͂����܂ł̂R�{�ɂ��悤�Ǝ��g��ł��܂��B
�@
�@�A�C�X�N�G�A�̊�{�R���Z�v�g�́A�w�V�X���b�N�X�@�X�}�[�g�@�}�j���t�@�N�`�������O�@�V�X�e���x�̐i����ڎw���A�l�ƋZ�p���Z�����鍂�i���Ȑ��Y�̐��̊m���������ł��B
��̓I�ɂ́A
�@�@���C�h�C���W���p���̂��̂Â����Nj����A���i���E��R�X�g�𗼗�����
�@�A�X�e�[�N�z���_�[�ɑ�����S�E���S�Ɗ����̒�
�@�B��i�̋Z�p�Ɛl�̗Z��
�ŁA�A�C�X�N�G�A�̈Ӗ�����Ƃ���́A
�@[ i ] �@�B�Ginstrument�ɉ����Aintelligence�i�m���j�Ainnovation�i�v�V���j�AICT�i�Z�p�́j�Ȃǂ����m�I�Ȑ��Y�ւ̑z��
�@�mSquare]�H�ꌚ���̌`��i�����`�j�ɉ����A�����E���R�Ƃ�����Ë@��H����C���[�W
�@�A�C�X�N�G�A�͕~�n30,794�u�i��9,000�j�ɂW�T���~�W�T���̐����`�̂R�K�̌����ł��B�P�K���q�ɃG���A�A�Q�K�������E�����{�݃G���A�A�R�K�����Y�G���A�ƂȂ��Ă��܂��B
�@���̌����́A�����ȍH�v���{����Ă��܂��B
�@��ڂ́A�P�K�q�ɂ���C�O�ɏo�ׂ���ۂ̓R���e�i�[�ɓ���āA����ΐ_�ˍ`����ʊւȂ��ŗA�o���ł��邻���ł��B�ʊ֎葱���Ɏ�Ԏ�邱�Ƃ��Ȃ��ƌ����Ă��܂����B
�@��ڂ́A�����S�̂��Ɛk�E�ϐk�\���ɂȂ��Ă��āA�P�K�̊�b����������ԂɂȂ��Ă��邻���ł��B
�@�O�ڂ́A���Y�����ŁA�L����9,700�u�A���̓t���[�g���̗p���A�����ɂ�LAN�P�[�u���ނ�A����⏃���̔z�ǂ����菄�炳��Ă��邻���ł��B���Y���Ă���@��̏d�ʂɑς��邽�����̑ωd��500����/�u�ɂȂ��Ă��邻���ł��B
�@���̉�Ђ��傫���������A�����v���グ�����Ă���Ђ݂́A�����@���ƁA�����Ɏg��������̔����Ă��邱�Ƃł��B
�@
�@�p�\�R���̃v�����^�[�͖{�͈̂����Ă��A�C���L�������āA�L���m����G�v�\���̓C���L�Ŗׂ���Ƃ����r�W�l�X���f�����\�z���Ă��܂��B
�@
�@�V�X���b�N�X������̔����߂�������̔̔��ɂȂ��Ă��邻���ł��B�ŋ߂��@��̃e�N�j�J���T�[�r�X���T�|�[�g���r�W�l�X�ɂȂ��Ă����ƌ����Ă��܂����B
�@
�@�p�\�R���̃v�����^�[�ƈ�����A���̈�Ì��̌����@��͈������̂ł����S���~�A�������̂͐��疜�~�Ƃ������Ƃł�����A����������@��i�n�[�h�j�ƁA�@��Ŏg�����Օi�̎���ƁA�V�X�e���\�t�g�ƁA�e�N�j�J���T�|�[�g�T�[�r�X�̂S�̕���Ŗׂ����Ƃ����r�W�l�X���f���ŁA�c�Ɨ��v���͂Q�O���߂��ɂȂ��Ă��܂��B
�@������A�C�X�N�G�A�Ƃ����Ő�[�̉��Ð�H����������Ă��炢�܂����B
��������́A�́H�̉Ɠd���[�J�̐������C���Ƃ͑S���Ⴄ���̂ł����B
�����̐������C���͂���܂���B
�@��Ԃ̏�ɁA�������ނ���g�ݕt�����V���[�V�i�@�B�̍��g�݁j�ɁA�u���b�N���ƂɎ��O�ɏ����������i�u���b�N�����t���A���ʂ�ׂ���������̃p�C�v��������Ǝ҂̎�ŁA�d�C��H�̔z���̂悤���Y��ɔz�ǂ���A�ׂ��p�C�v����������čs���܂��B
�@����͉t�̂ł�����A����𑗂邽�߂̃|���v��A�ق�A�v�ʂ̂��߂̂����ȕ��G�Ȑ������i����������l�ߍ��܂�Ă��܂��B
�@
�@���Ă���ƁA��l����Ƃ���H���������āA�w����Ȃ��Ƒ�ς��낤�ȁI�x�Ǝv���܂����B����ł̐����ł́A�e�H�����X�e�b�v���ɋ���āA���̃X�e�b�v���ɍ�ƃ}�j���A�����t���f�B�X�v���C�œ���ŕ\������A����ɏ]���č�Ƃ���ΐ�������Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł����B
�@��l�̍�Ƃ���������ƁA�ʂ̐l�����̃X�e�b�v�̍�Ƃ�����Ƃ��������ŁA���l�ɍ�Ɠ��e���t���f�B�X�v���C�œ���ŕ\�������B�������������ŁA���X�ƕ��G�ȍ�Ƃ����Ȃ��đg�ݗ��Ă�悤�ł��B���̃f�W�^�����̂Â��胉�C���ł��B
�@
�@��ƍH���͎��X�𑗂��܂����A�������C���̂悤�ɗ����Ƃł͂Ȃ��̂ŁA��̍�Ƃ��I�������Ԃ��������Ŏ~�܂��Ă���Ƃ��������܂����B
�@�܂��A��Ƃ̓r���ŕK�v�Ȋm�F�̓p�\�R�����g���Ȃ��瓮�쌟�����s���A���Y�����H���ɐi�݂܂��B
�@���C���̈�p�Ɂw�K�i�O�i�������x�Ƃ������D���\��ꂽ�@�킪�Q�����ł��܂����B
�����A�����̍�ƕs�ǂ����i�s�ǂŁA�`�F�b�N�Ɉ��������������̂��Ǝv���܂��B
�@���̂悤�ɐ��Y����̕i���Ǘ��́AIT����g���A�p�\�R���ɂ��X�e�b�v�A�X�e�b�v���Ƃɓ���`�F�b�N���A�C���e���f���g�����ꂽ�f�W�^���E�Z�����Y�����ł��B
�@�ǂ̕���̑���⌟���ł����Ă��A����l���������Ȃ���Ȃ�܂���B
�w���N�f�f�̌��ʂ̐��l�͐������A�M�p��������x���Ƃ��O��ł�����A�i���ʂ�M�����̍��������߂��܂��B
�@�����@�킪����ɓ����Ă��邩�ǂ����́A�W�������Ƃ������̂�����A������@�B�ɂ����Ď������A���̌��ʂ�����͈͂̐��l�ɓ����Ă��邱�ƂŁA����ɑ���o���Ă��邩�ǂ����肷��Ƃ������Ƃł����B
�@���̈�Ë@��̍Ő�[�H������w�����Ă��炢�A�����琔�\�N���́A���W�I��X�e���I��r�f�I��e���r�Ȃǂ̉Ɠd���i�̋K�i��ʐ��Y���x���Ă����������C���ɍ�ƈ�������������сA��l�����ӏ��Ƃ����P���ȍ�Ƃ��s���A�R���x�A�ŗ����Ƃ�����Ƃ����ʎY�H��̌��i�Ƃ͑S���Ⴄ���i�ł����B
�@�H����͑�ϐÂ��ŁA�������Ƃ��Ă��āA���w���ɌĂяo���}�C�N�̐����S���Ȃ��A��Ƃ��l�X�Ɛi�߂��Ă���Ƃ������͋C�ł����B
��Ǝ҂������̃y�[�X�ł���Ă���Ƃ��������ł��B
�@
�@���Đ��E����ւ������{�̉Ɠd���[�J�͍��A���킵�A���X�g���Ɏ������X�g�����J��Ԃ��A�Ȃ��Ȃ��悪�����Ȃ��̈���ŁA�V�X���b�N�X�Ђ͂���Ȃɂ������Ƃ������̂Â�������Ȃ���A�Q�O���߂��c�Ɨ��v���グ�Ă��闝�R���悭������܂����B
�@
�@�f�W�^�������̂����̂܂ܑg�ݍ��悤�ȏ��i�i�T�^�̓X�}�z��t���e���r�Ȃǁj�����A�̔����鎖�Ƃ́A�������{�ł͂�����撣���Ă��ׂ���Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B�t�����l�����Ȃ��ɂȂ��Ă��܂����̂ł��B
�@�w���قŁA�N�����Q�悵�Ȃ�����ŁA���̏��i���\������Z�p�����x�ȋZ�p��m�E�n�E�Ő��藧���Ă��鐻�i�ŁA���Ђ���낤�Ƃ��Ă��A�ȒP�ɒǂ����Ȃ����i�ŁA��������邽�߂Ƀf�W�^���Z�p����g�������I�ɃR�X�g�������Đ�������x�A���������r�W�l�X���f�����\�z����A���{�ł��J���E���Y�E�̔��E�T�[�r�X�Ŗׂ��邱�Ƃ��ł���Ƃ������{�̂悤�ȉ�Ђł����B
�@Panasonic��SONY��V���[�v�Ȃǂ́A���܂ł̎��Ƃ⏤�i�Ɏ������āA�Ⴆ�e���r���ƂȂǂ��̓T�^�ł����A������������͒�����؍��ɏ��ĂȂ����ɂȂ��Ă��邱�ƂɋC�Â��A���{�Ŏ��ɉ������̂��������o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���������ʂŁAPanasonic�̐V�������ƕ���iBtoB�A�J�[�G���N�g���j�N�X����A�n�E�X�A���f�G�l���M�[���쓙�j�ւ̃V�t�g�́A�������Ƃ��Ă͐�������������Ȃ��B
�������A�܂����g�ޕ��삪���R�Ƃ��āA����ȑg�D�͂��������A�т��H���镪��܂ň�Ă��邩�������Ă��Ȃ��C������B
�@��Ђ̋K�͂��傫���ƁA�ǂ����Ă��傫�Ȏs��ɖڂ��s���A�����ɐi�o���ăV�F�A�����Ȃ��Ƒ�ʂ̏]�ƈ������V��H���Ȃ��Ƃ������ƂŁA��s���_���B
�@���̑傫�Ȏs��͓��R�A�F���_���Ă���̂Ō݂̐H�������ɂȂ�B��肭�҂��Ȃ����ʂɏI��邱�Ƃ������B
�@���̓_�A���̈�Õ��͕����͐��X�A���牭�~�Ƃ����K�͂ŁA����A���E�I�Ɋg�債�Ă��P���~�O��ł��낤�i����͏���ȉ��߂Ȃ̂ŊԈႢ�����m��Ȃ��j�B
�ԈႢ�Ȃ������邱�Ƃ́A�����������i�̂悤�ȋ���s��ł͂Ȃ��B����ꂽ����Ȏs��ł���B�����炱���A�����Ɏ��Ƃ̎|�݂�����ƌ�����B
�@Panasonic�͏����d��̍j�̂ł���w�Y�Ɛl����̖{���ɓO���A�Љ���̉��P�ƌ����}��A���E�����̐i�W�Ɋ�^���Ƃ������x�Ƃ����o�c���O������x�悭�l����K�v���L��B
�@�ǂ����A�؍��̃T���X����LG�d�q�������d��̎А������H���Ă���悤�ȋC������B
�@Panasonic�͂��̐����ȍj�̂�Y��āA�ق��̓���͍����Ă��邩�̂悤�ȋC������B
�@����͐��n�����Ɠd�s��A�O���[�o�������ꂽ�Ɠd�s���Ɋ�Ƃ������c��A���W���邱�Ƃ̓�������Â�������B
�@�������A�A�C�X�N�G�A�����w���āw���͕K������x�Ƃ�����������ł����B
|
2014�N10��13���i���j
�䕗13�����߂Â��Ă��܂��B
�䕗�Ƃ́A�����͂ǂ������ӂ��Ɍ��߂Ă���̂ł��傤�H
�@�䕗19��������Ă��܂��B
�O���18���́A�\��~�̓쑤��ʂ������߁A���͖w�lje���͂���܂���ł����B
�@
�@19���͑傫�Ȑ��͂܂Ő��������䕗�ł��B�ꎞ��900�w�N�g�p�X�J���Ƃ������܂莨�ɂ��Ȃ��قNjC�������������䕗�ł��B���S�̖ڂ́A�F���X�e�[�V�������猩���f���ł́A�ۂ��A��������ƌ����Ă��܂����B
�@�w����ȋ���ȑ䕗���܂Ƃ��ɗ������ςȂ��ƂɂȂ�x�ƐS�z���܂������A�k�シ��ɏ]�����サ�A975�w�N�g�p�X�J���Ƃ������͂ɂȂ�܂����B���S�t�߂̍ő啗������܂��Ă��܂������A���t�߂�ʉ߂��鍠�͂ǂ��Ȃ��Ă���ł��傤�H
�@�䕗�͔M�ђ�C�������B���A10���Ԃ̕��ςŁA���S�t�߂̍ő啗����17��/�b�ȏ��ɂȂ��������䕗�ƌĂԂ��ƂɂȂ��Ă��܂��B
�@�䕗�͐ԓ����k�ŁA���o180�x��萼�̗̈�Ŕ������������ŁA�n���̎��]�i�����瓌�����j�̉e���ŁA�ԓ��t�߁i��ܓx�j�ł͐��ɐi�݁A���{�t�߂ł͕ΐ����̉e���œ��ɐi�ݐi�s���x�������Ȃ�Ȃ�����܂��B
�@�䕗�����܂��v���Z�X�́A�ԓ��t�߂͊C�������������ߑ�ʂɐ����C���������A�㏸���ċÏk���_���ɂȂ�ۂɕ��o�����M���G�l���M�[�Ƃ��Ĕ��B���܂��B
�@�����ꏊ�̊C�����������قǁA�䕗�̃G�l���M�[���傫���Ȃ�A��^�̑䕗�ƂȂ�܂��B
�@
�@�䕗���ړ�����ۂ́A�C�ʂ����������邽�ߊC������������A�n��ł͎R�J�̓ʉ��ɂ�門�C�Ő₦���G�l���M�[�������܂��B
�@�G�l���M�[�̋������Ȃ����2�A3���ŏ��ł��܂��B�@���{�t�߂܂Ŗk�シ��ƁA���̊��C�Ő��͂������A���ђ�C���܂��͔M�ђ�C���ɕς��܂��B
�@
�䕗�͕����̑����ƁA�K�͂̑召�ɂ�艺�L�̂悤�ɕ��ނ���܂��B
�@�����ɂ���A
�@�E�����i���b33�`44���j�A
�@�E���ɋ����i44�`54���j�A
�@�E�җ�ȁi54���ȏ�j�A
�@�K�͂ɂ���A
�@�E��^�i500�`800km�����j�A
�@�E����^�܂��͔��ɑ傫���i800Km�ȏ�j�B
�@���͋����Ȃ������܂����荏�X�ƕω����܂��B�����\�����邽�߂��u�ԕ��������ϕ����Ƃ����\�������܂����A���ϕ����Ƃ�10���Ԃ̕����̕����ŁA�ő啗����10���Ԃ̕��ϕ����̍ő��l�A�u�ԍő啗���͏u�ԕ����̍ő�l�ł��B
�@
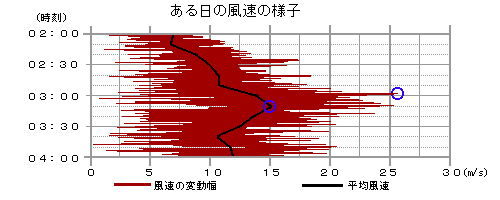
�@��̐}�͂�����̌ߑO�Q������S���̕������O���t�ɂ������̂ł��B�Ԃ̐��́A�P���Ԃɐ��������̕ϓ�����\���Ă��܂��B
�@�Ⴆ�A�Q���T�O������R���O�O���܂ł̂P�O���Ԃ̕����̕ω�������ƁA��ԕ������������Ƃ��łQ�D�S���^���A��ԑ傫���Ƃ��łQ�T�D�V���^���̕��������Ă��܂��B���̏u�Ԗ��̕����u�u�ԕ����v�ƌ����܂��B�܂��A���̂P�O���Ԃ̕����ς���ƂP�R�D�W���^���ɂȂ�A������u���ϕ����v�Ƃ����܂��B
�@�܂��A���ϕ�����u�ԕ����̍ő�l���u�ő啗���v�A�u�ő�u�ԕ����v�Ƃ����A��̐}�Ő�����̕����̕����ɂȂ�܂��B
�u�ő啗���v�͂P�O���Ԃ̕��ϕ����̍ő�l�A�u�ő�u�ԕ����v�͏u�ԕ����̍ő�l�ł��B
�@�V�C�\��Łu���������[�g���v�Ƃ����ꍇ�A�P�O���Ԃ̕��ϕ������w���܂��B
�@��ʓI�ɁA�u�ԕ����͕��ϕ����̂P�D�T����Q�{�߂��l�ɂȂ�܂��B
�@�\���x���\����A�u�Q�T���[�g���̖\���̋��ꂪ����v�Ƃ������ꍇ�A�u�ԕ����ł͂T�O���[�g���߂����������\��������܂��̂ŁA���ӂ��K�v�ł��B
��ʂɏu�ԕ����͕��ϕ�����1.5�{�`2�{���x�ł��B
�@������Ƃ�₱�����̂ł����A�u�ő�u�ԕ����v�Ƃ��������������܂����A�u�u�ԍő啗���v�͂���܂���B�Ԉ�����������ł��B
�@16�����݂̗\��ł́A�l����ʉ߂��āA�k���ɐi�ނ悤�ł��̂܂܂ł͂܂Ƃ��ɑ��ɂ���Ă������ł��B
�@��Q���Ȃ��悤�ɋF��܂��B
|
2014�N10���X���i�j
�FLED�����ҁ@3���̃m�[�x�������܂��߂łƂ��I
�i�ꕔ�L�����C�����܂����j
�@�䕗18���������ɒʂ�߂��A�f���炵���H����ɂȂ�܂����B
���͊F�����H�Ƃ����V�̃V���[������܂����B
�@�����������ŁA���N�̃m�[�x�������w�܂̔��\������A���N�O����m�[�x���܂Ɉ�ԋ߂��l�Ƒ�����A���҂���Ă�����������ƁA�ԍ肳��A�V�삳���3�l����܂��܂����B
�@�ŋ߁A���{�l�̎��͂̍������F�߂��Ă����悤�ŁA�m�[�x���܂̎�܂��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
�@�䂪�Ƃ̏Ɩ����́A���i�悭�g�����ԁA�䏊�A���ցA���ʂȂǂ́A�S��LED�d���ƁALED���nj^�Ɗی^�Ɏ��ւ��܂����B
�@LED�����v�͏���d�͂��Ⴂ�̂ŁA�����ςȂ��ɂ��Ă��d�C�オ�C�ɂȂ�܂��A�t��LED�Ɏ��ւ��Ă���A�g���Ƃ������_���A���Ȃ����͏����I���E�I�t�����܂߂ɂ���悤�ɂȂ�܂����B����œd�͎g�p�ʂ��P���i��N������j������܂����B
�@�d���͓_������A����������J��Ԃ��͓̂��ɖ��͂���܂���B�������A�u�����̓I���E�I�t��p�ɂɌJ��Ԃ��ꍇ�͎������Z���Ȃ�܂��B
�@
�@���̗��R�́A�u�����͕��d�ǂ̈��ŁA���d�J�n�̍ۂɁA���[�̃q�������g�ɓd���𗬂����߁A�d�q�������邱�Ƃœ_�����܂��B���[�̓d�ɕ����ɂ���q�������g���{�[�ƐԂ��Ȃ�ł��傤�B���̌シ���ɁA�O���[�����v���`�J�`�J���ăp�b�Ɠ_���܂��B���̓_���܂ł̏u�ԂɃq�������g������̂ł��B�������_�������q�������g�̕\�ʂ͕��d�d���ō������ێ�����܂��̂ŗ��܂��B�������A�_���鎞�̗���Ԍ������̂ł��B������u�����͂��܂�Z���ԂŃI���E�I�t����ꏊ�̏Ɩ��ɂ͎����̓_�ōD�܂�������܂���B
�@���̓_�ALED�͉���_�ł����悤�������̖��͂���܂���B
�R���s���[�^�Ȃǂ̓�����m�F�ł���悤��LED���`�J�`�J���Ă��܂��ˁB�����A����Ƀ��C�����XLAN�̃u���[�h�o���h���[�^��ݒu����Ă���ꍇ�́A�펞LED���`�J�`�J���Ă��܂����A��ꂽ���Ƃ��Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�����v�̎����́A�d���̏ꍇ�͐��܂ł̕��ώ��Ԃł����A�u�����͐V�i�Ɏ��ւ������̖��邳�̂V�O���ɈÂ��Ȃ鎞�Ԃ��������Ԃƌ��߂��Ă��܂��B���6000���Ԃ���ŋ߂�1�����Ԃł��B����ȏ�Ɏg���܂����Â��Ȃ�܂��B�Ō�͓_���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
�@LED���u�����Ɠ��l�Ɍ��߂��Ă��܂����ALED�͔�������d�g�݂��d����u�����ƑS���ʂł�����A�����͕��ʂɎg���ĂP�O�N�Ԃ��炢�͎g���܂��B�i��ʓI��4�����Ԃƕ\�����Ă�����̂������Ǝv���܂��j
�@�ŋ߁A�����Ԃ̃w�b�h�����v�܂�LED���g��ꂾ���܂����B���܂Ńw�b�h�����v�Ɏg����悤�Ȗ��邢LED���Ȃ������̂ł����A�ŋ߁A��W�i���b�g�j���x�̂��̂����i������A�\���Ȗ��邳��������悤�ɂȂ�܂����B
�@�ŋ߁A��芷�����z���_�̐V�^�t�B�b�g�̓w�b�h�����v��LED�����v�ɂȂ��Ă��܂��B
���܂ł̎Ԃ́A�n���Q�������v���A���^���n���C�h���d�ǁi���^�n�������v�j�ł����B
�@���^�n�������v�̓X�C�b�`���I������ƁA���S�{���g�̍��d���������āA���_�����܂����A���߂͏����Â��A���b�Ԃ���ƒʏ�̖��邳�ɂȂ�܂��B�_������͏����Â��Ƃ������_������܂����B�n���Q�������v�͐��N�Ԃŋ���ɂȂ�܂������A���^�n�������v�͎����������ăo�b�e���[�̓d�C�����܂�H��Ȃ��悤�ɂȂ�܂����B
LED�w�b�h�����v�͂���ɒ������ŁA�ȃG�l�ł��B�������A�X�C�b�`��ON����Əu�ԓI�ɂς��Ɠ_���܂��B
�@�M���҂���A�g���l�����o���肷�邽�тɃI���E�I�t�����܂߂ɂ��܂����A�����̐S�z������܂���B�������A�܂�LED�w�b�h�����v�͍����Ȃ��̂ł��B
�@���̑��A�u���[�L�����v��t���b�V�������v�⎺�����ȂǑS��LED�ɕς��A�n�C�u���b�h�ƍ��킹�ďȃG�l���O�ꂵ�Ă��܂��B
�@�b�����܂����̂ŁA���ɖ߂��܂��B
�@�����3�l�̃m�[�x����҂́A���ꂼ��J����̕��S����肭���ݍ����A���߂Đ��������悤�Ȉ�ۂ��܂����B�Ȋw�Z�p�͂��낢��ȕ���A�ޗ��i�f�ށj�A���H�Ȃǂ̐�[�Z�p�̑g�ݍ��킹�ŁA���܂łɂȂ����̂��n�������̂ł��B
�@
�@�w�FLED�x�ƕ����A�w�����̓������w�H�Ƃ̒�������x�Ƃ������O�������т܂����B
�������ꂩ�甭�������Ƃ���v���Ă��܂������A��������͐ԍ肳��ƓV�삳��������K���E���Ƃ��������̑f�q�̉��ǂ����ƂɁA�FLED�̔����������グ�āA���邢�F������LED���J�����A�ʎY���Ɍq���A���i�Ƃ��Ĕ̔��ł���������ʂ������悤�ł��B
�@LED�͔����̂ł�����A��ʂ̃_�C�I�[�h�Ɠ��l�ɔ����̑f�q�̕\�ʂ�P�^��N�^�̓�̕s�������g�U�i�\�ʂɔ�������悤�ȍ�Ɓj�����āAP�^�d�ɂɃv���X�AN�^�d�ɂɃ}�C�i�X�̓d�C��������ƁAP����N�Ɍ������d��������܂��B���̍ۂ�PN�̐ڍ��ʂŔ������܂��B
�@�d�q�i�i�C�i�X�j�Ɛ��E�i�v���X�j���ڍ��ʂŏՓ˂���ۂɌ��ƔM���o��̂ł����A���ʂ̓d���̂悤�ɁA�����̕��́i�q�������g�A�ޗ��̓^���O�X�e���j�ɂ��M�t�˂������ł͂���܂���̂ŁA�������ɒ[�ɏ��Ȃ��̂ł��B�d���̓q�������g��2000�x�O��ɔM�����A���z�������o���̂Ɠ��������Ō����o�܂��B�d����f��ŐG��Ƃ₯�ǂ���قǔM���ł��ˁB
�@�u�����͕��d�ǂł�����ALED��d���̔��������Ƃ͕ʂł��B
�u�����͊Ǔ��ɐ������H����Ă��܂��B���̐�����C�����d�ɂ�莇�O�����܂��B���̎��O�����ǕǓ����ɓh�z�����u���h���ɓ�����A�u���h��������A���������o��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�ł�����A�h�z����u���ޗ���ς��邱�ƂŁA�����F�A���F�A�d���F�Ƃ��낢��ȐF�̌��������܂��B
�ŋ߁A�u�������ȑO�ɔ�ׂđ�ϖ��邭�A�l�̊�F�Ȃǂ��Y��Ɍ�����悤�ɂȂ�܂����B
����͈ȑO�̃u���E���ǎ��̃J���[�e���r�Ɏg���Ă����R���F�iRGB�G�ԁA�A�j�̌����o���u���h�����g�����������Ƃɂ��A�����������i�i�ɗǂ��Ȃ������߂ł��B
��ʂɁA�w�����o���d�g�݁x�Ƃ��Ă͎��̂悤�Ȃ��̂�����܂��B
�@�@�����̕��̂̕\�ʂ�����˂����M���ˁG�@�d���A���z�������ł��B
�@�A������C�̕��d�ɂ�鎇�O�����������i���j�ɕς���G�@�u����
�@�B�����̂��g���d�q�Ɛ��E�̂Ԃ���ۂ̔�����p����G�@LED
�@�C�d�E�������Č��炷�G�@�G���N�g�����~�l�b�Z���X�iEL)
�@�D���̔������ہG�u�Ȃ�
�Ȃǂ�����܂��B
�@���̓��ALED�͐��E�Ɠd�q�̂Ԃ�����ł���ۂɌ����o��Ƃ����������g���Ă��܂��̂ŁA��ό������悭�A���A�����̓��œd�q�Ɛ��E�̈ړ������ł�����A���邱�Ƃ��Ȃ��A���Ɏ����������Ƃ�������������܂��B
�@
�@�ł�����ALED�̓������w�ȃG�l�x�ł��邱�Ƃł��B�������w�����������x���Ƃł��B
�@�d���͂����ςȂ��ɂ���A�q�������g���ׂ��Ȃ�A�K����܂��B�u���������l�ł��B
�@���[�������Ȃ�ƁA�`�J�`�J���o�܂��B
���̓_�ALED�̎����͑��̂��̂�萔�{�����������̂ł��B
�@LED�ɂ�R�EG�EB�i�ԐF�A�ΐF�A�F�j�̌��̂R���F���o�����̂�����܂��B
�@��ԍŏ��ɔ������ꂽ�̂͐ԐF�ł����B�ԐF�͂S�O�N�قǑO�ɏ��i������܂����B
���̌�A�ΐF����������܂����B�ԂƗΐF���������܂��Ɖ��F�ɂȂ�܂��B���FLED���o���܂����B
�@��ԓ�������͍̂���̃m�[�x���܂ɂȂ����FLED�ł��B
�Ȃ��F���Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ������̂��ƌ����܂��ƁA�����͔g�����Z���A����ɍ����ޗ����Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ������̂ł��B���̑f�ފJ����i�߂��̂��ԍ�搶�ƓV��搶�ł��B
�����T�t�@�C�A����ԗǂ��悤�ł��B���̏�������K���E���Ƃ��������̂����܂����A�V���R����Q���}�̂悤�Ȕ����̂ƈႢ�A�����Ȍ����ŁA���q�z������Ԃ̂��̂��Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ������悤�ł��B���̕\�ʂ�P�^��N�^�̕s���������A�d�ɂ𒅂���Ɗ����ł��B���̍�Ƃ���肭�i�܂Ȃ��āA����J����܂����B���̕ӂɂȂ�Ɠ���Ă悭�킩��܂���B
�@�F���ł����̂ŁA�ԐF�A�ΐF�̂R���F��LED����ɓ���悤�ɂȂ�A�������̂��ׂẴJ���[�̕\�����\�ɂȂ�܂����B
�@���Ȃ݂ɁA���F��̂ɁALED�ł͓�̕��@������܂��B
��́AR�EG�EB�i�ԁE�E�j�̂R���F��LED����ׂāA�����ɓ_�����A���������i�����j����Δ��F�ɂȂ�܂��B���̕��@�́A���̐F���������R�ɕω������邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�����̕��͋C�ɍ��킹�āA�F���������R�ɕς��邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�ŋ߂̔��FLED�͐F���o��LED�̕\�ʂɉ��F�̌u���h����h�z���A�u���h���ɐF�̌��������邱�ƂŁA���F�Ɍ����ϊ�����܂��B���̕��@�͈����ł��̂ő����p�����Ă��܂��B���FLED�̑f�q�̕\�ʂ�����Ɖ��F���u���h�����h���Ă��܂��̂ŕ�����܂���B
�@���āA�������ȑO�A�����̏܂����ۂ̃X�s�[�`���V���ɍڂ��Ă��܂����B
�@�w�l�ԁA�₯�����ɂȂ��ĕ����ɐ[���̂߂荞�܂Ȃ��ƁA�펯��ł��j��u���[�N�X���[�Ƃ������̂͐��܂�Ȃ��x�ƌ����Ă��܂��B
�@����Ɠ��l�Ȍ��t������܂��B
���E��̔����̃��[�J�ł���C���e���̌��В��A�A���h�����[�E�r�E�O���[�u�́A�w�J���҂̓p���m�C�A����x�ƌ����܂����B�w�p���m�C�A�x�Ƃ́w�Ύ����x�Ƃ����Ӗ��ł��B
�@�Ύ����Ƃ́A�w�e�ڂ��U�炸�A���̓��ɖv���ł���l�x�Ƃ����Ӗ��ł��B
�@�ӂ���̌��t�ɁA���ʓ_������悤�ł��ˁB
�R�l�̐搶���̎�܁A���߂łƂ��������܂��B
|
2014�N9��15���i���j
�o�C�I�}�X���d���āA�����m�ł����H
�@ ���͂߂�����������Ȃ�A������������������قǂɂȂ�܂����B���N�̏H�́A�ǂ���瑁���������ł��B
�@�䂪�Ƃ̖�ؔ��ɂ́A�_�C�R���A���J�u�A�ԃJ�u�A�L���x�c�A�n�N�T�C�A�C���Q�����A�H�L���E���A�T�c�}�C���A�i�X�A�ق���A�ɂ�ɂ��A�킯���A���m�c�l�M�A�l�M�A�C�`�S�A�ʂ˂��Ȃǂ̖����������A�肪�o�����̂���A�H�i�X�̂悤�ȉĂ̖�̖��c�̂��̂܂ŁA�����������Ă��܂��B
�@
�@��N�́A�H�̔ފ݂̍��A�펪��������̂ł����A���N�͋C����������܂����̂ŁA���������ڂɎ�܂������܂����B
�@�����́A��A��i���j������o�����t���ρi�V��j�ɗ����Y�ݕt���܂��B��������ƁA�P�T�ԂقǂłP�������炢�̏����ȗc������̐����_�i���̒��S�j��H�ׂ܂��B������H�ׂ���ƐA���͏�肭�炿�܂���B�������A��̗��ꂩ�炷��ƁA���̐����_����Ԕ��������A��ԉh�{���̍��������ɂȂ��Ă���̂ł��傤�B���R�E�̐��������͂��������̂ł��B
�@���N�͂�������h���z�i�ԁj��킹�āA��̔�h���ł��܂��B
�@���āA�ǂ����Ă��C�ɂ����邱�Ƃ́A��͂茴����d�͋����̂��Ƃł��B
�@���̍ɂȂ��āA��T�̓��j���ɁA�w�d���R��x�ƌ�����d�C��C�Z�p�҂R���̍��Ǝ������Ă��܂����B���̎��i�́A�d�͋����̎d��������̂ɕK�v�Ȏ��i�ł��B�d�C���Ǝ҂ƌ�����d�͉�Ђ�A�d�C�̏���҂̂��߂̔z���ȂNj��d�ƌ����镪��̎��i�ł��B
�@
�@���X�A���̂��߂ɁH�Ƃ������Ƃł����A���i�ۗL���g�ׂ̈ɂȂ�킯�ł͂���܂��A���̑̑��A���t���b�V���ɂ͑傢�Ɏh����^����Ə���Ɏv���ď��������Ă��܂��B
�@�]�݂͉���Ƌ��ɂǂ����悤���Ȃ������������Ă��܂��B�܂����o���������Ȃ�A�L���͂̒ቺ���������ł��B�L������̂Ɏ��Ԃ��|����A�J��Ԃ��A����Ԃ�����āA����Ɖ��������L�������ƌ����n���ł��BSD�������[�J�[�h�̂悤�ɁA��x�L�^����Ώ������Ȃ�����A���܂ł��L�^�����̂��A�܂�������ł��B���ꂪ���g�ƃf�W�^���@��̑傫�ȈႢ�ł��B
�@����ƁA���X�|���X�̐����ł��B��������ǂ�ł��A�Ȃ��Ȃ����ɓ��炸�A���Ԃ�������܂��B�ł����玎���ł́A�������Ԃ��s���ɂȂ�܂��B�����n���f�B�[�����Ē�����A�L��̂ɁA�Ǝv���Ȃ���`�������W���Ă��܂��B
�@
�@������������ۂƐ���āA���킵�����Ă��܂��B
�@�Ƃ����̂́A�����͂S�ȖڂŁA��b�i�d���C�w�j�A�d�́A�@�B�A�@�K�ł��B��������ׂč��i���Ȃ���Ȃ�܂���B�Ȗڍ��i�Ƃ������x������A�Ȗڂ��ƂɁA���i�_�ȏ�Ȃ炻�̉Ȗڂ͍��i�ƌ��Ȃ���܂��B�������A�L�������͍��i�����N������ĂR�N�Ԃł��B���̂R�N�Ԃɂ��ׂĂS�Ȗڍ��i�ł���Ύ��i���t�^����܂��B
�@���N�łT�N�ڂɂȂ�A���܂łS�ȖڑS�č��i���܂������A�c�O�Ȃ���R�N�Ԃŏ�肭�Ȗڍ��i���g�ݍ��킳��Ȃ��āA�ȑO�A���i�����Ȗڂ��������Ă��܂��A�ēx�A���̉Ȗڂ��܂߂āA���Ȃ���Ȃ�܂���B���̌J��Ԃ������Ă����ԂŁA���N�͖@�K�����c���Ă��܂������A����Ɏ��s���A��N�͊�b�Ɩ@�K�̂Q�Ȗڂ��āA�@�K�͂���ƍ��i���܂������A��b�͎��s���܂����B�����č��N�́H
�@��b�ƁA�d�͂Ƌ@�B��3�Ȗڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ���ԂɂȂ�A3�ȖڂɍĒ��킵�܂����B
�P�Ȗڂ��P���Ԕ��i�X�O���j�ł�����A�R�ȖڂȂ�A�S���Ԕ��ł��B�V�O�Β��̐g�ɂ͊����܂��B
�@���ʂ�10�����ɏo�܂��B���́A�ЂƂ܂��������A�{�P�[�Ƃ��Ă��܂��B
�@
�@���āA�����̘b�ɂȂ�܂����A�����{��k�Ќ�̕������q�͔��d�����≷��~�Ɏ��s���A���̌�A���f�������N������A�̑厖�̂��瑁�����A3�N�ڂɂȂ�܂��B�����ɁA���q�F���₵�������Ƃ������Ă��܂����A�w�l�̉\��75���x�Ɛ̂̐l�͌����܂������A�������̘̂b�́A���㉽�\�N�A���S�N�ƌ�葱������Ǝv���܂��B
�@
�@�Ȃ�Ƃ��Ō�̈���ōň����Ԃ�Ƃꂽ�����������̂��A������s���Ɍg����Ă���l�������ǂꂾ�����q�͂̕|���𐳂����������Ă���̂��H�^��������Ă��܂��B�X�ɁA�ނ�͊��ɕ|����Y�ꂩ���Ă���悤�ɂ������܂��B����ł����̂ł��傤���H
�@�����A����}�͐�������Ɏ��̂��N�����̂ŁA�̂�ׂ����Ǝv���܂����A�����}������}�͐ӔC���Ȃ�����̎��̂��������߁A�����܂�؎��Ɋ����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�@���̒���̌��q�F�̏�Ԃ��h���h���������钆�ŁA�L���Ȏ藧�Ă������Ȃ��������Ƃ����A�悭�v���o���āA���q�͂̕|���ƁA�Ȋw�Z�p�̌��E���悭�l���鎞���Ǝv���܂��B
�@�Z�p�͂����܂őz�肵���i�v�j��l���ň��S�ƌ�����b�ł����āA���R�̗͂͑z���y���ɒ����邱�Ƃ����܂��܋N����܂��B�����z��O������ƌ�����̂́A���q�͈ȊO�̐ݔ���C���t���ɂ��Ăł��B
�@���q�͊֘A�̃C���t���͑z��O�̂��Ƃ��N���Ă��Ώ��ł��Ȃ��Ă͑厖�̂ɂȂ���܂��B�z�背�x���������������قLj��S��͏オ��܂����A�c��ȃR�X�g��������A���ƃx�[�X�ł͐��藧���Ȃ��Ȃ�܂��B
�@���܁A���q�͈��S�ψ����K���ψ���e�n�̌��q�F�̍ĉғ��Ɍ����āA�������s���Ă��܂��B�R�����x����R����͈ȑO�ɔ�ׂđ����������Ă��܂��B
�@�������A���{�̍��y�́A���f�w��A�n���K�͂̃v���[�g��A�ΎR��A�Ôg���ǂ���Ƃ��Ă����E���ōň��̓y�n�Ȃ̂ł��B
�@���E�ɂ͒n�k��m��Ȃ��ňꐶ���I����y�n����������܂��B�t�ɖ����n�k������͓̂��{�ł��B�����������ِ��ƌ�����y�n���̓��{�Ō������ĉғ������邱�Ǝ��Ԃɑ傫�Ȗ�肪����Ƃ����l���Ă��܂��B�ĉғ��͉��������Ă����ł��B
�@���̔������̂ŁA�����d�͊����⌴�q�͈ψ���̈ψ���A�����̐��{�W�҂́A���̓����A�w�F�S���j��A�����{��т͐l���Z�߂Ȃ��y�n�ɂȂ�x�Ɩ{�C�ɍl�����͂��ł��B�@���q�͈ψ���̈ψ����������ǖڈψ�������������������\���Ă����܂��B
�@�K���ɂ��A�|�S���i�����R�O�����ȏ������j�̘F�S�́A��̕������P�V�O�O�x�ȏ�ɂȂ鍂���̃E�����ɂ���ėn���A�R��������o���A���̊O�������������̃R���N���[�g���̗e��i���͗e��j���Ńh���h���ɗn���Ă����͂��ł��B���g�͒N�����邱�Ƃ͂ł��܂���B
�@�Ȃ�Ƃ����ƁA���\�������c���A���x�������邱�Ƃ��o�����̂ŁA���ݗ��܂����Ƃ����b�ł��B����́A�C���������t�����A�E�����̉��x�������邱�Ƃ��ł�������ł��B
�@�����A�C���̒��������������x��Ă���A���͗e��̃R���N���[�g���n�����āA�w�`���C�i�V���h���[���x�ƌ����鎖�ԂɂȂ����͂��ł��B�����Ȃ�A�h���h���̃E�����R���͈͂��̂Ȃ���ԂɂȂ�A�n���[���ǂ�ǂ�Z�����A�c��ȕ��˔\���Ԃɂ킽�蔭�U���鎖�ԂɊׂ����ƍl�����܂��B�n�������ǂ��Ȃ��Ă���̂�������܂���̂ŁA�ǂ̂悤�ɉ������L���邩�A���������Ȃ���ԂɂȂ��Ă����ł��傤�B�n��ł́A���Ȃ��Ă����a�A���\�����͏Z�߂Ȃ��Ƃ�����ԂɂȂ����͂��ł��B�ꍇ�ɂ���ẮA�������_���ɂȂ�����������܂���B
�@�\�A����̃`�F���m�u�C���������̂��悭��r�ɋ������܂����A�����̍\�����Ⴂ�܂��B�@�`�F���m�u�C���^���q�F�́w�����F�x�ƌĂт܂��B���{�͉������^�ƕ������^��2��ނ̌��q�F������A���������킹�āw�y���F�x�ƌĂ�ł��܂��B
�@���{�́w�y���F�x�́A�F�S�̍|�S���̗e����ɐ������A���̒��ɔR���_������\���ɂȂ��Ă��܂��B���̐��̓E�����̊j����Ŕ�������c��ȔM�𐅂̕�������G�l���M�[�ɒu�������āA�����i���S�x�j�̐����C�ɂ��āA���C�^�[�r�����A���d�@���Ƃ����\���ł��B
�@���̌y���i���ʂ̐��̂��Ƃł��j�ɂ͂��������������܂��B�R���̃E�����Q�R�T�͏펞�A�����q�Ƃ������ː����o�������Ă��܂��B���̕��ː��̔�яo�����x�������ƁA�����̃E�����Q�R�T�ɋz�����ꂸ�j����͋N���܂���B���鑬�x�̒����q�i�M�����q�ƌĂ�ł��܂��j�ɂȂ�ƁA�E�������q�j�͒����q���悭�z�����A�j���n�܂�̂ł��B
�@���͒����q���z��������A���x��x�����铭��������܂��B�ł�����A���́w�����ށx�Ƃ��Ă�ł��܂��B���͊j�����A�����Ĕ��������邽�߂ƁA�j����Ő�����M�G�l���M�[���O���Ɏ��o����̓���������̂ł��B
�@�`�F���m�u�C���̍����^�����́A�����g�킸�ɒY�f�i�����j�������ނɎg�p���Ă��܂��B���A�\�A���J�����������ɍ̗p����Ă�������ł��B�R���_����j����̔M�����o�������͒��f��Y�_�K�X�̂悤�ȋC�̂��g���Ă��܂��̂ŁA���q�F�̍\���͑S���قȂ�܂��B�ł�����A���̂̋N���������{�̕����̎��̂Ƃ͑S���������Ԃł����B
�@�v�́A���q�͂͐l�Ԃ̐��䉺�ɂ���A���Ƃ����S�Ɏg����G�l���M�[���ƌ����܂��B
�w���Ƃ��g����x�Ƃ����Ӗ��́A�R�������i�����x�����ː��p�����j�̌�n���A��Еt���̎d���������ɐ��E���ł����܂��Ă��܂���B���w�g�C���̂Ȃ��}���V�����̂悤���x�ƌ����܂������A���̒ʂ�ł��B
�@
�@���q�͔��d�́A���d�R�X�g�������A���݂̓d�C�G�l���M�[������ɋ������邽�߂ɂ͕K�v�A�s���Ȏ�i���ƌ����Ă��܂��B�����x�����ː��p����������p���ǂ̒��x�����邩�A�R�X�g�v�Z�ɂ͏\�����f���Ȃ��ŁA�����̓d�C�͈����ƌ����Ă���̂ł��B�����������O�ŁA�����}�͌����ĉғ���ژ_��ł��܂��B
�@
�@�������A��U���̂��N����ƁA���������̌���ŋN���Ă���Ƃ���A�����ɗ�₵�����A���������̍ۂɐ����鍂�Z�x������������ɂQ�O�O�g�������܂��Ă䂫�܂��B�h�����ʂɂ���Ζ����A�P�O�O�{�����������Ă���̂ł��B���������̎ʐ^������킩��Ƃ���A�������ӂɂ̓^���N�̌Q�ꂪ�o���Ă��܂��B���ꂪ���Z�x�������Ȃ̂ł��B�^���N�������̌����Ŕj���A���������C�ɗ���o�܂��B
�@���̂܂܂ł̓^���N�̒u���ꏊ���Ȃ��Ȃ�̂ŁA�n�����������~�߂āA�������̗ʂ����炻���ƁA�y�n�𓀂点��Ƃ��A�㗬�őg�ݏグ�Ēn�����̗��ʂ����炻���ƁA�����Ȏ藧�Ă����������Ă��܂����A�c��ȃR�X�g���|�����Ă��邱�Ƃ��l���Ȃ���Ȃ�܂���B���ׂẴR�X�g�͓��d�̓d�C��ɂ����グ����Ă��܂��B
�@�l�͂悭�w�A��������A�M���Y���x�Ƃ����܂��B
�@���̂��N�������A���������œ����Ă����l�͎����o�債���ƌ����Ă��܂��B����������@��Ԃ���A�������������Ă����ƌ����܂����A�܂������͊��S�ɐ��䂳�ꂽ��ԂɂȂ��Ă��܂���B�l�Ԃ̗́i�m�b�j�ƁA���q�͂̂��߂������������Ă��܂��B
�@����ɂQ�O�N�A�R�O�N�Ƃ�����悤�ł��B�c��ȋ��������Ȃ���A��������̐l�����ː��𗁂тȂ��瓭���Ă���̂ł��B
�@�����������Ă���Ǝv���܂��H
����ƁA�א삳�E�����ŋ������n�߂܂����B��ό��\�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B
�@���āA��ԑ����d�͂��g���^�Ă��A�����[���ŏ��邱�Ƃ��ł��܂����B���d�͂͌����ˑ��̔��d�ʊ����������̂ŁA�������~�܂�ƁA�d�͂̈��苟���������ƌ����Ă��܂������A�����Ă͏I���ł��B�ߓd��A�ȓd�͋@��̕��y��A��Ƃ̐ߓd�w�͂łȂ�Ƃ��N���A�ł��܂����B�f�[�^���������ł́A�܂������]�T�����������悤�ł��B���܂ŁA���d�͂̓I�[���d���ȂǓd�C�������ɑ�ʂɎg�킹�邩���`���Ă��܂����B
���A�e���r�Őߓd�̂��肢��CM�ŗ����Ă��܂��B
����́A�d�C�G�l���M�[�͒l�i�����ł͂Ȃ��A��Ȏ������Ƃ������ɕς����邱�Ƃ������Ă��܂��B���ʂȃG�l���M�[�͎g��Ȃ��Ƃ����q�������ɑ��鋳����O�ꂷ�邱�Ƃ���ł��B
�@�O�u���������Ȃ�܂������A���ꂩ�炪�{�_�ł��B
���������ɑ���Đ��\�G�l���M�[�ɂ��Ē��ׂĂ݂܂����B
�@���R�G�l���M�[�ɂ́A���z�����d�A���͔��d�A�n�M���d�A���͔��d�A�g�����d�i���͔��d�̈��ŁA�㉺�Ƀ_����A���Ԃ͏㗬�̃_���̐��𗬂��Ĕ��d���A��d�C���]���Ă��鎞�ɁA�����̃_���̐����|���v�ŋ��ݏグ�ď㗬�_���ɒ��߂�����ł��j�A�g�Q���d�i�g�̗͂Ŕ��d����j�Ȃǂ�����܂��B
�@���̓��A�X�ю����ł���؍ނ̎c�ނ�Ԕ��ނ��R����^��ŁA�R�₵�Ĕ��d�������������܂��B���̉Η͔��d���ł����A���d����d�͗ʂ͑�^�Η͔��d����1/10����1/100���炢�̋K�͂̂��̂ł��B
�@�O���Y�̈����؍ޗA���ɂ���āA���{�̗ыƂ͊��肪����Ȃ��Ȃ�A�X�т͍r�����ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�@�X�т͔��̂⏜�����������Ă��Ȃ��ƁA�ǎ��̖؍ނ����܂���B�܂��A�ыƏ]���҂̍�����������Ă��܂��B
�@�����ŁA2012�N�ɍĐ��\�G�l���M�[�Œ蔃�搧�x�iFIT)���X�^�[�g���A2014�N�ɂ�FIT�F�肪156���ɂȂ�܂����B����ɂ�锭�d�ʂ͍��v��156��KW�ƂȂ��Ă��܂��B���q�͔��d������Q��ɑ������܂��B
�@�R������ł��邾���^���ɋ���������Ȃ��y�n�ɁA��r�I�����Ȕ��d��������������̂����ʓI�������ł��B�܂��A�Ԕ��ނ�p�ނȂǎ�ɓ������ʂɌ������K�͂̔��d�����e�n�ɓ_�X�Ƒ���Ƃ����l�����ł��B����ɂ��ыƂ̏]���҂𑝂₵�A��������}��A�̎Z���m�ۂ���Ƃ������̂ł��B
�@
�@�������A�����ʂ̉������Ȃ��ƁA�Ȃ��Ȃ��̎Z�������܂���̂ŁAFIT���F�肵�A�F�肳���Γd�͔��旿������ʂ̓d�͗�����荂�����Ă��炦�鐧�x�ł��B�]���̓d�͗����ɏ��������グ���邱�ƂŁA���R�G�l���M�[�̔��d�ʂ𑝂₵�Ă䂱���Ƃ������g�݂ł��B
�@����͑��z�����d�ɂ����Ă��A�S�����l�̏��u���Ƃ��Ă��܂��B
�@�܂��܂������ȉۑ肪�c����Ă���悤�ł��B�����Ɉ������d�ł��邩�H�����Ɉ��肵�ĉ����ł��邩�H���ۑ�ł����A���{�̐X�т��ۑS����A�ыƂ����͉����A�z�^���d�V�X�e�����\�z�����Αf���炵�����Ƃ��Ǝv���܂��B
�@���̂��߂ɂ́A�؍ނ������悭�R�₹��{�C���[�̊J����A��r�I���^�ō������^�[�r���̊J����A�؍ނ�X�т�����o���������[�v�E�F�C�Ȃǎ��ӋZ�p���J������ۑ肪����܂��B
�@����Ă��܂��āA�ÎR�ɂȂ��Ă��܂����I�̂ł͑S���Ӗ�������܂���B�X�т����C�Ɉێ����A�d�͋������ł���Ȃ�A�f���炵�����Ƃł��B
|
2014�N9��5���i���j
Technics���ēo��A�����ł��邩�H
| �@Panasonic�́A���X�x�K�X��CE�V���[�ƕ��сA���E�Q��R���V���[�}�[�V���[�i�ƒ�d�����i�W����j�̈�ł���h�C�c�̃x�������ŊJ�Â����ʏ́A�x�������V���[�i�����ɂ́@IFA�i�C�[�t�@�[)�j�ŁA �uTechnics�u�����h������v�Ɛ����ɃA�i�E���X���܂����B���V���Ŋ��B
�����I�[�f�B�I�́A���E�I�Ɍ���A���\���������肵�����v������܂��B ���A�S���E�Ŗ�1000���~�s��ƌ����Ă��܂��B
�@�Z�p�i���ɂ��A�A�i���O�����Hi-Fi�Ƃ����T�O�ł͔�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��f�W�^���Z�p���g�������������x�i�����𑜓x�j�̃I�[�f�B�I���g�߂ɂȂ��ė��܂����B
�@�@�i���j�w�n�C���]�x�Ƃ̓n�C���]�����[�V�����i���𑜓x�j�̈Ӗ��ł��B
�@��b�ɂȂ����̂́ACD�i�R���p�N�g�f�B�X�N�j�̃f�W�^���Z�p���A1980�N�ɊJ������܂����B�@�@�]�k�ł����ADVD�͉摜����舵���ƌ������ƂŁA���ʂ���C�ɑ傫���Ȃ�ACD���f�[�^��700MB�ɔ�ׂāA4.7GB�ƁA��7�{�̗e�ʂ�����܂��B
�@����CD���x�[�X�Ƃ��Ĕ��W���Ă����f�W�^���Z�p�́A���y����f���ɍL����A �ɂ��g�߂ŗe�ՂɒN�ł��g���鏤�i�ɂȂ�܂����B
�@�f����DVD�Ŋm�������Z�p�́A����Ƀn�C�r�W�����摜�^�ėp�Ƃ���
BD(�u���[�f�B�X�N�j�ɂȂ�AHD�摜�܂ʼnƒ�ŊȒP�Ɋy���߂鎞��ł��B
�@�����ŁA�����ɖڂ������܂��ƁACD�́A�T���v�����O���g�����S�S�D�PKH�� �ł��̂ŁA�Đ����g���͂Q�OHz�`�Q�OKH���܂łƂȂ�܂��B
�@�ʎq���r�b�g�ƌ�����K�i���P�U�r�b�g�ł����B
�i���߁j�T���v�����O���g���Ƃ����̂́A�A�i���O�̘A�������M�����ׂ����蕪����ۂ̎��g�@�@���ŁA�T���v��������g���Ƃ����Ӗ��ŁA�����������O���t���Ă��܂��B���R�A�T���v�����@�@�͑������������ɃA�i���O�̐M����\���ł��܂��B
�@�@�ʎq���r�b�g�Ƃ������̂́A�T���v�����O�����f�W�^���M���̑傫�������i�K���ɕ�������
�@�@�f�[�^������̂ł����A���i�K�ɕ�����̂���\������K�i�ł��B
�@�@������A�T���v�����O���g���Ɠ��l�ɂ�������ɕ����������قǁA���̃A�i���O�M����
�@�@�召�𒉎��ɍČ����邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�@�f�W�^���I�[�f�B�I��A�f�W�^���f���ł́A���̓�̎w�W�i�T���v�����O���g���ƁA�ʎq�@�@�@���r�b�g���j���L�^�E�Đ��܂��͘^���E�Đ�����ꍇ�̒����x�����߂�傫�ȗv�f�ł��B
�@�@������̗v�f�Ƃ��āA�`�����x������܂��B
�@�@�T���v�����O���A�ʎq�����ꂽ�f�W�^���M���͔��ɑ�ʂ̃f�[�^�ʂɂȂ�܂��B
�@�@���̑�ʂ̃f�[�^���L�^�i�^���j��Đ�����ꍇ�ɁA�C���^�[�l�b�g��ACD��DVD��BD��
�@�@���̑��̋L�^���f�B�A�iSD�J�[�h�A�e�[�v�AUSB�Ȃǁj����o���̑��邱�Ƃ��K�v�ł��B
�@�@���̐M���̑���M���x��1�b�Ԃɂǂꂾ����������邩���ۑ�ɂȂ�܂��B
�@�@CD��DVD�Ȃlj��L�̒ʂ�̋K�i�ɒ�߂��Ă��܂��B
�@�@�ŋ߁A�f�W�^���Z�p�̐i���ŁA���̓`�����x�������Ȃ�A�܂��܂������\�����Ă��܂��B
�@CD�����܂ꂽ�����i1980�N���j�̋Z�p�̌��E�ŁA�P�Q�����̃f�B�X�N�P���ɁA �x�[�g�[���F����X�����i��S�U���j���[�܂�悤�X�y�b�N���܂Ƃ߂��������Ă��܂��B
�@�ŋ߂̃f�W�^�����p�̐i���ŁADVD��BD�̂悤�Ƀf�[�^�ʂ������Ă� �e�ՂɑΉ����ł���悤�ɂȂ�܂����B�������A���i�Ƃ���ɂ́A�f�t�@�N�g�X�^���_�[�h�����邱�Ƃ��d�v�ł��B
�f���̐��E�́A�n��g�f�W�^���̕��y�ň�C���Y��ȃn�C�r�W�����f�����y���߂�悤�ɂȂ�܂����B���{�ł́A�S�Ẵe���r�������f�W�^�������A���E�ň���Y��ȉf�����y���߂Ă���Ǝv���܂��B�X�ɁABD�ƌĂ��n�C�r�W�����f���𐔔{���ꂢ�ɂ����摜���y���߂܂��B
�������A�d�g�ɂ������́A�������邽�߂ɕK�v�ȓd�g�̕���K�v�Ƃ��܂��̂ŁA�ނ�݂ɑ��邱�Ƃ��ł��܂���B�Z�p�I�ɂ͉\�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�����I�����s�b�N�ł́A���̃n�C�r�W�����f����4�{�Ƃ�8�{�̉𑜓x���������摜���e���r�Œ��p���悤�Ƃ����b���i��ł��܂��B�f���̐��E���ǂ�ǂ��Y��ɂȂ��Ă䂫�܂����A���̐��E���Z�p�I�ɐi��ł��܂����B
�@�����ŁA�ŋ߁A�o����Ă��������Ƃ��āACD�̖�R�{�A��U�{�̃f�[�^�� �g���n�C���]�����[�V�����i�n�C���]�j���������ڂ𗁂тĂ��܂����B���łɁA���Ђ������C���^�[�l�b�g����Ŕz�M���n�߂Ă��܂��B �l�b�g����_�E�����[�h�ł��܂����A�������A�L���ł��B
�@�n�C���]�����P�G�T���v�����O���g���@96KH���A�ʎq���r�b�g���G�Q�S
�@�n�C���]�����Q�G�T���v�����O���g�� 192��Hz�A�ʎq���r�b�g���G�Q�S
�̂Q��ނ�����܂��B ����A����ɑ����邩������܂���B
�@CD�́A
�@�@�@�@CD�@�@�@�@�@�G�T���v�����O���g��44.1KH���A�ʎq���r�b�g���G16
�ƂȂ��Ă��܂��B
���̂悤�ȑ�ʂ̃f�[�^��]������ɂ́A�����̓`���n���K�v�ŁA ���b�A�n�C���]�����ł́A��4.6Mbps��9.2M�������ƂȂ��Ă��܂��B���Ȃ݂ɁACD�́A��1.4M�������ł����B
�@���̂悤�ȑ�ʂ̃f�[�^���l�b�g�����P�[�u���Ȃǂ�ʂ��āA�_�E�����[�h�ł���Ƃ����f���炵������ɂȂ�܂����B�������A���ځA�_�E�����[�h���Ȃ��牉�t���ł���̂ł͂Ȃ��A��x�������[�� ����Ă���Đ��i���t�j����Ƃ����g�����ɂȂ�܂��B
�wCD�ƃn�C���]�͉����Ⴄ���x�ƌ����܂��ƁA
�@�@�@���y�̃_�C�i�~�b�N�����W�i�t�H���e�V���ƃs�A�j�V���A�����j��c�Ȃ��������Đ��ł���B �@�@�A�����̎��̃o�b�N�m�C�Y���S���ƌ����Ă����قǂȂ��B
�@�@�B�Đ��\���g���͈͂��ǂ̂��炢�L���B
���̂R�_�ł��B
�n�C���]�́ACD�ɔ�ׂāA
�@�@�@�ł͂P�O�O�{����P�O�O�O�{
�@�@�A�ł́A�P/�P�O�O�ȉ�
�@�@�B�ł́A�S�OKH��-�X�OKH���܂Ŋ��S�t���b�g�ɒ����ɍĐ��\�B
�@�@�@�@�l�Ԃ̎��ŕ���������g���͈͂�y���ɒ����Ă���B
�@�������A���̂悤�Ȓ������\�������茳�ɂ����Ă��A������Đ�����A���v���X�s�[�J�Ȃǂ��A���\�I�Ɍ������悤�ȑΉ��ł��Ȃ���A�����Ă��Ⴂ�͕�����܂���B
�X�ɁA�f�[�^��ł́A���̒��o�\�͂��͂邩�ɏ�����̂ł�����A�Ⴂ���ǂꂾ�������邩�ǂ����́H�H�H�ł��B
�@�ł��A�������i���y�j���̂́A�����������ɍ��܂�Ǝv���܂��B���������Ӗ��ł́A���[�J�́w�n�C���]�x��V��������Ƃ��āA�����I�[�f�B�I�� ���E���ė�����������_���Ă��܂��B
���ہA�I�[�f�B�I�}�j�A�������܂ŁA�ǂ������Ă��Ă���邩�ǂ����́A����� ���Ȃ��ƕ�����܂���ˁB
�f�[�^��ł́A���ɑf���炵�����̂ł��B
�����������ɁH�̃I�[�f�B�I�V�X�e�����Ƃɔ�������Αf���炵���ł��ˁB
�ł��A�����������߂ɂ́A�܂������̉�������n�߂Ȃ���A������Đ��V�X�e�����f���炵���Ă��A�����������ɂȕ������Ȃ��Ǝv���܂��B
���͋�ԂōL����A���˂��J��Ԃ����ɓ�����̂ł�����A�����̕ǂ⏰��V��Ȃǂ̔��˂Ƌz���̓��������ɂȂ�܂��B�������������̕��������������߂̑傫�ȗv�f�ɂȂ�܂��B�ł�����܂��A���y���Y��Ɋy���߂镔���̍H�v����������āA���ɑf���炵���f�W�^�������ŁA�f���炵���V�X�e���ʼn��y���A�Տꊴ���ӂ�鉹���y���߂�Ǝv���܂��B
�@�{���̂������y���A�y���ނ��߂ɂ͂������|����܂��ˁB
|
2014�N�X���R���i���j
�s�����ۑގ��͈ꔭ�Ő����B
���g���W�I������FM�ŕ�����悤�ɂȂ�܂��B
�@�U���P�Q���̂��̃y�[�W���A�s�����ۂ̑ގ��ɂ��ď����܂������A�W�����{�Ɉ�@�ɍs���A�s�������������Ă��炢�܂����B
�@�����͊ȒP�ŁA�H�����ċ�Ԃɂ��āA����Ȏ��܂ɑ��𐁂�����Ŗc��܂��܂��B���̌�A�������܂��P������ŁA���̂��������ɂ��ĂP�O���ԁA�x�b�h�ʼn��ɂȂ�A�X�ɏ�����ĐQ�ĂP�T���Ԃ����Ƃ��Ă���A�N���オ���āA��قǖc��܂����̂Ɠ����悤�Ȏ��܂ɑ��𐁂����݂܂��B���̑܂������@�ւɑ����āA�P�T�Ԍ�Ɍ��ʂ��o�܂��B
�@�K���ɂ��A�P��̏��ۏ��u�ŁA�������ʂ��}�C�i�X�ł����B�����ގ����ł��܂����B
���̃s�����ۑގ��́A��i�R�������j���P�T�Ԉ��ݑ����܂��̂ŁA�l�ɂ��Ε���p�Ƃ��āA�������ւ╠�ɂ��N���邻���ł����A������S���Ȃ��ł����B
�@�s�����ۑގ��́A�ǂ������킯���m��܂��A2���x�Ƃ������Ƃł����B
�@�����A���Ɛ��̃J�X�s�C���[�O���g�i��_�̃f�p�n���Ŏ�ۂ��Ă��܂��j��H�ׂĂ���̂��A�ǂ������̂����m��܂���B
�搶�̘b�ł́A�w���őގ��ł��ă��b�L�[�ł����ˁx�ƖJ�߂��H�܂����B
�@���̘b��ł����A�R��14���A���̃y�[�W�ŏЉ�܂������g���W�I�����̕⊮�����Ƃ��āAFM�������������Ƃ����L�����ڂ��܂����B�����n��ł́A�X�J�C�c���[���痈�N�t�A�S�����H����d�g���o��悤�ł��BTBS��90.5MH���A����������91.6MH���A�j�b�|��������93.0MHz�ƂȂ��Ă��܂��B
�@���̕⊮�����́A�S���I�ɊJ�ǂ��Ă䂫�܂����A���g���̓A�i���O�e���r���g�p���Ă������[�`�����l���т��g���܂��̂ŁA���ꂩ�烉�W�I���l�́AFM���������Ȃ��Ă�95MHz�܂Ŏ�M�ł��邩�ǂ����m���߂Ĕ����悤�ɂ��ĉ������B�]����FM�����̎��g����76-90MHz�ƂȂ��Ă��܂��̂ŁA���W�I�ɂ���Ă͂��̎��g���т�����M�ł��Ȃ����̂�����܂��B
�v���ӂł��B
�@���n����A���ꂩ��������n�܂�Ǝv���܂��B
�@
�@���W�I�����́A�ʏ�̒��g�̕����ɉ����āAFM�����A�C���^�[�l�b�g�ł̔z�M�ȂǁA���l�����܂��BNHK�͊��ɁA���W�����W���ŃC���^�[�l�b�g�z�M�����Ă��܂��ˁB
http://www3.nhk.or.jp/netradio/
�{���̂����ܘb�ł����B |
2014�N�X���Q���i�j
�w�H�ו���]�x��w���ݕ���x���l����
���̒����}���ɕω���i���𐋂��Đi��ł��܂��B���̕ω��̑����́A���܂Ől�ނ��o���������Ƃ��Ȃ������ł��B���܂�ɑ����X�s�[�h�ŕω����Ă���̂ŁA�Ȃ�����ɂȂ����悤�ł��B�ڂɂ͌����Ȃ��Ă��A�ω����h���h���i�݂܂��B
�@����ŁA���܂�ω����Ȃ������╪�������܂��B�ω����Ȃ�����ɐg��u���Ă���ƁA�T�N�A�P�O�N�Ƃ��������Ō��Ă��A���܂艽�����ς�����I�Ƃ����������������Ȃ��ł��傤�B
�@�������͕ω���������A�C�Â��A���ނ��Ƃ���ł��B�Ƃ��낪�A�Z���������Ă���ƁA�Z�����ɕ���āA���������Ȃ��Ȃ�܂��B���̓��A���̓��邵�ɂȂ��Ă��܂��B���̊Ԃɂ��A���͂���͑傫���ς���Ă���̂ł��B
�@
�@�ω���i���͂����Ȃ��̂�����܂��B
�@�ŋ߁A�x�X�j���[�X�ɂȂ�ُ�C�ۂ̘b�ł����A�n�����g���̐����ǂ����͕�����܂��A��ʂɂ��������o���Ă��܂��B���̒n���K�͂̉��g���ɂ���āA���܂Ōo�����Ȃ������悤�ȓy���~��̉J��A�W�����J�◳�����p�ɂɋN���Ă��܂��B
�@�y���~��̉J�́A�M�т∟�M�ђn���̉J�̍~����ŁA�V�����[�Ƃ����܂��B�ȑO�A�V���K�|�[���ɍs�����ۂɁA�}�ɋÂ��Ȃ�A�o�P�c���Ђ�����Ԃ����悤�ȉJ���~��A�P�T���قǂŐ�ɂȂ�܂����B���n�̐l�͊��ꂽ���̂ŁA�Ԃ��G��ŎP���������ɕ��C�ŕ����Ă��܂����B
�@���{�̉Ăɍ~��J�͗[���Ƃ����������ŁA�Ă̓����̋����������ŋC�����㏸���A�����_���������A���̉��ʼnJ���~��Ƃ������ۂł����B�������A�ŋ߂̏W�����J�͈ȑO�̗[���Ƃ����������ł͒ʂ��Ȃ��悤�Ȉꎞ�ԍ~�J�ʂ�100mm���z���Ƃ������̂������~����ł��B
�܂��A�V�������t�����ɂ��܂����B�o�b�N�r���f�B���O���ۂƂ����炵���̂ł����A�L���̏W�����J�͂��ꂪ�N�����悤�ł��B�����_�����X�Ɣ������A�����ꏊ�ɑ�ʂ̉J���~�点�錻�ۂ������ł��B���������W�����J���A���̉ĂɊe�n�ŋN���܂����B
�@�C�ے������\���Ă���V�C�\����A�����ς���Ă��܂����B�C�ۊϑ��V�X�e�����i��ł��܂����̂ŁA�ԓ����̐Î~�C�ۉq�����F�������ɒn�\���ɂ�ŁA�_�̓����𑨂��邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�܂��A���܂ł̃��[�_�[�ł͌��������Ȃ�����X�o���h�Ƃ����g���̒Z���d�g���g���A�_��J�̍~�����A�~���Ă���n����ڍׂɔc���ł���悤�ɂȂ�A��������X�ƃC���^�[�l�b�g�Ŕz�M���Ă��܂��B���L��URL�ɃA�N�Z�X����A�N�ł������܂��B
�@�@http://www.river.go.jp/xbandradar/
�@����̑�J�̍ۂɁA���̃z�[���y�[�W�Ŋg��}�ɂ��A���s�t�߂����܂����Ƃ���A�J�������~���Ă���Ƃ��́A�m���ɒn�}��ŐF���ς���Ă��܂����B���������֗��Ȃ��̂��g�����Ȃ��A���S�A���S�ɂȂ���܂��B
�@�q���̍��͉Ă̏������A�R�O�x���z���Ɩҏ��Ƃ������o�ł����B�����������́A�Ƃ̑O�ɁA�ł��������ăq���b�Ƃ�����C�������܂����B�܂��A�G�A�R���ȂǂȂ�����ł��B
�@���́A�ҏ��Ƃ����R�T�x�ȏ�ŁA�̉�������R�W�x�A�R�X�x�Ƃ����悤�ȋC���ɂȂ邱�Ƃ��������Ȃ��Ȃ�܂����B
�@�����ŁA��������̐l���S���Ȃ鎞��ɂȂ�܂����B
���܂ł́A�w���˕a�x�ƌ����Ă��܂������A�ŋ߂́w�M���ǁx�ƌĂт܂��B�M���ǂ�����邽�߂ɁA�w�K�x�ɃG�A�R�����g���܂��傤�x�ƌ����܂��B�ŋ߂̃G�A�R���͏ȃG�l�Z�p�̐i���ŁA�����̓d�C��H��Ȃ��Ȃ�܂����B
�@�������A�G�A�R���͎����̔M�����O�ɕ��o����G�l���M�[�̈ړ����s���@�B�ł��B
�G�A�R���͓d�C�ɗ��邱�ƂɂȂ�܂��B
�@���̓d�C�̓R���Z���g�ɂȂ��Βʂ���悤�ɂȂ��Ă��܂����A���͂��̑匳�́A�Ζ���ΒY��V�R�K�X��R�₵�Ĕ��d�����d�C�ł��B
�@���݁A���{�̌��q�͔��d���͓����{��k�Ђ̕�����ꌴ�����̈ȗ��A�S�ĉ^�]���~���Ă��܂��̂ŁA���d�͉��ΔR���ƌ�������̂�R�₵�āA���d����Η͔��d�ɗ����Ă��܂��B�ꕔ�A���͔��d�⑾�z�����d�╗�͔��d�Ȃǂ�����܂����A����͉Η͔��d�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�Η͔��d���͉��ΔR����R�₵�܂�����A�Y�_�K�X����ʂɔr�o���܂��B�Η͔��d���ɂ́A�������т���傫�ȉ��˂��瓒�C�̂悤�Ȃ��̂��o�Ă��܂����A���ꂪ�r�C�K�X�ł��B
�@���̔r�C�K�X�̑啔���͒Y�_�K�X�i��_���Y�f�j�ŁA���ꂪ�n�����g���̌����ɂȂ��Ă��܂��B�Y�_�K�X�́A�n���\�ʂ���M���F����Ԃɓ�����̂�h���z�c�̂悤�ȓ���������܂��̂ŁA���˃G�l���M�[�����Ȃ��Ȃ�A�\�ʂ̔M������ɒ~�ς���̂ł��B�@���̌��ʁA�n����̋C�����㏸���A�k�ɂ̉i�v���y��A��ɂ̕X���n���o���āA�C���ʂ��㏸���A�C�����オ��Ƃ����z���J��Ԃ��悤�ɂȂ�܂����B
�@
�@���̌��ʂ����܂Ōo�����Ȃ������悤�Ȉُ�C�ۂ��n���㎊��Ƃ���ŋN���Ă��܂��B�������A���{�ł���ɏ������悤�Ȉُ�C�ۂ��p�ɂɔ������������̂ł��B
�@�������͂������Ȃ�ł��ł���Ƃ�������ɐ����Ă��܂��B�̂̐l�́A�֗��ȓ����@�B���Ȃ������̂ŁA�䖝������s�ւ��̒��Ő����Ă��܂����B
�@�����邱�Ƃ́A�t�ɉ����������A�܂��͑��̉�������Ƃ����w�v���X�ʂƁA�}�C�i�X�ʂ̑��E���K������x�Ƃ������Ƃ��̂ɖ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B
���̊�{�ɂ́A�w�n���̎����͗L�����x�Ƃ������Ƃł��B
�@�����̒��ŁA�w���������܂Łx�Ƃ��A�w���肪�����x�Ƃ������t��g�������Ċ����A�s�����邱�Ƃ���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�w��肽������x�A�w�E�E�E������x�Ƃ�������ɐ����邱�Ƃ��A����������łڂ������ɐi��ł��邱�Ƃ������Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�ŋ߁A�w�H�ו���A���ݕ���E�E�E�x�Ƃ����X�������܂����B
��������łȂ��A���������܂��Ă���̂ŁA��������͊y�`���ł����A�H�ו������ݕ���ŁA���̌��ʁA�u�N�u�N�������l���������悤�Ɏv���܂��B
�@���f�ɐ�����I�@���������S�������K�v�Ȏ���ɂȂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
|
2014�N�X���P���i���j
�gSeptember has come. �h�@�X���ɂȂ�E�E�E
�@���N�̉Ă����낢��Ȃ��Ƃ�����܂����B�U��Ԃ��Ă݂�Ƃ��܂肢���Ăł͂Ȃ�����
�悤�ɂ��v���܂��B���ɁA�ŋ߂ُ̈�C�ۂ͖ڂɗ]�邱�Ƃ�����܂��B
���������n���A���鍑�Ɍ��肵�ċN����Ƃ������܂łƈ�����p�^�[���ł��B
�@
�@�Ȃ�ƌ����Ă��A����̍L���̏W�����J�ɂ��R����ŁA��������̋]���҂��o�����Ƃł��B�ق�̐�Km���ꂽ�ꏊ�ł͏��J�������悤�ŁA������Ɨ��ꂽ�ꏊ�ł́A���J�������̂��A�R���ꂵ���n��ł͓y���~��̉J�Ƃ������Ƃł��B
�����������ۂ͍��܂ł̋L���ɂ͂Ȃ������悤�Ɏv���܂��B
�@
�@�O���ɖڂ�������ƁA�A�����J���C�݂̎R�Ύ��͐��S�N���̊��̌��ʁA�����ď����Ȃ��Ƃ����b�ł��B�C�M���X�̍��J�����܂łɂȂ������悤�Ȓ����̑�J�������Ƃ������Ƃł��B�n���K�͂ŁA�ُ�C�ۂ�����Ă��܂��B
�@
�@�ŋ߂̕��A����i�̔��B�ŁA���܂łɂȂ������悤�ȉ摜���ڍׂɕo������悤�ɂȂ������Ƃ�����܂��B�����ЊQ�ł��A���ׂ��������A���ꂾ���ڂ������܂��B�������A���ꂾ���ł͂Ȃ��悤�ł��B
�@
�@�{���ɒn���K�ُ͂̈팻�ۂ��������Ă���Ƃ����b�ł��B
���{�ł́A�q���̍��Ɂw�����x�͌��t�ł͕����܂������ǂ��������̂��A�܂����̔�Q�͕��������Ƃ�����܂���ł����B�w�����x�̓A�����J�ŋN������̂Ǝv���Ă��܂������A�ŋ߂͓��{�̊e�n�ł��N���Ă��܂��B���̋K�͂͂܂��������悤�ł����A����ł���������������ꂽ�ƕ��݂��e���r�ł悭���܂��B
�@�����͂X���P���A�h�Ђ̓��ł��B���N�A���̍��ɑ䕗������Ă��鎞���ł����A���ɂ������̑䕗���㗤���܂����B������ŋ߂̓����ŁA�C�����x�̏㏸�ƕΐ����̕肪�����̂悤�ł��B
�@
�@���āA�Ȃ��Ȃ����̒��̌i�C�͗ǂ��Ȃ�Ȃ��悤�ł��B�A�x�m�~�N�X�Ɋ��҂��Ă����̂ł����A���{�l�������Ă�����悤�ɂ͂䂩���A�i�C�͖F�����Ȃ��悤�ł��B
���ɏ���ł��W���ɏグ�Ĉȗ��A�Ȃɂ��o�K�l���C�ɂ�����܂��B
�@
�@���������܂ŁA����҈�ÂɂȂ�A���S���P���ƂȂ��Ă���A��Ô�͐����������Ă��܂��B���̕��A����ł̃A�b�v�ő��E����Ă���悤�Ɋ����܂��B�����̗���ł������������ł�����A��ʂ̑����̕��́A�����̍������C�ɂ������Ă���Ǝv���܂��B
�@
�@�������A��ʁA���ꂩ��̕����ɂ������p�����Ȃ��̂ڂ�ɂȂ邱�Ƃ��l���܂��ƁA�������ǂ��m�ۂ��邩�A���̖��������Ă����킯�ɂ͎Q��܂���B��ϓ���ǎ�肪�K�v�ł��B
�@�����ŐF�X�Ƌc�_����Ă���̂ł��傤���A����ł��P�O���ɂ���A����ɔ����T���ɑ��邱�Ƃ͕K�����Ǝv���܂��B
�@
�@���A������B�₷���F�X�ƍl���āA����ɔ��f���悤�Ƃ��Ă��܂��B
�A�x�m�~�N�X�́w�R�{�̖�x�ŁA�����ɓ����Ƃ����b�ł����B�P�{�A�Q�{�̖�͊��ɑł���܂����B���Z�ɘa�A��ƌ��łȂǂŁA��Ƃ̊��͂����߂��A���ʂƂ��ď]�ƈ��̌ٗp�⋋�����m�ۂ��āA�x�[�X�A�b�v�ɂȂ��A�����̌���A����g��Ƃ����z�ɂȂ�Ƃ����\�z�ł����B
�@�������A����ŁA�ٗp���i�@�͂��̋t�̂悤�ȋK���ɘa�ŁA�ٗp�����J���҂ɂƂ��ẮA���܂ňȏ�Ɉ��������œ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�Ȋ��ɂȂ邱�Ƃ��l�����܂��B
�@���{�͊�Ɛł������̂ŁA�O���ɑ��āA�����͂��s���Ȃ̂ŁA�O���[�o�������ɏ��ĂȂ��̂��Ƃ��������ŁA��ƌ��ł��s���܂����B�������A�Ȃ��Ȃ���Ƃ����C�ɂȂ�Ȃ��̂ł��B
�@���A�~�h�����[�g�͂P�h�����P�O�O�~�O��ŁA��ϗ����������ł��B�ȑO�̓��{�Ȃ�P�h���P�O�O�~�ł�����A�A�o���h���h���L�тāA��ύD�i�C�ɂȂ����͂��ł��B
�@���ꂪ���̃��[�g�ł��S�����C���o�Ă��Ȃ��̂ł��B�ނ���P�h����80�~�O��ŁA�A������������������̕����A�f�Վ��x�͗ǂ������Ƃ�������Ȍ��ʂɂȂ��Ă��܂��B
�@
�@���A���E�̌i�C���ُ�C�ۂƓ��l�ɁA���������Ȃ��Ă��܂��B
���܂ł̌o�ϐ���͒ʂ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�o�ϊw�҂�o�ϕ]�_�Ƃ́A���ʂ����āA��t���̗��_��U�肩�����āA���������̎咣���������A���_�̂悤�Ɍ����܂����A���̋�����~����l��������邩�ł��B
�@�܂��A���{�̌o�ς͍��܂łƑS��������ɂ��邱�Ƃ��l���Ȃ���Ȃ�܂���B
����́A�H�ꂪ���{��������Ă��܂������Ƃł��B�P�O�O���Ȃ��Ȃ����Ƃ͌����܂��A�Ⴆ�A�Ɠd�̍H��́A���̑�ゾ�������Ă��A�߂��ɂ������H��Q�͍��A�V���b�s���O�Z���^�[�ɕς������A�}���V�����ɂȂ����肵�Ă��܂��B
�@���m�Â�������āA�t�����l�����߂č����O�ɔ������Ƃ����o�ς̊�Ղ��x����s�ׂ��Ȃ��̂ł��B�����������O���ɍH����ڂ��Ă��܂��܂����B�������̗���͕ς���Ă��܂���B
�@���̂��Ƃ��A���{�̊��͂��b�̗͂��Ȃ����Ă���ő�̗v���ł��B
�������A�������x�����}�ɉ����邱�Ƃ��ł��܂���̂ŁA�����Ȍo��͍��܂łƂ��܂�ς��Ȃ��Ƃ������ŁA���������Ȃ���Ȃ�܂���B�����ɁA���܂łƈ�����n���������܂�܂��B
�@
�@�A�x�m�~�N�X�́w�R�{�̖�x�Ő��藧�̂��Ƃ����b�ł����B�ʂ����āA���̂R�{�ڂ̖�Ƃ͉����H�@����͐����헪���ƌ����܂��B���̐����헪���S�������Ă��Ȃ��̂ł��B�@
�@�Ȃ��ł��傤�B���̒��͊������v�ł�����߂ɂȂ��Ă��܂��B�����̌��v�A��l�̌��v�A�����̏c���茠�v�A�����̓꒣�葈���A�ȂǑS�Ă����v�œ����Ă��܂��B
���̊������v������i��Ŏ�������Ƃ����悤�Ȗ�l��g�D�̓[���ł��B�S�����Ȃ��̂����ʂł��B
�@�������A���A���{�́A�����̍H�ꂪ�Ȃ��Ȃ��Ă��钆�ŁA������邱�Ƃŕt�����l���Y�݁A����ō��͂�~���Ă����Ƃ�����{�\�}������Ă��܂��B
��������܂ł̊������v�������Ă���l�X���A���܂łǂ���̍l�����ŁA�d�������Ă����ʂ͏o��͂�������܂���B
�@�Ⴆ�A�Y�Ƃ͑�ꎟ�Y�Ƃ̔_�ы��ƁA��Y�Ƃ̍z�H�ƁA��O���Y�Ƃ̃T�[�r�X�Ƃƕ�����Ă��܂��B�ŋ߂́A�����l���Y�ƂƂ����l�����܂��B
�@
�@��Y�Ƃ́A��ɏ������Ƃ���A�ȑO�̎p�Ƃ͂������ꂽ�p�ɂ����܂����B������Ђ��Ȃ��Ȃ����̂ł͂Ȃ��A�������_�A�H�ꂪ�C�O�ɍs���A���{�ɂȂ��Ȃ����̂ł��B�@�c���Ă��Ă��A��͂̍H��͓��{�ɂ͂���܂���B�������邱�Ƃŕt�����l���Y��Ōo�ς̊�A�����ɂȂ���̂��Ȃ��Ȃ����̂ł��B
�@
�@��O���̃T�[�r�X�Ƃ͑�ϊg�債�āA��������̓X�₢���ȕ֗��ȃT�[�r�X�����܂��B�������A���̋ƑԂ͕t�����l�ނƂ�������ł͂���܂���B
�@�����͉�邱�Ƃ������Ă��A���������B���邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł��B�₩�Ɍ�����T�[�r�X�Ƃ���������₩�ɂȂ��Ă��o�ς͒��������܂���B
�@
�@����ł́A���{�͂ǂ���������̂ł��傤���H
�@
�@�c���ꎟ�Y�Ƃł���_���Ƃ������邱�Ƃł��B
���A���{�̔_�Ƃ͑S�����ɑ̂ɂȂ��Ă��܂��B�����}�̔_�Ɛ���͏]���̂܂܂ŁAJA�_���̎d�g�݂̒��ŁA���ԑR�Ƃ����܂܂ŁA�ς��悤�Ƃ��܂���B�ꕔ�̋c���̒��ɂ͂��̂܂܂ł͓��{�̔_�Ƃ��ׂ��A������ɒׂ�Ă���Ƃ����l�����܂��B�����������v���܂��B
�@
�@�_�Ə]���҂̒��ɁA�����ꕔ�̍ˊo�̂���l�̓o���o���ƌ��C�Ɏd�������Ă��܂��B
���������l�̈ӌ���f���ɕ����A�V�����_���͎����ƌ�����͂��ł��B
�@���ꌻ����`�Ƃ������t������܂����A����c����n���c��c�����{�C�ŁA�����������C�Ȕ_���̐��������Ƃ�����̂ł��傤���B
�@
�@���̒��ł�������ׂ����Ƃ�������Ȏp��`���āA����������i�߂�B����Ȃ�܂��܂��ł����A�����̍l���͂��������A���ۂɂ��ƂȂ�ƁA�_����_���c�̂̔��ŁA�ƂĂ��Ď肪�����Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤�B
�@�c���͑I���Ƃ���������܂��̂ŁA�����炢�����Ƃł��I�����������邱�Ƃ͎��猾���o���Ȃ��̂ł��B
�@�_���̒��Ō��C�ɂ���Ă���l�͂ق�̈ꈬ��ł��B���������l�͌��݂̔_�������v�������ƌ����Ă��܂��B�_���̔�����Ȃ����āA�K�����Ȃ����āA���R�ɂ�点�ė~�����ƌ����Ă��܂��B�������A�命���̔_����_���c�̂ɏ������Ă���l�́A���܂ł̂Ԃ牺����A�A����Ԃɕ������̔_���ɑS�g���h�b�v���Z���Ă��܂����B���̂ʂ�ܓ�����o�邱�Ƃ����߂���Ă���̂ł��B
�@�N�����āA���܂Ŏ����ɓs���������Ǝv���Ă��鐭���d�g�݂�ς��邱�Ƃɂ͕s��������܂��B�V�������Ƃɑ��Ċ��҂������Ă��A���ݐ�Ȃ��̂����ʂł��B
�@�������A���{�̔_�Ƃ����������A����������Ȃ��Ȃ����_�n��c�ɂŁA���܂łǂ���̐���Œʂ���͂�������܂���B������艄����Ő������炦�����Ă���悤�Ȃ��̂ŁA�O�i����P�͂���܂���B���Ɍ������Ă��邾���̂悤�ȋC�����܂��B
�@�����ł͂Ȃ��A������������A�V�����_����ł��o���Ȃ���Ȃ炢���ł��B
���E�̔_�Ƃ����邱�Ƃ���n�߂Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�_�Ƃ����{�ꍑ�̒��ōl���Ă��Ă͉������Ȃ��ł��傤�B
�@�H�Ƃ��O���[�o����{�[�_���X�̗���̒��ő傫�Ȕg����A����ɑς��鐶������I��ł��܂����B���ꂪ�H��̊C�O�ړ]�ł����B
�@�ʂ����āA�_�Ƃ͐��Y�ꏊ���C�O�Ɉڂ��Ƃ������Ƃ͂���܂���B�_�Ƃ͔_�n�ƈ�̉��������̂ł��B
�@���{�ŁA���̃O���[�o���������o�ς̒��ŁA�_�Ƃ��������тāA���������Ƒ��𐁂��Ԃ��̂͂ǂ����邩���l���āA�������v������̎d�g�݂�Ŕj���āA�V�����p�ɐ��܂�ς�点�邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł��B���ꂪ�ł���A�A�x�m�~�N�X�̑�O�̖�ɂȂ肦�܂��B
�@�_�Ə]���҂̒��ɁA��ɏq�ׂ܂��������C�Ȑl���������l�����܂��B
���{�̃R���A���{�̉ʕ��i�������́j�A���{�̋����ȂǁA�l�i�͒��������̂ł����A�����Ă����������A���������̂͊C�O�ł�����܂��B
�@�������E���̊F����ɔ����Ă��炦��悤�Ȕ_�Y�������ƌ����Ă���킯�ł͂���܂���B���{�ł����ł��Ȃ��A�������������̂��A�l�i�͍����ł����A���E���̕x�T�Ȃ��������ɔ����Ă��炤�I���������V�����r�W�l�X���f���A�d�g�݂𑁂���邱�Ƃł��B
�@
�@�C�O���s���āA���n�̃X�[�p��ʕ����ɗ������ƁA��������̉ʕ����R�ς݂���Ĕ����Ă��܂��B�i���͖L�x�ɂ���܂��B�������l�i�͂������������̂���ł��B
�`�□��F���ȂǁA�������������āA�ƂĂ����{�Ŕ����ʕ��Ɣ�r�ł��Ȃ��i������ł��B�����S�͂����ς��Ĕ��������Ƃ͌����܂���B��������܂���B
�@�����������̂����Ȃ��̂ł��B���ꂪ�����S���Ǝv���Ă���̂ł��B�{���ɔ�������������A�ʕ��͓��{�ɂ�������܂���B
�@�����������{�̑f���炵���_�Y�����A�l�i�͍��������E�ɏЉ�āA���E���̂��������ɂǂ�ǂ��Ă��炤�悤�ȗA�o����d�g�݂̍\�z�����}�ɕK�v�Ȃ̂ł��B
�@�ꕔ�A�����I�Ɏ��g��ł��܂����A���{�̍H�Ɛ��i�A�d�����i��ԂȂǂɑ�\����鐻�i��A�o�������т�����킯�ł�����A���x�͓��{�̉ʕ��⋍���Ȃǂ�N�x��ۂ��āA�A�o����Ƃ����C���t���𑁂���邱�Ƃł��B
�@�����āA���܂ł̕č��̌�������ȂǁA�č��_�Ƃ̉��������߁A��肽���l�����R�ɔ_�ƂɎQ���ł���K���ɘa�����A���C�ɔ_�Ƃ���肽���l�ɔC����悤�Ɏ��R�����ׂ��ł��B
����̓A�x�m�~�N�X�̑�O�̖�̊�{���ƍl���Ă��܂��B
�Ƃɂ��������A�i�C�����āA�����̊y���������߂��������̂ł��ˁB
�X���ɂȂ�E�E�E�@���t�̉����Ȃǐ������܂������܂��B
�����C�Â��ė~�����ł��ˁB
|
2014�N8��24���i���j
��X�[�~�i�[�����V�O�����̔��\
�@�����V���ɂ��A�x��\���Z�A�͍��m�ƕ���ŁA�O��\���Z�̈�ł�����
��X�[�~�i�[�����A���t�A�S��17�s���{���ɓW�J���Ă���\���Z�Q�X�Z�̂V�O���ɂ�����Q�O�Z�������Ɠ`���Ă���B
�@��X�[�~�i�[���͂P�X�T�V�N�ɑn�����A�N�X���т�L���Ă������A�ŋ߂̏��q���̉e����A���̎u���̕ω��ŁA�������鑼�Z�Ƃ̋����ɔs�ꂽ�炵���B
�@�X�O�N��͂Q�O�O���l�����P�W�̐l�����A���́A��U���̂P�P�W���l�Ɍ��������B�\���Z���炷����q�l���������Ƃ������ƂɂȂ�B���ꂪ�ő�̗v�����낤�B
�@
�@�������A�ق��̗\���Z�̕��̘b���Ȃ��Ƃ������Ƃ́A��X�[�~�Ǝ��̗v�����l������B���升�i�Ґ�������ƁA�x��\���Z�͂P�Q�T�V�l�A�͍��m�͂P�P�O�P�l�A����ɑ��đ�X�[�~�͂킸���R�U�X�l�ƂȂ��Ă���B
�@��֑�w��ڎw�����̊l���A�D�������̏��Ր킪�����Ă���ƌ����Ă���B�\���Z�̕]���͓�֑�w�։��l�A���i���������̎��т��A���̊l�������ɏ��ő�̊�ɂȂ邪�A����ő��̗\���Z�ɑ傫����������ꂽ���Ƃ��A�����ɂȂ����悤���B
�@
�@����ɁA�ŋ߂̍��Z���͎����̊w�͂ɑ��������w���A�Q�l���������Ȃ��ƌ��������ɂȂ��Ă���悤���B�����������������A�y�����Ƃ����l�����Ȃ̂�������Ȃ����A�y���đ�w�ɓ���B
�@
�@��w�̕��������ȓ������x��p�ӂ��āA���E���w�g�𑝂₵����AAO������������A�n��n���ł����{������A�H�w���d�C�H�w�Ȃ����邽�߂̍��Z�̗��C�Ȗڂɕ������Ȃ��Ă��Ƃ����悤�ȁA���������ȑ�w�܂ł���B��w�͎��̌����X�����������ŁA�w���̊l���ɖ�N�ɂȂ��Ă���B
�@������������̐V��������̒��ŁA�\���Z�ƊE���傫���h�ꓮ���Ă���悤���B |
�Q�O�P�S�N�V���P�W���i���j
�x�e�����ƐV�l�̍��Ƃ͉����H
�@�w�������������̂��H�x�@�������ȃ^�C�g���ɂȂ������A�E��ȂǂŁA�w���̐l�̓x�e�������I�x�Ƃ��w���̐l�͐V�l������E�E�x�ƌ���������������B
�@�������A�d���̃x�e�����́A�����Ȍo����ς�ŁA�����̒S������̎d���ɑ��ẮA���ł����܂���肱�Ȃ����Ƃ��ł���l�̂��ƁB
�x�e�����ɗ��߂Έ��S���ł���B
���Ɍ���̎d���́A���̐l�̗͗ʂ����̂��������Ƃ������B
�@
�@�V�l�́A�܂��d�����o���邱�Ƃ���n�߂�B
�����ł́w��E�j�E���x�ƌ����炵�����A�܂��͊�{����������C�����A������}�X�^�[������́A���܂Ŋw���̂���悤�ȗ��K�����āA����ɂ��̏�̋Z�ʂ��K������Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��Ǝv���B
�@����͋Z�\�蕨�ɂ��錻���Ǝ҂ɂƂ��āA���ɑ�Ȍ��t���Ǝv���B
�x�e�����i�ꗬ�̐E�l�j�̏�ɁA�t���⏠�ƌ����l����������B
�@���āACar Life�̃y�[�W�ɏ������������A�����Ԃ��傫���l�ς�肵�Ă����B
�����Ԃƌ������i�����܂łƕς���Ă����̂��B
�@�ԉ�����ƌ����A���[�J�̃f�B�[���[������A�X�̏C��������A���É�������B���܂ŁA���[�J�[�n��ɓ����Ă��Ȃ��ԉ�������ԎЉ�ɂȂ�A�Ԃ��������ꂽ�����͑�ϓ�����Ă����B�����A���X�ɂ���ẮA���Ô̔��A�C���A���Ȃǃ��[�J�[�̃f�B�[������|���Ȃ��d���𐿂���������A���ЂŔ̔�������Ƃ�������o�c���Ă���X������B
�@
�@�{���A�Ԃ̓��J�j�Y���̏��i�ŁA�d�C���i�̓��C�g�ނ┭�d�@��o�b�e���[��W�I�A�J�[�i�r�ƌ����悤�Ȃ��̂������B
�@���ꂪ�A�ŋ߂̎Ԃ͌��Q����R���ȂǂŁA�d�C�E�d�q���i���H����������g���Ă����B
�@���܂ł́A�Ԃ̃��J���i�̏C���A�����A�����Ȃǂ��C���̑Ώۂł������B
���Ƃ��A�u���[�L�A�G���W�����A�n���h�����A�x���g�ށA�^�C�����Ȃǂł���B�����̏C���́A�T�[�r�X�}���̗͗ʁA�r�O��ŁA�C�����Ԃ��傫�����E���A�C����̏o���h����s��Ȃǂ��傫���ς��B
�@�Ƃ��낪�A�ŋ߂̃n�C�u���b�h�ԂȂǂ́A�C����R�[���Ƃ����A���̃��[�J�Ǝ��̃��[�J����x�����ꂽ���^�R���s���[�^���Ȃ��A�ڑ��R�[�h���Ԃ̃G���W�����[�����̐ڑ��[�q�ɍ�������ŁA�R���s���[�^�𑀍삵�āA�f�[�^������������B
���̊ԁA�������邱�Ƃ��Ȃ��B
�@����v���O�����͖c��ȃf�[�^�Ȃ̂ŁA�������ɂP���Ԉȏ��������B
�v���O�����̃o�[�W�����A�b�v���ł���A�C���͏I���ł���B
�@���āA������������ɂȂ�ƁA�T�[�r�X�}���̃x�e�����ƐV�l�̎d���ɍ����o��̂��ǂ����ł���B�x�e�����͍������������炤�B�V�l�͂���Ȃ�̋��������炤�B
�@���������́A�V�l�ł͂ł��Ȃ������Z�\�≽�����Ȃ��ƈӖ����Ȃ��B
�����P�Ɍo�����L�x�����ł́A���������͂��炦�Ȃ��B
�@�������A�v���O���������������邾���ŁA���ׂĎԂ̏C�����ł���킯�ł͂Ȃ����A�v���O����������������Ƃ�����ƂɃx�e�������V�l���S�����͏o�Ȃ��B
�@�������Ƃ���葱���āA�Z�\���K�����A�x�e�����̗̈�ɒB����B
����́A�@�\����J�j�Y���ȂǂɊւ��邱�Ƃł���A�v���O����������������Ƃ�������ɓ����Ă���ƁA�킯������Ă���Ƃ������Ƃ��B
�@���������V�����d���̗�����A�����̔��Ŋ����đΏ����Ă䂩�Ȃ��ƁA�C���t���Βu���Ă��ڂ��H�����ƂɂȂ肻�����B
�܂��A���X�����܂ł̓��[�J�̃f�B�[���Ƒŏ������ł��Ă�����������Ȃ����A�R���s���[�^�Ń\�t�g���蒼�����ďC�����鎞��ɂȂ�ƁA���̐�p�̃R���s���[�^��
��ɓ���Ȃ���A��������o�Ȃ����ƂɂȂ�B
����A�R���s���[�^���g��Ȃ��ԂȂ�C�����ł��邪�c�A���������Ԃ̓|���R�c��
�Â��ԂɂȂ��Ă���B
�@����̒����́A�x���悤�ŋC���t���Α傫���ω����Ă�����̂��B
�@���ꂪ���܂ł̃A�i���O����ƁA���ꂩ��̃f�W�^������̈Ⴂ�Ƃ�������B |
�Q�O�P�S�N�V���P�P���i���j
�䕗8���̔�Q�������A�Ȃ���ł����B
�@�~�J�����̑䕗�ƌ������ƂŁA�������A���ɑ�^�ƌ������ƂŐS�z���܂����B
�䂪�Ƃ̓A�}�`���A�����̃A���e�i�������Ă���̂ŁA�������������Ƒ�ϐS�z�ł��B����̑䕗�͑�^�ƌ������Ƃł������A�k��ƂƂ��ɋ}���ɐ��͂���߂܂����B
�@�䕗�̋����͒��S�C�����A���X�փN�g�p�X�J���i�ȑO�͉��~���o�[���j�ƌ����\�����g���܂��B����̑䕗�W���͈�Ԕ��B�������͂X�R�O�w�N�g�p�X�J�����x�܂ŋC����������܂����B���S�C�����ǂ̒��x���ŁA���S�t�߂̕��̋��������܂�܂��B������A�䕗�ő�Ȏw�W�́A�����Q�O���̖\���J���̍L���ł��B
�@���ꂪ�䕗�̃G�l���M�[�̑召��\���w�W�ł��B
�@�\���J�������S���甼�a�P�O�Okm�Ƃ����䕗������A���a�S�O�O�����ƌ����悤�ȋ���Ȃ��̂܂ł���܂��B
�@����́A�n�k�̑傫����\���w�k�x�x�Ɓw�}�O�j�`���[�h�x�ɕC�G������̂ł��B
���S�t�߂̋C���͕����A�n�k�̐k�x�A�h��̑傫���ɑ������܂��B
�\���J���̍L���͒n�k�̃}�O�Ƀ`���[�h�ɓ�����܂��B
�@�v�́A���S�t�߁i�k���j�̋����̑召�ƁA���̑䕗�i�n�k�j�̃G�l���M�[�̑召������Ƃ������Ƃł��B
�@����́A���S�C�������ɒႢ�䕗�������̂ŁA�呛���ɂȂ�܂������A�~�J���ł��̂ŁA�܂��^�Ă̏����ł͂Ȃ��A�䕗�̃G�l���M�[�́A�k�シ��ɏ]���A�}���ɐ������Ƃ������Ƃł��B
�䕗�́A�C�����������Ə㏸�C�����������Ȃ�A���S�C���͒Ⴍ�Ȃ�A�������������r��܂��B�L���͈͂̊C�������܂��\�������Ȃ���A�\���J���̍L���͂���Ȃɑ傫���Ȃ��ƌ����܂��B����̑䕗�W���͂��������䕗�ł����B
�@�H���̂Q�P�O���A�Q�Q�O���O��̍��͖k�����̋C����C��������ԍ����Ȃ������ł�����A�䕗�����������ꍇ�͋��剻����Ƃ������Ƃł��B
�@������ɂ��Ă��A�e���r�Ȃǂő呛�����܂����̂ŁA�A���e�i�͉��ɍ~�낵�ĕ�������܂������A���ʓI�ɂ͉e�����Ȃ��ĉ����ł����B
�@�䕗���痣�ꂽ�ꏊ�ŁA�W�����J������傫�Ȕ�Q���o�Ă��܂��B
�~�J�O�����h�����āA��J���~�点���悤�ł��B
�@������x�A���쌧�̏�c�s�ߍx�A�ؑ��ɍs���܂����A�ؑ]�쉈���ɑ��钆���{���̐��H�⋴������ؑ]�t�߂ŗ�������H�������オ���Ă��܂��܂����B
�@�����ɂ͑����A���Ԃ������肻���ł��̂ŁA�����͓����o�R�ŁA����V�����ɏ��A����ɂ䂭�R�[�X�ɂȂ肻���ł��B
��Q�ɂ���ꂽ�n��̊F�l�ɂ͂��������\���グ�܂��B
|
�Q�O�P�S�N�V���S���i���j
�܂��ɁAUFO�̂悤�ł����B
�@�V���P���A���Z���h�[���́w�y�V�|�I���b�N�X�x�̃`�P�b�g���A���߂ċ��Z���h�[���ɍs���܂����B���܂ŁA������̓d�Ԃ���h�[���߂Ă��܂������A���߂ăh�[���ɓ��ꂳ���Ă��炢�܂����B�S���łP�S�|�T���B
�@�������A��ʐȂł͂Ȃ��A�r�X�^���[���Ƃ������ʐȂŁA�H�������A�r�[�������݂Ȃ���A�ŏ�K�̂W�K����싅���y���݂܂����B
�@�r�X�^���[���́A�Q�O���قǓ����L���ŁA�傫�ȃe�[�u�����Q�ƃC�X�A����ɉ��ڃ`�F�A���ݒu����Ă��܂��B�r�[���͒M���ŁA��ς��������r�[���ł����B�H���͂ǂ��炩�ƌ����ƃI�[�h�u�������S�ł����B�����ɂ͂S�V�C���`�̃e���r������A�O���E���h�Ńv���C���Ă���I�肪�f���o����Ă��܂����B
�@
�@���̃e���r�͈�ʂ̒n�f�W���������邱�Ƃ��ł���̂ŁA�r�������_�|���N���g��Ƀ`�����l����ς��Ă��܂����B
�@�O���E���h�ł́A�y�V����s���܂������A�r���ŃI���b�N�X�ɂЂ�����Ԃ���܂����B
��������h�A�[���J����ƁA�x�����_�̂悤�Ȋϗ��Ȃɏo�邱�Ƃ��ł��܂��B�h�A�[���J�����r�[�A�����c�̑��ۂ�g�����y�b�g�̉���A�ϋq�̈���J�̐���オ��̐����̔M�C���`����Ă��܂����B
�@��_-���N���g��͓��g���撣���āA���̓��̓_�u���X�R�A�ő叟���܂����̂ŁA�F�A��ϑ����オ��܂����B
�@�����A�싅�̓e���r�Ŏ��X������x�ŁA�w��_���܂��������Ȃ��I�x�Ƃ��������Ȃ���̃p�^�[���������̂ł����A���̓��͔�����Ԃő�ϋM�d�Ȍo���������Ă��炢�܂����B |
 |
| UFO���~�肽�����悤�Ȏp�̋��Z���h�[�� |
 |
| �L�X�Ƃ������Z���h�[������ |
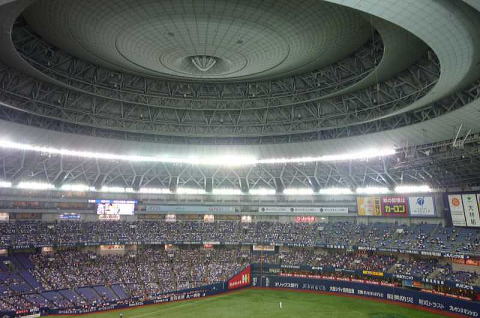 |
| �h�[���̉����́AUFO�̂悤�I�@����Ȍ��� |
 |
| �V��ɂԂ牺����������ȏ�������X�s�[�J�[ |
 |
| �r�X�^���[���͂���Ȋ����ŁA���났�Ȃ���y���߂܂� |
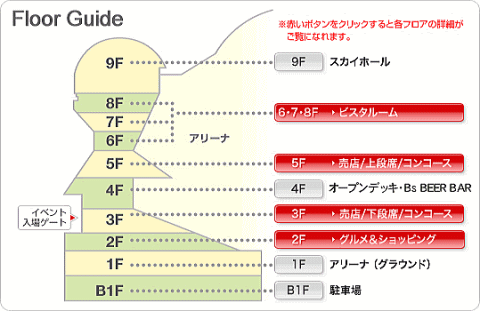 |
��X�͂WF�r�X�^���[���ɐȂ����܂����B
���������������h�[���̎��͂ɕ���ł��܂��B |
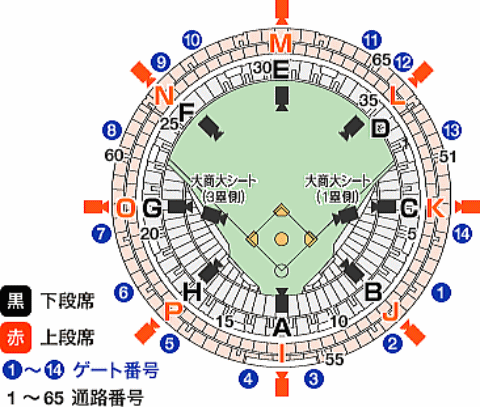 |
�Q�O�P�S�N�U���P�Q���i�j
�������A�s�����ۑގ����I
�@���N�A�N��x�A�l�ԃh�b�N���Ă���B
�݂ɂ��Ă̓����g�Q�����������邪�A���N���ُ�Ȃ��ƌ������Ƃł������B
�@����S���Ă������ŋ߁A�݂�������銴��������̂ŁA�߂��̏��������ɍs���Ĉ݃J���������B
�@�݃J�����͂Q�O�N�قǑO�Ɉ��ہA�A��ʂ鎞�A�w�Q�[�x�ƂȂ�A����Ȉ�҂������Ǝv����������ɃJ������˂����܂ꂽ�ɂ݂�����A���ꂪ�g���E�}�ƂȂ�A�݃J�����ƕ����ƃh�L�h�L����悤�ɂȂ����B�ł��邾��������悤�ɂȂ����B
�@���ꂪ�ŋ߂̓t�@�C�o�[�̐i���ŁA����������t�@�C�o�[���ׂ��_�炩���Ȃ�A���̌�A������Q��قLj��B�ł�����A�ˑR�̃g���E�}���v���o����āA�ő���̂���Ȏv�������Ȃ���d���Ȃ��Ă����B
 ���ꂪ�A�ŋ߁A�@��������݃J�������J�����ꂽ�B ���ꂪ�A�ŋ߁A�@��������݃J�������J�����ꂽ�B
����͕@�̒��i�@�o�j���ł�����Ɩ�Ⴢ�����A�J�������A���Ȃ��ʉ߂��ĐH���ɓ���B�w�lj����������ɁA�w�Q�[�x�ƂȂ炸�A���Ɋy�ɂȂ����B
�@�Q�N�O�ɂ��A������A�@����}�����Č��������Ă�������B���ׂ̍��J�����ł������ׂȉ摜���f��B�|���[�v�Ȃǂ����邱�Ƃ��ł���B
�I�����p�X�������A���E�V�F�A���V�O����������{���ւ��Ë@��ł���B
�@
�@�����̈݃J�����́A�A�����J�Ŕ������ꂽ�ׂ��K���X�t�@�C�o�[�̑����g���A�݂̉摜�����Ă����B����ň݂̒������߂Ē����ł���悤�ɂȂ����B
�@���̌�A�����̑f�q���i�����A�����^�̃J�����ł����ꂢ�ȉ摜���B���悤�ɂȂ����B�X�}�z�����̂�����B
�@���̏����ȉ摜�f�q�iCCD)���[�ɒ������݃J�������J�����ꂽ�B
�@����ɉ摜�̓n�C�r�W�������݂̒����掿���B���悤�ɂȂ����B���̌��ʁA�ׂ��ď_�炩���ǂɂȂ�A�掿�����i���ɂȂ����݃J�������ݒ��J���������������B
�@�����̐i���ł���B
�@�Q�N�O�Ƀs�����ی��������Ă�����Ă����B���̌��ʂ͗z���i�������Ă���j�ƌ������Ƃ������B����̈݃J�����̉摜�ł��A�ݕǂɓ����̖����f���Ă���̂ŁA���������Ǐ�̓s�����ۂ�����؋����ƌ���ꂽ�B�����ŁA�s�����ۑގ����Â����肢�����B

��́w�����T�b�v�S�O�O�x�i���c���j�A��̎ʐ^�̂��́B
�@����ɂQ��A���Ɨ[�A��T�ԘA�����Ĉ��ށB
�^�P�v�����J�v�Z���R�O�F�ݔS���̃v���g���|���v��j�Q���A�ݎ_�̕����}������B���̏�Ԃɂ��āA�N�����X�Q�O�O�ƃA�������J�v�Z���Q�T�O�̍R�������ŏ��ۂ���B�l�ɂ���ẮA����݂┭�]��A��ւ≺���Ǐ�̕���p������炵���B
�K���A���ɉ��̏Ǐ���Ȃ����ݑ����Ă���B
�V�O���قǂ̐l�͏��ۂ��ł��邪�A�܂��R�O�����炢�̐l�͖����Ȃ��炵���B
���������ǂ����̌����́A���t�����A���t�����A�ċC�����Ȃǂ̕��@������B
�@���ۂɐ������āA�݂̒��q���ǂ��Ȃ邱�Ƃ����҂��Ă���B
|
�Q�O�P�S�N�U���U���i���j
�d�͂̎��R���̓���
�@�d�͋ƊE�ɂ����R���̔g�������Ă��Ă���B
�@
�@�d�C���Ƃ́w�d�C���Ɩ@�x�ƌ����@���ŋK������ی삳��Ă����B�d�C���Ɩ@�́A�����i�ړI�j�ɁA�w���̖@���͓d�C���Ƃ̉^�c��K���������I�Ȃ炵�߂邱�Ƃɂ���āA�d�C�̎g�p�҂̗��v��ی삵�A����ѓd�C���Ƃ̌��S�Ȕ��B��}��ƂƂ��ɁA�d�C�H�앨�̍H���A�ێ��A����щ^�p���K�����邱�Ƃɂ���āA�����̈��S���m�ۂ��A����ъ��̕ۑS��}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ���x�ƂȂ��Ă��܂��B
�@�@���p��͓���̂ŁA������ɂ����\���̂悤�Ɏv���܂����A�v�͓�̖ړI�A���Ȃ킿�w�d�C�̎g�p�҂̗��v�ی�x�ƁA�w�d�C���Ƃ̌��S�Ȕ��W�x��ړI�Ƃ��Đ��肳�ꂽ���̂ł��B
�@���̖ړI��B�����邽�߁A���ƋK���ƕۈ��K��������܂��B���ƋK���Ƃ́A����ɓd�C�d������A���d�����肵�Ă͂����Ȃ��Ƃ����K���ł��B�����œd�C���Ƃ͔F���ꂽ���Ǝ҂ł������Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@
�@�d�C���Ǝ҂Ƃ͓d�C�d���A���d���A�d�C�̎g�p�ꏊ�ɔz�d���A�d�C�̔̔����s����ЂŁA�S���ɂX�̓d�͉�Ёi���������ƂP�O�j������܂��B����ȊO�ɁA���Ԃ̉�ЂŁA���ЍH����Ŏg���d�C�d���Ă����ЁA���̗]�����d�C���Ă����ЁA�Ȃǂ�����܂��B
�@
�@����������̓I�ɏq�ׂ܂��ƁA���{�ɂ͂X�d�͉�Ёi�k�C���A���k�A�����A�k���A�����A�ߋE�A�����A�l���A��B�d�́j�Ɖ���d�͂��傫�ȋK�͂̓d�͉�ЂŁA�@���I�ɂ́A������w��ʓd�C���Ǝҁx�ƌĂ�ł��܂��B
�@��ʓd�C���Ǝ҈ȊO�̓d�͉�ЂƂ��ẮA���d�C���ƎҁA����d�C���ƎҁA����K�͓d�C���Ǝ҂ƌ������Ђ�����܂��B
�@���܂ł́A�قƂ�ǂ���ʓd�C���Ǝ҂Ŕ��d����A���d����A�z�d����Ďg�p�҂ɓ͂����Ă��܂����B�����{��k�Ђ̌�A������ꌴ�����̂őS���̑S���q�͔��d�������_���ɂȂ�A�܂�����_���̂��ߔ��d���X�g�b�v���Ă��܂��B���d�̖͂�R�O���������q�͔��d���Ŕ��d�����d�C�ł�������S��������~����Ƃ������Ƃ́A���̕��𑼂̔��d�Řd���K�v������܂��B
�@���͔��d���̓_���Ȃǂ̑�K�͂ȍH�����K�v�ŁA�R�ԕ��Ń_�����݂ɓK�����ꏊ�͂��łɊJ�����s�����Ă��܂��B���̂��ߐV�������͔��d���̌��݂͂��܂���҂ł��܂���B
�@���͏����͔��d�ƌ������ƂŁA�J���a�Ȃǂ𗬂���̐��𗘗p���Ĕ��d����Ƃ��������ȋK�͂̔��d���������������Ĕ��d����Ƃ����l�����ɂȂ��Ă��܂��B�������A����ł͓���A���{�ŏ�����ʂ̓d�͂�₤���Ƃ͂ł��܂���B
�@�����œd�C���Ɩ@�̌������ŁA���܂ň�ʓd�C���Ǝҁi���d��֓d�Ȃǁj�ɗ^���Ă������F�ƋK����啝�Ɍ������A�d�C���Ƃ̎��R���̕����Ɍ������Ă��܂��B
�@���z�����d�͉ƒ�̉����ɐݒu���鏬�K�͂̂��̂���A�H��Ւn�▄�ߗ��Ēn��k������n�Ȃǂ̍L��ȓy�n�ɐݒu�����K�͔��d���̌��݂��i��ł��܂��B
�@���z�����d�p�l����p���[�R���f�B�V���i�[�i�������𗬂ɕϊ�����@��j���܂��܂������ł���A�Ȃ��Ȃ��̎Z������Ȃ����߁A���{�����������o���Č��݂̑��i�������Ă��܂����B�ŋ߂͐����L�����b�g�ƌ�����K�͂ȑ��z�����d�����e�n�Ɍ��݂���o���܂����B����͈�ʉƒ�̓d�͏���ʂ����ςR�L�����b�g���x�ł�����A��ʉƒ�̂P���������炢�̓d�͂�d���܂��B
�@��ʂ̓d�͎��v�ɑΉ�����ɂ́A�V�R�K�X�iLNG)��Ζ���ΒY��R�₷�Η͔��d�����L���ł��B�������A�Ζ���ΒY��V�R�K�X��R�₷���Ƃ͓�_���Y�f�i�Y�_�K�X�j���ʂɔ��������A�n�����g���̌��ɂȂ��Ă��܂��B
�@�����ōŋ߂́A�t���V�R�K�X�iLNG)��A�����A�K�X��R�₵�č����K�X�^�[�r�����A����ňꎟ���d���s���A�K�X�^�[�r������o�Ă��鍂���K�X���{�C���[�ɓ����A�������č������C�ŏ��C�^�[�r�������d����ƌ����R���o�C���h�T�C�N�����d���ł����ڂ���Ă��܂��B���łT�O���L�����b�g���炢�̔��d���\�ł��B�R������͂S�T�`�T�T�����炢�Ƒ�ό����������̂œ�_���Y�f�̔r�o�����炷���Ƃ��ł��܂��B
�@������ɂ��Ă��A�������������Ȕ��d�̎d���ŁA��J���ɏW�����Ĕ��d����̂ł͂Ȃ��A�d�C���v�̑傫���ꏊ�i�s��n�̋߂��j�Ŕ��d����Ƃ��������Ői��ł��܂��B
�@�w�����͐�Έ��S���I�x�ƌ������S�_�b�͓����{��k�Ђ̎��R�̗͂ɂ��낢�p�����炯�o���܂����B�����̒u����Ă���ꏊ������킩��܂����A�����d�͂��킴�킴���k�d�͂̊NJ��n��ł��镟���ɑ��A������A�܂��k���d�͂̊NJ��n��ł���V�����̔��芠�H�����������Ƃ�����Ε�����Ƃ���A�킴�킴���S�L�������ꂽ�l�����܂�Z�܂Ȃ��Ӓn�ɑ����Ă��܂��B����͗��Ԃ��A�����͈�x���̂��N�����Ƒ�ώ��ӏZ���Ɋ�Q���y�ڂ��Ƃ������Ƃł��B�ł��邾����Q�̍ŏ�����}�邽�߂ɂ͎��ӂ̏Z�������Ȃ����Ƃ��O��ł��B�����炻�������n�ɏW�����Ă��܂��B
�@����ł͑��d����ۂɁA���d���̓d�C��R���œd�C���ɕ��U���܂��B���d���鋗���������قǂ�������̓d�C�����X���܂��B
���������Ӗ��ł́A����̉����ɑ��z�����d�p�l����ݒu����̂��ł������I�ł��B
�@�����ŁA�����̍ĉғ��̂��߂̈��S������莋����钆�ŁA�ĉғ��̕~���������̂ŁA�X�̓d�͉�Ђ��Ɛ肵�Ă����d�͎��Ƃ̋K�����ɘa���A�N�ł��d�͎��ƂɎQ���ł���悤�ɂȂ�܂����B���ꂪ�d�͎��Ƃ̎��R���ł��B
�@�������A���d���̌��݂͑�ςȓ������K�v�ł���A���S����M�����̖ʂŏ]���̓d�͉�Ђ������Ă��鑗�d�����g�����ƂɂȂ��Ă��܂��B
�@�\�t�g�o���N�̑��В�����K�͑��z�����d���̌��݂ɏ��o���Ƃ����j���[�X������܂����B�K�X��Ђ�LNG���g�����R���o�C���h�T�C�N�����d����Ƃ����j���[�X������܂��B���̑��A�S�|��Ёi���S���j�����Ђ₢���ȉ�Ђ����ЍH��p�̓d�C��d�����߂ɔ��d�������݂��A�]�����d�C���X�̓d�͉�Ђɔ���i���d�j�ƌ����������e�n�Ō����܂��B
�@�����Ȃ�ƂX�d�͉�ЂƂ��ẮA���܂œd�͎��Ɩ@�ŋK������A�Ɛ��F�߂��Ă����̂ŁA�NJ��̒n��̓d�C�g�p�ҁi���Ƃ��A���ɏZ��ł���l�͊��d�͂ƌ_�d�C�̋������A�g�p�����x�����j�͂��̓d�͉�Ђ���d�C�킴��܂���ł����B�d�͂̎��R���ɂ��A�d�C�̎g�p�ҁi�e�ƒ���܂߁j�͈����d�͉�Ђƌ_�ēd�C���g�����Ƃ��\�ɂȂ�܂��B
�d�͉�Ђ͍��܂ł͈��肵�����q�l���Œ�I�Ɍ����܂�܂����̂ŁA����グ�͈��肵�Ċm�ۂł��܂����B�d�͂̎��R���ɂ��A���q�l�����̓d�C���ƎЂƌ_�āA�����Ă䂭�\�����o�Ă��܂����B
�@�����ō����̒����V���g�b�v�Ɂw�֓d�A�Г��S���Љ������x�Ƃ������o���ɂȂ�܂����B�֓d�͎��Ђ̑g�D�����A�S�̎Г����Ђɕ�������Ƃ������Ƃł��B
�@���q�͔��d��ЁA�Η͔��d��ЁA���z�d��ЁA������Ђ̂S�ł��B
�@���͌��q�͔��d��Ђł��B���A�����͑S���A�^�]���~���Ă��܂��̂ŁA����グ�̓[���ł��B�t�Ɉ��S������̂��߂̒lj��H�������ɂ������Ă��܂��B�������Ȃ��Ă������͑��z�̈ێ��������܂��B�d�C���Ƃ�蕪���邱�ƂŁA�Г��̂����ȉۑ肪�����Ă��܂��B
�@���z�d��Ђ͑��Ђ��甃�����d�C��A���Ђ̓d�C���^�ԍ������H�⍂���S���̂悤�Ȗ����ɂȂ�܂��B���܂ł͂��ׂĎ��Ђ����d�����d�C�ł������A���ꂩ��͑��d���̌��ݔ��A��C�̂��߂̈ێ���Ȃǂ����炢�Ȃ���A���Ђ̓d�C�ɉ����A���Ђ����d�����d�C�𑗂�Ǝ҂ɗ��ꂪ�ς��܂��B
�d�C�ɐF�͒����Ă��܂���̂ŁA�ǂꂪ���ЂŁA�ǂꂪ���Ђ̓d�C���͕�����܂���B�v����œd���Ɠd���𑪒肵�āA���l�Ŕc�����܂��B
�@�����I�ɂ́A���{�ɔw���ɂȂ��K�͂ȑ��d���Ԃ����݂��ꐮ������A���̔w������ׂ����ɂȂ鑗�d�����w���Ƃ��獜�̂悤�Ȍ`�Ő�������Ă䂭�Ƃ��������ōl�����Ă��܂��B
�@�ŏI�I�ɂ́A���d��Ђ͍��L�����邩�A�X�̓d�͉�Ђ��o�������V������Ђɓ�������邩�ǂ��炩�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�@�H�Ƃ̔��W�͓d�C�Ȃ����Ă͕s�\�ł��B
��~�ł������A���ɕ��ׂ��������ɓd�C�G�l���M�[�������ɐ��ݏo���A�����Ɉ���
�ɋ����ł��邩���ۑ�ł��B
�@���̎�i����@�͂��낢�날��ł��傤���A�d�͉�Ђ͂��̖ړI���������邽�߂ɂ������͂��ł��B
�d�͉�Ђ͉c����Ƃł���Ɠ����ɁA��������тт���Ƃł��B
�����Ɏ��R������悤���A�d�͂̋����҂Ƃ��Ă̎g������������킫�܂��Ď��g��łق������̂ł��B
|
�Q�O�P�S�N�U���T��(��)
�X�^�b�t�זE�̑��݂̐^�U�́H
�@�����V���̍���̗[���A�����̒���������ƁA�g�b�v�ɏ��ە�����STAP�זE�̌����_���𔒎��ɖ߂����ӂ������Ɠ`���Ă��܂��B
�@����ŁA�ޏ��ٌ̕�m�́A�ޏ����S���I�ɒǂ��l�߂��A�d���Ȃ����ӂ������A���ӂ�����ꂽ�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ������Ă��܂��B
�@���̃j���[�X�́A���ە�����ƌ����Ⴍ���Y��ŁA�ƂĂ��V�N�Ȋ����̏��������E�I�ȑ唭���������Ƃ������ɂ����̂Ǝv���܂��B���������쎟�n�I�ȃo�����[�͒u���Ă����āA�w�{����STAP�זE�ƌ������\�ɕω�����זE�蓾���̂��ǂ����x�ƌ����^����m�肽���Ƃ���ł��B
�@�����i�����w�������j�̔��\�́A����STAP�זE�̃l�C�`���ւ̘_�����e����艺���邱�Ƃ���ɏI�n���Ă���悤�Ɏv���܂��B�����c�ɂ�������Ă��銴�����܂��B
�@�Ő�[�Ȋw�Z�p�͔��Ɂw�H�L�ȏ�ԁx��w�����̊ԈႢ�x�Ŕ����A�������ꂽ�Ƃ����ߋ��̎�������������܂��B���Ƃ��A�y�j�V�����́A�V���[���ɔ|�{�����ۂɃA�I�J�r�����܂��܍������A���̎��͂ɔ|�{���Ă����ۂ������Ȃ��Ă����Ƃ�����������A�A�I�J�r�ɎE�ۍ�p������Ƃ������ƂŁA��������Ƀy�j�V�������������ꂽ�Ƌ������܂����B
�@�܂��A�����̕���ɂ����Ă��A�]��_�C�I�[�h�Ƃ��������̑f�q������܂��B
����͍]�蔎�m���V���R���ɕs�����������Ă�����������Ă������ɁA�\�肵�Ă����s�����̗ʂ��ꌅ�����Ԉ���ĉ������B���̂��ߗ\��̎����͂߂��Ⴍ����ɂȂ����B�@���ʂȂ炻�̃_�C�I�[�h�͎����̎��s�Ŏ̂Ă�Ƃ��������ׂ�ƁA���܂łɂȂ��������������B�����č]��_�C�I�[�h�ƌ����S���V�����������������̑f�q�����A�m�[�x���܂��l�������B
�@����ȊO�ɂ������������b�͂�������B
���E���œ���A��R�̉Ȋw�҂��V���������A������ڎw���Ď������J��Ԃ��A�ςݏd�ˁA�w�͂��Ă���B
�@���������v���ŁASTAP�זE�̔����̃j���[�X�����āA�S�͒e�B���ە�����͎���̒����Ƃ��Ă͂₳�ꂽ�B
�@���ꂪ�A�����̐�������ے肳��A�w�f�[�^�̉������˂��x�Ƃ������t�ŏ������Ă��鎖�ԂɂȂ����B�{���Ɏc�O�Ȃ��Ƃ��I
�ʂ�����STAP�זE�͑��݂���̂��H�@���Ȃ��̂��H�@���̐^���݂̂�m�肽���I
�@�����͓��{�̒��D�G�ȉȊw�҂��W���G���[�g�W�c���B���z�̍��Ɨ\�Z���g���ĉ^�c���Ă���B���̗����ɂ����āA�Ȋw�҂��^���̂��ǂ����ł���f�[�^��������A�˂��Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�����A����͔��Ɏc�O�Ȃ��Ƃ��B
�@���ە�����̐�ʂ̋L�҉�ŁA�wSTAP�זE�͂���܂��x�ƌ������Ă���B
����Ȃ�A�ꍏ�������A���̑��݂������āA�G��߂𐰂炷���Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�����ASTAP�זE�̑��݂��Č��A�ؖ��ł��Ȃ��Ȃ�A���ە��������ӂ߂���̂ł͂Ȃ��A���͂Ŕޏ������܂ŃT�|�[�g���Ă�����������̃X�^�b�t�����߂ɂȂ�B
�@�����ɉ��̈Ӑ}�����������ǂ����͕�����Ȃ����A����ȑ傫�Ȕ�����ޏ���l�ł���͂����Ȃ��B����������������A���͂�f�[�^���Ȃǂ��T�|�[�g�����l���^���������ׂ����Ǝv���B
�@�ǂ������A���ە����������҂̂悤�ɂȂ��Ă���C������B |
�Q�O�P�S�N�T���Q�T���i���j
�����V���f�W�^���ł́w�g�c�����x��ǂ�ŁI
�@�����{��k�Ђɂ��Ôg�ŁA������ꌴ�q�͔��d���̘F�S����p�s�\�Ɋׂ�A���ɉߍ��ȃV�r�A�A�N�V�f���g�ƌ�����R���_���n���āA�����郁���g�_�E�����������A�F�S�n�Z�Ƃ����ň����ԂɊׂ����B
�@���̍��X�Ɣ��肭��ٔ��������̂̉ߒ��ɂ��āA���{���̒����ψ����A���̑��̒������܂Ƃ߂��A������ꌴ���̌���̒��ł������g�c�������瓖���̌���̗l�q��������肳��A�w�g�c�����x�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��A����ꕔ���J���ꂽ�B������V�����܂Ƃ߂āA������₷���A�����Ȃǂ������āA��P�͂����R�͂ɂ܂Ƃ߂��B���́A��P�͂����J����Ă���B
�@�L���͒����V���f�W�^���ł̃y�[�W�Ɍf�ڂ���Ă���B
URL�͉��L�̂Ƃ���B
�@�@ http://www.asahi.com/special/yoshida_report/?iref=comtop_rnavi_r1
�@��Q�͖͂����A�Q�U���Ɍf�ڂ����\��A��R�͂͋߁X�ƂȂ��Ă���B
���̋L����ǂނƁA���{�Љ����{�l�C�����_�Ԍ���悤�ȋC������B
����A�؍��̃`���h�Ńt�F���[�̒��v���̂�����A�����̏C�w���s���̍��Z�����]���ɂȂ����B�ɂ܂������̂ł���B
�������A���̃j���[�X�����Ăт����肵���̂́A�D���ȉ��D�����S����ɔ��A��q���ق����炩���ɂ������Ƃł���B�����������Ƃ��؍��ŋN�����Ă���B
�@�����������̂̓t�F���[�̒��v���̂Ƃ͑S�����i���قȂ邪�A����œ����Ă���
�҂́A�Ɩ���A�����̐g�̊댯��`���Ă��A�ӔC���ʂ����`��������͂��B
�����������_�ŁA���́w�g�c�����x��ǂނƁA���X�ƘF�S�n�Z�ɋ߂Â��A�t�߂̕��ː��ʂ��オ��A��@�����钆�ŁA����̖��������ĉ��Ƃ����ĘF�S���p���悤�ƑΉ��ɕ��������l�B�ƁA�����͈̂����Ȍ��Ђ�U�肩�����Ă����l�i���̒��Ȃǁj�Ⓦ�d�{�Ђ̐l�����Ƃ̊ԂɁA�l�ԂƂ��Ď��ׂ��ԓx��������邱�Ƃ����Ď���B
�̂͂悭�w�������x�ƌ������t�������Ƃ�����B���������N��������ʂłȂ��Ă�
���̌��t�͎g��ꂽ�B�������A�{���Ɏ��������ʂ�������Ȃ��ƌ�����ʂɑ����������A�����ɗ��܂��āA�Ɩ���̐ӔC���ʂ����邩�H
���������l���ǂ̂��炢���邩�ł���B
��������A���̋L����ǂ�Œ��������B
���āA�����b��ς���ƁA���{�̎��q���́A���܂Ő푈�͂��Ȃ��Ƃ������@�̂��ƂŁA���q�����͊O���̌R���ƈႢ�L���ɔ����A�����̖��͗a���Ă��邪�A���̗L���͋N���Ȃ��Ƃ����O��ł������B����Ӗ��ł́w�C�y�ȌR���ł������x
�������A���������͌��@���߂�ς��悤�Ƃ��Ă���B�댯�ȕ����n��ɔh�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ肻�����B�����Ȃ�Ύ��q���H�R���̑����͖��𗎂Ƃ����Ƃ��N����B���ɁA�A�����J�̓x�g�i���푈�A�C�����C���N�푈�ȂǂŎႢ���m������l������ł���B���q�����͎d���Ƃ͂����A�댯�Ȑ��ɏo�����邱�Ƃ��N����B
�@�����̍ĉғ�������ɐi�߂��悤�Ƃ��Ă��邪�A���������̎��̂ɑ��鋳�P���{���ɐ��������悤�ȑł���Ă���̂��낤���H
�@���d�@�����v��������A�d���������~�܂�A�|���v���������F�S����₹�Ȃ������B������ً}�p�W�[�[�����d�@�͍���ɐݒu�����B��������v�I�ƌ����̂�
���������B�������A�h�g��������グ���Ă���B�������A�z��O�̂��Ƃ��N����B
���̑z��O�̔@���Ȃ邱�Ƃ��N���Ă��A��Α��v�Ȃ悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�����������Ƃ��ł���̂��낤���H
�����͕s�\�ł���B�����猴���͓��{�ł͉ғ��܂��͑����Ă͂Ȃ�Ȃ��B
���Ƃ��A�߁X�x�m�R�͕�����Ƃ������Ă���B�V�����Ō���x�m�R�͙z�Ƃ��đf���炵���i�F���B�������A�ЂƂ��ё啬����A�V�����Ⓦ���������H�͕��ʂɂȂ�B�ΎR�D���~�蒍���A�߂��̕l�������̊C�ʂɑ�ʂ̊D���~��B�C����
�ΎR�D��������ƁA���܂���p���ł��Ȃ��Ȃ�B
�z��Ƒz��O�ŁA�z��O�̂��Ƃ��N�������グ���Ƃ����̂́A���q�͔��d�ł͒ʗp���Ȃ��B
�@�Η͔��d���������A�����̏��C���₷���ƂŃ^�[�r�����B��₷���͑�ʂ̊C���ł���B�ΎR�D�ŗ�p��̃p�C�v���l�܂邱�Ƃ��l������B����͑厖�̂ł���A���d���̋@�\�̓X�g�b�v����B�������A���d���ł��Ȃ������ŁA����ȏ�̔�Q�͏o�Ȃ��B
�@��͂茴���́A���q�j�̕���ƌ�������������Ă��錴�q�����ƂŃG�l���M�[�����o���Ă���̂ŁA�R�Ăƌ������w�����ŔM�G�l���M�[��̂Ƃ͑S���U�镑�����Ⴄ�B
�@�����̑�Q�͂��y���݂ɓǂ�ł݂����B |
�Q�O�P�S�N�S���P�R���i���j
�w�d�q�낤�����x�@�_�C�\�[�Ō������I

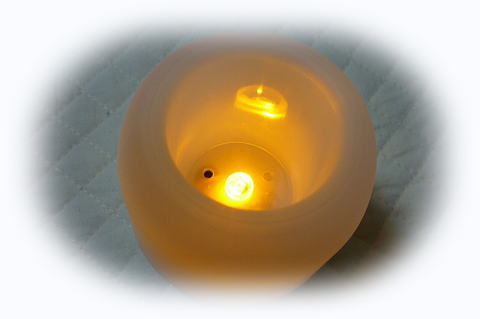 |
 |
| �I�����W�F��LED���낤�����̗h�炬�̂悤�ɖ��ł���B |
�ق̂��Ɍ���LED�̌� |
 |
���i���wLED�s�v�c�ȃL�����h���x
�@�E���𐁂�������ƁA������I�_���I
�@�E�d�rLR44�{�^���d�r3�i����j����
�@�E�A���g�p�ڈ����ԁF20-24����
�@�E�i���j��n�Y�Ɓ@������ |
| |
�����v�Z�����Ă݂悤�I�@�ޗ����v���P�O�O�~�ȉ��A������ő���邩�H
�@�X��̔����[�g�̃}�[�W�����ڂ���A�d���ꉿ�i�͂S�O�`�T�O�~���H
�@�ޗ���͈�̂�����łł��Ă���̂��낤�H
�@
�@���{�̃��m�Â���̊��o�ł́H�H�@�ޗ������łP�O�O�~�ȏシ��͂��B
�@�{�^���d�r�iLR44)�̓e�X�g�p�ɂȂ��Ă��邪�A�ꉞ�_������B
�@�d�r�ゾ���łP�O�O�~�ɂȂ�B
�@���i������ƁA���L�̕��i�ɂȂ�B
�@�@����F
�@�A���i���ރr�j�[����
�@�B���i�̐��^�i�FABS�����i��̕����j�A�|���v���s�����i�{�̏㕔�j
�@�C�I�����W�FLED
�@�D�v�����g���
�@�E����pIC
�@�F�{�^���d�r�i�e�X�g�p�j�F�R�@LR44
�@�G�X���C�h�X�C�b�`
�@�H�}�C�N�F���𐁂�������Ώ�����A�ēx�����Ɠ_������ |
|
�Q�O�P�S�N�S���U��(��)
�N���[�Y�D�ő��̉Ԍ��ƃf�B�i�[���y����
�@��Ђ̏��҂ŁA�鍑�z�e�����̃N���[�Y�D�ɏ�D���A��염�݂̉Ԍ��ƃf�B�i�[���y���܂��Ă�������B
�@��N�Ȃ�A���łɉԂ��U���Ă��鎞����������Ȃ����A���N�̍��͑�������炢�����ɂ́A�Ԃ����������Ă��傤�ǃ^�C�~���O�I�ɂ͍ō��̎����������B
�@
�@��염�݂ɂ͂�������̃\���C���V�m���A�����Ă��āA��R�̉Ԍ��q�łɂ��킢�A�o�[�x�L���E������Ă���O���[�v����R�������B
�@�����͐^�~�̊����ɂȂ�A���O�ł͉Ԍ��ǂ���ł͂Ȃ������Ǝv���B
�@
�@��X�͒鍑�z�e���̃N���[�Y�D�ŁA�D���͒g�������K�Ȓ��߂��y���B
�@�t���R�[�X�����Ƃ����������C���A���{���ȂǍō��̉Ԍ��������Ă�������B���̈ꕔ�̎ʐ^���A�b�v���܂��B
|
 |
| ������������̍� |
 |
| ���̗��݂̍��A�x���`�ɍ����Ă���l�͊����� |
 |
| �鍑�z�e���̃N���[�Y�D�i��V�O�l���j |
 |
| �鍑�z�e���̃N���[�Y�D�ƎV�� |
 |
| �[���̍��m�{�A����i |
 |
| �������蔖�Â��Ȃ����鍑�z�e���Ƒ�� |
2014�N4��5���i�y�j
�w���N�x����ɘa����܂����A���v���ȁH
4��5���̒����V���A�����ɂ����l�ԃh�b�N�w����������얞�x�Ȃǂ�
�����l���������A�ɂ߂�Ƃ����L�����ڂ��Ă��܂��B
�@�����Ől�ԃh�b�N�����l�̒l�������Ƃ���A����܂ł̊��荂���l�ł����N���������Ƃ������������炾�����ł��B�V���6���ɐ����Ɍ��߂āA���N4������^�p����ƂȂ��Ă��܂��B
�@����ɂ��Ɛ����A��_�Ɋ�l���ɂ߂��Ă���̂ŁA����ő��v���H���܂ł̐��l�͉��������̂��Ƃ����^�������قǑ啝�Ȋɘa�ɂȂ��Ă��܂��B�Q�l�܂ŁA���̊�l���L���܂��B
�@�������̗���́A�ŋ߁A��������C���̐l�̕����B�҂��Ƃ������ԓI�ȕ���������B���������l�͍��܂ł̊�ł́A��l���邱�Ƃ������B���N���̂Ɍ����ň��������邱�Ƃ́A����܂����̂ł͂Ȃ����H�Ƃ��������ł���B���^�{�͂ǂ��Ȃ����̂��H
������́A���N�Ō��C�Ȃ̂ɁA���܂ł̊�l���Ă��邩��Ƃ������R�ň�҂�����ʂɏo���B��Ђ������Ȃ��������Ƃ����v�f������悤���B
���o�Ǐ��A�����ǂ�����ꍇ�́A���܂łǂ���悭�Ǘ����邱�Ƃ�����ƌ����Ă���B
 ����́A���s���̏��w�Z�̓��w���������B ����́A���s���̏��w�Z�̓��w���������B
�ŋ߂́A���w���ɗ��e�����s����悤�ŁA���e���ꏏ�ɎQ������l�����������B����������ς�������̂��B
����A�����Ƃ������̂�����B
���w���ɂ́A�����e�ƁA�����̂����������A�������������Ă��������Č��\�ł���I�Ƃ����w�Z������ƕ������B
��N����l�ɗ��e�A�c����4���̍ő�7�l���o�Ȃ�����w���͓��₩���낤�B����ɂ��Ă����{�͕��a�ȍ����Ǝv���B
|
|
���s�̔���l |
�V������l |
���k������
mmHg |
130���� |
88�`147 |
�g��������
mmHg |
85���� |
51�`94 |
�얞�x�iBMI)
|
�j���Ƃ� |
�j�� |
���� |
| 25���� |
18.5�`27.7 |
16.8�`26.1 |
�̋@�\
ALT�qGPI�r |
0�`30 |
10�`37 |
8�`25 |
���ڽ�۰�
mg/dl |
140�`199 |
151�`254 |
30�`44��
145�`238 |
45�`64��
163�`273 |
65�`80��
175�`280 |
LDL�ڽ�۰�
mg/dl |
60�`119 |
72�`178 |
30�`44��
61�`152 |
45�`64��
73�`183 |
65�`80��
84�`190 |
2014�N3��30���i���j
���E��ɂȂ����g���^�����Ԃ̖L�c�͗Y�В��̒k�b
���o�V���������Ǝv�����A�g���^�����Ԃ̖L�c�͒j�В��̒k�b���ڂ��Ă����B
�В��ɏA�C���ꂽ���́A�L�c�Ƃ̌䑂�i�Ƃ����]���ŁA�O�ʓI�ɂ͂Ўア�����������A�ŋ߂̖L�c�͒j�В��̊��U�肪�f���炵���B�K���K���U�߂܂����Ă���B�n�ƉƂł��̂悤�ȎВ����r�o����Ƃ���Ƀg���^�����Ԃ̐�������������B
2010�N�ɃA�����J�Łw�v���E�X�x��肪�\�ʉ����A������ɌĂяo����āA�Ή�����p�͋C�̓łȊ��������B���̌�̖L�c�͒j�В��̑Ή��͍U�߂ɕς�����悤�Ɏv���B
�x���������̂��A�����ꂽ�̂��킩��Ȃ����A�f���炵��������{���W�J���āA���E�̎����ԎY�Ƃ���������Ă���悤�Ɋ�����B
�ȉ��A���ꓚ�����Љ��B |
�g���^�̐����͑������H
2014�N�R�����A���[�}���E�V���b�N�O�ɋL�^�����ߋ��ō��v���X�V���錩�ʂ��B14�N�ɂ͐��E�̔���1000������������Ă���B����ł��L�c�͒j�В��́u�܂��X�^�[�g���C���ɗ������Ƃ��낾�v�Ƌ�������B���̈Ӗ��͉����B�A�C�U�N�ڂ̓W�]�́H�L�c�В��ɕ������B
�܂��A�X�^�[�g���C���ɗ������Ƃ��낾�I
�L�c�͒j�В��́u��x�Ɠ������s���J��Ԃ��Ȃ��̂��c�m�`�v�Ƌ�������
�A�C���O��09�N�R�����͐Ԏ��ł������A�Ɛт��}���Ă��܂��B
�u���[�}���E�V���b�N��R�[�������o�����A�g���^�̗ǂ��Ƃ���∫���Ƃ��낪�����₷���Ȃ����B��͂�䐔�̋}�g��͂悭�Ȃ������B���͂���͖J�߂��邪�A���̗����ł͑�ςȂ��Ƃ��N�����Ă����Ƃ������������͂���B
�}�g��̂Ƃ��͐l������ĂȂ��B�����̃X�s�[�h���l�ވ琬�̃X�s�[�h�������Ă��������Ȃ����B�N�ւɂ��Ƃ���ƁA���鎞�������}�ɐL�������ƂŁA�����̊����キ�Ȃ��Đ܂�
�₷���Ȃ����B�������i�̎d������̔��X�̋��͂������ĂȂ�Ƃ����݂Ƃǂ܂�A�܂��V�����N�ւ𑫂��Ă�����悤�ɂȂ����v
�u�����̎������N���������Ƃ́A�����܂߂ď]�ƈ��݂�Ȃ̐����@��ɂȂ����Ǝv���B
�g���^�Ƃ�����Ђ͈�x����������A��x�Ɠ������s���J��Ԃ��Ȃ��c�m�`�������Ђ��B
���j���ォ��U��Ԃ������A�w���̌������S�N�Ԃ����������獡�̃g���^������x�ƌ�����悤�Ɍo�����������v
�ō��v�X�V�������Ă��u�܂��X�^�[�g���C���v�ƌ����̂͂Ȃ��ł����B
�u����܂ł͋O���C�����ׂ��ۑ肪���m���������A���ꂩ���͑�ς��B�]�ƈ��͕�����Ă��Ȃ��B�g���^�́i1937�N�́j�n���ȗ��̗��j�̒��ł����Ȃ��Ƃ��o�����Ȃ��獡������B���A�ǂ������o���������100���N���}�����邩�B���̐��ʂ͉ߋ��̓w�͂̐��ʁB
���̓w�͎͂��̐���Ő��ʂ��o��B�g���^�͂��������o�g���^�b�`������Ă�����Ђ����A��葱�����Ђ��B������₦���w�X�^�[�g���C�����x�ƌ���������v
14�N�ɂ͐��E�ŏ��߂Ĕ̔��䐔��1000����̑��ɏ��܂��B
�u600����ɒB����܂ł͊�{�I�ɓ��{�ő����ėA�o����r�W�l�X���f���������B�ʂ�L�����Ƃ������ɂȂ������B���ꂪ���A1000����܂ŗ����Ƃ��ɗʂ�L�����Ƃ����������́w���P�ʁx���Ƃ����ƁA����ł̓_���Ȃ�Ȃ����Ǝv���B���͑傫�ȕω��_���B
�V���������̌��P�ʂ͉��������A�ꐶ�����l���Ă��邪�A��艿�l��n������Ƃ��A�����������Ƃ��厖�ɂȂ��Ă���v
�������Y�A300����ɂ͂������u�������Y300����v�̕��j�͈ێ��ł��܂����B
�u�s�ꂪ�k������Όv�Z��͐��藧���Ȃ����A�g���^�͂����ɂ�������Ă���B
�����Ԃ͒n��ɍ���Y�Ƃňב֕ϓ��ł����C�O�ړ]��������Ƃ������̂ł͂Ȃ��B�ٗp�m�ۂ̂��߂ɖ������300������c���킯�ł͂Ȃ��B
�����̂��̂Â���̋����͂��ێ����邽�߂ɕK�v������A�g���^���d�����̕��i��Ђ��A�Ƃ��ɓw�͂��Ă������ƌ����Ă���v
�u�䐔��ǂ�Ȃ��v�ƌ����ƃg���^�͐������Ȃ��̂��Ƌ^������l���o�Ă��܂��B
�u�����͂��Ȃ킿�䐔�̐L�т��ƍl����l������B����͂킩��₷�����A���E�̔���1000�������悤�ȉ�Ђ��䐔��ǂ��Ă���̂ł́A�ԈႦ��悤�ȋC������B�g���^�͂����܂Ŏ����I�Ȑ�����ڎw����Ђ��B�Ɛт��}�㏸������}�~�������肷��̂̓_���B
�P�N�P�N�A�����ɔN�ւ����ނ��Ƃ�������Ђ���邱�ƂɂȂ�B�����܂ő䐔�͌��ʁB
������В��A�C�ȗ������Ɓw�����Ƃ����Ԃ����낤�x�ƌ����Ă���B�w�����Ԃ��ĉ����x�Ƃ݂�Ȃ��l���邱�Ƃ��厖�B��l�ЂƂ肪�����ƁA�����Ԃ�ڎw���B�x�X�g�͂Ȃ��A��Ƀx�^�[�A�x�^�[�B����̓g���^�̌��_�ɂ���l�������v
������Ԃւ̔��f�A����������
���E�̐V�Ԏs������n���ƁA�k�Ă⒆�����L�тĂ��܂����A��������������V�����̐����͓݉����錩�ʂ��ł��B�u���ׂĂ̒n�悪�����ȕ����ނ���ُ�ŁA�e�n�ł����Ȗ�肪�N����̂�������O���Ǝv�������������B
�В��A�C���炵�炭�́A���N�w���N���������N�Ɂx�w�ł���Η��N�͕��������ȔN�Ɂx��
�����Ă������ŋ߂͍l�������ς���Ă����B
�ǂ����ŕK����肪�N����Ƃ����O��ŁA���̉ۑ�ɂǂ��Ή�����̂��Ƃ����ӎ�����ɋ��L���邱�Ƃ��厖���B
���ꂼ��̒n�悪���X�̃I�y���[�V�������ǂ��i�߂邩�ɏW�����Ă���Ό��ʂ͂��̂��Əo�Ă���v
�G�R�J�[����ł̓n�C�u���b�h�ԁi�g�u�j�Ő�s���Ă������A���B�������ӂƂ���
�N���[���f�B�[�[���ԂȂǂƋ������������Ȃ��Ă��܂��B�u�g�u�����������͑��Ђ����܂蒍�ڂ��Ă��Ȃ��������A�ŋ߂͂g�u�𓊓����郁�[�J�[�������Ă����B�g���^�̎�������Ԃɑ��锻�f�͐����������Ǝv���B
�����͂g�u��p�́w�v���E�X�x���������A���̓J���[����N���E���ȂNJ����̎Ԃɂ��ݒ肵�Ă���B�g�u���Ԃ̒��g��ς��邮�炢�̑��݂ɂȂ�A���q�l���I�ׂ�o���G�[�V�����̈�ɂȂ����B�g�u�Ńg���^�͑����̌o��������B�m�E�n�E���玸�s����܂ŁA�����Ȍo����ς�ł��鋭�݂�����v
�u���ꂩ���A�ǂ̃G�R�J�[�����y����̂��A�s��Ƃ��q�l�����߂邱�Ƃ�����A�܂��悭�킩��Ȃ��B�����A�g���^�̂g�u�Z�p�͓d�C�����ԁi�d�u�j�ɂ��R���d�r�ԁi�e�b�u�j�ɂ����p�ł���B�g���^�͂��ׂĂ�p�ӂ��Ă���Ƃ����Ӗ��ŁA���ЂƔ�ׂĈ�ԃ��X�N���������Ǝv���Ăق����v
��N�S���ɑ啝�ȑg�D���������{���A��БS�̂��i���S���́u��P�g���^�v�A
�V�����S���́u��Q�g���^�v�Ȃǂɕ����܂����B
�u�g���^�������I�ɐ������邽�߂̑����ŁA�傫�ȕω����B1000����܂ŋK�͂��傫���Ȃ������ƂɑΉ����A�e�n��̐ӔC�҂m�ɂ����B
�����I�ȃI�y���[�V�����͑�P�g���^�A��Q�g���^�Ȃǂ�S������U�l�̕��В���A���E�e�n�ɔz�u�����W�l�̒n��{�����ɔC����B�]���������ɂ͂܂��������A���������߂�X�s�[�h�͑����Ȃ��Ă����B���ꂩ��͕��В��Ȃǂ̊炪�����ƊO���猩����悤�ɂ������v
�V�g�D�̒��ŖL�c�В��̖����͒������̏������������邱���B
�Z���I�ȍ��N�P�N���ǂ����邩�Ƃ��������̃I�y���[�V�����͂ł��邾������ɔC����B
�����A������������Ă��10�N������v���͕�����Ȃ��B�����Ɏ��̖���������B
����܂ł́A�����������ƂɎ��Ԃ�������Ƃ肪�Ȃ������B�Ɛт��Ԏ����������������肵�Ă���ƁA��肽�����Ƃ������ł��Ȃ��B����Ɩ����Ɍ����ē������ł�����ɂȂ��Ă����B���̈Ӗ��ł��g���^�͍��A�X�^�[�g���C�����v
�u����̓������j�́A�ȑO�̂悤�Ȕ̔��䐔���Ƃ邽�߂̓����ł͂Ȃ��B�Ⴆ�A��N����R�N�ԁA�u�V�H������݂��Ȃ��v�ƌ����Ă��邪�A�������������Ȃ��̂��Ƃ����ƁA�����ł͂Ȃ��B�]���Ɠ����悤�Ȃ����̎g�����͂��Ȃ��Ƃ������b�Z�[�W���B
�Ⴆ�A���܂ł������Ȃ������z�œ����䐔�������悤�Ȃ��̂�������ǂ�ǂ�g���܂��傤�ƌ����Ă�B�k���ύt���悤�Ȃ�Č����ĂȂ��B�����܂Ŗڎw���͎̂����I�ɐ������邱�Ƃ��v
�U���ɎВ��A�C�U�N�ڂɓ���܂��B�ǂ̂悤�Ȋ�Ƃ�ڎw���܂����B
�u�g���^�̎����I�������������Ă���铊���ƂɎ����������ɂ������B
�z���Ȃǂʼn��l���オ���Ă������Ƃ�F�߂Ă��炢�A�������ň���I�ɕۗL���Ă��炦��������B�Ⴆ�A�g���^�Ԃ����l�ɂ�����ɂȂ��Ďx���Ă��炢�A����҂ɂ̓g���^���̔z�������N���̂悤�ɂȂ鑶�݂ɂȂ肽���B���b�Z�[�W�̏o�������ς��Ă����K�v������B
�g���^�͉����l���A�ǂ̕����Ɍ��������Ƃ��Ă���̂��A�o�c�g�b�v�͂ǂ��������f�����Ă���̂��B�����������b�Z�|�W�𑗂�A�����Ƃƒ��ړI�A�ԐړI�ȃL���b�`�{�[�������Ă��������v
|
�Q�O�P�S�N�R���Q�P���i���j
�w���E�Ă��˂���x�������Ƃɗ��s���H
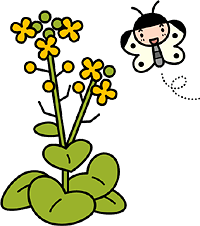
�@�����͏t���ŋx���A�w�����������ފ݂܂Łx�Ƃ������t������܂����A�Ȃ����^�~�̊����ŁA���k�Ȗk�͒�C�������B���A�䕗���݂̕��Ő���ɂȂ�Ƃ����V�C�\��ł��B���ł������̍��̋C���͂W�D�U���Ƃ����^�~�̊����ł��B
�@�E�O�C�X���R�����߂ɚe�������A�卪�┒�̐c����Ԃ��炫�A�t�������Ă��܂����A�ǂ������̓~���R�͂����ЂƖ\�ꂵ�����ł��B
�@�e���r�ō���p�Ȃǂ����Ă��܂��ƁA�\�Z�ψ����{��c�ő�ϋC�ɂȂ���{�ꂪ�����Ƃ��甭�����܂��B���ꂪ�ُ�ɋC�ɂ�����̂ł��B
�@�����͂��̌��t���w���E�Ă��˂���x�Ɩ��t���܂����B
���̌������i�\���j�́u���{�����I�v�Ǝv���܂��̂ŁA���W�o�^���悤���Ǝv���܂��B��k�ł����E�E�B
�@�̂͂��܂蕷���Ȃ������̂ł����A�P�X�X�O�N��̊C�������⋴�{�����̍�����A�������b����Ƃ��g���������w���c�_���Ē����x�Ƃ����������ŁA����Ƃ����c�_���킹���Łw���c�_�x�Ƃ������t�ɓ��������a���������Ă��܂����B�w�c�_���Ē����x�ŏ\�����Ǝv���܂��B���̏�Ɂw���x������Ӗ��͉��Ȃ̂��H�@�悭������܂���B�����Ȃ��A�悭�g���Ă��܂��B�N�ɂ͂����Ă����������������o�����̂��H�ł��B���X�Ƌc�_�����������Ȃ��ł����ƌ��������B
���������A�����ƓƓ��̌�����������܂��B�����Ƃ��悭�g�����t�ŋC�ɂȂ錾�t�Ɂw�E�E�搶�x�Ƃ������t������܂��B���ł����Ȃ̂悤�Ɏg�������Ƃ��������܂����A�ȑO�ɔ�ׂāw�E�E�搶�x�͌������悤�Ɋ����܂��B�w�E�E����x�����\�����Ă��܂����B
�@
�@�ŋ߁A�悭���ɂ��錾�t�Ɂw���c�_�x�������ł����A�w��������x�Ɓw�Ă��˂��Ɂx������܂��B�w�E�E�ɁA��������Ǝ��g��ŎQ��܂��x�A�w�E�E�A�Ă��˂��ɂ��������܂��x�Ȃǂ��A�퓅��̂悤�Ɉ��{�����̌�����o�܂��B
������X�����������܂��B���܂ŁA����������g��ł��Ȃ������̂��H
���܂܂ŁA�Ă��˂��ɐ������Ȃ������̂��H�Ɩ₢�����ł��B
������A������āA�������w���E�Ă��˂���x�Ɩ��t���܂����B
�@�ŋ߁A�����Ƃ͌��t�̗V�сi�����܂��ȕ\���j����������悤�Ɏv���܂��B
�����Ƃ͊j�S��˂������t�ŁA�Ȍ��ɁA�����ɓ��ق��ׂ������A����͊��҂��Ă������Ȃ��Ƃ�������܂����B
�@����̓��ُ��́A���O�Ɏ�����e�ɑ������������O��ŏ��������̂��A��b������ۓǂ݂��邾���ł���A�������b�͑�ǎ҂������B
�@�����ł���A�����Ƃ̌��t�͊��������̌��t�ɂȂ�B�����A�����w���E�Ă��˂���x���J�������̂�������Ȃ��B
�@�����I�Ȍ��t�i�X�g���[�g�ȕ\���j�ŕ�����₷�����ق���ƁA��肪�o�����ɍ��邩��A�ǂ���ɂł����߂��ł���悤�Ȃ����܂��ȁA�����ƓƓ��̕\�����g���B�ω��������ł���B���E�ɋȂ��錾�t������A�㉺�ɕω����錾�t������A���ɕ����Ă��Ă�������Ƃ��Ȃ������܂��ȉ������B
�@���Ƃ��w�E�E���������܂��x�Ƃ������t�́A�����Ƃ⊯���̌��t�ł́w�E�E�͂��Ȃ��x�Ƃ����ے�I�ȈӖ��������ł��B���ꂪ�����A�m��I�ɂȂ�w�O�����Ɍ������܂��x�ƂȂ�炵���B
�@���Ԃł́w�������܂��x�ƌ����A�u�^���ɂ��̖��Ɏ��g�݁A�ۑ��o���O�����ɑΏ�����v�Ƃ����Ӗ��̌��t�ł��B
�@
�@�����Ƃ⊯������́A��������������Ƃ���̌��t�ɒʂ���̂�������܂���B
�@����������₱�����A�ǂ���ɂł����߂ł���悤�Ȍ��t���g��Ȃ��Ƃ������}�������o�Ă��Ăق������̂ł��B�w���Ȃ���A���Ȃ��̂Ȃ���Ȃ��x�Ƃ͂����肵�Ăق����B
�@�O���[�o������������ŁA���O���ƕt�������ɂ́A���{�I�Ȃ悭�����Ή��[���A���������Εs���N�Ȃ����܂��ȁA���_���Ȃ��Ȃ��o���Ȃ��Ƃ�����������⊵�K��Ŕj���A���A���𑁂��͂����肵�Ȃ��Ƌ����ɕ�����B
�@������A�����͔��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����I�グ���āA���ʂ������Ă������ɁA���₱��͔����i�^�����j�A����͍����i�����j�Ƃ����悤�ȑԓx�ł́A���Ԃ̊�Ƌ����ł͑S�����Z���Ȃ��B�����̐��E�����l���낤�B
�@�����������Ƃ�}�Ɋ��҂����̂����A�����ɗ���ꂽ�B
����}���w�搶�x��A���������A�w���c�_�x���A�w��������x�������}�Ɠ��l�Ɏg���������B����Ŗ���}�����v�͂ł��Ȃ��ȁI�Ɗ������B���͂������݊�����Ȃ��Ȃ����B
�@���t�͑���Ǝv���B
�키�����ƁA���Ȃ킿���̒������v���Ă䂭�g���������������Ƃ́A�����ŕ�����₷�����t�ŁA�s���������Ȃ�ƁA�w����A���̎��̘b�͂��������Ӗ��łȂ��A�������x�ƌ������ł��Ȃ��悤�A������ǂ�����ł䂭�l�������B
�������������Ƃ������o�Ă��Ăق����B
�@�V�N�x�\�Z�͑��X�ɐ��������B�i�C�̍��܂��h���ɂ͑����������邱�Ƃɉz�������Ƃ͂Ȃ��B�傫�Ȍ������Ɣ���i�C��ɑg�ݍ���ŁA�ĂёS�����鏊�ōH�����n�܂�B�������A���ɐl�肪�S������Ȃ��Ȃ��Ă���炵���B
�@�H���̎d���͋@�B�������Ă��A�@�B�̑��삪�v�邵�A��{�͎�d���Ȃ̂ŁA������i�݁A�RK�ƌ�����H������œ����l�͏��Ȃ��Ȃ��Ă���B
�@�H�����������ςݏグ�Ă��A�H�����i�܂Ȃ���ΊG�ɕ`�����݂ɂȂ肩�˂Ȃ��B
�@�������A�{���Ƀf�t����E�p���A�i�C���ǂ��Ȃ邱�Ƃ����҂������B
�@�����łȂ���A�؋��������ςݏグ���āA���̔j����ɂȂ���B
|
�Q�O�P�S�N�R���P�S���i���j
���N�A���g�iAM)���W�I������FM�����H
�@�����Ȃ̓d�g�R�c�FM�����̌��������s���A���A���g�̃��W�I�����ɁA�����ԑg�ʼn���������FM�����������邱�Ƃ\�����B
�@����܂ł�FM�����ɂ��AM���W�I�����̕⊮���p�ǂƂ���76.1MH���`89.9MH���ŁA�O���g���M��A�n���I�E�n��I���Ƃ��ĔF�߂��Ă����B
�@������A�A�i���O�e���r�̃��[�`�����l���Ŏg���Ă������g���̋��d�g�𗘗p���āA94.9MH���܂ł̎��g�������p���A�ЊQ��A���i�s�s�^�A�O���g���M��A�n���I�E�n��I��A�ЊQ��j�̂���FM���p�ǂ̓��������߂��B���g���́A90.1MH���`94.9MH��
�ȒP�Ɍ����ƁA������Η��N���ɁANHK���A���A�����̃��W�I�����Ɠ����ԑg����������FM�������n�܂�Ƃ������ƁB
���ł́A���������A���������A���W�I��オFM�d�g���o���悤�ł��B
�莝����FM���W�I�̎�M���g����76MH���`99MH���̂��̂Ȃ�A����FM���������Ƃ��ł���悤�ɂȂ肻���ł��B
���̐}�́A�����Ȃ̓d�g�R�c��̎������甲�����܂����B |
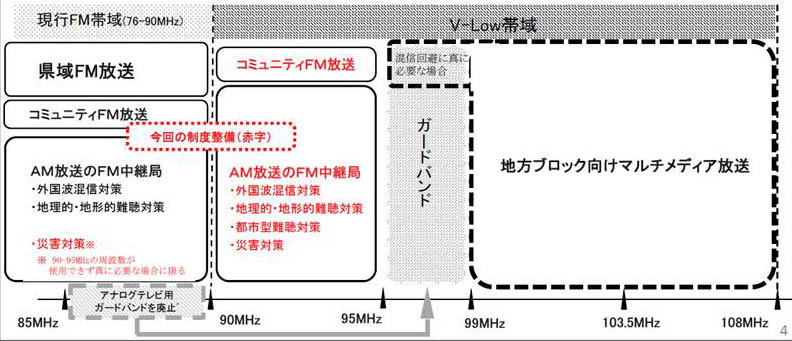
2014�N3��7���i���j
PET�摜�f�f�͂ǂ��܂Ői�̂��H
�@����A�N�Ɉ�x�̐l�ԃh�b�N�����B
��N��A�Q�A3��߂��̕a�@�Ō��N�f�f�������A��ʂ̕a�l�Ɠ����悤�Ɍ��N�f�f����̂͂�����C�����悭�Ȃ��̂ŁA���̐��N�O�������́w�p�i�\�j�b�N���N�Ǘ��Z���^�[�x�ŁA�N�����ɉƓ��Ɠ�l�Ŏ邱�Ƃ�N���s���̈�Ƃ��Ă���B
���N�����������ɁA�l�ԃh�b�N�����B���ʂ͓��ɑ傫�Ȗ�肪�Ȃ��������A��C�ɂ�����_���������B
�@�l�ԃh�b�N�͊�{�R�[�X�ƁA�lj����ڂ��I�v�V�����őI���ł���悤�ɂȂ��Ă���B���̒��ŁA��ᇃ}�[�J�[�Ƃ����I�v�V����������̂ŁA����N�Ă���B����͍̌����āA�K�����o������Ȃ���ς��������o���邱�ƂŎ�ᇂ̃}�[�J�[�ɂȂ�ƌ����Ă���B
�@��ᇃ}�[�J�[�ŗL���ɂȂ����̂͑O���B�K�����ł���PSA����������B�����̎�ᇃ}�[�J�[�����̌��ʁA�Ɠ��̐��l����N�ɑ����č��N�����E�l��荂���A�S�z�ɂȂ����̂ŁAPET�i�摜�j�f�f�������邱�Ƃɂ����B
�@�a�@�ɍs���āA���Ȃ̐搶�̏Љ������������A�K�����m�肵�Ȃ��ƕی����K�p����Ȃ��ƌ���ꂽ�B��ᇃ}�[�J�[�̒l�����E���Ă��Ă��A�ی��������Ȃ����Ƃ����������B
�@����Ȃ�A���̂��߂̎�ᇃ}�[�J�[�Ȃ̂��Ǝv�������A�������ʂ��Q�N�������l�������Ă���̂ŁA����Ŏ邱�Ƃɂ����B
�@PET�����́A�����O�Ƀ��W�I�A�C�\�g�[�v�i���ː����ʌ��f�j�𒍎˂��āA��1���Ԉ��Âɂ��āA�S�g�Ɏ��s���n������Ԃő��肷��B
�K��������A�K���͍זE���������̂ŁA�����i�G�l���M�[�j��������������B���ː����ʌ��f�͂��̓����ƈꏏ�ɂȂ��Ă��āA�K���ɏW������̂ŁA���̕��z���R�����摜�ɂƂ�K���̌��o���ł���炵���B
�@���܂ŁA�C���^�[�l�b�g�̏��ł́APET�摜�f�f�̓K�����o�̍Ő�[�Z�p�ŁA���������x�̏����ȃK���܂Ō��o�ł��闝�z�I�Ȍ������@���Ƃ���Ă����B
�@������PET�͋@�킪���ɍ����ŁA���A�����~������炵���A���̂��߁A�f�Ô�p���ׂ�ڂ��ɍ����B�ی��K�p���Ă�3���~�`4���~����炵���B�@���ʂ�X��CT�X�L�����ƃZ�b�g�ɂȂ��Ă��āA�S�g�X�L��������B
����ł�10��6��~�ł������B
�@�f�Ô�����̂́APET�̋@�B�̏��p��傫�����炾�Ǝv���Ă������A����ȏ�ɍ����̂́A���ː����ʌ��f�i�A�C�\�g�[�v�j�̖�܂������炵���B
�@�����������w�肳��A���̓����ɎȂ���A���̖�܂��L�������Ȃ�����̂ŁA�L�����Z���������Ȃ����Ƃ����������B�L�����Z������A6���~�قǃL�����Z�����������̂Œ��ӂ�����B
�@���ː����ʌ��f������A���ԂƂƂ��ɕ��ː����o���ĕ��Ă䂭�B�����炱�̖�i�͎戵���敪���������Ǘ�����Ă���B
�܂��A����PET������A�D�w����⏬���ɋ߂Â��Ȃ��悤���ӂ��ꂽ�B�����͑̂���ア�Ȃ�����ː����o��炵�����Ƃ�������ꂽ�B
�@�Ȃ̌����͖����ɍς�ŁA���̌��ʂ��ɍēx�a�@�ɍs�����B
���������܂ŁA�f�f���ʂ́A�܂��K���̋^���͂Ȃ��Ƃ������Ƃ������̂ŁA����͈��S�ł������A���̐搶�̘b�ł́A�w����PET�����܂�i�߂܂���B��͂茟�f�́A���ځA�ڂŊ��������邱�Ƃł��x�Ƃ����b�������B
�w�݂͈݃J�����ŁA���͑咰�J�����ŁA����ȊO�̓����͒����g�摜�f�f�Łx����A�w�܂����v�ł��x�Ƃ����b�����B
�@���̐搶�̘b�ł́wPET�͍������ɂ́A���̒��Ō����Ă���قǁA���o�\�͂̓_�Ŋ��ɍ���Ȃ��x�Ƃ����b�������B�����PET��ے肵���b�ł͂Ȃ��A���N�f�f�Ƃ����a�C�����邽�߂̍s�ׂƂ��Ă͂Ƃ����Ӗ��B
�@�K���ɂȂ��Ă��܂����ꍇ�A�]�ڂ���x����������̂ɂ͗L���Ȃ̂ŁA���̏ꍇ�͕ی����K�p�����B
�@�l�ԃh�b�N�⌒�N�f�f��PET����l�����\���邪�A�ŋ߁A�����a�@�ł͂��܂�i�߂Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ������B
�@���Ԃ̐l�ԃh�b�N����ɂ��Ă����Ë@�ւ�PET���X�I�ɐ�`���Ă���B���ꂪ���ɂ̌��f���ƌ�������̕\�����g���Ă���B
�@�Ȃ̌��f���ʁA�ُ�͂܂������Ȃ��Ƃ������n�t������������̂ŁA���S�����B���S����10���~���������A�������͍l�������悾�I
�@��������x�͌o�����Ă����Έ��S�ł���B
|
2014�N2��14���i���j
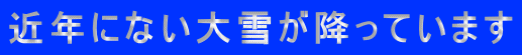
�����͖閾��������A�Ⴊ�~��A���Ȃ��A�~�葱���Ă��܂��B
�O�C���͂Q�D�Q���ŁA�O�͎v������芦���������܂��A�ϐ�
��10cm���x�ɂȂ��Ă��܂��B�O�ɏo��ɂ͒��C�𗚂��Ȃ���
��ςł��B���͋ߔN�A�Ⴊ���܂�~��Ȃ������̂ł����A����
���͒������A���ꂩ��������~�݂����ɂ���܂���B�@�傩�Â�
�̏�����̏d�݂ɑς���悤�ɁA�x�������܂����B���̂܂܂ł�
�}���d�݂Ő܂ꂻ���ł��B�{���ɋv���Ԃ�̔���̐��E�ł��B

��O��ꠂɐς�������X�q

�傩�Â��̏��A�}����̏d�݂Ő���Ă��܂�

���H����Ƃ̌i�F�ł����A�����Ⴊ�~���Ă��܂�
2014/02/14�@AM10:45����

����̉ԗ��i�J�����j�Ɣ~�ɐς�������

�Ƃ̑O�̌���
2014�N2��8��(�y)
�X�J�C�c���[�ɏ��܂���
�@�Q���Q���ɓ����ɍs���A�@�����X�J�C�c���[�ɏ��܂����B
�@�A���e�i�̐�[�܂ł͂U�R�S���i���T�V�j����܂��B
���j���ő�ύ��ݍ����Ă��܂������A���ʃ��[�g�� �X���[�Y�ɒʉ߂ł��܂����B
�@�܂��A�����R�T�O���̓W�]�f�b�L�֑�^�W�]�V���g��(�G���x�[�^�j�ŏ��܂��B
�b���P�O���̒������G���x�[�^�ł����A45�b�قǂ�����܂��B�ł������Ƃ����Ԃɒ����܂��B
�@����ɂP�O�O����ɂ���W�]��L�܂ŏ��^�G���x�[�^�ɏ�芷���܂��B�����͒n�㍂�S�T�O���ɂ���A��s�@�̑�����̒��߂̂悤�ȍ��o���o���܂��B�p�m���}�̂悤�Ȍi�F���L����܂��̂ŁA���������͂ł��B
�@��͂�A�n�ォ�猩�グ��X�J�C�c���[�ƁA����Č����낷�i�F�Ƃ͑S���C���[�W���Ⴂ�܂��B�f�W�J���ŎB���Ă����ʐ^��Y�t���܂��̂ŁA�����������B
�@
�@2���͒g�����t���̂悤�ȏ����K�X���ۂ���Ԃł����̂ŁA�ʐ^�͍���ł��B
�X�J�C�c���[�̌����z�[���y�[�WURL�͉��L�̂Ƃ���ł��B�������������B
�@�@http://www.tokyo-skytree.jp/
�@�@
�@ �@�@ �@�@
�@���Ԃ̃X�J�C�c���[�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�[�����C�g�A�b�v���ꂽ�c���[
�@ �@ �@
�@�W�]��L�̈ē��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����낵���i�F
�@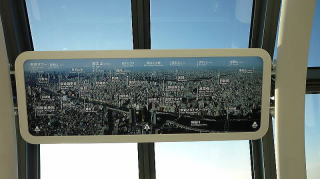 �@ �@
�@�W�]��L�̈ē��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����낵���i�F
�@ �@ �@
�@�@�W�]��L�̈ē��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����낵�����c��
�@
�@ �@ �@
�@�@�W�]��L�̃K���X�̂̂�����(���j�@�@�@�@�@�K���X������n��̌i�F
�@
�@�@�@��^�W�]�V���g���ɏ�荞��(����j
|
2014�N2��6��(��)
���ҕK���͔������Ȃ��̂��H
�@ IT�@��̑㖼���������p�\�R���̔̔����v�킵���Ȃ��炵���B�����̓X�}�[�g�t�H����^�u���b�g�[���ii-Pad�Ȃǁj�̋}���ȕ��y�ŁA�p�\�R�����v��H���Ă���B
�@
�@�X�}�[�g�t�H���͊؍��̃T���X���d�q��Ђɂ���Ă��܂��������ŁA���{���[�J�͋�킵�Ă���B
�@�ꎞ���A���{���[�J�e�Ђ̓p�\�R���ŋC��f���Ă����B�ꎞ�͕x�m�ʁANEC���g�b�v�ŁA���ŁA�����A�V���[�v�Ȃǂ����ǂ������A���łɃf�X�N�g�b�v�͉ߋ��̂��̂ɂȂ�A���{���[�J�e�Ђ͓P�ނ����B
�@�ƒ�p�Ƃ��Ă͈ꕔ�̐l�i�Q�[���}�j�A��p�\�R���D���Ȑl�Ȃǁj�ȊO�Ɏg���Ȃ��悤�ɂȂ����B
�@���[����C���^�[�l�b�g��A�p�\�R���Ńe���r������悤�Ȏg���������镁�ʂ̐l�́A�m�[�g�^�p�\�R���ŏ\�����Ƃ������B
�@�m�[�g�^�p�\�R���͍ŐV�^�ł͔��ɓ��쑬�x�������Ȃ�S�����Ȃ��g����B���̃m�[�g�^�p�\�R���͗p�r�ɂ����2��ނɕ������B
�@�Ƃ̒��ŁA�e�[�u������̏�Ŏg���^�C�v�ƁA�����������o�C���p�̃^�C�v������B�O�҂̃^�C�v�́A���m�{��AHP��ADell��A�G�C�T�[��A�A�b�v����AASUS�Ȃǂ��傫�ȃV�F�A�������Ă���B����ɑ����ĕx�m�ʂ�NEC�Ȃǂ����邪�ANEC�͍ŋ߁A���m�{�ɐg���肵���B���m�{�͒����̉�ЂŁAIBM����p�\�R�����Ƃ����A���g�b�v�V�F�A�ɋ߂Â��Ă���B
�@����A���������p���o�C���m�[�g�^�p�\�R���́A��Ј��Ȃǂ��Ɩ��p�Ƃ��Ďg������Panasonic�̃��b�c�m�[�g����ϐl�C������B���̕���͎����^�т��邽�߂ɁA���ŁA���ɂ����āA�y���āA�d�r���쎞�Ԃ��������Ƃ��v�������B�J�o���ɃX�|�b�g����Ď��������Ă����Ȃ����x���K�v�ɂȂ�B����������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�v�����̓�����v�������B�y���ċ��������ł���}�O�l�V���E����`�^���������g���A�A���~���y���ċ��x���傫�������𐬌`����➑̂Ɏg�p���Ă���B������������Ȏd�l�ɂȂ�Ɠ��{���[�J�͉�R�A�Z�p�͂�����B���̑��l�i�͍����B
�@��ʂ̃m�[�g�^�p�\�R���͐��\�ƒl�i�����������̐��E�B���b�c�m�[�g�͈Ⴄ�p�r�Ɋ��H�����o���Ă���B
�@���͍����̒����V���ɁA�\�j�[���wVAIO�x�u�����h�̃p�\�R�����Ƃ��玖����P�ނ����߂��Ƃ����L�����ڂ��Ă����B�܂����I�Ƃ�������������B
��ʂ�NEC�����m�{�ɐg���肵���L�������������肾�B�p�\�R�����Ƃ��Ԏ������ł͎d�����Ȃ��B
�@
�@�ߋ��̐��҂͕K�����ނ���̂��H
�@���������Ӗ��ł́A���݁A���E��IT���Ƃ�Ȋ����Ă���T���X���������ɗ��āA���X�É_�����ꍞ�߂Ă����Ƃ����L��������B
�@
�@�؍��ő�̔��s�������ւ钩�N����1��8���A�u�w�T���X���d�q�Ȃ��؍��o�ρx�ɔ�����v�Ƒ肷��А����f�ڂ����B
�@�T���X���d�q��2013�N10�`12���c�Ɨ��v��8��3000���E�H���i��8100���~�j�ƁA
1�N�O���2���߂����������B�؍��o�ςɉe�����y�ڂ����Ԃɔ�����̂́A�؍����{�����ׂ��d���ł���Ǝw�E���Ă���B
�@�u�t�B�������h�ł��ėA�o��25%�A�����J��������35%�A�@�l�Ŏ���23%���߂Ă����m�L�A�́A�A�b�v���ƃT���X���d�q�̍U���ɂ���Čo�c���قڔj�]���A���ł̓}�C�N���\�t�g�Ђ̎P���ɓ����Ă��܂����B
�@�m�L�A�̖v���Ńt�B�������h�͍��S�̂̐����ɋ}�u���[�L��������A���Ɨ����傫�����ˏオ���Ă��܂����B
�@�X�}�z�͋߂�������1���~�ɂ܂ʼn��i�������邾�낤�B����ɂ��̌�́A5000�~���炢�ɂ܂łȂ�\���������B
�@��{�@�\����������A�lj��@�\�̓A�v���őΉ�����Ƃ����`�̒ቿ�i�X�}�z���A���㔄��グ�䐔�̒��S�ƂȂ�V������r�㍑�ł́A�嗬�ɂȂ�͂������炾�B
�@�����Ȃ������A���݂̃T���X���d�q�́u5000�~�X�}�z�v�ɑΉ��ł���̂��B�������ɋ^��ł���B
�@
�@�T���X���d�q��������邾���Ȃ�A���F�͈��Ƃ̘b�ōςށB���́A�؍��o�ς��T���X���d�q�ɑ傫���ˑ����Ă��܂��Ă��邱�ƁB
�@�T���X���d�q�̔��㍂��2013�N��230���E�H���i��22���~�j�ȏ�A�؍��o�ρiGDP�j��2�����߂Ă���B���̈Ӗ��ł́A�T���X���d�q���X���Ɗ؍��o�ςɐ[���ȉe�����y�ڂ��B
�@�ꉞ�A�T���X���d�q�Ɏ����傫�ȉ�ЂƂ��ẮA���㎩���ԁA�S�|���[�J�[�̃|�X�R�A�Ɠd��LG�Ȃǂ����݂���B�����̉�Ђ̓T���X���d�q�ɔ�ׂ�Ə����B�T���X���d�q�̃T�C�Y���ʊi�ɑ傫���B
�@���̂܂܁A�T���X���d�q���R�P�����ɁA�؍��o�ς��x�����Ђ����݂��Ȃ����ƂɂȂ�B
�@�ƍٌ^�̌o�c�҂̔��f��������ɓ������āA�Ɛт�L���Ă����Ƃ����Ӗ��ł́A��p�̍��C�i�z���n�C�j�O���[�v�𗦂���s����i�O�I�E�^�C�~���j���Ǝ��Ă���B
�@�����A���������o�c��@�́A�J���X�}�I�Ȍo�c�҂���������̔������傫���B�o�c���}�C���h�ɂȂ��Ĕ��f���x��A���z�Ɋׂ邱�Ƃ��z�肳���B
�@������������A������u���̃T���X���d�q�v���o�Ă��邩������Ȃ����A���̂Ƃ���͂�����������͌����Ȃ��B�T���X���ɂƂ��Ă��A�؍��ɂƂ��Ă��A�������Ƃ𗦂���J���X�}�o�c�҂̍ˊo�ɗ�������c�P�������߂Â��Ă���悤�Ɏv����B
�@���̗L���ȁw���ƕ���x�̏����o���̖����A
�@�@�_�����ɂ̏��̐��A���s����̋�������A
�@�@�����o���̉Ԃ̐F�A���ҕK���̗�������킷
�@�@�������l���v�����炸�A�����t�̐��̖��̂��Ƃ�
�@�@�������҂����ɂ͖łтʁA�ɕ��̑O�̐o�ɓ��� |
�@��Ƃ͉i���ɉh���邱�Ƃ͓���B��Ƃ͐������ł���B�������͎���������B
�@�����d��̑n�ƎҁA�����K�V����������Ă�����Ђ�25�N���ƁA����ɂ�50�N���ƂƂ����ߖڂɁA��Ђ��ǂ������c�邩�A�זE�̐V��ӂ��s���邩�A�g�D�͂܂��ɐ����̍זE�Ɠ������ƁB���̕ω��ɑΉ��ł��邩�ǂ����ɂ������Ă���B |
2014�N2��5��(��)
�w�ڍՁi���������j�x�������m�ł����H

�@���{���͓��{�e�n�ő����Ă��܂����A�����ƌĂ�������R���钆�ŁA�ŋ߁A���ɐl�C�������Č��̎��ɂȂ��Ă���R�����̎��ł��B
�@�ŋ߁A���{�𗣂ꂪ�������A����ʂ̌����ɂ��𑠂̕���p�Ƃ������A������x�̓h����Ɋׂ����B���̈��͌����ɑh�����B
�@�����v���͉����H
�@�@�@���{���͖�����Ĉ��ނ��́A�ʂ��玿��
�@�@�A���đ����ɂ�������āA���ꂵ�����Y���Ȃ�
�@�@�B���m������Ј��ɁA�i���Ǘ��̓O��
�@�@�C�~�G��������ʔN�����ɐ�ւ�
�@�@�D�C�O�ւ̐i�o�A���Ƀt�����X�ɒ��́A���c�X�J��
�@�R���̎R���̏����Ȏ�Ђ���O���N���āA��L�̂悤�Ȏ�̃R���Z�v�g��O�ꂵ�Ď��s���A���܂����ɂ�������Ă���Ă������Ƃ����ЂƂ̍��ʉ��ɐ��������B
�@���傤�ǁA���{�l�����n�����āA�ʂ����߂鎞�ォ��L���Ȑ����A�������߂鎞��ɂȂ�������ɂ��܂����v�����ƌ�����B
�@���{���̒���́A��̓`���ɌӍ��������āA�g���甲���o���Ȃ������B���͏����ȁA�������⍑�̎𑠂Ƃ����t���ɂ��������Ƃ��A�ނ����̉��v�ɒ��肵�₷�������B���̂܂܂łׂ͒��Ƃ������ˍۂɗ�������Ă������Ƃ������B
�@�O�ꂵ�āw�������낤�x�Ƃ������_�����Â��Ă���B
�@�w�ڍՁx�͍���A�ꗬ�u�����h���āA���̎��ɂȂ����A�Ȃ��Ȃ���ɓ���Ȃ��B
����15�N�ɐV�H�ꂪ�������ғ�����B��������ΐ��Y�ʂ�����Ƒ�����̂ŁA��ɓ��邩���E�E�E�E�B���҂������B
�@
���L�̃z�[���y�[�W�����Q�l�ɁI�I
�@�w�ڍՁx�̏Љ�L��
�@�@http://www.nippon.com/ja/features/c006
�@����
�@�@http://www.asahishuzo.ne.jp/index.php
�@�ŋ߁A�����邱�Ƃł����A�w���̒��͎��ɖʔ����I�x�Ƃ������ƁB
�@���̒��ɂ͂����Ȏd��������A�݂�Ȉꐶ�������A�w�͂��Ă���B�������A�d���ɂ���ẮA�Љ�̗����A�Z�p�̒�����A�j�[�Y�̕ω���A�~���Ȃǂ����Ȋ��ω��ɂ�莖�Ƃ����藧���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ������B
�@�v�́A���܂ł���Ă��������ł͊��̕ω��ɑΉ��ł��Ȃ��̂ŁA���Ƃ����藧���Ȃ��Ȃ�B������ׂꂽ��A�P�ނ����肷��B
�@
�@���{���������݂����{�𗣂ꂵ�āA���������t�����ɂ��鏤�i���ƌ����Ă����B���ɁA���̃z�[���y�[�W�����Ă��A�s��̏k���������ɃO���t�Ŏ�����Ă���B�����ʼn������łĂȂ���Ђׂ͒��^���ɂ���B
�@
�@�t�������̂悤�ɁA���{��Ƃ������܂ł̎��Ƃ��p�����Ȃ���A�t���̒��Ńh���h���L�т邱�Ƃ��ł���B
�@���̍��A�Ⴂ�͉��Ȃ̂��H
�@�v�́A���l�Ɠ������Ƃ�����Ă��ẮA���ʂ͊F�Ɠ������ƁB
���l���ׂ��A�������������ׂ��Ƃ������Ƃɂ����Ȃ�Ȃ��B
�@�����ŁA���l�ƁA���ЂƈႤ���Ƃ����B���̈Ⴂ�����ω��ɑ��ēK��������e�A���g�݂łȂ���ΈӖ����Ȃ��B���ł�����ł����ЂƈႤ���Ƃ����ΐ����c����ł͂Ȃ��B
�@�w�ڍՁx�́A�w���������A������Ƃ������������݂����I���X�����Ă������x�A���������B�ꂽ�j�[�Y�������Ɍ������đΉ������B
�@���{���ɂ́A�����A���R�[���������Ă���B
�����A���R�[���́A�T�g�E�L�r���瓜�����i������̍�肩���i�@�ێ��j���y��ŃA���R�[�����y�����đ������A���R�[���ŁA�������J��Ԃ��A���x���X�T���ȏ�ɂ������F�E���L���G�`���A���R�[���̂��ƁB
�@�����M�����������{���ɓK�x�Ɋ�߂��ĉ����邱�ƂŁA�y��̍��������߂₷���Ȃ�A�A���R�[���x���̒��������R�ɂł��A������Ƃ������ݖ��ɂȂ�A�܂����ʂ��ł���B
�@����������ɏ����A���R�[�����Q�O���O��ɔ��߂ĉ�����B
�@��������������Ƃ����������́A�R���̐��ēx�����̕\���ŁA30-50���O��̐��ēx�����̂��̂�����A����ȏ�ɐ��Ă��ăR���̒��S���������g���̂������ƌĂԁB
�@
�@����ɑ��A�����́A���đ�����������Ȃ��B���Ď��Ƃ����Ăѕ��́A�����A���R�[����S�������Ȃ��A�M���������܂܂̂����ŁA�����肯�̂Ȃ������̂܂܂̈�ԍ����Ȃ����ł���B
�@��ʂ̑������́A���r���̃��x��������Ε����邪�A�����\�ɏ����A���R�[���������Ă��邱�Ƃ�\�����Ă���B
�@�l�i����������A�w�ڍՁx���đ�����������悭���ꂽ�ƌ�����ł͂Ȃ��B
�����l�i������ɂ́A���q���[�����邨�������A���킢���Ȃ��ƌ�����������Ȃ��B
�@�w�ڍՁx�����܂��܂ŁA���̍����v���i����ۏ��邽�ߑ�ςȓw�͂�����Ă���B�ڂ������e�́A��̃z�[���y�[�W���������������B
�@�������t���̒��ɁA�����ɂ��Ό��������o�����Ƃ��ł���Ƃ����ǂ����Ⴞ�Ǝv���B
�@������������́A���ɂ�����ł�����B
�@�v�́A
�@�@�K���w���Ƃ��Ȃ�x�Ƃ��������ӎu��
�@�A���܂łƈႤ�s�����N����
�@�B����ŊԈႢ�Ȃ����H�A�`�F�b�N���Ȃ���C������
�@�C�S�Ј��̃x�N�g�������W����
�@�D���g�݂��i�荞��
�ȂǁA���̂Â���̌��_����������Ǝv���܂��B
�@ |
2014�N2��5��(��)
���̐����̓����́H
9-3��1/3+�P���H
�����Ђ̓��Ў����ɏo�������ł����A�����҂͂S�O���ł����B
���āA���Ȃ��̓����́H�@������1�ł��B
9-3��1/3+�P�̌v�Z�́A�|���Z�A����Z���ɂ��邱�Ƃ͏��w�Z��
�K�������Ƃ��Ǝv���܂��B3��1/3���X�ł��B
9-3��1/3+1��9-9+1���P�@�@�ƂȂ�܂��B
���̌v�Z���ł��Ȃ��l�������Ă���悤�ł��B���Ȃ��͂ł��܂������H
�i2��5���A�����V���������j
2014�N2��4��(��)
�w�j���́x�������m�ł����H
�g��@�O����̍�ŁA��ρA���̐[���l�̐S����₷��
�\�������f���炵�����ł��B�������ɂ悭�ǂ܂�邻���ł����A
�g�삳����]��̃j���[�X�ŁA���߂Ă��̎���m��܂����B
��������̏ꏊ�Ōf�ڂ��꒘�쌠�̖��Ȃ������ł��̂�
�Љ�܂��B�@�{���ɂ��������ӂ��ɂ��肽�����̂ł��ˁB
��l���r�܂������邽�߂ɂ�
�����ł���ق�������
���h�߂��Ȃ��ق�������
���h�߂��邱�Ƃ�
���������Ȃ����Ƃ���
�C�Â��Ă���ق�������
�������߂����Ȃ��ق�������
�����Ȃ�ĕs���R�Ȃ��Ƃ���
�����Ԃ��Ă���ق�������
��l�̂��� �ǂ��炩��
�ӂ����Ă���ق�������
���������Ă���ق�������
�݂��ɔ��邱�Ƃ������Ă�
���ł��鎑�i�������ɂ��������ǂ���
���Ƃŋ^�킵���Ȃ�ق�������
���������Ƃ������Ƃ��́A
�����Ђ����߂ɂ���ق�������
���������Ƃ������Ƃ��́A
����������₷�����̂���
�C�Â��Ă���ق�������
���h�ł��肽���Ƃ�
���������肽���Ƃ�����
�����ȋْ��ɂ͐F�ڂ��g�킸
�������䂽����
���𗁂тĂ���ق�������
���N�ŕ��ɐ�����Ȃ���
�����Ă��邱�Ƃ̂Ȃ�������
�ӂƋ����M���Ȃ�
����ȓ��������Ă�����
�����ĂȂ� �����M���Ȃ�̂�
�ق��Ă��Ă��ӂ���ɂ�
�킩��̂ł����Ăق���
|
�Q�O�P�S�N�Q���P��(�y)
���E���������I�@�唭���̏��ە�����͂ǂ������l�H
�����̐V����e���r�����āA�������B���܂ł̐����̂��ƂɂȂ�זE����̊T�O��
�ł����I�̑唭���A���₱��͔����Ƃ����ׂ��Ȃ̂��낤���H
�Ƃɂ����C�M���X�̃l�C�`�������A�w�������_����M������̂��I�x�Ɠ��������Ă����قǁA�Ƃɂ�������I�Ȕ������Ƃ������ƁB
���̔�����(�����ҁj�͂R�O�̂肯����i���n���q�̂��Ƃ炵���j�ŁA�e���r�Ŕq������Ƃ������ʂ̐l�Ɍ�����B�G�v�����p�Ō����Ɏ��g�ގp�͂��킢�炵������������B���̏��ە�����͂�͂蕁�ʂ̐l�ł͂Ȃ����Ƃ����������B
�ޏ������w�Q�N���̎��ɏ������G�b�Z�C������B�����ǂ�ŁA���̕�����������l�͂������l���Ǝv���B��l�ł��Ȃ��Ȃ��`���Ȃ����͂��I
������Љ��B
�@���̕��͂́A�P�X�X�V�N�A�u��S�R����N�Ǐ����z����t���R���N�[���v�i�����V���ЁE�S���w�Z�}���ً��c���Áj�ŋ��璷�܂ɑI��A�S���R���N�[���ł����I�����Ƃ�����i�ł��B
�u�������ȉ��l�������Ă��ꂽ�@��l�ɂȂ�Ƃ������Ɓv
�@�@�@�@���ˎs����Z���Q�N�E���ە����q
�@���͑�l�ɂȂ肽���Ȃ��B���X�����Ă��邱�Ƃ����邩�炾�B����́A�������������Ȃ��Ă���Ƃ������ƁB�������̂ł͂Ȃ��B����S�̐��E���ł���B������m��Βm��قǏ������Ȃ��Ă����̂��B���́A����Ȍ������瓦�������āA������Ȃ��āA�d�����Ȃ������B�����̂ĂĂ܂ő�l�ɂȂ�Ӗ����ĂȂ낤�B����Ȗ₢�����̒��������߂Ă����B�ł��A���͓������������B�����ȉ��l�������Ă��ꂽ�B���͂��̖{�������Ƃ����ƒT���Ă����悤�ȋC������B
�@�u�l�v�Ǝ��́A���Ă���ȂƎv�����B��l�Ƃ��A�����Ԃ��ꂻ���Ȍ�������A�����邱�Ƃ��A����邱�Ƃ��ł����ɂ����B��l�ɂȂ�Ƃ������́A�����̂āA���������߂鎖���Ǝv���Ă����B�ł��A���l�́A�����������B�u���܂��́A��������Ɩ���ɗ����āA�������T�����[�}���ň�����A�d���A�d���ɒǂ��Ă��閲���݂Ă���B�����āA��x�b�h�ɓ���Ƃ��܂��͂悤�₭�ڂ��o�܂���Ӓ��A�����̖{���̎p�ɖ߂��̂��B����ۂǂ�������Ȃ����A���̂ق����v�ƁB���͂��̎��A�������邩�猻����������̂��Ƃ�������������ꂽ�悤�ȋC�������B
�@�����ȉ��l�́A�l�Ԃ̖{���̎p�Ȃ̂��Ǝv���B�{���݂͂�ȉ��l�������̂��Ǝv���B�����A�݂�ȑ�l�Ƃ������ʂ����Ԃ�A�Љ�ɓK�����A�����Ɛ���Ă��������ɁA�Y��Ă��܂����̂��Ǝv���B
�@�����A�����ȉ��l�Ɓu�l�v�������A�i���̖��̋�z�������B���́A�i���̖��������Ƃ́A���������낵�������Ǝv���B�����Ă��邱�Ƃ̂��炵����Y��Ă��܂��Ǝv�����炾�B����ɁA�{���̉i���̖��Ƃ́A�����̌����q���ցA�܂����̎q���ւƎ���Ă������Ƃ��Ǝv���B
�@���l�́A�l�͎��琯�ɂȂ�A���l�͐����琶�܂��ƌ����Ă����B���́A���l�͎���ł������l�X�̖��ł���肢�ł���悤�ȋC�������B�l�Ԃ͎��琯�ɂȂ�A���l�ɂȂ�A����ł���i�����͂��܂�݂����������B�������̉i���́A����������i���̖����A�����ƃX�e�L�Ȏ����Ǝv���B
�@�u�l�v�͉��l�Ƃ�������ɂ��鎞���A���Ȃ̂������Ȃ̂��킩��Ȃ��B�ƌ����Ă�������ǁA�����Ɓu�l�v�́A�����̒��̌����̐��E�ɏ����ȉ��l��������邱�Ƃɂ���āA�炢�����ɂ䂳�Ԃ�������A��������̗��E�������o���Ă���̂��Ǝv���B
�@�u�l�v�͉��l�ɂ�������Ă���悤�Ɍ������B�܂�A�����̎q������ɁA�Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�B�����A���R�z���Ŗ������������鉤�l�������܂����v���B�ł��A���͂����v�����Ƃ��������₵�������B�Ȃ��Ȃ玩���̎q��������A���̎������悢�Ǝv���Ƃ������Ƃ́A���̎�����ے肷�邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv�������炾�B�܂����́A��l�ł͂Ȃ��B�Ȃ̂ɁA������A������ے肵�Ă��ẮA���̐�ǂ��Ȃ��Ă����Ă��܂��̂��낤�Ǝv���ċ��������B�ł��A�܂�����ł́A�u�O�����Ȑ������v��u�v���X�v�l�v�ȂǂƂ������̂́A���݂��Ȃ��悤�ɂ��v�����B
�@���ɂ́A��ʐ�������Ǝv���B���������鎖��������A�̂Ă鎖������Ɠ����ʑ�Ȏ��Ȃ̂��Ǝv���B�ǂ��炪�����̂��́A�킩��Ȃ��B�܂��A�������̐�ǂ���̓��ɐi�ނ̂����B�����A�����邱�Ƃ́A�݂�Ȃ�������ǂ������Ă��ẮA���̐��͐��藧���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ������Ƃ����Ȃ̂��Ǝv���B
�@���͉��l�̐��E���A�l�Ԃ̐��E�̕����X�o���V�C���Ƃ�����Ǝv�����B�Ȃ��Ȃ�A�l�Ԃɂ͓w�͂Őςݏd�˂Ă������̂����邩�炾�B�q���̂��납��|���Ă������̂́A�Ȃɕ��ɂ�������Y���Ǝv�����炾�B���l�̐��E�ł͐��܂ꂽ������l�����炻�ꂪ�ł��Ȃ��B
�@�G�����̉Ƃɍs���Ă�������Ă��܂������l�́A�����u�l�v�̑O�ɂ͌���Ȃ��Ǝv���B�Ȃ��Ȃ�A�����u�l�v�ɂ͉��l�̑��݂̕K�v���Ȃ��Ȃ������炾�B���Ɓu�l�v�͓������������B�u�����̂ĂĂ܂ő�l�ɂȂ�Ӗ��v�̓������B����́A�u��l�ɂȂ�ׂɁA�q������▲������v�Ƃ������Ƃ��B�Ō�̐Ԃ��O�~�x�A�[�́A���悤�Ȃ�̃��b�Z�[�W�Ȃ̂��Ǝv���B
�@���ꂩ��́u�l�v�������O�������Đ����Ă�����Ǝv���B���l�́A�܂������̌�����Ȃ��A���l�����Ȃ��ė҂������Ă���l�̏��֍s�����̂��낤�B
�@���͖{�̕\���ɖ��O���������B���l�������Ă��ꂽ�����l�ɂȂ��Ă��Y��Ȃ��悤�ɁB
�@���l�̑��݂������������͂킩��Ȃ����A���̖{��ǂޑO�̎��ɂƂ��Ă͖��ł������B�������A���Ȃ��Ƃ��A���̎��̐S�̒��Ő����Ă��鉤�l�͌������Ƃ������Ƃ͕�����Ȃ������ł���B
�@���̒��ɁA�������ȉ��l�ƗF�B�ɂȂ�l���������疾�邢����������Ă���B�����v���Ă�܂Ȃ��͎̂������ł͂Ȃ��̂ł��낤�B |
�@���̕��͂�ǂ�ŁA��͂�ޏ��͐q��̒��w�Q�N���ł͂Ȃ��A�������肵���l���ς������A�ӎu�͂̋����Ƒ�������������B�������l���Ɗ������o�����B
�F����́A�����������܂����ł��傤���H
|
2014�N1��15���i���j
���u�Б�w�̒���I
�@ �v���Ԃ�ɁA��Z�ł��铯�u�Б�w�A���o��w�ɂ�K�₵���B
�@����́A��N�A���������ǐS���̐V��������{�݂̌��w���ړI�ł����B
���܂ł̑�w�́u�w�юɁv�ł��̂ŁA��w�̌����͂��ׂĖ��@���ȋ��������сA�����͒����ƃC�X������ԂƂ����C���[�W�ł������A����A�s���Ă݂āA�V������w�̎p�A�w�ѕ������āA�w���̒��͕ς�����ȁI�x�Ƃ�����ۂ����B
�@������w���̍��A���傤�����Ĉ��ۓ����̐^���Œ��ŁA�w���ْ͋����ɕ�܂�Ă����B������A���u�Ђ��A�����ق���l�ɁA�w���͓����̏�ŁA�L�����o�X�͑傫�ȗ��ĊŔ��������сA���ꂪ��w�̎p���H�ƈٗl�Ȋ��������̂��o���Ă���B���X�A����C�X�Ō����̓�����Ƀo���P�[�h��z���A��ʂ̐^�ʖڂȁH�w���������ɓ���Ȃ��悤�ȍs�ׂ����s�����w���^�������ʂł������B
�@����A�L�����o�X������Ă݂āA�т����肵���̂͑��ƌ�45�N�ɂ��Ȃ邪�A�ԃ����K�̌����͐̂̂܂܂ɔ������������B�������N�V�����Ƃ���������S���Ȃ������B�L�����o�X������w���͂܂�ŁA�j���̓�l�g���`���z����������A�b�������Ă����̂���ۓI�������B�L�����o�X�����w���ň�ꂩ�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���ďo���������A�Ђ����肵�Ă��Ĕ��q�����������B
�C�O�̑�w�̃L�����o�X���ʐ^�Ō��Ă���悤�ȍ��o�Ɋׂ����B
�@�̂́A�L�����o�X���̃��C���ʂ�͂�������̊w���ł������Ԃ��Ă����̂����E�E�E�E�B
���u�Б�w�͍��o��L�����o�X���苷�ɂȂ����Ƃ������ƂŁA�L��ȓc�ӃL�����o�X�Ɉړ]���A�ꎞ�͍��o��L�����o�X�͊w�������������炵���B
�@���s�s���̉��h���͗����ق����J��w���A���u�Ђ��ړ]���āA�w�������Ȃ��Ȃ�ƐS�z�����Ƃ����b�����B
�@�c�ӃL�����o�X�́AJR���u�Љw���������A20���قǕ����Ȃ���ΐ���܂Œ����Ȃ��B�������AJR�w���s�s���͖{�������Ȃ��A�s�ւȓy�n�ɂ���B
�@�����L�����o�X�͔��ɍL���A�����ƌ����̊Ԋu������������Ă���̂ŁA�L�X���͏\�ɂ��邪�A�ړ�����ρB����ȍL���͗v��Ȃ��̂ł́H�Ǝv���قǍL��ȓy�n�ł���B
�@���̓c�ӃL�����o�X�͊w���ɂ��܂芽�}����Ȃ������悤�ŁA���u�Б�w�͍��o���A��}�����B�c�ӃL�����o�X�͗��H�n�𒆐S�Ƃ�������Ƃ��A���o��L�����o�X�͕��n���S�̊w�ɂɕ����t�����A�W���悤���B
�@���āA����̖ړI�͊����ɂȂ����ǐS���Ƃ�������Ȍ����̒������w���邱�ƂŁA���̐ݔ������APanasonic�̓����Ō�y�̐X�{�N���ٓ���IT�����AV�ݔ��̊Ǘ��^�c�S���҂Ƃ��ċ߂Ă���̂ŁA�ނɗ���Ŏ��Ԃ������Ă��炢�A�ٓ����ē����Ă�������B
�@�ǐS���͍��o��L�����o�X�ɂ������^����̐Ւn�Ɍ��Ă�����Ȍ����ł���B
�n���S�G�ې����o��w�̐擪�ԗ����ō~���ƁA���D���o�Ă����A���̌����ɒ��ڒʂ��Ă���B���֗��ł���B�n���P�K�ɂ͍L���H��������A�n���K�ɂ́A�T�����I�ȋ�Ԃ�����A�Q�K�ƂR�K�Ɂw���[�j���O�E�R�����Y�x�Ƃ�����ԁA�{�݂�����B
�@�����͂��ꂩ��̑�w�̐V����������A�l�����A�w�ѕ�����A���H�����Ƃ��đ���ꂽ���̂ŁA���{�ŏ��߂Ė{�i�I�ɉ^�p����Ă���炵���B���̂��߁A�S���̑�w�W�҂����w�ɗ�����Ƃ����b�ł������B
�@�p���t���b�g�ɂ��A
�ǐS�ق����[�j���O�E�R�����Y�͏���m���ɁA�m����n���ɕς��Ă䂭�w�V�����w�т̏�x�ł��B�l�X�ȃq�g�E���m�E�R�g�E���Əo��A�����𒇊ԂƂƂ��ɋc�_���W�J���Ă䂭���ƂŁA�V�����w�т̉\���ݏo���Ă䂫�܂��B
�@�A�C�f�A�����ł͐���オ���Ă����܂��B�������߂���Ƙb���܂�Ȃ��B
�@�l�̓R�~���j�P�[�V�������J��Ԃ������ɁA�A�C�f�A�͒b�����A�����������ƒʂ��Ă䂭�B�ǐS�������[�j���O�E�R�����Y�́A���悻2,550�u�i��770�j�ɁA�u�Ђ�߂��v���u�����v�ɕς��Ă䂭���܂��܂ȑ��u��z�u�������K����ł��B�����̒��ɖ����Ă��锭�z�́A�\�z�́A�����͂������Ŗڊo�߂����Ă݂܂��I�@�@ |
�ƂȂ��Ă���B
 �X�{����̘b�ł́A�J�ݓ����͊w�������̏ꏊ���ǂ��g�������̂��A�s�v�c�ȋ�ԂƑ����Ă����悤�ŁA�P�Ȃ�T������i���X�̉����̂悤�ɍl����l�����������ł����A�ŋ߁A����Ƃ��̏ꏊ�̎g�����A�R���Z�v�g����������A��������̊w�����݂��ɉ�b������A�v���[��������A�p�\�R���Ɍ������Ď�������Ȃǂ����Ă���B �X�{����̘b�ł́A�J�ݓ����͊w�������̏ꏊ���ǂ��g�������̂��A�s�v�c�ȋ�ԂƑ����Ă����悤�ŁA�P�Ȃ�T������i���X�̉����̂悤�ɍl����l�����������ł����A�ŋ߁A����Ƃ��̏ꏊ�̎g�����A�R���Z�v�g����������A��������̊w�����݂��ɉ�b������A�v���[��������A�p�\�R���Ɍ������Ď�������Ȃǂ����Ă���B
�w���̊�t�����Ă���ƁA�y�����������V��ł���Ƃ��������ł͂Ȃ��A������ڎw���Ď��g��ł���ȂƂ�����ۂ��������B
�@���ɂ͑��_���܂Ƃ߂Ă���l�A�h�������Ă���l�A�x���`���[�r�W�l�X�̊�揑�������l�A���ɂ͊O���l�w������R���āA�b������ł����B
�@
�@�����̂悤�ȍ̐l�Ԃɂ͂��̋�Ԃ͗��������Ȃ��B�Ȃ����Ƃ����ƁA���l�̘b�������������A�f�B�X�v���C�������������ł���Ƃ������A�f�B�X�v���C�Ɉ͂܂ꂽ���͋C�̒��ŁA�����ɏW�����邱�Ƃ�����B�ނ�ɂ͂��ꂪ�ł��邻�����B
�V���l�͉�X�̐l�ԂƂ͈Ⴄ�ȁI�Ƃ������o���������B
�@
�@IC�J�[�h�̊w�������A�m�[�g�p�\�R���͎��R�Ɏ���邵�A�����u���^�̃f�X�N�g�b�v�p�\�R�������\�䂩����ł��āA���R�Ɏg����B
�@�����ō���������ŁA�݂�Ȃ��W�߂ăv���W�F�N�^�[���g���v���[���e�[�V�������ł���B���̋�Ԃ͂܂��ɁA�����ȃC�x���g���̃v���[���e�[�V���������v�킹��ݔ��ƕ��͋C�������Ă���B
�@�����������ƂɊ��ꂽ�l�ނ���Ƃɓ���A�Ɩ���̃v���[���e�[�V��������������ł���Α�ό��\�Ȃ��Ƃł���B
�@�쐬�����l�̃f�[�^�͊w���̃T�[�o�ɓ���ĕۊǂ��ł���B�e�ʂ͊e�l�łPGB����^���Ă���炵���B�l��USB�������ɓ���Ď����A�邱�Ƃ��ł���B
�@�܂��A�l�̉��h��⎩��̃C���^�[�l�b�g�����w�̃T�[�o�ɃA�N�Z�X���A�����ȃf�[�^�������肷�邱�Ƃ��ł���B���ׂĂ�IC�J�[�h�̊w���AID�ƃp�X���[�h�ŊǗ�����Ă���B���̃��[�j���O�E�R�����Y�͂܂����s����̈���o�Ȃ��Ǝv���B�������A����ɉ��������݂����Ă����Ƃ����b��X�{�N����f�����B
�@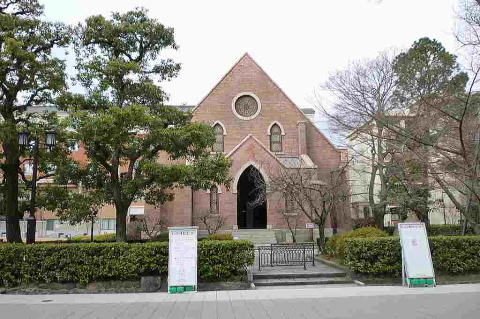 ���u�Б�w�́A��N�ANHK��̓h���}�A�w���d�̍��x�ŁA�V�����搶�ƐV�����d����̐������܂����A���ɕ`���ĕ������ꂽ�B���̗R�����錚���������������Ă���B ���u�Б�w�́A��N�ANHK��̓h���}�A�w���d�̍��x�ŁA�V�����搶�ƐV�����d����̐������܂����A���ɕ`���ĕ������ꂽ�B���̗R�����錚���������������Ă���B
�n���҂̎v�������܂ł���ɂ��A����̗���ɉ������V���������g�ݓ���Ȃ����w���W���Ăق������̂��B
�@����̌��w�ł́A���̉\����傫�����o�����悤�Ȉ�ۂ����B
 |
| �L�����o�X�̃��C���ʂ肩���N���[�N�L�O�������� |
 |
| �G�ےʂ�̔��Α��ɂł����@�ȑ�w�@ |
 |
| ���[�j���O�E�R�����Y�Q�K��������� |
 |
| ���[�j���O�E�R�����Y�̈�p |
 |
| ���[�j���O�E�R�����Y�̈�p |
 |
| �R�K�̃f�X�N�g�b�vPC�Ɍ������w�� |
|
11��13��(��)
�ϋv���Z�̓�����ɏo�Ȃ��܂���
�@�a�̎R�����ϋv���Z�𑲋Ƃ���52�N���V�O�i�Ê�j���}���A���Z�̓�����J����܂����̂ŁA�v���Ԃ��JR�V�����w�����a���Řa�̎R�w�ɍs���A�w�O�̗����ŊJ���ꂽ�T�g�A�U�g�̓�����ɏo�Ȃ��܂����B����͂Q�U�����Q�����A�j�P�R���A���q�P�R���ł����B
�@
�@���܂ʼn����������J����A���̓s�x�Q�������Ă��܂������A����͂V�O�Ƃ����ߖڂ̔N�ŁA�����̏W�܂�ƈ�����v��������܂����B
�@�l���W�O�N����Ƃ��X�O�N����Ƃ�������悤�ɂȂ�܂������A�͂��V�O�ɂȂ�ƂU�O�̎��Ɣ�ׂāA�̗͂�L���͂̒ቺ�ȂǁA����ɂ��������܂��B�܂����N�œ��X�𑗂点�Ă�����Ă��邱�ƂɊ��ӂ��ĉ߂����Ă�������ł��B
�@�@�@�@�@�@�@
�@�o�Ȏ҂̑S���ʐ^���B��A���̌㉃����n�߂܂����B�����Q�͎�X�����A�j���Q�͔�������A��������Ƃ��̔N�ɂȂ�Ɖ��ł��A���ɂȂ�܂��B
�@���������ŔM�S�ɐ��������Ă���A�����b�����Ă������X�����Ă����̂ő��ɏZ��ł��鏬���͎Q�������Ē��������B���̑S���ʐ^�������A�����œ͂����̂ŁA�p�\�R���Ɏ�荞��ŏ����摜�������Ă݂��B�w���܂肭�����茩����Ƃ܂����H�x�Ƃ�����������Ǝv���̂œK���Ȍ��������l��������ł��B�����ق��I�I
�@���������邱�Ƃł����A�X���ł����������킵�Ă��A�T�O�N�ԁA��x�������Ă��Ȃ��ƑS��������Ȃ��B�ł����X�����Ă���ƁA�ω�����C���[�W���A�����ē��Ɏc���Ă���̂ŁA�u��������������ȁH���������������ȁA���������Ȃ������ȁv�Ƃ����ω��������Ȃ���A�w����ɂ���I���v���Ԃ�x�̂������Ō݂����m�F�ł���B
�@������͏��w�A���w�A���Z�A��w�ƈ���������o�[�Ɉ����đ�ϊy�������́B�ǂ̓�������A�C���u���Ȃ����Ԃ����Ɉ�����̂ł����y�����B
�@
�@��Z�́w�ϋv���Z�x���n���P�T�O�N�ɂȂ���{�ł����w�̗��j����w�Z�ł��B
�@�n�����Éi�T�N�i�P�W�T�Q�N�j�ł�����A�����ېV�̂P�U�N�O�ɑn������܂����B
�@�ϋv���Z�̃z�[���y�[�W�͉��L�ɂ���܂��̂ŁA�ڂ����͕�Z��HP���������������B
�@�@http://www.taikyu-h.wakayama-c.ed.jp/
����ł́A�X�i�b�v�̉������̎ʐ^��Y�t���܂��B�݂�Ȍ��C���̂��̂ł��B��ό��\�ł��ˁB
������S����邱�Ƃ���ĉ��U���܂����B
|
2013�N3��16���i�y�j
���q�@�̏C�����ꌩ�w
�@3��14���A�������݂��������A���C�E�C�����s���Ă��鐳�q�@�̌��w��ɎQ������@�����܂����B
�@����̉�̏C���̖ړI�́A ����������ʼnJ�R��̐S�z���N�������ƂƁA�n�k�ɑ���ϐk�����{�����Ƃ̓�������ł��B
�@��Ƃ����S�Ɋm���ɍs����悤�����̎��͂��d�ʓS���g�݂̌������ł��A���q�@���������������Ə�ł��B
�@�S���̌������x�����b�R���N���[�g�����h�ȃ}���V���������悤�Ȋ��Ȋ�b������Ă��܂��B
�@
�@��ƌ����͂R�K���ĂŁA�R�K�ɓo��A���q�@�̉����̈�ԒႢ�ʒu�ɂȂ�悤�Ɍ����Ă��܂��B�������͑n�����̂��̂���A�P�R�O�O�N�ȏ�o���Ė����g���Ă�����̂���A���̏C���Ŏg��ꂽ�N�㕨�̊���W�����Ă��܂����B�Â����͌`���c��������A�ۂ̂悤�Ȃ��̂��\�ʂɒ����Ă�����A�Ђъ��ꂪ�������肵�Ă��܂��B
�@
�@����̌��w��͈�ʕ�W������܂������A���J�H�l�̓`��ŎQ�������Ē����܂����B���̈�A�̌��w��I������A���悢�扮�������Ɏ��|����Ƃ����b�ł����B
�H������̎ʐ^���������������B |
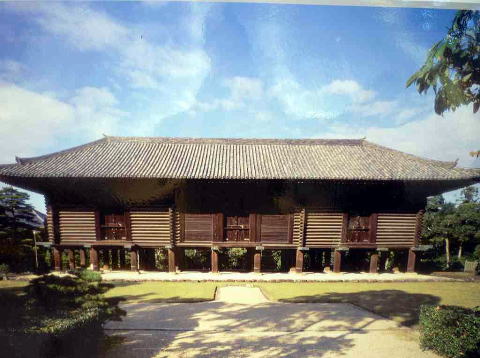 |
| ���q�@�̎p�i�ʐ^�]�ځj�A�Z�q���ŗL�� |
 |
������A�H���p�����ŕ���ꐳ�q�@���S�������Ȃ�
���̒��ɂ����ۂ�ƕ����Đ��q�@������B |
 |
| �Z�q���̌��� |
 |
| ���q�@�̓����A�V�����������Ɏg���Ă���B |
 |
| �ϐk���H���ɂ��k�x�V�܂őς���i�ʐ^�j�B |
 |
| �⋭�̂��߂̐V�����ؑg�� |
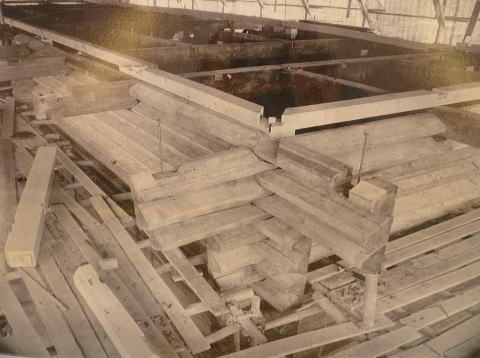 |
| �吳����̑�C���̗l�q�i�ʐ^�]�ځj |
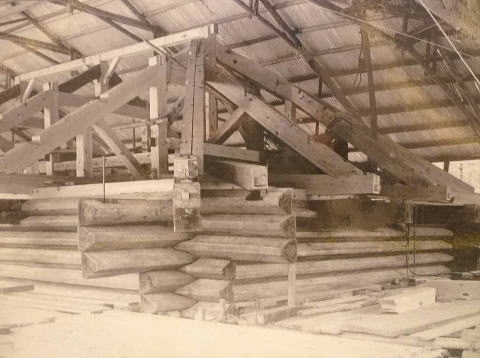 |
| �吳����̑�C���̗l�q�i�ʐ^�]�ځj |
 |
�����̕����ւ��̂��߁A�����͂����ꂽ���
�n���T�������g���Ă���B�_�ЂȂǂŁA�������ɂ��Ȃ�
�T�����ځA�����Ɏg���Ă���Ƃ��������B
�T�����͐��ɋ����؍ށB��ʂ̓��{���z�̉����̖�n�ɂ́A�����g���̂����ʁB |
 |
| ���抢�̒�A���㖈�ɖ͗l���Ⴄ |
 |
| ����g�p���銢�A���I�Ɏd�オ���Ă���B |
 |
����̊��ŕ�������Ԃ�W�����Ă���B
�V���͋��i��n�Ɗ��̊Ԃɓy��u�����B�ŗ��߂�j |
 |
�Â����͓y��u���ė��߂�B
���Ɍ����Ȃ��̂ŁA�]���H�@�̓y���߂��̗p����B |
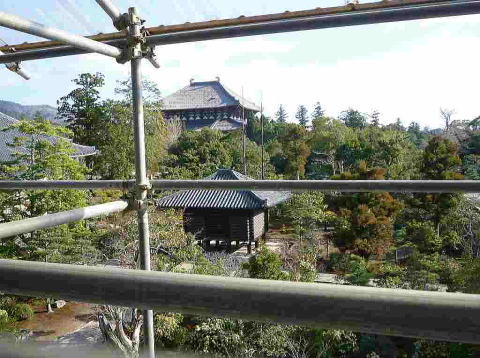 |
| �H����������啧�a������ |
 |
| �ޗnj����̎��Ƒ啧�a |
���q�@�ɂ��ď������Љ�܂��B
���e�́A�ꕔ�]�ڂ����Ē����܂����B
���q�@�̗R��
�@�ޗǁE��������̒����E�n���̊�����厛�ɂ́C�d�v���i��[�߂�q�ɂ��݂����Ă��܂����B���̑q�ɂ��������W�܂��Ă����f�����q�@�ƌĂꂽ�̂ł��B
�@�������A���������ɒu���ꂽ���q�́C�Ό��̌o�߂ƂƂ��ɂ������S��ł��܂��A�킸���ɓ��厛���q�@���̐��q������������̂܂܍����܂Ŏc�����̂ł��B
���ꂪ���Ȃ킿�A���q�@��ɂł��B
�@�W���I�̒����A�ޗǎ���̓V������(756�N)�U��21���A�����V�c�̎������̊����ɂ�����A�����c�@�͓V�c�̌䖻�����F�O���Č�∤�i�ȂǘZ�S���\�_�ƖZ�\��𓌑厛�̖{��Ḏɓߕ�(�啧)�ɕ���܂����B
�@�c�@�͑̕O��܉�ɂ���т��̕i�X�͓����̐��q(���݂̐��q�@���)�Ɏ������āA�i���ۑ�����邱�ƂƂȂ�܂����B���ꂪ���q�@�̋N��ł��B
�@�啧�J�����͂��ߓ��厛�̏d�v�Ȗ@��ɗp����ꂽ����Ȃǂ̕i�X��A�������200�N��̕������㒆���̓V��S�N(950)�ɓ��厛㮍��@�̑q�ɂ��琳�q�Ɉڂ��ꂽ�Y��ނȂǂ������A�����c�@�̕i�X�ƕ����Č��d�ɕۊǂ���邱�ƂƂȂ����̂ł��B
���q�@�͂��̂悤�ɂ������̌n����萬�藧���Ă��܂��B
�@���q�@��ɂ͐�L�]�N�̊ԁA����̊ē̉��ɓ��厛�ɂ���ĊǗ�����Ă��܂������A�����W�N(1875)�̏d�v���ɂ��ݓ����Ȃ̊NJ��ƂȂ�A�����Ŕ_�����Ȃ��o�ċ{���ȂɈڂ�A���������{�����̏��ǂ���Ƃ���ƂȂ����̂ł��B�@���݁A�×��̐��q�̂ق��ɁA����Ɂi���a37�N�v�H�j�E����Ɂi���a28�N�v�H�j������A���ܕ͂��̗���ɂɕ��[���ĕۑ�����Ă��܂��B
��ɂɂ���
�@���q�͂��Ƃ̓��厛�̐��q�ŁA�ޗǎ���ȗ����P�����Ă�����ɂł��B
�w����A�P�w�A�{�������ŁA�������ɑ����Ă��܂��B�Ԍ���33���[�g���A
���s��9.4���[�g���A������2.7���[�g���A������14���[�g���̑傫���������A�����ɂ͒��a��60�Z���`�̊ے������R�̑b�̏�ɂǂ�����Ɨ�������ŁA����Ȗ{�����x���Ă��܂��B
�@���̍��s�ȍ\���ƒ[���ȘȂ܂��͂܂��Ƃɓޗǎ�����̑厛�ł��铌�厛�̐��q�A�킯�Ă����ƓI�����u�����ɂɂӂ��킵�����̂ł��B
�@�q�͎O�q�Ɏd���A�k(���ʂɌ������ĉE)���珇�ɖk�q�A���q�A��q�ƌĂ�Ă��܂��B�k�q�Ɠ�q�́A�傫�ȎO�p��(�Z��)���䌅�ɑg�ݏグ���w�Z�q����x�ŁA���q�͖k�q�̓�ǂƓ�q�̖k�ǂ𗘗p���ē�k�̕ǂƂ��A�������ʂ͌������͂߂ĕǂƂ����w�q����x�ł��B
�܂��A�e�q�Ƃ������̒����ɓ���������A�����͓�K����ƂȂ��Ă��܂��B
���̕�ɂ͓ޗǎ���̑n���ȗ��A�����̊�@�Ɍ������Ă��܂��B
�����S�N(1180)�̕��d�t�̓ޗǏĂ�(��s�đł�)��A�i�\10�N(1567)�̎O�D�A���i����̕��ɂ��啧�a����A�����U�N(1254)�̖k�q�ւ̗����Ȃǂ����̎�Ȃ��̂ł����K�^�ɂ��厖�Ɏ��炸�A��邬�Ȃ��p�ō����ɓ`����ꂽ�̂ł��B
�������A���̊Ԃɂ͌o�N�ɂ�鋀���A�J�R��Ȃǂ����Ȃ��͂Ȃ��A�����̈ێ��̂��߁A�召�������̏C�����s���Ă��܂��B
������O�ς̂����ŁA�����̒��Ɋ������S�̑т�A�{�����x���鍪���̕@�ɂ��Ԃ������͌㐢�̏C�����ɉ�����ꂽ���̂ł��B
�@��ɂ̌��z�N���ɂ��ẮA���̂��ƂڋL�^�����������Ȃ��̂Ŗ��m�ł͂���܂��A�����Ɍ�����L������A�������Ƃ��V���R�N(759)�R���ȑO�ɏo���オ���Ă������Ƃ͊m���Ƃ���Ă��܂����B
�@�܂���ɂ��Z�q�Ɣq�Ƃ���ɂ܂Ƃ߂����قȍ\���ł��邽�߁A�͂����đn���̓������猻�݂̂悤�Ȍ`�ł������̂��A���邢�͒��q�͌�Ɍp�������ꂽ���̂ł͂Ȃ��������Ƃ������Ƃ����Ƃ̂������ŋc�_����Ă��܂������A�ߔN�ł͎g�p����Ă��錚�z�ނ̉Ȋw�I����(�N�֔N��@)�ɂ���āA���[�Ƒ��O�シ�鎞���ɁA�ŏ����猻����悤�Ȏp�Ō��z���ꂽ��
�ƌ�������L�͂ƂȂ��Ă��܂��B
�@���̐��q�́A�����X�N(1997)�ɍ���(���q���Ӓn��͎j��)�Ɏw�肳��A���N�ɂ́u�Ós�ޗǂ̕������v�̈ꕔ�Ƃ��Đ��E��Y�ɓo�^����Ă��܂��B
�@���q�@�N�\
�@http://www.kunaicho.go.jp/event/shososeibi/nenpyo.html
�@��̏C������ʐ^
�@http://www.kunaicho.go.jp/event/shososeibi/shintyoku.html |
2012�N9��2��

�@LED�d���ɂ���
�@�ŋ߁ALED�d����LED�Ɩ����̒l�i���������Ă����B
�V��̓d����u��������LED�Ɏ��ւ��āA�ȃG�l���悤�ƍl����l�������Ă���炵���B�Ɠd�ʔ̓X�A�R�[�i����r�o�Ȃǂ̃z�[���Z���^�[�ɂ͑�ʂ�LED�d����LED�Ɩ������Ԃ悤�ɂȂ����B
�@�䂪�Ƃ��A�]���̃_�E�����C�g�̓d���^�u���ǂ�A�T�[�N���C���i�u�����j�Ȃǂ���ALED�Ɩ����Ɏ�芷������B
�@�d���͐^��ɂ����Ǔ��Ƀt�B�������g�Ƃ��ă^���O�X�e�����g���A����ɓd���𗬂��ĂQ�O�O�O�x�ȏ�̍����ɂ���������̂ł���B�^���O�X�e���͂R�R�W�O�x�Ɣ��ɗZ�_�������̂ŁA�d���̃q�������g(�����́j�ɂ͂����ĕt���̍ޗ��ł���A�����Ԏg���Ă����B�d�����Z�p�J�����i�݁A�ׂ����̃^���O�X�e�����R�C����Ɋ����āA���������ɃR�C����Ɋ����������Q�d�R�C���d���Ƃ����̂����Łi�����̃}�c�_�d���j�Ƃ��Ĉꐢ�������Ƃ�����B
�d���͐^��ɂ���ƁA�^���O�X�e�����M�ŏ����āA�₹�ׂ��āA���ɒf������̂ŁA���ɕs�����K�X�̃A���S�������ď��i������Ă���B
�@�u�����͓d�����d�͏����1/3�`1/4���x�ŁA�ȃG�l���������A����ł��u���ǂ���芷����ۂɊǂɐG���ƔM���قǔM�������Ă���B���̔M���d�C�G�l���M�[���X���Y��ł���B���ɂȂ�Ȃ��ŔM�Ƃ��Ĕ��U�E�����Ă���B
�@���̓_�ALED�͖w�ǔ��M���Ȃ��̂ŁA�d�C�G�l���M�[���w�nj��ɑ���A�d�̓��X�����Ȃ��B���܂ł͓d���ɑ���قǂ̔����ʂ�LED���ł��Ȃ������̂ŁA��ɓ���Ȃ������B����Ȃ��̂͂����������ɍ����ł������B���ꂪ�ŋ߁ALED��łRW��TW(���b�g)�ʂ̂��̂������ł���悤�ɂȂ����B
�@LED�͒P�F�̔����f�q�ŁA�J�����ꂽ���ɂ�����ƁA�ԁA�I�����W�A���A�A�A�����Ĕ��F�ƂȂ��Ă���B��ʏƖ��p�͔��F�łȂ��Ǝg���Ȃ��B
�@LED���̂Ŕ����ڏo���Ă���̂ł͂Ȃ��A��ʂ̂��͉̂��F��LED�̕\�ʂɓ���Ȍu���h����h���āA���̔g����ϊ����Ĕ��F�̌��ɕς��Ă���B
���̌u���h���̎�ނ�ς��邱�ƂŁA�����F��d���F�̌����o�����Ƃ��ł���B
�@������̔��F���o�������́A������R�EG�EB�i�ԁA�A�j�̌��̂R���F��LED����ׂāA�����ɔ���������Ό����ڂɂ͔��F�Ɍ�����B
����͉t���e���r��v���Y�}�e���r�̕\�ʂɖڂ��߂Â��āA�ׂ��ȗ����������
RGB������ł���̂�������B�ǂ̐F���������ŐԂ��⍇������ĉ��F�₻�̑��̐F�����R�ɕ\�����Ă���B
�@������A���������Ȑ����~�̓V�䓔�pLED�Ɩ����i�V�[�����O���C�g�j�̓����R���Ŋ�����RGB��LED�̔����̓x������ς��邱�ƂŁA�d���F�⒋���F��A�Ԃ��ۂ��F��A���ۂ��F��ΐF�Ȃǎ��R�ɉ��o�ł�����̂�����܂��B
�@�c���ɂ͓d���F���������B�܂��A�d�����Ǐ��ɂ͒����F���K���Ă���B�d��������F�A���[�h���o���F�ȂǁA�����̃V�[���ɂ�莩�R���݂ɐF��ς��邱�Ƃ��ł���B����͂R���F��LED���ł������Ƃɂ��B
���܂ŁA�Ɩ��̖��邳�́A�d���Ȃ�U�OW(���b�g�j�Ƃ��A�P�O�OW�Ƃ����悤�Ƀ��b�g�i�d�͎g�p�ʁj�ŌĂ�ł����B�u���������ǂQ�OW�^�Ƃ��A�T�[�N���C���R�OW�ȂǂƌĂ�ł����BLED�d���ł�����d�͂SW�Ƃ��VW�Ƃ��\���͂��Ă��邪�A���܂ł̓d���ƌu�����Ƃ͏����������ς���Ă���B��ɏq�ׂ��悤�ɁALED�͏ȃG�l�̏��i�Ȃ̂ŁA�d���P�O�OW��LED�Ȃ�P�TW�O��A�d���U�OW�Ȃ�LED��9W�O��A�d���S�OW�Ȃ�LED�S�D�TW���炢�B���̊W�����̕\�Ɏ����B |
���L�̒l�͖ڈ��Ƃ��Ă��������B
| ���� |
1520��m |
910���� |
485���� |
170���� |
| ����d�� |
�d�� |
100W |
60W |
40W |
20W |
| �u���� |
27W |
13W |
|
|
| LED |
15W |
9W |
5W |
2�`3W |
�@���̖��邳�H�̕\�����A�P�ʂɂ��ďЉ�܂��B
���̗ʂ�\���P�ʂɂ́A�����A���x�A�P�x�A�Ɠx�̂S�̒P�ʂ�����܂��B
�����i�����o���Ă���Ƃ���j�́A�_�ł�������A�u�����̂悤�ɖʂł������肵�܂��B�܂��A��������o����̗ʂ�\���P�ʂ������ŁA����P�ʂ������i���[�����j�ł��B
LED�d���̔��ɉ����[�����ƕ\�����Ă��܂��ˁB
��������Ȃ�̂ł����A�������͂ދ��̂��l���āA���̋��̂̔��a�̂Q��ɓ��������̏�̖ʐς�ʉ߂�����̗ʂ����x�ƌĂт܂��B�����āA�������甼�a��2��ɓ������ʂ��Ȃ��~���`�̂Ȃ��p�x�𗧑̊p�ƌĂсA�P�ʂ͂����i�X�e���W�A���j�ƌ����܂��B�P������a/r2���@�P�ʂ͂����i�J���f���j�ƌĂт܂��B
����ɁA�����̒P�ʖʐϓ�����̌��x���P�x�i�P�ʂ͂���/�u�j�ƌ����܂��B
�@�ȏ�́A������\���P�ʂł����A��������o�������ǂ⏰�ɓ������Ėʂ��Ƃ炵�܂��B���̏Ƃ炳���ʂ̖��邳���Ɠx�i�P�ʂ̓��b�N�X�j�ł��B
1���b�N�X�͂P����/�u�ł��B1�u�ɂP�����̌������B���ďƂ炵���ꍇ�̖ʂ̖��邳�ł��B���������̌����ł��A�������L���A�����������ƏƓx���Ⴍ�Ȃ�܂��B
��Ƃ�Ǐ����������ꍇ�́A�Ɠx���ǂ̂��炢�K�v�����d�v�ŁA�����̗ʂ͒��ڊW������܂���B�����ɓǏ��̏ꍇ�͖{�̃y�[�W�����邢���ł��B
�@LED�d����LED�V��Ɩ������ꍇ�́A�����i���[�����j�Ƃ����\��������Ă��܂��B����͂���LED��������S�̂̌��̗ʂ�\���Ă��܂��B
�@�d���͋P���Ă��镔���i�t�B�������g�j�͏������̂ŁA���ڌ���܂Ԃ����ł����A�A�u�����͌��\�傫�ȊǑS�̂Ō����o���܂�����u�����͌��Ă��܂Ԃ�������܂��A���邢�̂ł��B�������������̂̓����ƁA���̗ʂ�\�����߂ɁA������P�x����x�Ȃǂ��K�肵�Ă��܂��B
�ȏ�A�]�k�ł����B |
��������Ȃ�܂����A�����������_�I�Ȑ����͉��L���N���b�N���Ă������������B
shoumeiYougo_tan-i.pdf �ւ̃����N
2012�N9��1��
���E�C�R��w�Z�̐��w�̓������Ɖ�
���w�R���R��g���āA�O�`�P�O�܂ł̐�������鐔���������Ȃ����x�ł����B
�͎��̂悤�ɂȂ�܂��B
�����ł��܂������H
| �O |
�i�R�|�R�j�~�R���O |
| �P |
�i ��R�~��R�j���R���P |
| �Q |
�i�R+�R�j���R���Q |
| �R |
�R+�R-�R���R |
| �S |
�i�R���R�j+�R���S |
| �T |
�R�I�|�i�R���R�j���T |
| �U |
�i �R�~�R�j�|�R���U |
| �V |
�R�I+�i�R���R�j���V |
| �W |
�i�R�I���R�j�R�恁�W |
| �X |
�R+�R+�R���X |
| �P�O |
�R�D�R�~�R���P�O |
�����ŁA�R�I�͂R�̊K��ŁA�R�I�Ƃ́A�R�~�Q�~�P���U�ł��B
���ꂪ�ł����l�́A�����_�炩���A���D�G�Ȑl�ł��B
�������Ȃ�A����{�鍑�C�R��w�Z�ɓ��w�ł��܂��B
�@
2012�N�W���P�O���i���j
�V�_�Ղ̃M�����_�`
�@�W���V���A���H���߂��܂����̂ŁA�w�c�����������\���グ�܂��x
�@�ҏ����������Ă��܂������A�ق�̏����H��������悤�ɂȂ�܂����B
�����A���̉āA���߂āw�c�N�c�N�{�E�V�x�����Ă��܂����B�����ł��B��������̂�����Ƃ������ԂŁA���̌�A���z���Ƃ�Ɩ��~�݁A����Ɂw�N�}�[�~�x�̑升���ɂȂ�܂����B��͂薢���A�M���Ă������Ă��܂��B
������ƁA�^�C�~���O������܂������A�V���Q�R���A���V���{�̓V�_��������A�����M�����_�`�i�݂����j���B���Ă��܂����B��������̉���҂̒�����I�����ꂽ�M�����������������āA�e�p�[��H�ŁA�����Ԃ錒�N�I�ȃM���������C�ɐ_�`��擱������A�S������A���F������グ�A��ϐ���オ���Ă��܂����B
�V���̏��X�X��k�����ɉ�����A�������z���ēV���{�܂ōs���A���̌�A�Ăіk�シ��Ƃ����R�[�X���������܂����B
���̉Ă̕����������͂����܂��B
|
 |
�А��̂����|�����Ƌ���
�_�`������Ă��܂����B |
 |
�擱���̒j�����J�𐁂�
���H���m�ۂɌ����ł��B |
 |
�Y��ȃM�����B�ł��B |
 |
�_�`�͌��\�d�����ł��B
�����ۑ���S���ł��܂��B
���������M���������I |
 |
�����̏������l��
�Ȃ��Ă��܂��B |
 |
�����Ƃ����Ԃ�
�ڂ̑O��ʉ߁B
|
 |
���X�X�͐l�����
���Ă��܂����B |
2011�N10��13��(��)
�n�E�X�H��̏Љ�
�@���쌧��c�s�̋ߍx�ɁA�����S�ؑ��Ƃ�������������B���͎͂R�Ɉ͂܂ꂽ��ϐÂ��ȓy�n�ŁA���{�ň�ԁA�N�ԓ��˗ʂ������ƌ����Ă���B
�����Ŏʐ^�̂悤�ȃr�j�[���n�E�X���ŁA�N���A�w�T���`���x�͔̍|�����Ă���B
�@�����͓~��͒g�[���A�Ă͊O�C�����C��Ŏ�����Ă��̂��ł���B�͔|�I�ɂ͗ΐF�̃T���`���̗t���ς����ꂢ�ɕ���ł���B���k�͔|�Ȃ̂ŁA�y�͎g�킸�A�n�E�X�͂قƂ�NJ��S����ԂȂ̂ŁA���_��ɋ߂��B |
 ��600�u�̌���
��600�u�̌���
 �͔|�I�ɕ��w�T���`���x
�͔|�I�ɕ��w�T���`���x
�T���`���́A���^�X�̂悤�ȗt���ςŁA��������������ē��ɂ悭�����B
�ꕔ�A�c��A���t��������̏����Ȃ��̂�����B
���̃n�E�X�̗l�q�́A�l�b�g�J�����ŏ펞�i���ԁj���j�^�[�ł��܂��B
�A�N�Z�X�͉��L��URL����͂��ĉ������B��ʂ�
�p�X���[�h��ID
�������\������܂��̂ŁA�����Ɂ@
guest�@�Ɠ��͂��ĉ������B
��ʂ̏㉺�A���E�̋����}�E�X�̃|�C���^�ŃN���b�N����ƁA�J����
�̊p�x�����R�Ɉړ����邱�Ƃ��ł��܂��B�S��ʂ��N���b�N�����
�摜���S��ʕ\���ɐ�ւ��܂����A�掿�͑e���Ȃ�܂��B
���̏���ʂɖ߂��ꍇ�́A�L�[�{�[�h�̍���ɂ���@ESC�@�L�[
�������Ό��ɖ߂�܂��B
http://fecaiyu.luna.ddns.vc/
���܂��J���Ȃ��܂��́A�uActiveX���C���X�g�[�����Ă��������v�ƌ���
�\�����o��ꍇ�̓C���X�g�[������Ό��邱�Ƃ��ł��܂��B
2011�N9��24��(�y)
����d�ԁ@���s���̃g�[�}�X�d��
����������Ɉ��������A���{����ŁA���̋C����14�x�A������Ɣ������B
���̏o�ƂƂ��ɋC���͂���オ��A�����̂ɂ͍ō��̃R���f�B�V�����B
�����8000�������Ă݂āA���̒��q�͓��ɖ�肪�Ȃ��̂ŁA������
�P�����ɒ��킵�悤�B�L���m��EOS7D�����ɂԂ牺���āB

���s�t�߂̒I�c�A�L���ȓc�̌b�݁A��䂪����Ă���B

����d�ԁA�͓��X�i���s�s���j���o���Ƃ���

�q���ɑ�l�C�̃g�[�}�X�d��

���s�̉ƕ��݂ɕ����ƌÖ��Ƃɂ���ȊŔ�����
2011�N8��16���i�j
�������B�F�u����v�̍ĊJ�͐�Δ����I
�@�����������̋C����34�x�O�゠��A����10���]��͑�ςȖҏ��������Ă���B����܂ŃN�}�[�~�̑升�����肪�������Ă������A�����[���A���߂ăc�N�c�N�{�E�V�̖��������B�������܂������̐����A�����Ɍ��C���Ȃ��B�܂��N�}�[�~�̐��̕��������傫���B�G�߂͒����ɏH�Ɍ������Ă��邱�Ƃ��������B
��N�Ȃ�A8��10���O��Ƀc�N�c�N�{�E�V�����n�߂邪�A���N�͈�T�ԗ]��G�߂��x��Ă���悤���B�V�C�\��ł͍��T���ɑO�����쉺���Ĉꎞ�A�H�̋�C�ɓ���ւ��炵���B
�@�J���~��Τ���낻��H��̎�܂��̏����ŁA���̍k���i�V�n�Ԃ��j�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��G�߂��B���̏����ł͔_��Ƃ͖��������B
���悢��A���������߂ɂȂ�悤�����A�N���Ȃ낤�ƁA�����̐��i�����͔����B��Δ����������B�F�u����v�̉^�]�ĊJ���B
����́A���q�F���̂��N����Ǝ肪�����Ȃ��B�����đ҂̂݁H�ƂȂ�B�i�g�����E�����p�ނɎg�����q�F�Ȃ�āA�������B
���L��URL�Ɂu����v��5�d�̈��S����Ƃ��Ă���̂ň��S���I�Ɛ������Ă���B�m���Ɍ��q�F���̂̎��̂ɑ��Ă͈��S�����m��Ȃ��B���q�F�̎��͂̎��R���͉����A�ǂ̒��x�̋K�͂ł��N���邩������Ȃ��B���������͂�����w�z��O�̒n�k�ƒÔg�x�ƌ����Ă��܂����Ă���B�����炲�܂�����Ă��A�������̂��N�������Ƃ͎����ł���A�������̎����̂��߂ɍ��㉽�\�N�ɂ��킽�肢�낢��ȑΉ������Ă䂩�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���R���̔j���łȂ��A�l�̂̌��N�₷�ׂĂ̐����ɕ��̈�Y�킹�邱�ƂɂȂ�B
�y���F�̌����ł���A��N����Ȃ��A�N����͂����Ȃ��ƌ����Ă������q�F�̃����g�_�E�������ɋN���Ă��܂����B
�u�����v�ł����������Ƃ��N����ƁA��₷���Ƃ���ł��Ȃ��B�c��ȕ��ː��������T���U�炳��āA�k���A���A�����n���͐l���Z�߂Ȃ��y�n�ɂȂ肩�˂Ȃ��B���̎��͂܂��ɓ��{�͒��v����B
���L��URL���������B�F�E�����ɂ��ďڂ���������Ă��܂��B
����͂����ꕔ�ł��B
����̉^�]�ĊJ�́A��Αj�~���Ȃ���Ȃ�܂���B
http://www.jaea.go.jp/04/monju/
http://www.geocities.jp/tobosaku/kouza/fbr1.html
http://www.fepc.or.jp/present/cycle/kousoku/index.html
http://www.geocities.jp/tobosaku/kouza/fbr2.html |
2011�N8��10���i���j
�Ă̓d�͕s���͏���邩�H
�����͉ғ��Ȃ��I
8���͗��H�ł����B��̏H�ɂȂ�A�{�i�I�Ȗҏ�������Ă����B
�d�͎g�p���i�g�p�d�͗�/�����d�͗ʁj�������݂X�O���O���ɂȂ�A�]�T���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�@�ł������A��ԑ����ꂽ�����d�͂ɗ]�T������A���k�d�͂ɑ��d���Ă����ƌ������Ƃł�����A���̒��s�v�c�ł��B
�@���N����A�싅�̃X�g���C�N�E�{�[���̕\�����t�ɂȂ�܂����B����͍��ە\���ɍ��킹���̂ł����A�w**�X�g���C�N�E**�{�[���x�ƌ����Ă����̂��A�w**�{�[���E**�X�g���C�N�x�ƂȂ��Ă��܂��B
�@�t�̍��Z�싅�̎������Ă��Ĉ�a���������܂����B����܂�NHK BS�e���r�̑僊�[�O���p�����Ă��āA�A�����J�ł̓{�[���A�X�g���C�N�̏����t�̂��Ƃ͒m���Ă��܂����B�X�g���C�N�ƃ{�[���̂ǂ�����Ɍ������́A�ǂ��ł��ǂ��̂ł����A�v�͕�������̖��ł��B�@
�@�������A�ĂɂȂ�v���싅�����A���܁A���C�Ƀv���C���Ă���Ă̍��Z�싅�����Ă��đS����a���������Ȃ��Ȃ�܂����B�l�Ԃƌ������̂́A�����������̂ł��B
�@�싅�̃{�[���A�X�g���C�N�͂ǂ�����Ɍ��������A�ǂ��ł��������Ƃł��B
�ł����́A���{�������X�g���C�N���Ɍ������̂��A�����A����������܂��H
�����A�o�b�^�[�����s�b�`���[�Ɍh�ӂ�\�����̂����m��܂���B
�@���̂��Ƃ́A�ǂ�����Ɍ��������A�ǂ��炩�Ɍ��߂�������Ƃł��B
���ɁA�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����m����v���͂���܂���B���܂�A����ɏ]���ςނ��Ƃł��B
�@����Ɠ����悤�Ȃ��Ƃ��A�Ԃ̉E�n���h���ƍ��n���h���ł��B
�C�M���X�Ɠ��{�ȊO�́A���E���w�Ǎ��n���h���ł��B���{�͂ǂ������o�܂��A�C�M���X�ɂȂ���ĉE�n���h���ɂȂ��Ă��܂��B
����͖싅�̂悤�ɊȒP�ɓr���Ő�ւ��邱�Ƃ͏o���܂���B�Љ�C���t���ɂ�����邱�Ƃł�����B
�@���l�ɓd�C�̎��g��������܂��B���ꂪ��ςȃl�b�N�ɂȂ��Ă��܂��B�����A�S�����U�OHZ���A�T�OHz�ɓ��ꂳ��Ă���A�ҏ��ɂ���r�I�_��ɑΉ��ł��܂��B���{���т�100���{���g��d�͑��d���H�����{���{�݂��āA����Ɋe�d�͉�Ђ̔��d���̓d�͂ڂȂ��A�K�v�ɉ����Ċe�n�ɕϓd����ݒu���ēd�����グ�A�������Ďg���B
�@�������A���g�����Ⴄ�ƁA���ɂȂ����Ƃ͏o���Ȃ��B��x���g���ϊ����A�ǂ��炩�̎��g���ɍ��킹�邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�A���̂��ߎ��g���ϊ������K�v�ɂȂ�B
�@��������d�͑��d�͌𗬂��������ōs�������������b�g������B
���������d�̓C���t�������Ȃ���A���͔��d��A���z�����d��A�n�M���d�𑝂₵�āA�E������i�߂�ׂ����I�Ə�X�v���Ă���B
�@���ɁA�������B�F����͐�Δ����I
�@���q�F�̗�p�Ƀi�g�����E�����g���B�i�g�����E���͋����ł��邪�A���ɐG���ƁA���f�����Đ��f��������B����̕��������ł����f�������N�������B
�@���������͔R���_���Q�O�O�O�x�߂������ɂȂ�A���ꂪ���ɐG��Đ��f�������������́B
�@�y���F�����́A�����p�ނƁA�����q�̌����ނƂ��Ďg���B���ŗ�₷���q�F���B���̌��q�F�ł���A��₹�Ȃ��������������ő傫�Ȏ��̂��N�����B
�@���ꂪ�A�i�g�����E�����p�ނɎg���w����x�̏ꍇ�͂܂���������Ⴄ�B
���̂��N�������ɁA�i�g�����E���ł�����p�ł��Ȃ��B���q�F�����z����t�̃i�g�����E���͑�ʂ̕��ː��������܂�ł���B�����̉t�̃i�g�����E���𐅂Œ��ڗ�₹�Ȃ��B�i�g�����E���͐���������Ɛ��f�����A�������邩��B�F�S�̔R���_����₹�Ȃ��B
�@����̂悤�Ȏ��̂��A�w����x�ŋN�����Ȃ�A�S������グ���I�@�F�S�n�Z�A�F�S�����Ƒ����A���̍ۂ̕��ː������̔�U�ʂ͕������̂̔�ނł͂Ȃ��I�@�@�ߋE�n���A���i�A���ӂ͂��ׂĔp�ЂɂȂ�̂ł͂Ȃ����H
�@�w����x�̍ċN���A����̊J���͐i�߂Ă͂Ȃ�Ȃ��B��Δ����I�I
|
2011�N7��3��
�c�a���w�Z�̂U�O�N�Ԃ�̓�����
����A���w�Z�̓��������A�v���Ԃ�ɋ��m�Ɗy����������߂������B
�a�̎R���L�c�S�c�a���A�����c�a���w�Z�A���a�R�P�N���Ɛ����Q�Q���W�܂����B
�O��͂P�S�N�O�������̂ŁA�܂��F����A�����ŖZ�������ł̓�����ł��������A
����͂U�V�A�W�ɂȂ�A�S���H���^�C�����A���Ԃ����������b������オ�����B
�����b�ɂȂ������搶����ς����C�ŏo�Ȃ���A�ꌩ���ē������ƌ��ԈႤ
�قǎ�X�����̂ɂ݂�Ȃ����܂������Ă����B�@
���̍ɂȂ�ƁA�P�P�l�����ɑ��E���Ă���B
�@�a�̎R���L�c�n���́A���a�Q�W�N�V���P�W���ɗ��j�I�ȏW�����J������A�L�c�삪
�×����A�e�n�Œ�h���������̐l��������ĖS���Ȃ�ꂽ�B
���傤�ǁA���w�Z�S�N���̎��̏o�����ł������B�㗬����Ƃ�������Ă����
�����A��������o���Ă���B���̘b��搶���炨�������A�����̑�ЊQ�̏�
�v���o���A����������l�S���Ȃ����͎̂c�O�ł������B
�@���N�R���P�P���̓����{��k�Ђ̒Ôg�̉f�����J��Ԃ����Ȃ���A�����̑吅�Q��
�v���o���Ă���B�L�c��̏㗬�ɂ́A��ӂłP�U�O�O�����̍��J���~��A�o�P�c��
�Ђ�����Ԃ��悤�ȓy���~�肾�����ƕ����Ă���B
�@�c�a�̓c��ڂ���ʁA�̂悤�ɂȂ�A�����ԁA���Z����ԂŁA�����{��k�Ђ�
�Ôg�̗L�l�ƃ_�u���Ă��܂��B���Q��Ôg�͂��ׂĂ̐ςݏグ�Ă����Ƃ₻�̑���
�Љ�C���t����j�Ă��܂��B����܂ł̓c��ڂ̓��͋����Ȃ��肭�˂����������ŁA
�Ԃ͒ʂ�Ȃ������B�吅�Q�ŁA���ʂ��������A��搮�����A�l�p�̓c��ڂɂȂ�A
�c�����i�͈�ς��A�傫���l�ς�肵���B
�݂���̒l�i���悭�Ȃ��Ă������������̂ŁA��삩��݂���ɖw�ǑS�_�Ƃ���n
�]�������B�c�a�c��ڂ́A���A���h�Ȃ݂����L�����Ă���B
�@�����{��k�Ђɑ���ꂽ�n��̕��X�́A��ςȂ���J������Ă���Ǝv���܂����A
�����̂��̒n�A���̒n�ɍ����p��K�ɕ`���āA���܂ňȏ�̓��H��A�X���݂�A
�����̏��V���������鎖�����҂��Ă���B
2011�N7��2��
���`�E�}�J�I�̃c�A�[�ɎQ��
�v���Ԃ�ɁA���`�i�z���R���j�A�S��i�}�J�I�j�̃c�A�[�ɎQ�����܂����B
�C�M���X�A�|���g�K������Ԋ҂���ĂP�S�N�ɂȂ�A�̐����ς��傫��
�ς�����ƕ����Ă��܂����̂ŁA�ԊҌ�̍��`���ǂ��ς�����̂��A
�����̖ڂŊm���߂ɍs���܂����B�@�@���`�͐��܂�ď��߂āA������
�T�Q�N�O�ɁA�i��Ђɓ����ĂQ�N�ڂ̐V���Ј�����Ƀ`�����X���j
���̊C�O���s���������ł���A�{�[�C���O�V�O�V�Ƃ������̂��ג����Q�ȁA
�Q�Ȃ̑�ϋ����W�F�b�g�@�ŁA�s���͂S���ԁA�A��͂R���Ԃ�������
���Ƃ��o���Ă��܂��B�����Ԃ̔�s�ŁA���{�Ƃ͑S���ʐ��E�̍��ŁA
�������璴���w�r�����ї����A�ŏ��̊C�O���s�͊����Ƌ����̘A����
��ψ�ې[�����̂ł����B���̌�A�d������Ő���K��܂����B
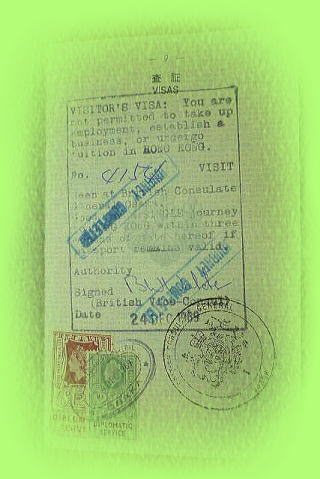
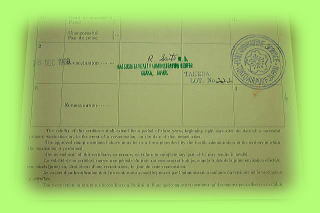
���͓�����Passport��VISA�A�@�E�͗\�h�ڎ�ؖ���
�̂͊C�O�n�q�͑�ς������B�������A�R�U�O�~/$�̎���
�p�����璆���ɕԊ҂��ꂽ���`���ǂ��Ȃ��Ă��邩�A�w���s�̃y�[�W�x��
�ڂ������܂��B��������������ł��̂ŁA���炭���҂��������B
2011�N5���P�V���k�l
�E�������R����H
����́w���́A��₵�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��x�@�ɂ��ď����Ă݂܂��B
�w�E�������R����x�ƌ����܂����A��R����v�ƌ������ۂ́A�]���̕����R����A���Ȃ킿�A�R������C���̎_�f�ƌ������ĔM�≊���o���ĔR���A���̌��ʁA�Y�_�K�X�i��_���Y�f�j�Ɛ��ƒY�i�܂��͊D�j�ɂȂ�Ƃ������ۂƂ́A�S���Ⴄ�T�O�A���ۂ������܂��B���ʂ��Ă��邱�Ƃ́A�w�M���o���x�ƌ������Ƃł��B�M���o������A�R����ƌ����\�����g���Ă��܂��B
�w�E�������R����x�ƌ������Ƃ́A�ǂ��������ۂȂ̂��ł��B�R����E�����̓E�����Q�R�T�Ƃ������̂ł��B�����ŁA���q�̍\�����ǂ��Ȃ��Ă��邩�ɂ��Đ������܂��B���Z�̕����ŏK�������Ƃ�����͂��ł����A���q�̐��E������Ɓi���ۂ́A�]��ɏ������ĖڂŌ�����傫�����ł͂���܂���j���S�Ɍ��q�j������A���̎����d�q������Ă��܂��B�����������z�Ƃ��̎�������f���i�n����ΐ���ؐ��Ȃǁj�Ɠ��l�ł��B�F���̋���ȋ�ԂƁA�ڂőS�������Ȃ����q�̐��E�������悤�ȍ\���ɂɂȂ��Ă��邱�Ƃɑ�ϑ傫�ȋ���������܂��ˁB�����Ⴄ�_�́A�d�q�͓����傫���A�����ʂ̃}�C�i�X�̓d�C�������Ă���Ƃ������Ƃł��B
���āA���q�̒��S�ɂ��錴�q�j��`���Č��܂��傤�B�@���̒��g�͓�̎�ނ̗��q������܂��B�@����z�q�ƌĂ��v���X�̓d�C�����������q�ŁA�d�C�ʂ͓d�q�Ɠ����ʂł��B
���q�j�̂�����̗��q�������q�ƌĂԗ��q�ł��B����͖��O�̂Ƃ���d�C�I�ɂ͒����œd�C��ттĂ��܂���B���q�̎�ނɂ���Ă����̐����قȂ�܂��B�E�����͓V�R�i�n����j�ɑ��݂���ł��d�������ł��B
��Ԍy�������i���q�j�͐��f�ł��B���Ɍy���̂̓w���E���ƂȂ�܂��B
���āA�E�������q�̓E�����Q�R�T�A�E�����Q�R�W�Ȃǂ�����܂��B���̐����͉����Ӗ����邩�ł��B�E�����͌��q�ԍ����X�Q�ł��B���q�ԍ��͌��q�j�̒��̗z�q�̐���\���Ă��܂��B�z�q�̐����ς��A�ʂ̕����i���q�j�ɕς��܂��B����ł͌��q�ԍ��X�Q�̃E�����ɃE�����Q�R�T�ƃE�����Q�R�W������̂́A�����Ⴄ���ł��B����͗z�q�ƒ����q�̐������v���āA�Ă�ł��鐔�������ʐ��ƌ����܂��B�������q�ԍ��ł���Ȃ���A���ʐ����Ⴄ���̂����ʌ��q�i�A�C�\�g�[�v�j�ƌ����܂��B
���q�F�R���ɗL���ȃE�����́A�E�����Q�R�T�ł��B�Ƃ��낪�E�����z������̌@�����E�����͖w�ǂ��E�����Q�R�W�ŁA�E�����Q�R�T�͂O�D�R������O�D�V�����炢�����܂܂�Ă��܂���̂ŁA����������x���R������S���ɍ��߂��Ȃ킿�Z�k���āA���q�F�R���Ƃ��܂��B
���q���e�́A���x���X�V���Ɣ��ɍ��Z�x�ɔZ�k����K�v������܂����A���q�F�ł͐�������Z�k�E�������g���܂��B
�E�����R���́A�W���R�j���E���ƌ��������ׂ̍��ǁi���a���Pcm�j�̒��ɁA���a�W�����A�����P�������炢�̗���ɏĂ��ł߂�ꂽ��ԂŁA�ǂɋl�ߍ��܂�Ă��܂��B���̊ǂ͒������Sm�قǂ����A�R���_�ƂȂ�܂��B
�R���_�𑩂ɂ��āA��������c�ɕ��ׂ���Ԃ����q�F�̒��S�ɂ���܂��B
���ꂪ�F�S�ł��B�E�����͏�ɕ��ː����o���Ă��܂��B���q�ԍ����傫�ȃE�����́A���q�j���傫���A�s����ȏ�Ԃɂ���܂��B��ɏ��������ː����o�������Ă��܂��B
�F�S�ł́A�E�������̂��o�������ː��i�A���t�@���A�x�[�^���A�K���}���A�����q���Ȃǂ�����܂��j�ŁA���ɒ����q�������̌��q�j�ɓ�����ƃE�������q�j�����āA�����ȓ�̌��q�ɕς��܂��B���̌��ʁA���E�f��Z�V�E����X�g�����`�E���Ȃǂ̕����ɕς��܂��B��������q�j�����Ɠǂ�ł��܂��B���q�j�������ʁA�d���E�������q�͖����炢�̌��q�ʂ̌��q�ɂȂ�܂����A���̍ۂɋɂ킸���Ȏ��ʂ������Ȃ�܂��B��������ʌ����ƌĂт܂����A����͑O������������q�j�G�l���M�[�ƂȂ�܂��B
���q�j����Ő��������E�f��Z�V�E����X�g�����`���E���Ȃǂ͕s����ȏ�Ԃ̌��q�ŁA���ː����o����������ȏ�ԂɂȂ낤�Ƃ��܂��B���̍ۂɂ��킸���̎��ʌ������N���āA����M�����܂��B���̔M�͌��q�F���ғ������A���������Ă����ՊE����ƌ�����ő�o�͂ɔ�����Ȓl�ŁA�ő�ł��V�����炢�ł��B���Ԃ̌o�߂Ƌ��ɔ��M�ʂ͌���܂����A���Ƃ��Ƌ���Ȕ��M�ʂ��������킯�ł�����A�������Ƃ��Ă����ɑ傫�Ȓl�ɂȂ�܂��B
�P�O�O���L�����b�g�̌��q�͔��d���ł́A�^�]���~������ł��A�V���L�����b�g���炢�̔M���o�܂��B�ꌬ�̉Ƃŏ����d�͗ʂ͕��ςR�L�����b�g�ƌ����܂�����A���q�F����~��������ŁA�Q�����ȏ�̓d�͗ʂ��܂��������Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
���̔����M�𐅂��z���āA��₳�Ȃ���A�R���_���̂��h���h�����M���č����ɂȂ�A�₪�ĂP�O�O�O�x�A�Q�O�O�O�x�Əオ��A�ō����x�͂Q�W�O�O�x�ɂ��Ȃ�A�R���_���n���ė������܂��B���̑O�ɔR�����̃W���R�j���E�����n���܂��B�W���R�j���E���͐��Ɣ�������ƁA���f�����܂��B���̐��f�Ƌ�C���̎_�f���������Đ��f��������Ƃ����o�߂����ǂ邱�Ƃ������̂ł��B
�ł�����A�R���_�͐��ŗ�₵�����邱�Ƃ�����茴���̈��S�^�]�Ɍ������Ȃ���ƂƂȂ�܂��B |
�Q�O�P�P�N�T���P�T���i��)
���q�͂̋���ȃG�l���M�[�ƕ|��
�O��Q�������o�������A�������͈ˑR�Ƃ��Ď��܂�Ȃ��B���q�̓G�l���M�[�̋��傳�ƕ|�������Â��v���m�炳��Ă���B����Ŕ픘������Ȃ���A�h�앞�𒅂āA�C���⎼�x���オ�钆�̍�Ƃ��������X�̈��S���F�����ł���B
���ɁA�P�C�Q�C�R���@�Ƃ��A�����g�_�E�����Ă���ƌ���������������O�ɂȂ��Ă����B�P���@�͔F�߂��`�ɂȂ������A�Q�C�R���@�����l�ȏ̂悤���B���B���{�l�͑��̍����Ə����ς������`�q��L���Ă���悤�ŁA�����ɔ[�����F�߂�Ƃ��낪����B�����g�_�E���͑�ςȎ��̂������͂����A���ƂȂ��Ă͓��ɉ��������Ȃ��Ȃ����B
�������A���ː������͑��ς�炸���o����Ă���̂ŁA����ɓ��A���̑̓��Ɏ�荞�܂�A�~�ς��Ă䂭�ƁA��ϊ댯�ɂȂ�B
�i�P�j���q�G�l���M�[���ǂ�قǐ������̂�
�i�Q�j�Ȃ��A��₵�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂�
�ɂ��āA�Q��ɕ����ď����Ă݂邱�Ƃɂ���B
����́A
�i�P�j���q�G�l���M�[���ǂ�قǐ������̂�
���q�͔��d���Ŕ������錴�q�G�l���M�[�Ƃ͂ǂ��������̂Ȃ̂ł��傤���B
�L���ȃA�C���V���^�C�����m�́u���ΐ����_�v�Ɋ�Â��Ă��܂��B
�ȒP�ɐ������܂��ƁA�w�����͂��̎��ʂ���������ƁA�G�l���M�[�����A�G�l���M�[�����ʂ͌����������ʁi���ʌ����Ƃ����j�~�����̂Q��ɂȂ�x�ƌ������̂ł��B��������ŕ\���ƁA
�@�@�������~�b�Q
�ƂȂ�܂��B
�@�����GC�́A�R�~�P�O�W�@���[�g��/�b�ł��̂ŁA���̂Q��ł�����A
�����G�l���M�[���i���ʌ����������̎����j�~�X�~�P�O16�@�kJ�l
�i���j�P�ʁ@�kJ�l�̓W���[���ƌĂԎd���ʂ̒P�ʂł��B�P�kJ�l�͂P�kN�l�i�j���[�g���j�̗͂����̕����ɂP���������d���ʂ������܂��B���������܂��ƂP�O�Q�O�����̂���P�������グ�鎞�̎d�����P�kJ�l�ł��B
�P�b�ԂɂP�kJ�l�̎d��������A�PW�i���b�g�j�ɂȂ�܂��B
�PJ/sec���PW
�Ƃ����C�������Ȃ�悤�ȁA�ƂĂ��Ȃ��傫���ɂȂ�܂��B
�@��������̂ŁA�\����ς��܂��ƁA�E����1�O�������j�������ɔ�������G�l���M�[�́A�Ζ��Q�O�O�O���b�^�[�i�h������10�{�j�ɑ�������G�l���M�[�ʂƂȂ�܂��B�ΒY�Ȃ��R�g���ɑ������܂��B
�@�����G�l���M�[�邽�߂̔R�����d�ʂŔ�r����ƁA�E�����͐Ζ��̖�Q�O�O�����ɂP�A�ΒY�̖�R�O�O�����̂P�ł悢���ƂɂȂ�܂��B
�@�����Ō�����Ȃ��悤�ɒ��ӂ��������Ƃ́A���̂P�O�����̃E�����R�����R���āi�j���āj�A���ׂĂ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��i0�O�����ɂȂ�j�Ƃ����Ӗ��ł͂���܂���B�@�P�O�����̃E�������q�̓��̂킸����O�D�P����i��番�̈�O�����j���E�������瑼�̕��ː����q�ɕς��A���̊j����̑O��Ŏ��ʂ��������܂��B���ʂ̌��������u���ʌ����v�ƌ������Ƃł��B
�@���q���O�D�O�O�P�O�����̎��ʌ�����������A�Ζ��h������10�{�i�Q�O�O�O���b�^�[�j�ɑ�������G�l���M�[�������Ƃ������Ƃł��B
�@���q�G�l���M�[�́A�����킸���ȗʂŋ���ȃG�l���M�[��������Ƃ����_�ŁA���݂̃G�l���M�[��ʏ����Ƀ}�b�`�����G�l���M�[�����ƌ����܂��B
�t�ɁA�ǂ�Ȓn�k��Ôg�Ȃǂ̍ЊQ���N��������A�V�X�e���ُ̈펖�̂��N�����Ă����S�����ۂ���Ȃ���Α�ςȃG�l���M�[���o�����ƂɂȂ��Q���g�債�܂��B����͐���_���}������āA�����̉^�]�͒�~����܂������A���̌�̗�p�V�X�e������d�Ȃǂ̉e���ō쓮���Ȃ��������߂����ȃg���u�������X�Ɣ������܂����B
����́A���̗�₵�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��H
���y���݂ɁI |
�@
 �@�@
�@�@
 ����͐��f��R���Ƃ���̂ŁA�����Ă��S���r�C�K�X�͏o�Ȃ��B�g���^�̓[���G�~�b�V������搂��Ă���B�R���̐��f����C���̎_�f�ƌ������Đ����ł���B���̍ۂɓd�C����������d�g�݁B�������A�u���f�K�X���ǂ����đ���̂��H�v�ł���B
����͐��f��R���Ƃ���̂ŁA�����Ă��S���r�C�K�X�͏o�Ȃ��B�g���^�̓[���G�~�b�V������搂��Ă���B�R���̐��f����C���̎_�f�ƌ������Đ����ł���B���̍ۂɓd�C����������d�g�݁B�������A�u���f�K�X���ǂ����đ���̂��H�v�ł���B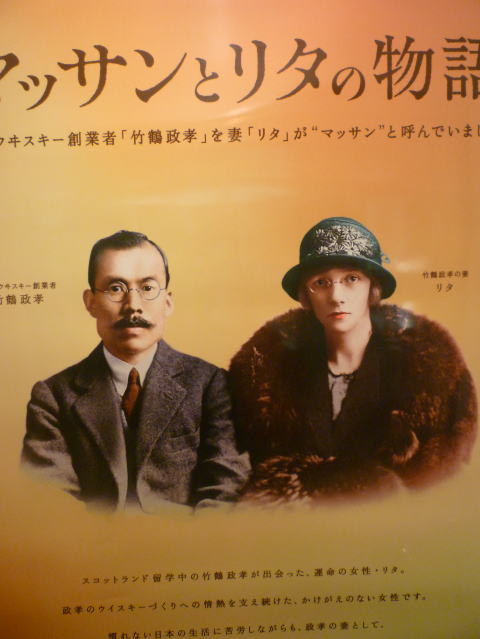 �@�@
�@�@
 ���i�́A�����Ȍv�������g���A�ŐV�̋Z�p��n�C�e�N�ޗ��荞��ŊJ�����Ă���Ǝv���B���������͑f���炵�����̂��Ǝv���B
���i�́A�����Ȍv�������g���A�ŐV�̋Z�p��n�C�e�N�ޗ��荞��ŊJ�����Ă���Ǝv���B���������͑f���炵�����̂��Ǝv���B ����̒����V��TOP�L���ŁA�g���^��FCV�i�R���d�r�ԁj�Ɋւ���֘A������S��
����̒����V��TOP�L���ŁA�g���^��FCV�i�R���d�r�ԁj�Ɋւ���֘A������S�� �@�@
�@�@
 �@�R������̒��]
�@�R������̒��]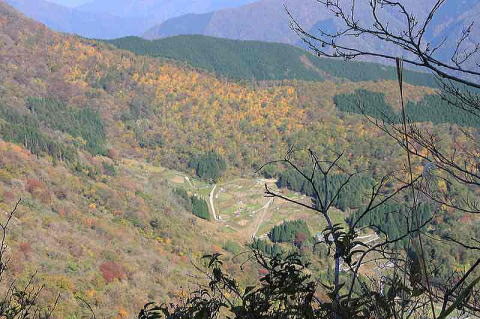 �@�r���̍g�t
�@�r���̍g�t �@�X�X�L�ƍg�t
�@�X�X�L�ƍg�t �@�r���̍L��
�@�r���̍L�� �@�ό��o�X�Ƃ��ꂿ����
�@�ό��o�X�Ƃ��ꂿ����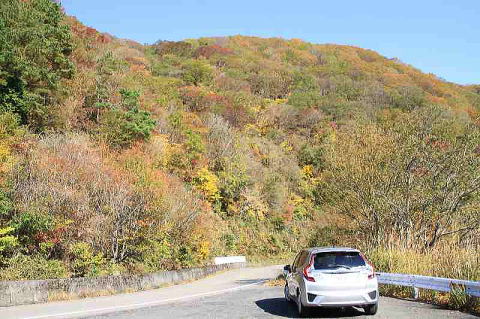 �@�}�C�J�[�ƍg�t
�@�}�C�J�[�ƍg�t �@�@
�@�@
_Aoki-11.jpg) �ŋ߁A��s�@�ɂ͊C�O���s����Ƃ��ȊO�͂قƂ�Ǐ��Ȃ��Ȃ�܂����̂ŁA�ڂ������Ƃ͕�����܂��A�v���y���@�͔�s���x���Ⴂ�̂ŁA�V��ɍ��E����āA�ӂ�ӂ�Ə㉺�ɗh��ċC���������Ȃ�悤�Ȃ��Ƃ��������̂��o���Ă��܂��B
�ŋ߁A��s�@�ɂ͊C�O���s����Ƃ��ȊO�͂قƂ�Ǐ��Ȃ��Ȃ�܂����̂ŁA�ڂ������Ƃ͕�����܂��A�v���y���@�͔�s���x���Ⴂ�̂ŁA�V��ɍ��E����āA�ӂ�ӂ�Ə㉺�ɗh��ċC���������Ȃ�悤�Ȃ��Ƃ��������̂��o���Ă��܂��B �n�u��`�ƃ��[�J����`�����ԘH���́A����ɉ���ƂȂ����������J��Ԃ��܂��̂ŁA���̓x�ɋ@�̂ɋ����Ռ��������A�\���I�ɂ��̏Ռ��ɑς��Ȃ���Ȃ�܂���B
�n�u��`�ƃ��[�J����`�����ԘH���́A����ɉ���ƂȂ����������J��Ԃ��܂��̂ŁA���̓x�ɋ@�̂ɋ����Ռ��������A�\���I�ɂ��̏Ռ��ɑς��Ȃ���Ȃ�܂���B �q��@�͎����ԂƓ��l�A�����ɋ@�̂��y�����邩����R��ɒ������܂��B����ƁA�G���W���̉��P�ł��BMRJ�͍������A�ȔR����ꂽ�v���b�g���z�C�b�g�j�[�i�J�i�_�j���̃W�F�b�g�G���W���𓋍ڂ���悤�ł��B
�q��@�͎����ԂƓ��l�A�����ɋ@�̂��y�����邩����R��ɒ������܂��B����ƁA�G���W���̉��P�ł��BMRJ�͍������A�ȔR����ꂽ�v���b�g���z�C�b�g�j�[�i�J�i�_�j���̃W�F�b�g�G���W���𓋍ڂ���悤�ł��B ���̂悤�ȃE�B���O��G���u�������A�z���_�ɂ̓o�C�N�ŁA�x�����[����h���[�����Ƃ����q�b�g���i������܂������A���̃K�\�����^���N�̗����Ɏ��t���Ă����̂��L�����Ă��܂��B���̎�������A�{�c�@��Y���͑��ɉH�������������A���̊肢�����߂Ă����̂ł��B
���̂悤�ȃE�B���O��G���u�������A�z���_�ɂ̓o�C�N�ŁA�x�����[����h���[�����Ƃ����q�b�g���i������܂������A���̃K�\�����^���N�̗����Ɏ��t���Ă����̂��L�����Ă��܂��B���̎�������A�{�c�@��Y���͑��ɉH�������������A���̊肢�����߂Ă����̂ł��B �Ȃ�ƁA���̘b��̃W�F�b�g�@�́A���̎ʐ^�̂悤�Ȍ`�ŁA���܂Ō������Ƃ��Ȃ��嗃�̏�ɃW�F�b�g�G���W�������t���Ă��܂��B
�Ȃ�ƁA���̘b��̃W�F�b�g�@�́A���̎ʐ^�̂悤�Ȍ`�ŁA���܂Ō������Ƃ��Ȃ��嗃�̏�ɃW�F�b�g�G���W�������t���Ă��܂��B
 �@�@
�@�@
 ���̃^�u�[�ƌ���ꂽ�w�W�F�b�g�G���W�����嗃�̏�Ɏ��t�����x�Ƃ������z����萋���܂����B����ɂ͓����A�q��@�̋Z�p�ɏڂ����l��������}��A���̖͂Ҕ����������悤�ł����A���쓹�i�v���W�F�N�g���[�_�͖Ȗ��Ȍv�Z�����ƂɁA���x�ƂȂ�������ςݏd�˂����ʁA�����_�ɃG���W�������t����x�X�g�|�W�V�����i������X�C�[�g�X�|�b�g�ƌĂ�ł��܂��j�����A��C��R�̒ጸ��A����ɂ��R��̌����A���x�̑����ȂǁA���܂łɂȂ����X�̐��\���オ�ł��A����ɋ��x�������嗃�ɃG���W�������t���邱�ƂŁA�]���̂悤�ɋ��x���������邽�ߋ@�̌㕔�̕⋭���ނ��s�v�ɂȂ�A�q���i�i�L���r���j���R�O�����L���Ȃ�A���Ȃ̊Ԋu�����������܂����B�܂�������U�����������A���S�n����ϗǂ��Ȃ�܂����B�@���ʂ͗ǂ����Ɛs�����ɂȂ�܂����B
���̃^�u�[�ƌ���ꂽ�w�W�F�b�g�G���W�����嗃�̏�Ɏ��t�����x�Ƃ������z����萋���܂����B����ɂ͓����A�q��@�̋Z�p�ɏڂ����l��������}��A���̖͂Ҕ����������悤�ł����A���쓹�i�v���W�F�N�g���[�_�͖Ȗ��Ȍv�Z�����ƂɁA���x�ƂȂ�������ςݏd�˂����ʁA�����_�ɃG���W�������t����x�X�g�|�W�V�����i������X�C�[�g�X�|�b�g�ƌĂ�ł��܂��j�����A��C��R�̒ጸ��A����ɂ��R��̌����A���x�̑����ȂǁA���܂łɂȂ����X�̐��\���オ�ł��A����ɋ��x�������嗃�ɃG���W�������t���邱�ƂŁA�]���̂悤�ɋ��x���������邽�ߋ@�̌㕔�̕⋭���ނ��s�v�ɂȂ�A�q���i�i�L���r���j���R�O�����L���Ȃ�A���Ȃ̊Ԋu�����������܂����B�܂�������U�����������A���S�n����ϗǂ��Ȃ�܂����B�@���ʂ͗ǂ����Ɛs�����ɂȂ�܂����B �������A�z���_�̓W�F�b�g�G���W���܂Ŏ��ЂŊJ�������А��Y���܂��B�W�F�b�g�G���W���܂Ŏ��ЂŊJ���E���Y���邱�Ƃ́A�q��@�ƊE�ł͍l�����Ȃ����Ƃ̂悤�ł����A�z���_�̓G���W���ɂ��������A���̓�s�������ɃN���A���܂����B
�������A�z���_�̓W�F�b�g�G���W���܂Ŏ��ЂŊJ�������А��Y���܂��B�W�F�b�g�G���W���܂Ŏ��ЂŊJ���E���Y���邱�Ƃ́A�q��@�ƊE�ł͍l�����Ȃ����Ƃ̂悤�ł����A�z���_�̓G���W���ɂ��������A���̓�s�������ɃN���A���܂����B ���ЊJ���̃W�F�b�g�G���W���@HF120
���ЊJ���̃W�F�b�g�G���W���@HF120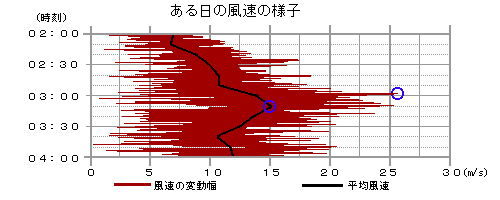


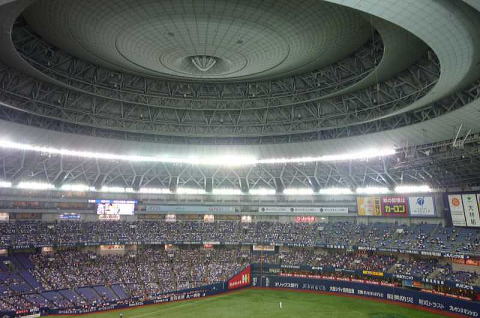


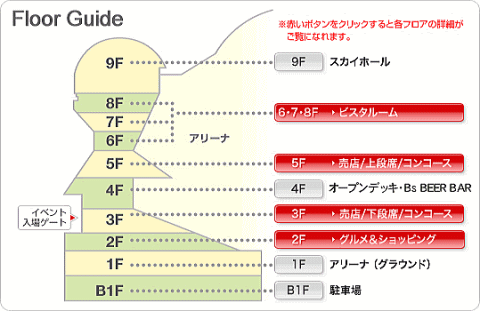
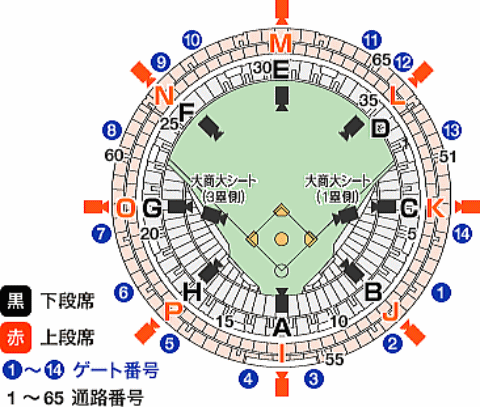
 ���ꂪ�A�ŋ߁A�@��������݃J�������J�����ꂽ�B
���ꂪ�A�ŋ߁A�@��������݃J�������J�����ꂽ�B

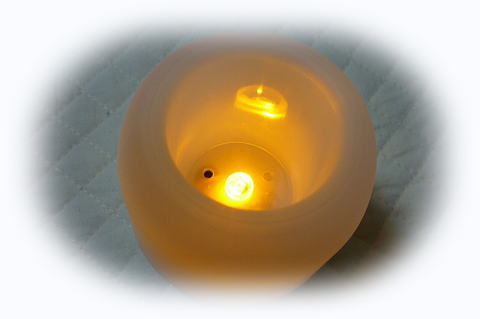








 ����́A���s���̏��w�Z�̓��w���������B
����́A���s���̏��w�Z�̓��w���������B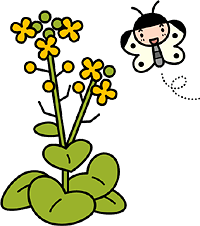
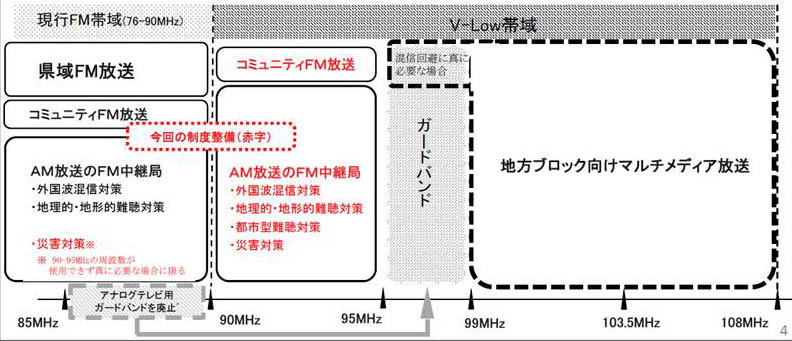
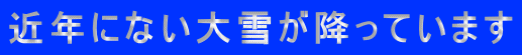





 �@�@
�@�@
 �@
�@
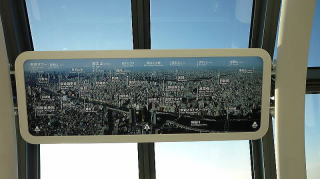 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@


 �X�{����̘b�ł́A�J�ݓ����͊w�������̏ꏊ���ǂ��g�������̂��A�s�v�c�ȋ�ԂƑ����Ă����悤�ŁA�P�Ȃ�T������i���X�̉����̂悤�ɍl����l�����������ł����A�ŋ߁A����Ƃ��̏ꏊ�̎g�����A�R���Z�v�g����������A��������̊w�����݂��ɉ�b������A�v���[��������A�p�\�R���Ɍ������Ď�������Ȃǂ����Ă���B
�X�{����̘b�ł́A�J�ݓ����͊w�������̏ꏊ���ǂ��g�������̂��A�s�v�c�ȋ�ԂƑ����Ă����悤�ŁA�P�Ȃ�T������i���X�̉����̂悤�ɍl����l�����������ł����A�ŋ߁A����Ƃ��̏ꏊ�̎g�����A�R���Z�v�g����������A��������̊w�����݂��ɉ�b������A�v���[��������A�p�\�R���Ɍ������Ď�������Ȃǂ����Ă���B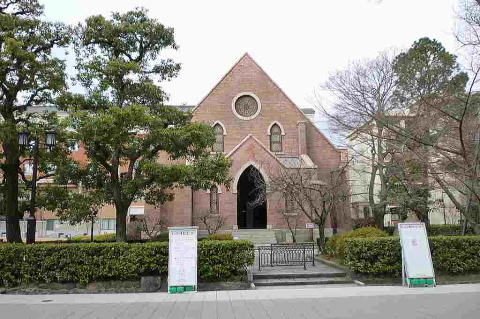 ���u�Б�w�́A��N�ANHK��̓h���}�A�w���d�̍��x�ŁA�V�����搶�ƐV�����d����̐������܂����A���ɕ`���ĕ������ꂽ�B���̗R�����錚���������������Ă���B
���u�Б�w�́A��N�ANHK��̓h���}�A�w���d�̍��x�ŁA�V�����搶�ƐV�����d����̐������܂����A���ɕ`���ĕ������ꂽ�B���̗R�����錚���������������Ă���B