2018年8月4日(土)
最近の洗濯用洗剤の力
変なタイトルになったが特別な意図はない。
今朝、暑くならない内に車を2台洗車した。家の近くの裏山で、ツクツクボウシの鳴き声が10分ほど聞こえた。家内の話では昨日も、朝6時頃にちょっとの間、鳴いていたらしい。まだ、鳴き声はひ弱で、へたくそな感じだった。
まだまだ暑い日が続いているが、例年、ツクツクボウシが鳴き出すと、今年の夏も終わりに近づいたと感じる。ところが今年は、どうやらそうもゆかないようだ。
8月7日は立秋で、この時期から湿気が少し下がり始めるが、気温はまだまだ高い。
この夏は、梅雨が6月30日に明けてから異常高温が続き、近年にない熱波が続いている。
日照りが続いているので、久しぶりに車の洗車を思い立ち、日の出前の涼しい内?に2台の掃除と洗車を行った。以前は大きな車に乗っていたので洗う面積が広く、大変だったが、今はフィットが2台になっているので、随分楽になった。
お隣さんとは、顔を合わせるとよく話をするが、「いつもきれいにされていますね」というお褒めの言葉を頂いた。
家の駐車は2台横に並べているが、洗車時は1台を近くの空き地に移して、1台ずつ洗うことになる。ところが、最近、空き地(または道路)に駐車するのは厳禁という通達が回っていて、警察が巡回して見つければ駐車違反切符を切られる。
早朝なので、まさか取締りの巡回はないと、勝手な解釈で1台ずつを持ち出す。
思い通り、2台を無事に掃除と洗車を終えた。
最後にアルミホイールを洗剤(マイペット)で洗い、拭き取るが、このタオルがどうしても油汚れする。それで、作業が終わった後、タオルの洗濯をすることになる。
家内に洗濯機用の粉洗剤を少しもらい、バケツに水を入れて手もみ洗いをする。
そこで、ふと、随分昔のことを思い出した。
小学校の低学年だった頃?、今から約70年足らず前のことになるが、「『ソープ・レス
・ソープ』という洗剤があった」ということを思い出した。
それまでの洗剤は、いわゆる石鹸(固形)だった。まだ、電気洗濯機が普及する少し前のこと。
随分大昔のことなので、記憶間違いがあるかもしれないが、『戦争未亡人会』という遺族会があった。今は、未亡人という言葉は禁句になっているそうだ。
太平洋戦争(第二次世界大戦)で、夫が戦死し、妻が家を切り盛りしている家庭が田舎にも結構たくさんあった。
当時、私は小学校の低学年か、通う直前だったと思う。
その戦争未亡人会が斡旋して売っていたのが、『ソープレスソープ』という白い粉石鹸だった。これが実によく汚れが落ちるという実演をしていた。そこへ部落のお母さんたちが集まって話を聞いていた。そのことを思い出した。
子供だったので、石鹸の落ち具合の良し悪しはよく分からないし、興味もなかったが、母親たちはその説明に耳を傾けていた。『いいものができたのね!』という感じ。
どうやら、今までの洗濯石鹸(固形)は、油脂(油)に化成ソーダ(NaOH)を混ぜて、煮詰めたものだった。それが普通に使われていた。肌の弱い人は手がかぶれたりした。
ソープレスソープは、今の化学洗剤で、化学合成で造られたもの。アメリカのデユポン社が開発したもので、アメリカの占領政策の一環として、未亡人会に販売を委託したようだ。まだ、一般には売っていなかったが、ごく少量の粉で大変良く落ちるという評判だった。
そういう約70年前の出来事を、車の洗車で汚れたタオルを手もみ洗いしながら思い出した。
今の洗剤は、洗浄力が非常に強くて、わずかな量で十分な洗浄効果が出る。しかも蛍光染料が入っているので、洗い上がりが真っ白になる。
多分、70年前のソープレスソープの何倍、いや何十倍も洗浄力が強くなっているのだろう。
そういえば最近の電気洗濯機は、ドラム式が多くなったが、洗い物はドラムの回転で上から下に堕ちることを繰り返すことで洗浄する。
昔の撹拌式や噴流式電気洗濯機はパルセーターという羽根が勢いよく回り、水をじゃぶじゃぶかき回すことで、洗浄した。
今は水の動きはゆったりで、しかも水量も少ない。
どう考えても、以前の撹拌式や噴流式の方がよく汚れが落ちると思うが、洗濯機事業部長を勤めた知り合いの先輩に聞いたところ、今は洗濯の環境が変わったという話だった。
まず、
①最近は毎日、洗濯するので、あまり汚れていないこと。
②洗剤の洗浄力が非常に強くなったので、洗剤に汚れ落としの働きを任せて、洗濯 機は、水を動かす程度でよい。
③服や下着がうす手の生地が多いので、強い水流では布を傷める
ということだった。
以前の手もみ洗いの時代には、洗い板(波のような凸凹の模様があった)の上に洗濯物を載せて、手でごしごしこすって洗った。
この70年間で、主婦の仕事が本当に楽になったと思う。主婦の家事に費やした時間が少なくなった分、家の外で働く人が増えてきた。
そう言えば、『家内』という呼び方は最近、あまりしないようだ。
『嫁』とか『妻』という方が多い。
世の中の様変わりを実感する。
朝、7時前から初めて、終わったのが8時半前だった。
朝日は昇り、暑くなったので、麦わら帽子を被って、洗車後の後片付をした。
気が付くと、セミの鳴き声は、ツクツクボウシからクマゼミの大合唱に代わっていた。
|

2018年7月29日(日)
「産業革命以前の未来へ」を読んでの感想
ビジネスモデルの大転換が始まる
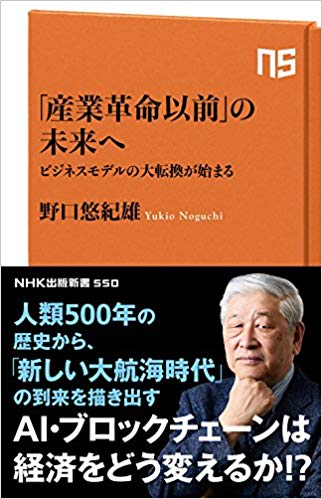
NHK出版新書550
著者 野口悠紀雄
本体820円+税
大阪の天神祭の前後、例年なら7月末の頃は、年中で一番暑い時期だが、今年は梅雨が明けたのが6月30日と半月ほど早かったので、一ヶ月間、猛暑が続いている。それも尋常な気温ではない!。
体温より気温が上がると、人体はいろんな面で不都合が生じる。以前は『日射病」と言っていたが、最近は『熱中症」と呼ぶようだ。暑さで体内の熱が発散されず、体内に籠もり、体の機能が損なわれ、場合によれば死に至る。
そんな夏の暑い日は何もする気になれないので、電車内や家で暇をしている時は文庫本を読むようにしている。手元に何冊か買って置いているが、その内の一冊をご紹介する。
『産業革命以前の未来へ』という不可解なタイトルがついた本を見つけ、書店で少し立ち読みすると、グーッと引き込まれたので買った。著者は有名な野口悠紀雄氏。
あらましを紹介すると、以下のような内容だ。
世界のビジネスは大きく様変わりしている。
これに伴い、組織の形や人々の働き方も大きく変わる。その変化を先取した国家や企業や個人は大きく伸び(儲けて)発展し、変化に対応できない国家や企業や個人は後れを取って衰退する。
よく言われる企業は「変化への対応力」だということ。ここまではごく一般的なことで、全く疑う余地もない事実だ。
この本は、歴史的な大きな潮流に着目し、論点を展開している。
まずは、中世末に大きなうねりを起こした大航海時代から、イギリスで起きた蒸気機関や鉄鋼の製造による産業革命を経て現在に至る数百年の歴史を見据えている。
いまどき、「大航海時代を振り返る」というと時代錯誤がはなはだしいと思われるが、これは500年も前の出来事だ。
大航海時代は、スペイン、ポルトガルに始まり、イギリス、オランダへ受け継がれた。
今、世界はその時と同じような大変化を迎えようとしている。一言で言えば、産業革命以前の独立自営業の世界への「先祖がえり」だという。
産業革命以降、現在まで続いてきた流れが、今、「先祖がえり」し、大きく転換しようとしている。 この見方がすこぶる新鮮で、面白い。
もう少し、分かり易く書くと、
産業革命以降、ビジネスモデル(経済の姿)の基本は、さまざまな工程を一つの企業の中に統合し、組織を大規模化することにより、効率化を図ってきた。
しかし、1990年代以降、新興国(開発途上国)の工業化や、情報・通信技術の進歩によって、この基本が変わりつつある。
新しい経済において重要なのは、大組織の中で決まりきったことを効率的に実行することではなく、まったく新しいビジネスのフロンティアを見出すことだ。それに成功するかどうかが、これからの企業や個人のあり方に大きな影響を与える。
本書のタイトルは一見して奇妙な表現だ。しかし、「未来を開く鍵は、産業革命よりも前の時代に見出すことができる」というのが本書の考えの基本の立場である。
本書の基本的なメッセージを要約すれば、「産業革命によって、以降のビジネスモデルは垂直統合され、集権化され、組織化され進展してきたが、これからの新しい経済の最先端は、それ以前の時代の分権的なビジネスモデルへと先祖帰りしつつある」ということになる。
しかし、現代の社会において大組織がいまだに支配的であることは否定できない。
だが、経済活動の中心が産業革命前のような小組織や、個人に移る萌芽は既に見られる。人々の働き方もフリーランサーが増えつつある。
昨夜(7/28)サンテレビで、大企業に勤める若い4人のサラリーマンが、自分たちの小さな会社をつくり、今勤めている大企業の休みの日に自分たちの事務所に集まり、アイデアを話し合い、新しいアイデア商品作りを模索している光景が放送されていた。
4人は、それぞれ役割分担していて、ソフト開発、ハード開発、機構設計、電子回路設計と、各人の得意分野(専門分野)で構成された集まりで、大企業や従来の製造業では商品企画に上がらないような、とんでもないアイデアを出し合ってそれを試作して、改良を重ね検討している。
まだ商品化されたものはないが、今までのメーカが取り組んだきた商品開発の姿とは全く違うアプローチで取り組んでいる。4人は結婚していて、家族の生活の中から、不便さを解消するモノや、便利なグッズのアイデアを出しあっている。
そういう小集団の会社や、個人が起業して仲間を増やしてゆく会社も沢山見受けられるようになってきた。そういう事例は、『ガイアの夜明け』などテレビで紹介されている。何か、共感するところがあるのか、そういう番組は最近、注目されている。
また、異業種から成熟しきった家電分野に乗り込んで成功しつつある企業もある。
アイリスオーヤマという会社は元は樹脂成型品(プラスチック加工業)を生業にしていた。その会社が家電分野にじわじわと参入している。
日本の家電メーカは韓国や中国の安い家電商品に苦戦して、国内は何とか販売をキープしているが、海外市場を見ると全く以前の勢いがない。サムスンやLG電子に席巻されてしまっている。
この現象は20年ほど前から顕著になり、海外旅行をしていると肌で感じるが、“Japan is No.1”と言われた頃は、アメリカやヨーロッパ各国(先進国)に行くと、国際空港ロビーや都市の繁華街の看板やネオンサインは、Panasonicや、Sonyや、Toshibaや、Hitachiや、Sharpなどの日本の家電メーカ、CanonやNikon等のカメラメーカ、その他、電子部品のTDK、など特に電機関係の会社の広告塔が目立った。
それが最近は、SamsungやLGなどの韓国メーカが目抜き通りの看板を占め、日本メーカの看板は目につかなくなった。それくらい衰えている。
そういう産業競争の勝敗を見ると、産業革命後に大成功したイギリス、続いてアメリカ(合衆国)、そして日本という時代の流れ、そして今、韓国、中国のメーカに時代が移ったことを感じる。
これは、今までの流れ(著者の言う産業革命以降のビジネスモデルの盛衰)の出来事である。本書が主張する点は、その産業革命後のビジネスモデルが、現在、次第に変わりつつあることを鋭く指摘している。
その事例が上記の4人で起こした小さな会社のビジネスの模索のような流れである。
もう少し事例を追加して考える。
コンピュータはアメリカのIBMが大型コンピュータで世界を席巻した時代があった。IBM360シリーズというベストセラーのモデルを発売し、日本でも大手企業は競って導入した。コンピュータ室や電子計算機室という完全空調した部屋で動作させ、当時の情報処理の先端を競った。特殊な知識や技能を持った人しか使えなかった機械だった。
それが、ムーアの法則による半導体の進歩で、電子回路の集積度が天文学的に進化し続け、それまでの大型コンピュータの性能を凌駕するパーソナルコンピュータ(パソコン)の時代が来る。そこで生まれたのがAppleであり、マイクロソフトである。
その経緯は、下記のとおり
マイクロソフトの由来は、1975年4月設立と言われるが、正式登録は1977年2月になっている。
ビルゲイツと、アレンの二人で立ち上げたコンピュータOSソフトMS-DOSからだった。
一方、Appleは、
1975年にインテルが8080をリリースすると、Altair(アルテア)8080というコンピュータ・キットが早速発売されるようになり人気を博した。ウォズは8080より6800の流れを汲むモステクノロジーの6502の方が安く、しかも簡易な回路のコンピュータができると確信し、1975年10月から半年間かけて設計、1976年3月に最初のプロト機を完成させた。
ホームブリュー・コンピュータ・クラブでデモを行った。ジョブズは自分達で売る事を考えていたが、ウォズはヒューレット・パッカードの社員であるが故に「開発した製品を見せなければならない」と上司にこの機械を見せるが製造販売を断られ、自分達で売り出すこととなった。
ジョブズは、マウンテンビューにあったコンピュータショップのバイトショップのオーナーであったポール・テレルに電子基板(メインロジックボード)を見せた。テレルは非常に強い興味を持ち、30日以内に50台を納品できたら現金で代金を支払うと提案する。
ジョブズは愛車のワーゲンバスを1500ドルで売り、ウォズはヒューレット・パッカードのプログラム電卓を250ドルで売り払い100台分の部品を集めた。さらにアタリで製図工をしていたロン・ウェインも株式10%分の権利を持つことを条件として参加した。彼はApple
Iのマニュアルなどを作成する仕事に従事した。彼らは本格的に基板、マニュアルの製作にあたった。また、彼らの会社の名前は『Apple』となった
1976年6月に、バイトショップに『Apple I』を50台納品。666.66ドルの価格がついたが、あまり売れ行きが良くなかった。失望したロンは10%の配当権を放棄する代わり、800ドルを受け取って会社を去る。しかし8月を過ぎると売上は好転し、ジョブズとウォズは昼夜時間を惜しんでApple
Iを製造した。ロンはその後別な会社に勤めるなどし、2010年現在はネバダ州で年金生活を送っている。放棄した10%の権利を2010年まで保有していれば、200億ドル以上の資産を得ていたはずだが、辞めたことに関しては後悔していないという。
『Apple I』の最初の取引で約8,000ドルの利益を手にした。Apple Iを大量に作って売ろうと考えたジョブズは、アタリ時代のボスであったノーラン・ブッシュネルに融資を頼んだ。ブッシュネルは投資を断るが、代わりにベンチャーキャピタル会社セコイアのドン・バレンタインを紹介した。バレンタインもジョブズの話に興味を持てず、話を断るが、代わりに同じく個人投資家のマイク・マークラを紹介した。マークラは、フェアチャイルドセミコンダクターとインテルのストックオプションで財を成し、若くして隠遁生活を送っていたが、ジョブズの話に興味を持ち、1976年11月にAppleに加わった。マークラは個人資産の92,000ドルを投資し、さらにバンク・オブ・アメリカから信用貸付枠を勝ち取った。
25万ドルの融資はマークラが個人で保証をしたが、代わりの条件として、ウォズニアックがヒューレット・パッカードを退社してApple専業になることを求めた。ウォズニアックは2、3日考えた末に「自分は経営者には向いていない」と断ったが、ジョブズがウォズニアックの家族にも働きかけるなど猛烈な説得を行い、最後にはウォズニアックが折れた。1977年1月3日、3人はApple
Computerを法人化した。
1977年5月、マークラはナショナル セミコンダクターから、友人であったマイケル・スコットを引き抜き、彼を社長の座につける。スコットはAppleをより組織的にするため、社員番号を入れた社員証を発行した。社員番号1は、ウォズニアックに与えられたが、ジョブズはこれをスコットに抗議する。しかし、社員番号1を与えればジョブズの放漫が増すと考えたスコットはこれを拒んだ。ジョブズは結局、社員番号0(振込先の銀行が0番に対応していなかったので実務上は2)を手に入れることで妥協した。ちなみにマークラが3番、スコットが7番の社員番号であった(スコットは5番目の社員であったが、社員の増加を見込んで好きな数字を選んだ)。
ヒューレット・パッカードを退社したウォズニアックは、Apple Iの再設計を開始した。処理能力の向上と外部ディスプレイへのカラー表示、内部拡張スロット、内蔵キーボード、データ記録用カセットレコーダをもつ『Apple II』をほとんど独力で開発し、1977年4月に発表する。価格は1,298ドル。Apple IIは爆発的に売れ、1980年には設置台数で10万台、1984年には設置ベースで200万台を超え、莫大な利益をAppleにもたらした。Apple II発売に際してApple Iを回収、無償交換キャンペーンでバージョンアップ対応したため現存するものは少ない。
1980年にAppleは株式公開を果たし、750万株を持っていたジョブズは2億ドルを超える資産を手に入れることになった。また、フォーチュン誌で長者番付に名を連ねた唯一の20代(当時25歳)となり、コンピュータ業界の天才児としてもてはやされる事となる。
このように、現在世界の長者番付のトップに君臨する会社や経営者ですら、起業当時はガレージで組み立てや製作をしていた。
この様子は、産業革命後の製鉄所や、蒸気機関車や、蒸気機関を製造した大規模な大規模な工場と全く発祥時の姿が違う。
このマイクロソフトも、アップルも従来の大企業だったIBMやヒューレット・パッカード等の超一流の会社ではないところが、新しい時代の始まりだ。
そして今、GAFAと呼ばれる『Google、Apple、FaceBook、Amazon』
おもしろいデータがある。
上段は、2017年のフォーチュン・グローバルが発表した世界トップ10社の売上高
下段は、2017年のフォーチュンが発表したアメリカの時価総額トップ6社
| 2017年「フォーチュン・グローバル500」 |
| 順位 |
企業名 |
売上高
(10億ドル) |
| 1位 |
ウォルマート |
485.9 |
| 2位 |
国家電網 |
315.2 |
| 3位 |
中国石油天然気集団 |
267.5 |
| 4位 |
中国石油化工業団 |
262.6 |
| 5位 |
トヨタ自動車 |
254.7 |
| 6位 |
フォルクスワーゲン |
240.3 |
| 7位 |
ロイヤル・ダッチ・シェル |
240 |
| 8位 |
バークシャ―・ハサウェイ |
223.6 |
| 9位 |
アップル |
215.6 |
| 10位 |
エクソンモービル |
205 |
GAFAと呼ばれるIT企業が時価総額で他の大企業を上回っているかが分かる。
企業の時価総額は、将来の成長性を考慮して決まる要素が大きい。
そういう意味で、GAFAがアメリカ、世界経済のけん引役に立っていることが分かる。
| 2017年 アメリカの時価総額トップ企業 |
| 順位 |
企業名 |
時価総額
(10億ドル) |
| 1位 |
アップル |
886.9 |
| 2位 |
グーグル |
719.2 |
| 3位 |
マイクロソフト |
681 |
| 4位 |
アマゾン |
600.8 |
| 5位 |
アリババ・グループ |
488.4 |
| 6位 |
フェイスブック |
449 |
昨日のニュースで、FaceBookやLineが時価総額で20%ダウンしたということが話題になっている。これは FAGAがだめになったという意味ではなく、一時のショックだと思われる。
時代は刻々と移り変わるが、ある時、手のひらを変えたような変化ではなく、じわじわと新しい事業の芽が生えて、ある時に大きく成長し、既存勢力を追い越し、変化が起きる。
本書に戻ると、章建は下記のとおり。
第1章;ビジネスモデルの「先祖がえり」が始まった
第2章;産業革命は何を変えたのか
第3章;IT(情報・通信技術)革命がフロンティアを生み出した
第4章;IT革命の勝者『GAFA』について
第5章;ユニコーン企業は次の勝者になれるか
第6章;新しい情報技術『AI』と『ブラックチェーン』が未来に向かい新しい可能性を
切り開きつつある。
第7章;現在の中国出はすべての変化が起きている
第8章;日本はどうすべきかについて
この本はじっくり読むと、最近なかなか出会わなかった示唆に富んだ本だと思う。
ぜひ、ご一読を!!
|

2018年6月26日(火)
GEの苦悩は象徴的だ!
現役の頃、枚方公園の丘陵地にある松下電器の社員研修所(通称; 社研、現在は人材開発カンパニー)で、『技術研修所』に8年間勤めた。約20年ほど前のこと。
当時、日本の有名企業の経営者、社長職や、副社長職、取締役の方々にお願いし、『技術マネージメント塾』と称して、松下電器の将来の経営幹部候補研修を行った。
そこで、盛んに取り上げられたのが、GEのジャック・ウェルチCEOだった。彼は当時のGEを見事に立て直し、再び世界のGEとして甦らせた人物だった。
その考え方や手法を分析し、経営幹部の資質を高めようと研修に取り込んだ。
ジャック・ウェルチは事業の『選択と集中』を掲げて、何でもありの巨大なGEという会社の事業を絞り込んだ。
 GEは、当時アメリカはもとより、世界最大の電気会社で、そのルーツはエジソンに辿り着く。エジソンは傑出した発明家として知られ、生涯におよそ1,300もの発明と技術革新を行った人物である。例えば蓄音器、白熱電球、活動写真である。 GEは、当時アメリカはもとより、世界最大の電気会社で、そのルーツはエジソンに辿り着く。エジソンは傑出した発明家として知られ、生涯におよそ1,300もの発明と技術革新を行った人物である。例えば蓄音器、白熱電球、活動写真である。
エジソンはJ・Pモルガンから巨額の出資・援助をしてもらい、エジソン・ゼネラル・エレクトリック会社(現ゼネラル・エレクトリック社 )を設立した。GEは電球などの家電だけでなく、発電から送電までを含む電力系統の事業化に成功した。
その後、更なる事業の拡大と共に、事業領域をドンドン広げ、何でもありの巨大な企業になった。規模が大きい会社は、血の巡りが悪くなり、気が着けば経営危機に陥っていた。ジャック・ウェルチは、それを立て直しGEの中興の祖になった。
同様に、IBMも大型コンピュータの世界最大の会社に成長後、半導体の急激な進化で、ダウンサイジングが起き、パソコンの台頭で急激に衰退し、経営危機に陥った。
それを救ったのは、ルイス・ガースナー会長である。
彼は、1993年、コンピュータ事業とは全く縁のないナビスコ社から引き抜かれCEOに就任し、柵(しがらみ)がなく思い切った不採算部門の売却、世界規模の事業統合、官僚主義の一掃、顧客指向の事業経営を行い、独自システムと独自OSによる顧客の囲い込みをやめ、オープンシステムを採用したシステムインテグレーター事業へ戦略を大きく転換した。
また顧客の要望を聞き、顧客はトータルなサービスを望んでいると考え、IBM分社化の動きを停止した。これによりIBMはLinuxを推進する大手コンピュータ企業の筆頭となった。1995年にネットワーク・コンピューティング、1997年にはe-ビジネスを提唱した。
この二人は、アメリカの先端企業の経営の見本として、社内研修の格好の教材になったのを覚えている。
さて、今日の日経新聞を見て驚いた。
米ゼネラル・エレクトリック(GE)は25日、企業の自家発電設備などに使われる産業用ガスエンジン事業を投資会社に売却する。同社は業績立て直しに向け非中核事業の売却を進め、製造業の巨人による事業リストラが、関連業界の再編の呼び水となる動きが見える。米投資会社のアドベント・インターナショナルに32億5000万ドル(約3500億円)で売却するらしい。
GEの産業用エンジンは電力や航空、オイル・ガスなどを含む7つの主要事業含にまれていない。2017年12月期の売上高は13億ドル(約1400億円)と、主力の航空機エンジンなどに比べて規模が小さく、フラナリー最高経営責任者(CEO)の事業構想から外れた。
GEはジェットエンジンでは、プラット&ホイットニーやロールス・ロイスと並ぶ世界の航空機のジェットエンジンをこの3社で独占的に供給している。
その名門企業のGEは、ジャックウェルチ(1981年から約20年にわたってGEを率いた)が過去に手掛けて大きく成長する柱となった金融事業が金融危機で経営環境が悪化し、損失が膨らみ、2017年10~12月期に約1兆円の最終赤字に転落した。2018年1~3月期も住宅ローン事業での追加損失により赤字決算となった。
昨年8月に就任したフラナリーCEOは業績立て直しに向け、18年度に200億ドル規模の事業売却に取り組むと表明していた。
電力、航空機エンジン、医療機器の3事業を中核と位置づけ、その他の事業は大幅に整理・縮小する方針を打ち出した。
これまでに、ヘルスケア事業の一部売却や、鉄道車両エンジンなどの輸送事業の外部専業メーカーとの経営統合を決めた。屋台骨を支えてきた電力事業も再生可能エネルギーの台頭により低迷している。
GEは25日を最後に100年以上続けたダウ工業株30種平均の銘柄から外れた。
(注釈)ダウ工業株30種平均
最も有名な株式市場の指標で、日本では「ダウ工業株30種平均(ダウ平均)」、「ニューヨーク・ダウ」、「ニューヨーク平均株価」などと呼ばれる。
ダウ・ジョーンズ社による株価指数は、すでに1884年以降Dow Jones Average(ダウ平均)の名称で公表されていたが、当時のアメリカの産業構造を反映し、鉄道事業者が中心の構成であった(鉄道株9種、工業株2種)。
19世紀末の経済発展を受け、従来のダウ平均(現在の輸送株20種平均)と分離する形で、1896年に農業、鉱工業などの12銘柄により、Dow Jones Industrial Average(ダウ工業株平均)の算出が新たにスタート。
1928年に、30銘柄となった。
その後、情報通信業や医療などのサービス業を取り込みながら、現在に至る。
銘柄構成企業は、以前はすべてニューヨーク証券取引所(NYSE)上場企業であったが、1999年11月に初めてNASDAQ上場企業から選択され(インテルとマイクロソフト)、2018年6月現在、5社がNASDAQ上場企業となっている。
GEは業績悪化により株価は1年前の半分以下に下落。
時価総額では約1130億ドルと競合する独シーメンス(約970億ドル)に迫られている。
フラナリーCEOは2018年度をリストラの年と割り切り、事業売却とコスト削減に集中する方針。肥大化した組織をスリム化し、負の遺産を一掃して反転をめざす。
このGEの歩みを見ると、社会の変化に、自社の強み事業を対応させることの経営の難しさがよく分かる。20年ほど前に、ジャックウェルチがその変化に対応して一時期は復活したGEですら、更なる社会の変化に対応できなくなり苦悩している。
企業の強みは規模の大・小ではない。社会のニーズの変化に対応できなければ成り立たないということを如実に物語っている。
Panasonicも、松下幸之助という卓越した創業者のもとに一致団結し、社員が頑張った結果、世界的な大メーカになった。当時は、需要が供給を上回る状態が続いていたから良い商品を出せば売れた。要は、人々が欲しいモノが沢山あり、3種の神器(冷蔵庫、テレビ、洗濯機)、3C(カー、クーラー、カラーテレビ)と言われたように、次々と人々の欲望を満たす商品を開発し販売してきたから会社はドンドン大きくなった。
現在は、モノが身の回りに溢れていて、お腹が一杯、満腹状態になっている。
これ以上、『ご馳走も食べられない!』、『もう結構』というような状態になっている。
しかし、満腹でも『別腹』という言葉があるように、これなら欲しいというモノはある。
そういう商品を開発しなければ、なかなか売れない時代になっている。
民生分野の商品ではなく、ジェットエンジンや、医療機器のMRIや、CTスキャンなど超高度な技術力を生かし、自社のモノがダントツに優れているという商品を造れれば勝機はある。普通の商品をちょっと改良した位では、人々は見向きもしてくれない。
それくらい深く考えて取り組まなければ成功できない。
少し、論点がずれたが、GEは電球から原子力発電や、ジェットエンジンや、高度な医療機器へドンドン事業構造を変えながら成長してきたが、そのGEですら、アメリカのダウ工業株30種平均の銘柄から姿を消すという時代の流れを実感した。
企業が生き物であるのなら、『生まれることは、いずれ寿命を全うする時が来る』という経過を辿るのだろうか。
下のダウ30銘柄の会社も、GEと同じくリストから外れる時期が訪れるかも?
(参考資料)ダウ30銘柄
| No |
シンボル |
企業名 |
業種 |
採用日 |
上場市場 |
| 1 |
AAPL |
Apple Inc. |
コンピュータ |
2015年3月19日 |
NASDAQ |
| アップル |
| 2 |
AXP |
American Express Co. |
金融 |
1982年8月30日 |
NYSE |
| アメリカン・エキスプレス |
| 3 |
BA |
Boeing Co. |
航空機 |
1987年3月12日 |
NYSE |
| ボーイング |
| 4 |
CAT |
Caterpillar Inc. |
重機 |
1991年5月6日 |
NYSE |
| キャタピラー |
| 5 |
CSCO |
Cisco Systems, Inc. |
情報・通信業 |
2009年6月8日 |
NASDAQ |
| シスコシステムズ |
| 6 |
CVX |
Chevron Corp. |
石油 |
2008年2月19日 |
NYSE |
| シェブロン |
| 7 |
DIS |
The Walt Disney Co. |
娯楽・メディア |
1991年5月6日 |
NYSE |
| ウォルト・ディズニー・カンパニー |
| 8 |
DWDP |
DowDuPont, Inc. |
化学 |
2017年9月1日 |
NYSE |
| ダウ・デュポン |
| 9 |
GS |
Goldman Sachs |
金融 |
2013年9月20日 |
NYSE |
| ゴールドマン・サックス |
| 10 |
HD |
The Home Depot Inc. |
小売業 |
1999年11月1日 |
NYSE |
| ホームデポ |
| 11 |
IBM |
International Business Machines Corp. |
コンピューター |
1979年6月29日 |
NYSE |
| アイ・ビー・エム |
| 12 |
INTC |
Intel Corp. |
半導体 |
1999年11月1日 |
NASDAQ |
| インテル |
| 13 |
JNJ |
Johnson & Johnson Inc. |
医薬品 |
1997年3月17日 |
NYSE |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン |
| 14 |
JPM |
JPMorgan Chase and Co. |
金融 |
1991年5月6日 |
NYSE |
| JPモルガン・チェース |
| 15 |
KO |
The Coca-Cola Co. |
飲料 |
1987年3月12日 |
NYSE |
| ザ コカ・コーラ カンパニー |
| 16 |
MCD |
McDonald's Corp. |
外食 |
1985年10月30日 |
NYSE |
| マクドナルド |
| 17 |
MMM |
3M Company |
化学 |
1976年8月9日 |
NYSE |
| スリーエム |
| 18 |
MRK |
Merck & Co. |
医薬品 |
1979年6月29日 |
NYSE |
| メルク |
| 19 |
MSFT |
Microsoft Corp. |
ソフトウェア |
1999年11月1日 |
NASDAQ |
| マイクロソフト |
| 20 |
NKE |
Nike, Inc. |
その他製品 |
2013年9月20日 |
NYSE |
| ナイキ |
| 21 |
PFE |
Pfizer Inc. |
医薬品 |
2004年4月8日 |
NYSE |
| ファイザー |
| 22 |
PG |
Procter & Gamble Co. |
日用品 |
1932年5月26日 |
NYSE |
| プロクター・アンド・ギャンブル (P&G) |
| 23 |
TRV |
The Travelers Companies,Inc. |
保険 |
2009年6月8日 |
NYSE |
| トラベラーズ |
| 24 |
UNH |
UnitedHealth Group Inc. |
保険 |
2012年9月21日 |
NYSE |
| ユナイテッド・ヘルス |
| 25 |
UTX |
United Technologies Corp. |
航空宇宙・防衛 |
1939年3月14日 |
NYSE |
| ユナイテッド・テクノロジーズ |
| 26 |
V |
Visa |
その他金融 |
2013年9月20日 |
NYSE |
| ビザ |
| 27 |
VZ |
Verizon Communications Inc. |
通信 |
2004年4月8日 |
NYSE |
| ベライゾン・コミュニケーションズ |
| 28 |
WBA |
Walgreens Boots Alliance, Inc. |
小売業 |
2018年6月26日 |
NASDAQ |
| ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス |
| 29 |
WMT |
Wal-Mart Stores Inc. |
小売業 |
1997年3月17日 |
NYSE |
| ウォルマート・ストアーズ |
| 30 |
XOM |
Exxon Mobil Corp. |
石油 |
1928年10月1日 |
NYSE |
| エクソンモービル |
|

2018年6月14日(木)
『アーキテクチャー』とは何か、ご存知ですか?
最近、新聞や雑誌を読むと、『アーキテクチャ』という単語が眼につく。
元々は、『建築学、または建築様式のこと』
辞書によると、『コンピュータの特性を決定するデータの形式や、ハードウェアの機能分担などを含めたコンピュータシステムの基本構造』となっている。
何のことかよく分からないので、もう少し表現を変えてみる。
コンピュータの用語としてよく用いられてきたが、近年はもっと広い意味を持たせて言われることが多い。
分かり易く言うと、例えば、自動車にはエンジン車と、ハイブリッド車と、電気自動車の3種類がある。これは自動車を走らせる方式のアーキテクチャで分類した表現。
エンジン車には、ガソリンエンジンとジーゼルエンジンがある。これは燃料で見たアーキテクチャとして2種類があると言える。
物事の基本になる構造や、構成のことと思えばいい。
ハイブリッド自動車の例を挙げるなら、1モータ方式と、2モータ方式と、3モータ方式が商品化されている。自動車は4輪車だから、各車輪に一つずつモータを取付ける方法もあってもよい。
商品を企画・開発する際に、いろんなアーキテクチャーの中から何を選ぶか?
これがモノづくりをする場合に一番肝心で重要なことになる。
何故かと言えば、アーキテクチャはその商品の特性や性能を決定づけるからである。
アーキテクチャの選択を間違うと、いくら頑張っても他の優れたアーキテクチャを採用した商品に勝てない。
実例を挙げると、ハイブリッド車は『プリウス』が代名詞になるほど浸透した。
どの駐車場に行っても、必ずプリウスが並んでいる。最近は『アクア』が多くなった。
トヨタは他社に先駆けて、ハイブリッド車を開発し販売した。先行者利得という言葉があるとおり、他を圧倒してプリウスやアクアが良く売れた。
しかし、初代のプリウスは自動車としての魅力に欠けた、全く面白くない車だった。
それはアクセルを踏んでも、ちょろちょろとしか加速しない、かったるい車だった。しかし、当時の車としては、ダントツの低燃費車として注目された。
値段は少し割高だったが、排ガス規制が厳しくなる中、プリウスだけが世間の注目を浴びた。 トヨタの宣伝文句は「21世紀に間に合いました」だった。
その後、プリウスは2世代、3世代、4世代とモデルチェンジを繰り返し、初代の欠点を次第に改良してきた。そして、『ハイブリッドはプリウス』というリードを保ってきた。
これは、トヨタのハイブリッド(HV)方式が大変優れたアーキテクチャを採用していたから実現できたこと。
一方、ホンダはトヨタに対抗して、フィットにハイブリッドを搭載したが、(運転の面白さではホンダが優れていたが)、燃費競争では今まで一度もプリウスに勝てなかった。
ホンダの初代のハイブリッドは1モータ方式で、エンジンのクランクシャフトにモータを直結した簡単な方式を採用した。この方式は現在も各社で採用されているが、簡易型ハイブリッド方式のようなもので、この方式はいくら頑張ってもプリウスには勝てない。
プリウスが初代から採用したハイブリッド方式は、発電用モータ(発電機)と、駆動用モータを別個に搭載した2モータ方式だった。これはコスト的に高くなるが、NO.1メーカの強みで、部品メーカの協力を得て作り上げた理想的なアーキテクチャを採用した。
だから、未だに他社のハイブリッド車に敗けないで頑張っている。
ホンダは次のハイブリッド車のアーキテクチャとして、1モータでありながらエンジンとモータを切り離す構造を採用した。これでモータだけで走行ができるようになったが、リチュウム電池の充電をしっかり確保することが難しく、結果としては燃費競争でプリウスを上回ることができなかった。しかし、初代のハイブリッドより大幅に燃費を改善し、走りの良さの点ではプリウスを上回り、もう少しのところでプリウスをキャッチアップするところまできた。1モータの限界まで来たと言える。
トヨタハイブリッド方式は2モータ方式、1種類で高級車からアクアまで統一している。
ホンダは、高級車向けには3モータ方式を採用し、アコードなどには2モータ方式を採用し、フィットクラスの価格の車には1モータ方式を採用するという3種類のアーキテクチャを開発し商品化してきた。
ホンダの看板車で、最量販ゾーンのフィットでアクアに勝てないのでは、いつまでもアクアを追い越すことができない。
そこでホンダは1モータ方式のアーキテクチャを放棄して、次の2019年のフルモデルチェンジで2モータ方式のアーキテクチャを採用することを決定した。(日経Tech)
トヨタのハイブリッド方式はモータとエンジンのいい所取りをするようになっているが、これが最善かと言えば、いくつかの弱点もある。
そこを突いたのが、ニッサン ノートe-Powerである。これもハイブリッド車であるが、ニッサンはハイブリッドと言わないで、意識的に呼び方をe-Powerと表現している。
このe-Power方式は2モータ方式のアーキテクチャを採用しているところは同じだが、
エンジンは発電機(発電用モータ)に直結している。発電機はリチュウムイオンバッテリーを充電し、バッテリーから駆動用モータを回して車輪を駆動するようなっている。
この方式(アーキテクチャ)は、基本的にニッサンが有しているEV車のリーフにエンジンと発電機を加えて取り付けたようなもの。
このノートe-Powerが爆発的な売れ行きになり、登録車中、NO.1となっている。
何故、人気があるのかと言えば、プリウスの弱点とされた出足の鈍さを、ガソリン車以上に走りが良いモータの特性を生かし切った点にある。
プリウスのモータより大馬力のモータを搭載しているからだ。
このニッサン、ノートe-Powerに弱点は高速道路を走行中は、ガソリン車と変わらない燃費に下がることだ。
その理由は、高速で走るためには、常にエンジンを高回転して発電機を回し、発電量を高めないと駆動モータを十分駆動できないためである。
燃費を最大化するためには、ガソリンのエネルギーを如何に有効に走りに生かすかにかかっている。ノートe-Powerは街中を走るには素晴らしいアーキテクチャなのだが、高速道路走行では、エンジン⇒発電機⇒バッテリー⇒モータという一連のつながりで、各部分の効率の掛け算で燃費が決まるからだ。
今、仮に各部の効率を考えてみると、エンジン効率は40%、発電機効率は90%、バッテリ効率は90%、モータ効率は90%と置いてみると、
総合効率は、0.4×0.9×0.9×0.9=0.2916 となる。
エンジンで直接、車輪を駆動すると、エンジン効率だけになるから、0.4 となり、この方が高効率になる。
単にハイブリッドにすれば、効率が改善できるというわけではない。
そこで、ホンダの起死回生策は、次のフィットでは、良いとこどりをしようということで、街中ではノートe-Powerと同じ方式で走るが、高速道路ではエンジンと車軸を直結するクラッチを組み込む。
そうすれば、一定の高速走行中は最大燃費を実現できる。
街中の走行はノートe-Powerと同じで、強烈な出足も実現できる。
2019年には各社のハイブリッドの新型車が発売されると言われているので、今後の各社のアーキテクチャの違いや改良点を見るのが面白い。
加えて、安全運転支援機能もいろんなアーキテクチャがある。
(レーダー方式)、(レーダー+カメラ方式)、(2カメラ方式)など、いろんなアーキテクチャが採用されているが、それぞれ一長一短があり、今後どの方式がアーキテクチャとして生き残るか、市場の評価を得るか、興味深々と言える。
モノづくり、商品企画は商品のコンセプトを明確にし、どういうアーキテクチャでそのコンセプトを実現するか非常に重要なことが分かる。
回り道をせずに、商品コンセプトを実現するためのアーキテクチャの選び方が成否を握る。
|

2018年5月18日(金)
日本3大随筆集って、ご存知ですか?
最近、ローカルの本屋さんが閉店するところが多い。寂しく残念な気がする。
しかし、大阪市内には大型の本屋が沢山あり、そういうBig Book Storeは健在だ。
老舗の店は、旭屋、ジュンク堂などビルごと本屋になっている。毛色の変わったところでは、CCC(カルチャ・コンビニエンス・クラブ)のTUTAYAも相変わらずやっている。
こういう大型店舗は、独自の経営方針を貫いていて、今までにないやり方で営業している。
ジュンク堂に行けば、自由に本を閲覧できるし、おまけに店の本をじっくり読めるよう椅子まで用意している。立ち読みではなく、座って読んで下さい!という感じだ!
CCCのTUTAYAは、入店するとコーヒーの香りが漂う。本屋のインクの臭いと違った雰囲気だ!
さて、会社の近くの天満の商店街に、(株)西日本書店という本屋がある。ここで時々、立読みをさせてもらうので、気にいった本は買うようにしている。
最近は文庫本を中心に、沢山並んでいるものから眼についたものを買う。文庫本は電車の中で、ちょい読みするにはとてもいい。かさばらず、軽くて、カバンに収まる。
しかも、値ごろな価格なので、財布を気にすることもない。
特にどういうジャンルの本ということもない。経済、政治、社会問題、人生訓、健康、科学・技術といろんなことに興味を持っている。
店の本棚を見ると、最近は文庫本が増えた。一方で、しっかり装丁した単行本が少なくなってきた。単行本は文庫本の倍くらいの値段で、しかもちょい読みして捨てるにはもったいないので、これは!という本以外は買わなくなった。
以前、よく眼についた『ハウツーもの』が少なくなった感じもする。
変わらないのはPC関連の本、カメラなどの趣味の本、旅行の本などで、車関係の本は半分くらいに減った。クルマ離れが影響しているのだろう。そういえば、どのジャンルの本棚の前で立ち読みしている人が多いかを見れば、その流れがすぐ分かる。
週刊誌や雑誌は店で読むものという感じで、皆さん堂々と立ち読みしている。
週刊誌はコンビニでも立ち読みが多い。店も仕方なく大目に見ている感じがする。
ちょっとした単行本や、技術関連の本など手に入りにくい本はアマゾンで買う。
在庫があれば即日配達をしてくれるので非常に便利だ。本屋にない本でも、アマゾンを調べると、まずないことはない。
そういう流れの中で、一風変わった本が注目されている。
いわゆる歴史もので、応仁の乱や、徒然草や方丈記や歎異抄などである。
日本3大随筆集と呼ばれるものは、古い順に、「枕草子」「方丈記」「徒然草」となる。
・枕草子は、平安中期に、清少納言が書いたもの
・方丈記は、平安末期から鎌倉時代に、鴨長明が書いたもの、
・徒然草は、鎌倉末期から南北朝時代に、吉田兼好(兼好法師)が書いた
これらの随筆集は超有名なモノばかりなので、いろんな本が出版されている。
その中で、最近、読んだ本で、現代語訳で分かりやすく、肩の凝らない本を紹介する。
枕草子の代わりに、親鸞聖人の歎異抄を選んだ。
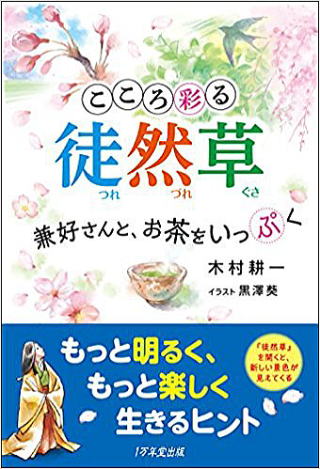 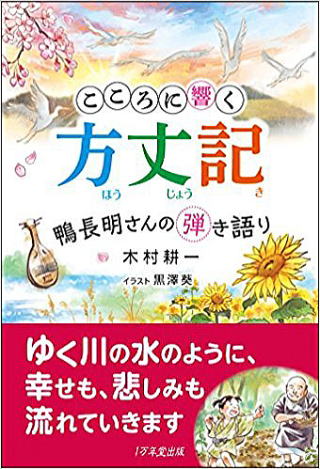 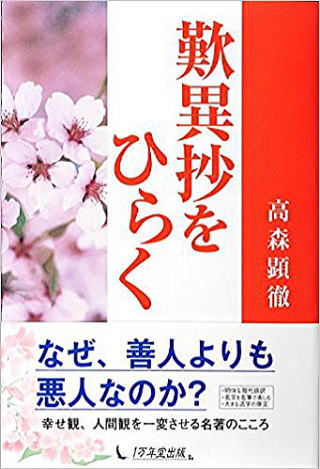
一万年堂出版から発売されている本で、誰にも分かるよう平易に解説し、本文中にカラーのイラストや挿絵が入り、現代感覚でまとめられている。
本文中の文字は大きめで、しかも漢字には、ひらがなの送り仮名を振っているので、この本の読者は老人から小学生まで、非常に広い年齢層をターゲットにしているように思う。
この3冊をアマゾンで買い、まず、『方丈記」を読んだが、約2時間で読み終えた。
それも、全然、苦にならずに、スーッと頭に入ってくる。
中学や高校の歴史に出てくる有名な本なので、一応曲りなりにも記憶に残っている。
だが、有名な書き出しや、くだりや、一節は覚えていても、その意味するところまで覚えていなかったり、誤解していることも知った。
一万年堂出版は、「いつまでも読み継がれる本を提供する」という理念で、H12年に設立された出版社で、歴史は若い。
それぞれ仏教的無情感のような雰囲気が漂っている感じを受ける。
無常感は悲壮感と受け取られやすいが、そうではなく、『全ての生き物は生まれては、必ず死ぬ。」この道理は普遍なもの。だから、あたふたすることなく、生きている間は存分に生を楽しもうという考え。これがお釈迦様の到達した考え方、仏教だ。
しかし、それが次第に無常観という空しさのように受け継がれてきた。
ぜひ、一冊を手にして読んで下さい。
『方丈記』の紹介文
ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず
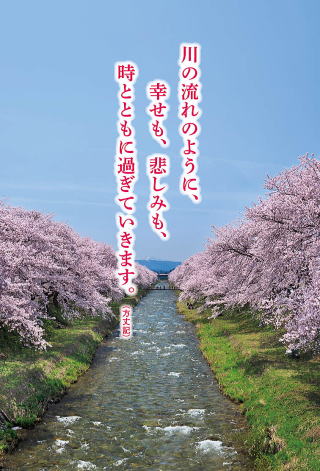 誰もが知っている有名な『方丈記』を大きな文字で、分かりやすく意訳しました。 誰もが知っている有名な『方丈記』を大きな文字で、分かりやすく意訳しました。
鴨長明といえば「世捨て人」というのが一般的なイメージですが、実は、琵琶と琴を愛する一流のミュージシャンであり、和歌の名人でもありました。
不幸や災難に遭い、失敗と挫折を繰り返しながらも前向きに強く生きた長明の名文には、生きるヒントが満載です。
時代背景もよく分かる解説付き。京の都を描いた美しいイラスト、心が洗われる写真と共に、800年もの間、読み継がれてきた名作古典を、存分に堪能できる1冊です。
|

2018年5月17日(木)
朝日新聞夕刊のコラム『素粒子』を読んで
朝日新聞夕刊の一面に小さなコラム『素粒子』が連載されている。この小さな枠の中で、時事問題を見事に風刺しているな!と感心して、楽しく拝読してきた。
ひと月ほど前だったか、正確な日にちは忘れたが、この記述者(ライター)が交代した。新人のライターの表現は、何かぎごちなく、もう一つピンとこなかった。
それが、ここ数日、筆がさえてきたというか、以前の辛辣な風刺のタッチが戻ってきた。引き続いて、楽しく読ませてもらっている。
5月17日(木曜日)、朝日新聞・夕刊 『素粒子』記事を紹介する。
まやかし、ばっかりだわ。
× ×
原発重視を続けるのに、必要な新増設を明記しない第5次エネルギー基本計画素案
× ×
加計学園の車なのに、出張記録に「官用車利用」と書いた特区担当の内閣府次長
× ×
愛媛県知事の参考人招致を「当事者じゃない」と拒む与党。
特区選定と無関係だった前知事は何度も呼んだのに。
一党多弱の国会では、正義も通らなくなるのかな?
不吉な予感がする。
「やったことはやった」と正直に、ありのまま認める素直さがほしい!
その上で、詫びるか、やったことを堂々と正当化するのは別問題だ!
自分に都合の悪いことは、避けて、都合のいいところを強調するのは、聞いていて非常に違和感と不信感が募る。
そうしないと、『まやかしが通る世の中』になる怖さが広がる!
|

2018年5月15日(火)
モータとEV(電気自動車)の話
今日は30度を越える真夏日になった。未だ、5月も半ばだというのに・・・。
それはさておき、五木寛之氏の著書『まさかの時代』を紹介したが、このところ、いろんな出来事は『まさか』ということが多い。
本では述べれれていなかったが、その『まさか』が起きる要因は、『不連続の時代』に入ったからだと思う。
不連続とは、以前(過去)とのつながりがないということで、思考や、技術や、行動など、ありとあらゆる動き(変化)が連続性を持たない時代と言える。
これは、小生が初めて言い出した考え方で、もし取れれば特許でも申請したい!
これは、冗談。
さて、この不連続の結果、我々が『まさか』と思う事が増えてきた。
政治の世界でも、総理という国の最高位の人が自分のお友達との関係で、国政を停滞させている。そんなたわいないことで、国の政治や行政を曲げることがあってはならないし、そういう次元の低いことを国会で審議すること自体が『まさか』である。
しかし、一方で、政治は『信なくば立たず』の世界だから、野党が追及することもまた理解ができる。
分からないのは、与党の自民党と公明党がなぜ、もっと政治のあるべき姿に照らして、不信を払しょくするような行動に出ないのかである。
安倍さん一人に、自民党全員が引きずられてしまっているように感じる。それほど、自民党議員のレベルや良識が低下し、正義がなくなってしまっているのか?
大所帯を良きことにして、長いものにまかれる気持ち良さみたいな気分に浸っているのか? よく分からないが、いい加減にしてもらいたい。自民党はそんな体たらくな人材の集合だったのか? まさに烏合の衆と言える。
さて、話を本来のテーマに戻す。
トヨタ自動車は世界に先駆けて「プリウス」を発売し、ハイブリッド自動車の代名詞になり、既に第4世代のモデルチェンジを行っている。ハイブリッド車(HV)では完全に先行したトヨタ(日本)だったが、HVはモータ技術、バッテリー技術、ソフトとハードの制御技術、加えて、従来のエンジンメカニズム技術と大変複雑な要素が絡み合う難解な技術開発が必要になる。
トヨタ自動車はその資金力にモノを言わせ、HVでは完全に世界を制覇した。
HVは、トヨタがダントツトップを走ってしまったため、世界の自動車メーカは、いまさらHVをやっても追いつかないという状況を察したので、違う取り組みを始めた。
それが電気自動車(EV)ということになる。
EVは、HVに比べて、構成要素がぐんと少なくなり、部品点数は普通のガソリン車が4万点以上の部品が必要だが、EVなら1万5千点ぐらいで作ることができる。
しかも、ノウハウの塊だったガソリンやジーゼルエンジンを造るむずかしさがない。
要は手を出しやすい領域なのだ。
特に、自動車大国になった中国は、自国の自動車産業を早く立ち上げて国内需要を満たすと同時に、安い価格で世界に輸出しようと企んでいる。
アメリカは、3大自動車メーカだったGM、フォード、クライスラーが今はあまりその存在の大きさを感じなくなった。むしろ、EV専業のテスラが注目されている。
このように産業構造が変わる不連続な時代は、ビックスリーと言われた世界トップのアメリカの自動車会社ですら、落ちぶれてゆく。 『まさか』の時代だ!
さて前置きはこのくらいにして、EVはモータと、バッテリーと、制御技術の3つの要素が必要になる。車体の構造設計は飛行機と違い車の場合はそう難しいものではない。
そこで、まずEVは電気で走るから、バッテリーの電気をできるだけ有効に、効率よく使わなければ、走行距離が得られない。
いかに少ない電気で走れるかだ。
ガソリン1Lで何キロ走るかというのと同じことで、1KWhの電力量で何km走れるか、または逆に1kmを走るのに何KWh必要かということになる。
ガソリン車の場合は『燃費』と呼んだが、EVでは『電費(でんぴ)』ということになる。
この電費を良くするには、モータの効率化と制御回路の最適化が必要になる。
モータの効率を上げる策は、いろいろ考えられている。しかし、試作車を1台作って、電費競争する場合はコストを度外視しても良いが、量産車(市販車)の場合は材料調達、材料コストなど大量生産ができることが大切な条件になる。
そこで、コストと性能のバランスが設計に求められる。このことは、商品を設計する際に設計者に常に求められる要件であり、そのバランスがユーザが求めるニーズとうまく合致すれば、ヒット商品となる。
話は少し逸れるが、イギリスに小さな電機メーカに『ダイソン』がある。
この会社は世界の家電メーカとは一味違った商品を出して有名になった。
商品の目的は同じであるが、その目的を果たす手段が従来の家電商品と違った。
その代表例が、羽根のない扇風機だ。
丸い輪っかから、優しい風が吹いて出る。不思議な風、扇風機だ。
そのミラクル性で、ダイソンは大きく成長した。
原理は、羽根で直接、空気に圧力を加えて送風するという発想ではなく、筒状のタービンで空気を輪っかの周囲から噴き出すことで、輪っかの中心付近から風を起こすという奇想天外な発想だ。もちろん、扇風機のスタンドの部分にはタービンとモータが仕込まれている。そのモータは普通のモータではない。
さて、EV用モータは、HV用モータと同様に、交流同期モータという種類のモータを使っている。モータにはたくさんの種類があり、直流用と交流用に大別できる。
直流用モータは以前は電車にたくさん使われてきたが、一般的にモータの回転部分(回転子)のコイルに電流を送るために、整流子とブラシという部品が必要になる。
この2つの部品は常に接触しているので、回ると火花が出て、カーボン(炭素)で出来たブラシが消耗する。整流子も長く使うと、すり減ってくる。
この種のモータは交流でも使用できる。家電商品では、掃除機、ミキサー、ドライヤー等に使用されている。大きな回転音が出るモータである。回転数が大きく、毎分約4万回転もする。
さて、交流モータとして、一番たくさん使われているのが、誘導モータ(インダクションモータ)という形式の物で、構造が簡単で長持ちするのが特徴だ。
だから産業用として、工場には大量に使用されている。(写真の左図)
 インダクションモータの特徴は、 インダクションモータの特徴は、
①回転し初めに大きな電流が流れる
②回転数(理論上)は、極数と、交流の周波数で決まる
③構造が簡単で、長寿命、
④価格は安い
(注)理論上の回転数を同期回転数(同期速度)という。
実際の実用回転数は、同期速度より少しおそい。
このことが、インダクションモータが回転するためのトルク(力)となる。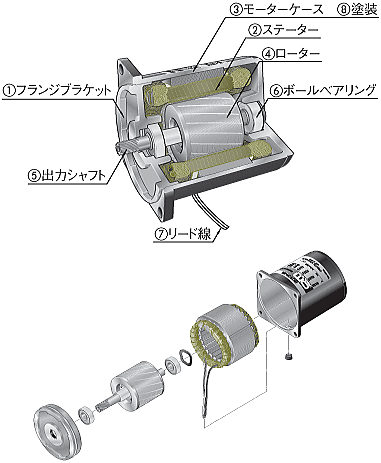
このモータの構造は、右図のとおり。
回転子(ロータ)と固定子(ステータ)があり、固定子にはコイルを巻いている。
このコイルは極数があり、2極や4極等がある。
同期回転数=120×周波数÷極数
で計算できる。
たとえば、60ヘルツの交流を4極のモータにつなぐと、
120×60÷4=1800回転/分
で、同期速度は毎分1800回転となる。
実際の回転数は、数%遅くなる。
同じような構造のモータとして、同期モータ(シンクロナスモータ)がある。
これは、固定子はインダクションモータと同じであるが、回転子の構造が少し変わる。
簡単に言えば、回転子に永久磁石を埋め込んだ構造になっている。
誘導モータは、固定子のコイルに発生する磁界が回転磁界になっている。その磁石に引っ張られて、回転子が回転する。引っ張られるためには回転子に磁石を埋め込めばいいので、そういう構造にしたのが同期モータであり、このモータは同期速度で回転する。効率は誘導モータよりも高い。
誘導モータがなぜ回転するのかは、固定子の回転磁界内に、回転子が置かれると、回転子に、「フレミングの右手の法則」で電流が流れる。この電流により生じる回転子の磁界が固定子の回転磁界と作用して、引っ張られて回転する事になる。
さて、同期モータは誘導モータより効率が高いことが分かった。
今までのHVやEVは全部、この高効率の同期モータを採用してきた。
しかし、同期モータの回転子に使う磁石の材料が、特殊なレアメタルという希少金属材料が必要で、非常に高価であり、しかも中国で産出される金属なので、中国が「自国の車にしか使わせない」と言えば、他の国のEVやHVは造れない。
今は、曲がりなりにも中国からの輸入に頼っているので、何とか製造はできている。
その材料はネオジュウム、ホウ素、サマリュウム、コバルトなどと言われる材料である。これらの材料を主原料の鉄にわずかに混ぜることで、強烈な磁石ができる。
また、磁石は温度が高くなると磁力が弱くなる性質があり、そうならないように使われるのが、ジスプロシュウムという金属である。これもレアーメタルだ。
強い磁石を使えば、同期モータの効率は非常に上がる。
そこで、日本の自動車メーカは、できるだけレアメタルを使わないで、高効率モータを製造する技術開発を進めてきた。一定のめどをつけつつある。
一方で、ドイツのアウディは、従来の誘導モータで効率化を図り、大きなトルク(力)を発生させるモータの開発を行ったという発表があった。
これは特別な発明ではなく、従来の誘導モータの効率を高めるため、モータの損失を出来るだけ減らすという発想で取り組んだもの。
モータや変圧器などの電気器具の損失には、「鉄損」と「銅損」と呼ぶ二つがある。
鉄損は電磁石を作るための鉄心の材料や、鉄心の磁束が通りやすい性質を持たせるとか、磁石が通過する際に生まれる渦電流を少なくすることで下げることができる。
銅損は、巻線の銅線を隙間なく巻いたり、太くしたり、電流が流れる際の抵抗値を下げることで少なくできる。
そういう工夫を積み重ねて、できるだけ従来の誘導モータで、何とか目的を達成しようと開発したものである。
モータ技術は、変圧器技術と共に枯れた技術だと言われてきたが、HVやEVが生まれることで、今、世界の自動車メーカや、モータメーカがしのぎを削るようになった。
モータは一般的に回転数が上がると、回転力(トルク)が下がる。
自動車の速度、最高速度を高めるためには、ギアーで回転数を増減するか、モータ自体の回転数を高くする必要がある。
トヨタのプリウスに使用しているモータは、毎分、最高18万回転すると言われている。もし、4極同期モータを使っているなら、周波数は上の計算式から、6000Hzまで
上げなければならない。これはリチュウムイオン電池の直流をインバーターで交流に直すが、その際にVVVF(バリアブルボルテッジ・バリアブルフレケンシ)という電圧と周波数を自由に変えられる制御回路で、車の走行状態に応じたモータの特性を生み出すように制御している。
もちろん、このVVVFで使われている回路素子は半導体である。こういう制御をする際に、大量の熱が出る。その熱は損失となるので、電子回路と言えども、できるだけ発熱しない素子の開発が進められている。
現在、EVの走行距離が、満充電で500km位になっている。
クルマは走るだけでなく、快適に過ごすことも求められる。そのためのエアコンは相当の電気を食うので、EVは暖房や冷房すると、極端に走行距離が短くなる。
もう一つ、EVの欠点は、充電時間が長い事。
大量の電気をリチュウムバッテリーに充電するには、スタンドなどの急速充電でも40~50分必要になる。
サービスエリアで昼食をとる時間中なら良いが、一気に目的地に向かいたいときに、充電に小一時間かかるのは耐えられない。
そこで、今、『電費』を改良する課題と同時に、充電時間をガソリン並みに数分間で超高速充電ができる電池の開発に、各メーカが躍起になっている。
新しい個体リチュウム電池や、リチュウム空気電池と言われる電池の開発のめどがつきつつあり、2025年頃にはそういう課題をクリアしたEVが登場すると思われる。
果たして、その頃まで、自分は車を運転しているかどうか分からないが、世界の自動車は大きく変化を遂げつつある。
|

2018年5月13日(日)
第5次エネルギー5か年計画を見る!
2030年度に目指す電源構成の割合は原発が20~22%と位置付けた。
核燃料サイクル政策の維持、原発の輸出を積極的に進めるなど、原発推進の従来の姿勢は変わらない。
20~22%という電源構成からすれば、原発は30基程度の稼働が前提となる。今の原発の寿命を60年に延長することになるが、非現実的だ。
現在、新安全基準の下では8基しか稼働していない。
福島第一原発の事故後、再稼働反対の世論や、エネルギー政策への不信が強い中、30年度電源構成に初めて、再生可能エネルギー(風力発電や太陽光発電など)による発電を22%~24%の主力電力として初めて打ち出す。再生可能エネルギーは発電量が不安定であり、送電線に接続する際の制限の課題などの克服が要る。
第5次エネルギー政策の骨子は、
①原発を重要なベースロード電源とする。
新安全基準に適合した原発の再稼働を進める。
新増設の必要性は明記しない。
②核燃料サイクルはプルサーマル発電を一層推進する。
③原発輸出の推進
④石炭火力発電は需要なベースロード電源と位置付け、高効率技術を採用する。
となっている。
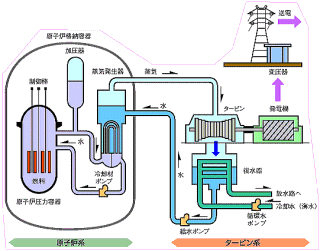 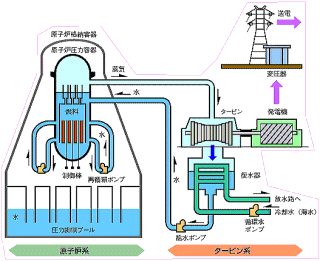 原発は原子炉の熱を取り出す方式により2種類ある。 原発は原子炉の熱を取り出す方式により2種類ある。
左の図の原子炉は、加圧水型原子炉 (PWR)で三菱重工業製西日本に多い。
原子炉で発生する熱を一次冷却水で取出し、原子炉格納容器内の熱交換器で二次冷却水を加熱し、蒸気に変えて、外部に取出しタービンを回す方式。
外部の蒸気には、放射性物質があまり含まれないので、万一、漏れても安全と言える。この原子炉の制御棒は、圧力容器の上側に設置されている。
右の図は、沸騰水型原子炉(BWR)
東芝、日立製作所製、東日本に多い。
福島原発で事故を起こした原発はBWR方式で、東電が主体に進めてきた。
両者には長短それぞれ特徴があるが、安全面からは、BWRは炉心から放射能を含んだ高温・高圧の一次冷却水が蒸気とり、外部に取り出してタービンを回す方式。
福島第一原発事故で、炉心溶融(メルトダウン)し、建屋が爆発したニュースの映像を見た時は非常に衝撃を受けた。
これで、東日本は壊滅する、日本が崩壊すると言う思いがした。
時の政権は民主党の管直人だった。思えば、大事故はどういうわけか、野党がやっと政権を取った時に発生している。
淡路・神戸大震災も、村山内閣の時だった。
もし、鋼鉄製の炉心(圧力容器)が爆発して、格納容器が壊れていたなら、桁違いの放射性物質が放出され、東日本や東京まで汚染されることになる。
幸い、炉心は溶融したが、格納容器の冷却に成功し、破壊は免れた。しかし、2000度近い高温のウラン燃料は3m近い分厚いコンクリート製の原子炉格納容器の底を溶かして、残りわずか数十cmのところで冷却ができ、固まった。
底のコンクリートが溶けてしまえば、放射能を閉じ込めることができずに、大量の放射性物質が漏れ出る寸前だった。
炉心が爆発すれば、一瞬にして大量の放射能がまき散らされる。
そこで、そうなる前に、圧力を下げるため蒸気を外部に放出する事になるが、蒸気には大量の放射能を含んでいるので、外部に放射性物質が放出されることになる。
そこで、万一の事故に対し、蒸気中の放射性物質を取り除くフィルターを通して、放射能が外部に出ないよう対策が必要になるが、その装置が非常に高価で、フィルターの性能が十分でない。
蒸気を外部に放出する際は、周囲の住民に放射線被ばくの危険性がある。
そこで、なかなか新・安全基準を満たすことが難しい。
そういう事情もあり、BWR方式、すなわち東電を中心にした東日本地域に設置されている原発は新・安全基準に対する対策が遅れ、再稼働ができていない。
安全対策に何千億円もかけ、数年間、稼働させるだけで、廃炉にするような原発に依存するのではなく、その金を再生可能エネルギーの開発にかけて、送電線網の全国規模の整備、構築費に使う方が、将来に向けた電力エネルギー政策としてはベターだと思う。
電力各社は、何故、原発再稼働に拘るのか?
手持ちの原発内には、十分なウラン燃料が貯蔵されているので、それを使いたいのだろう。
しかし、原発を稼働させることは、ウラン燃料の燃えカス(放射性物質)の処分、処理問題が起きる。これについては何も決まっていない。何とも無責任な話だ。
|

2018年5月12日(土)
言い得て妙! 山口代表の言葉
朝日新聞デジタル版に、公明党の山口代表の記事が掲載された。
加計問題「どんな国政上の意味あるのか?」 公明・山口氏
(加計学園問題について)国家戦略特区の制度を用いて四国に獣医学部を新設し、すでに開学をして学生が学び始めている。
これらについてどういう意味があるのか、なにゆえの主張なのか、(国会で)議論することがどんな国政上の意味があるのか、結果として何をしたいのか。
時間を費やすのであれば、そういうことを(野党側は)はっきり主張する必要がある。 そこがぼやけているという印象がぬぐえない。
印象付けの事実解明に直接結びつかないような発言を何度繰り返しても、それは深まることにはならないという印象を持ちました。(党参院議員総会のあいさつで)
この記事を読んで、びっくりした。
公明党の代表で弁護士でもある山口代表が、こういう言い方をするとは!
大切なことは、
①(安倍総理が言っているように、)事実を確認をすること。
②やったことの善・悪にけりをつける。
③(その上で、)国民の判断や司法の判断を待つ。
今は、①の段階で、前に進まなくなっている。
質問に対する答弁が、整合性が取れていない。
そういう中で、少なくとも整合性を取ることが先決だ。
それは事実を事実として認めるしかないだろう。
事実を認めれば、次の段階に進める。
公明党も、事実確認のため協力をすべきだ。
与党として、自民党や安倍政権の肩を持つということでは納得のゆく追求ができない。
事実を追及することと、与党の足を引っ張る材料にしようとするのは、意味が違う。
事実は、誰にも曲げられないことだ。
今やっていることが、国政上の意義や意味があるのか?という言い方は、このゴタゴタの責任を野党にありとほのめかす表現は卑怯だ。
|

2018年5月12日(土)
愛媛県庁に正義(事実を語る)が生きていました!
このところ、国会の森加計の審議や、官僚トップのセクハラ騒動など、異常な出来事が続き、日本の中央政府はどうなっているのか? といやな空気が立ち込めていましたが、昨日、愛媛県の中村知事が事実を語りました。
中村知事の記者会見の内容は安倍政権にたてつくという印象もあり、勇気が要る行動だと思いますが、中村知事は『事実を述べないと真実が消されてしまう』という切実な思いから、Fact(真実・事実)をありのままに述べられたのだと思います。
大変立派な方です。
それに比べて、官僚のトップ(次官)や首相補佐官や首相秘書等という立場の国の偉い方々が、事実を隠して、別の筋書きや、記憶忘れを言い訳に答弁してきましたが、ここにきて事実を記録したメモや、メールや、書類や、名刺などドキュメントが現れ、隠し切れなくなってきて、ウソがばれ出しました。
柳瀬秘書官の参考人質疑の答弁で納得ゆかないのは、秘書という役割に居ながら、2年間も加計学園の獣医学部開設に関わるいろんな学園側と、愛媛県側とのやり取りの情報を、自分のボスの『安倍総理に伝えていない』と言い切っていることですが、これはあり得ない話です。
それは、安倍さんがいつ知ったという期日を国会で答弁しているので、それまでに秘書が総理に報告したと言えば、安倍総理が知っていたということになるからです。
だから、誰が聞いても、納得がゆかないような、総理には報告していないということを何回聞いても、かたくなに認めないのです。
利害関係のない普通の人が聞いて納得行く話ではありません。
ということは柳瀬秘書官がウソをついているとしか考えられないのです。
総理は重要案件が沢山あり、「そういう話は伝えるに及ばないことだ」という言い訳をしていましたが、それなら秘書としては失格でしょう。秘書は日常のことを細かく伝えるのが仕事です。ましてや、お友達の加計学園の獣医学部開設の話ですから。
柳瀬秘書官の返答は誰が聞いても納得がゆかないのです。
それにしても、国会を長期間にわたり空転させた大罪は誰が責任を取るのかです。国会の開催には多額の費用が掛かります。資料のコピー代等はしれたものでしょうが、空回りする審議の返答の準備をする人件費だけでもバカになりません。その上に、重要法案の審議が止まるわけですから、その損失は膨大なものになります。
国会の直接費用だけで、何億円、何十億円の損失です。
そういう状況を生み出した根源が安倍総理や昭恵夫人にあるのなら、潔く責任を取らなければ、おさまりが着かず、ますます混乱します。
自分がやったことは、やったという潔さが一番大切です。
『やっていながら、やっていない』というウソを貫き通すことは、いずれバレます。
政府、特に官邸が腐っているのではないかと言う気がします。正々堂々と事実を明らかにして、やったことはやったと言えばよいのです。
安倍総理の理屈では、『やっていないのだから、それ以上言えないのではないか!』と言う話を聞きました。『事実をしっかり、徹底して調べる』とも言いました。
しかし、事実をしっかり調べた結果、秘書官の話を聞けば、『それはないでしょう!』という答弁を繰り返す。
今回、その答弁をひっくり返すドキュメントのいくつかが公表された。
14日に国会が開かれますが、どういう展開になるか注目です。
その上で、国民がどうそれを判断するかは、別の話です。
隠さなけらばならないようなことをしながら、やっていないというウソは通じないことを今回の事件を鏡にして、それこそ、この種の再発が起きないような手立てを仕組化し、実行することが大切です。
嘘をついた人や、公務員法規違反した人や、トップの責任問題はその次の話です。まずは、国会を正常化しなければなりませんね。
中村知事は、まじめに取り組んでいる県の職員が官邸のウソに対して、黙って見過ごせないという強い正義感で今回の発表をされたものだと思います。
正義は地方に生きていました。
|

2018年5月10日(木)
普通はあり得ないおかしな話
やはり、ウソをついているな!
柳瀬唯夫元首相秘書官が10日午前中、衆院予算委員会、午後は参議院で加計学園関係者との面会について、参考人質問に応じた。
そのNHKテレビの内容がネットでも紹介されているので、追記した。
フォントの色が青い部分が記事の紹介部分
********************************************
冒頭、「国会審議に大変なご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません」と謝罪した。そして加計学園、愛媛県、今治市の職員と2015年4月2日に首相官邸で面会したこと、さらにその直前の同年3月頃と6月前後の計3回、加計学園と面会したことを明かした。さらに加計側の出席者の1人が今春、開学した獣医学部の吉川泰弘学部長だったことも認めた。
柳瀬氏は加計学園関係者と知り合ったきっかけは、2013年に安倍晋三首相が河口湖の別荘で、安倍総理が主催のバーベキューとゴルフ会を開いた時だと説明。
安倍首相が「腹心の友」と呼ぶ加計孝太郎理事長もバーベキューの席にいたことを認めた。
さらに「庭でバーベキューをして秘書官も十数人いますし、総理のご友人、親族もおられ、加計さんもおられた」などと状況を説明した。
自らが安倍首相らとゴルフをしたことも認めたが、緊急時の要員として後方にいたとし、「総理と加計理事長が、どういうお話をしていたかわからない」と、安倍首相と加計理事長との間で交わされた会話について、自らはあずかり知らない立場にいたことを重ねて強調した。
午後に行われた参院予算委員会では立憲民主党の蓮舫議員が質問に立った。
蓮舫:最初の面会は3月24日と聞いているんですが、なぜ加計学園関係者と会ったんでしょうか?
柳瀬:アポイントの申し入れがあって、今度上京するのでお会いしたいと。
蓮舫:具体的な案件がわからないけれど、上京したのでお会いしたい。
つまり首相秘書官である柳瀬さんと学園関係者はそれくらい密接な関係ということでしょうか。
柳瀬:元々総理の別荘のバーベキューでお会いし、面識はありましたので…
蓮舫:加計関係者とバーベキューでお会いし、どなたから紹介されたんですか。
柳瀬:総理は河口湖の別荘で、ご親族やご友人を集めてバーベキューをよくやっておられました。ご紹介いただくとかそういう場ではございません。
何十人も人がいる中でお会いしたというわけで特に誰かに紹介されたわけではございません。
蓮舫:全く紹介されていなくて、何十人も人がいる中で、お会いをした。
その人から連絡がきて、案件もわからないでお会いをする間柄なんですか?
3月24日の面会で、あなたから加計学園に「国家戦略特区でいこう」と助言していませんか。
柳瀬:記憶がクリアではありませんけど、3月の最初にお会いしたときも構造改革特区で何度もやっているけれどうまくいかないという話がありまして、その時に国家戦略特区制度をスタートしていましたし、安倍政権として大事な柱でございましたので、その時に国家戦略特区の話になったと思います。
柳瀬氏は焦点になっている安倍首相の関与の有無については一貫して否定。
だが、柳瀬氏が否定すれば、するほど疑惑はますます深まったといえる。
柳瀬氏は愛媛県職員や加計学園関係者と面会した際の記録の存在について立憲民主党の長妻昭議員から問われても「メモは取っておりません」と答弁。
安倍首相への報告については「いちいち報告したことはない」と述べると議場からは「エーッ」という声があがった。
長妻氏は記者団の取材に「首相経験者は秘書官経験者に私が話を聞いた限りでは『そんなことはありえない』と言っている。信用できない」と話した。
この発言には与党議員からも驚きの声があがった。
自民党の閣僚経験者は「秘書官がメモを取らないなんてありえない。
こんなのウソに決まっているじゃないか」と憤る。
実は、官邸が細かい過去の記録をキチンと保存していることについて、安倍首相自身が語っていたこともある。
2014年3月21日、フジテレビ系の「笑っていいとも!」に、安倍首相は現役の首相としてはじめて出演した。
このとき、司会のタモリとのトークで、安倍首相は番組5千回記念で当時の小泉純一郎首相が電話で生出演したことを紹介し、「そういう記録は全部残っているんですよ。やっぱり官邸には」と自慢げに語っていたのだ。
ところが、加計学園問題が国会で取り上げられ、愛媛県や今治市の職員らが官邸を訪問していた事実が問題になった昨年7月には見解が一変。
萩生田光一官房副長官は(当時)は、官邸の記録について「官邸訪問者の記録が保 存されておらず確認できない」と説明した。
経産省出身で首相秘書官の経験もある江田憲司衆院議員も、柳瀬氏を厳しく追及した。
「総理秘書官として常識外れのことばかり。
(秘書は)首相の政策補佐。
許認可や補助金の対象となる可能性のある事業者に会うことは常識に外れている。
総理か政策秘書官から指示があったとしか思えない」
今後、国会で加計問題はさらなる火種を残すことになった。
前出の閣僚経験者は、怒りをあらわにした。
「天下国家のために働く官僚たちが、なぜ安倍さんの友達の私的な利益のためにウソをつかなければならないのか。自浄能力を失った組織は崩壊するしかない」
**************************************************
NHKテレビ中継を見て感じた点は、愛媛県のメモにあった平成27年4月2日のほか、「同年2、3月ごろ」と「4月2日以降」も首相官邸であったことを認めた。
認めざるを得ない状況になったから、一転して認めたと言える。
それは、いろんな議事録などの資料が公開されたので、今までは『記憶にございません』で通してきたことが通じなくなったからだ。
しかし、安倍総理には、平成27年に3回も加計学園関係者にあったことや経緯を報告をしていないと答弁した。
安倍総理は2017年1月20に加計学園の獣医学部新設を初めて知ったと言っているから、この点はつじつまを合わせるために、絶対そう言わざるを得ないからだ。
総理秘書官が2015年2月、3月、5月に加計学園関係者と会っていながら、ボスの総理にその話を伝えていないと言っているが、これはあり得ない話だ。
総理と数人の総理秘書官は、政策や、日程・スケジュールなどのあらゆる調整、相談をしている。これは当然の仕事だから。
当然、『従来の規制の岩盤をドリルで穴を開ける』と格好よく言った安倍総理の政策の一丁目一番地という規制緩和の取り組み内容を、秘書が加計学園関係者と数回も会っていながら、その内容や経過を総理に2年間も、全く伝えなかったということは常識はずれだけでなく、ありえない話だ。これは嘘をついている証拠だ。
そのウソを強引に権力で押し通そうとするから、総理がいくら『丁寧にきちんと説明責任を果たす』と言っても、むなしい言い訳になる。
このことが、森加計学園の問題の根底に常に横たわっている。
こういう無駄な、無益な議論に時間を費やすことが許されてはならない。
世界は猛烈な勢いで変化している最中に、日本が悠長な総理の案件などというたわいもないことで、国会が空転したり、意味のない参考人招致などで、言った言わないのやり取りを聞くのは忍びない話だ。
しかし、政治家や行政府や公務員は勤めを正しく果たさなければ、根幹が崩れる。
だから、『やったことはやった』と認め、その上で『今後は注意して取り組む』という潔さが欲しい。国民に正直に詫びることが、正常化の第一歩だ。
言葉だけがいくら誠実に、正直に、真摯にと繰り返しても、やったことを認めず、しっかり検証するというような言い方は、自分の非を認めない権力を傘にきた物言いとしか映らない。いくら言い訳しても、真実は曲げられない。
真実は、誰が聞いても納得ができ、つじつまが合うという事。
韓国の前、朴大統領は禁固24年の刑を受けた。韓国は大統領まで断罪する国だ。
日本は優しい国民性の国だから、情状酌量が通じることが多いが、法律がどうのこうのより、社会正義や世間の常識に照らして、『おかしいことは、やはりおかしい。』
秘書が2年間も加計案件をボスに一言も伝えていない!ことは通じない話。
日本の優秀な官僚トップがなぜ、こういう事態に巻き込まれなければならないのか?
上司がまずい事、私的な事など官僚の立場で、それはできませんと言えばいい話だが、上昇志向の強い人(官僚)は、人事権を握られると、自分の正義まで曲げてしまうのか。情けなく、かわいそうで、みじめな気がする。
上司から『カラスは白いよな!そうだろう!』と言われて、『いや、カラスは黒いです!』と反論できる人がどれだけいるだろう。
上司がカラスは白いと無茶を認めさせようと迫ってくる時に、正義を貫いてそれに反発できる人が何%いるだろうか。
今の官僚は政治家より低くなっている。
『政高・官低』になっている。
これは、官僚の人事権を首相官邸(政治家)が握っているからだ。
サラリーマンも同様だ。官僚も人の子だった。
今日の参考人招致で、森・加計問題は終わらないだろう。
|

2018年5月6日(日)
モノを捨てられますか?
昨日は『こどもの日』で、久しぶりに我が家もにぎわった。
今日は日曜日、大型連休も今日で終わりで、東京の娘や孫も帰り、元の静かな我が家に戻りました。明日からは普段の生活に戻る。
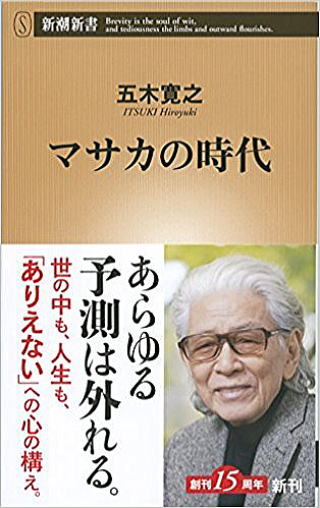 今日は時間潰しに、五木寛之氏の『マサカの時代』新潮新書を読みました。 今日は時間潰しに、五木寛之氏の『マサカの時代』新潮新書を読みました。
表紙は左のとおり、『あらゆる予測は外れる。
世の中も、人生も、「ありえない」への心の構え』という帯が付いています。
また表紙の裏には、
世界情勢も日本社会も、そして個人の人生においても、予期せぬ出来事はいつでも起きる。
不況や戦争、天災に病気、人はその繰り返しの中で生きながら、それでも「まあ、大丈夫だろう」と思い込む。
しかし今、時代の風は大きく変わりつつあるようだ。
ひたひたと迫りくる歴史的な大変化、常識のルールも通用しない「マサカの時代」とどう向き合うか、これからを生き抜くヒントが満載!
五木さんの随筆的なタッチで書かれた肩の凝らない本ですので、是非、一読されることを勧めします。
その中で、『モノを捨てる心を捨てる』というタイトルの文があります。
日常、特に必要でないモノが身の回りにたくさんある事について、
これは戦中戦後のモノ不足時代に育ったせいだろう。
その時代の後遺症で、未だにモノを後生大事にして置いておく生活を続けている。
ほとんどのモノは捨ててしまっても、生きてゆくことに何の差支えもない。
また、後生大事に置いているモノを今後使う予定もない。
では、モノ(ゴミに近い?)を捨ててしまった後に残るものは何だろう。心の大掃除か。
モノに執着するのは、生活上の問題ではない。要するに心の問題である。
しかし、心の問題であるなら、部屋に散乱しているガラクタにとらわれることもないではないか。モノが溢れようが無視すればいいだけの話。捨てるもよし、捨てざるもよし。
拘泥(こうでい/こだわる)する心こそ問題である。
改めて部屋を見ると、古道具屋のごとき部屋がなんとなくいとおしいくなってくるのはどういうわけか。
『はかなきこの世を、共に生きてきたモノたちよ』と叫びたくなる気持ちを抑えることができない。モノが捨てられない、それもまたいいではないか。
モノにこだわる心があるからこそ重荷に感じるのである。
この世を共に生きてきた仲間と思えば、溢れるモノに対する感覚もまた違ってくる。
もし、あらゆる無用のモノを捨てて、すっきりした空間に身を置いたとしたら、自分は果たして幸福だろうか?
モノを捨てられないのは、執着心のせいである。執着はどこから来るのか。
生きていればこその執着だろう。
生きている限り、執着は消えない。
モノに執着し、ヒトに執着し、イノチに執着するのが人間だろう。
そういうふうに考えれば、身の回りのガラクタは、大げさに言えば、自分の人生の証、人生の友のようなもの。そうなると捨てられない!
これは人それぞれの考え方だ。
我が家はというか、家内は女には珍しく、驚くほどスパッとモノを捨てることができる。特に衣類は古くて着なくなったモノは、あまり着なかったものであろうが、傷んでいないモノも、お構いなしに処分する。これは衣類に限らない。
最近、家内と『終活』という話をよくする。
互いに身の回りを少しずつ整理して行こうと話あっている。
特に、自分の趣味であるアマチュア無線の機器や部品は、自分しか分からないモノなので、これは自分が処分を担当している。
以前に比べると、必要なモノ以外は随分処分した。
処分方法は、Yahooオークションという手段があり、今までは廃棄物として捨てたようなモノでも、出品すれ売れる。
そういう意味では、時代が変わったな!と感じながら、こまめに整理を進めている。
おかげで、我が家はすっきりとした状態を維持している。
逆に、捨てられない奥さんの家もある。
近くでもらってきたふるいモノを家の内外に置いている。そうなるともう大変だ!
自宅でも、職場でも、モノを後生大事に置いている人が居る。そういう家や職場は、足の踏み場もないほど、モノで溢れている。
そこまで行かなくても、一見して、もので一杯だな!と感じる。
玄関に入ると、履物がいくつも並んでいれば、その家の中は相当なごみ屋敷!
でも、自宅は自分の空間だから、自分の好きなようにすればいい。
しかし職場は、使わないものは捨てて、仕事のしやすい環境を維持しなければ、作業がしづらくなり、生産性が落ちる、また品質不良の原因にもなる。
4S;整理・整頓・清潔・清掃とはよく言ったものだ。
|

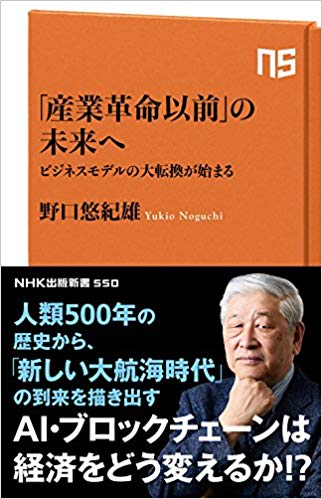
 GEは、当時アメリカはもとより、世界最大の電気会社で、そのルーツはエジソンに辿り着く。エジソンは傑出した発明家として知られ、生涯におよそ1,300もの発明と技術革新を行った人物である。例えば蓄音器、白熱電球、活動写真である。
GEは、当時アメリカはもとより、世界最大の電気会社で、そのルーツはエジソンに辿り着く。エジソンは傑出した発明家として知られ、生涯におよそ1,300もの発明と技術革新を行った人物である。例えば蓄音器、白熱電球、活動写真である。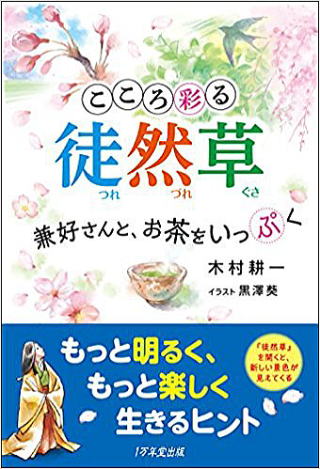
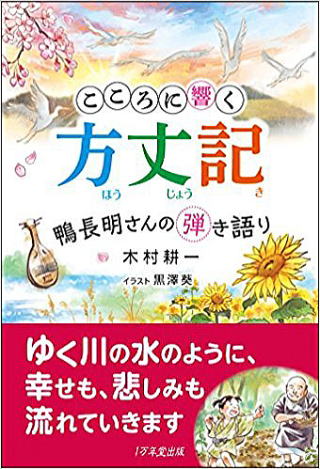
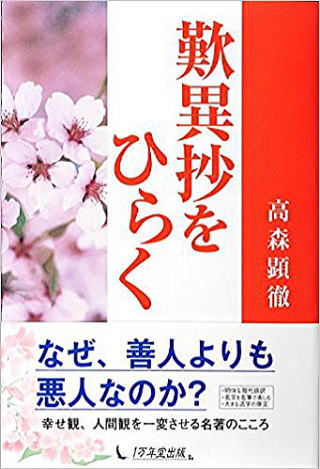
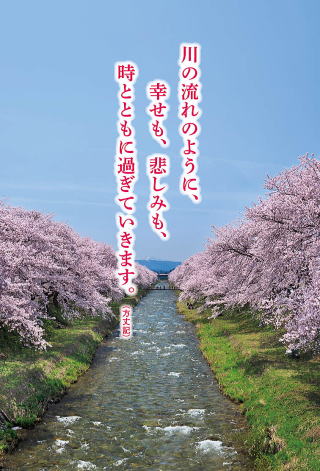 誰もが知っている有名な『方丈記』を大きな文字で、分かりやすく意訳しました。
誰もが知っている有名な『方丈記』を大きな文字で、分かりやすく意訳しました。 インダクションモータの特徴は、
インダクションモータの特徴は、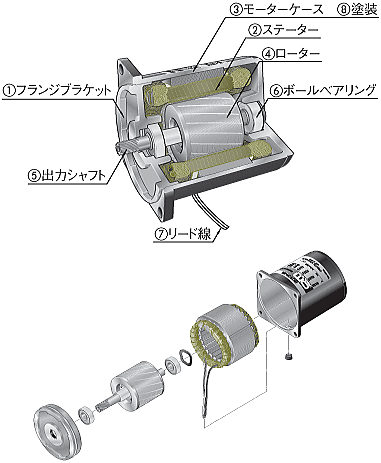
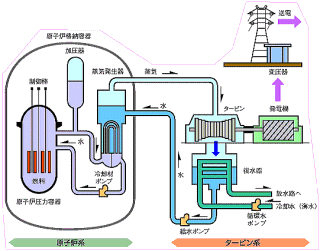
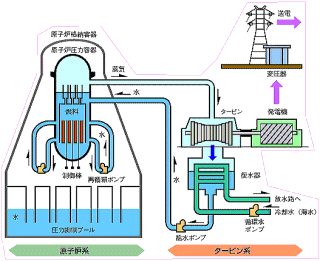 原発は原子炉の熱を取り出す方式により2種類ある。
原発は原子炉の熱を取り出す方式により2種類ある。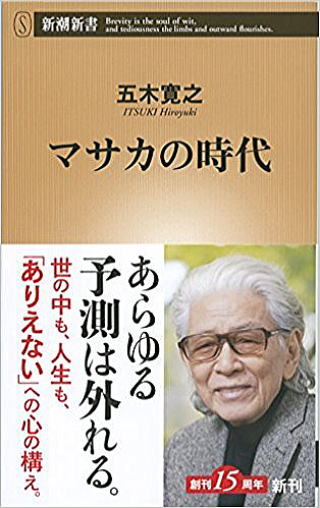 今日は時間潰しに、五木寛之氏の『マサカの時代』新潮新書を読みました。
今日は時間潰しに、五木寛之氏の『マサカの時代』新潮新書を読みました。