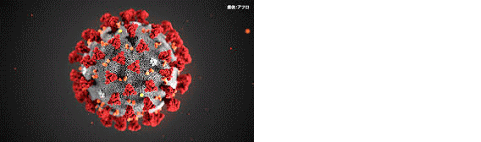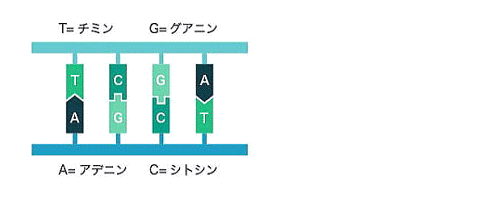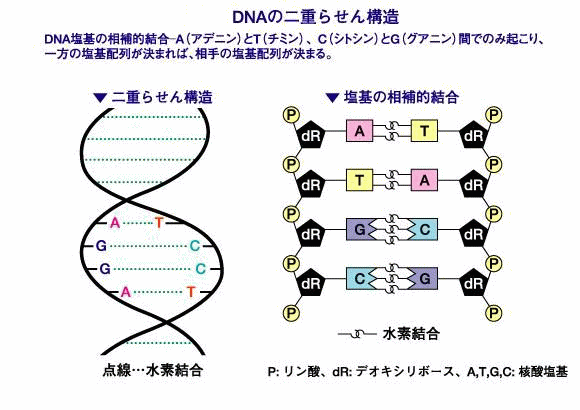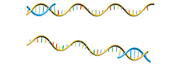コロナウイルスについて
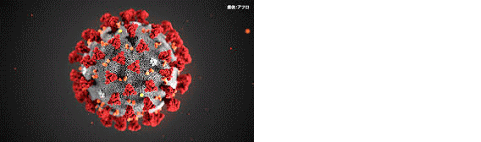
正式名称は、COVID-19
病原体である細菌やウイルスは小さいので、肉眼で見ることができない。
その大きさは細菌が1μm(1/1000mm)程度で、ウイルスはさらに小さく、細菌の1/10から1/100ぐらいの大きさ。
現在、流行している新型コロナウイルスは、太陽のコロナのように突起が出ている丸い形をしているので、『コロナウイルス』と呼ばれている。このコロナウイルスと同様なウイルスは他にもたくさん存在する。
細菌とウイルスの違い
細菌は単細胞生物で自ら増殖し数を増やすことができる。その形は一定ではない(ふにゃふにゃしている)。
ウイルスは自分だけで、単独では増殖できず、他の生物の細胞(宿主細胞)の中に入り込んで増えることができる。ウイルスは一定の形を保ち、これを精製して抽出すれば結晶になる。結晶とは、ある分子や原子が規則正しく整列した状態で、例えば、水晶は石英の分子が整然と並んでできたもの。結晶は無機物(無生物)を意味する。
ウイルスは生物と無生物の両面を持った不思議な物質と言える。
細菌は(光学)顕微鏡で見えるが、ウイルスは小さすぎて光学顕微鏡では見ることができない。電子顕微鏡によりその形状が明らかになった。しかし、電子顕微鏡は大がかりな装置で、真空中で高い電子線に晒されるので、検体を生きたままで見ることができず、設置場所は限られ、簡単に検査器として使うことができない。
遺伝子とは、どういう定義なのか?
①
生物の形・質を決めるもの
②
親から子に伝わるもの
遺伝子発見の歴史
英国人 グリフィスは、肺炎双球菌(細菌)のS型菌(病原性あり)とR型菌(病原性なし)を使い、煮沸したS型菌と生きたR型菌を混ぜると病原性が現れることを発見した。R型菌にS型菌の何かが作用して病原性を持つように変化することを発見した。これを形質転換と呼んだ。(実は遺伝子のことだった)
『DNAが遺伝子である』ことを提唱したのは、1930年代、エイブリーであった。
彼も肺炎双球菌(細胞)の研究をしていたが、ある酸性物質(核酸=DNA)が形質転換(遺伝)に作用していること、そしてその核酸(DNA)は、たった4つの単純な物質から成り立っていることを発見した。
4つの物質とは、A(アデニン)T(チミン)C(シトシン)G(グアニン)という核酸で、『ヌクレオチド』と呼んだ。
|
高分子
|
構成単位
|
種 類
|
機 能
|
|
核酸(DNA)
|
ヌクレオチド
|
4種類
|
遺伝情報の担い手
|
|
タンパク質
|
アミノ酸
|
20種類
|
生命活動の担い手
|
ヌクレオチドは熱に強い。
タンパク質は、熱に弱い。
AとT、CとGは互いに結合しやすい化学構造を持っている。水素結合をしやすい。
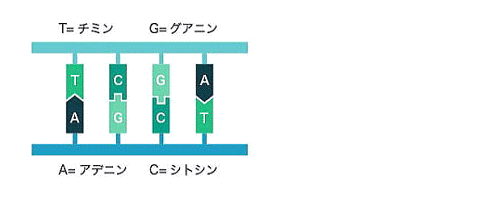
その後、アーウィン・シャルガウは、『シャルガウ法則』を提唱した。
動物や植物や微生物など全ての生物は、どのようなDNAであっても、その構成は4つの内、AとT、 CとGの含有量は等しいということを発表した。
即ち、 Aの数=Tの数、 Cの数=Gの数
例えば、
ACACACATAAGCATAAGCGCGCCGCGGAGAAC :センス鎖
TGTGTGTATTCGTATTCGCGCGGCGCCTCTTG :アンチセンス鎖
センス鎖 Aが12、Tが2、 Cが9、Gが7
アンチセンス鎖 Aが2、Tが12、 Cが7、Gが9
合計 Aが14、Tが14、Cが16、Gが16
A=T C=G ;シャルガウの法則
研究者は「この条件を満たすには、どういう分子構造をしているのか?」を求めて研究に没頭した。
従来の学説に固執するベテランの研究者は、『複雑な遺伝情報がたった4文字で成り立つはずがない、他にまだ見つかっていないタンパク質があるはずだ!』という立場で反論が多くあった。当時はアナログ技術の時代で、デジタル情報理論が進んでいなかったので、たった4文字の組み合わせで膨大な遺伝情報が伝達できる認識が出来なかった。若い研究者たちは、X線回折画像解析や化学データなどをもとに、実験により理論を構築し、反論を崩していった。
全く新しいことに挑戦する場合は、必ず反論が出る。それに耐えて自らの主張を論理構築することで、ある瞬間に大発見につながる良い事例だ!。
二重らせん構造の発見、提唱
1953年 ジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックの若い二人により、今まで謎の難問の『鍵』が発表された。その内容は、『DNAは二重ラセン構造をしており、互いに他をコピーした対構造になっている』というものだった。
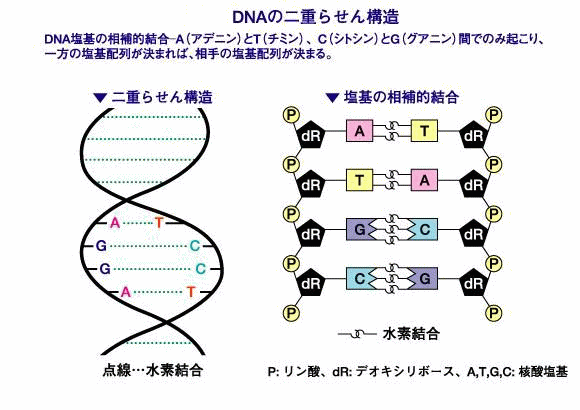
二重ラセンがほどけると、ネガとポジ(鏡の実像と虚像)のような関係になる。
ポジを元に新しいネガが作られ、元のネガをもとに新しいポジが作られる。
そして新しい二対の二重ラセンが生まれる。このポジとネガのラセン状の帯が遺伝情報として生命の自己複製の仕組みとして働く。
細胞内でDNAが複製される時には極めて複雑な連鎖反応が生じている。
数十以上の酵素や機能タンパク質により、その反応が支えられている。
まず、DNAの二重ラセンを特別なしくみでほどく。
ラセンをほどく際に生じるねじれを解消するしくみも必要になる。
ほどかれた地点には複数の酵素群が集結し、核酸の材料となるヌクレオチドを集めて一つの鎖を鋳型にして新しい鎖を合成し始める。
細胞の狭い核の内部では数々の空間的な問題が生じる。
それを解決しながらDNAの複製が進められる。
この反応は、ほんの数分で行われる。
DNAを見えるようにするには、10億個以上のDNA分子が必要になる。
DNAを増やしたい場合は細胞の力を借りる。特別な大腸菌を使い、その内部でDNAを増やしてもらう。
この方法は手間暇がかかり、医療現場では役に立たない。簡単にウイルスの有無や、種類を検査できる方法が求められた。
PCR検査器の発明
PCR検査はその難問に見事に応えた。PCRとは、ポリメラーゼ・チェイン・リアクション(ポリメラーゼ連鎖反応)。1988年、米国のパーキン・エルマー・シータス社が開発した。任意の遺伝子を試験管(チューブ)内で自由自在に複製・増殖する技術である。
PCRの原理
事前にチューブ内にポリメラーゼ(酵素)と、プライマー(人工合成した一本鎖DNA)と、十分な量のA、T、C、Gのヌクレオチドを入れて置く。
反応のプロセスは以下のとおり
① 複製したいDNAが入ったチューブを短時間、100℃近くまで加熱する。
②AとT、CとGの結合が外れ、バラバラになる。

③DNAはセンス鎖と、アンチセンス鎖に分かれる。
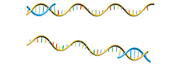
④ チューブを一気に50℃まで冷やす。
⑤その後、再び徐々に72℃まで加熱する。
⑥ポリメラーゼ(酵素)はセンス鎖の一端に取り付き、プライマーの助けを借りて センス鎖を鋳型にして対構造のDNA鎖を4つの文字で紡いでゆく。

⑦この合成反応は約1~2分程度で終わる。これでDNAは2倍になる。

⑧この工程を繰り返す。DNAは倍々で増え続ける。
⑨1サイクルは、数分で終わる。
⑩DNAは10サイクルで、2の10乗で1024倍、20サイクルで100万倍。30サイクルで10億倍になる。30サイクルに要する時間は2時間足らず。PCR検査は開始から終了まで、約2時間で結果が得られる。PCRマシンは単に温度を上げ下げするだけの装置で、DNAがもつ転写機能をうまく活用したもの。ただ、庫内の温度を100℃近くまで上げるので、ポリメラーゼ(酵素)が活性を失わないよう耐熱性酵素(ポリメラーゼ)を使う。
PCRの優れた点
ごくわずかなDNAがあれば、それだけを抽出して増せること。この特性を利用して、犯罪捜査で鑑定に活用されている。
この場合のカギは、2種類のプライマーを用いること。プライマー1は、ごく短い10から20文字程度の一本鎖のDNAで、任意に人工合成したもの。(この程度の短いDNAは人工合成ができる)
人間の30億個のゲノムの中のどこかに1000文字程度の特定の遺伝子を取り出し増幅したいとする。元になるゲノムは、ごくわずかな量である。プライマー1は約10文字から成り、この端の部分のアンチセンス鎖に対合するよう配列を合成している。
以下順次、反応を示すと
・100℃に加熱すると、わずかな量のゲノムサンプルは、センス鎖とアンチセンス 鎖に分離する。周囲にはプライマー1が大量に入れられている。
・次に、50℃まで下げると、大量のプライマー1は一斉にゲノムの中に散らばり自分とマッチングする配列を探す。もし、対合が成立するとプライマー1はそこに落ち着く。
・長い一本鎖のDNAに、短いプライマー1が結合した状態となる。
・ポリメラーゼはこの場所をきっかけに初めてのDNAの合成を開始できる。
・プライマーはポリメラーゼが反応を引き起こすための土台として働き、ポリメラーゼはプライマーに新たな文字をつなげてゆく。
・プライマー1は対合するアンチセンス鎖の文字を鋳型として決定されてゆく。
・ゲノムの構造は膨大で、類似の配列は何か所かあり、プライマー1はいくつかの場所に結合する。
・ポリメラーゼによる合成は複数の場所で起きる。
重要なことは、プライマー1にアンチセンス鎖状の1000文字部分の左端に必ず対合するということ。
・プライマー2というもう一つのプライマーを用意する。
・プライマー2は、1000文字配列を挟んでプライマー1と反対側の端の配列に対合する10文字から成っている。
・プライマー2は、プライマー1とは逆に、センス鎖に対合するように配列を作っている。
・センス鎖に結合したプライマー2はポリメラーゼが反応のきっかけをつくり、新しいDNA鎖の合成を引き起こす。
・プライマー2はセンス鎖に対合しているから、合成の方向はアンチセンス鎖と対合している先ほどのプライマー1とは逆方向になる。
・プライマー1から開始される合成反応と、プライマー2から開始される合成反応は1000文字の配列を互いに挟み込むように向かい合いながら、それぞれ別の鎖を合成するように仕組まれている。
・その結果、出来上がるのは1000文字配列を含む新しい二本鎖のDNAである。
・このサイクルを理論上、無限に繰り返えすことができる。
・その都度、1000文字鎖は増幅される。
・プライマー 1と2が互いに働く場所は、この1000文字を挟む部分しかない。
・この部分だけが増幅される。
・こうして、目的のDNAが得られることになる。
1本の髪の毛や、一滴の血液や汗から、DNAを増幅して、犯人の特定ができる。また、検体から新型コロナウイルスの存在の有無を調べることができる。
PCR検査が進まないわけは?
PCR検査器は庫内の温度を上げ下げするだけの単純な機器で、電子レンジ程度の大きさの器具。最近は測定の自動化が進んでいる。
日本には自動PCR検査機を製造しているメーカがあり、すでに欧州に大量の輸出を行っている。
日本製のPCR自動検査器が海外でたくさん使われているのに、なぜ日本では使われないのか?
一つは、医療機器の縛り(医療機器法による規制)
一つは、感染症法により特定伝染病の検査は保健所が行うことになっている。 その結果、保健所に検体の収集、検査作業、結果の報告などの業務が集中し、人員不足も含め円滑な処理できなかったこと。
今後の社会活動の再開に向けて!
やっと、政府は20万件/日の検査ができる体制にすると発表したので、今後、検査体制は増強され改善される見込み。
高齢者施設や、病院や、学校、さらには『Go to キャンペーン』やスポーツ観戦など参加者はPCR検査を受け、陰性を確認することで感染予防、クラスターの発生が未然に予防できる。
特に、高齢者施設や医療関係者の定期的なPCR検査によって、感染拡大が防げるはずだ。さらに、旅行に出発直前に感染陰性を確認した人だけ参加できるツアーなどが実施されれば、ツアー客同士や旅館やホテル、旅先の関係者の感染予防が図れる。
その他、抗原検査や抗体検査等を併用すれば、社会活動を感染予防しながら進めても、クラスター発生が防げるのではないか?
|