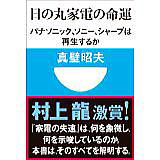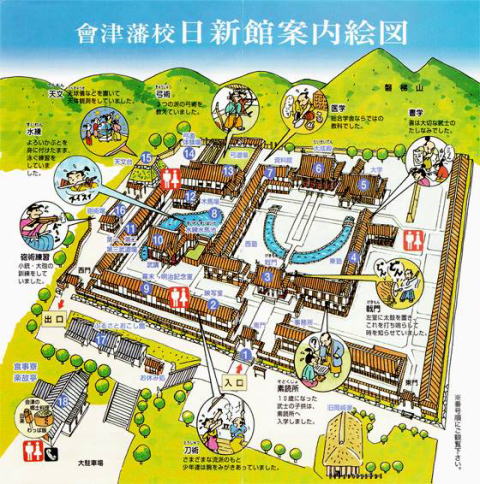12��29���i���j
���{�̉Ɠd�͂Ȃ��T���X���ɕ������̂��H
�@���N��2���c���݂̂ƂȂ����B���̈�N�͖����ɑ傫�ȏo�������Ȃ��߂������B
�@�A�x�m�~�N�X�̌��ʂŁA�~/�����[�g�͑傫���ς��A�P����100�~����܂ʼn~���ɂȂ�A�o�Y�Ƃ͏����Ă���B
�@�t�Ɍ����͂��ߗA���ɗ��鎑�ނ͍������A���ꂩ��W�����ƒl�オ�肪�n�܂�B
���킹��4���������ł��オ��̂ŁA3�����ɋ삯���ݎ��v���N���A4���ȍ~�͌i�C�̑����������邱�Ƃ͖ڂɌ����Ă���B
�@����ɂ��Ă��A���{�́w����ꂽ10�N�x�Ƃ悭�����邪�A10�N�ǂ��납15�N�ȏ�ɂȂ�B�����Ԃ��ԁA�o�ς���������C���Ȃ��B
�@���ɑ��̉Ɠd���ł����������d��A�O�m�d�C�A�V���[�v����������Ԃ܂��悤�ȏɊׂ�A�������Ă���B
�@���Ƃ��ň��̏͒E������悤�����A�܂����f�ł���ł͂Ȃ��B
�@�Ȃ����̂悤�ȏɗ����s�����̂��A���������ɂȂ邽�߂ɂ͂���Ȃ�̗v��������͂��B���̐^���𐳂������݁A�Ή����Ȃ��Ə��͂���ɐ[���Ȃ�B
�@
�@�V���[�v�͂����N�O�܂Łw�T�R���f���x�Ƃ����V�[������ʂɌւ炵���ɓ\��A�t���t���n�C�r�W�����e���r�����Ђ����|���Ĕ���Ă����̂��L�����Ă���B
�@�~�c���h�o�V�J�����̂R�K�̃e���r�����ɑ��������ʂ��A���̗l�q�����Ă����B
���傤�ljƂ̃e���r���Q�X�C���`�̃u���E���ǃe���r�ŁA���낻�딃���ւ��鎞���ł������B
�@�o�����������������͂Ȃ�ƁA�܂��v���Y�}����߂��A���ς�炸�����߁A�p�C�I�j�A�̃e���r�Z�p�҂��͂����݁A���̕\����掿�i�F�j�̗ǂ��A��ʂ̕\���̑����Ȃǂ蕶��ɂ��A����d�͂��傫�����Ƃ̓n���f�B�ł��������A���Ƃ�����Ă����B
�������A�����͂��Ă����B�t���e���r�͉掿���e�i�ɂ悭�Ȃ�A����d�͂̓o�b�N�Ɩ����k�d�c�ɕς��邱�ƂŁA��w�����d�͂ɐ��������B
�@�䂪�Ƃ̃e���r�͒n��g�f�W�^���e���r�������n�܂�A���������ւ����i����o���Ă������ɁA�T���~�̕⏕�����炢�A�T�O�C���`�̃t���n�C�r�W�����v���Y�}�i�o�������������������j���w�������B���̃e���r�͉��̃g���u�����Ȃ����g���Ă���B
�@�������������̎s�ꂾ�������Ă���ƁA�傫�ȉۑ�͌����Ă��Ȃ��B���[�J���u���t���e���r�������A�A����v���Y�}�e���r�������ƌ݂��ɋ����Ă����B
�@�����������ŁA�؍��̃T���X���Ƃk�f�d�q���}���ɗ͂����Ă����B
���傤�ǂ��̒��������������̂́A���[���b�p���s��A�y���[�ɗ��s���ă��}�̗ʔ̓X�ɍs�����Ƃ��������B
�@�X�ɕ���ł���e���r�͂r�������������Ƃk�f�d�q�̃e���r����ŁA�قƂ�ǂ��R�Q�C���`�ȉ��̒����^�e���r�������B�Ƃɂ��������B�掿�����Ɉ����Ȃ��B���n�͂܂��f�W�^���������Ȃ������̂ŁA�]���̃A�i���O�������f���Ă����B
�@���̒��ɓ��{���[�J�Ƃ��āA�r�������Ƃo�����������������̂R�Q�C���`�e���r����䂸�������悤�ɋL�����Ă���B
�@�u���E���ǃe���r����͐��E���A�ǂ��ɍs���Ă����{����o���������������������������ł����B���ꂪ�����Ƃ����ԂɓX�͊؍����̃e���r�ɐ�̂���Ă��܂����B
�@�e���r�����ł͂Ȃ�����@���①�ɂ��A���̑��Ɠd���i�̓T���X����k�f�d�q�������|���Ă����B���{���͂����e�������Ȃ��Ă����B
�@�w�i���������@�����@�m���D�P�x�ƌ���ꂽ�P�X�X�O�N�����ɔ�ׂ�ƁA�Ȃ�Ɛ��̒��̕ω����������Ƃ��Ǝ��������B
�@���̂���܂łɁA���������Ƃ��A�n�a�ƂȂ��Ă����̂ŁA�Г��̂��Ƃ͂悭������Ȃ������B
�@�o�����������������̊C�O���݈������͉������Ă����̂��H�@
�@�ǂ��������n���|�[�g��{�Ђɑ����Ă����̂��H�@
�ނ炪�~�b�V�������ʂ����Ă���̂��A�傫�ȋ^��ƕ������������������B
�@���n���݈��͂���Ȃ�Ɏs��̕ω���A���i�̗v�]�ɂ��Ė{�ЂɃ��|�[�g�𑗂��Ă����͂����B
�@�������A�{�Б��܂��͎��ƕ���������̘_���ŁA���n�̗v�]���Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@���ƕ��̐�������̓��{�b�g�⎩���@�Ȃǂ��ʂɕ��ׂĂ���B�l��Ő�������̂Ȃ玩�R�ɑΉ��ł��鐻�i�̐�ւ����A���{�b�g�⎩���@�ł͂��̓s�x�A�ݒ��ς���K�v������A����ł���H��̗���ōl����ƁA�������̂��ʂɍ�葱���邱�Ƃ��R�X�g�I�ɂ��i�������肷��̂œs���������B�w����Ȃ������̂�����Ă���̂�����A�������蔄���Ă���x�Ƃ������ƂɂȂ�B������ꗝ����B
�@�Ԉ���Ă����̂́A�w���[�J�̓��[�U�̃j�[�Y�ɍ��������i�����x�Ƃ����喽��������̏���ȓs���ŃS���������܂����Ƃ���ɂ���B
�@���{���i�͍��i���A���t�����l�A���@�\�A�����\�͂悭������B���������E�̎s���ɔ̔���L���Ă䂩�Ȃ��ƁA���{�̎s��K�͂����ł͂������E�ɗ��Ă����B���̕s������͂Ƃ��̐̂ɏI���A���Δ���鎞��͂��łɉߋ��̂��̂ɂȂ��Ă����B���m�]��̎���ɓ����Ă����B���{�ł͔����ւ����v�����S�̎s��ɐ��n���Ă����B
�@������A���E�̎s��ɑł��ďo�邽�߁A���{�ƈႤ���[�U�̐����̎d������Ԃ��悭���ׁA����ɍ������̂Â�������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
�@�w���q�l���x��w���q�l��x�Ƃ������t�͂��ꂢ���ƂŁA�����̓s���̗ǂ��悤�ɂ悭�����Ă������A���s����Ă��Ȃ������̂��B
�@���{�̉Ɠd���[�J�͂��ׂĂ��̋�����̂悤�ȗZ�ʂ������Ȃ����i�J���Ɛ����𑱂��Ă����B
�@�����Ɋ؍��̃T���X����k�f�d�q�͓��{�̂��̂܂˂����Ă��̂Â�������Ă����F���ĂȂ����ƂɋC�t�����B�l�i���������Ĕ��邾���łׂ͖���Ȃ����Ƃ�ɐɊ����Ă����B�؍��̎����̎s��͋K�͂��������A�������������ł͐��藧���Ȃ��B
�@�����Ŗڂ������̂��A��O���A�������a�q�h�b���ɗA�o���邱�Ƃ��ۑ�Ƃ����B
��i������ł́A�A�����J��[���b�p�ɂ̓u�����h���m���������[�J�����݂��Ă��邵�A����ɉ����ē��{���[�J���X����}���Ă���̂ŁA�]�n���Ȃ����Ƃ�������B
�@�C���h�̓G�A�R���͑傫�ȉ������ăK���K���₦����̂��ǂ��Ƃ���Ă����B�ȃG�l�Ȃǂ͖��ł͂Ȃ��A�}�C�R������ō����ȍ����ȏ��i�͔���Ȃ��B
�@�܂��C���h�̗①�ɂ̃h�A�ɂ̓J�M�������邱�Ƃ����߂�ꂽ�B���C�h���①�ɓ��̐H���i�𓐂ނ̂�h�����߂炵���B
�@�܂��A�C���h�l�V�A�̗①�ɂ͐��ʊ�ɐ������ĕX�����A�������������X�ɂ��ĐH�ׂ邽�߂ł������B������I��������������A���o����������悤�ȗ①�ɂ��X�������ł���Ⓚ�ɁA���X�@�̂悤�ȗ①�ɂ����ꂽ�B
�@�P���ȋ@�\�ŁA�ǂ̃��[�J�ł������悤�ȓ��e�̏��i�����A��������n�̗v�]���i�ɍ��킹�A�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���{�ł͂���Ȃ��̂����X����Ă�����Ȃ��A����������{�@�\�ɓO�����悤�ȏ��i���a�q�h�b���ł͔��j�I�ɔ��ꂽ�B
�@�T���X���͌��n�̓Ɠ��̃j�[�Y�����݁A���n�̐l��������l�i�ݒ肵�Ĕ̔����n�߂�����A�����Ƃ����Ԃɓ��{�̉Ɠd��ǂ��������B
�@��������ƁA�������̂����̂͂��Ƃ��ȒP�Ȃ悤�Ɏv���邪�A�����Ԃ����l�ŁA���W�r�㍑�����̎Ԃ��Ƃɂ����l�i���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�C���h�̃^�^�����Ԃ͂R�O���~�̂S�֎����Ԃ����b��ɂȂ����B���C�p�[�͈�{���������Ă��Ȃ��B�֎q���e���Ȃ��̂��B�`�a�r�Ȃǂ̍����Ȑ���@�\�͂Ȃ��B
���������Ď~�܂邾���Ƃ������́B
�@���͂����������̂Ŕ���邪�A����Ɉ����Ă��K�v�ȋ@�\�����鋣���ɂȂ�B
���̋����ɏ����Ȃ���Δ���Ȃ��B�P���ɉ��i�������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��Ȃ��Ă���B
�@�T���X�����傢�ɔ���܂������w�i�ɂ�������g���Ƃ�����B
������i���̍l������ς������Ƃɂ���B
�@���{���[�J�͂ǂ������ǂ����́A��荂�i���Ȃ��̂����Ƃ����l�����Ŏ��g��ł����B�O�̃��f�����i���𗎂Ƃ��Ƃ������Ƃ̓^�u�[������Ă����B
������V���i�͂��̂��тɂǂ�ǂ�i�����ǂ��Ȃ邪�A�l�i�������Ȃ�Ƃ������Ƃ��J��Ԃ��Ă����B
�@�������̂⍂�i���Ȃ��̂����ɂ́A�����ޗ������H�@�ȂNJJ���ɐl��⎞�Ԃ�������ł����B���̂��ׂĂ͐��i�ɓ]�ł����R�X�g�ł���A���i�̒l�i���h���h�������Ȃ邱�Ƃ��Ӗ�����B
�@�����̏��������シ�鎞��ɂ́A�����������m�Â���͐����������B�������A���݂̂悤�ɔK�Ј���A���o�C�g���������߁A�����������オ��Ȃ��Ȃ�������͏��i�̉��i���グ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�i���̍l���������̂܂܂ɂ��āA���i���i��������Ί�Ƃ͗��v���o�Ȃ��Ȃ�B�����������z�ɓ����Ă��܂����Ƃ�����B
�@�T���X���͌��n�j�[�Y�ɍ��킹�����i�����[�U��������l�i�ɐݒ肵�A���[�U�̕s����N���[�����ǂ��o�邩�����ɂ߂�悤�ȕi���̍l�����ɕς����B
�@������w�̊��s�Ǘ��x�Ƃ����Ăѕ��ŕ\�����A���̐������w�W�Ƃ��Ă���B
�@���̈Ӗ������[�U�����i���g���āA�s�ǂ��Ǝv�����ǂ����ŁA�s�ǂ��Ǝv���A�X���������i��V�i�ɓ���ւ��鏈�u���Ƃ�B�����炻�̕��̕��i��i�ɂ͗]���ɗp�ӂ��Ă����B
�@���̂��߂ɂ́A���{�̃��[�J�̍l�����ƈႤ���g�������Ă���B
�@����͕��i��i�ɂɂ��Ăł���B���{�̃��[�J�͓O�ꂵ�čɂ����Ȃ�����B���̋��ɂ̓g���^�����Ԃ��w�Ŕ����x�ŁA�w�������C���ɂ͕K�v�ȕ��i��K�v�Ȃ����������A���i�ɂ͎����Ȃ��x�Ƃ����d�|���ł���B
�@����͐������C�������łȂ��A�C���̂��߂̕�C���i�ɂ��Ă�������B�܂����i�����łȂ������i�i���i�j���A�q�ɂɐςݏオ��ɂ͑���Ȃ��B�ɒ[�Ɍ����w���������ʂ����������x�Ƃ����l�����ł���B
�@���̂��߂ɂ́AIT����g�����V�X�e�����������A�w�Ƀ[���ɂ��R�X�g���Ɍ��܂ʼn�����x�Ƃ������g�݂ł���B�O���܂ŋ������i�����j�̍l�����A���z�ł���B
�@�������A���q�l�͑҂��Ă���Ȃ��B�~�������ɑ��A��ɓ��ꂽ���B
�s�ǂ͑��A���ւ��Ăق����A�����Ăق����B
�������Ă���Q���A����P�T�Ԃ��҂ĂȂ��B���{�ł͔���Ă���Ԃ͐������҂��Ƃ������Ƃ�����BBRIC�������ł́A���q�l�̗v�]���Ⴄ�̂ł���B
�@����ɑΉ����邽�߂ɂ́A�ʏ�A���ʂŔ����ʈȏ�̏��i�ɂ�C���p���i�ɂ�������x�m�ۂ��A���q�l���璍����s�ǂ̘A��������A���Ή����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������������ł��郁�[�J�͎���ɂ��q�l�̐M�p���������A�u�����h�Ƃ��Ē蒅����B
�@�T���X���͑��C���Ή����s�����ƂƁA���̂��ߍɂɂ��Ă����{���[�J�ƈႤ���g�݂������B
�@�����āA���[�U���s�ǂƊ����Ȃ��A�v��Ȃ�����̕i���͂��q�l���[�����Ďg���Ă���郌�x���Ƃ����悤�ɍl�����B
�@
�@���{�ł́A�w���[�J�����������i�����x���łȂ��Ƃ��߂��x�Ƃ���������������A����ɍ��i����悤�ɐv���A�������Ă����B�������A�g���̂̓��[�U�ł���A�g���l�����̕i���͂��������Ǝv�����ǂ����ł���B
�@����@�̉��ꗎ���̐��\�ƁA���n�̏���͑����̊W�Ȃ邪�A���{�ł͐��n�����܂Ȃ��悤�ɐ����͂������B���ꗎ���͐�܂̐��͂Ƃ̌��ˍ����Ō��܂�B
�@�a�q�h�b�������̐���@�͑傫�ȃp���Z�[�^�Ő����悭�Q�����A�悭���ꂪ���������@�������Ƃ����l�����ł���B����낿���Ƃ��������̐���@�͔ނ�ɂ͕s�Ǖi�Ƃ����f��Ȃ��̂ł���B���{�̐���@�͂���낿��낵�������̂��̂������Ȃ����B�ނ�́A���n�̏��݂͖��ɂ��Ȃ��B
�@
�@����ꏊ���ς��A�l�������傫���ς��B
��������Ȃ��ŁA�w���{���i�͍��i���A���@�\������l�i�������A�����Ă��������͔̂����x�ƍl���Ă������{�̃��[�J�̘��������v�����ɂȂ����B
�傢�ɔ��Ȃ��ׂ��ł���B
�P�O�O�~�V���b�v�ɍs���A����Ȃ��̂܂łP�O�O�~�łł���̂��Ƌ�������鏤�i�������������ł���B���ɂ͔����Ă����ɉ�����̂�����B�ł��A���Ƃ��ƂP�O�O�~������Ƃ�������肪����̂ŁA���Ă��s��������Ȃ��B
�@�P�O�O�~�V���b�v�̏��i�̗�͋ɒ[�Șb�ł��邪�A�T���X����k�f�d�q�͓��{�̉Ɠd���[�J���������āA���̎�_�������ɓ˂������珟�����̂ł���B
�@����Ȃ�A�T���X����k�f�d�q�̎�_�͉�����T���āA������˂����헪�����Ȃ���Δނ�ɏ��ĂȂ��B���{���[�J�͋Z�p�͂ł͒�͂������Ă���B
�ނ�ɖ����āA�䂪���ɂ��鋭�݂����A�����ɏ��Ă�B
�o�����������������͂P�R�N�x����͍����������Ƃ������\���������B
���āA�����������ȂƐ헪�������Ď��g���߂Ɍ��ʂ��o���̂��ǂ����H
�܂��^�₪����B
�ł��A���������[�J�ɕ��A���Ă��炢�����B
|
11��10��(��)
�w�����ĂȂ��x�Ƃ͂ǂ��������ƁH
�@2020�N�A�����I�����s�b�N���v�Ɍ����ăv���[���e�[�V�����ŁA���N���X�e�������{���u�����ĂȂ��v�̐S���X�s�[�`���A�傫�Șb��ƂȂ�܂����B
�@�u���Ȃ��͂����ĂȂ��̐S�������Ă���Ǝv���܂����H�v�Ƃ����A���P�[�g�����̌���
�Ȃ��73���̏�����YES�Ɖ��������ł��B
�@�u���{�l�����́A���E�ň�Ԃ����ĂȂ��̐S������Ǝv���I�v
�@�u�g�߂ȒU�ߗl��Ƒ��ɑ��Ă��A��ɂ����ĂȂ��̐S�������Đڂ��Ă���v
�@�u�T�[�r�X�Ƃœ����Ă��邪�A���q�l�ɂ͏�ɂ����ĂȂ��̐S�������Đڂ��Ă���v
�ȂǁA���㏗�����A���{�l�̔����ł����g�����ĂȂ��h�̐��_���Z�����Ă��邱�Ƃ�
������܂����B
�@���{�ň�������̂ɂƂ��āA�s���͂����C�����Ȃǂ̃T�[�r�X�͓��X������O�̂悤�ɎĂ����܂��B�ǂ��Ή������Ă��炤�ƌ��ȋC�����ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA���R�Ǝ����ł��S������悤�ɂȂ�̂�������܂���B
�w���ĂȂ��̐S�x�Ƃ́A����̗���ɗ����ĐS���܂鉞������̂����_�ł��B
�@�u���ĂȂ��v�ɂ͑��肪�������邱�ƂŁA���ĂȂ�������т�������Ƃ����W������A
�����������݊W�́A�����̂������ʂɂ����Ċ�{�ƂȂ���̂ł��B
�@��l�ЂƂ肪�u���ĂȂ��̐S�v�������čs�����邱�Ƃ��A�L���Ȑl�ԊW�⊈�͂���Љ�Â����i�߂Ă������ƂȂ�܂��B
�@�w���ĂȂ��̐S�x �͉p��ł� �g�z�X�s�^���e�B�h �ƂȂ�܂��B
�@�u�l�Ɋy����ł��炨���v�Ǝv�����S��p���̂���
�@�u�����S���犽�}���悤�v�Ǝv���C�����̂���
�@����ł́A���ĂȂ��̐^���Ƃ��āA���̓��̂��ĂȂ��ɂ��Ē��ׂĂ݂܂����B
�@���̓��������������痘�x�̍�@�Ƃ��āA�w���x�̎������x������܂��B
������w���x�����x�Ƃ������Ă��܂��B
�@��@���͕��̂悫�悤�ɓ_������u����_�Ă鎞�A���l�ɂƂ��Ē��x�ǂ������Ɂv
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̎��E���̏ꏊ�ł̋q�̋C�������@���čs������
�@��@�Y�͓��̂킭�悤�ɒu������u�����E�i���́A�v�ƂȂ�c�{���������āv
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_���ɂ����鏀���̏d�v��������Ă���
�@�O�@�~�͒g���ɉĂ͗����� ����~�͒g��������H�v�����A�ĂȂ炷����╗��ŗ����Ƃ�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̂������Ă��鎨��ڂɂ���ď����ۂƂ͈قȂ��Ԃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������@�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ɂ�鉉�o���l�����u���ĂȂ��́A�����z���S�ŁB
�@�l�@�Ԃ͖�ɂ���悤�Ɂ@�@������̉Ԃ��炢�Ă�����Ԃ�����������p�ɐ����邱��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���̂̕\���́A�{����m��A���Ȍ��ɁB�v
�@�܁@�����͑��߂��@�@�@�@�@�@����u��Ƃ�������čs����S�|���Ȃ����A����S���ۂ���܂��v
�@�Z�@�~�炸�Ƃ��J�̗p���@�@����u������ӂ炸�A���l�ɖ��f��J����������ȁv
�@���@���q�ɐS����@�@�@�@�@�@����u�����ɂ��A�݂��ɑ���̐S���C�����āv
�Ƃ���Ă��܂��B
�@�@�@�@��ω����[�����t�ł�����A���߂ł͐^�ӂ��\���`�����Ă��Ȃ����Ƃ����l�т��܂��B
�@����͗��x���u�����Ƃ͉����v�Ɩ��ꂽ���ɓ����������ƌ����Ă��܂����A
�����ɂ�����l���Y��Ă��܂��Ă����ȋ������l�܂��Ă����悤�Ɏv���܂��B
�@����̐S���Ƃ����u����ɗՂލۂ́A���̋@����ꐶ�Ɉ�x�̂��̂ƐS���āA��q�Ƃ��Ɍ݂��ɐ��ӂ�s�����v�u�o����Ɂv�Ƃ����܂��B���ꂪ�w������x�ł��B
�@����ɁA����ꂽ���A�e�����ԕ��ɂ����Ղȑԓx���Ƃ炸�ɁA��ɐV�N�ŁA���̉���厖�ɂ���Ƃ������Ƃł��B
�@���߂ĉ�����l���C�������Ƃ͓���ɂ����Ă�������O�A�ނ��낻���ł͂Ȃ��e�����l�ɂ������悤�ɋC��z��̂��^�̈Ӗ��ł��傤�B
�@���S�N���`�����Ă����A���̌��t�͉��[��������܂��B
�@����Ƒf���炵����u�����o�����߂ɂ́A����Ɍ}������̂ł͂Ȃ��A������l�P����łȂ��A�����͉����������̂�����������Ă���Ǝv���܂� �B
|
10��28���i���j
JAL�i���q�j���G�A�o�X���w������
�@����̓��o�V���ɁA���{�q���B�q��@���̃G�A�o�X[A350] �̍w�������肵���ƌ����j���[�X���f�ڂ��ꂽ�B2019�N���珇����������B���܂ŁA�č��ւ̔z��������A�@��̑唼�̓{�[�C���O�Ђ��璲�B���Ă����B�������ANA�����l�{�[�C���O�Ђ���@�ނ��w�����AAMNA��B787�����ɂ�������^�s���Ă���B
�@JAL�����܂ł�B777����������g���Ă������A����̌����B777�̌�p�@�I�тŁA�傫�ȏo�����ɂȂ�B
�@JAL�͌��݁AB777�����ې��ƍ������ʼn^�s���Ă���B��p�@�ɂȂ�G�A�o�XA�R�T�O�����l�̉^�s�ɂȂ�B
�@���������͍��ې��̔{�A��q500�l�߂����ڂ��āA�H�c�[�D�y�ȂǒZ������1�����������B���̂��ߋ@�ނɂ͒������ɍł��傫�ȕ��ׂ�������Ռ����傫���B
�@B777��A350�ɔ�ׂčŒ�ł�2-3���͑ϋv���ɗD���ƌ����Ă����B
JAL��A350�ɐ�ւ���ƂȂ�ƁA�ϋv����V���������ɗv���镉�S�Ȃǂ������݁A���R�X�g�ŃG�A�o�X�̓{�[�C���O���s�����ƌ����Ă����B���q�Г��ł����������������L�����Ă����B����Ɋ���e���{�[�C���O�@�ނł̓p�C���b�g�̗{�����y�ɂȂ�B���ꂪ����A350�Ɍ��܂����̂́A�G�A�o�X�Ђ��ϋv���̗�镔����ۏ���Ƃ����D�����o���A���̌��ʃ{�[�C���O��舳�|�I�ɃG�A�o�X���L���ɂȂ����Ƃ������Ƃ��B
�@���̂��Ƃ�i�߂�ꍇ��A���Ƃ�i�߂�ہA�������K������B���̋�������ɏ����Ȃ���Ώ������܂Ƃ܂�Ȃ��A�������ĂȂ��B
�@���̋�������ɕK�������@������B����́A�w�x���`�}�[�N�x�ƁA�w�x�X�g�v���N�e�B�X�x���s�����Ƃ��B�����ΊȒP�Ȃ��Ƃ����A���ꂪ�ȒP�ɂ͂ł��Ȃ��B
�@��ʓI�Ɍ����āA�w�d������������Ώ��Ă�x�ƕ������Ă��Ȃ���A�Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ��̂��A���̓�̂��ƁB
�@���̂��ƌ����ƁA�d���ɂ͉ߋ��̎����Ƃ̂�����݂�A�g�b�v�̉����A�Г��ł͍��܂Ŋ��ꂽ���Ƃ�ւ��悤�Ƃ��Ȃ��A�������������Ȕ����K�������Ă���B
���܂ł̂�����g�����ꂽ�����Ȃǂ��g�������S���҂ɂ͈��S�œs���������B������w�x���`�}�[�N�i��r���́j�x������āA������̕��������ėǂ��Ƃ������_���o�Ă��A�������߂�i�ɂȂ�ƁA�w�x�X�g�v���N�e�B�X�i��Ԃ������m���̗p�����茈�߂邱�Ɓj�x�łȂ����̂�I�Ԃ��Ƃ������B
�@���̌��ʁA��g�d����J���������i���v���悤�ɔ��ꂸ�A�g�b�v�ɂȂꂸ�A���܂��s���Ă���Ԏ�A������Ύ��s��Ƃ������ʂɂȂ�B���ꂪ���ʂ̃p�^�[�����B
�@�����JAL�̃G�A�o�XA350�̌���ɂ͋������B���̌������������q���ȑO�Ȃ�A����(���̖����j�̊�F�����������Ȃ��猈�߂Ă����o�܂�����͂������A����͌����ɂ����������Ƃ��ł���̂��Ƃ������������B
�@�����A��ԋ����Ă���̂́A�������Ă���ANA��������Ȃ��B
�@���ꂪ�ł����̂ɂ́A�̑�Ȃ�l�����o�b�N�ɍT���Ă������炾�B
�����JAL��Z���ԂŌ����ɍČ������l�A���Z���̖��_��A�����B
�@�����͋��Z���𐢊E�ꗬ�̉�ЂɈ�ďグ�A���̂Â���ɂ����Ă͓�Ѝw���͓�����O�A�����O�ꂵ���x���`�}�[�N�����s���A�����ċ��킹�Ă��ǂ�����I�ԁA�����x�X�g�v���N�e�B�X���s���Ă����l�B�����狞�Z���͐L�тĂ����B
�@����̌�����ȑO�̓��q�̑̎��Ȃ�A��ł��Ȃ��������Ƃ�����Ă̂����B
���̌���ŁA����̓��q���ǂ��ς���Ă䂭�̂��y���݂��B
|
9��7���i�y�j
���H�̖������߂Â��܂���
�@�ҏ��������Ă��}�ɗ������Ȃ�A�C����10�x�قlj������ω߂����₷���Ȃ�܂����B
�@�䂪�Ƃ̍؉��́A�L���x�c�A�n�N�T�C������o���A�����Ɉ���Ă��܂��B
����̓_�C�R���ƐԁE���̃J�u���̎펪�������܂����B
�@�����̏H��̉�ɖ�A�邪�����Y�ݕt���āA���̗c�������肵����̐c�̐����_��H���r�炵�A���������������c���_���ɂȂ��Ă��܂���Q�ō����Ă��܂��B
�@�����ŁA�ŋ߂͉肪�o��Ƃ����ɖԂ�킹�A�邪����Ȃ��悤�ȑ�����Ă��܂��B
����Ȗʓ|�Ȏ�Ԃ������Ȃ���A�Ȃ��Ȃ���������ł��Ȃ��Ȃ�܂����B
�@
�@���āA���N�̒��H�̖�����9��19���i�ؗj���j�ɂȂ�܂��B
�@�w������A�r������Ė��������x�Ƃ��������m�Ԃ̖��傪����܂��B
����́u���H�̖����߂Ȃ���A�r�̎��������Ă���ƁA���̊Ԃɂ��邪�����Ă��܂����v�Ƃ����Ӗ��ł��B
�@����قǁA���H�̌����Y��ŁA�҂��ł���Ă����Ƃ������Ƃł��傤�B
�@���ꂪ�^�Ă̌��ł͏��������A���������C�łڂ���Ƃ��Ă��āA���͂ɂ͉Ⴊ�u���u������Ă��āA�������ł�Ƃ����ł͂���܂���B
�@�H�̖�͋C�������傤�ǔ��ɍ����A������Ȃ��Ȃ�A��C�͐���ŁA����Y��Ȍ���������ł���I�@���ꂪ���H�̖����ł��B
�@������A�^�Ӗ앓���̋�ɁA�w�̉Ԃ�A���͓��ɁA���͐��Ɂx�Ƃ����傪����܂��B
��������z�����ɒ��ލ��A�������̋�ɏo��^�C�~���O�͖����̍��������ł��B�G�߂͍̉Ԃ�A�ƂȂ��Ă��܂����珉�Ăł��傤���B
�@���������w�������ł�x�Ƃ����C�����́A���{�l�Ɠ��̂��̂��Ǝv���Ă��܂����B
�����A���ׂĂ݂�ƁA����͒����́w�A�z���x���炫�Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ�������܂����B
�@�w�A�z���x�Ƃ́A�F���A�����͉A�i�}�C�i�X�j�Ɨz�i�v���X�j�Ƃ̑g�ݍ��킹���琬�藧���Ă���B���̕ϓ]�́A�A�A�y�A���A���̌܌��f�Ɋ�Â��Đ��i�����Ƃ������R�N�w�܂��͎��R�Ȋw�œ��m�I�Ȑl���ς␢�E�ςɑ傫�ȉe����^�����Ƃ������̂ł��B
�@���{�ɂ͐��ÓV�c10�N�i602�N�j�ɓ`������Ƃ���Ă��܂��B
�@
�@�z�͑��z�ŁA����̎n�܂�͓��̏o�A���V���l��q�݁A��������̌��N��K���△�����F��A�[���ɂ͂����l�Ɋ��ӂ���Ƃ����F���̂̐l�͍s���Ă��܂����B
�@����͎q���̍��A���ꂪ�F���Ă����̂����Ċo���Ă��܂��B
�@���͒��̃��W�I�̑����炢�͂��܂����A�����l�Ɍ������ċF�����������l�͂��Ȃ��ł��傤���E�E�B
�@�����āA�̂̐l�͖�͂����l�����łāA�S���x�߂�Ƃ���������J��Ԃ��Ă��܂����B
������A��ɏЉ���悤�Ȗ��傪���܂�܂����B
�@����͒�����؍�����{�ȂǁA�w�A�z���x�ɉe���������Ō����邱�Ƃł�
���m�����ł́A�L���X�g����C�X�������̂悤�Ɉ�_���ł���A�_�͐�ł���A����ȊO�͔F�߂Ȃ��Ƃ����l�����ł��B�A�z���̗z�͔F�߂邪�A�A�͔F�߂Ȃ��Ƃ����l�����ɂȂ�܂��B
�@�ނ�͔��͔F�߂邪�A���͔F�߂Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B������ނ�ɂ̓O���[�͑��݂��Ȃ��̂ł��B�O���[�͔������̂ǂ��炩�ɂȂ�܂��B
�@���{�l�͐����ɂ͂��{�ɏ��w�ɎQ��܂��B���~��ފ݂ɂ͂����₨��ɎQ��܂��B���������_�l�A���l�����̂��߂炢���Ȃ����R�Ɏ���邱�Ƃ��ł��܂��B
�@���̗D�_�s�f���́A���{�l�Ɠ��̂��̂��Ǝv���Ă��܂������A���͂���͒����l��؍��l�ɂ����ʂ���v�l�̂悤�ł��B���̍����͒�������`������w�A�z���x�ɂ������̂ł��B
�@���{�l�͉A�z����Ǝ��̉��߂◝���ɂ�肳��ɔ��W�����A���{�l�̐S�̒��ɐ�����悤�ɂȂ�܂����B������A�傫�Ȏv�z�I�e���́w�x�ł��B
�@����4000�N�̗��j�͑�Ϗd�����̂��������Ƃ������Ƃł��B
�@
�@���s�ł́A���H�̖����Ɉ���Ŋe�n�ł����ȍÂ����J����܂��̂ŁA����s���Č��ĉ������B�ڂ����͉��L�̃z�[���y�[�W�łǂ����B
�@http://souda-kyoto.jp/tsuki/
|
�W���P�W���i���j
���{�̉Ɠd���[�J�̖v���ƁA�����ԃ��[�J�̌����Ȃ킯
�@���Ă͓��{�̑�\�I�ȎY�ƂŁA���E�ɖ���h���A�ՐɌ������Ɠd���[�J���������Ėv�����A�����̎��̊�@��A���v�̈�����A�Ԏ��ɔY�܂���Ă���B
�@����œ������{�̎����ԃ��[�J�͗��X�Ǝ��Ƃ��g�債�A�g���^�͐��E��̐��Y�ʂ��ւ�A�z���_�A���Y�}�c�_�ȂNJe�Ђ������Ɏ��Ƃ��g�債�Ă���B
�@���������Ƃł���Ȃ���A�����Ⴄ�̂����ȑO���牽��ƂȂ��G��Ă����B����͏���������p�x����l���Ă݂����B
�@
�@�Ɠd���i�̃J�^���O�ƁA���Ɨp�Ԃ̃J�^���O���J���Ă݂悤�B
�@�Ԃ̃J�^���O�́A�t�B�b�g�Ȃ�t�B�b�g�Ƃ����Ԃ��Љ��̂ɁA��{�ɂȂ�x�[�X�O���[�h���ǂ��������\��@�\�ɂȂ��Ă��邩�ڍׂɐ������Ă���B���̏�Ŋ�{�ԂɃv���X���āA�����ȕt���@�\���t���āA�l�i�͂��ꂱ��Ƃ����W�J������Ă���B
���Ƃ��A�P�R�O�O�b�b�̊�{�Ԃ͂P�Q�O���~�A�P�T�O�O�b�b�̊�{�Ԃ͂P�S�O���~�A����ɃJ�[�i�r�A�A���~�z�C�[���A�T�C�h�G�A�o�b�N�A�M��z���K���X�A��\��V�[�g�A�J�[�I�[�f�B�I�A�d�s�b�ȂǂȂǂ����Ȃ��̂�t����Ƃ����炢����Ƃ����\���ɂȂ��Ă���B
�@����v���X�\���ɂȂ��Ă���B
���q����͎��R�Ɏ����̍D���ȃO���[�h���`���C�X�ł���B
�@����ɔ�ׂāA�Ɠd���[�J�̏��i�J�^���O�́A��ԍ����O���[�h���i���Љ�A�����������t���Ă��邱�Ƃ�����ɑi���Ă���B�����āA����Ȃ��A����Ȃ��ł͂����Ȃ�܂��ƃh���h���O���[�h�������ė����ł̏��i���Љ��B
�@����}�C�i�X�\���ł���B
�@��ԗ����ł̏��i�́A���\���������ȋC�����āA�����̂��S�O����悤�ȑi�����ɂȂ��Ă���B��Ԉ�����{�O���[�h���i�ŏ\���ł���B
�@�ł��A�ŐV�̐V�����Z�p��t�������i�͍����ł����A�������������b�g������܂���A�Ƃ����\���łȂ���Ȃ�Ȃ��B
�@��Ԉ�����{�O���[�h�̏��i��O�ꂵ�Ĉ�������A���E���Ő킦�鉿�i�ɐ������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���ꂪ�O���[�o������̂��̂Â��肾�Ǝv���B
�@���Ƃ��A�G�A�R�������Ă݂悤�B
�l�b�g������ԕt�A���|�����{�b�g�t�A�l���Z���T�[�t�A�C�I���E�L�t�A���̑��E�E�E�t�łP�T���~�A������g�[�\�͂̃x�[�X�ɂȂ鏤�i�͂V���~�Ƃ��������ɂȂ��Ă���B
�@�����ȕt�����l��t���āA�������i�낤�Ɩ�N�ɂȂ��Ă���悤�Ɍ�����B
���̊J���̂��߂ɁA��������̋Z�p�҂������A�܂��܂��l��������ށB
�@�ԂƉƓd���i�̂��̏��i�i����W�J�̎d���̈Ⴂ���C�ɂȂ�B
�@���{�l�͍����i����A�����\�A���@�\�A���@�\�̏��i�Ȃ班�X�����Ă��������̂��Ƃ����Ǝ��̐��Ȃ�����B�@��������{���̏��i�͕i�����ǂ����\���ǂ��Ȃ����Ƃ�������B
�@�܂��A���{���L���ɂȂ�A���������������Ȃ��Ă��邩�獂�����̂ł������B
�������ł���A���[�J�œ����l�̐l������������Ƃ��Ӗ�����B
�@���[�J�͍����l����ł����x���������߂ɂ́A�ł��邾���t�����l�̍������i��̔��������B���������v�f�ō��܂ł���Ă����B
�@�������A���{�̍����̎��v�͂�����Ɠd���i�͍s���n������O�a���Ă���B
��͔����ւ����v�����S�ɂȂ�B
�@�����āA���{�̍ő�̗A�o��̃A�����J�����l�ȏ�ԂɂȂ��Ă���B�܂�s��͐��n�����Ă���B
�@�A�����J�͂��łɓ��{�̃��m�Â���ɔs��āA���ł�20�N�ȏ�����B�A�����J�̐����Ƃ͂��łɕ��Ă���B���������̒��ŁA�A�����J�l�̕��ϔN���̓h���h��������A���{�ƕς��Ȃ��Ȃ��Ă���B���������{���ǂ�ǂ������B
�@�A�����J�l�͂��Ƃ��ƍ�����`�̐l�X�ł���B�ނ�́A�w���i�͂��̖ړI���ʂ����Έ������������x�Ƃ����l�����������Ă���B
���Ƃ��A�X�`�[���A�C�����Ȃ�A�v�������茳�C�悭��ʂ̃X�`�[�������o���āA���[���Ǝ�ۂ悭�A�C�����|���ł�������B���ꂪ�ނ炪�]�ރX�`�[���A�C�����ł���B���̉��i�͂R�O���ȉ��ł���B�R�[�h�̗L�薳���͊W�Ȃ��B
�@����ɑ��āA���{�̃R�[�h���X�A�C�����͂P�T�O���`�Q�O�O��������B�������X�`�[���͂���낿���Ƃ����o�Ȃ��B�w����ȃ`�~�`�~�������i�̓X�`�[���A�C�����ł͂Ȃ��x�Ƃ����b��20�N���O�ɕ��������Ƃ�����B
�@���ׂĂ̏��i�ɂ��āA�ނ�͂����������o�������Ă���B
�@
�@���{�����s����i���ŗA�o�悾�����A�����J�s���[���b�p�s�ꂪ�O�a���A�����ւ����v�����S�ƂȂ钆�ŁA�Ɠd���[�J�͓K�ȑΉ������Ȃ������̂��s���ł���B
�@��i����ɓ��{�����ɊJ���������t�����l���i��ׂ�������ėA�o���Ă����B
���̂Â���̊�{�����t�����l�ɂ���̂�����A�x�[�X�ɂȂ鉿�i�͍����B
�@����ŁA�؍��A�������[�J�͐V�����ő䓪���Ă������X�ɁA��{�@�\���������葢�肱���i��O�ꂵ�Ĉ����A�o���Ă����B����Ɍ��n�̗v�]�ɍ��킹�����̂Â���������B
�@���Ƃ��A�G�A�R���͗�[�����A�K���K����₷�Ƃ������ƂɓO�����B����Ȃ���{�̉��\�N�O�̂��̂Â���ł���B�Z�p�͍ŐV�̂��̂��g���̂ŁA�������i���Ȃ��̂��ł���B
�@�V�����͔N�����Ⴂ�̂ŁA�ނ�̔�����͈͂̒l�t���ɐ������Ȃ���Δ���Ȃ��B
���{���͂������Ƃ͕������Ă��邪�A�������Ȃ��l�i�Ŏ肪�o�Ȃ��A��������Ȃ��B
�����������s����葱�������ʁA�T���X����k�f�d�q�ɕ����Ă��܂����B
���{�̉Ɠd���[�J�͋Z�p�͂ŋ������̂ł͂Ȃ��B
������Ƃ����v���オ�肪�A�w���̂��Ĕ̔����ĉ��ڂ̐��E�ł���I�Ƃ��������̌��_���������������x�̂��ƁB
����ɋC�Â��Ď��g�߂A�K���Đ��ł���B
�@�����肷��K�v�͂Ȃ����A���n�̗v�]�A���q����̗v�]�ɍ������i����邱�Ƃɐs����B
�@�܂��A���̏��i�̊�{�O���[�h�̌����}��A�@�\�A���\�A�i���ɂ͂�����肢�����̂�B���̏�ŁA���i�����q�l�̗v�]�ɍ��킹��悤��Ƒ̎���ς���B
���ꂪ�ł���ΐ����ԈႢ�Ȃ��B
�Z�p�̖��ł͂Ȃ��B
�����K�V���n�Ǝ҂͂������������Ă����B��������̊Ԃɂ��Y��Ă���B
|
�W���P�V���i�y�j
�l�̋Z�i�킴�j�ƃR���s���[�^�����̍�
�@���N������A���s�R�̑�����߂��āA���̍�����H�̋C�z��������G�߂ɂȂ邪�A�ǂ������N�͂܂��W����t�͂��̏����������悤���B
�@�ŋ߁A�e��Ƃ̓Z�L�����e�B�̋�����ŁA�₽��Ɠ��傪�������Ȃ��Ă���B
�@�o������������������K��悤�Ƃ��Ă��A�n�a�ł���A�Ȃ��Ȃ����傪�ł��Ȃ��B
���O�ɐ\�����݂��A�������Ȃ��Ɠ��傪�ł��Ȃ��B����ُ͈�Ƃ��������悤���Ȃ��B
�@�Ȃ��A���̂悤�Ȃ��ƂɂȂ����̂��H�@
�v��������͂��B����������l���Ă݂�B
�@�Z�L�����e�B�[�Ǘ��͉�Ђ̋@����O���ɘR��Ȃ��悤�ɁA�����ȑ鎖�ł��邪�A�w�O���ɏ�R���x�Ƃ������Ƃ��Ȃ��N����̂��H�@���l��������B
�@�R���s���[�^���E��Ƀ`���z����������A�܂��d���ɏ\�����p����Ă��Ȃ��������̓Z�L�����e�B�Ƃ������t���Ȃ������B
�@�������A���A�ǂ̐E������Ă��A�e�l�̊��̏�ɃR���s���[�^������A�f�B�X�v���C�Ɍ������ăL�[�{�[�h���������Ă���B
�@���[�h�Ń��|�[�g���쐬���Ă���l�A�G�N�Z���Ŕ���グ�v�Z���Ă���l�A�p���[�|�C���g�Ŕ��\��̎���������Ă���l�ȂǁA���ꂼ��̎d���ɂP�O�O���R���s���[�^���g���Ďd�������Ă���B
�@���A�P�O�N�قǑO�܂ł́A�܂��S�����R���s���[�^���g���Ƃ���܂ł͍s���Ă��Ȃ������B���ꂪ�����Ƃ����ԂɍL����A����R���s���[�^���Ȃ���Ύd�����o���Ȃ��܂łɂȂ��Ă���B
�@����̓R���s���[�^���g�����ƂŁA�d���������A���m�ɂł��邩��ł���B
�@�d�q���[���̓t�@�b�N�X�𗽉킵�A�L�^���c�����߂ɍ����t�@�b�N�X���g�����Ƃ����邪�A�قƂ�ǂ̘A����ʐM�͓d�q���[���ɑ������B
�@�Ȃ��A����قǑ����ʐM�̎�i���������̂��H
����͒ʐM�̑����ƁA�`���������e����₷�����m�ɑ���悤�ɂȂ�������ł���B
�̂���ʐM�̎�i�͂����ȕ��@���������B
�@�E�吺�ŋ���œ`����B
�@�E�̂낵���グ��B
�@�E��r�𑖂点��B
�@�E�`���������B
�@�@�ȏ�͖������炢�܂ŁA���̌�A
�@�E���[���X�M���i�g���c�[�j�ŕ����𑗐M�A��M����B
�Ƃ����悤�ȕ��@�Ői�����Ă����B
  ���[���X�M���𑗂邽�߂̓d���i�L�[�j ���[���X�M���𑗂邽�߂̓d���i�L�[�j
���͐Ԃ����������E�ɐU���Ďg�����u���L�[
�E�͍����������㉺�ɐU���Ďg���c�u���L�[
�@���ł��d�M�i�g���c�[�j�͗L�����肩�A�����ő��邱�Ƃɐ������A����I�ȒʐM��i�Ƃ��čL�������B
��ꎟ���A����ł͐���Ɏg��ꂽ�B
�@���̃g���c�[�̓d�M�́A�v�����̐l�łP���ԂɂP�Q�O��������P�T�O�����̑��M�܂��͎�M�����x�B�������W�����Ă���Ă��̒��x�ł���B���X�R�O�����炢���������Ȃ��B����ƌ뎚��������B�����ʖ�̐l�Ɠ��l�Ȋ��o��������Ȃ��B
�@�A�}�`���A�����̃��x���ł͂P���ԂɂU�O��������P�O�O�������x�ɂȂ�B���ꂪ�l�Ԃ̎��ŕ����A��őł��E�̑��x�ł���B
�@�Ƃ���ŁA�R���s���[�^�͂ǂ�قǂ̑����ő��M�܂��͎�M���ł���̂��낤���H
�@�f�W�^���ʐM�ł́A�r�b�g�Ƃ����P�ʂ��g���Ă���B���ꂪ���̍ŏ��P�ʂŁA�O���P�����蓖�Ă��Ă���B�R�C���𓊂��ė��A�\�Ă�̂Ɠ��l�ŁA�\���P�A�����O�ƍl���Ă������B�O���P�̂ǂ��炩�ł���B������P�r�b�g�ƌĂ�ł���B
�@�P�r�b�g�͂O���P�A�@�Q�ʂ��\���ł���B
�@�Q�r�b�g�́A�O�O�C�O�P�C�P�O�C�P�P�̂S�ʂ��\���ł���B
�@�W�r�b�g�́A�Q�T�U�ʂ�̕\�����ł���B
�P������\������̂��W�r�b�g�����蓖�Ă�̂���ʓI�ɂȂ��Ă���B
������P���[�h�ƌĂ���P�o�C�g�i�P�a�j�Ƃ����B
������P�����͂P���[�h�ł���A�P���[�h�͂W�r�b�g�ł���A�P�o�C�g�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�ŋ߁A���ʂ����G�ɂȂ��Ă����̂ŁA�W�r�b�g����P�U�r�b�g�A�U�S�r�b�g�Ƃ����V�X�e�������邪�A��{�ɂȂ��Ă���̂͂P���[�h�W�r�b�g�ł���B
�@���[���X�M���ɖ߂��čl����ƁA�v���ʐM�m�����M���M�ł��鑬�x���P���ԂɂP�Q�O�����Ƃ���Ȃ�A�P�b�ԂɂQ�����ƂȂ�B�P�����̂W�r�b�g�����蓖�Ă��Ă���̂ŁA�P�����͂P�U�r�b�g�ł���A������P�U�������i�r�b�g�E�p�[�E�Z�J���h�j�ƌĂԁB
�l�Ԃ̎����ő���M�ł��鑬�x�͂P�U�����������x�ɂȂ��B
�@�Ƃ��낪�A������f�W�^���ʐM�ɒu��������Ƃǂ����������ɂȂ邩�H���l���Ă݂�B
�C�I�l�b�g�Ȃǂ̌�����͈�ʂł��P�O�O�l�������A�ŋ߂͍����̂P�f������������g���o���Ă���B
�@�P�O�O�l������������g�����ƍl����ƁA�P�l���������P000�L�����������P�S��������������P�O�O�l�������͂��̂P�O�O�{�A���Ȃ킿�A�P�O�O�l���������P���������ƂȂ�B
�@���̉���ŁA�P�����i�P���[�h=�W�r�b�g�j�𑗐M�A�܂��͎�M�����Ƃ���ƁA�v�Z�ł͂P�Q�T���������킸���P�b�ő��M�܂��͎�M�ł��邱�ƂɂȂ�B
���[���X�����ɂ��ʐM�ł́A�P�b�ԂɂQ�������������̂��A���݂̃f�W�^���ʐM�ł͂P�Q�T�������A�i���ۂ͂��̔������炢�ɂȂ�j�����M�A��M�ł���̂ł���B
���������̔�r�ɂ����ẮA�R�O���{����U�O���{�̑��x�ƌ�����B
���ꂪ�����̉�X�̐����ɑg�ݍ��܂�ē����o���Ă���̂ł���B
�g�̉��Ŏg���Ă��鏤�i�̓`�����x�i�ʐM�̑����܂��͏��ʁj�̗��������ƁA
�@�@�E���y�b�c�́A�P�D�Q�l������
�@�@�E�f�W�J���̎ʐ^�@�P���́A�R�l�a�ʁi�����דx�Łj
�@�@�E�z�[���y�[�W�Ȃǂ̎ʐ^�@�P���͂T�O���a
�@�@�E�n�f�W�e���r�́A�P�U�D�W�l������
�@�@�E�����Z�O�e���r�́A�S�P�U�j������
�@�@�E�P�C�^�C�̓p�P�b�g�Ƃ����\�����g���Ă���B
�@�@�@�@�P�p�P�b�g���P�Q�W�a�i�o�C�g�j
�@�@�@�@�S�p�P�������Q�a�i�o�C�g�j
�@�@�@�@������A�P�p�P�b�g=�U�S�����@�ɑ�������B
�@�@�@�@�P�p�P�b�g�i�S�p�U�S�����j������O�D�R�~�̔�p�ɂȂ�B
�@�����A�����Ɉ�ꂽ���A�f�W�^���Z�p�̐i���ŁA����ȏ�����Ƃ����Ԃɓ`�����ꂽ��A�r�c�J�[�h��t�r�a�ɋL�^�����B�������������Ȃ��̂̒��ɖc��ȋ@������������̂ŁA��Ђ̓Z�L�����e�B���������Ǘ����邱�Ƃ��K�v�ɂȂ����̂ł���B
�@����ŁA�J���ꂽ��ƂƂ����C���[�W�͑�Ȃ��ƁB
�e���݂̂���I�[�v���ȉ�Ђ͂��ꂩ�狁�߂��A����������Ђ��L�т�悤�ȋC������B
|
�W���P�T���i�j
�I��L�O���ɓ�����
�@�����͑�U�W��̏I��L�O���ł��B�@���߂ɓ��{�����قœV�c�A�c�@���É��l���}���āA�L�O���T������ɍs���A�m�g�j�e���r���p����Ă��܂����B
�@���S���l�Ƃ������������]���ɂ�����̑�킩��U�W�N���}�����킯�ł��B
�@�ǂ��������R���������ɂ���푈�ƌ�����i�ʼn����ł��邱�Ƃ͂���܂���B�����Ă������Ă��o���ɑ傫�ȋ]���������܂��B
�@���{������A��̑��ŏ����Ă����Ȃ�A������͂ǂ��Ȃ��Ă����ł��傤���B
���̐�����莩�R�ŁA�L���ŁA��]���鐶�����ł���ƍl����l�͏��Ȃ��Ǝv���܂��B�@
�@���{�͕����܂������A���̐����̖L����������ł���̂͂�������̋]���̂��Ƃɐ��藧���Ă��܂��B����͕�����Ȃ������ł��B
�@�Ƃ���ŁA������؍����獡�Ȃ��A�������A������ɓ��{�̐펞���̔؍s�H�ɂ��ĐӔC��Ӎ߂�v�����ė��܂��B����͂܂��܂��G�X�J���[�g���Ă���悤�ɂ��v���܂��B��ʁA�싞�ɍs�������Ɂw���{�R�ɂ��R�O���l��s�E�I�x�Ƃ����Ŕ�����A���{�̊�t�Ō��Ă�ꂽ���h�ȁw�푈�L�O�فx������A���������w�ł����B
�@���̏ꏊ�ɒ����̏����w�������j�̕��ɂ䂫�A�����{�R�̔؍s�����炵�Ă���B�؍��ł����l�ȗ��j�̋�������Ă���B
�@���̗��j�̓��e���{���ɐ��������j�̐^���ɗ����̂ł���A����͗��j�𐳂����m��Ƃ����_�ő�ȋ���ł���B�������A���낢��ȉߋ��̏o�����𑼂̖ړI�̂��߂ɗ��j��Ԃ��Ďg���Ă���̂ł���A���������������������؍��̎�҂͓��{�ɑ��āA���܂ł�������l�������������邱�ƂɂȂ�B
�@���܂Ȃ��A�����邲�ƂɁA�ނ�ɂ�锽���f�����J��L�����A���X��H�ꂪ�j��Ă���B��ʂ̒����̃f���ŁA�������Ə����K�V���n�Ǝ҂����߂Ď�����荇�������̔��W�̑b�ƂȂ������������d��̍H����A�����̏]�ƈ����j���������������B����Ȃǂ͒ʏ�l�����Ȃ��s���ł���B
�@���݂��ɐ������j�����m�F�������Ȃ���A�����̗F�D���W�̂��߂ɁA���݂��̍��̎q�������ɐ��������炪����Ȃ���A���܂ł����l�Ȃ��Ƃ��J��Ԃ����B
���{�͑������̂��ƂɋC�Â��A�����Ɗ؍��̎�]�Ƙb���������Ƃ��d�v���Ǝv���B���ꂪ�����Ԃ̐헪�I�F�D�W�ɂȂ���B
�@�I��L�O���ɑ�����t���������_���ɎQ�q���邱�Ƃ��Ȃ��A�����̂��H
���̑�����t�����Q�q���A��v�҂��ԗ삷�邱�Ƃ��Ȃ��A���߂Ȃ̂��H
���������_���ɂ���Ƃ����̂ł��傤�H �@��v�҂��ԗ삷��s�����C�O����Ƃ₩��������؍����͂Ȃ��Ǝv���܂��B �@��v�҂��ԗ삷��s�����C�O����Ƃ₩��������؍����͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�ނ�͂��������̂��Ƃ���Ă��܂��B
�@
�@���{���ߋ��ɂ���Ă����Ƃ���钆����؍��ł̔؍s�������Ȃ��Ƃ������Ƃ��O��ɂ���܂��B�������A���̂��ƂƖ����_�Ђֈԗ�̂��߂̎Q�q���邱�ƂƁA�ǂ����ѕt���̂��悭������܂���B
�@���������^��������Ă��܂�����A�e���r�Łw�璹������v�ҕ扑�x�Ƃ����{�݂����邱�Ƃ�m��܂����B���a�R�S�N�i�P�O�T�X�N�j�ɍ����扑�Ƃ��Č��݂������̂ŁA��v�҂̂��⍜������ �扑�Ƃ������Ƃł��B����A�w������m�̕�x�ł��B �扑�Ƃ������Ƃł��B����A�w������m�̕�x�ł��B
�@�C�O���s������ƁA�e���Ɂw������m�̕�x������A�悭�c�A�[�ŗ������܂��B���������ꏊ�͌����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������ł��B
�@�����͉q���������A�������Ă���h�i�ȕ��͋C�̕Y���ꏊ�ł��B��ʂ��M���V���ɍs���܂������A�A�e�l�̖�����m�̕�������܂����B���傤�ljq������シ�鎞�Ԃ������̂ŁA��������̐l�����ɍs���Ă��܂����B
�@�������C�y�ɁA���̂��߂ɐ��ŖS���Ȃ�������q�ނ��Ƃ͓�����O�ł��B
�@�����������z���炷��A�w�����_���x�͉����ʂ̈�������͋C�������܂��B
���ꂪ�������{�Ɠ��̋C�����ǂ����悭������܂���B
�@�����_�Ђɂ͂���͂���܂���B��v�҂̌��i�p���j���J��ꏊ�ɂȂ��Ă��܂��B
�@
�@�����_�Ђ͕�C�푈�̍�����̐펀�҂��J���Ă���Ƃ������Ƃł�����A�����A�吳�A���a��3��ɂ킽��A�����ېV�̍����̐푈�̉p���A�����E���I�푈��A��ꎟ���E����A��̑����m�푈�Ȃǂ̌R�l�i�p��j���J���Ă��܂��B�����ɈȑO�͓V�c�É������Q�肳��Ă��܂����B
�@�����ʼnp��Ə����܂������A�J���Ă�����X���w�p���x�ƌĂԂ̂������ł��B
�@������؍����炷��A�����{�R����`�̏ے��������Ɍ�����̂�������܂���B���݂̓��{�ɂ͑S���W���Ȃ��Ǝv���܂����A�R����`����������Ă���̂�������܂���B����͒��ڕ����Ă݂Ȃ��ƕ�����܂���B
�@���������S�z�͌��݂̓��{�ɂ͑S���Ȃ��Ƃ������Ƃ��������Ă��Ȃ���A�ނ炪���������邱�Ƃɉ����Ӌ`�������܂��B�ނ炪�����̕s�������O�ɖڂ�������{��Ƃ��v���܂��B�����Ɠ��{�̐����Ƃ͕��������āA�b���������邱�Ƃ��K�v���Ɗ����܂��B
�@�^����������͖̂����_�Ђ�����̂ɁA�Ȃ��璹������v�ҕ扑������̂��H
�悭������܂���ł����B
�@���L�̋L����ǂ�ŁA�����_�ЂƂ͕ʂ��Ƃ������Ƃł����A��v�҂��d��������Ƃ����ӂ��Ɍ����܂��B������m�ł��낤���L�͎҂ł��낤���A���Ƃ̂��߂ɐ킢�S���Ȃ������͕������J�邱�Ƃ��ԗ�ł��B�펀����I�ʂ����͍̂��������Ƃł��B
�@�����A���̑������b��A�e�E�̑�\�҂��A��v�҂̈⑰���A��ʂ̍������A�C�O�̂u�h�o���A�C�w���s�����A�C�O����̊ό��q���A���ł����Q��ł��邻���������𐮂��邱�Ƃ��d�v���Ǝv���܂��B
�@�璹������v�ҕ扑�ɂ��āA���L�̂悤�ȋL�����l�b�g��Ɍf�ڂ���Ă��܂��̂ŏЉ�܂��B
�@++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
�@�w�璹�P����v�ҕ扑�x�͍��̐����Ƃ��ē��{�͂��Ƃ��C�O����������̕��̎Q�q���ς��܂���B��ʎQ�q�̑��A���ƓI�s�����n�ߐ�F��A�⑰��A�@���c�̓��ɂ��N�Ԃ�ʂ��Đ�v�҂ɑ���ԗ�̐���������^�s�����s���Ă���܂��B
��i�̐璹�����̍��̎����A7���̂��~�A8���I��L�O���A�t�A�H�̂��ފ݂ȂǓ��ɂ�������̕����Q�q����܂��B
�@�w�璹������v�ҕ扑�i������m�̕�j�́A�R�l�R���݂̂Ȃ炸��ʖM�l�����܂݁A�܂����Ɉ⍜�̈ꕔ���⑰�ɓn���ꂽ�l�X�����܂ޑS��v�҂̏ے��I�⍜���������A�����̂���ł���܂��B�킪���ɂ͖����ȗ��A�w�����_�Ёx������܂����A�I���A�@���@�l�ƂȂ�A�O���̌����g�ߓ����A����Ɍw�ł邱�Ƃ��ނ��������Ȃ�A���O���̖�����m�̕�ɗނ�����̂�������̂Ō��Ă邱�ƂɂȂ�E�E�E�v�ƁB
�@�ł͐璹������v�ҕ扑�̂������͂ǂ��������̂��B���ɂ��̌o�߂��ӂ�Ԃ��Ă݂悤�B
���[�������Ȃ̖����̒��ɂ́A�x�ߎ��ψȗ��⑰�̔���Ȃ��⍜�������u����Ă������A���a25�N1��9���A�䓇�̐�v��4822���̈⍜���ČR�ɂ�著�҂��ꂽ�̂��_�@�ɁA���ŕ������Ĕ[�����悤�Ƃ̍l�������܂����B
�@28�N9��26���������ȁA�����ȁA���t�@���ǂ�������c���J���A��v�҂̕�����ɂ����đ��c����ꍇ�̖��_�i���Ɍ��@��j�ɂ��Č��������A���ʂ́u�x��Ȃ��v�Ƃ̌��_�ł������B
28�N10��6���������Ȃ͈⍜���Ɋ֘A�̐[���c�̂������A���ŕ����邱�Ƃɂ��Ĉӌ������B���ʂ͑S�c�̎^���ł��������A��ԊW�̐[�������_�Ђ�������Ă��Ȃ����Ƃ��w�E����A�����_�Ђ̈ӌ����K�v���q�ׂ�ꂽ�B
28�N11��18�����O���ɋL�����֘A�c�̂̑�2�����J����A���x�͖����_�Ђ�����r�c���{�i���o�Ȃ����B
�r�c���{�i�͎��̓_�������ȉ���ǒ��Ɏ������B
��F�扑�͈����⑰�̔���Ȃ��⍜��[�߂邽�߂ɍ����̂����A�����S�̂̏ہ@�@���I��Ƃ���悤�Ȃ��ƂɂȂ�ƁA�����_�ЂƏd�����邱�ƂɂȂ��ď�����������@�@�@�̂ł͂Ȃ����B
���F�S�̂̏ے��Ƃ���l���͂Ȃ��B
��F���̂��u������v�҂̕�v�ƂȂ�悤�����A����͍����ɃA�����J�̃A�[�����g����n�@�@��A�z�����A�S��v�҂��\�����Ƃ�����ۂ�^����̂ł͂Ȃ����B
�@�@���������ꂪ�����̕�n�ł��邩��A���ݎ��@�l�ƂȂ��Ă�������_�Ђɑ����́@�@�@�Ƃ����悤�ȁA�����̌������������͂Ȃ����B
���F���͖̂������̂�����A����[���ɍl�����Č��肷��B
��F��͏@���{�݂ł͂Ȃ��̂��B��������ō�邱�Ƃ͌��@�ɒ�G���Ȃ����B
���F��͏@���{�݂ł͂Ȃ��B���̏؋��ɏ��ǂ��Ⴄ�B
�@�@(��͌����ȁA�@���{�݂͕�����)
�ȏ�̂悤�Ȍo�߂���������A���a28�N12��11���A������b���u������v�҂̕�v
�Ɋւ��錏���t�c�ɕ���A�t�c�Ō��肳�ꂽ�B
�扑�̐��i
���{��28�N1���A���͂��߂ă}���A�i�����Ȃǒ��������m�y�уA�b�c���̈⍜���W�����{�������A���̑��̎�v�퓬�n��ɂ��Ă��A�W���̗�����������n���蒀�����{�Ɉڂ��v��ł������B�����̎��W�⍜�̂����A�g�����������Ȃ����̂��߈⑰�Ɉ����n�����Ƃ��ł��Ȃ����́A����ь��Ɍ����ȓ��ʼn����u���̈⍜�ŁA�⑰�Ɉ����n�����Ƃ̂ł��Ȃ����̂̔[���̂��߂́u��v���������悤�Ƃ����̂ł���B
�������A�u��v�̌������̂ɂ��Ă͈Ӌ`�������͂��ޗ]�n�͂Ȃ����A���̖��́A�����ꏊ�ɂ��ẮA�u��v�̐��i���߂����ďd��Ȗ������Ă����B
���Ȃ킿�A�����_�Ђ͏]����v�҂݂̂��܂��܂�Ƃ���Ƃ��č����̑����̒��S�ɂȂ��Ă������A�V���Ɍ��݂����u��v�̂�����ɂ���ẮA�����A��v�҈ԗ�Ɋւ��鍑���̊ϔO���A������邨���ꂪ����̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł���B
�@���̓_�ɂ��Đ��{�́A���́u���������v�� �u�����_�Ђ͑S��v�҂́u��v���J����̂ł���̂ɔ����A�u��v�͓��ʂ̎���ɂ���⍜��[�߂�{�݂ł����̂ŁA���҂̐��i�͂��̂�����قȂ�A���҂͊ϔO����A���̂���G������̂ł͂Ȃ��v
�@�Əq�ׂĂ���B
�@�܂������̌����Ȉ��g����ǒ��c�ӔɗY���́A���_�ɂ��Ď��̒ʂ�������A
�u��v�̊�{�I���i�𖾂炩�ɂ��Ă���B
�u��̐��i�́A�[�I�ɂ����A��v�����҂̖����⍜�����[����[���{�݂ł���B
���������āA���̕�́A�S��v�҂����J��������_�ЂƂ́A���{�I�ɐ��i���قɂ��A
���҂͂��ꂼ�ꗼ����������̂ł���B
���A���̕�́A�O���ɂ����閳����m�̕�Ƃ��قȂ���̂ł���B�O���ɂ����閳����m�̕�́A���c�̐�v�҂̕悩���̂��ڂ��A����ɂ���đS��v�҂��ے�������̂Ƃ��錚�O���Ƃ��Ă��邪�A����A���ɂ����Č��������́A���̂悤�Ȏ�|�͊܂܂�Ă��Ȃ��B���̖ʂ���������_�ЂƂ͎���قɂ���v
���āA���a31�N11��28���A���{�͊t�c�ɂ����āA����28�N12��11���̊t�c����ɂ��čĊm�F���A�u��v�̌��݂𑣐i���邱�ƂɂȂ����B�܂����ݏꏊ�ɂ��ẮA���{�͓����A�{�������L�̐璹��������z�{緐ՂƂ��邱�Ƃ���肵���B
�����_�Ђ���ѓ��{�⑰��́A�]���A�����_�Ћ����Ɍ������ׂ��ł���Ǝ咣���Ă������A�吨��A���{�̈ӌ���F�߂���Ȃ��Ȃ�A���̑��12��3���A�����̈⑰�������ƁA���[���������c�d�����i�푈�]���҉����X���j�Ƃ̊Ԃɗv�|���̂悤�Ȋo�������������B
�L
1.���́A������v�҂̕�͐M�I�ɖ����_�Ђ��������̂łȂ��A���ݎs���J�[�@�@�����Ɉ��u���锪���]���̌�⍜�y�э���C�O�����[���鏊������l�̖�����@�@�⍜���[�̕�ł��邱�ƁB
2.�{��̌��݂ɂ��A800���⑰�̗J�����Ă�������_�Ђ̑����Ə����̈ێ��A�y�с@�@���_�I�A�o�ϓI���e���̔g�y���Ȃ��悤�ȑ[�u�����邱�ƁB
�@�A�ẮA�Ⴆ���ۊ��s�ɂ��䍑�K��̊O����\�ғ��ɑ��A�䍑���{�W�҂��@�������Җ��͈ē������Ȃ����邱�ƁB
3.�����_�Ђ̑����쎝�ɂ��āA����ʏ퍑��̉�����ɐ��{�����āA���_�I�A�o�ρ@�I�[�u���Ȃ����ނ邱�ƁB
4.�{��̒n��͖����_�Ђ̊O���̋C���Ŏ戵�����A�����@�I�[�u���u���邱�ƁB
�ȏ�
�����āA���{��12��4���̊t�c�ɂ����āA�璹�����Ɍ������邱�Ƃ𐳎��Ɍ��肵�A
33�N8�����H�A��34�N3���ɏv�H�A���̂́u�璹������v�ҕ扑�v�Ƃ��ꂽ�B
�@�璹������v�ҕ扑�ɂ́A���̌�A�C�O�Ŏ������ꂽ��v�҂̌�⍜���[������A
����20�������ɋy��ł���B��v�҂̕扑�Ƃ��āA�����Ƃ��Ɉԗ�̐���s�����ׂ����Ƃ͓��R�����A�扑�̐��i�͌��ݓ����Ɖ���ύX�̂Ȃ����Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
���̂��Ƃ�34�N3���̊t�c�ɂ����Ă��u�����̌�⍜�������ӔC�������Ă����\���グ��v�Ƃ��������Ċm�F����Ă���A�܂��A39�N2��21���̑�46����O�@�\�Z�ψ���̑�ꕪ�ȉ�ɂ�����A���Г}��c�V�g���̎���ɑ��鐭�{���قɂ����Ă��m�F����Ă���B
����ɁA���a50�N2��27���A��75����̏O�@�ИJ�ψ���ɂ����āA���Г}�̘a�c�k�쎁�̎���ɑ��A�����Ȃ̔��؉���ǒ��́A�璹�����扑�̐��i�ɂ��āA���̌o�܂𖾂炩�ɂ��A�u�����s���̌�⍜�����[�߂��Ă���v�Ɠ��ق��Ă���B
�܂��a�c�����u�O���̍��o��璹�����ɂ��Q��肤�悤�U�����ׂ��ł͂Ȃ����v�Ƃ̎���ɑ��A�c��������b�́u�E�E�E�璹�����̏ꍇ�͍����哌����̐�v�҂̕��Őg���̂킩��Ȃ��Ƃ��������l�̂Ȃ��⍜�ŁA�i�O���̖�����m�̕�Ƃ́j�͈͂��Ⴄ�̂ŁA�{�l�̊�]�ɂ���Ă��肢����̂��Ó��Ǝv���v�Ɠ����Ă���B
�@�ȏ�̒ʂ�A�璹�����扑�̐��i�ɂ��Ă͋^�O�̗]�n�͂Ȃ����A���ڂ��ׂ����Ƃ͎��̌o�߂ƂƂ��ɁA�������O���ꂽ�悤�ɁA�璹�����扑��S��v�҂��ے�����扑�Ƃ��Đ��i�Â��A�ʒu�Â��悤�Ƃ���Ӑ}���A�ꕔ���Ɍ����Ȃ�扑��d��Ɍ����邱�Ƃł���B��Ɍf�ڂ����扑�̃p���t���b�g�͂��̍D��ł���A�扑���݂̌o�܂�m��Ȃ������ɂ��Ƃ��������F����^���A���̊�{�I���i�ɂ��ĂȂ������I�ɂ����܂������邱�Ƃ́A�㐢�̂��ߗJ�������Ƃ���ł���B
���́A��������������_�Ѝ��ƌ쎝���������邱�Ƃ����҂���Ɠ����ɁA���̋łɂ́A�璹�����扑�������_�ЂɈڊǂ���邱�Ƃ�ؖ]���Ă�܂Ȃ��B
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
�ȏ�̓l�b�g����R�s�[�����L���ł��B
|
�W���P�S���i���j
�w���̊ۉƓd�̖��^�x��ǂ�ŁI
�@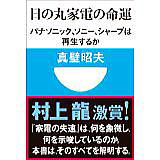
�@���ɁA�W���V���ɗ��H���߂��܂������A���̌�A����ɖҏ��������Ă��܂��B
���̉Ă͗�N�ȏ�ɋC���������A�ُ�C�ۂ̂悤�ł��B�N�X�C�����オ���Ă���̂��S�z�ł��B
�@�������A�G�߂͒����Ɉڂ�ς���Ă��܂��B
�@�W���P�O�������A���̉ď��߂ăc�N�c�N�{�E�V�����Ă���̂��܂����B�@�@���T�����납��U�����܂ł̒Z�����Ԃł����B���̌�A�����A�������ԑтɖ��Ă��܂��B�����A���̏����ł��̂łU���ȍ~�A�C�����オ��ƃN�}�[�~�̖����ɐ�̂���܂��B
�@����̒��A�����͋C�����Q�S�x�O��ŔM�і��Ƃ�܂����B�����������ȁI�Ƃ������ɂȂ�܂����B�����͑��ς�炸�R�T�x�ȏ�̏����ł��B
�F�l�ɁA�c���A���������\���グ�܂��B
�@�����̃e�[�}�́A�w���̊ۉƓd�̖��^�x�Ƃ����^�C�g���̖{�̓nj㊴�ł��B
�u�p�i�\�j�b�N�A�\�j�[�A�V���[�v�͍Đ����邩�v�Ƃ����T�u�^�C�g���������Ă��܂��B���҂͐^�Ǐ��v���A�o�ł͏��w�فE�V���B�艿�͂V�Q�O�~+�ŁB
�@�J�o�[�ɂ́A�u�w�Ɠd�̎����x�́A�����ے����A�����������Ă���̂��B�{���́A���̂��ׂĂ��𖾂���B�v���㗴�������Ă���B
�u�Ɠd�e�Ђ͌Ȃ̋Z�p�͂��ߐM���邠�܂�A�ڋq�̃j�[�Y�ɉ����鏤�i���J���ł��Ȃ������B���������v���E�E�E�ǎ���C���ꂽ�o�c�w�Ɏc���ꂽ���Ԃ͌����đ����͂Ȃ��v�ƂȂ��Ă���B
�@�@��P�́@�����K�V���̉Ƒ���`�����̂Ă��p�i�\�j�b�N
�@�@��Q�́@�������\�j�[�X�s���b�c
�@�@��R�́@�y�d��ɒǂ����܂ꂽ�V���[�v
�@�@��S�́@���Â����m�d�b�ƕx�m��
�@�@��T�́@�s�U�ɚb���Ɠd���[�J�̋��ʍ�
�@�@��U�́@�A�b�v���A�T���X���d�q��C�O����������R
�@�@��V�́@�D�ΏƂɍ����m�ۂ����d�d�e��
�@�@��W�́@���{�̉Ɠd���[�J�͐����c���
�Ƃ����\���ɂȂ��Ă���B
�@���{�̓d�@���[�J�W�Ёi�p�i�\�j�b�N�A�\�j�[�A�V���[�v�A�m�d�b�A�x�m�ʁA�O�H�d�@�A�����A���Łj�ɂ��āA���͂��s���A����̑Ώ��̓��������Ă���B
���ɁA�Ɠd���[�J�A�p�i�\�j�b�N�A�\�j�[�A�V���[�v�R�Ђɂ��Ă͑����˂������͂����Ă���B
�@���݂̓��{�Ɠd�R�Ђ̋ꋫ�́A�o�c�w�̎���ɂ���ƌ��_�Â��Ă���B
�R�Ђ̌o�c�w�̖��O����̓I�ɋ����Ȃ���A���X�̕��j����g�݂͂��e�Ђŏ��������e�̈Ⴂ�͂��邪�A���ʂƂ��ĂR�ЂƂ��傫�Ȏ��s���d�˂Ă������ƂɌ��y���Ă���B
�@�p�i�\�j�b�N�ɂ��ẮA�������v�ŗ����������悤�Ɍ��������A���͑傫�ȕ��̈�Y���Y��ł��܂������ƁB���̌�̑�؎В�������ɏ������g�債�����ƁB�����d��̗ǂ��`����ے肵�āA���S�͂�r���������Ƃ������Ă���B
�@�\�j�[�̓\�j�[�X�s���b�g���o�c�w���j�A���̂Â���̃\�j�[�̗ǂ��`�������������Ă��܂������ƁB���낤���ĕی����s���ׂ��Ă���̂ŁA���Ƃ����̂��ł��邪�A���̂Â���Ƃ����_�ł͔�펖�ԂɂȂ��Ă���B
�@�������ɋN�Ƃ����z���_�͍������C�ŁA���������Ƃ��āA�����������Ɨp�W�F�b�g�@�̐����A�̔�����ȂljH�����Ă���B
�@�V���[�v�͉t���̃V���[�v�A�T�R���f���ňꎞ���A�t���e���r�ŃV�F�A�m���D�P���Ƃ�A��Ԓ��𗎂Ƃ����������������A���E�̌i�C�A�T�u�v���C�����A�~���A�t�������Z�p�̗��o�A�R�X�g�����ȂLj�C�Ɍo�c�����ς�����B�����������ŋ���ȍ�H��̌��݂ɋ��z���������Ƃ��o�c���낤�����������ɂȂ����B�����ŏ��ĂA�V���[�v�̓f�W�^������̔e�҂ɂȂ��͂��ł������B
���ʂ͋t�ɂȂ�A�傫�ȓq���ɔs�ꂽ���̑��Q�͖����ɂȂ�Ƃ������ʂɂȂ����B
�@�������A���{�̃��[�J�͂܂��Đ��ł���\����L���Ă���B�������A�c���ꂽ���Ԃ͑����Ȃ��ƂȂ��Ă���B
�@�ċN�ł��邩�ǂ����͌o�c�w������ǂݐ��āA����Ə����ɓK�ȑΏ��ł��邩�ǂ����ɂ�����B
�@�ċN�ւ̓��A���̃|�C���g�͉����H
�@���Ƃ����藧���ǂ����́A���[�U�A���q����A�ڋq���~�������m��T�[�r�X��ł��邩�ǂ����ɂ�����B
�@�ߏ�Ȑ��\�A�قƂ�ǎg��Ȃ��@�\�Ȃǂ�t���āA���ꂾ���������̂�����A�����Ă������ƈ���I�ɍl���Ĕ����Ă��A�����l�͉��������B
�@����͏��i����łȂ��A�T�[�r�X�ɂ��Ă������邱�ƁB
�@���q���~�������̂��A�~�����Ƃ��ɁA�[���������i�Œ���̂���Ƃ̎g���ł���B���ꂪ�ł���A���̊�Ƃ͐������ł���B
�@���݂͐��E�I�ȉ��i�����ɓ���A������x�O���������i�����ɓ˓����邱�Ƃ�����B�����鉿�i�Ŕ���悤�ł͊�Ƃ͐��藧���Ȃ��B
�@�������A�w�����ē����x�Ƃ����������邪�A����́u�ׂ�������l���Ă��Ă͌��ʂƂ��ē��ɂȂ�Ȃ��v���Ƃ������Ă���̂ŁA�����āu������v�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B���̈Ӗ�����Ƃ���A����̓v���E�X�̒l�t���ɂ���B
�@�v���E�X�����̒l�i�Ŕ������ꂽ���͂т����肵���B�\�z���T�O���~�`�P�O�O���~�������i�ł������B�\�����Ȃ��������i�Ńn�C�u���b�h�Ԃ����A��C�ɑ�ʂɔ̔����邱�ƂŁA�ʎY���ʂ��o���A��������Ɋ�������킹��A�Ƃ����g���^�̐�p�ɔ���𑗂肽���B
�@���܂łɂȂ������Z�p�╔�i�A�ޗʂ��g���ꍇ�͂ǂ����Ă��l�i���オ��B�@��e�ʃj�b�P�����f�d�r�A���͂ȏ��^���[�^�[�A�c�b�|�`�b�C���o�[�^�[�Ȃǂ͍��܂ł̎����Ԃł͎g��Ȃ��������ނł��B���܂ŏ��ʂ�������Ă��Ȃ��������̂̒l�i���������A��ʂɎg�����Ƃ�O��ɁA�������@��ޗ������t�����������A�傫�����i�����������邱�Ƃ��ł���B
�@�g���^�̓v���E�X�̃n�C�u���b�h�헪�ɐ��������B���̐����Ńg���^�����Ԃ͂��������E�̃g���^�Ƃ����C���[�W���o���オ�����B��Ƃ͏�ɂ��������E�炪�K�v�ł���B���q�l���猩���u�����h�C���[�W�����ɏd�v�ɂȂ�B
�@���̖{�́A���ɖڐV�������e�͂Ȃ��B�����Ă��邱�Ƃ͑S���Ȃ��Ƃł���B
���{�̐����Ƃ��ȑO�ɔ�ׂāA�͋����Ɍ�����ƌ����Ă���B���̐^�̗v���͉����H�@���̂��Ƃɂ͐G��Ă��Ȃ��B
���͂͏\���ɂł��Ă���B���̓��e�͗ǂ������ł��邪�A�Ȃ��H�����Ȃ����̂��H�ɂ��ẮA�o�c�w�̃~�X�W���b�W���v�����I�Ƃ����\���ɏI����Ă���B
�o�c�w�̃~�X�W���b�W���������v���͉��Ȃ̂��낤���H
���̂��Ƃɂ���ɓ˂�����łق����B
���́w���z�L�x�ɂ͈ȑO����A���̐^���ɐG��Ă���̂ŁA�������������B |
�W���P�P���i���j
�w�Ȃ�ʂ��Ƃ́A�Ȃ�ʂ��̂ł��x
NHK��̓h���}�w���d�̍��x������オ���Ă��܂��B�h���}�����Ă����
��ÂƂ����n�ŁA�Ɠ��̕��K�╶�������t���Ă����̂�������܂��B
�w�������������Đ����邱�Ɓx�́A����Ƃ������ʁA�����ڂŌ��āA
�w������肪�{���ɐ������������ǂ����H�x�@���f���v�鎞������܂��B
�ŋ߁A�q���������^�i�����j�����X�A�b��ɂȂ�܂����A�]�ˎ����
���m�̎q����^�͑�ό����������悤�ł��B�@�q���ł���Ȃ���A
�z�Ƃ����p���������܂��B�i�h���}�����Ċ����邱�Ɓj����͋����{�R��
��������ɂ��������鋤�ʂ����Ƃ��낪����悤�Ɏv���܂��B
����͂ǂ����琶�܂�Ă�����̂Ȃ̂ł��傤���H
�w���������Ă���x�Ƃ����ْ������s��������������̂�������܂���B
�������͗ǂ��Ӗ��łْ̋����A���`���͂Ȃ��������Ȃ����̂ł��B
�w�Ȃ�ʂ��Ƃ́@�Ȃ�ʂ��̂ł��x�ɂ��āA�������ׂĂ݂܂����B
�@�Y�̝| �i���イ�̂����āj�́A���E��Ô˂�10�܂Ŕˎm�̒j�q�q��ŁA���V�ق֓��w����O�ɁA�����n��ɏZ��6�`9�܂ł̎q�ǂ�����(�j�q�̂�)��10�l�O��̃O���[�v���������Ă��܂����B���̏W�c���u�Y�i���イ�j�v�ƌĂсA���̂����̔N���҂���l�Y���i�����j�ƂȂ�A���̒��Ŏ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����܂���߂����̂ł��B
�@�������ԂɁA�Y�̒��Ԃ̂����ꂩ�̉ƂɏW�܂�A�Y�������̂悤�ȁu���b�v����ЂƂ݂�Ȃɐ\���������A���ׂĂ̂��b���I���ƁA������獡���ɂ����āu���b�v�ɔw�����҂����Ȃ��������ǂ����̔��ȉ���s���܂����B
���̓��e�́A
��A�N���ҁi�Ƃ������̂ЂƁj�̌��ӂ��Ƃɔw���Ă͂Ȃ�܂���
�@��A�N���҂ɂ͂����V�����Ȃ���Ȃ�܂���
�@��A�R���i�����j�����ӂ��Ƃ͂Ȃ�܂���
�@��A�ڋ��ȐU�������Ă͂Ȃ�܂���
�@��A�ア�҂������߂Ă͂Ȃ�܂���
�@��A�ˊO�ŕ���H�ׂĂ͂Ȃ�܂���
�@��A�ˊO�ŕw�l�i����ȁj�ƌ��t�����ւĂ͂Ȃ�܂���
�@�Ȃ�ʂ��Ƃ͂Ȃ�ʂ��̂ł��B |
�@��ẤA�˂̊w�⏊���P�U�U�S�N�Ɍ��݂��ꕽ���Ȏ��オ�����Ă��܂����B
�P�W�O�O�N��ɑ�Q�[�ɂȂ�A��ÂƂ������������R���̒��Ŕ˂��������т�ɂ́A����ɗ͂����A�D�G�Ȑl�ނ���Ă邵���Ȃ��Ƃ����˂̋������ӂ̂��Ƃɐ��܂ꂽ�̂��w���V���x�ł��B�w���V�فx�͂P�W�O�R�N�ɂT�N�̍Ό��������Ċ������܂����B
�@�Y���C�������P�O�Έȏ�̒j�q�̎q�킪�A���V�قł���ɍ���������܂����B
���ނ��_��A��w�Ȃǂ̎l���܌o�A�F�o�A���w�Ȃǒ����̌ÓT���g���܂����B
�@���V�ق͗D�G�Ȑl�ނ�y�o���A���̌�̉�Â̐B�Y���ƂɊ�^���܂����B
���V�ق͕�C�푈�Ŗ��a�@�̖������ʂ����A���̌�Ď����܂����B
���̌�A���V�ق̗��O���p�����l�����̓w�͂ōČ��Ɏ��g�݁A�P�X�W�T�N�i���a�U�O�N�j�S���ɋN�H�����s���A�R�S���~��������Îs�ᏼ���͓��ɒ��H���A�P�X�W�V�N�R���ɊJ�����܂����B
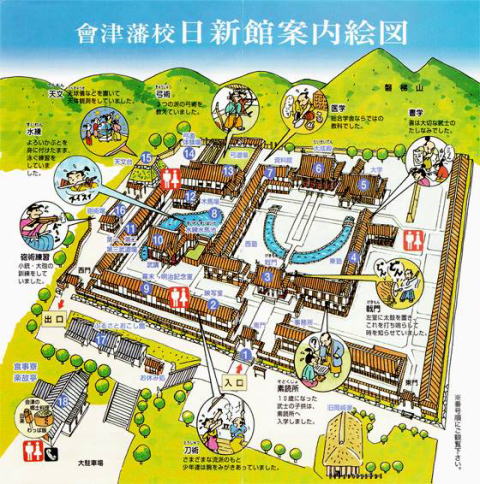
�w�Y�̝|�x�̌���łƂ��āA�w�����Â����錾�x�Ƃ����̂����邻���ł��B
�@�@�l���������܂��@
�@�A���肪�Ƃ��A���߂�Ȃ����������܂�
�@�B���܂�����܂�
�@�C�ڋ��Ȃӂ�܂������܂���
�@�D���Ɍ������Ă����܂�
�u����Ă͂Ȃ�ʤ�@���˂Ȃ�ʁA�@�Ȃ�ʂ��Ƃ́A�Ȃ�ʂ��̂ł��v
���������s������������w�ׂA�w�����߂��q�x�͂Ȃ��Ȃ�܂��ˁB�������肽���ł��B
|
8��10���i�y�j
Panasonic�͂Ȃ���킵�Ă���̂��H
�@���{�̉Ɠd���[�J�͂��Ƃ��Ƃ����܂��͔s�킵�Ă��܂����B
���{�̂��ƌ|�Ƃ܂Ō���ꂽ�w���̂Â���x�́A�Ȃ��������ȒP�ɔs�ꂽ�̂��H���̕���ɐЂ�u�������Ă�����l�Ƃ��āA�c�O�Ŏd�����Ȃ��B
�������A�E�𗣂�A��ÂɐU��Ԃ�ƁA���낢��Ɨv�������������Ƃ�������B
�@���܂��܁A�l�b�g�ł���L����q�ǂ����B�����l���Ă��邻�������v���ɂ��āA�悭�������e���L����Ă����B�����悤�Ȃ��Ƃ��l���Ă���l��������̂��Ȃ��Ƌ������̂ŁA�L�����Љ�A�����̎v���������Ă݂��B
���������ɂȂ邪�A�Ȃ�قǂƋC�Â�����邱�Ƃ������͂��B
�@**************************************************************
�u���́v�̐��E�ƁA�u����v�̐��E
�@�w���̂Â���x�Ƃ͖{���A����҂����N���N����悤�Ȃ��̂��l���邱�ƂƁA��������邱�Ƃ̂Q�̋ǖʂɕ����čl����ׂ��ł͂Ȃ����B
�@��ʂɁw���̂Â���x�Ƃ����ꍇ�A�u���́v���\�����i���i�j�ƂƂ炦�Ă��܂��Ƃ���ɁA����̌�������B
�@�u���̂�����v�u���̎v���ɂӂ���v�u���̂̂��v�Ƃ��������t�������悤�ɁA�u���́v�͖{���A�`������̂ł͂Ȃ��A�v����l�����A�A�C�f�A���w���Ɖ��߂���
���Ƃ��ł���B
�@����A�u����v�́A���̎v���Ȃ�A�C�f�A�Ȃ����̓I�Ȍ`�ɂ���Ƃ��̃v���Z�X�ł���A�����Ƃł����w���Y�����x�ɓ�����B
�u���́v�͓��̐��E�A�u����v�͎葫�������E�A�ƌ��������Ă������B
�@�A�b�v���̌g�ђ[���uiPhone�v�ɏے������悤�ȁA����҂����N���N������́A�u���ꂪ����Ύ����̐������ς��̂ł͂Ȃ����v�Ǝv����悤�Ȃ��̂ݏo���̂��A�u���́v�̋ǖʂ��B
�@
�@���i�ɕt�����l������̂́A���Y����i���ł͂Ȃ��A���������a�V�Ȑ��i�R���Z�v�g��\�t�g�E�G�A�A�f�U�C���̕������B
�@������5000�~�����Ȃ��悤�ȗL���u�����h�̃r�j�[�����o�b�O��20���~�Ŕ����̂��A�u���́v�̂Ƃ���ň��|�I�ɏ���҂𖣗����Ă��邩��ɂق��Ȃ�Ȃ��B
�T�[�r�X���A�\�t�g���u���̂Â���v
�@���̂悤�ɁA���̂Â����ǂ��u���́v���ڋq�ɓ͂����A�̃v���Z�X�ƍl����Ȃ�A���̂Â��肪�H��Ƃ������Y����ɕ���ꂽ�v���Z�X�ł͂Ȃ����Ƃ�A���̂Â���ɂ���Đ��ݏo�����̂��A�����I�Ȑ��i�Ƃ͌���Ȃ����Ƃ�������B
�@�u���́v�i�ڋq�ɂƂ��ĉ��l����v���j���}�e���A���ɖ��ߍ���ł����̂������ƂȂ�A�l�ɖ��ߍ���ł����̂��T�[�r�X�ƂƂ������ƂɂȂ�B
�@�T�[�r�X���\�t�g���A�l�̊����ɂ���Đ��ݏo�����S�Ă��u���̂Â���v�ł����āA�P���A�Q���A�R���Y�Ƃƕ����邱�Ǝ��́A�Â��l�����Ȃ̂ł͂Ȃ����B
�@�����āA����҂̃j�[�Y�����Ƃ������_����A�Ⴆ�ΊO�o�ł��Ȃ�����҂ɃR���r�j��X�[�p�[���i����͂���Ƃ������n�[�h�ƃT�[�r�X����̂Œ���u�\�����[�V�����v�̔��z���A����܂��܂��d�v�ɂȂ�B
�u����v�ɌX�����u���́v�Ō�����������{���
�@1990�N��܂ł̓��{�̂��̂Â���̋��݂́A���ɉ��Ăɏo����Ă���̂Ɠ����悤�Ȑ��i���A���Ă������i���������ɂ���邱�Ƃ������B
�@���{��Ƃ͐��Y�Z�p�ɖ����������邱�ƂŁA���@�\�E���t�����l�̐��i��A�o���A���n������i���s�����������ꂽ�B
�@���̂��߁A���{�̂��̂Â���́u����v�ɖv�����A���̊Ԃɂ�����ҕs�݂ɂȂ�A��������ׂ����Ƃ����u���́v���l���锭�z���̂��ɂȂ��Ă��܂����B
�@�P�̎Y�Ƃɕ����Ђ��Ђ��߂��Ă��邪�䂦�ɁA����҂������Ƒ��Ђɖڂ��s�������ɂȂ�A�ی����i���������J��L���Ă��܂����ʂ����邾�낤�B
�@
�@�������A��i���̍w���͂��������ވ���A�V�����Ŕ���Ȓ��ԑw���䓪���Ă��������̃O���[�o���s��ɂ����āA�l�X�Ȑl��A�l�X�ȉ��l�ς����݂��A����҂̗v������C�ɑ��l�����Ă���B
�@����ŁA�f�W�^�������i�݁A���ł��N�ł������悤�Ȃ��̂������悤�ɂȂ������Ƃ���A�u���́v�ɂ��čl���邱�Ƃ�����܂ňȏ�ɏd�v�ɂȂ��Ă����B
�@���ہA�����̂Â���Ő��E��Ȍ����Ă����Ƃ́A�ǂ����u����v�ł͂Ȃ��u���́v���d�����Ă���B
�@�uiPhone�v������A�p�_�C�\���̃T�C�N�����i���S�����j�����̑|���@��A�ăA�C���{�b�g�̃��{�b�g�|���@�u�����o�v������ł���B
�@�����͂���������i�Ɏg���Ă���v�f�Z�p�ɂ͐^���ł��Ȃ��ڐV�������̂͊܂܂�Ă��Ȃ��B�����Z�p�̑g�ݍ��킹�ŏ���҂Ɏx���������̂ݏo���Ă���̂��B�����āA��������u����v�͑�p�⒆���A�}���[�V�A�ȂǓK���ōs���Ă���B
�u�ǂ����邩�v���u�������邩�v���d�v
�@���[�U�[�́A�Z�p��C�m�x�[�V�������̂��̂����߂Ă���킯�ł͂Ȃ����A�g�����Ă̂Ȃ��@�\�Ƀ��N���N���邱�Ƃ��Ȃ��B�i�����悯�������ł��������Ƃ����l���V�����ɂ��Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A�唼�͂���Ȃ��@�\��A�ō��ł����Ă��ߏ�ȕi���ɂ������̂͂��߂Ǝv���Ă���B
�@���Y�҂��ǂ������������ł��邩�ł͂Ȃ��A�ŏI�I�ɏ���҂���������ǂ����ł���B�u����҂����N���N����悤�Ȃ��̂�����邩�v�u�@�\�≿�i�ȂǁA���n�̏���҂̗v���ɍ��������̂�����邩�v���r�W�l�X�ɂ����Ă͑S�ĂȂ̂��B�����Ă���́A�K�������V�����Z�p���Ȃ��Ă����ݏo����B
�@���{���i�̒��ɂ��u�E�H�[�N�}���v��u�E�H�V�����b�g�v�ȂǁA�������肷��悤�Ȋv�V�I�ȃA�C�f�A���`�ɂ������̂��Ȃ������킯�łȂ͂��B
�@�������u���v���i�̑�������{�ɗ����Ă���T���X�������łȂ��A�A�b�v���ɂ��Ă��A�_�C�\���ɂ��Ă��A�q�b�g���Ă��鐻�i�́A���{�̋Z�p�͂�����Ώ\�����ꂽ�͂��̂��̂��肾�B
�@���{��Ƃɂ́A�����������i�ݏo���O��ɂȂ锭�z�͂��Ȃ��킯�ł��A�Z�p�͂��Ȃ��킯�ł��Ȃ��B�Z�p�ւ̉ߐM��A�V�����s��ւ̑Ή��̒x�ꂩ��A�u���́v�̕������u�^���ɍl���Ă��Ȃ��v�����Ȃ̂��B
�@���C�h���ق��ƒ낪�����C���h�ł͌��������①�ɂ��D�܂�邵�A��������G�A�R���ɒg�[�͂���Ȃ��B�Ⴊ�}��銴���ǂɔY�܂���Ă���~�����}�[�Ȃǂ̓���A�W�A�ł́A�T���X��������o�����E�����ʂ̂���G�A�R���������I�Ƀq�b�g�����B
�@���{�ł��j�Ƒ������i�ވȑO�̍��x�����̏����i�K�͗ߏ��S�̂����X���������悤�ɁA�V�����ŐÉ��������߂�j�[�Y�͂قƂ�ǂȂ��B�������ł̓K���K���₦��N�[����①�ɂ��D�܂��B
�@����Ȃ̂ɁA�]���Ɠ������l�ςɊ�Â��āA�����ō��X�y�b�N�̐��i�𐢊E�ɂ�T�����Ƃ��čs���l�܂��Ă���̂��A���{��Ƃ̌��I�B
�@�O���[�o�������ɏ��ɂ́A���{��Ƃ͂�������Ɂu����v�ɐs�͂���̂ł͂Ȃ��A�����Ɓu���́v�ɖڂ������A�V�t�g���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�O���[�o�����A�f�W�^�������i���݂̂��̂Â���ɂ����ẮA�u�ǂ̂悤�ɂ��邩�v�ł͂Ȃ��A�u�ǂ̂悤�ȁw���́x�����邩�v�ŏ����͌��܂����炾�B
�@*************************************************************
�Ƃ����L���ɂȂ��Ă���B
�S�������ł���A���̐��z�L�ɂ����l�Ȃ��Ƃ����܂ŁA���������Ă����B
�@Panasonic�������d��ł��������A����A������25�N�����O�A�r�f�I���S�����̎������������B���E����Panasonic�r�f�I����Ԃ悤�ɔ��ꂽ�B
VHS���\�j�[�̃��ɏ����āA��C�ɔ̔����L�тāA�����d��̗��v�̑唼���҂������ł������B
�@���̎����͂����ɑ�ʂɁA���肵�ė������邩���ۑ�ŁA��������̗͂����ł������B�Г��ł͗��v���҂�����͏d���A���̎��ƂɌg����Ă����l�ނ̓h���h�����i���Г��̏d�v�|�X�g���߂�Ƃ����������������B
�@���̍��́A�܂����ƈ���āA�w�ǂ����́i���i�j��Δ����x�Ƃ����s��ł������B�ƒ�p�r�f�I�͐��E���Ŕ���܂���A�V�F�A�̓i���o�[�����������B
�@���̍��A���łɃ��[�r���o�n�߂Ă������A�`���傫���āA�ƂĂ������^�ׂ�悤�ȕi���ł͂Ȃ������B������VHS-C�Ƃ��������ȃe�[�v��V�K�i�Ƃ��ċN�����A���^�̃��[�r�J���������i���������Ƃ�����B�����JVC��Panasonic�����S�ɂȂ葢���Ĕ̔������B
�@
�@���Ŕs�ꂽ�\�j�[�́A�\�j�[�������A�W�����T�C�Y�̐V�K�i���[�r�����i�������B���̃��[�r�̓e�[�v����8�o�������̂ŁA�I�[�f�B�I�p�̃J�Z�b�g�e�[�v��菭���������炢�̃e�[�v���g�����̂ŁA���i�����^�ɂł��āA���^�掞�Ԃ�VHS-C��15����20���������̂ɁA�W�������[�r��30���Ƃ�45���^��ł����B
�@�ʔ̓X����Panasonic��VHS-C���~�߂ĂW�������Ăق����Ƃ����v�]�������������B���q�l�̐����ق������X�̗v�]�ł������B
�@�������A���̐���ʔ̓X���璼�ځA��Њ�����������c�ŁA�wPanasonic�͂W�������[�r�͑���܂���x�Ɛ錾�����B
�@���̍�����A�����d��Ɂw���ʂڂ�x�A�w�Ƃ�悪��x�̕����������Ȃ����悤�Ɏv���B���ʂ́AVHS-C�͓r���łƂ�����Ĕ���Ȃ��Ȃ����B
�@���̌�A���炭���āA�f�W�^���̎���ɓ���B
���̎��́A�\�j�[���X�����f�W�^���ɂ���������BPanasonic��VHS-C�ő厸�s�����ꂢ�o���������Ă����̂ŁA�ƊE�ł܂Ƃߏグ���f�W�^�����[�r�̐V�K�iDVD���̗p�������^�̃r�f�I�J�������J�������������B����ł���ƃ��[�r�r�W�l�X�͑��𐁂��Ԃ����B
�@���Ƃ��ƁA�����d��̑n�Ǝ҂̏����K�V���́A�n�ƈȗ��A�w���q�l���x��W�Ԃ��Ď��Ƃɓ������Ă����l�ł���A�����d��͂��������Е��ł������B
���������Ђ������a43�N������}���ɋƗe���g�債�A�Г��͌��C���Ɉ��Ă����B�J���[�e���r�͋ƊE�i���o�[�����ŁA�i�����ǂ��A�F����Ԃ��ꂢ�łƂ����Ă����B���̌�̃r�f�I���Ƃ͑O�q�̂Ƃ��藲�����ɂ߂��B�������A�㔼�̃r�f�I�͗l�q���قɂ��Ă����悤���B
�@���ꂪ�A���̃r�f�I�̈ꎞ���ɁA���q�l�����������A�������ꒆ�S�̃��m�Â���ɑ����Ă��܂����Ƃ���ɁA����̋��̃��[�c��������B
�@
�@�w���̑���x��M�S�ɂ�肷�������ʁA�w���m�Â���x�������ƊԈႦ���B
�w���̂Â���x�͊��A�v�A�����܂ł���A�̂��̂Â���ł���B�������̂̈Ӗ��ɂȂ��āA�w�������́A���i���Ȃ��́A����̂Ȃ����̂������Ɉ����A���肵�đ��邩�x�Ƃ������Ƃɉ�Ђ̎厲���ڂ��čs�����B
�@���s���̎���Ȃ炱��͈�̉��ł����Ă������B�������A���ɂ��̗]��̎���ɂ����������Ă����B���ɊC�O�ł���������鎞��ɓ����Ă����B
�@�����瓖���A�����H��ō���Ă������͂�ۂ��ߋ@�B���A�������A���{�b�g�������Ď�g��ł����B
�@�C�O�ƍ����H��̐����R�X�g�̈Ⴂ�́A�傫���͐l��������B������w��Ǝ҂��[���ɂ���A�����ō���Ă�����͍����x�Ƃ��������ŁA��������{�b�g����i�߂āA�����̃��C���̏Ȑl���Ɏ��g�B
�@�������A���ʂ̓��{�b�g���͓������傫���Ȃ�A�Z�ʐ��������Ȃ��āA���܂�����Ƃ����ł��Ȃ��B���Y���鏤�i�̋@���ւ���A�������鏤�i�̐�ւ��ɑ��ď_��Ȑ��Y�V�X�e���łȂ���A�C�܂���ɂȂ��Ă����s��̗v���ɉ������Ȃ��Ȃ����B
���{�b�g��@�B�͓������̂葱����ɂ͓K�����V�X�e���ł���B���ނ╔�i�͂����������Y�V�X�e���Ƀ}�b�`����B�������A�Ɠd���i�Ƃ��đg�ݗ��Ă�ɂ́A�@���ւ��������ɑ����Ή��ł��邩���傫�ȃ|�C���g�ɂȂ��Ă����B
�傫�ȓ��������ă��{�b�g�⎩�����������Y���C���͂��̌�ꕔ�������ēP������A�Z�����Y�Ȃǂ̐��Y�����ɗl�ς�肵���B
�@���āA���Ƃ́w�����̂��߂łȂ��A���ƍ����̂��߁A���E�����̐i�W�̂��߁A���ǂ���炵���ł���悤�Ɂx�Ƃ����̂��A�����K�V���̗��O�ł������B
���ꂪ�A����Ɂw���Ƃ̂��߁x�A�w�ׂ��邽�߁x�A�w�����̂��߁x�ƂȂ���
�@
�@���{�͐��E�ő�Q�A�R�Ԗڂ̑傫�Ȏs��K�͂�����B���{�����Ɋ�悵�����i�����̂܂܊C�O�ɗA�o����A���̂����Ői��ł����B�w����Ȃɂ������m�i�����\�A���@�\�A�ȃG�l�A�Ȃǁj�ō��i���Ȃ���A���E���ǂ��ł������x�Ƃ����v���オ�肪�������B
�@���E�͍L���āA���{�ƈႤ����A�����Ȑl�̐����K��������B
���ɂ�萶�����X�^�C�����Ⴄ�̂�����A�ǂ��������������Ă���̂�������ΈႢ�͂���������B
�@�V�����̐l�X�͂܂��܂��s�ւȐ��������Ă���B�����̌���ɏo�����āA�������Ȃ̂��A�����̕s�ւ��������ł������͂Ȃ����������o���B
���̍�Ƃ����Ȃ��ŁA���{�ʼn��K�Ȑ��������Ă���l���������_�Ɋ�悵�����i��A�o���āA�����l�i�ł��X�ɕ��ׂĂ�����Ȃ��B
���̏����̌��_�ɋC�t���̂��x�ꂽ�B���ɑ������Ȃ��b�Ȃ̂��B
�@�������A�܂��҉�̗]�n�͂���B���Ƃ͒x�ꂽ��������������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B���̏؋����A�b�v����i-pad��i-pod�Ai-phone�ȂLj�A�̏��i�ł���B
���܂œ��l�ȏ��i���Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B
�f�W�^�����y�^�Ă��ł��邍��3�Ƃ����t�H�[�}�b�g���̗p�������i�͂���܂ł����������B�����̓f�W�^���ŒP�ɘ^�Ă��ł���Ƃ������i�ł������B
�A�b�v����i-pod�������I�ɔ��ꂽ�̂́A���y�\�t�g���l�b�g����_�E�����[�h�ł���Ƃ����\�t�g�𗍂߂��Ƃ���ɂ���B����̓n�[�h�̖��ł͂Ȃ��A�\�t�g�ƃn�[�h�̈�̉��������m�ł���A�㔭�g�ł��҉ď��Ă����Ƃ������Ă���B
�@Panasonic���h���ꂩ�甇��������A�ȑO�̂悤�Ȍ��C�������߂��邩�ǂ����́A�����͂����邱�ƂȂ���A���[�U���]�ނ��́A���Ȃ킿�A�������i�����āA�킭�킭����悤�Ȋ�����^��������̂Â��肪�ł��邩�ǂ����ɂ������Ă���B
�@�����������i�����ɂ́A�Z���X���v��B���̃Z���X�́A������Ƃł͂Ȃ��A�����̐����̏�ŕs�ւȓ_�͉����A���[�U���C�t���Ă��Ȃ����Ƃ������o���A��Ă��āA�����Ɗ�����^����悤�Ȃ��ƂɋC�t�������I�Ȋ��A�����������̂Â���A�w����Ί��邩�x��O���Ɏ�g��ł䂭���Ƃɐs����B
�@
�@���̘͐̂b�ɂȂ������A�����̌����C���ɏ�邱�Ƃ������ɏ��i��悵�āA���傢�ւ��Łw���̂Â���x�����āA�����悤�Ȏ���ł͂Ȃ��Ȃ����B
|
8��9���i���j
���ˈ����Z�Ɩ������Z�̖싅������
�@8��8�����Ă̍��Z�싅���n�܂����B���N���̍�����ԏ����A�b�q�����R����G�߂ł���B���N�́A�J������ɁA���ˈ����Z������A�a�̎R�̖������Z����O�����ɏo���̂ŁA�v���Ԃ�ɁA���Z�̎������e���r�Ŋϐ킵���B
�@�������Z�͘a�̎R���L�c�s�ɂ���A�L�c��͌��ɂ���B�߂��̎R�X�̓~�J�����ŕ����A�L�c�~�J���̎Y�n�ɂȂ��Ă���B
�@���̕ϓN���Ȃ��������Z���ߋ��ɑ傫�Ȏd���������̂ŗL���ɂȂ����B
�����ēi�����@���i�������j���j��1966�N�ɓ�����i���āA1970�N�ɓ��{�A1979�N�ɂ͐Έ�A���c�̃o�b�e���[�ŏt�ĘA�e�������B
�@���ɂ��̔N�̉Ă̎����ł́A���ō��Z�Ɖ���18��̃h���}�𐧂��A�N���Y����Ȃ����Z�싅�̗��j�����B
�@
�@�a�̎R���͖싅������Ȍ��ŁA�Â��͋ˈ����Z���a�̎R���w�i�a���j����ɋ����ėL���������B���̌�A�������Z���D�����L���ɂȂ����B
�@���̌�́A�a�̎R�s���̋ߑ�t�����Z��a�̎R�q�ٍ��Z�Ȃǂ̎��w�Z���݂��Ɍ���\���������B
�@���w�̏ꍇ�́A���ł��X�|�[�c�ł����Ґ����W�܂�A������I���g�ŁA�p�ˋ������P�����Ă܂��܂��Z�ʂ����߂�B����ɔ�ׂČ������Z�͌����Ƃ�������ł���A���w�̂悤�Ȃ��Ƃ��ł��Ȃ��B
�@���������̗��Z�̎��������Ă��Ă������������B���ˈ����Z�̑I��̑̊i�͑S����������łāA�������肵�Ă���B���Z���̖��n�ȑ̊i�ł͂Ȃ��A�������ꂽ��l�̑̊i�ŁA���ɂ͐��l�A�d�ʋ��̑I�肪����B
�@�����Ƀv���싅�I��ɂȂ��Ă�����肵�Ȃ��悤�ȑ̊i�������A�����^���\�͂����I�肪����ł���B�����A�������𑗂�A�Ǘ��h�{�m���J�����[�v�Z�����H������������H�ׂāA���K���j���[�����Ȃ������ʂ��Ǝv���B
�@����ɔ�ׂāA�����̍��Z�͋ߗׂ̒��w�Z�Ŗ싅������Ă����w�����W�܂����Ƃ������藧���ł���B���܂��܁A�����ɗD�ꂽ�ē����āA�Z���X�ƋZ�ʂ��������I�肪�W�܂������Ɏv�������Ȃ���т�������B
�@�a�̎R������������������́A���������Ŗ싅����肽���Ƃ����u��҂��W�܂�A�����ē����Ă���Ă����B������10���N�Ԃ͋����������ł����B
�@
�@�����Ɏ��w�����Ґ������̖싅����Ґ����A�w�Z�̏�銈���̈�Ƃ��Čo�c�I�Ɏ��g���ʂ��ŋ߂̍��Z�싅�̎p���Ǝv���B
�@�S���ŋ��w�̋������ւ鍂�Z�͂��̂悤�ɂȂ�ׂ����ċ����Ȃ������Z������ł���B�w�싅�D���ŁA�L���Ȋē��v�邩��x�ł͑S�����e�͂ł��Ȃ��Ȃ����B
�@�����́A�����ē̑��q����i�����@���j�ē��A�C���A�Ăє��������𐁂����Ă���邩�Ɗ��҂������A�����ȒP�ɂ͏������Ă��炦�Ȃ������B
�@�����ēi��������j�́w�����X�}�C���x�ŗL���ɂȂ������A�Ⴋ���͌������X�p���^���w�������āA���ɂ͑ޕ�������A�����Ă䂯�Ȃ��I�肪���āA�ꎞ�͊ē𗣂ꂽ���Ƃ�����炵���B���̊Ԃ̓{�[�����O��Ŏd���������肵�āA�l�����ߒ������悤���B���̌�A�Ί�̊ēƂ��đ听���ꂽ�B
�@
�@���q�̔����ē͍�����߂ăe���r�Ō������A���e�̔����������̏Ί炪�I�n����ꂽ�B
�@���̉Ă͎c�O�Ȃ���s�ꂽ���A�߂������A���������싅�������Ă���邾�낤�B�������A���w�̓��Ґ��싅�ɑł����Ă邩�ǂ����A�y���݂��B |
7��26���i���j
�l�����! �Ƃ́H
�@ 7��24���̋L���ŁA����A����Љ�̔��W�̂��߂Ɉ�ɂ���ɂ��l�ވ琬���L�[���Ƃ������Ƃ��q�ׂ��B�l���琬����Ƃ������Ƃ͑�ϓ�������[���ȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�ƒ�Ŏq���������邱�Ƃ͓�����O�̂��Ƃł��邪�A�w�Z��Љ�l�̋���͂܂��܂��d�v�ɂȂ�B������������x���̋���I
�@�w�������x���̋���Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂��H�x���l���Ă݂����B
�@����Ƃ́A�w�����̂��߂̖��������x�n�E�c�E����ł͂���܂���B���̓��{�̋���͑�w�����Ɏ邽�߂̋���ɂȂ��Ă���悤�ȋC�����܂��B�����Ɋw�Z��m�̖ړI������悤�ł��B����͂���Ƃ��đ��������܂���B�������A��w�Ȃǂ͍������x���̒m���〈����g�ɒ����邽�߂̎�i�ɉ߂��Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�����ŁA��A��̗�������Ă݂܂��B
�@7��24���̋L���̑����ɂȂ�̂ł����A20���I�ő�̔����ƌ�����g�����W�X�^�������x����������3���̌����҂̈�l�ŁA�V���b�N���[�̎q���̍��̘b���Љ�܂��B
�@�V���b�N���[�͏�����������A������ƕς�����q���ł����B�w�Z�̗���
�i�����j�̎��Ԃɐ搶���w�{�[�g���I�[���ł����ۂɁA�ǂ������͊W�ɂȂ��āA�{�[�g���O�ɐi�ނ̂���������Ȃ����x�ƌ��������o���܂����B�搶�̖͔͉̓I�[���̎x�_�𒆐S�ɁA��Ɛ��ʂɍ������I�[���̐�[�Ƃ̊W�������Đ�����`���܂����B
�@����ɑ��āA�V���b�N���[�͔������A�I�[���̐�[���Œ肵�������ʼn��o���܂����B�ǂ���������ł����A�搶�̓V���b�N���[�̔��z���^���������ł��B���̐搶�ɂ͈�������z������q�����Ɉ�Ă邱�Ƃ̈Ӌ`���������Ă����̂ł��傤�B
�@�w�Z�𑲋Ƃ��A�x���������ɓ���܂����B�����ŏ�i���玟�̌����e�[�}��^����ꂽ�B���̃e�[�}���Љ�܂��ƁA
�@�w�N���A���]�i�����̒��Ɉ�l���肾���ꂽ�Ƃ���B�����ł����ɋ~�o���Ă��炤���A�������Ăԕ�����l����I�x�Ƃ������̂ł������B
�@����͔��R�Ƃ����e�[�}�ŁA������ł����͂��肻���ł����A��������͔̂��ɓ�����ł����B
�@�w�������Ăԁx������͂Ȃ��̂ŁA���̂��߂ɖ������g���������@�͂Ȃ��B
�����̖�����͐^��ǂ��g���Ă����̂ŁA�傫���āA�d���ĂƂĂ����������Ȃ��B�������A�����ɓd�r�����Ղ��_���ɂȂ�g�����ɂȂ�Ȃ��B
�@�����ŁA���̃e�[�}�ɑ���ŊJ��Ƃ��Ă܂Ƃ߂��̂��A�w�����^�ׂ�傫����d���ŁA�d�r�������������A���Ȃ������@��x�ł������B
���̓����A��ɓ���^��ǂ��g���ł́A�������P�O�O���s�\�ł���B
�@���܂łȂ��S���ʂ̃��m�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���̍��A�����̂��g���𗬂��ɕς��鐮�����ʂ���������Ă����B�����Ŕ����̂��g���āA�d���̑�����p������f�q�낤�ƍl�����B
�������A�����A�Q���}�j���E���i���́A�V���R���ɑ����Ă���j�̏����Ȍ������K�v�ł��������A��������Z�p���Ȃ������B�����ƌ����Ă����[�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B���ƃe���i�C���i�X�X�D�X�X�X�X�X�X�X�X���j�Ƃ������x�ɂ��邱�Ƃ��ڕW�ɂȂ����B���̉����̂��ߌ����ɖv�����A���Ƀ]�[�������e�B���O�@�Ƃ������@�����A�����x�̌��������̂ɐ��������̂ł���B���̌�����s���d�˂����ɖv�����A�o���オ�����̂��g�����W�X�^�ł��B
�@�g�����W�X�^�͐^��ǂƔ�r���āA�ė��قǂ̑傫���ŁA�d�C��H��Ȃ��A�U���Ȃǂɋ����ȂǁA�f���炵�������������Ă����B
�����̃g�����W�X�^�͖�����������̎�_�������Ă����B���삪�s����A�����ɉ���A�ȂǂȂǁB
�@
�@�������A��{�I�ɗD�ꂽ�����������m�́A���ꂪ�����_����������Αf���炵�����m�ɂȂ�B
�@�J������ǂ��������A���肵�đ����g�����W�X�^�����܂�A���̌�A���X��IC��LSI�����܂ꂽ�B������ق�̂S�`�T�O�N�O�̂��Ƃł���B
���̌��ʁA���݂̃P�C�^�C��A�X�}�z�ɔ��W���Ă����B
�@�����A�x���������̏�i���V���Ј��̃V���b�N���[�ɁA�w�N�͐^��ǂ�O�ꂵ�ĉ��ǂ���x�Ƃ����w�����o���Ă�����A�V���b�N���[�͐^��ǂ̐��\����ɖv�����A�^��ǂƂ��Ă͂������̂ݏo������������Ȃ����A�g�����W�X�^�Ƃ������܂łɂȂ��������i�̊J���ɐ������Ă��Ȃ������͂����B
�@�l�Ɏd���⌤���̃e�[�}��^���鎞�́A���́w�e�[�}�̖ړI�������A���̂��߂ɂ��̃e�[�}�Ɏ��g�ނ̂��H�x�m�Ɏ������Ƃł���B
�����Č����A�r���ō��܂��Ȃ��悤�Ƀo�b�N�A�b�v����A�������������w��������Ǝv���B
�@���̋���́A�w���̖��������x�ł���A�����������Ƃ��ړI�ł���A�w���̖����������Ƃɂǂ������Ӌ`������̂��x�������Ă��Ȃ��B
�m�E�n�E��g�ɒ����邱�Ƃɗ��܂��Ă���B
���̕ӂ��������������w���⓮�@�Â�������Ǝv���܂��B
|
7��24���i���j
�d�]���l�]���z�������A�����N���邩�H
�ŋ߁A�m�[�g�p�\�R����A�^�u���b�g��A�P�C�^�C��A�X�}�z�ȂǁA�ŋ߂̏��[���̐��\���オ�������B
�@���ɃX�}�z�̋@�\��\�ɂ͖ڂ���������̂�����B����Ȏ�̂Ђ�ɏ�鏬���Ȃ��̂ɑ�R�̋@�\�������Ă���B�������A���̋@�\���X�g���X�������邱�ƂȂ����삷��悤�ɂȂ����B
�@�������g���@��́A�L���ɔ�ׂēd�g�̑ш�̐���������A�ǂ����Ă������x���Ȃ�Ƃ����ۑ肪�t���܂Ƃ��Ă����B���ꂪ�ŐV�̋Z�p�Ō����ɉ�������āA�܂��܂�����X�s�[�h�������Ȃ��Ă���B
�@�v�͑�ʂ̏��̂���肪���ɑ����ł���悤�ɂȂ�A����ɑΉ����Ă����ȃT�[�r�X���t�������悤�ɂȂ�A���[�U���g�����Ȃ��Ȃ��قǂ�������̋@�\�����ڂ��ꂽ���i���X�}�z�ɑ�\�����B
�@����́A�S�����Ɏg���Ă���CPU�i�}�C�R���j���i�i�ɐ��\�A�b�v�������Ƃɂ��B
�@�w�����̂̏W�ϓx��18�����`24������2�{�ɂȂ�x�Ƃ����L�����o������1965�N�ɃC���e���Ђ̃S�[�h���E���[�A���m�����\�����B
������A�w���[�A�̖@���x�ƌĂ�ł���B
�@���̌�A�����̏W�ω�H�͂��̖@���ɑ���A�{�X�Q�[���ŏW�ϓx���g�債�����Ă����B
�@���݁A���E�I�Ɍo�ς̓f�t����ɂȂ��Ă��邪�A�����ɂ��̐^��������B�Ƃ����̂́A�w�����͎̂Y�Ƃ̕āx�ƌ����A������@��A���i�ɖ����Ɏg���A�@��⏤�i�̐��\��@�\�̌���̗v���ɂȂ��Ă����B���̔����́iIC��LSI��V�X�e��LSI�ȂǂƌĂ�ł���j�́A�E�F�[�n�Ƃ��������ȃV���R���ޗ��̏�ɉ�H��`���č\������̂����A���̏W�ϓx����2�N�łQ�{�ɂȂ�ƁA�����V���R���̍ޗ��ɂQ�{�̓d�q��H���쐬�ł���B
�@����ɂ�艽���N���邩�H�Ƃ����ƁA�l�i�̓V���R���ޗ��̎g�p�ʂ͓����Ȃ̂ŁA�����l�i�Ő��\��@�\���h���h���ǂ��Ȃ邱�ƂɂȂ�B
�@�ȑO�̃��m���V�������m�����\�E�@�\���悭�Ȃ��Ēl�i���ς��Ȃ��A�܂��͏ꍇ�ɂ���Ă͈����Ȃ�B
�@�w�Y�Ƃ̕āx������������Ԃ�����A���̏��i�����l�ɂ������̂������Ȃ��Ă䂭�B
�@������A���[�A�̖@������������A�f�t���͕̏ς��Ȃ��ƌ����̂��A�����̂��Ȃ������ł��B
�@�s�v�c�Ȃ��ƂɁA���̂��ƂɐG����Ă��錩���͂܂��������Ƃ��Ȃ��I�B
�@�o�ϊw�҂�o�ϕ]�_�Ƃ́A�o�ς̃g�����h�͂��A��t���̌����������ɓW�J���Ă��邪�A�f�t����A�����̊C�O�ړ]��A���W�r�㍑�̖ڂ�������i���Ȃǂ̗v�������ɂ��邩�H�@���������Ă�����͑S����������Ȃ��B
�@�b�������ɖ߂��āA�g�����W�X�^����������āA���̂��A�����̏W�ω�H����������A����Ɏ���o�߂ɂ��āA���������G��Ă݂����B
�@�g�����W�X�^��1947�N�ɃA�����J�̃x���������̃o�[�f�B�[���A�u���b�e���A�V���b�N���[��3�l�ɂ���Ĕ������ꂽ�B���̎��̃g�����W�X�^�͓_�ڐG�^�i�|�C���g�R���^�N�g�j�g�����W�X�^�ƌĂ�A�d���̑�����p���������B����͂���܂Ŏg���Ă����^��ǂɑ��邱�Ƃ��ł����p�ł���B
���̌�A�ڍ��^�g�����W�X�^����������A���ꂪ���݂̔����̏W�ω�H�iIC��LSI�Ȃǁj�̌��^�ɂȂ����B���ɉ���I�Ȕ����ł������B
�@�g�����W�X�^�̔����ȗ��A�����̏W�ω�H�̔����A���̌�̑f���炵�����W����P�������āA����A�������p�̃V���R���E�F�[�n�̍ޗ��̏�ɁA100���ȏ�̃g�����W�X�^���ڂ��č\���ł���悤�ɂȂ����B
�@���̂��ƂɐG��A�\�t�g�o���N�̑����u����Řb���ꂽ�L�������āA���̐l���������Ƃ��l���Ă���ȁI�Ǝv�����̂ŁA�Љ��B
�@�@*********************************************************
�@���В��u2018�N�ɃR���s���[�^�[�͔]�ɒǂ����v
�@�\�t�g�o���N�̑����`�В���23���ߑO�A���Ђ��J�����@�l�����̃Z�~�i�[���u2018�N�ɃR���s���[�^�[�͐l�]�ɒǂ����v�Ƃ̌��ʂ����q�ׁA�Q���҂����������B
�R���s���[�^�[�̃`�b�v�P���ɑg�ݍ��܂��g�����W�X�^�̐���300���ɓ��B���A�l�Ԃ̔]�זE�Ɠ����ɂȂ�Ƃ����B
�@�����̂́u�W�ϓx��18�`24�J���Ŕ{������v�Ƃ����w���[�A�̖@���x�Ă͂߂Čv�Z�����Ɛ��������B
�@����ɖ�30�N���2040�N�ɂ́A�R���~���x�̃X�}�[�g�t�H���i�X�}�z�j�[���ł��b�o�t�i�������Z�������u�j�̔\�͂ƃ������[�̗e�ʂ͌��݂̖�100���{�ɁA�ʐM���x�͖�300���{�ɂȂ�Ƃ̎��Z����I�B
�@�u�����I�ȓ����ʖ\�ɂȂ�A������Â����x�����A�����̐l�̓��������傫���ς��v�Ƃ������W�]��������B
�@�R���s���[�^�[�̏����\�͂�ʐM���x�͌��݂��}���ɐi��ł��邱�Ƃ��������A�Q���҂Ƀr�b�O�f�[�^�i�@��Ȃǂ��甭�������ʂ̏��j��N���E�h�Z�p�̊��p��i�����B�\�t�g�o���N�ł͒ʐM�e�Ђ̒[���̓�����ڑ��Ȃǂ̃r�b�O�f�[�^�����p���A��n�ǐݒu�̍œK���Ȃǂ����������Ɛ��������B
�@�@*********************************************************
�@�ȏオ������̋L���ł����A����͊��Ɍ����Ă��邱�ƂŁA�ʒi�V�������ł͂Ȃ��B
�@�v�͍�������������Ĕ����̂��i�����A�W�ω�H�ɓ��ڂł���g�����W�X�^�̐����l�̔]�זE�̐��i300���Ƃ������Ă��邪�A���ꂪ��������������܂���B����͈�߂ł��B�j�ɕ��сA�����ǂ��z�����������B�����Ȃ����łɁA���̒��͂ǂ��Ȃ�̂��H
�@�����ʖX���[�Y�ɂł���悤�ɂȂ�A��a�����Ȃ��A�Ȃ̂���b�����ł��A���ꂪ�b���Ă��|�邱�Ƃ��ł��閲�̂悤�ȋ@�B���o������͂��B
�C�O���s�ɂ͕֗����I
�@�r�W�l�X�̐��E���傫���ς��A�܂��܂��O���[�o�������i�݁A�A�{�[�_���X�ɂȂ�B
�@���̌��ʁA���E���̐l����͂ǂ̍��œ����Ă��A����J���A��������Ɍ���Ȃ��߂Â��Ă䂭�͂��B
�@�����Ȃ���A��i���Ő������Ă���l�̍��������͈ێ��ł��Ȃ��Ȃ�B�@�@���E���ǂ��ŏZ�������A�ǂ��œ��������A�������������炤�ɂ́A�����t�������Y�ގd�����ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�܂��܂��������������Ȃ�B
�@��������������̋����łȂ��O���[�o���Ȋ��ł̋����ɂȂ�B���ꂪ���K�R���y�e�B�V�����̖{�����B
�@���{�̍���������������ێ����邽�߂ɂ́A�ǂ�����������H
�@��ɂ���ɂ��A���琅�������߂āA���t�����l�̎d�����ł���l�ނ��琬���邱�Ƃɐs����B
�@�������A�l�Ԃ͂��ׂėD�G�Ƃ͌���Ȃ��B�D�G�ȓ��]�������Đ��܂ꂽ�l������A�����łȂ��l������B�������A�w�͂�������郌�x���܂ł͋���ō��߂���B
�@�l�ވ琬�ɗ͂���ꂽ��Ђ⍑������L�тĂ䂭���낤�B
�����łȂ���Ђ⍑�͔��W���~�܂�A�u���Ă��ڂ��H�����ƂɂȂ�B
�@���{�͎��������Ȃ��A�L���ʐς����Ȃ��A�_�Ƃł͐H���Ă䂯�Ȃ������B������]�ˁA���������ʂ��ċ��琧�x�������ɐ�삯�Ċ�������Ă����B�����ېV�́w�B�Y���Ɓx����͂܂��ɓ����Ƃ��Ă͐挩�̖����������B
���̌��ʁA���݂̖L���ȕ�炵���ł���悤�ɂȂ����B
�@���A���߂���̂͂�����i�������x���̋���݂̍���ł���B
���E�勣������͂����܂ŗ��Ă���B��Ƌ����ɑł������A�勣���ɐ����c��ɂ͐l�ނ̈琬�A����ɂ��ׂĂ��������Ă���ƌ����ĉߌ��ł͂Ȃ��B
�@�����}�͐�̑��I���A�Q�@�I���ő叟�����B�傢�Ɋ��҂������I
�@�A�x�m�~�N�X�Ő��Ԃ͑呛�����Ă���B�i�C���ǂ��Ȃ�̂͌��\�Ȃ��Ƃł����A���̐�̂���ׂ����{�̍��Ƒ����ǂ������p�ɂ��悤�ƍl���Ă���̂��A���葽������������}�̐ӔC�Ƃ��Ď��g��łق����B
�@���݂̓��{�͈�̑O�ɓ��{���u���ꂽ�Ƃ͂��܂�ɂ������ʒu���ς���Ă��Ă���B������������茩�����A�������c�����Ȃ��ƁA�ł����������Ă��Ȃ��B�ŋ��̖��ʌ����ɂȂ�B
���������肪�K�v�Ȏ���ɂȂ����B�I�I�I
�@����͉�Ќo�c�ɂ��S�����Ă͂܂�B |
7��23���i�j
�����̈��S�ɂ�2�̐��������
�@�����d�� ������ꌴ�q�͔��d���́A���Ȃ��A���Z�x���ː����������n���R�����������A�C�ɘR��o�Ă��邱�Ƃ�F�߂��B����͑�ςȊ��j��ɂȂ���B�ǂ̒��x�̗ʂ��C�ɘR��Ă���̂��������c�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�C�ݐ������͂�ł���t�F���X�̒������Ȃ�A�܂������A�O�m�܂ōL������Ƃɑ�Ō���^���A�C�m�����ɔ��W����B
�@���܂ŁA�����Ɋւ��镶�ʂ����������Ă������A����͌��q�̓����⌴�q�̑f����A���q�͂Ƃ����n�[�h���ɂ��ď��������̂ł����B
�@���q�͔��d���́A�E���j���E�����A�����Ċj���������ՊE��Ԃŏ펞���̔��M�ʂŁA�t���p���[�Ŕ��d����B�d�͎��v�̑����ɉ����āA���d�ʂ߂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����͂��������Ӗ��ŁA�x�[�X�d���ƌĂ�Ă���B
�@�ُ�i���́j����A����_�����͐���_��F�S�̔R���_�̊Ԃɑ}�����邱�ƂŁA�����q���z�����A�����q���E�������q�j�ɓ�����ʂ����炷���ƂŁA�j����ʂ����炵�A���M�������Ă䂭�B�������≷��~��ԁi�퉷�j�ɂȂ�܂ŁA���ŗ�₵�����Ȃ���A�E�����R���_�̉��x���㏸���n����B���ꂪ�����g�_�E���Ƃ�����ԂŁA�����Ȃ�Ό��q�F������s�\�Ɋׂ�B�S��R���N���[�g����A�ǂ�ǂ�ɗn�����Ă��܂��قǁA�����ɂȂ��ʂ̕��˔\�����o�����B���q�F�͉��������Ă��A���������V�r�A�Ȏ��̂ɂȂ�Ȃ��悤�ɉ��d�ɂ����S�{����Ă���A�Ƃ����b�����܂ł����������B���ꂪ���S�Ƃ�������̈���ł���B
�@���S�Ƃ�������̓�ڂ͉����H
�@����A�������̂��N�����ꍇ�A�����œ����]�Ǝ҂�A�ߗZ�������S�ɑޔ�����ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���E�ꃌ�x���̍������S�������āA���̊�Ŋe�n�̒�~���̌��q�F��R�������i����ĉғ�������Ƃ����̂��e�d�͉�Ђ̎v�f�ł���A���{�E�����}������ɓ��ӂ��A����A���i���悤�Ƃ��Ă���B
�@�������A��ʁA�V�����m�������d�В��Ɍ��������y�������Ƃ́A�ĉғ��̐\���ɂ��Ď��O�̘A�����Ȃ������Ƃ������Ƃł���B
�@������ݒu���Ă��鎩���̂⌧�ȂǂɁA���O����`���邱�Ƃ����Ȃ��A�Ȃ�����ɂ���A�������ɂȂ��Ă���B
�@
�@��ڂ̈��S�Ƃ́A�\�t�g�ʂ̈��S��ł���B
�@����A�������̂����������ہA�ǂ������菇�ŏ���`�B���A�Z�����ǂ��������̎d�������邩�H�@
�@����͔��ɖȖ��Ɍ������āA�l�����邠�����ʂ�z�肵����������P�������{���A����ɔ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�����͂��̃\�t�g�ʂ̈��S�\���ł��Ă���Ƃ͌����Ȃ��B
�@�������̂�3�̗v�����l������B
��͌��q�͔��d�����̃V�X�e�����́A�@��ڂ͌��q�͔��d�����̏]�ƈ��̃~�X�A�����l�Ў��́A�O�ڂ͓V�Ђɂ���Ĉ����N������鎖�́B
�@����3�̎��̗v���̓[���ɂł��Ȃ�����A���̂��N���郊�X�N�̓[���ł͂Ȃ��B����Ȃ��[���ɋ߂��Ƃ��Ă��A�[���ɂȂ�Ȃ��B
�@�����ł���A���̂��N�����ꍇ�ɂǂ����邩�Ƃ������S�����������̑�Ƃ��čl���āA�������Ēu���K�v������B
�@���{�͍��܂ł���3�̎��̗v���ɑ��āA�w�����͐�Έ��S�x�Ƃ����_�b���Y��ł����B�����玖�̂��N�����ꍇ�̑Ή��������ɉ��A�����ɗL���ȃ��E�h�܂̕��p���Ȃ��A���o�H�̎w�����Ȃ��A���˔\�g�U�f�[�^�̊��p���ł��Ȃ������B����C���̑Ή��ɂȂ��Ă����B
�@���S�_�b�����ꂽ���A���̂͋N����Ƃ����O��ŁA�N�����ꍇ�̏��u�̎d����������ʂ��猟�����A�ĉғ��܂ł����ȌP��������K�v������B
�@�V�����m���͂��������\�t�g�ʂ̑Ή����܂߂ď\���������A���߂čĉғ��̋c�_�����藧�Ƃ������Ƃ��������������̂��Ǝv���B
�@�S�������Ă��A�����̍ĉғ��͐V�������S������A���ŏ����̌����Ɍ����ċ�����Ƃ������ƂłȂ���A���̂̃��X�N�͉ғ�����������ɂ��������č��܂��Ă䂭�B
�@�����̗��n�Z�����ĉғ��Ɏ^�����Ă���Ƃ����̂́A�����̗Ƃ������œ��Ă���Ƃ����ȊO�̉����ł��Ȃ��B�܂��͐���������B
�������A��x���̂��N����ƁA�����ԁA�����͔j��Ă��܂��B
����Ȃ�A�����ȊO�̎��R�G�l���M�[���d�����ݓ��ŁA�V�����d�������悤���z��]�����邱�Ƃ�����B
�@ |

 ���[���X�M���𑗂邽�߂̓d���i�L�[�j
���[���X�M���𑗂邽�߂̓d���i�L�[�j �@��v�҂��ԗ삷��s�����C�O����Ƃ₩��������؍����͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�@��v�҂��ԗ삷��s�����C�O����Ƃ₩��������؍����͂Ȃ��Ǝv���܂��B �扑�Ƃ������Ƃł��B����A�w������m�̕�x�ł��B
�扑�Ƃ������Ƃł��B����A�w������m�̕�x�ł��B