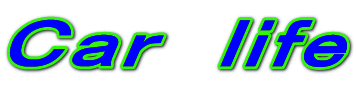
自動車の新しい技術などについて、情報発信して参りま
2025年2月7日(金)
LED非常信号灯
| 愛車、2020年納車のフィット4ハイブリッドが2回目の車検を受けた。今回は何も悪いところがないので部品交換は法定の範囲でやってもらったので、いつもより安く上がった。 法定部品交換は、発煙筒の交換だった。(使用期限は4年、未使用だが廃棄処分)部品代は2700円 LED信号灯があるのを知った。Amazonのエーモン(amon)で691円(送料込)なので買ってみた。 超お買い得価格だ! エーモン(amon)ホームページ https://www.amon.co.jp この商品は、オートバックスでも販売している。 保安基準適合品、内部突起(UN-R21)適合品で、車検対応品。 新車に付属の発煙筒は赤い煙が出るので昼間はよく見えるが、夜は見えにくい。このLED非常灯は輝度が高く、かつ点滅するので、夜は強力な非常灯として威力を発揮するだろう。 発煙筒は新品に変えてもらったので、このLEDランプは、予備として車内に積み込んでおく。 よくできたライトなので、ご紹介します。  これが届いた商品(LED非常信号灯)  箱の中身、非常灯、単4電池2個、使用開始ラベル(メモ) 仕様 ・普通の車の発煙筒ホルダー(直径27mm)に装着可 ・夜間 約200m先まで危険を知らせる ・高輝度LED 9個搭載 ・点灯時間 20時間以上(新品バッテリー) ・ON/OFF スイッチ(黒丸ボタン) を押すと点滅する ・マグネット付きで、車の屋根など鉄板部に吸着、設置できる。(車の窓を開け、屋根に設置できる) ・車検 4年毎に、発煙筒のように入れ替える必要がない。 |
| エンジンは自動車が生まれた時から原動機として使われてきた。その原理は、石炭や石油(ガソリン)等の化石燃料を燃やして回転エネルギーを発生させ、それを駆動力に使う。 エンジンには、蒸気機関車に代表される外燃機関と、車のエンジンの内燃機関があるが、熱効率の点では内燃機関が圧倒的に優れている。ちなみに蒸気機関車の熱エネルギーは10%台に留まる。車のエンジンの熱効率は、ガソリンエンジンが25~35%、ジーゼルエンジンが25~35%程度と言われてきた。しかし技術の進化により、さらに10%程度改善が図られている。 直近は、エンジンのコンピュータ シミュレーション解析ができるようになり一層加速されるようになった。 その大きな進化は、着火方式、燃料供給方式、弁(バルブ)開閉方式、可変圧縮方式、ピストン・シリンダー摩擦低減技術、シリンダー冷却技術、排ガス還流技術、希薄燃焼技術、ターボ技術など多方面にわたる。最近のガソリンエンジンは45%を超えるような高効率エンジンが話題になっている。 車に搭載するエンジンは、加速時の力強さ、定速走行時のフィーリング、高回転時の静かさなどいろんな状況に応じて高次元の要求を満たす必要がある。最近は地球温暖化対策として排気ガス規制が加わり、さらに高い難度の要求が加わる。 それらを満足するため各自動車メーカは独自技術開発に勤しんでいる。ゼロエミッションを謳うEVが注目されているが、電池容量とコスト、さらには充電時間の問題で、一時のような派手な勢いがない。特に日本はハイブリッド車開発で先行し容易に手に入るので、EVへのシフトは進んでいない。 長期的に見ると、2030年前後まではガソリン車からハイブリッド車へ移行し、その後はEVに変わるかもしれない。そのためには、画期的な大容量、低コスト、急速充電可能な電池が望まれるが、現状では未だ『解』が見えていない。 そこで、当分の間は、ハイブリッドによる低燃費、低排気ガスの兼ね合いで凌ぐことになる。 一層厳しくなる排ガス規制をクリアするには、できるだけ薄い混合気(空気とガソリンの混合)を安定してシリンダー内で燃やすことが要求される。しかもエンジン出力を落とさずに。 そのため、ガソリンと空気の混合気を生成する方法として、従来のキャブレータ方式から電子制御インジェクター方式に変わってきた。古くからあるキャブレータは霧吹きの原理で、吸気の負圧を利用してガソリンを霧状に噴射する。構造上、ガソリンの霧の粒は比較的大きく、不揃いになる。これでは緻密な燃焼制御ができないので、電子制御噴射器(インジェクター)が開発された。これはエンジン制御コンピュータの信号で精密に噴射量を制御できる。これでエンジンがプログラムに従い制御できるようになった。 このインジェクターを取付ける場所によりポート噴射と、エンジン気筒内に直接噴射する直噴がある。 ポート噴射は、シリンダーに通じる吸気ポート(空気の通路)にガソリンを微細化した霧として噴射する。マイコン制御によりプログラムされた噴射量を精密に設定できるので、エンジン制御の最適化が行えるようになった。最近の車は殆どこの技術を採用している。 ジーゼルエンジンは高圧噴射器(高圧インジェクター)を使い、軽油をシリンダー内に直接噴射する。 ジーゼルエンジンは圧縮比が20~30と非常に高く、シリンダー内の空気が圧縮されることで高温になる。そこに軽油を霧状に噴射して瞬時に燃焼させる。点火プラグは不要である。高圧高温下で自然着火させる。 ジーゼルエンジンは始動時、(シリンダー内が低温時)、着火しにくいのでヒータで噴射器周辺を暖める予熱器がついている。 ジーゼルエンジンは加速時に黒い煙を吐き出す。これは未燃焼燃料の燃えカスで大気汚染の原因になる。最近は厳しく規制されている。 この黒い排ガス対策として、燃料噴射器を1000気圧程度で噴射する超高圧インジェクターが開発され、しかも精密に噴射量を制御することで黒い煙の発生を防いでいる。さらに排気管途中にフィルターを取り付けてガスの浄化をしている。だから以前のような煙は出ない。同時にNOxという窒素酸化物もフィルターで除去している。 このジーゼルエンジンのインジェクター技術をガソリンエンジンに生かして、ガソリンを燃料噴射器(インジェクター)でシリンダー内に噴射する直噴方式が開発された。ポート噴射方式に比べて混合気の精密で安定した燃焼制御がしやすく、希薄燃焼制御ができる点が優れている。  フィットハイブリッドe-HEV 4気筒エンジンルーム ホンダはハイブリッド車用に開発した2.0Lと1.5Lガソリンエンジンは直噴方式を採用する。特に、次のコンパクトクラスの新型車から1.5Lで初めて採用する。この直噴方式は、ピストンの位置(上死点~下死点)により細かく精密に噴射量を制御でき、最大4回噴射を行う多段噴射方式を採用する。これにより希薄燃焼時も安定した着火ができ出力向上を図っている。 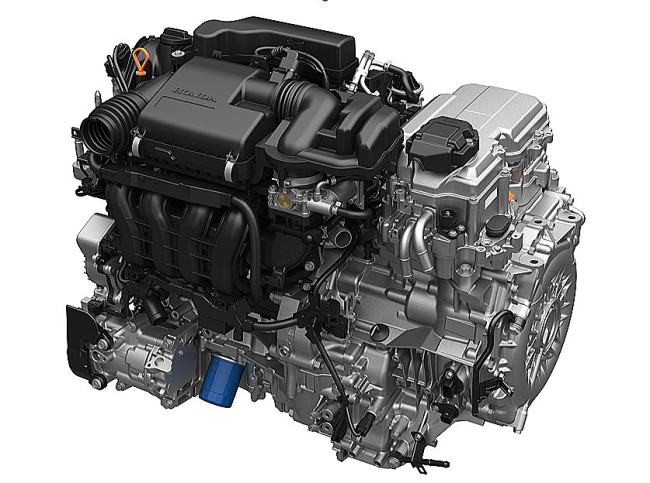 4気筒エンジン+HVモーター機構 この技術のすごいのは、エンジンが3000回転/分(rpm)しているとき、一気筒当たりで着火タイミングは1500回/分となり、1秒間に25回着火(爆発)動作を繰り返す。着火時間は40ms。この短い時間内に4回、精密にガソリンを噴射する。そういう高速動作を制御することができる技術はすごい。 分野は違うが、微細な液体の吐出事例として、パソコンに接続して使うプリンターとして、インクジェット方式がある。インクジェットプリンターのヘッドは、ピコリットル単位の微細なインクを超高速でプリンター用紙に噴射して、カラープリントを行なう。1ピコリットルは、1ナノccであり、1ccの10-9という超微粒子になる。これはカラーインクを1mmの1/100から1/1000の小さな粒(水蒸気に匹敵するぐらい)にしてノズルから噴出させ印画紙にカラーをプリントする。以前の『カラー写真』と遜色がない印刷ができるようになった。 カラープリントは、CMY(C:シアン(青)、M:マゼンタ(赤)、Y:イエロー(黄))の3原色で、フルカラーを表現している。わずかなカラーインクの吐出量の誤差があれば、奇麗なカラーの表現ができない。最近のインクジェットプリンターのプリント画質は非常にきれいになった。技術の進歩のおかげだ。 超微細な吐出量を制御できるようになったのは、デジタル技術の進化の賜物だ。 世の中には、考えられないような商品が身近にある。 マツダはエンジンに拘った開発を続けているメーカだが、通常、10前後の圧縮比を、スカイアクティブXエンジンでは圧縮比を16.3に上げ、ガソリンの理論空燃比14.7以上にし、超希薄燃焼を行わせる技術を開発した。ジーゼルエンジン並みの圧縮着火方式であるが、ガソリンは軽油に比べて着火し難いので、スパークプラグを使用し、希薄ガスを確実に着火させる。この独自の方法をSPCCI(Spark Controlled Compression Ignition)と呼んでいる。高圧縮希薄燃焼方式SPCCIエンジンはハイオクガソリン仕様のみ。ガソリンが高騰している中で、ちょっと気にかかる点だ。 ニッサンは独自の可変圧縮機構(Variable Compression ratio engine)を開発し、世界で初めてVCエンジンの量産技術に成功した。以下は、ニッサンのNET情報より転記。 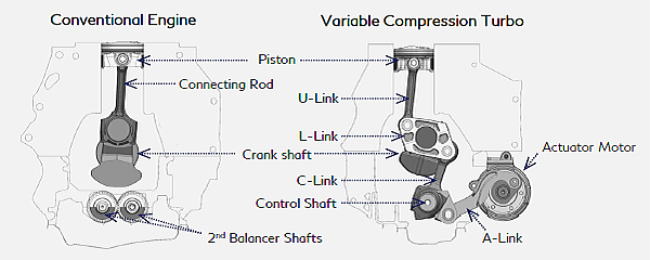 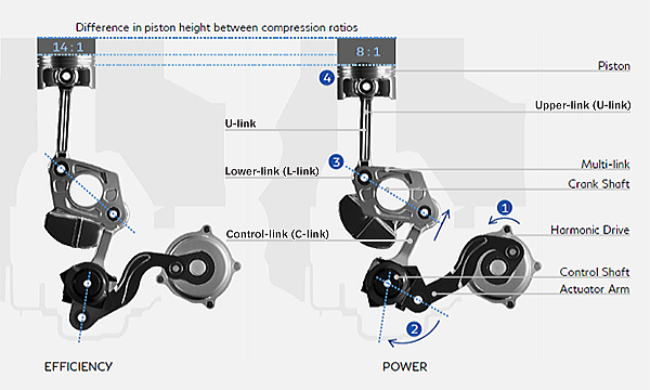 VCターボエンジンは、ピストン上/下死点位置を連続的に可変するマルチリンク機構を採用し圧縮比を自在に切り替えることで、トレードオフの関係にある低燃費とハイパワーを同時に実現する量産型世界初のエンジンです。 ガソリンエンジンは、シリンダー内に取り込んだ混合気を圧縮し点火し燃焼させます。 このとき、高圧縮ほど高効率運転ができるが温度上昇により異常燃焼(ノッキング)が発生するため圧縮比には限界がある。 巡航時など吸気量が少ない時は限界圧縮比は高く、逆に加速時など吸気量が多い時は限界圧縮比は低くなる。特にターボによる過給された混合気を吸気をしている状況では、限界圧縮比はさらに低くなる。このように、負荷の状況に応じて、理想的な圧縮比は変わる。 従来のエンジンは、ピストンとクランクシャフトが直接コンロッドでつなぐ構造のため、圧縮比を変えることはできません。 VCターボエンジンは、コンロッドに替えてマルチリンク機構でクランクシャフトを回転させる構造とし、リンクの端点をアクチュエータで可動にすることにより、ピストンとクランクシャフト間の距離を変化させ、圧縮比を8:1から14:1の間で無段階に自在に可変できる。ドライバーのアクセル操作に対応し、最適な圧縮比へ変化させる。 ・圧縮比の変更が必要な場合、ハーモニックドライブがアクチュエータアームを動かす ・アクチュエータアームがコントロールシャフトを回転させる ・コントロールシャフトの回転によってLリンクを動かし、マルチリンクの角度を変える ・マルチリンクはシリンダー内のピストンストロークの上下位置を調整し、圧縮比が変更される リンク配置の最適化 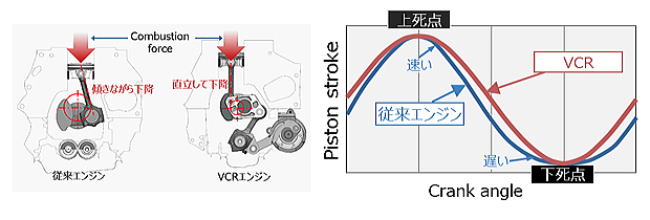 ピストンが上下した際のアッパーリンク(U-link)の角度変化が小さく、より直立したままスムーズに下降することで、シリンダー壁面との摩擦を低減して燃費向上に貢献します。また、ピストンの上下動が上死点と下死点で対称となり、振動を抑制することができます。 技術の仕組み 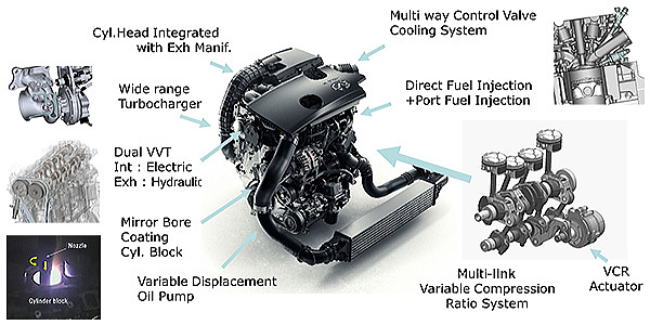 VCターボエンジンは、新開発の高効率ワイドレンジターボと過給圧をきめ細やかにコントロールする電動ウェイストゲートにより、ターボラグを抑え高効率に過給し、瞬時に大出力を発生させる。低負荷時は電動VTCによりバルブタイミングを連続的に変化させ、アトキンソンサイクルによりポンピングロスを低減し、高圧縮比による高熱効率の達成と組み合わせることで低燃費を実現する。 VCターボは1998年より研究を開始。リンク機構による可変圧縮比方式を開発、リンク配置の最適化、高度な解析技術による部品形状の最適化、高精度熱処理などの工法革新を経て、世界初の量産化を実現。 少々難しい内容です。圧縮可変の考え方は古くからありますが、量産化したのはニッサンが初めてです。 回転機構の構造が複雑になりますので、コストや耐久性、寿命などの点で注目すべきエンジンです。 トヨタ ヤリス等に搭載した1.5Lダイナミックフォースエンジン(M15A-FKシリーズ)は3気筒であった。トヨタは40%を超す高い熱効率をたたき出した4気筒2.0Lエンジンをベースに、1気筒省き3気筒の新エンジンを開発。これを1.5Lダイナミックフォースエンジンと称して、ヤリス、ヤリスクロス、アクア、シエンタなどコンパクトカーに搭載した。このエンジンはロングストローク、ポート形状改善、直噴インジェクターなどによる高速燃焼を実現し、熱効率は40%を超えるということだった。燃費と馬力の両立を図った。確かにヤリスはキビキビと走るという評判で、特にハイブリッド車は大ヒットモデルとなった。  ヤリスに搭載した3気筒エンジン 縦長に見える。実は、2.0L 4気筒エンジンから、1気筒省いたエンジン。 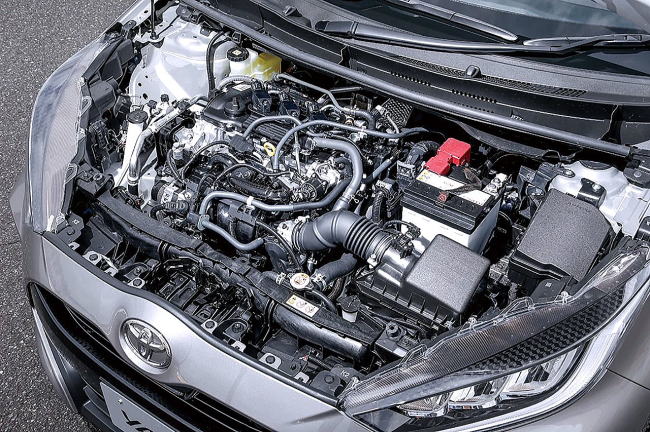 ヤリスの3気筒エンジン搭載エンジンルーム エンジンの上部に細いパイプが何本も配置され、ゴチャゴチャして見える。余り見栄えが良くない。 3気筒ダイナミックフォースエンジン(M15A-FXシリーズ)はコンパクトカー用エンジンの定番として使われると思っていた矢先に、何故か、新型1.5Lエンジンは4気筒に戻した。3気筒エンジンは4、5年の短命寿命に終わる。 新型エンジンは4気筒で、ショートストローク化し、エンジンのサイズを小型化し、高性能化を図った。 3気筒を4気筒に戻したわけは、エンジン車の場合 ①低回転時(信号待ちなど)のエンジンの振動が大きい。 ②高速時の馬力不足 で、ユーザから厳しい指摘があったそうだ。 しかし、ハイブリッド車の場合、①②ともモータアシストのおかげで、あまり気にならないそうだ。 やはり、3気筒の振動や騒音が車の品格を落とすことになって、走りはいいがやかましいという評判に3気筒では無理か?という判断で、4気筒に戻すことになったのだろう  新型プリウス エンジンルーム 1.5L 4気筒エンジンを搭載 新型プリウスは車高が低くスポーツカー風のカッコいいデザインに仕上がっている。大変評判が良い。大きく傾斜したフロントガラスなどデザイン優先をしたので、乗る場合はちょっと気が引ける。この低い車高を実現できたのも、エンジンを4気筒に変え、高さを低くしたおかげとか? 同じ1.5Lであれば、 3気筒エンジンはロングストロークになるので、トルクが稼げる。しかし、ハイブリッドが主流になる現状では、トルクより小型化を図りたいという意図があったようだ。それで4気筒エンジンに戻した。エンジン開発には、数百億円の費用が掛かると聞いた。この巨額の開発費を掛けられるのは、資金が潤沢にあるトヨタだからできる技だ。ユーザにとっては素晴らしいことだと思う。 |
2025年1月19日(日)
コンパクトカーのエンジンは、やはり4気筒に決定?
| 前回は[コンパクトカーのエンジンは3気筒に変わるか? という視点でまとめた。しかし、トヨタ自動車は、新世代エンジンを4気筒エンジンにすると発表した。これは注目に値する。 トヨタが前モデルで、1.5Lエンジンとして3気筒エンジンを選択。開発した時点では、『3気筒エンジンが1.5Lエンジンとしては4気筒に比べて優れている』点をアピールした。 一方で、3気筒エンジンは、コンパクカークラスとしてはエンジンフィーリング上、不利と判断したようだ。 3気筒エンジンは軽自動車では定番のエンジンで、1000ccクラスまでの車では優れた点を生かせるのだろうが、1500cc位のエンジンになると、一気筒当たりの容量が大きくなり、爆発力が強くて、3気筒ではそのトルク変動による振動を抑え込むのが難しいのだろう。バランスシャフトを挿入し、振動を打ち消す方法もあるが、余計な機構を追加するより、4気筒にしてスムーズなエンジンフィーリングを得る方がベターと判断したようだ。 さて、注目すべきは、トヨタとホンダの2大メーカが今後のエンジンの方向づけを行っている。両社とも、30年代までは、ハイブリッドが主流になると見ている。EVについては否定的な表現はしていないが、いろんな面で時期尚早ということかと思う。 トヨタ、ホンダのハイブリッド車用エンジンは2.0Lと1.5Lの直4エンジンに統一。 トヨタTHS、2.0Lは直4NAとターボの2種、1.5Lは直4NAとターボ 1.5L3気筒エンジンは短命に終わる。4気筒化により、ショートストローク化し、体積で10%、全高で10% 小型化を図る。出力、熱効率を3気筒エンジンより向上させる。 エンジンの小型化により、ボンネットの高さを低くでき、デザインの自由度が増える。燃費は12%改善。 ホンダeHEV、2.0Lは直4NA(直噴)、1.5Lは直4NA(直噴) 現行の2.0Lは直噴とポート噴射の2種類があるが、新型は直噴に統一。吸気ポートを工夫し気筒内に 強いタンブル流を生成させ、燃費効率の向上を図る。直噴の噴射タイミングは4段の多段噴射方式。 1.5Lはポート噴射方式から直噴に変更する。2.0L同様に多段噴射方式、吸気のタンブル流の発生等に より燃費とパワーアップを図る。 一覧表にまとめると
車は、地球環境保護のため排気ガス規制強化が続いている。その解として。EVが導入されて来たが、 EVは電池容量(走行距離)、充電時間、コストの課題が残っている。 ハイブリッド車は、このEVの課題を解決するまでのつなぎとしての役割を果たすことができる。 そこで、ハイブリッド車のエンジンとして、最適なエンジンを求めて開発に取り組んでいる。今回、トヨタの3気筒エンジンから4気筒エンジンへの回帰は、車に要求されるスペックを満たしながら、ユーザニーズを満足するための決断だろうと思う。 トヨタは公式的には、1.5Lの3気筒エンジンは、4気筒エンジンに比べて燃費や出力面で優れているというのが、3気筒エンジンを導入した時点でのアナウンスだった。 今回、4気筒エンジンに戻した時のアナウンスは、4気筒エンジンはショートストローク化により、体積で10%、全高で10%小型化できた。出力、熱効率を3気筒エンジンより向上した。これによりボンネットが低くでき、デザインの自由度が上がる。また空力の改善で燃費は12%改善したとなっている。 3気筒を4気筒に変更した本当の理由は書かれていない。 本当の理由は、3気筒エンジンのトルク変動の振動、騒音が主原因だと思われる。 現に、『ヤリスは、走りが良いが、やかましい』との評判だ。 車を買う際は、しっかり試乗して、比較して、納得して 決めるように!!!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年8月15日(木)
軽自動車は3気筒エンジンが定番になっている。
コンパクトカーでも3気筒エンジンが増えてきた。
今後、3気筒エンジン搭載が増えるのだろうか?
| 軽自動車はホンダ、スズキ、ダイハツの御三家はもちろん、ニッサン、マツダ、ミツビシ、スバル(スズキ、ダイハツのOEMが多い)すべて3気筒エンジンを搭載している。以前、スバルが4気筒エンジンを積んでいたが、自社開発を止めてOEMになり、今は3気筒エンジンになっている。 3気筒エンジンは軽自動車専用エンジンと思っていた。ところが、最近、トヨタのヤリス、アクア、ニッサンノートなどコンパクトカーが4気筒から3気筒エンジンに代わってきた。 3気筒エンジンは、軽自動車に乗れば分かるが、エンジンを吹かすと振動や騒音が大きくて、品位が良くなく、普通車には向かないエンジンだと思っていた。 ところが、トヨタがヤリスに積み、ニッサンがノートに積んで売り出したのには驚いた。 なぜ、普通車の定番だった4気筒から3気筒に変えたのか? そのわけを調べてみた。 最近、VWやBMWも3気筒エンジンを積んだコンパクト車を発売している。1000cc~1500cc程度のエンジンでは、3気筒に何かメリットがありそうだ! 欧州は自動車の排気ガス規制が一段と厳しくなり、ジーゼルエンジンが注目されたが、ジーゼル車も規制をクリアが難しくなり、欧州やアメリカや中国は、EV(電動車)に大きく舵を切った。 EVは排ガスはゼロなので、規制をクリアできる。 理想的な自動車と言われていたが、EVは三つの大問題を抱えている。 ①バッテリー容量;満充電でも走行距離が短い ②充電時間;充電スタンドが少なく充電時間がかかる ③バッテリーコスト;車の値段が高い 昨年冬の大寒波に遭遇して、EVが立ち往生する事故が多発した。 マイナス10~20℃以下になる北国では、極端にバッテリー容量が下がり、スペックどおりの走行距離が確保できない。立ち往生事故が続出し大混乱になった。厳寒の地で止まると人命に直にかかわる問題だ。 しかも、暖房を入れると、さらに走行距離が短くなる。そういう事故が多発した。 日本は排ガス対策としてハイブリッド車の開発を行い、トヨタ自動車は世界に先駆けプリウスを発売した。曰く、『21世紀に間に合いました!』 世界中に販売したプリウスは次世代の車として絶賛を浴び、特にアメリカでは大人気となった。余り、一人勝ちしたので、海外自動車メーカはハイブリッド開発を諦め、ハイブリッド車の先を行く車としてEVを位置づけ、開発に全力を投じてきた。 EVは、エンジン車に比べ、部品点数は1/3になり、車の開発は特に難しい話ではない。ただし、大きな課題として、巨大なバッテリーが必要になる。 車は、コンパクトカーでも1トン前後、普通車は1トン半以上もある重量物である。それを一気に加速し、時速100km以上で連続して走らせるには強大な馬力のモータ、それを駆動するための大容量バッテリーがいる。 しかも、短時間で繰り返し充電ができ、長寿命でなければならない。 今まで、EVが実用化できなかったのは、これらの問題がクリアできなかったからだ。 この条件に見合うバッテリーは今のところ、リチュウムイオン電池しかない。そこで、世界中の自動車メーカはもちろん、電機メーカ、その他のメーカがリチュウムイオン電池の開発にしのぎを削ってきた。 リチュウムは金属の一種で、化学反応が激しく起きる物質であり、取扱が極めて難しい。しかし、その反面、電池としての性能は素晴らしい特性を発揮する。従来、車に搭載してきた鉛バッテリーの比ではない。 リチュウムは希少金属(レアーメタル)で、中国や南米など限られた地域にしか存在しないと言われ価格的には高価な材料である。 ガソリン車は満タンで、800km~1000kmほど走ることができる。少なくとも、EVも満充電すれば数百km(400~500km)以上、走行できなければ安心して使えない。 現状は400km程度であり、しかもエアコン(特に暖房)を入れると、走行距離が数十kmほど減る。だから厳寒の地で、前記のような立ち往生が多発した。 (注釈)ニッサン SAKURA(軽自動車);走行距離:180km ニッサン リーフ(コンパクトカー);走行距離:322~458km EVのバッテリーは、車のフロア(床下)に収納されている。リチュウムイオン電池は頑丈なアルミケースに収納し、発火や漏電がないよう万全の安全対策が施されている。 リチュウムイオン電池は1個で約3ボルトなので、百数十個直列に接続されている。(約3百数十ボルト) その電池コストが、EVの全材料コストの1/3~1/2程度かかるようだ。 車としての『走り』は、モータ駆動の特徴である大トルクにより大変気持ちがよい加速が得られ、静かな走行が可能である。 しかし、現状のEVは整理すれば、 ①走行距離が短い(満充電でも) ②充電時間がかかる(高速充電でも数十分かかる) ③充電スタンドが少ない(特に地方に行けば、・・) ④バッテリー寿命が気にかかる(約10年と言われているが、・・・) ⑤車の価格が高い などがあげられる。特に①②③は、ユーザとして致命的な問題だ! 結論;現状、EVは未完成商品だ! 話を本題に戻す 世界中で地球環境保護のため自動車の排ガスが問題視され、エンジン車からEVに移行する動きが激しくなる中、EVの大きな課題が注目されてきた。EVを購入するのに躊躇する人が増えている。 そこで、エンジン車が見直され、エンジン車でもできるだけ排ガスを出さない対策が検討されてきた。 一つの案は、4気筒エンジンを3気筒にすることだ。 例えば、1500ccエンジンで考えると、4気筒エンジンなら気筒当たり375ccとなる。3気筒にすると、気筒当たり500ccとなる。トルクが太く、エンジン効率は気筒当たり500cc前後が一番良いらしい。 (参考)トヨタ ヤリス(3気筒エンジン)と、ホンダ フィット(4気筒エンジン)仕様
3気筒エンジンはシリンダーが少ない分、幅を縮めることができるので、コンパクトなエンジンが造れる。これはハイブリッド車には電装品が多くなる分、狭いエンジンルームに収めるにはメリットがある。 また、エンジン部品(ピストン、バルブ(弁)、クランクシャフト、点火装置等)が減り原価を下られる。 だから、軽自動車には3気筒エンジンが定番になっている。 しかし、良いこと尽くめの話はない。必ず欠点もある。 それはエンジントルクの脈動による振動が増えること。 軽自動車に乗ればすぐ気づくが、独特の振動と、騒音が入って耳障りだ。これはエンジンが回転する際に生ずるもので、振動、騒音対策を十分施さなければ、『やかましい!』ということになる。乗用車としては余り品格が良くない。 ヨーロッパ車やトヨタのヤリス、ニッサンのノート、スズキなどの3気筒エンジン車は基本的な振動・騒音課題を抱えている。 そこで、普通車としてどう品格を保つか? 車の雑味?をどう処置するかだ。 徹底して、振動・騒音対策をすれば、4気筒並みに抑え込むことができるが、それにはコストがかさむ。 トヨタは次期コンパクトカー(ヤリスなど)から再び4気筒に変えるという発表をした。 ヤリスがよく売れているにも拘らず、4気筒に戻すことは3気筒の限界に気づいたのかも知れない。 ホンダは軽自動車N-BOXでトップセールをやっているので、3気筒エンジンの良し悪しが分かっている。だから、FITをはじめ普通車は4気筒エンジンを続けている。 ニッサンはノートe-Powerが評判になりよく売れている。e-Powerは単純なシリーズハイブリッド方式で、エンジンは発電専用なので、エンジンや発電モータの効率がいい回転数付近で使用するので、3気筒の雑味が生じる振動や騒音に対する防振、防音対策は比較的やりやすいので、上質の車に仕上がっている。 そう考えると、トヨタのヤリス、トヨタハイブリッドシステム(THS)はシリーズ・パラレル方式なので、エンジンが駆動にも関わり広い範囲の回転数で稼働するため、3気筒の振動対策が難しい。 ヤリスは、エンジンが力強くよく回るが、半面『やかましい』、『振動が大きい』という話はよく聞く。 なるほど! 納得 |
2024年8月6日(火)
新型ガソリン車にアイドリングストップが付かなくなるわけは?
"アイドリング ストップ"が人気ない!
| 最近、新型車でアイドリングストップ機能が廃止されている! 一時期、『アイドルストップ機能』は、省エネと地球環境保護のための排ガス削減対策として、セールスポイントとなり、競って車に搭載されてきたが、ドライバーはこの機能に不満を抱いているようだ。 ドライバーの不満点は、 ①エンジンの始動のたびに「キュルキュル」と音を出し、ブル・ブルッと揺れて煩わしい。 ②専用バッテリーは、1.5倍ぐらい高価で、バッテリー寿命が短い。 場合によるが、2年ほどでダメになる事も。 ③期待したほど省エネ効果がない。(精々、4~5%程度か?) 等々 トヨタは、新型ヤリス、新型RAV4、新型カローラ(ガソリン車)で、アイドルストップ搭載を止めた。その理由は、燃費向上が4~5%位であり、この程度なら新型エンジンで改善ができ、アイドルストップのメリットがないと判断した。加えて、運転フィーリング的にも良くない。 ホンダは軽自動車、フィットなどはアイドルストップキャンセルスイッチを着けているので、ユーザが自由にキャンセルできる。(エアコンを入れるとアイドルストップしない) アイドルストップ車は、バッテリーが大きくなる。 信号待ちが多い場所では、たびたびエンジンが停止するので、再スタートの回数が増える。スターターは大電流が流れるので、バッテリー負荷が大きく寿命が短くなる。その対策としてバッテリーメーカーはアイドルストップ車専用バッテリーが販売されているが、サイズが大きく、重く、値段が1.5倍位高い。 フィット3は、ディーラで交換した場合は3万円もする。非常に高価になる。 アマゾンでは、Panasonic製で1.6万円で売っているが。これが普通仕様なら、1万円。 ハイブリッド車は、エンジンスタートは、走行用大容量リチュウムイオンバッテリーで行なう。 エアコンのON-OFFに関わらず、常時アイドルストップが働く。エンジンスターターは発電モータでエンジンスタートするので殆ど振動はない。やはりハイブリッドは素晴らしいシステムだ。 詳細資料 Amazon 価格では、 Panasonicバッテリー 容量の違いで2種ある。いずれもアイドル・ストップ対応品 ・CAOS Blue Battery N-M65/A4 ¥10,432 11.0kg 12.9×19.7×22.7mm ・CAOS Blue Battery N-N80/A4 ¥16,991 12.5kg 12.9×23.8×22.7mm フィット3 バッテリー推奨品 N-N80/A4 (アイドルストップ車用) 我が家は、2台のフィットに乗っている。 ガソリン車(フィット3)は、常時、アイドリングOFFに設定している。 その理由は、 ①エアコンは常時ONで使う。 ②近所に買い物に出かける時に使うので、ガソリン代は気にしない。 ③信号はほとんどない。 だから、アイドリングストップ機能は不要。 今は、N-M65/A4を搭載中。 このバッテリーもアイドリングストップ用となっている。容量が少し小さいだけ。(軽自動車用?) アイドルストップさせないので、これで十分なはずだ! この猛暑にエアコンをガンガンかけても正常に動いている。 さて、7月交換したので、何年持つか? |
2024年3月6日(水)
本格的なEVになれそうな全個体電池が現れる!
| EVはまだ未完成な状態だと、3月4日に書いたが、少し先の光明が見えてきたようだ。それが全個体電池と言われるものだ。従来のリチュウムイオン電池は電解質に有機溶剤を使って、電池内のイオンの流れを円滑にしていた。この有機溶剤は液体なので、温度による収縮があり、経年劣化も起きやすく、極低温状態では電池として十分な性能が出せなかった。この電池をEVに搭載すると、必然的にいろんな課題が生じる。 そこで、リチュウムイオン電池に代わる新しい電池が生まれることを期待していたが、やっとその解が見えてきたようだ。それがリチュウムイオン全個体電池というもので、電解質に全く液体を使わない構造で電池を造っている。これが全個体電池と言われるもの。 衝撃に対して安全で、出火の心配もなく、温度特性もよく、電池容量も大きい優れモノだ! それが出光とトヨタ自動車の共同開発で実現し、量産は2027年頃と言われてる。その記事を見つけた。 内容は要約して下記のとおり。 トヨタと全固体電池で組んだ出光、技術トップが明かす苦節20年 両社は2023年10月に共同会見を開き、全固体電池を搭載した電気自動車(EV)を2027~2028年に市場投入すると宣言。約10年間一緒にやってきた。 全固体電池の技術のポイントは擦り合わせだ。だから、当社だけトヨタだけでもできない。技術をどれだけオープンにして一緒にやるかが大事だった。材料の供給に向けて、年間で最大数百トン規模の硫化物系固体電解質を生産するパイロットプラントを出光興産の千葉事業所内に設ける。 ぜひ、この全個体電池が行き詰まり感を漂わせているEVを蘇らせてほしい。それまで、また別の発見があるかもしれない。開発者の挑戦は果てしなく続くものだ!! |
2024年3月4日(月)
ちょっと待て! EVは未だ時期尚早だ!
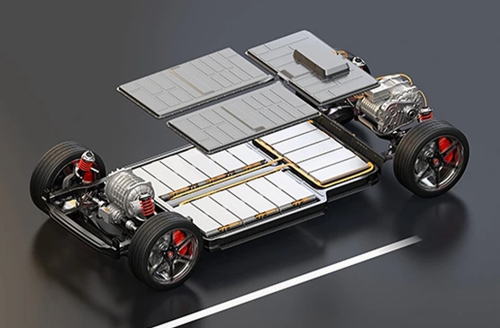
| このところ、アメリカやヨーロッパ各国で、EVの販売に急ブレーキが掛かっている! アメリカのテスラが既存のエンジン車を抜き去りEVで独走し販売を伸ばしてきた。このEV化の流れに対し、世界の自動車各社は競ってEV開発を進め、EVを販売するようになった。各社は『今後、エンジン開発を止め、EVに特化し開発リソースを絞る』というコメントまで出した。EVオンパレードの状況になっていた。その中で、トヨタ自動車だけが、『EVも良し、エンジン車も良し、ハイブリッド車も良し』の三方良しの方針を守っていた。トヨタ自動車会長の豊田章男氏は「一気にEVにはならない」と言ってきた。その意味は将来EVに変わることは否定しないが、現状では未だいろんな課題があるという意味だった。それが今、ずばりと当たっている!!! EVは電池とモータで走る車だから、エンジン車に比べて部品点数が1/3から1/4と少ない。しかも、エンジンのように複雑なメカや、高精密加工や、製造ノウハウが必要でなく、新規参入の壁は高くない。特に中国のような自動車産業の後進国は、数十社以上の多くの新参メーカが生まれ、あっという間にテスラの領域までを脅かすまで成長した。 ところが、この半年間で、車のユーザのEV評価が著しく変化し、EVの販売に暗雲が立ち込めてきた。そのトリガー(要因)になったのは、この冬の寒さであった。ヨーロッパやカナダやアメリカ合衆国など北の地方では、氷点下数十度という寒さにより、途中で車が止まり、暖房もできないような過酷な状況に追い込まれた人が沢山居た。これはバッテリーが外気温の極端な低下により機能不全になったことが原因だ。EVは主電源にリチュウムイオンバッテリーを搭載している。バッテリーはリチュウムの酸化・還元反応で生じる電位差により電圧を産む。この化学変化は温度が下がれば活性化が落ち、そのため電圧が低下し、さらに電流容量が下がり、EVのモータを駆動する電力が低下する。そうなればEVは走れなくなり、走っても距離が極端に短くなる。これでは車に安心して乗ることはできない。命にも係わる。そういう厳冬の状況を経験し、アメリカやカナダやヨーロッパでEV離れが急速に拡大している。 一方で、中国のEV離れは少し背景が違ってくる。中国はバッテリー材料のリチュウム鉱床が早くから発見され、それを使い、リチュウムイオン電池の生産を始めていた。電池の製造技術は先行する海外製品のコピーをして、次第に実力をつけ、今現在では、先行する電池メーカと対峙できるようになった。その中国製の安いバッテリーを搭載し、安いEVが市場に出回った。 電気自転車(電動二輪車)は既に30年ほど前、上海に行った時、街中を走っている姿を見た。しかも二人乗りで走っていた。日本ではホンダのカブに代表される原付オートバイが多いが、中国では小型エンジンがうまく作れないので電気自転車を販売し、目に付いたことを覚えている。 廉いリチュウム電池とモータを組み合わせるだけで造れるEVは、自動車後進国の中国にとっては自動車産業に進出する千載一遇のチャンスだった。中国人は儲かると分かると、みんなが飛びついて取り組む。 その結果、300社におよぶEVメーカが誕生した。日本電産(NIDEC)はそういう新参メーカにEVのドライブアクスル(モータ・ギアーと制御システムを組合せたもの)を納入し、売り上げを伸ばした。 急激に成長したEVメーカとして、BYD(比亜迪汽車)が中国国内から世界市場に躍り出た。株の時価総額で見ると、テスラが97兆円、トヨタが35兆円、そしてBYDが20兆円に上っている。その他、新興メーカとしては、NIO、Xpemg、LiAuto等がある。中国はEVで世界を制覇しようと考えていた。 アメリカやヨーロッパの巨大自動車メーカは、ジーゼルエンジンやガソリンエンジンの排気ガス(炭酸ガス、NOx等)による地球温暖化、気象変動に対し、このままでは地球の自然環境保護ができないという立場から、排ガスゼロ(ゼロエミッション)のEVに切り替えようという戦略で強力に舵を切った。これにいち早く対応したのがテスラだった。過去の自動車業界とのしがらみがなく、新規参入の利点を生かし、瞬く間にブレイクした。ヨーロッパのベンツ、BMW、VWや、アメリカのGM、フォード等の巨大自動車会社もエンジン車から完全にEVへシフトする戦略を打ち出して取り組んだ。 一方、日本はトヨタ自動車がプリウスを1997年に発売して既に26年が経ち、ハイブリッド車のノウハウを積み上げてきた。世界の自動車メーカは今からハイブリッド車を追いかけてもトヨタに勝てないという判断と、いずれハイブリッドからEVに代わる。それなら一気にEVにシフトした方が勝ち目があるという判断のもとに一斉にEVに開発リソースを振り向けた。そして、EVが各社から発売され、EV時代が到来した。 ところがこの冬の厳寒期を越えて、一気に風向きが変わってきた。次期自動車はハイブリッドになると。そうは言っても、車の将来はEVであることに間違いはない。ハイブリッドはそれまでのつなぎという立場だ。 今、トヨタのハイブリッド車がアメリカで引っ張りだこになっているようだ。 なぜ、ハイブリッドが見直されたのか? 現状のEVは、普通に使う車としては不完全な商品。安心、安全に乗るにはまだまだ課題が多い。 EVの課題は何か? ① 車の値段が高い EVは複雑なエンジンがないので安くなるはずだが、リチュウム電池が非常に高価。リチュウムは希少金属で、世界中で数か所しか鉱床がなく、量的に少ないので非常に高価。それを膨大な台数の車に大量に使うには価格的に無理がある。 ② 走行距離が短い(長距離を走るには大容量バッテリーが必要、そうなると一層高価になる) 1トン以上の自動車を何百kmも走らせるには、膨大なエネルギーが必要になる。ガソリンならできる。現状のリチュウムイオン電池では、車重とコストとの兼ね合いの限界がある ③ 充電時間が長い ガソリンや軽油ならスタンドで、数分で満タンにできる。EVは高速充電スタンドでも数十分もかかる。 ④ 充電スタンドが少ない(充電インフラの問題) ガソリンスタンドは、どこにでもあり油切れの心配はいらない。受電スタンドはまだまだ少ない。特に急速充電スタンドはさらに少ない。 EVが普及するためには? ・バッテリーの革新的改良が必要だ! トヨタやホンダ、ニッサンが進めている全個体リチュウム電池や、革新的な電池が発明され、『軽量、小型、大容量、長寿命(繰り返し充放電可能)、短時間充電、優れた低温特性、その上に値段が安い』という 新電池の出現を待つことになる。これは非常に難しい課題だ。現状で、少しずつ先の明かりが見えつつある。その時が本格的なEVの出番になるだろう。多分、2030年前後になるのではないか? ・もう一つ、充電インフラの整備・拡充が必要だ! ガソリンスタンドと同じようにセルフで充電でき、短時間で満充電できる高速受電スタンドの整備が要る。EV時代になると、充電スタンドがガソリンスタンドと同様に沢山必要になる。どこでもすぐ立ち寄れて充電できる環境整備が要る。電力の供給、すなわち発電、送電、変電所のインフラも同時に整備が必要となる。日本で考えると、乗用車がEVに代われば、大雑把な計算で、EV一台当たり平均走行時1kWの電力を消費するとして、500万台のEV車が運行していると、500万KWの電力を消費する。これは100万KW級の原子力発電所が5か所必要になる。原発は危険な設備であり増設は認められないのなら、太陽光発電や風力発電による自然エネルギー利用の発電を進めなければならない。こういう議論も、ガソリン車がEVになれば電力供給インフラとして整備することが必要になる。 EVの普及はそう簡単な課題ではないことが理解できる。 |
2024年1月31日(水)
またまた、トヨタ! ヤリス、アクア、シエンタ 79万台の大リコール
トヨタ非常事態では!!
| トヨタ自動車は、車体とタイヤをつなぐ装置の一部に不具合があったとして、約79万台のリコールを国土交通省に届け出た。 リコールの対象は「ヤリス」と「アクア」、「シエンタ」の3車種で、2019年12月から今年1月19日までに製造された79万台あまりです。 国交省によりますと、車体とタイヤをつなぎ、地面からの衝撃を緩和する「ロアアーム」という装置の一部に不具合があった。 凍結を防ぐために道路などにまく融雪剤が頻繁にかかると、亀裂が生じて走行できなくなる恐れがある。 これまで20件の不具合が確認されていますが、事故は報告されていません。 トヨタは交換用の部品の準備ができ次第、無償で交換するとしています。この3車種については、去年6月にも同じ部品で別の不具合があり、リコールを届け出ています。 これだけ、立て続けに、不正や不良が起きるのは前代未聞ではないか? そうなると、たまたまではなく、起きるべくして起きたと言えそうだ。これは企業体質の表れだと言えそう。 小生が気にかけてきたことは、トヨタの車種展開(モデル数)が非常に多いことだ。トヨタ自動車販売ルートは、トヨタ店、トヨペット店、カローラ店、ネッツ店、さらにレクサス店の5ルートがあり、、レクサス店を除く4系列店は全車種を取扱、販売できるように改められた。これで各販売店は売りたい車を自由に販売できる。店は互いにしのぎを削り商売競争を展開してきた。 同時に、トヨタ自動車は販売店の販売力を後押しするため、非常に多くの車種(モデル)を投入し圧倒する販売力で他社を凌駕してきた。ここまでは企業努力であり企業競争である。 しかし、この異常とも思えるモデルを開発するためには、物凄い開発力が必要になる。他社がまねのできない開発力を駆使し、世界一のトヨタだからこそできる圧倒する戦略で攻めてきた。自動車業界二位のホンダに2倍の生産、販売をやってのけている。 このツケが今回の一連の不祥事や品質不良問題の起因になっているような気がする。 自動車は4万点の部品から成り立っていると言われる。EVになると部品点数は半分になる。いずれにしても膨大な数の部品を組合せて成り立つ商品である。その開発にはすごい人的パワー、技術力を駆使し、しかも商品は絶対安全、安心をクリアしなければならない。そういう規制された商品を湯水のごとく開発、製造することは至難の業ではできない。法規で規制された技術基準、品質基準は絶対遵守しなければならない商品である。 現在の自動車産業は、100年に一度の転換点に差し掛かっていると言われる。EV化、排ガス対策、安全運転支援システム、省燃費化、など課題が山積している。 こういう様々な状況下で、さらに開発期間の短縮、コスト削減が求められているので、現場の対応力が限界に来ている感じがする。 そういう状況下では、守るべき事柄の順序(プライオリティ)が崩れることがある。絶対守るべき規制基準を見失い、開発、日程、コストが優先されたのではないか? これは、企業の掟、経営方針に対する齟齬となる。 世界NO.1のトヨタ自動車及びその関連会社に次々と起きる不祥事を見聞きして、以上のような印象を持っている。 日本の製造業を代表するトヨタ自動車だから、抜本的な対策を打って、素晴らしい会社に生まれ変わることを期待している。 |
2024年1月31日(水)
トヨタ自動車 佐藤社長の記者会見
(日経クロステック記事より)
| なぜトヨタグループで不正が続くのか? 日野自動車とダイハツ工業に続いて不正の調査報告書を公表した豊田自動織機。世界最大の自動車メーカーである上に、足元の業績も極めて好調なトヨタ自動車のグループ企業で不正の連鎖が起きている。 それはなぜなのか?。 報道陣の疑問にトヨタ自動車の佐藤恒治社長が答えた。 【トヨタグループで認証不正が起こるのはなぜか。他社と何が違うのか。】 佐藤社長: まずは組織的な問題があると思う。今回共通するのは、認証制度というものに対する組織的な手当て、例えば、開発部署と認証業務を遂行する部署が同一部署内にあり、けん制力が効かずに不正に走ってしまったというような背景が共通してある。そうした組織上の課題に手を打ててこなかったというのが大きな要因の1つとしてあると思う。 さらに、技術の高度化が非常に速く進み、業務の負荷が高まっている中で、足元でしっかりと正しい仕事をすることの大切さに関してバランスを崩していったところがあると思う。 今回起きていることはあってはならないことだ。従って、1回立ち止まってしっかりと反省し、問題に向き合って改めて前に進んでいく。これが今、トヨタグループとして進めていかなければならないことだと思う。そこに我々も一緒に汗をかいていく。 【トヨタ自動車がグループ企業に対してプレッシャーを与えているのではないか。】 佐藤社長: これはトヨタ自動車のプレッシャーというよりも、自動車の開発が100年に1度の変革期にあり、従来の仕事のプロセスや、やり方が通用しない時代に入っている(ことの影響が大きい)。 こうした中、新しい取り組みを行い、新たな技術をどんどん開発していかなければならない。商品力の強化や、安全・安心(の価値)を高めていくための技術開発が進んでいる。 不確実なところに挑戦しているので、これはトヨタ自動車のプレッシャーという前に、そもそも自動車産業が抱えている課題だと思う。この難しさにどう向き合っていくのか、失敗に対してどう柔軟性を持つのか。そうしたところの心理的安全性を、もう少し担保した開発の仕組みづくりが全般に必要なのだろうと思っている。 【日野自動車とダイハツ工業、豊田自動織機の3社の不正は共通する部分があるか。それとも個別の問題か。】 佐藤社長: 共通する部分と個別の部分とそれぞれ存在しており、一言で回答するのは難しい状態だ。根っこにある共通する部分は、認証制度に対する理解と順守に対する意識(の低さ)だと思う。その部分は個別の案件によらず全体を見て取り組んでいく必要がある。 不正が起きた背景にある要因はそれぞれ異なっているため、1つひとつ丁寧に向き合っていく必要がある。豊田自動織機でいえば、事業部ごとの連携のあり方やパワーバランス、コミュニケーションの質などにしっかりと向き合っていかなければならない。ダイハツ工業でいえば、クルマづくりに対してもう一度あり方を見直していく必要がある。ケースごとに違う部分もあるというのが私の理解だ。 |
2024年1月29日(月)
大丈夫か? トヨタ自動車 グループ企業の不正相次ぐ
| 1月29日午後2時半に記者会見、同夕刻 NHKテレビで、さらに日経ニュースを読んで目を疑った。『まさか、またか?』 というのが実感だった。未だ、ダイハツ自動車工業の不正車両認証問題が起きて渦中にあり、またまたトヨタ自動車主力グループ会社の豊田自動織機がジーゼルエンジンに不正試験や申告があったという。 1月29日14時半に記者会見で発表。 朝日新聞電子版によると、 トヨタ自動車グループの源流企業である豊田自動織機は29日、トヨタ向けの自動車用ディーゼルエンジンの試験で不正があったと発表した。 豊田自動織機が該当エンジンの出荷を止めることに伴い、トヨタも「ランドクルーザー」や「ハイエース」などの人気車種でディーゼル搭載車の出荷を停止する。 豊田自動織機はこの日、国内向けフォークリフト用エンジンについて、排ガスなどをめぐる認証試験で不正があったことを受けて、特別調査委員会の報告書を公表した。 新たな不正を公表したのは、乗用車用のディーゼルエンジン3機種で、出力認証試験時に異なるソフトを使った装置で出力性能を測定していたという。発表によると「該当のエンジンについては改めて検証し、出力基準を満たしていることは確認している」としている。 該当するエンジンを搭載したのは、SUV(スポーツ用多目的車)の「ランドクルーザー300」、「ランドクルーザープラド」(生産終了済み)など世界10車種。うち国内向けに販売しているのは6車種で、現在販売している車種については出荷を止める。これらの2022年度の国内販売台数は8.4万台だという。 トヨタは「当局に丁寧に説明し、立ち会い試験など適切な対応を進めていく」とし、「試験を委託した立場として、法規に従った手順にのっとっていなかったことを認識できておらず反省している」とコメントしている。 また、豊田自動織機はすでに公表している国内向けフォークリフト用エンジン3機種に加えて、6機種(うち5機種は旧型)と、建機用エンジン1機種(旧型)についても、試験で実測値と異なる数値を使うなどの不正をしていたことを明らかにした。 と報じている。 よく読むと、これはダイハツ自動車工業の検査違反(認証試験違反)に通じる内容である。規格を通すために、部品を試験途中で取り換える、プログラムを変更するなどの作為的対処をしているところが同じだ。 これは、おそらく内部告発により、現場の実状が暴露されて問題になったと推測できる。内部告発でなければ、こういう類の問題は埋もれて表面に出て来ない。 それにしても、トヨタグループの法規違反や品質トラブルが多すぎる。この分ではまだ続きそうな予感がする。 デンソーの燃料ポンプの樹脂製インペラ(プロペラ)が金型の不具合で、成型時に樹脂の分布が不適当になり、樹脂が膨潤してケースに当たり回転不良になり、燃料ポンプとして働かなくなり、エンストするという前代未聞の大量の不良を出している。 これは純粋に品質不良問題であり、ダイハツや今回の豊田自動織機のエンジンの問題とは性格が異なる。 それにしても、世界NO.1のトヨタ自動車の度重なる品質不良や、自動車づくりの過程における規制違反やごまかし行為は内在する企業体質(現場の体制)に纏わることで、根が深いと思われる。 日本のモノ造りは大丈夫か? という疑念を抱かせる問題だ。 企業は事業計画を立て、その実行に向かってまっしぐらに行動する。高い目標を掲げ、それを達成してこそ、成長できるし、他社に勝てるし、結果として儲かることになる。 モノ造りが非常に高度化し、複雑化した現在、環境保護などの課題も加わり、かつ短期開発が要求され、開発現場は過大な負荷がかかっている。車のEV化、安全システムなど新しい技術の導入、コスト、日程、品質確認等、開発製造現場は過酷な状況にある。 しかし、いくらそういう状況にあっても、品質、安全性、法規は絶対守らなければならない事柄で、最優先事項だ。トヨタ自動車はそういう面で、モノ造りのリーダとして先頭を走り続けてきたメーカだったはずだ。 今それが開発製造現場で緩んできているのではないか? いや、現場の実態を管理者や経営者が見抜けていないのかもしれない。または圧力を現場にかけているだけになっているのかもしれない。それほど、競争が激しいのかもしれない。 以前は、厳しい企業競争をしても、一線は守ってやってきた。その一線を守ることができるのは、企業理念(掟)だと思う。理念は口に出して、唱えても何の効果も生まない、何の役にも立たない。 理念(経営方針)を実行に移して初めて、その企業の命が吹き込まれる。 企業も人の一生と同じで、規模が大きくなり、成熟化して来ると、いろんな弊害(不都合なこと)が生じる。 今回の豊田自動織機のニュースは、ダイハツの不祥事、デンソウの燃料ポンプ不良に引き続いて発生した大不祥事であり、単なる出来事ではない。根が深い課題が見て取れるような気がする。 そうではないことを期待しながら、・・・・。 |
2023年12月24日(日)
ユーザを裏切る ダイハツの不正行為に呆れる!
| 年末の慌だしい時に、自民党の政治パーティの売上が一部キャッシュバックされ、それが不記載など、相変わらず政治とカネの不祥事が起きている。合わせて、ダイハツの不正問題は前代未聞の大事件に広がってきました。自動車は便利で、日常生活に欠かせない道具ですが、一面、危険な商品です。だから自動車を安全に安心して使えるように規制した法律があります。『道路運送車両法』です。 この法律の目的は、「道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止、その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。」と書かれています。 簡単に言えば、自動車の安全運行を図るため定めた法律です。その中に、「保安基準」があり、「型式指定規則」が定められています。「型式指定」は、型式認証制度として実施されています。 これは、「自動車の製作者(自動車メーカ)が、新型の自動車の生産・販売を行う場合に、あらかじめ国土交通大臣に申請または届け出を行い、保安基準への適合性等について審査を受け無ければならない」となっています。 自動車メーカは、新車を製造し発売前に、この審査を受けて合格しなければなりません。 ダイハツは、この「型式認証検査」において、不正の申請を行っていた事実が判明し、国土交通省の立ち入り検査に発展しました。この審査が不適合であれば、その車の販売はできません。 ダイハツはこの不正を1989年から繰り返し行ってきたようで、実に30年以上に及んでいます。今まで販売し、買ったダイハツ車が安全基準を満たしていないとなれば、ユーザは安心して乗ることができません。そういう事態に陥っています。これは前代未聞の出来事になっています。 自動車は約4万点に及ぶ部品から成り立っていますので、「不良ゼロ」を目指しても、部品不具合が生じることが間々あります。販売した車が走行不良や事故を起こし、その原因が部品にある場合は、メーカは速やかに法律に則り、国土交通大臣に『リコール』の届け出を行い、修理、対応することが求められます。 これに関し、今、問題になっているのは、デンソーが製造したガソリン燃料ポンプの不良問題です。以前からこの問題が囁かれてきましたが、なかなか不良の真因が分からず、リコールを繰り返してきました。デンソーはトヨタ系列の世界的な部品メーカで、トヨタをはじめ多くの自動車メーカの車に採用されています。トヨタに次いで、ホンダ車にも多く採用され、全世界で、1千数百万台にのぼる膨大な台数のリコールがこれから行われます。 この不良原因は、ポンプに使っている羽根(エンペラ)がガソリンにより樹脂が膨潤して側壁に当たり、回転しなくなり、ガソリンが正常に供給できなくなり、エンストを起こすというものです。この件に関して、ホンダ車で死亡事故が一件起きてしまいました。こういう予期しない部品不良は時々起きることがあります。その都度、メーカは『リコール』で対応しています。 今回のダイハツの不正は、『部品不良』という案件ではなく、『安全基準違反』ということですから、メーカとしての責任は厳しく問われることになります。これは、ダイハツの企業存続可否がかかる出来事。 『ダイハツ』という会社は、どういう会社だったのか、(Wikipedia 等より) ダイハツは、主に軽自動車および小型車を主力とする自動車メーカーで、本社は大阪府池田市ダイハツ町。日野自動車などと共にトヨタグループ16社の内の一社で、トヨタ自動車の完全子会社。 【歴史】 量産車を手掛ける日本の自動車メーカーとしては最も古い歴史を持ち、初の国産エンジンを開発する目的で大阪高等工業学校(大阪大学工学部の前身)の研究者を中心に、1907年に「発動機製造株式会社」として設立され、創立50周年の1957年に『ミゼット』で国内や東南アジアで大ヒットを記録し、1972年まで東洋工業(現マツダ)とともにオート三輪業界の覇権を争い、1951年に「大阪発動機」から現在の「ダイハツ工業」へと社名を変更した。 四輪市場には1963年のコンパーノから参入。しかし当時四輪車への新規参入には通産省(現在の経済産業省)が難色を示したため、スムーズな参入が出来なかった。また堅実な社風であったため、派手にアピールする手法も取らず、地味な印象となり、すでに評価を得ている先行メーカーに割って入って新規顧客を獲得するのは容易ではなかった。同じころ自動車業界は再編の波が吹き荒れ、ダイハツにも三和銀行によってトヨタ自販・トヨタ自工との提携話が持ち出され、1967年11月に両社は業務提携に至った。同時期にトヨタ傘下入りした日野に比べると対等な関係で、それぞれの経営に自主性を持って運営していく声明文が出された。この翌年、ダイハツ自動車販売株式会社が設立された。 トヨタとの提携、『パブリカ』をベースとした『コンソルテ』、トヨタ・カローラをベースとした『シャルマン』を生産し、四輪生産のノウハウとブランド力を蓄積していった。 1977年には、ダイハツ独自開発のコンパクトカーである『シャレード』を投入。それまで振動の問題などから国内外のメーカーから敬遠されていた4ストローク直列3気筒ガソリンエンジンを搭載し、軽自動車程度の価格に見合わぬ高い燃費・動力性能でカーオブザイヤーを受賞、ダイハツの四輪車は名実ともに大躍進を遂げた。 (注)トヨタ、ダイハツ、スズキなどの1000cc~1500ccの小型車に3気筒エンジンが多く採用されている。3気筒エンジンは軽量化や低燃費化が出来る特徴がある反面、振動が大きい弱点もある。加工法の進化や振動対策が進み、最近はBMWなどドイツ社など海外メーカ車においても、小型車には3気筒エンジンが多く搭載されるようになった。3気筒エンジンは既に軽自動車に採用されてきた。ホンダは軽自動車は3気筒エンジン、小型車は4気筒エンジンを搭載している。 1980年、軽自動車の『ミラシリーズ』が登場。ここに『アルト』を擁するスズキと軽ボンバン戦争が勃発した。 1981年にダイハツ自動車販売はダイハツ工業と合併。 1995年には同じトヨタ傘下の日野自動車と商品相互供給に関する基本契約の締結を発表、以降現在まで部品の取引を行っている。 1998年にはトヨタが株式を51.2%取得し、トヨタの連結子会社となった。 1995年登場の『ムーヴ』、2003年登場の『タント』が大ヒットしたことで、2006年度には軽自動車総販売台数で30年以上連続1位であったスズキの牙城を崩し、ついにダイハツがトップに立った。 その後、2017年まで11年間連続で首位の座を守り続けている。 また軽トラック市場も『ハイゼット』などを主力に、スズキとシェアトップを奪い合っている。 2009年から軽自動車から撤退したスバルにも軽自動車・軽福祉車のOEM供給を開始。 2016年度の国内販売台数は57万台だが、これに加えてトヨタ・スバルへのOEM供給・受託生産が25.5万台あり、軽自動車メーカーとしてのみならずトヨタグループの重要な生産拠点としての役割も大きい。 2016年にトヨタがダイハツの株式を100%取得し、完全子会社となった。 これ以降ダイハツはトヨタグループにおいて軽自動車を含む小型車部門としての立場を明確にし、新興国向け戦略の一翼を担うことになる。国内では、マツダ、トヨタ、スバル等への小型車や軽自動車のOEMが増えている。 【開発思想】 長らくトヨタから小型車・小型エンジンの開発・生産・OEM供給を委託されてきた。デュエット、およびキャミ、スパーキー、パッソ、パッソセッテ、2代目bB、ラッシュ、ルーミー/タンク、ライズといった車種のほか、ヤリス(ヴィッツ)やベルタ、パッソに搭載された1KR-FE型エンジン、3代目ヴィッツや、2代目カローラアクシオ、初代後期型プロボックスなどに搭載された1NR-FE型エンジンはその代表である。軽セダンの「ミライース」、軽スーパーハイトワゴンの「タント」、および「ムーヴ」、これらをベースにした福祉車両や軽トラックにおいてダイハツが50%を占めるに至っている。 【独自技術】 一方で技術的分野では、親会社トヨタと異なる独自のものが多い。代表的なものとしては、ハイブリッドではなく内燃機関・シャーシの改良によって低燃費を実現する『e:Sテクノロジー』が挙げられる。 エンジンは、90年代後半から採用され始めた『TOPAZ(TOP from A to Z)』と名付けられたシリーズで、低圧縮比による低燃費だけでなく、独自の触媒早期活性化システムとインテリジェント触媒により、貴金属の使用量を大幅に削減しながら長期使用でも安定した低排出ガスを実現している。同様にトヨタがD-4系の直噴技術を発展させているのに対し、ダイハツはポート噴射にこだわる姿勢を見せており、1KR型エンジンやKF型エンジン、そして一連の自動車用ダイハツエンジンとしては最新型となるWA型エンジンではポート噴射により直噴と同じ効果を低コストで実現している。 衝突被害軽減ブレーキなどの運転支援システムに関してもトヨタに頼らず、『スマートアシスト』と呼ばれる技術を独自に開発している。トランスミッションについても、トヨタが子会社のアイシンと共同開発しているのに対し、ダイハツは内製に徹している。2019年にはトヨタ・アイシンが発進用にギアを装着したCVTを開発する一方、ダイハツはギアを高速側に採用し動力分割機構も搭載した『D-CVT』を発表している。 プラットフォームでは、トヨタの新世代コモンアーキテクチャー戦略「TNGA」に準じた、独自の軽自動車専用「DNGA」の開発を行っており、軽自動車では2019年7月に発売された4代目「タント」が、登録小型自動車では2019年11月に発売された2代目「ロッキー」)がそれぞれの初出となった。 ダイハツは関西に基軸を置いた自動車メーカとして発展して来た。「ダイハツ」という名前も親しみやすく、多くの人に愛されてきた。 今回の車両認証不正はメーカとして絶対遵守すべき規制法規を破ったことで許される余地はない。 大変厳しい制裁が行われるだろう。 記者会見等を見ると、社長や副社長の話は、「短時間開発の極度なノルマがストレスとして加わり、認証破りの原因になった」という話で終始した。これを聞いて、責任は現場にあり、経営者の責任ではないというふうに聞こえるのが残念だ。現場が直接手を下した責任は逃れないが、そこまで現場を追い込んだ責任はトップにある!という潔さが要る。 不詳の要因は、ほとんどが経営責任者にある。だから不祥事が起きれば、トップはまず自らの責任を表明し責任をとる態度を示さない限り、企業風土は良くならない。不祥事が起きると、トップは「不祥事が生じたことを詫び、このようなことが再発しないようにしっかり再発防止に努め、風土を改めるのが私の責任です」などと決まり文句で弁解する。未練がましい! 「私自身に管理責任があるが、直接不祥事に関わっていません!」と開き直っているのと同じ。 なぜそうなるのだろう? 社内の隅々まで見通せていないからだ。トップは方針や計画を出せば、後は現場任せ、現場を知らない。社内巡回を繰り返し行い、従業員の働く現場の生の姿を見、従業員の話を直に聞いて、隠れている問題(潜在する課題)を見つけ出す努力をしていない会社に起きる現象だ。 言葉ではなく、現場、現実、現物を見て回ることが大切だ。自らがモノづくりに興味を持つようなトップのいる会社は、こういうたぐいの不正や不良は起きない。 ダイハツ車を愛し、乗り続けているユーザは、『乗っても大丈夫かな?』という不安に駆られていると思われる。30年間も不正行為を続けている実態から、今すぐ危険という不具合は起きないと思う。でも、安心して乗り、次もダイハツを買おうという人は少なくなり、買う人は勇気がいることになりそう。 そうなると、本当にダイハツは生き残れるのだろうか? そんな感想を持ちながら、今後の展開を注視してみたい。 |
2023年10月4日(水)
Fitのお化粧直し 第三弾!
| 我が家には、Fitが2台ある。ホワイトが自分用のハイブリッド車、黄色が家内用のガソリンエンジン車。 ハイブリッド車は、買ってから3年半になる。HONDA e-HEVハイブリッドシステムを搭載している。これは既に、紹介記事を掲載しているので、興味があるい方は下のリンクをクリックして、ご覧ください。 ・第一弾フェイスアップ 20220511 ・第二弾フェイスアップ 20220916 Fit4は大変すばらしい出来栄え。3年半乗って満足しているが、デザイン、特にフロントのマスク、顔つきが野暮ったく、今一だ。 この点は今なお、好きになれない!我慢して乗っている。 発売当初、Hondaは盛んに『柴犬』をイメージしたと強調していたが、デザイナーの悪い癖が出たというか、ユーザの受けが悪い。だから今一、販売が伸びないでいる。もったいない話だ。最近、マイナーチェンジで顔つきを改善したが、元の印象が強く残っているので、なかなか販売も伸びないようだ。でも、マイナーチェンジで、RSを追加した。これはなかなか良い顔になっている。 初代Fitは、コンパクトクラスで大ヒットを飛ばした。コンパクトで室内の広さが断トツで、一クラス上の広さを実現していた。だからユーザに受け入れられたのだと思う。 今乗っている『柴犬』イメージのFitは、『かわいい!』ということを主張していたが、そのかわいさが、十分顔に表現されていないように感じた。ボディー全体のイメージは悪くないが、車を印象付ける曲面がダルで、ボテッーとした印象を受ける。ふっくらした顔つきは、知性やチャーミングさが感じられないというのが小生の印象だ。これは好き好きなので一概に言えないが、まあ、余り売れていないところを見ると皆さん、そういう印象を持っているのだろう。 競合車は、TOYOTA Yaris、 NISAN Note e-Powerになるが、こちらは、『走るぞ!』という姿が伝わってくる。うまく曲線を活かして、引き締まった曲面でうまくまとめている。Fitは余りにも、“優しさ”に振り過ぎて失敗したと言えそうだ。 でも、車のできは、実に素晴らしい。長年、いろんな車に乗り継いできたが、コンパクトでありながら、上級車のような感覚で運転ができる。視界や、乗り心地、ハンドリング、静粛性など非常に高いレベルにまとまっている。何より運転していて、疲れないのがとてもいい。よくできた車だ! そこで、顔のフェイスアップに取り組んできた。 飾り部品やテープを貼って、『お化粧直し』をしてみた。その経緯を写真で紹介する。 まず、購入時のFit4 e-HEV  グリルにガーニッシュを付けた これで、Fit4『柴犬』の鼻?のイメージが相当変わった。良くなったと思う。  エアーダクトにステンレスモールを飾りを付けた。 一層引き締まった。  エアーダクト部の一体感を出す黒テープで化粧した 白い部分を隠して、フェンダの広がりを演出してみた。 これが現在の最終のデザイン! 当分この状態で乗ってみる。 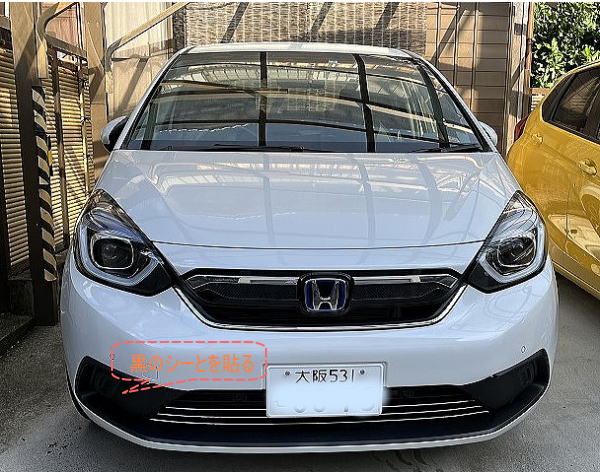 !?  日本に一台しかないFit4、 何やかや、トライして遊んでいる。 |
2023年6月12日(月)
車のバッテリー電圧12Vを48Vに変更する動き!
| 自動車バッテリー電圧は、普通車や軽自動車は12V、大型バスや大型トラックは24V系に世界で統一されてきた。鉛蓄電池の電圧は1個当たり2V程度であり、12Vのバッテリーは6個直列接続している。 最近、車に搭載する電子機器が著しく増え、それに伴いエアコンや、ヒータや、ウィンドウ開閉、AWSやABSのモータなど一台で数十個のモータが使用され、従来考えられなかった大量の電力を消費するようになった。一方、省電力に寄与しているのはヘッドライト、バックランプ、ウインカーなどのLEDランプである。 しかし、相対的には、消費電力が大幅に増えている。 一説には、12V系の車で、200A(2.4KW)を超すようになったそうだ。車両に必要な電力は年々増加している。これを賄うため発電機やバッテリの大容量化が図られ、それらの重量の増加や、ハーネス(配線)の線径が太くなり、接続コネクターが電流に耐えるように頑丈になり、車両の重量の増加や、コスト上昇の要因になっている。 車両に12Vが採用されてから60年が経過している。今後、さらなる電力増加を見据えると、48Vに変更することにより、いろんなメリットが得られる。 まず、12Vから48Vに変更すると同じ電力に対して、電流は1/4になる。配線部(ハーネス)の電力損失は線材の抵抗に電流の2乗をかけたものなので、電気配線経路で消費される電力は1/16に下がる。 |
2022年11月20日(日)
フィット4の静音化対策がうまくいった!
| フィット4ハイブリッドが納車されてから2年9か月が過ぎた。あっという間に初回の車検が近づき、ホンダからハガキが入っていた。 前のフィット3ハイブリッドは、スポーツハイブリッドというシステムで、i-DCD方式を採用、これはドイツ製のダイレクトクラッチを巧妙に組み込んだもので、1モータで発電と駆動を行うという発想で生まれた車だった。 この方式はエンジンとモータの切り替えが複雑で、それを制御するプログラムの熟成不足による不具合もあり、約1年ほどゴタゴタとクレームが続いた。発売時に即購入したので、何回もリコールを受ける羽目になった。不具合の内容をホンダディーラに苦言したこともたびたびあった。 車の不具合はいろんな運転場面で生じるので、なかなか再現しにくいことが多い。再現しなければメーカやディーラは不具合を認めようとしない。しかし、不具合の件数が増えると、本腰を上げて対策に取り掛かり、原因追及して、対策案が出れば、リコールで修理する。 不幸にもフィット3ハイブリッドのi-DCD方式は着想は良かったが、出足でつまづいた。一度、躓くと販売が伸びなくなる。噂が広まれば、なかなか払しょくするのは難しい。 しかし、このi-DCD方式ハイブリッドを熟成した結果、その後、フリードなどほかのモデルにも搭載した。もちろん、不具合点はなくなり、非常に良くなった。しかし、今後のハイブリッドは2モータだという流れに逆らえなかった。 トヨタやニッサンが2モータ方式を採用して、ガンガン販売を攻めてくる中で、1モータということだけで、何か後ろめたさを感じたのも事実だ。 既にホンダはアコードなどの高級車で2モータハイブリッドのi-MMD方式を採用していた。これはシリーズ方式で、走行は駆動モータで、発電はエンジンを回して発電モータで行うという方式だ。燃費や走行性能が高く、高い評価を得ていた。 ただ、このi-MMD方式はモータが1個増える分、コストアップになり、小型車では採用されていなかった。 そこで、ホンダは駆動モータと発電モータの鉄心の径を大きくし、鉄心の積み厚を薄くしたモーとを造った。この2つのモーターの鉄心の径(形)を同じにすることで、大量に電磁鋼板を打ち抜くことに成功した。これにより、エンジンの軸の横に2つのモータを配置でき、車幅の狭いコンパクトカーにも収まるようにした。さらにモータに使用する高性能磁石にネオジウム等の希土類材料を使わない、または使用量を大幅に削減し、コストを下げることに成功した。 i-DCD方式は、ダイレクトクラッチのギアーとクラッチは複雑なメカで構成され、この部分にコストがかかっていた。これが2モータ方式では不要になる。新しい2モータ方式をホンダはe-HEVと名付けて、高級モデルからコンパクトなフィットまでこの方式に統一した。さらに、来年には軽自動車にもe-HEVが搭載されるはずだ。 このe-HEVは、ニッサンのノートe-Powerなどと違い、高速道路の走行時、エンジンと車軸を直結するクラッチが採用されているので動力伝達の効率が高く燃費が良くなり、非常に合理的な方式だ。 いよいよ、ハイブリッドの方式も、トヨタハイブリッドTHS(シリーズ・パラレル)方式と、ニッサンe-Power方式と、ホンダe-HEV方式に集約されてきた。 今後、ハイブリッド車は、モータの高効率化、リチュウム電池の改善、Power制御回路のロスの改善の競争になるはず。 もう一つ言えることは、シリーズ方式の場合は今後、ハイブリッドからEVに変わる際に、エンジンを取り外して電池容量を大きくすればいいということになるので、技術移転がすぐできることにある。 さて、愛用のフィット4ハイブリッドe-HEVは、今年10月にマイナーチェンジされ、駆動モータとエンジンの馬力が各10馬力ほどアップした。リチュウム電池容量についてのアナウンスはない。走りがさらに良くなり燃費も改善されたという話だが、試乗していないので何とも言えない。今話題は、新しくフィット4RSが追加になったこと。これは、ホンダの戦略で、RSは『Road Sailing 』の略。道路上をセイリングするように颯爽と走るという意味らしい。 愛用のフィット4ハイブリッドは巷の評価ではスタート時に少々もたつき感があるということだが、家内の黄色いフィット3(1300cc、ガソリンエンジン車)の方がアクセルの応答が良い感じがする。 しかし、フィット4ハイブリッドは、穏やかなアクセルワークで、高齢者には安心して乗ることができる。ブレーキやアクセルの反応が鋭ぎるのは事故につながりかねないので、自分にはこの方がちょうどいい。 さて、前置きが長くなったが、本論に入る。 フィットはもともとコンパクトカーとしては静かな車だ。フィットは初代から2代目、3代目と乗り継ぎ、今は4代目に乗っている。3代目から特に静かな車になった。さらに今、愛用中の4代目ハイブリッドは、一ランク上の車のような乗り心地や静かさになっている。 Youtubeを見ると、車の静音対策の動画がたくさんアップされている。貨物車は別として、乗用車は静かに走ってくれるに越したことはない。車内の会話や音楽もよく聞こえるようになる。 ■車の騒音のもとは、 ①エンジン音 ②タイヤ音(走行音) ③風切り音 ④社外の音 などがある。 ■音とは、空気の粗密波であり、何かモノが空気中で動く(振動する)と発生する。 だから、空気のないところ(例えば、月面では、音は生じない。 ウチワを扇ぐ時は、空気が風になっても音にはならない。扇風機の羽根はウチワより早く廻るので、低いウナリのような音がする。扇風機の風力切替スイッチを『弱』にすると、羽根はゆっくり回転するので音にならない。『強』にすると風切り音が大きくなる。 人の耳には、一分間に20回以上、空気が振動(揺れ)すれば聞こえる。一番高い音は一分間に2万回ぐらいの振動を音として聞くことができる。音を感じる範囲、可聴周波数は人により差がある。 ■音を生じなくする方法は、 ①空気を無くすること;真空にする。 ②空気中で、振動する物を無くすること。 ③振動する空気(音)を遮断すること。 ■音の種類 ①通過音;発生した音が空気中を伝わってくる音。 ②共振音;振動が構造物を振動させて発する音。 ■音の遮断は、①、②を無くせばよい 車の場合は①も②も存在するので、静音化はできても、無音化は不可能だ。 エンジン音はハイブリッド車の場合、モータ走行時は、ほとんどない。しかも、エンジンは発電モータを回すだけなので、余り高負荷(高トルク)状態にならないので、高回転数になることはないので基本的に静かである。このエンジン音を遮断するには、エンジンとキャビン(客室)を仕切っている壁(鉄板)に防振材や遮音材や吸音材等を貼っている。また、いろんな穴をブッシング等で塞いで、通過音を無くしている。また、ボンネットの裏に防振材や吸音材を貼って共振音を小さくしている。 走行音は、荒れた道や高速道路を走ると、『ダー』という連続音が入ってくる。これは結構耳障りになる。 この走行音を完全に無くすることは不可能だ。 風切り音は、高速運転中、空気が車体に当たることで発生する。車の形状によるところが大きい。 社外の音の侵入は、フロントガラスを防音ガラス(二重ガラス板の間に薄い樹脂のシートを張る)にしたり、窓ガラスを厚くしたりする。これは自分では対策できない。メーカの設計仕様になる。 ■今回やった対策は、 ・前席・後席フロアーマットの下に、ゴム防音シートを貼る。 ・各ドアー(前後4枚のドア)の内側(鉄板部)に防振シートを貼る。サービス用穴を防音シートで塞ぐ。 ・ボンネット内側に防振シートを貼る。 フィット4は吸音材が貼られていたが、ボンネットの鉄板内側に防振シートを貼る。 ・後部トランクの収納部の鉄板に防振シートを貼る ■効果的な防音対策箇所の見つけ方 フロアーやドアを指で叩けば、コーン・コーンと共振音がする。防振シート(ブチルゴムなどゴム系材料を薄いアルミシートに塗ったシート)をこの場所に貼ると、鉄板の共振音が無くなり、コツ・コツという音に変わる。これで、走行音(ロードノイズ)やエンジン音などが随分小さくなる。ドア開閉音もドシッとした音に変わる。 一般的に共振しやすい場所は、鉄板が平面の箇所になる。鉄板が絞り加工されていたり、補強部材(補強棒・アングルなど)が装着されている所は余り共振が起きないので、防振シートの効果が少ない。 ・フロアーマットの下に敷く防振ゴムシートはフロアーマットに合わせて裁断してマットの下に敷くだけ。 ・ドアーは、ドアー内張を剥がして、鉄板部に防振シートを張り、サービス用開口部は防振シートで塞ぐ。 ドアーの内張の剥がし方は、Youtube等で説明しているので、比較的簡単に作業ができる。 こんな対策をした結果、静かな車に仕上がった。 騒音がどの程度低減できたか、数値測定していません。ネット上で「音響測定アプリ」をダウンロードすれば、スマホを簡単な騒音計として使用できる。 今回は対策前の騒音レベル測定をしていなかったので、対策後の測定値とは比較にならないので聴感の感想です。高速道路走行中も、隣と普通の声の大きさで会話ができるようになった。特に大きな声を出さなくてもよくなり、ラジオやテレビの音声もよく聞こえる。 ■「音」の対策はむずかしい! 長年、オーディオ関係の仕事をしたので、音にはちょっとした知識とこだわりを持っている。 スピーカはボックスは板厚が再生音に大きく影響する。薄板でボックスを造ると、スピーカの振動により生じる音圧変化でボックスが共振して、いわゆる箱鳴りの現象を起こす。こういうスピーカシステムはHI-Fi再生には程遠い。音質改善には、箱は板を厚くし、箱の中に吸音材を詰める。 市販の高級Hi-Fiスピーカは、大きさに比べ、ズシッと重い。これは2、3cmの厚板を使いスピーカキャビネットを作っているからだ。スピーカユニットのマグネットも強力な大きなものを使い、振動板をがっしりしたフレームに取付けているので、高級スピーカは重くなる。単純に言えば、スピーカは重いほどいい音が出る。 ■対策によりどういう音に変わるのか? タイヤノイズは、『ザァー』という耳につきやすい高い連続する雑音(ノイズ)から『ゴー』という低い聞きやすい音に変わった。 この『ゴー』という音をさらに小さくするには、徹底した防振、防音、吸音対策をしなければ取り切れない。 これは素人では難しい話になるので、この辺で適当に手を打った方がいい! ■音の世界は、際限がない!! 音は感覚であり、同じ音でも心地よく聞こえる時もあれば、やかましく耳障りに感じることもある。だから、静かになったと思っても、前と同じかなと思うこともある。これは音を右脳で感じ判断しているから、気分次第であいまいになる。そういう意味では、自己満足なところがあるのも『音の世界』だ! しかし、メーカは、科学的な分析や実測データを根拠として改善してゆかなければならないので、音や音質の測定や評価にいろんな機材を使用する。 音響測定器には、音量(音圧;通常dBで示す)、音質(周波数特性)、ひずみ(雑音)を測定する ・周波数分析器 ・騒音計 ・振動計 などなど ■耳に聞こえやすい(耳につきやすい)音 下記の青線のAカーブという聴感補正を加えて測定する。 .svg.png) Aカーブは平均騒音レベルで使用するために定義されましたが、Aカーブは環境騒音や産業騒音の測定、および潜在的な聴覚障害やその他の騒音の健康への影響を評価する際使用されています。 人間の可聴周波数範囲における難聴と非常に良好な相関関係を示しているため、Aカーブ重み付けはすべての測定に義務付けられています。 Aカーブは、2,3KHzが最も耳の感度が高く、低音域では感度が低くなることを示しています。 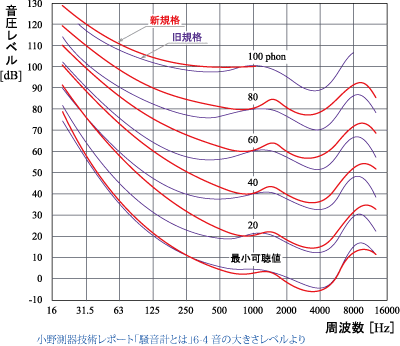 音の大きさによって、耳に聞こえる音の周波数に対する感度も変わります。これをフレッチャーマンソン曲線と呼び、左の曲線で示されます。周波数毎の音圧レベルの尺度であり、一定の音量として聞こえるというレベルを示しています。 小さな音は、低音と高音が聞き取れにくくなる傾向を示しています。 Hi-Fiアンプでは、この曲線を参考にして、Loudness Control SWというボタンが付いたアンプがあります。 このスイッチをONにしますと、ボリュームを絞った時(小さな音量で聞く時)に、低音と高音が増強されるようになります。 ■ちょっと余談 自動車はマフラー(消音器)がなければ、エンジンの排ガス音は張り裂けるような大音量を出します。 F1レースのけたたましい音は、レーシングカーにはマフラーを使っていないからです。マフラーを使うと、エンジンの排気が妨げられので、公道を走らないレーシングカーはマフラーは取りつけていない。   また、ジェットエンジン音は、離陸時に耳が裂けるほど大きな音を出します。ジェット戦闘機の音はさらに一段と大きい。戦闘機は音速を超える超高速で飛ぶためターボジェットエンジンを使い、燃焼ガスを直接排気して推力を得ています。旅客機にはターボファンジェットエンジンで、エンジンの直径を大きくして、大量の空気を吸い込み圧縮して排出するため、一種のマフラーのような効果が生じ、比較的静かで高効率・低燃費のエンジンになります。そのため、形状は写真のように樽(たる)のようなずんぐりした形になります。 飛行機は車のような消音のためのマフラーは使用していない。 車のマフラーは電気的に言えば、LPF(ローパスフィルター、ハイカットフィルター)の働きをします。 耳が裂けるような排気音の高い周波数の音を低減する働きをします。加えて全体の音量も下げる。 そのために、マフラーの中は、いくつかの仕切りや穴をあけたりして、消音化を図っています。 車の走行時の排気音や室内音を静かにするには、コストがかかり重量が増えるので、車のグレードや価格と見合った静音化を施している。 高級車は静かに走り、軽自動車はやかましいということ。でも、最近の軽自動車は大変静かになっている。 ■参考資料(使用した防振材料ト) 購入先;Amazon、モノタロウ ①制振シート ¥1,740 dualmax 100mm×100mm×2mm 30枚入 ロードノイズ低減 自動車用断熱シート ②制振シート ¥2,790 ZHUBANG 800mm×460mm×2mm 2枚入 遮音 制震シート ③制振シート ¥1,690 日東電工 480mm×0.5m 軽量制振材 レジェトレックス アルミシート 1枚 D300K ④ 吸音シート ¥439 東京防音 300mm×300mm 吸音・防音材ホワイトキューオン 各社からいろんな防音、防振、吸音商品が販売されています。 適度な重量があり、ゴムの厚みや粘着力がある、日本メーカ製が信頼できると思います。 |
2022年9月16日
愛車 フィット4のグリルにステンレスモールを着けました!
| 5月11日の記事で、グリル(ガーニッシュ)を貼ったことで、顔つきがキリっと引き締まるようになりましたが、さらに手を加えました。 ナンバープレート下のエアー取り入れ部の桟に『キラリと光るラインがあればどうかな?』と考え、試しに調理で使うアルミホイルに両面テープを貼り、幅1cmぐらいの帯状テープを造り、これを張り付けたところ、まずまずのイメージになりましたが、アルミホイルは極薄く、しわになり、きれいな光沢が得られませんでした。 そこで、『光輝く適当な飾りモノがないか?』 近くのオートバックスで店内を見て回ると、いろんなモールやテープが沢山陳列されていました。その内でフィットのエアーダクトの桟に適しそうなモールを買って帰り、試験的に張ったアルミホイルテープを剥がし、ステンレスモールに張り替えました。 見事にうまく貼り付けができ、上々の出来栄えに仕上がりました。 納車時のFIT4(左側の白いFIT);元の顔  グリルガーニッシュを着けた装いに変身(左側の矢印部);グリル追加の顔  細いステンレスモールを着けた姿(左側の矢印部);今回の顔つき 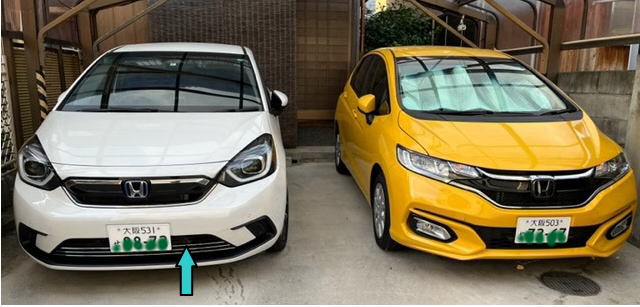 これで、フロントマスクがかなり引き締まって見えるようになり、よくなったと自画自賛しています。 下記の写真のプレートの下の3本の輝くラインです!  これで、しばらく乗ってみます!! デザインの印象は、ほんの数mmの幅や細さや曲面や角のR、色合いや、輝きで随分印象が変わります。 日本は、最近、目立つ、ガッツなデザイン志向のクルマが多いようですが、個人的にはあまり好みではありません。やはり、ヨーロッパの車のデザインは洗練された美しい姿を追求しているようですが、以前に比べると、世界的に『目立ちたがりや』のデザインがトレンドのようです。 |
2022年5月11日(水)
愛車 新型フィット4のフェイスアップをしました!
| 新型フィット4(eHEV)を買って、早くも2年が経ちました。 いろいろと賛否のある新型フィットですが、車としてはまれにみる完成度の高さだと思います。何十年も車を乗り継いできましたが、これほど運転して、しっくりとくる車は今までになかったものです。それだけに愛着が湧くのですが、余り売れていないようで残念です。 この名車?が何故、ユーザに余り受けが良くないのか? 唯一考えられる要因は『顔つき』だと思います。 発売時に、『柴犬』をイメージしてデザインしたと聞きましたが、今はあまりそのことを言わなくなりました。 私は、『柴犬』はもっと凛々しい顔だ!という厳しいコメントをホンダに送りました。 今、クルマはトヨタはじめ、ニッサンなどもこれでもかというイカツイ、派手なデザイン志向になっています。そういうトレンドの中で、このFIT4のフロントデザインは、ヌメ-としたダルイ感じがします。これは私見ですので他の人がどう感じるかは分かりません。車としては非常に高い完成度を有しながら、販売が伸びない!要因に違いないと思います。 そこで、この新型フィットの顔つきの改造を手がけました。フロントグリルパーツを購入して、自分で取り付けてみました。これで、ガラッと引き締まったデザインに変わりました。 下の写真をご覧ください。 Before⇒After  ガレージに並べている2台のフィット 白;フィット4(e-HEV)自分用 黄;フィット3(ガソリン車)妻用 Before  After  |
2022年2月12日(土)
新形フィットはなぜ売れない?(ハード編)
| この新型フィット4がいまいち売れていない! そのわけは? このフィット4は私が、50年間乗り継いできたどの車より、『運転しやすく、安全・安心して乗り心地もよく、長時間運転しても疲れない車に仕上がっている』と感じている。 とてもよくできた完成度が高い車だ! 売れない理由が分からない。 あえて私見を言うなら!! FIT4は今、流行の車のデザインから差別化?して、新しいデザインコンセプトを導入したようだ。 それが良いか、悪いかは、好み次第だ。 ホンダはこのFIT4発売時に、『柴犬のイメージ』として打ち出したが、柴犬ならもっとキリっと引き締まった顔つきにすべきではなかったかと残念だ。 だからと言って、『キーンルック』と言われるプリウスの細いツリ目のデザインや、マツダの『ジンべーザメ』のような大口を開いたデザインも好みではない。ワーゲンのゴルフやベンツのようなドイツ車のオーソドックスなデザインの方が好印象が持てる。 車を選ぶ際、顔つきは大きな要素になる。この素晴らしいFIT4が苦戦しているのは、顔つき以外にないと思う。側面や後面や、室内のデザインは大変よくできていると思う。それだけに、フロントのよく言えば『清楚で、しとやかな顔』、悪く言えば『のっぺりとしまりのない顔』が今一、購買意欲につながらないのではないかと思う。 発売時に見た瞬間、『これは!、なぜだ!』と思ったほどだ。でも、納車から2年間、この顔に付き合っていると、不思議と最近は良き相棒になっている。 一方で、トヨタ ヤリスやアクアがバカ売れしている。ヤリスは、いかにも軽快に走りそうな形をしている。パッと目を引くのは分かるが、それだけではないだろう! ヤリスが売れる理由は燃費がいいことか? ヤリスはフィットに比べて大人2人分ほど軽い。車重が軽ければ燃費は良くなる。ヤリスやアクアと、ノートは3気筒エンジンを搭載している。 自動車エンジンの潮流は8気筒⇒6気筒⇒4気筒、最近小型車には3気筒エンジンが増えてきた。 気筒数が少ないと、ピストンとシリンダの摩擦などのロスが少なくなる。これは省燃費につながる。 ただし、3気筒独特の騒音や振動は増える。それは軽自動車に乗れば分かる。 1200ccから15000ccクラスのエンジンはトルクも大きくなるので、十分な騒音や振動対策が必要だ。3気筒と4気筒では振動モードが変わる。そこで、3気筒独特の振動を打ち消すためバランサーという重りをクランクシャフトと逆回転させ、エンジンと逆の振動を発生させてキャンセルする方法があるが、ノートやヤリス、アクアにバランサーは組み込まれていない。これはコストの課題なのだろう。 4気筒のフィットに比べて、エンジン騒音や振動は大きいはずだが、自動車マガジンの記事に書かれていないのが不思議だ。 YouTubeや自動車雑誌の自動車評論家と言われる方々の記事を読むと、「シャーシ・フレームが新設計で剛性が何%上がった」とか書かれいるが、その内容は彼らがメーカ説明会で聞いたことを受け売りして記事にしている。だからどの雑誌やTubeを見ても同様な内容になっている。 雑誌社や評論家は、メーカの宣伝マン? 評論家はメーカサイドに立つのか、ユーザサイドに立つのか? 聞いてみたい。 メーカサイドに立つのならメーカの宣伝文句のとおり記事にすればいい。実はそういう記事が多い、・・・。 ユーザー側に立つのであれば、きちんと科学的にテストし、客観的に分析した記事を載せてほしい。例えば、車内騒音は、騒音計を車内の決めた位置において計測し、何デシベル(Aカーブ)かを記事に記載してほしい。主観的に静かで騒音は低いなどというあいまいな記述は頂けない。 もちろん、走行する道路や、晴れの日や雨降りの日などの気象条件なども同じ条件で測定すべきだ。 さらに、走行した時刻でも外部騒音は大きく変わる。 測定条件をできるだけ同一にして、物理的客観的な数値で表示すべきだ。 人間の五感(視覚、聴覚、視覚、触覚、嗅覚)の内、聴覚は周囲の雰囲気や精神状態で大きく左右される。 それだけに、測定器の計測による評価が大切になる。  デジタル騒音計の例 (注)聴感レベルを知る場合には、通常、Aカーブという補正を使う。 これは、人間の耳に感じる音を周波数により補正したカーブのこと。下図の青い線がA補正カーブ 人間の耳は、2~4KHzが一番よく聞こえることを示している。 .svg.png) 例えば、ヤリス、ノート、フィットの新型車を、同じ条件で計測し、データを公表すれば貴重なデータとなる。 そういう雑誌やYouTube の記載を見たことがない。 今の記事は、走る道も、天候も、走る時刻も、ガソリンの量も、乗車人数も、それぞれ違う条件で、車内騒音は静かだとか、少々やかましいとか、エンジン音が気になるとか、遮音がよくできているとか、評価基準があいまいで、主観的な表現になっている。 これなら何とでも書ける。 騒音計を使って、条件を同一にして、測定すればメーカも文句は言えない。 そういう科学的なデータを示して、記事が書ける評論家やマガジンやYouTuberが早く出てきてほしい。 私が現役で、オーディオ全盛期を過ごした頃、オーディオ評論家という先生方が沢山活躍していて、音楽雑誌に記事を投稿していた。各社のアンプやチューナやデッキやスピーカ等のオーディオ機器を自宅の部屋(視聴室)で聞いて、その評価を記事に書いたその道のプロの人たちだった。 彼らは東京近郊に住んでいて、関西にはほんの数人しか居なかった。東京のオーディオ(専門)メーカは、足しげく評論家回りをし、先生方と関係を密にしていた。我々関西メーカは地の利では勝てないので、評論家廻りの専従者を置いて、評論家対策をしていたが、所詮、東京近郊のメーカには勝てなかった。 オーディオ評論家(先生方)は、新製品を紹介する際、自分の好みや聴感に頼って記事をまとめる。言い方を変えるとなんとでも記事は書ける。これは自動車評論家も全く同じだと思う。 こんな記事を参考にしたり、真に受けたりして商品を買わされるのは、いかがかと思う。自分の目で見、耳で聞いて、車には乗ってみて、運転してみて、初めてその自動車の良さや不具合が実感できる。 ちなみに、オーディオ先進国だったヨーロッパやアメリカの著名なオーディオ評論家は、自宅にラボを持ち、オーディオ計測器を設置し、各種の特性を計測し、その実測データを根拠に、聴感テスト評価を雑誌に掲載していたのを覚えている。 評論家はメーカに対し、いいものはいい、改善すべき点や劣っている点はズバッと表現する。 このようなユーザーフレンドリーな評論家や雑誌社が現れることを期待している。 そのうえで、ユーザが自分の好みで、商品を選んで買えばいい。 こういう成熟した社会が早く来てほしい。日本はまだまだ、そうはなっていない。YopuTubeでも、科学的根拠に基づいた記事が発信できれば、『いいね!評価』がぐんと上がるのではないか! 『科学的根拠』とは、「あいまいな主観でなく、再現性がある事実に基づく」という意味。 |
2021年12月22日(水)
わが人生、車の履歴書
| 初めて車を買ってから約50年、今まで乗り継いできたマイカーの紹介です。 ■1970年頃;日産 ブルーバード1300(中古車);FR車:約2年間 フロントとリアーのボンネットが、ぼってりと垂れ下がったデザインが特徴、変速機は3速ハンドルチェンジ、職場の先輩から譲り受けた中古車だったが、大きなトラブルなく乗れた。当時の車内はビビり音がよく出た。  ■1972年頃;日産 サニー1000(新車);FR車、カローラ1100と競い合った名車:約9年間 新車を購入、小型・軽量でよく走った。冬はチョークボタンを引いてエンジン始動した。4,5回で始動できなければバッテリーが上がった。電子点火装置を自分で取り付けて対応した。当時のバッテリーは性能が悪く、低温時に電圧が低下し、セルモータや点火プラグの放電が弱くなりエンジンがかかりにくかった。出勤時にエンジンがかからなくて、イラついたことを思い出した。「+100の魅力」の宣伝文句のカローラと競った名車  ■1980年頃;日産 ブルーバード1800(新車)、FR車、初の排ガス規制対策車;5年間 サニーより、一回り大きな車体で、この頃から『排気ガス規制』が始まった。詳しくは、後記する。  ■1985年頃;トヨタ コロナ1800EX(新車);FF車、電子燃料噴射エンジン:4速オートマ;7年間 コロナとコロナマークⅡがあり、こちらは安い方のコロナ。オーバードライブ4速オートマ車。軽快に低燃費でよく走った。  ■1992年頃;ホンダ アスコット2000(新車);FF車、VTEC・DOHCエンジン:8年間 初めてのホンダ車、エンジンのホンダに偽りがなかった。高速道路の走行も静かで、ハンドリングがしっかりしていて安心して走れた。スピード違反で捕まったこともある。  ■1997年頃、トヨタ クレスタ2500(新車);直6エンジン、コロナマークⅡの兄弟車:6年間 直6エンジンのなめらかな音が気に入った。燃費はチョイノリで8km/L程度。トヨタらしく、可もなく不可もない車で、特に印象はない。  ■2003年頃、ホンダ インスパイア2500(新車);米国産、V6エンジン:8年間 2度目のホンダ車、V6エンジンの力強さは抜群、よく走る車だった。ハイオク仕様だが、レギュラーガソリンを入れていた。燃費はチョイノリで8Km/L、高速で12km/L。クレスタより一段と静かで、高速道路ではしっとりとしたハンドリングで、安心して走れた。  ■2011年頃;ホンダ フィット1500ハイブリッド・IMA方式、燃費はまあまあ:3年間 現役を去り、そろそろ身の回りのダウンサイジングを始めたので、コンパクトカーに乗り換えた。初めてのハイブリッド車、燃費が今までの車の半分に減った。有難い。燃費;一般道のチョイノリで15Km/L、高速道路で20Km/L程度  ■2015年頃;ホンダ フィット1500;スポーツハイブリッド・i-DCD方式 リコールが5回もあった;5年間 ホンダハイブリッドの2世代目、1モータ+DCD(ダイレクトクラッチ)の独自のハイブリッド方式。初代HVから大幅な燃費改善がなされた。モータ出力をアップし、モータ走行が可能になった。リチュウムイオン電池。 燃費;一般道のチョイノリで20Km/L、高速道路で25Km/L程度、少々硬めのサスペンション設定。  ■2020年;ホンダ フィット1500;ハイブリッド・e-HEV方式;使用中 ホンダハイブリッドの3世代目、2モータ方式ハイブリッド車、i-MMDからe-HEVと名前が変わった。 熟成されたHVシステムは、実にスムーズで力強く走る。まれにみる完成度が高い車だ!燃費;一般道のチョイノリで25Km/L、高速道路で27Km/L程度。この車は、今まで50年間乗ってきた車の中で、一番自分にはしっくり乗りやすく大満足。価格も手ごろで、サイズもぴったりくる優れモノなのに、なぜか今一、売れ行きが伸び悩んでいる。この素晴らしい車が、余り話題や人気にならないのはなぜか不思議に思う。この良さはじわーっと認められ、ドライバーが惚れる車になるはず。 “清楚で、つつましい佇まいだが、味わい深く、安全運転をしっかり支えてくれる安心できる車”  今、乗っているフィットハイブリッド e-HEV です。 今まで乗り継いできた車の記憶を辿り、印象を書いてみました。 ■ブルーバード1800から、『排気ガス規制』が始まり、自動車メーカはいろんな対策を試みました。 このブルーバードには、新開発 Zエンジンが工業技術院のエンジン開発技術賞を受賞したもので、技術の日産のエンジンにふさわしいと思い買ったのですが大失敗でした。Zエンジンは、希薄ガスの燃焼を確実に行うため、一気筒に2個点火プラグを取り付け点火し、高速燃焼させることで排ガスを削減するという謡い文句でした。レギュラーガソリン仕様で、圧縮比を10以上に高く設定していたため高速道路を80Km以上で走ると、エンジンから常時『チリチリ(または、カリカリ)』というノッキング音が発生しました。 ディーラにその話を伝えると、デストリビュータの位置をずらして、点火タイミングを遅らせました。この対策で燃費は悪くなり、出足が悪くなりました。極端に走りが悪くなったので、再度ディーラに持ち込むと、今度はエンジンとヘッドカバーに挟むガスケット(銅製パッキンシート)を厚いものに交換したということでしたが、これにより圧縮比が下がり燃費が悪くなりました。何回かディーラとやり取りしましたが解決しませんでした。 多分、ディーラもこのZエンジントラブルで困っていたと思います。この時のディーラの対応の悪さと、サービスマンの高飛車な態度に、『技術の日産』に惚れていた気持ちが完全に萎えてしまいました。その後は、日産が嫌になり、全く乗る気がせず、現在まで1台も買ったことがありません。 今も、テレビコマーシャル等で、矢沢栄吉の『ヤッヤエー、ニッサン』と格好よく宣伝しているのを聞くとむかつき、複雑な気持ちになります。 しかし、最近、ノート e-Powerが、『カーオブザイヤー2021』を取るなど、好評のようです! ■良い印象が残っている車は? トヨタ コロナ1800EX FF方式 その頃、クラウンやコロナマークⅡなどの高級車はエンジンの気筒毎に電子燃料噴射器を設けて、混合ガスの最適制御を行い、馬力アップと排気ガス削減の両立を図っていた。一般車にこの装置を取り付けるにはコストが合わない。そこで、電子燃料噴射器1個で、4気筒にガソリンを供給する方式をこの車に初めて採用した。従来のキャブレータから電子燃料噴射に変わり、燃費が良くなり画期的な車になった。それまで、冬の厳寒期のエンジンを始動させるのが至難のことだったのが、この車は確実にエンジンがかかった。但し、弱点は高速道の登坂時に速度が落ち、カーブではタイヤのきしみ音が出るなど、高速での性能は良くなかった。この車を手放したのは、発進時にエンジンが空転して車が動かなくなったこと。出勤途中で何回かこのトラブルが生じ、出勤に間に合わないこともあった。原因はオートマのトルコン不良で、修理に20万円ほどかかると聞いたので、買い替えを考えていた。 近くのホンダ店に初めて行ってみた。その時に勧められ試乗させてもらったのが、アコード姉妹車の「アスコット」だった。これは2000CC 4気筒 VTEC・DOHC・バランサー付エンジンで、乗った瞬間にその加速のすごさと、走りの違いが実感できた。静かで、燃費もよく、実によく走った。後輪のサスペンションは、ダブルウィッシュボーンで、ディスクブレーキを採用したスポーツ仕様だった。大変乗りやすく運転しやすく疲れないと感じた。前方・後方とも視野が広く、ハンドルやペダル、その他のスイッチ類の配置もしっくりくるものだった。初めてオートクルーズ付きの車に乗ったが、高速道路では大変楽に運転できた。娘が三重大に入学したので、大阪と津市の行き来を何回となく行ったのを覚えている。この車は、非常によくできた車で、不満な点は全くなかった。 その後、少し余裕ができたので、憧れの6気筒車が欲しくなり、当時大人気のトヨタマークⅡの3兄弟のクレスタ2500に乗り替えた。この車は、トヨタらしく無難な作りで、特に印象はない。マークⅡは大ヒッ商品で、皆さんが乗っていたので良い車だったと思う。 その後、アスコットの好印象が忘れられず再びホンダのディーラに出向き、インスパイア・V62500に乗り換えた。直6のトヨタエンジンに比べ、ホンダのV6エンジンは同じ2500CCでもパワーフルな感じを受けた。VTEC・DOHCのホンダの技術には感心した。この車も実によく走り、静かで、運転して疲れない車だった。 アメリカホンダ製の輸入車で車体が大きく、歳と共に、取り回しが少々面倒になってきた。 ■その後、現役を引退したので、生活をダウンサイジングし、車もコンパクトカーに乗り替えた。 フィットは初代フィット(妻用)に乗っているが、コンパクトカーとしては車内が広々としているのが特徴だ。 ■FITハイブリッド車を3世代乗り換えてきた印象? ・1世代は、IMA方式 ・2代目は、i-DCD方式、 ・3代目は、e-HEV方式 それぞれのハイブリッド方式に特徴があるので、少し詳しく書いてみる。 初代 IMA方式は、いわゆるマイルド・ハイブリッド方式で、エンジンとモータ軸が直結した簡単な構造。 発進時は、モータがエンジンをアシストし、スタートはスムーズだが、燃費は大きく改善できない。 ヨーロッパ車(ベンツ、BMWなど)は、この方式を採用している。彼らは48Vの鉛電池を使用。 フィット IMA方式はニッケル水素電池を使い、電圧は高く、IMA方式の方が進んでいた。 2代目 i-DCD方式は、別名、スポーツハイブリッドと呼ばれ、エンジン車のギアーチェンジの感覚を生かしながら低燃費を図った。ドイツ製のダイレクトクラッチという変速機を巧妙に組み込んで、1モータでありながらハイブリッドの特徴を生かそうと苦心した力作だった。 しかし、このダイレクトクラッチの複雑な制御と、モータ制御プログラムの熟成不足があり、いろんな走行状態で不具合が発生した。その都度、リコールで改良を重ね、最終的には特徴のあるHV車に仕上がったが、不評はぬぐい切れず、販売台数は平凡な数字に終わった。 3代目 e-HEVの誕生 ホンダは既に、2モータハイブリッド(i-MMD方式)を高級車(アコードなど)で採用し、このクラスでは断トツの燃費性能を誇っていた。このi-MMD方式をフィットの小型コンパクトカーに採用するには電装部品の小型化と、大幅なコストダウンが必要だった。 ■e-HEVシステムの構造? 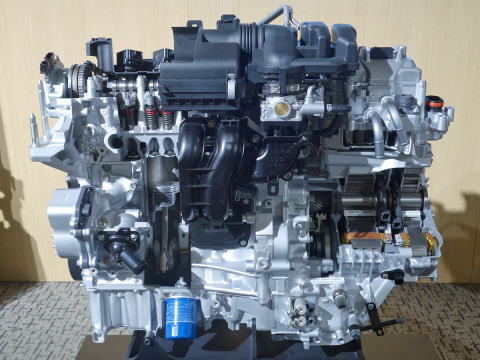 走行用&発電用 2モータ;高トルクを発生するため走行用モータはコアが部厚い モータ部の解説写真 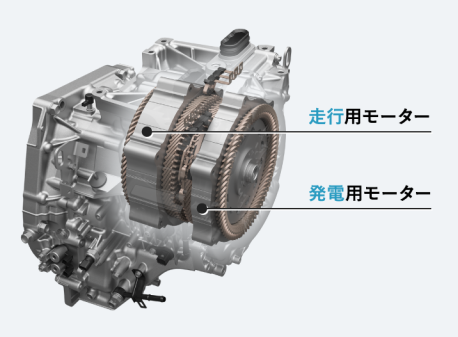 ■e-HEVの特徴? ①走行用モーターと、発電用モーターの固定子コアー形状が同じ コアー用ケイ素鋼板を打ち抜く金型が同じものを使用でき、安価に鉄心が大量生産できる。 鋼板の枚数を変えるだけで、積厚みを変え、走行用と発電用モータが効率的に生産できる。 ②エンジン軸とモーター軸をクラッチでON-OFFする構造を採用している。 これにより、高速道路走行時は、エンジン直結で走るので、燃費が良い。 走行状態に合わせて、3つのモードがある。合理的なシステム。 ■eHEVシステムの3つの走行モード? 新型フィット ハイブリッドは2モータ式で、e-HEVと呼ばれている。日産ノートe-Powerとよく似たシリーズハイブリッド方式だ。ホンダは日産e-Powerと一味違い、ホンダらしい工夫が加えられている。それは高速道路を走行中はエンジンと車軸が直結にした方がロスが少ないので、時速約70km以上ではクラッチで直結するようになっている。(下図参照)
ノート e-POWERはエンジン⇒発電機⇒バッテリー⇒モーター⇒車軸とつながるシリーズ方式。 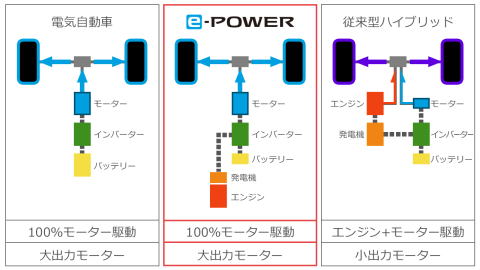 e-HEVは、エンジンのパワーをロスすることなく走行に生かせる。 ノート e-Powerは高速道路での燃費はあまりよくないと聞いている。 フィット eHEVは高速道路走行でも高燃費を叩きだす。(実燃費 25Km/L~28Km/Lぐらい) ■なぜホンダや日産や、トヨタ系列のダイハツが、シリーズハイブリッド方式を採用したのか? 『ハイブリッドの次期はEV』という見通しの下、シリーズハイブリッドはすぐEVに転用できるから。 シリーズハイブリッド方式はモータで走るので、大きな出力のモータを積んでいる。EVのモータとして共用ができる。シリーズハイブリッドからEVへはエンジンを外せばすぐにできることになる。 EV時代を睨むと、シリーズハイブリッドはその過渡段階と言える。いつでもEVが造れることになる。 ■トヨタ ハイブリッド方式(THSシステム) 初代から一貫して2モータシリーズ・パラレル方式でエンジンとモータのいいとこどりをした方式。車は発進・加速時に大きなトルク(回転力)が必要になるが、モータはそれに適合する特性を発揮する。逆に高速走行時はトルクよりパワーが必要になるが、エンジンは高速回転域に大きなパワーを発揮できるので、この二つの特性をうまく生かしたのがトヨタTHSハイブリッドと言える。 エンジンとモータの特性の違いを車の走行状態に応じて最適に組み合わせるため独自のメカニズムが組み込まれている。それが遊星歯車で、モータは複雑なプログラムで制御される。トヨタ自動車の開発力の凄さが窺える。 ■世界の自動車の新潮流 トヨタ THSがハイブリッド車のデファクトスタンダードになりつつあり、トヨタが一人勝ちになったので、世界の自動車メーカはHVを経ずに、一気にEVに舵を切った。 まさに、『ゲームチェンジ』が起きた。 トヨタ自動車は、それに気づき、THSシステム特許無償公開を発表したが、外国メーカがこれに呼応したところはない。各社はいまさら、トヨタハイブリッドTHSを追いかけても勝てないと踏んでいる。 その代表がテスラだ。今後、続々と世界の自動車メーカからEVが発売される。 ■EVになれば、自動車産業の姿が大きく変わる。 EVはエンジン車に比べて、部品点数は一気に1/3以下になる。 すそ野が広いと言われる自動車関連産業は沢山の部品供給で成り立ってきた。それがEVに変わることで不要になる。今はその過渡期に差し掛かっている。各部品メーカは脱自動車分野に生き残りをかけて取り組み始めている。 |
2021年12月6日(月)
高齢者ドライバーが[ プリウス ]で事故を起こしやすい要因は?
| 毎日のように、新聞やテレビで高齢者ドライバーの事故のニュースを見る。本当に痛ましい事故が多発して事故に遭った人はもちろん、事故を起こした人も、大変痛ましく思う。交通事故は起こさないように十分注意して運転している。 先日、11月の誕生日に更新した新しい免許証を交野警察に行きもらってきた。有効期間は3年間だ。 さて、表題の『プリウスの事故が多い』のには、何か訳がありそうなので、ネットで調べてみた。 同じようなことを不思議に考える人があるようで、ネット上に数件の記事を発見したので紹介する。 理由;下記の理由で、高齢者には運転時、疲れやすく、注意が散漫になるのでは? ①視野が悪い(特に後方視界が狭い);視覚疲労 ②ステアリングの軸が左にズレている;ステアリングの中心が左側に寄っている。 ステアリングに路面の振動が伝わってくる;腕の疲れの原因 ③シート材料やシート形状が良くない;腰痛の原因 ④電子式シフトノブが分かりづらい;従来の感覚と違う;脳に負担をかける ⑤ペダルレイアウト;ブレーキペダルが中央寄りで、普通に踏むと足がアクセルペダルに当たる。 ブレーキペダルを踏んだつもりが、アクセルペダルを踏んでしまう。;足の疲れ このような要因が重なると、精神的、肉体的な疲労につながり、高齢者は運転感覚をマヒさせるのでは? トヨタ車は素晴らしい車を販売している。以前に乗った車は、コロナ1800EX、クレスタ2500の2車種。 どちらも普通によくできた車だった。ただ、特に惚れ込むところはなかった。 その後、家内用にヴィッツ クラヴィア1300を買ったが、後方窓が狭く、後方視界が超狭く、後部座席の枕(ピロー)を取り外して使っていた。また、運転席(特に助手席)に座ると、太ももが圧迫されるほど狭く、助手席はタイヤえぐりが大きく、足を伸ばせなかったのを覚えている。 その後、初代FITに買い替えたが、見違えるほど室内にゆとりがあり、前後の視界がよく驚いた。同じコンパクトカーでも、こんなに違うのかと驚いた。 ホンダは、MM思想と呼んでいるが、“Man maximum,Mecha minimum”の設計思想が貫徹されている。 いま、我が家には、FIT3 1300(ガソリン)と、FIT4 e-HEVハイブリッドがある。両方ともホンダの特許であるセンタータンクレイアウトにより、コンパクトカーでありながら、誰もが認める室内の広さは秀逸だ。 しかも、操作部は使う身になってレイアウトされ、運転していて疲れにくい。 トヨタ車は、最近、たくさんの車種を販売している。トヨタ自動車は、車種により販売店を分ける販売方法を止め、すべてのトヨタディーラ(5系列店)で、すべての車種が販売できるように改めた。これで、ディーラー間の販売競争も激しくなる。加えて、若者の車離れが激しく、トヨタですら大変な状況になると思われる。 そこで、目を引くヤンチャで、ガッツのあるデザインの車が多くなったのもその性だろう。 デザイン優先で車づくりをすると、運転者の目線でモノ作りする原点から少々ズレてきているのではないかと勝手に考えている。(あくまで、個人の考え) その結果、プリウスは電子制御による新しい操作方法の採用で、高齢者ドライバーには従来の運転感覚からズレているのではないかと思う。 確かに、友人のプリウスに試乗させてもたっら際にも、そういう感じがした。 |
2020年11月8日(日)
トヨタの一人勝ちが意味するもの?
| トヨタの一人勝ち、経営戦略のすごさ! どこまでやり切るのか? 10月の自動車販売速報が発表された。乗用車部門ベスト10で、なんと登録車10車種中、トヨタが8車種に及ぶ。ホンダが、やっと、フィットとフリードの2車種のみランクアップ。 その他の自動車メーカはベスト10に入ってこなかった。 2020年10月車名別販売台数ランキング 乗用車ベスト10 1位 トヨタ「ヤリス」:1万8592台(ー) 2位 トヨタ「ライズ」:1万3256台(ー) 3位 トヨタ「ルーミー」:1万1487台(前年同月比165%) 4位 トヨタ「カローラ」:1万275台(前年同月比91.8%) 5位 トヨタ「アルファード」:1万93台(前年同月比196.7%) 6位 トヨタ「ハリアー」:9674台(前年同月比536.3%) 7位 ホンダ「フィット」:9001台(前年同月比287%) 8位 ホンダ「フリード」:7849台(前年同月比179.7%) 9位 トヨタ「ヴォクシー」:6258台(前年同月比142.4%) 10位 トヨタ「シエンタ」:6077台(前年同月比65.3%) 軽自動車ベスト10 1位 ホンダ「N-BOX」: 1万6052台(前年同月比101.7%) 2位 ダイハツ「タント」:1万3099台(前年同月比118.3%) 3位 スズキ「スペーシア」:1万2245台(前年同月比98.5%) 4位 ダイハツ「ムーヴ」1万472台(前年同月比137.4%) 5位 ダイハツ「タフト」:7471台(ー) 6位 日産「ルークス」:7069台(ー) 7位 スズキ「ハスラー」:6536台(前年同月比140.8%) 8位 ダイハツ「ミラ」:6161台(前年同月比114.8%) 9位 ホンダ「N-WGN」:5943台(前年同月比3229.9%) 10位 スズキ「アルト」:5325台(前年同月比82.7%) 軽自動車を含めてトップは、ヤリスだった。2位は、相変わらずホンダのN-BOXが続く。 このように、殆どトヨタ車一色に塗りつぶされたのは初めてではないか? 「他の自動車メーカは何をしているのだろう?」と疑うような結果だ! この理由はいろいろ考えられるが、一つは今年5月から、ディーラで取扱できる車種をブランドで分けすることをやめたこと。トヨタの各ディーラは全トヨタ車が扱えるようになった。 各販売店にとっては扱うモデルが倍増し、トヨタ系列店同士の競合がなくなったので「商売はし易くなった」と表面上は喜んでいる。これはトヨタ販売店にとってはメリットといえる。 ただデメリットもある。 「扱い車が一気に2倍以上も増え、各モデルの商品内容を覚えるのが大変。同じ車種を扱っている店舗が近くに沢山できたので売れ行きのよくない拠点は他店舗に吸収され消滅してしまう可能性がある」ということが挙げられる。 言い換えると、トヨタ系列のどこの店でも、トヨタ車なら何でも買えるということになった。ユーザは、近くのトヨタ系列店に行けば、欲しい車に試乗でき、買うことができる。今までは、トヨタ店、トヨペット店、カローラ店、ネッツ店の4系列店と、レクサス店があり、それぞれの名列店が販売できる車種が決まっていた。 現在、トヨタ(レクサスを除く)ブランドで販売している車種は、なんと51車種。 トヨタのHPから車名を拾い上げると、(こんなにたくさんあったのかと驚愕する!) アクア、アリオン、アルファード、エクスファイア、カムリ、カローラ、カローラスポーツ、カローラツーリング、カローラフィールダー、クラウン、グランエース、コペンGR SPort、コースタ、シエンタ、CH-R、JPNタクシー、GRヤリス、スープラ、タウンエース、ノア、ダイナ、ハイエース、ハイエースコミュータ、ハイエースワゴン、ハイラックス、86、ハリア、パッソ、ピクシスエポック、ピクシスジョイ、ピクシストラック、ピクシスバン、ピクシスメガ、プリウス、プリウスα、プリウスPHV、プレミオ、プロボックス、MIRAI、ヤリス、ヤリスクロス、ライズ、RAV-4、RAV-4PHV、ランドクルーザー、ランドクルーザープラド、ルーミー、ヴェルファイア、ヴォクシー、ウェルキャブ、 (注)下線のモデルは軽自動車(ダイハツOEMらしい) その内、人気車種は8車種となっている。 アルファード、クラウン、ヤリス、GRヤリス、ヤリスCROSS、ハリアー、ハイエース、ROOMY 系列店の特徴を調べると、 ■トヨタ店 戦前戦後にかけてトヨタの発展を支え、約70年以上の歴史を持つトヨタ車販売のパイオニア的なチャネル。歴史と伝統に裏打ちされた上質なおもてなしを展開している販売チャネル。クラウンなど役員送迎用の高級セダン、営業車・ライトバンやトラックなどの商用車を中心に取り扱う、主に富裕層や法人向けのディーラー。 キャッチコピーは「最上の出会いをトヨタ店で」。 ■トヨペット店 1953年に設立されたトヨタで2番目のチャネル。コロナやマークⅡを中心に時代を切り拓き、常に日本のミディアムカー市場をリードしている販売チャネル。 40~60代程度の子育てが一段落した、ある程度、年齢層が高めで、比較的裕福なファミリー層に向けたディーラー。 キャッチコピーは「もっとクルマの話、しませんか。 Answer, for you. TOYOPET」。 ■カローラ店 1961年にパブリカを扱うパブリカ店として営業を開始、その後1969年、カローラ店に名称を変更。ロングセラーを続けるカローラをはじめ、豊富な品揃えの量販チャネル。 20~30代程度の小さな子どもがいる比較的若いファミリー層に向けたディーラー。ミニバンやコンパクトセダンなどエントリー層向けの大衆車を多く扱っています。店舗によってはダイハツの軽自動車も取り扱っています。 キャッチコピーは「うれしいこと、全力で。あなたの街のカローラ店」。 ■ネッツ店 2004年にネッツ・ビスタ両チャネルが融合し、新しい「ネッツ店」が誕生。ヴィッツ等のコンパクト車種や、ヴォクシー・ヴェルファイア等のミニバン車種などをラインナップし、トヨタの新しいお客様層を拡げていくチャネル。 10~20代前半のスポーティーなモデルを好む若年層向けのディーラー。 キャッチコピーは「-the Creative-」。 ■レクサス店 年収1,000万円以上の高所得者層向けに、トヨタが世界65カ国で展開している高級車ブランド。 キャッチコピーは「EXPERIENCE AMAZING」 ユーザは、次々と車を乗り継ぐので、以前に買ったセールスと互いに親しい関係にあることが多い。セールスは、自分の得意様(ユーザ)に、次も乗り換えてもらいたいので、訪問をしたり、情報提供したりサービスするが、そのユーザがトヨタの他の車に興味を持った場合、自分の店で取扱いできない車種は販売できなかった。 そこで、今回、店による販売車種の規制を完全撤廃し、どの店(ディーラ)でも買えるようにした。 この話を聞いたときは、全国にあるたくさんのトヨタディーラ同士で食い合いが起き、値引き競争が激しくなるのではないか?と思ったが、結果はそうなず、良いほうに転がったといえる。 トヨタは、世界NO.1自動車メーカであるが、珍しく車のデザインの統一性を重視しないように感じる。言い換えると、いろんなデザインがあり、何でもありの状態だ。 レクサスだけが、デザイン性を統一性を保っている気がするが、トヨタ車はバラバラのデザインになっている。これがトヨタの販売の幅を広げているのかもしれない。 マツダは『魂動』をコンセプトとして、すべての車で一目見ればマツダ車だと誰でも分かる。大きな口を張ったフロントグリル、小生は『ジンベーザメ』と言っているが、このマツダのデザインの評価は欧州においても高いと聞いている。個人的には好きになれないが。 ドイツ社のベンツ、BMW、VWなどは落ち着いた洗練された美しい形にまとめているが、日本の車、特にトヨタ車は、『これでもか!』という目を引く(目立つ)顔つきや、口を開けたデザインにまとめている。洗練された上品さが感じられないが、デザインは個人の好みだから売れるデザインがいいのかもしれない。 ホンダはトヨタとマツダの中間的なデザイン志向で、何かの統一したデザインにしたいという感じを受けるが、まだ『これだ!』という確たる形に行き着けていない感じがする。 トヨタ車はデザインがバラバラなので、今回の販売系列の見直しの成功の一つの要因ではないか。しかし、メーカとして、これだけたくさんの車種を製造し、販売することは、工場の工程管理や部材調達管理や、営業の受注管理作業が膨大になり、大変な業務負担になっているはずだ。それを上手くこなしてやっているのだから感心する。 ITを徹底して活用した結果、できることだと思われる。 ディーラの販売モデル規制をなくしたのは、今後の自動車の販売量が減少するのを見込んで、先手を打った経営戦略のはず。それが、コロナウイルスの流行で各店の生き残りがかかり、懸命に販売に努力した結果が出たのだと思う。このコロナ禍の中で、一番早く業績を回復させ、業績の悪化を最小限に留める経営力はさすがにすごい!。 それにしても、自動車会社として、(兄弟・姉妹車)もあるが、51車種を製造・販売し続けることは大きな課題だと思う。 一モデルに数色の塗装色も用意し、その他グレードもあるのだから、その組み合わせは天文学的な数字になる。トヨタも他の自動車会社も、シャーシ(車体)やエンジンやモータや、その他部材の共用化を図り、部品点数を少なくする取り組みに力を入れてやっている。 トヨタ一人勝ちの販売力が、車種のバリエーションの多さで、ユーザの『どんな好みにも応えられる』ということで売れているのなら、車種を絞りこめば販売が落ち込む心配が出る。 販売量が増えている間は利益が出るが、売りが伸びなくなってきたときに、効率や、管理にかかる費用がどう利益に影響するか見どころである。その時、トヨタ自動車の経営がどういう方向に向かうかが注目に値する。 5月以降の全車種取り扱い措置は、近い将来車の需要の成長の鈍化、または減少を見通した車種の絞り込みを狙ったものとみるのが妥当かも。 |
2010年7月12日(日)
新型フィット4を半年乗った印象と評価
(納車後、半年経過しました)
| 12月に早期契約した新型FITは、オートブレーキホールド(ABH)と、電子オートパーキングブレーキ(EBP)の部品の不具合で、2か月発売が延期されました。これは軽自動車のN-BOXに先行搭載していたシステムと同じものですが、N-BOXに不具合が見つかり、その対策に時間がかかったという経緯でした。 やっと2月に納車になった新型フィットハイブリッドは、後輪ブレーキがドラム式からディスク式となりました。このクラスのコンパクトカーは、すべてドラム式ブレーキが一般的ですが、FIT4はブレーキ性能が高いディスクになり、この点は待った甲斐がありました。 発売が遅れた件はこれくらいにして、『半年点検が8月です』というハガキが届きました。早やくも、半年がたった! 今まで約2000kmほど走りました。新型FIT4 フィットハイブリッドのテクノロジーについては、以前に紹介しましたので、今回は乗った印象についてです。 一言でいえば、実によくできた車で、満足度は95点です! 前のFIT3ハイブリッドは、納車直後に不具合を見つけ、その後、5回もリコールがありました。その理由は、1モーターとエンジンを7速DCD(ダイレクト・クラッチ・ドライブ)というドイツ製変速機を巧に組み合わせ、駆動する方式を採用し、2モータ並みの燃費を実現するというホンダらしいアイデアでしたが、検討や熟成不足で、いろんな走行状況でトラブルが発生しました。 残念ながら、このi-DCDスポーツハイブリッド方式は発売の出足でつまずきましたので、その後、改良し大変よくなったにもかかわらず評価がいまいち上がらず不調に終わりました。 そこで、一念奮起して、e-HEVに切替えました。 ホンダの名誉のために書き添えますと、i-DCD方式はリコールの後、徹底した改善や熟成を行い、問題点を解決し、スムーズなドライビングを取り戻して大変良くなりました。この改善したシステムは、ホンダ車の小型車に採用され現在、販売されています。 今回の新型フィットは、新しく2モータハイブリッド方式を採用したもので、この方式はアコードなど大型車に既に搭載済みで、高い評価を得ているハイブリッドシステムです。 しかし、コスト的には高くなりますので、コンパクトカーに搭載するには、大幅なコストダウンと、システムの小型化が必須ですので、その課題を技術開発により解決し、新型FIT4に初めて採用されました。 さて、満足度95点の意味は、コンパクトカーの常識を超えた一ランク上の出来栄えになっていることです。 その内容は? とにかく、運転して疲れないこと!です。 (どこまで走っても、楽に、安全、安心して疲れを感じないで、運転ができること) ①静かで、振動が少ない; ・タイヤのノイズ(ロードノイズ)が低く押さえられ、道路の段差などのコツコツ感がない ・風きり音が少ない ・エンジン音が気にならない ②燃費が非常に良い;(エアコン動作時) ・買い物や、チョイノリでも、24km/L前後 (前のFITハイブリッドは、17km~20km/Lだった) ・高速道路走行は、26km~27km/L前後 (前のFITハイブリッドと同程度) ③走り(発進や加速)が超スムーズ ・モータ駆動なので、スルスルとスムーズに走り出す感じ ④前方視界は秀逸(後方視界も良い) ・前方のピラーが細いので視界が遮られない ・後方も十分よく見える ⑤椅子の座り心地は非常に良い、長距離にも疲れない。後席も同様。 ⑥高速道路では、アクセルペダルから足を離しておける。楽ちん運転で疲れない ・アダプティブ・オートクルーズは前方の走行車を捉え、安全に追走してくれる。 ・レーンキープは、車線の中央を自動運転してくれる(ハンドルは軽く握っておくだけ) ・車間距離も自由に設定できる。 ⑦オートブレーキなので、信号待ち毎にブレーキペダルを踏んでおく必要がない ・オートパーキングブレーキ付きなので、発進はアクセルを踏めば解除する。 ⑧エアコン操作の、ダイヤルツマミ式は大変使い勝手がいい。 ・デジタル時代にも、アナログ感覚のツマミ方式は超使いやすい。 ・スイッチの回す切れ味(クリック感)がすごくいい ⑨2本スポークスハンドルは太さも適当で、非常に使いやすい ・今時、珍しい2本スポークスタイプだが、運転してみると、よく手になじむ。 ・ハンドルの太さ、握りの太い部分も手ごたえがピッタリでよい ⑩ハンドルが、しっとりとして軽い。 ・16インチタイヤ装着車は、VGR(バリアブル・ギアー・レシオ)になっている。 ・切り始めが軽くて楽にハンドルが操作できる。 ⑪その他(アクセサリー) ・ECT-2;走行時間や渋滞状況等を適時に知らせてくれる (音声合成の声のひずみが大きい。音声を良くしたい、小さいスピーカの性か?) ・カーナビ;(Panasonicストラーダ、CNーF1XVD 9インチ大画面) これを自分で選んで、大正解だった。安くて高性能なナビだ。 (HD画質で、IPS液晶は綺麗で最高、地デジ放送もフルセグできれいに受信) (GPSと天頂衛星を組み合わせているので、ナビの表示精度は抜群に良い ・ドライブレコーダ;コムテック ZDR-015 (前・後カメラは200万高画素、HD並みの高画質録画でクッキリ) ・レーダー探知機;ASUURA VA-810E (GPS受信により、地図精度がナビ同様に高い) 今回の買い替えは、高齢者でも身にあった大きさで、楽に運転でき、安全をサポートしてくれる安全補助装置付の車を探していました。勿論、燃費も課題の一つ。それにぴったりの車が、新型FIT4ハイブリッド。 もちろん、サポカー補助金(10万円)も頂きました。 この新型FIT4ハイブリッドは、期待に十二分に応えてくれるもので、評価は95点です。 では、残りの-5点は何か? それはフロントデザイン もう少し、センスがあり、嫌味のない顔つきができないか?と残念だ! 今、国内で売れている車は、ダボハゼかジンベエザメのようにガバッと大口を開いたイカツク目立つものが多いが、私はこのようなデザインは好みではない。 今回のフィットは、逆に少々おとなし過ぎる感じを受ける。飽きがこないで長く乗るには、このくらいがいいのかもしれないが、もうちょっと何かピリッと引き締まったものが欲しい。人もそうだが、顔つきは最も大切なセールスポイントになる。どんなに素晴らしい性格(商品内容)でも、やはり見た目(外観デザイン)は、直感的に気に入るか、惚れるかを決める要素になる。 そういう意味では、ドイツ車に一日の長があり、軍配が上がると思う。大いに参考にしてほしい。嫌味がなく、特徴を出しながら、洗練され、うまく新鮮味も醸している。 この点がマイナス5点とした。機能や性能面のマイナスはなかった。 それほど完成度が非常に高い車に仕上がっている。 (追伸) 欲を言えば、もう一歩の静かさと、サスペンションのしなやかさがあれば、一層凄い。 そして、実燃費は30km/Lを狙ってほしい。燃費の改善余地はまだ大いにあるはず。 PCU(パワーコントロールユニット)のパワーデバイスを、RC-IGBTからSiCに代えると、発熱が抑えられ、現状の冷却装置が不要になるはず。その分の放熱ロスと軽量化で、効率は数%改善できるはず。 但し現状ではSiCのコストと、調達面の課題があるのだろう。 さらに、もう少しリチュウムイオン電池容量を大きくすれば、燃費の改善が図れるはず。これもコストアップに直結する課題だが。 でも今は満足しています!! |
2020年5月3日(日)
(憲法記念日)
『軽』がよく売れている理由は?
| 最近、軽自動車がよく目につくと思いませんか? 以前は田舎に行った時だけでしたが・・・。 今、確かによく売れています。各戸の駐車場や、スーパ等の駐車場でも『軽』が目立ちます。 新車の販売台数の実に6割が軽自動車になっています。 軽自動車は世界に類例を見ない日本独自の車両法により、自動車税や重量税、車検など税制面で特例措置され優遇されていますので、普通車に比べると維持費が大幅に安くなります。 以前はチョイノリ車とか、田舎で見かける車とか言われてきましたが、最近は堂々とファミリーカーになりました。 ここまで、販売が伸びてきた主な要因は、実用上、普通車と変わらないような車になったこと。 軽自動車は昭和24年に発効し、長さ2.8m、幅1m、高さ2mエンジンは150ccでした。 翌年に、長さが3m、幅が1.3m。高さは2m、エンジンは350cc 現在は、長さが3.4m、幅が1.48m、高さは2.0m、エンジンが660cc以下となっています。 導入時はエンジン容量が僅か350cc(後、360cc)に制限されていましたので、馬力が弱く、車のサイズも小さく、狭く、何とか走るという程度でした。坂道に至ると、途中で止まるのかと思うほど、しんどい状態でした。一人乗りでは何とか走っても、二人乗れば急に加速が落ちました。エアコンなどとんでもないものでした。 それが、衝突安全基準が導入されたことにより、車体が大きくなり重量が増えるためエンジン容量が660ccに拡大され、これにより車として一人前の馬力を出せるようになりました。 車体の幅と長さは厳しく規制されていますが、高さは2mですので、背が高い軽自動車が開発され、車内空間が大きく拡大し、普通車と変わらない広がりを手にしました。 今よく売れているハイトワゴンタイプの『軽』はそうして生まれました。 最近、さらに省エネ・省燃費規制が厳しくなり、軽自動車は再び大きな課題に遭遇しましたが、 日本の各自動車メーカは競って挑戦し課題をクリアして普通車の領域まで迫ってきました。 普通車の排ガス対策や燃費対策としては、ハイブリッド方式があります。これはモータと大容量バッテリーと電力制御回路(CPU)が、エンジン車にプラスしなければなりませんので、どうしても30万円ぐらい高くなります。もちろん、ガソリンエンジンやジーゼルエンジンだけで、排ガス規制をクリアしている車もありますが、規制値が次第に厳しくなる中で、やはりハイブリッドやEVに移行する動きが活発化しています。 軽自動車は安いのが大きな魅力でしたが、最近の『軽』は小型普通車(1000cc~1300cc)並みの値段になりました。しかし、実用性は普通車に近づき、走りや燃費もよくなりました。 そこには並み並みならぬ新技術が盛り込まれています。 軽自動車メーカは、ダイハツ、スズキがTOP2として君臨してきましたが、2、3年前からホンダが巻き返して、N-BOXやN-WAGONなどNシリーズが爆発的に販売を伸ばし、ベストセラーカーになり、ホンダは軽自動車でもTOPメーカになりました。 ホンダはもともと小型に強みを持ったメーカですが、なぜか軽自動車はダイハツ、スズキの後塵を拝してきました。それがNシリーズで爆発的に売りを伸ばしたのですが、その理由は? ホンダは、ヤマハやスズキなどと並んでオートバイメーカTOPの座を維持しています。 オートバイのエンジンは馬力(出力)が大きいことが求められます。それは、自動車に比べ車重は軽いので、馬力がモノをいうことになります。 エンジンは馬力を重視するか、トルクを重視するかにより設計内容が違ってきます。 このページで何回も紹介しましたが、出力とトルクと回転数の関係は、 出力=回転数×トルク (P = n×T) で表されます。 オートバイ用エンジンは、回転数を高くすることで、馬力が大きくなるような特性を持たせます。毎分1万回転を超えるようなエンジンで、高回転型出力重視エンジンです。 自動車は車体が重いため、動かすにはトルクが大きいことが求められます。 トルクは回転力とも言われ、 トルク=力×腕の長さ (τ=F×L) 今まで、軽自動車はバイクと同様に出力重視する設計をしてきましたが、ホンダはNシリーズのエンジンは回転数は押さえて、トルク重視型に変えました。 それにより、走りだす際の加速が良くなりました。普通車から『軽』に乗り換えると、一番いやな点は、スタート時のモタモタした加速でした。次にエンジン音がやかましいこと。そして狭いこと、この3つが改善されたことが大きく販売を伸ばした要因でしょう。 省燃費と排ガス規制をクリアすることも課題でしたが、トルク中心にエンジンにすることで大きく改善しました。 エンジンはシリンダー内をピストンが上下することで、吸入-圧縮-爆発-排気を繰り返します。 このシリンダーの内径(ボア)と、ピストンが上下移動する長さ(ストローク)をかけた数字がエンジン容量になります。 円筒状の茶筒のような感じですね。 エンジンは、ストロークに対して、ボアを小さくすれば、ロングストローク型エンジンになります。 逆に、ボアを大きくすれば、ショートストローク型エンジンになります ロングストローク型エンジンはトルク重視型(低回転型) ショートストローク型エンジンは出力重視型(高回転型) 以前、軽のエンジンはショートストローク型エンジンが多く、馬力競争をしていました。 それが、燃費や走り(加速)を重視するようになり、トルク重視のロングストローク型エンジンに代わってきました。 さらに、環境問題で排気ガス規制が厳しくなり、これをクリアするためにピストンの表面積が小さいほど爆発時の熱損失が少ないことが分かりました。高効率・省燃費につながります。 これにより、ますますロングストロークエンジンが増えてきました。 しかし、シリンダー径を小さくすることにも限界があります。 吸気弁や排気弁や点火プラグなどをシリンダ上部のヘッドに取り付けますが、これらの部品の面積が必要ですので、限界があるのです。 さらに、ピストンの上下往復運動を回転運動に変えるクランクシャフトがエンジン下部についていますが、クランクシャフトが回転する空間が必要になります。そういう制約をクリアしながら最適値を求める作業になります。 今のところ、ホンダのエンジンが一番、ロングストローク型になっているようです。 そういうエンジン技術や、制御技術や、CVTなどトルク変換装置の進化により、最近の『軽』は普通自動車に肉薄するところまで良くなってきました。 ターボ付『軽』なら、普通車とそん色なく加速や走りが得られるようです。 その他の安全支援装置も、軽自動車が最先端技術を搭載している例が多く見受けられます。 車体の塗装も普通車と同じで、品質や外観の見栄えも良くなっています。 ナンバープレートも『軽』は黄色とされてきましたが、白のプレートも許可されているそうです。 (もちろん、+何円か必要でしょうが) 小回りが利いて、ガソリンも食わず、走りはそん色なく、外観もきれいで、椅子や内装もよく、走行音も静かで、あらゆる面で快適に普通車並みになったと言えます。 良いことづくめの『軽』です。ただし、値段は普通車並みになりました。 しかし、維持費(税金、車検、保険など)は安いです。 というわけで、『軽』が売れる理由が分かりました! |
2020年4月26日(日)
FITのステアリングリモコンとナビがつながりました。
(その5)
| 2月23日に納車になった新型FIT4のその後の情報です。最近、車は自動運転や、安全支援システムや、ハイブリッドや、エンジンなど様々な制御をコンピュータ(CPU)で行いますので、各CPU間の信号のやり取り(通信)に『CANシステム』というバスラインが構築されています。CANについては以前に書きましたので、ここをクリックして下さい。 従来の接続方式では結線数が多くなり、配線だけで数十Kgになるほど重くなります。 これでは、配線材料コストや、作業や、重量など大きな問題になりますので、CANという通信方式によりたった2、3本の線で接続し、デジタル回線でCPU間の信号のやり取りを行います。 問題はナビや、ドライブレコーダや、ETCなどアクセサリーを取り付ける際、メーカ純正アクセサリーを選ぶか、自動車部品店(オートバックスなど)で買い取り付けていました。純正品は値段が高いので、安く上げるには、アフターマーケットと呼ばれる自動車部品を取り付ける人が沢山いました。今はアマゾンなどでも安く買え、自分で取り付けるか、ディーラに頼んで取り付けてもらうという方法があります。 前車のFIT3は純正ナビを着けましたが、このナビはM電機製で性能が悪く、とんでもない道案内をすることがしばしばありました。そこで、今回はPanasonicストラーダ CNーF1XVD(9インチナビ)と、フロント・リア2カメラ方式ドライブレコーダをアマゾンで買い、ディーラで取り付けてもらいました。 Panasonicストラーザ CNーF1XVDは? 大変すばらしい!。 何が素晴らしいのか? ①液晶画面が大きい(9インチ) ②液晶画面のドットが小さいので高解像度・高画質、大変明るい(4Kテレビ並み) ③画面角度が変えられる ④『みちびき』も受信するので、地図の表示精度が非常に高くなった。 GPSは最低4個のGPS衛星電波を受信し、現在地を計算して割り出している。 この場合、位置精度は約10mぐらいの誤差が生じる。 最近、位置精度を上げるため、天頂衛星とGPSを同時に受信し、位置を補正する方法がとられている。 『天頂』とは、真上(頭上)という意味で、完全に常に天頂にあれば理想的だが、地球の回転軸が23.5度傾いているので少しずつずれて、8の字を描いたような動きになる。 だから『準天頂衛星』と呼んでいる。 日本は『みちびき』と命名した準天頂衛星を現在4機体制で運用中で、これとGPSを組み合わせると、位置精度(誤差)は10cmぐらいに収まる。(精度が100倍以上良くなる。) 最近のナビや、ドラレコや、レーダー取締検知器には、この『みちびき』の電波も受信するようになっている。 さて、ステアリングリモコンで、ナビの音量UP/DOWN等の調整ができないことに気づいた。 納車されるまで問題なくできるものと思っていた。 今回のFITには、デジタル回線が張り巡らされていることを知った。これがCANシステムという新デジタル通信方式。 車は停車時や走行中にいろんなノイズや電波(電磁波)が飛び込んで来る。バスラインにいろんな信号が侵入する。この予期しないノイズでCPUが誤動作しかねないので、CANシステムは外来ノイズに強力に対応したシステムになっている。 さて、ステアリングリモコン(ステリモコン)ボタンの音量UP/DOWNや、チャンネル切替等が使えないので、嫌な感じがしていた。そこで、ネットで、FIT用CANシステムインターフェイス(変換器)を見つけ、注文し、今日、ホンダディーラで取り付けてもらった。  左の写真がインターフェイス 左の写真がインターフェイス GAP-HAVT366 ナビを一度取り外して、結線の束のステリモコンのバスラインとインターフェイスを接続し、インターフェイスとナビを接続する作業をしてもらった。 約1時間で終了。 無事に音量アップダウンと、チャンネル切替や選曲ができるようになった。 但し、モード切替(テレビ⇔SD⇔DVD⇔FM⇔AM切替)は不可。最低限の切り替えがステリモコンで行えるようになり、一件落着した。 今後、どのメーカもCAN方式(他の方式もある)が採用されるので、車を買う際は、少し高いですが、純正ナビを取付けることをお勧めします。 その理由は、純正ナビはすべての動作ができるからです。 アフターマーケットのナビは、純正品に比べると、 ①安いですが、取付費が別途発生する、 ②必ずインターフェイスが必要になる、(インターフェイスは1万円前後で高価) ③全ての動作ができるわけではない、 純正ナビは、バックカメラや、ドライブレコーダや、ETC等との連携もできる。 さらに、純正ナビはインタ-ネットやWiFiなどに接続したり、事故等の緊急時に、ボタン一つでセンターにつながるサービスも受けられます。但し、このサービスは別途、月額料金が必要です。 というわけで、今回の新型FITの納車時から今までの経緯をレポートしました。 参考まで、インターフェイスの販売先と、部品名をお知らせします。 販売先;(株)時風プレイス TEL072-466-3430 〒598-0034 大阪府泉佐野市長滝983-9 部品名 ホンダ車用ダイレクト接続プラグタイプB GAP-HAVT366 8,900円 ホンダ車用ステアリングリモコンCANカプラ GAQ-HAVC202 1,800円 今日、納車後、2か月が経ちましたので、初めて洗車した。 新型FITは、『気持ちいい!、心地よい』がコンセプトです。 洗車時に気づいたことは、車体表面がなめらかな曲線で構成されているので洗いやすい。デザインがシンプルで、ゴテゴテしていないので飾り部品が少なく、突合せ部なども引っかからずに洗える。これも洗車時の心地よさだと実感。 現状の印象は? 大満足です!。 乗り換えを検討されている方は新型FITをお勧めします。(ホンダ星田店に感謝!!) |
2020年4月12日(日)
成熟化した市場(ユーザ)が求めるものは何か?
(クラスレス市場が到来?)
| 世の中が豊かになり、いろんなモノが店頭に並び、欲しいモノは何でも手に入る時代になった。 日本は太平洋戦争で75年前に破れ、一時は焼け野原になり、日常の生活物資が不足し、大変貧しい生活を余儀なくされた。しかし、国民の頑張りにより、次第に立ち直った。特に朝鮮動乱の特需(米軍の物資を供給)を担い、急速に経済が立ち直ることができた。 子供の頃(昭和24~5年頃)はまだ貧しい時代だったので、小学校入学当時の写真を見ると、兄のお古の服を着て、脛に継布を縫ったズボンをはいている子もたくさん写っている。 中には下駄ばきの子供もいた。それが小学校卒業写真を見ると、全員が学生服を着ている。昭和30年頃には生活もよくなってきたのだろう。詳しくは覚えていないが、・・・。 そして、神武景気や、いざなぎ景気などの好況を迎え、テレビは白黒からカラーテレビに変わり、洗濯機、冷蔵庫、掃除機など次々と家電商品が出廻り、生活が豊かになった。 家事の内、食事を作ること、洗濯をすることが重労働だったが、冷蔵庫、洗濯機が果たした役割は大きかった。特に洗濯機は主婦の仕事を解放したと喜ばれた。 縁あって、昭和43年に松下電器に入社した。当時はテレビもステレオも真空管を使っていた。ラジオがトランジスタに変わりつつある時代だった。配属はステレオ事業部商品技術部。 そこで、セパレートステレオや、シスコン(システムコンポ)や、コンポや、CDプレーヤの開発などを技術、企画、管理業務を30年近く手掛けてきた。 この頃、日本の家電メーカはアメリカを抜いて、世界一の座につき、経済は素晴らしい勢いで成長を遂げた。 “Japan is NO.1”と言われた良き時代だ。 しかし、まだ人々が欲しい商品がたくさんあり、需要が供給より大きい時代であった。 良い商品を作れば売れる時代であった。 さて、現在、その状況が大きく変わってきた。 家電はどの商品も、世帯普及率が殆ど100%になり飽和状態だ。市場は成熟化した。 あとは、壊れたものを買い替える買替需要が残るだけとなった。 そう思い込んでいたが、少しこの考えは間違っていたようだ。 英国のダイソンの掃除機は、日本メーカの掃除機より高い値段でありながら良く売れている。家に掃除機があるのに、ダイソン掃除機を追加購入する人も多い。 それはなぜか? ダイソン掃除機はゴミをよく吸い込むことと、コードレスでは初めて家庭用掃除機としても使えるモノだったからだ。 他メーカと同じような範疇の商品を造っても、買替需要を満たすだけで終わる。新しい需要を喚起できない。ダイヘン掃除機は見事に新しい需要を掘り起こした。 もう一つの事例は、ユニクロ。成熟しきった衣類(アパレル)業界は値段競争が激しく、スーツ2着で5万円、さらにそれが3着で5万円となり、泥沼・底なし状態に陥っていた。 そういう厳しい業界に打って出たユニクロは、新しい生地(フリース)が当たり、縫製がしっかりしていることを売りに、店舗拡張し国内で765店舗、あっという間に業界NO.1に成長し、今や世界のブランドになった。中国では748店舗も展開し、パリのシャンデリア通りのオペラ座近くにユニクロパリ店がオープンしている。あっという間に全世界に急成長した企業となった。 さらに一つ、家電商品で伸びつつあるのが、アイリスオオヤマだ。このメーカは元は樹脂成型加工メーカで、プラスチック成形品の請負事業会社だったが、自社ブランドで製品を売りたいという社長の思いで、植木鉢を樹脂で造ってホームセンターなどに卸して販売した。その後、電球や蛍光灯がLEDに変わる際、LEDやLED電球を増産し、照明器具では業界TOPの座に着いた。いまや、炊飯器やテレビなど家電商品も手掛けて急拡大している。 既存のメーカが潰れたり、事業縮小したり苦戦する中で、新規参入の事業者が市場を奪い成長する変化が起きている。 これらの事例は、成熟した市場でも経営のやり方、商品開発の仕方、商品企画の狙いなどで、新参メーカが既存メーカに勝てるという事実を示している。 既存メーカは、従来から積み上げてきたノウハウを生かし、新しい取り組みをすれば勝てるはずだが、なかなかその強みが発揮できず、そういう姿は見えない。 さて、このページはタイトルが『カーライフ』となっているので、車についてはどうか? 今回、ホンダが売り出している新型FITは、今までの車造りのコンセプトから、大きく舵を切ったように見える。 今まで、自動車は、メーカが高級車、中級車、普及車という車格を設定し、いろんな車を商品化してきた。中級車は高級車の領分を超えない(侵さない)程度の出来栄え(商品力)に押さえて造りこんだ。逆な言い方をすれば、中級車はこの程度で良いという線引き(割り切り)をして商品を造ってきた。各種車両のランキング(車格)に応じた位置づけがされてきた。これはメーカが決めるメーカ主導の商品企画(コンセプト)の在り方である。 各メーカがそういう車づくりを繰り返す内は自動車業界の序列も大きく変わらない。 だから、トヨタ自動車を頂点とした日本の自動車メーカの序列はゆるぎないものだった。 さて、今回、ホンダが発売した新型FITは、サイズは小型車(コンパクトカー)に入る車両だが、従来コンパクトカーは、『これぐらいでいい』という割り切りで各スペック(仕様)が決められていたが、今回の新型FITは、その概念を破り、小型車だけれども、乗り心地は中・高級車に匹敵するような上級(上質)感を醸し出すことに狙いを置いて開発されたようだ。 成熟化した市場では、『クラスレス』が目を引く。 『クラスレス』とは、従来の階級・階層に属さないという意味。 同じようなモノがあふれる社会では、他人と違ったモノが欲しくなる。 随分、以前にトヨタ自動車が『小さなクラウン』という、『ブレビア』や『プログレ』という5ナンバーサイズで、造りが良くて価格は高級車なみという車を発売したが売れなかった。当時はまだ車はステイタスで、「大きいことはいいことだ」という時代であった。 さて、新発売のトヨタヤリスは、コンパクトカーとしてきびきびと走り、燃費はブチ切りに他を上回り、世界最高を狙うというコンセプト。それ以外の用件、例えば騒音はコンパクトカーとして我慢できるレベルであればいい。車内の狭さ、窮屈さは少々割り切ってもいいというもの。ヤリスは従来の延長線に新製品を開発することが狙いだと思う。 これは今回の新型FITとは大きくコンセプトが違う。 車を造る場合に、つぎ込むことができるコスト(原価)は各社凡そ同じような金額になる。その限られた金(コスト)を何に、どのようにかけるか! これが販売の成否を分ける。 販売部門やマーケティング部門は、『何もかも他社に負けないものにしてほしい』という要望が強く出るが、そうすればコストが上がり、売値が狙った値段からズレてしまう。もしくは利益が出ない。 総花的に何でも良くすることはできないので、コストの絞り込みや割り切りが必要になる。 新型フィットは、『乗り心地、使い心地の良さ』を主テーマに成熟化したユーザが求める今までになかったコンパクトカーを提供しようとしたもの。 それは、燃費競争において、燃費数値を割り切っていることでも分かる。割り切ったと言っても、旧型車両より改善している。スペックの業界NO.1を狙う競争には組しない。これは勇気のいる決断だ! ユーザはこの程度まで燃費が良くなれば、多少、燃費が負けていようが、大きな購買のマイナス要因にならないはずだ! という割り切りの元に今までにない上質の乗り心地を優先させた。 この決断は、強い思い、強いコンセンサス(同意)がなければできることではない。 何故なら、今までやらなかったモノづくりをして、成功するかどうかは、売ってみなければ分からないからだ。今のところ、その割り切りと、上級車に求められているような乗り心地の改善にかけたことがユーザには受け入れられ好評のようだ。事実、自分が載ってみてもそう感じる。 唯一、顔つきは気にかかるところがあるが、・・・。 ホンダのデザインは、下手だなぁ! 成熟化した市場が求めるものは何か? これは製造業(事業)の永遠のテーマだと思う。 |
2020年4月10日(金)
新型FIT4ハイブリッドの印象
(その4)
| 2月23日(日)に納車された新型FITハイブリッドは2ヶ月になろうとしている。今までの走行距離は約800km。今まで乗った感想を一口で言えば、従来のコンパクトカーを超える1ランク上の出来栄えになっている。まず、静かなこと。買い物などの街中のチョイノリ、自動車専用道の高速運転時など、どの場面においても大変静かで、余計な音が入ってこない。これは素晴らしい。 ハイブリッドシステムが、2モータ式のeHEV(i-MMDから呼称を変更)に変わり、走行はモータが担うことになる。バッテリーで走行用モータを駆動して走る。EVと同じ。バッテリーの電気がなくなってくればエンジンがかかり、発電モータを回して発電し、バッテリーに充電する仕組みになっている。高速道路で約80km以上の速度では、エンジンがタイヤを駆動する。これは一定の高速運転ではエンジンが直接タイヤを駆動した方が効率(燃費)が良いからである。利に叶った方式だ。(日産ノートe-Powerはこのメカが搭載されていないので、高速走行時もエンジン→発電モータ→バッテリ→走行モータ→タイヤという駆動になる。) 今まで約800km走ったところでは燃費は25km/リッター。以前にFIT3ハイブリッドが21km/リッターだったから随分燃費はよくなった。しかも、走りが非常にスムーズになった。 運転のしやすさも、前方、後方の見晴らしがよく(視野が広く)、とても運転しやすい。前方の視野はフロントガラスを支える柱(桟・これをAピラーと呼んでいる)が非常に細いので、視界を遮らないことによる。ワイパーも見えないのですっきりとしている。さらに、後方の視野に大変良い。 プリウスやヴィッツ、今回のヤリスにしても後方視界が悪い。以前、ヴィッツに乗っていたが、非常に後方視界が悪く、後部座席の枕を外していた。車庫入れの時も大変だった。今回のヤリスも後方視界は良くないので、車庫入れは自動化されている。余計な話になったが。 新型FITは座席の出来栄えも素晴らしいことが話題になっている。前席しか乗らないが、座って大変気持ちが良くて、不思議と疲れない。これはいろいろと工夫してイスを造ったと聞いている。まさにその苦労の成果が感じられる。 前車のFIT3ハイブリッドは、道路の凸凹の個所を通過する際に、コツコツした突き上げを感じたが、新型FIT4では、凸凹の上下の揺れをいなしてくれるので、ふんわりと通過できる。 ハンドルは今時、珍しい2スポークスで、輪っかの下のスポークがないので邪魔にならない。しかも握りの部分を太く膨らませているので、握りやすい。 良いこと尽くめなのだが、気になる点が二つある。 一つは、乗り込んでスタートボタンを押すと、液晶モニターがセットアップ表示するが、これが数分間表示し続け、長すぎると感じる。たくさんのCPUを搭載しているので、CPUが同期するまで間が要るのかもしれないが、せいぜい10秒から20秒程度で表示が走行表示モードに切り替わってほしい。これはすぐにソフト変更して改善してほしい点だ! 二つ目は技術的な話になる。 HONDA純正インターナビ(今回はPanasonic製を採用している)を装着すれば何の問題もないのだが、今回は、オートバックスやアマゾンなどで市販されているPanasonic CN-F1XVDという9インチ大画面ナビを取り付けた。ナビの機能や動作は全く問題はなく、大変きれいな画面で、ナビ動作も地図上の狂いもなく正確に案内する。問題は、ハンドル(ステアリング)についているリモコンボタンで、音量UP/DOWNや、地図、テレビ、ラジオ、CD、SDなどのモード切り替えボタンが動作しないこと。もちろん、ナビのボタンでは問題なく動作する。 この原因は、新しく導入されたCANシステムにある。従来の車のアクセサリー、その他を接続する仕様とは全く違うCAN-BUSシステムというデジタルシステムを採用しているから、一般市販のどのメーカのナビともつながらない。 言い換えると、HONDA純正インターナビを装着しないと、ステアリングリモコンは動作しないということ。 単純にコネクターを結線するだけでは動作しない。デジタル回路になった時の融通の利かなさだ。この問題の解決法は市販ナビ用接続コードなどを販売している業者がCANシステムとつながるインターフェイス(変換器)を市販してくれることを待つしかなく、それがないとステアリングリモコン(ステリモ)は使えない。ステリモを使えなくても特に不便ではないが、せっかく、ついているUP/DOWNボタンを押しても動作しないのは、何かいやな感じがする。 そこで、CAN-BUSはどういうものか? *************************************************************************** 最近の車には様々なサブシステム用に約70個もの電子制御ユニット(ECU)が搭載されている。最も重要なプロセッサはエンジンコントロールユニットである。 その他に、トランスミッション、エアバッグ、アンチロック・ブレーキ・システム(ABS)、クルーズコントロール、パワーステアリング、オーディオシステム、パワーウィンドウ、ドアーミラー調整、ハイブリッドカー・電気自動車用バッテリー充電システム制御などを行っている。 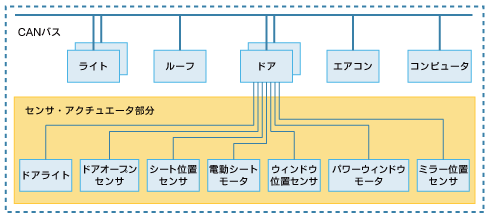 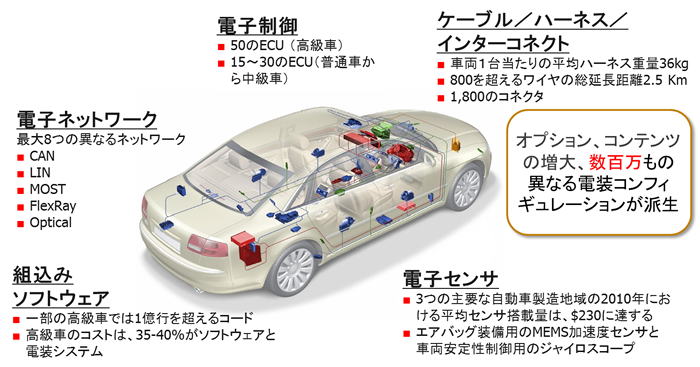 いくつかは独立したサブシステムとして動作するが、他のサブシステムとの通信は不可欠である。サブシステムはアクチュエータを制御したり、センサからフィードバックを受け取ったりする。この要求を満たすためにCAN(Controller Area Network)が考案された。 CANの重要な利点の1つは、異なるシステム間の相互接続(通信)により、ソフトウェアだけで幅広い安全性・経済性・利便性を実現できることである。このような機能を従来の自動車電装の配線により実現しようとすると、膨大な結線が必要になり、コストと複雑さが増大する。 そのいくつかの事例を挙げると、 ・自動始動/停止 : CANバスを介して、車両周辺からの様々なセンサ入力(速度センサ、ステアリング角度、空調オン/オフ、エンジン温度)を照合し、エンジンを停止することで燃費と排気を改善できるかどうかを判断する。 ・電動パーキングブレーキ : ヒルホールド機能は、車の傾斜センサと道路速度センサ(ABS、エンジン制御、トラクション制御)をCANバス経由で入力し、車が坂道で停止しているかを判断する。同様に、CANバスから供給されるシートベルトセンサからの入力(エアバッグ制御の一部)により、シートベルトが締められているかどうかを判断し、車が動き出すと、パーキングブレーキが自動的に解除される。 ・アダプティブオートクルーズ:最高速度を設定すると、前車の走行に応じて一定の車間を確保して追随走行する。停止から設定速度まで。高速道路はもちろん、一般道路でも対応する。 ・駐車支援システム : 運転者がギアを後退に入れると、トランスミッションコントロールユニットはCANバスを介して信号を送信し、駐車センサシステムとドア制御モジュールを作動させる。ドア制御モジュールは助手席ドアミラーを傾けて、縁石の位置が見えるようにする。また、CANバスは降雨センサからの入力を受けて、後退時にリアガラスのワイパーを動かす。 ・車線逸脱防止支援/衝突回避システム : 駐車センサからの入力はCANバスを通して車線逸脱警報などの運転支援システムに外部近接データを送る。最近では、これらの信号がCANバスを通して能動的衝突回避システムにおけるブレーキ・バイ・ワイヤを作動させる。 ・ヘッドライト自動切替:対向車に応じてハイ・ロービームの自動切換え、ライトの自動ON/OFF など、など ************************************************************************** 新型FITにはハイブリッドシステムe-HEVや、ホンダセンシング等をコンパクトカーに導入するために新しいデジタルネットワークであるCANシステムを採用した。これは、性能向上や、安全支援や、いろんな便利機能などを搭載するためだ。インターネットやWiFiやブルーツースなどで外部とつながる事も可能になる。車は単なる移動手段だけでなくなってきた。 アクセサリーメーカは、カーメーカと開発中に情報を共有し、CAN-BUSを組み込むことが必須になる。それが純正ナビとして採用される。 単体の(従来型)ナビは、中国製なら1万円少々で買える時代になった。国内でこういうモノを造ってもコストが合わない。大きく時代が動いてきた。 今回のFITには、前方・後方にドライブレコーダ(ドラレコ)を取り付けた。さらにレーダー取締受信機も着けた。これらには、GPS受信機が内蔵されているので、ナビと同様に位置測位をする。「前車発進お知らせ機能」、「後車衝突危険表示」、「速度表示」、「車線逸脱表示」など、ドラレコにも、ナビにも、車本体(ホンダセンシング)についているような安全表示機能が搭載されているので、いろんなモノから、同時に注意喚起の女性の声が聞こえる。そのままではやかましいので、出来るだけ案内音声は省く設定にしている。 これが、システムとしてBUSにつながっていれば、バラバラに単独に動作することがない。 今後、車を買う際は、それらを丸ごとシステムとして装着して買う方がベターだ。 しかし、便利や安全など付加価値はたくさん得られるが、高価な買い物になる。 だから、車の買い方として、選択の余地が多くなったいうことかも知れない。 |
2020年3月25日(水)
燃費改善の余地は残されているか?
| 技術はドンドン進化する。燃費の改善、燃費競争もその一つである。しかし、『一体どこまで進化するのか?』『際限なく進化し続けるのか?』と言えば、答えは限界はあると言える。それは『エネルギー保存の法則』に則ったもの。 車が走るためには、車に運動エネルギーを加えることが必要だ。その運動エネルギーは、従来はガソリンや軽油の熱エネルギーをエンジンで回転エネルギーに変換し、タイヤを駆動し車は走った。その際、ガソリンが持つエネルギーの何%が回転エネルギーに変換できるかどうかで燃費が変わる。エネルギーの変換効率(熱効率)が問題になる。 エンジンの熱効率は近年、コンピュータシュミレーション(CAD,CAE,CAT,CAMなど)技術の進化で大きく改善した。従来はガソリンエンジンが25%、ジーゼルエンジンが30%程度と言われた時代があった。それが最新のガソリンエンジンは40%を超え50%を目指して開発が進められている。 熱効率は一昔前のガソリンエンジンの2倍になった。同じ距離を走るのに要するガソリンが半分になったことを意味する。そういえば、昔のアメ車(アメリカの大型車)は、1リッターで4kmほどしか走らなかった。 ガソリンやジーゼルエンジンは大きな馬力を生み出すことができる。車のフロントの狭いエンジンルームの中に納まって、100馬力や200馬力の出力を生み出すことができる。これは電柱の上に取り付けられた柱上トランス(普通は円筒状のもの)で20とか30と数字が表示されているが、単位はKW(キロワット)で、これを馬力に変換すると、1馬力(hp)=0.76KWだから、20KWの柱上トランスは、26馬力しか出せない。軽自動車のエンジンでも50馬力程度が出せる。如何にガソリンエンジンが小さな体で大きな力(エネルギー)を発生できるかを示している。 ガソリンエンジンは長所と短所がある。長所は形が小さくても大馬力が出せること。短所は回転数が低い時はトルク(回転力)が弱いこと。馬力=トルク(回転力)×回転数だから、回転数が低い時は馬力も小さいと言える。だからそのままでは1トン前後の重い車を動かすことができないので、歯車を組み合わせて回転数を減速してタイヤに伝える。これがトランスミッションと呼ぶ変速機だ。最近はギアー方式からCVTと呼ぶベルト方式が多くなっている。 そういう工夫をすることで車は走ることができるが、このエンジンの短所を補うために開発が進んできるのがハイブリッド車だ。ハイブリッド(hybrid)とは、異種のものの混成物、雑種という意味で、ハイブリッド車はエンジンとモータを組み合わせた車ということだ。 なぜ、ハイブリッドなのかと言えば、エンジンとモータのトルク特性が大まかに言えば、逆特性を持っているから、二つを組み合わせると、相互に補完し合って車として要求される理想の特性が得られるからだ。エンジンは回転数の上昇に伴ってトルクが増大する。モータは回転数がゼロの時にトルクが最大で、回転数の増大とともにトルクは下がる特性を有する。この二つのトルク特性に着目して生まれたのがハイブリッド車だ。 ところが、車を走らせるためには、100馬力というような大きな力が必要であり、モータを回すために大量の電気が食う。この電力を賄うための電池が今まで手に入らなかった。従来の鉛蓄電池は電極に使用する鉛が非常に重い金属のため、大容量のバッテリーを積むと、それだけで車重が重くなり実用に耐えなかった。最近、リチュウムイオン電池が開発され、1/10以下の重さで大容量の電池が造れるようになった。このことがハイブリッド車が生まれてきた大きな背景にある。リチュウムイオン電池の前に、プリウスに搭載されたのは、Panasonicや三洋電機が商品化していたニッケル水素電池がある。これはリチュウム電池に比べて、電池の電圧が半分以下しかなく、大きな容量を得るには重くなった。 現在はリチュウムイオン電池のさらなる進化を目指し各社がしのぎを削っている。この市場はこれからますます活性化して大きな産業が生まれる可能性を秘めている。 今回は、新型FIT4が本格的な2モータハイブリッド方式のe-HEVを搭載し、従来のi-DCDハイブリッドに比べて格段に良くなったことは既に書いたとおり。ハイブリッド車の理想形に近い構成が完成したと言える。トヨタTHSⅡも一つの完成形とも言える。両社はシリーズ方式か、パラレル方式かの違いがあるが、両者とも2モータ方式で、巧妙に運動エネルギーを電気エネルギーに回収し、消費するガソリンの量を最小化している。 FIT4をさらに省燃費にするには、何が残されているかを考えてみた。 一つは、車重を軽くする。 これは、モノを動かす時に、軽いものは少ない力で動くという運動エネルギーの法則による。車重を軽くすると、衝突時の安全性や、振動・騒音が大きく伝わってくるなどのトレードオフの課題が生じ、どうバランスさせるかだ。 二つ目は、エンジンやモータのエネルギー変換効率(熱効率)をさらに改善する。 これは基本中の基本課題だが、現状の効率を大きく改善する余地はあまり残されていない。改善余地はゼロではないが、次第に究極の姿に近づいていると言えそう。特性改善曲線は成熟化・飽和しつつある。 三つ目は、あらゆる損失(ロス)を最小化する。 いろんな損失が随所に存在する。これをひとつずつ潰してゆく地味な作業が要る。なぜなら、あることを改善すれば、逆の面で性能が劣化したり使い勝手が悪くなったり、いろんなマイナス面が生じる。あることを改善すれば、改悪の課題が生じるというトレードオフとの戦いになる。 例えば、FIT4では、リチュウムイオン電池、1セル(1個当たり)の電圧は約3.6ボルト、それを直列に接続して172.8Vを得ている。この電圧をPCU(パワーコントロールユニット)の回路で、三相交流最大570Vまで昇圧する。この電圧を駆動モータに加えることで、最大80KW、253Nmという出力とトルクを発生させている。この570Vを発生させる電子回路に使用する電子素子は、RC-IGBTと呼ばれる最新のパワー半導体素子を使っている。 インバータ回路は回路電流をON-OFFさせることで、自由に電圧と周波数を発生させコントロールできる回路を構成している。電流をON-OFFする際に、回路が完全に接続され、OFFすれば完全に切り離されれば問題は生じないが、実際はON状態でわずかな電気抵抗分があり、OFF状態でもわずかな漏れ電流が生じている。特にON状態で大電流(100A以上)が流れた場合、わずかな電気抵抗(r)があれば、そこで発熱する。 発熱量は、 P=I2×r になり、電流が大きいので、発熱量は無視できない大きさになる。 FIT4のエンジンルーム内を見ると、PCUのアルミ製の箱から2本のパイプが出ている。これはIGBTなどの半導体素子を冷却するための冷却水パイプが専用ラジエータに接続されている。 エンジン用ラジエータの右側に、PCU冷却用の小型のラジエータが設置されている。見た目では、家庭用エアコンの室外機の1/3ぐらいの放熱板が付けられている。多分、200W~300Wぐらいの放熱をさせているのではないかと思う。 この放熱は燃費を悪くする。もしこれがゼロなら、200~300W分が車の燃費に寄与することになる。半導体で消費する電力は馬鹿にならない。パソコンでも小さな放熱器と、それを冷やすため小さなファンが回っている。ファンの近くに手を近づけると熱く感じる。 これが、一桁違いの大きな放熱が必要なPCUの発熱ならなおさらのことだ。しかし現状ではこの放熱をしっかりしないと、半導体素子の温度が150℃を超え、破壊に至る。現状では素子の特性上、この発熱を小さくすることができない。 半導体素子は主にSi(シリコン)を使うが、最近はSiC(炭化シリコン)やGaPなどを使い、回路がON時の抵抗分を極力小さくできる新しい素子の開発が進んでいる。現状ではまだ高価で使えない。いずれ近い内に、発熱の小さな素子が安価になれば、PCUボックスから出入りする2本の水冷用パイプがなくなり、小さなファンがエンジンルーム内で回ることで冷却ができるようになるはずだ。そうなれば、燃費はさらに良くなる。 商品や製品は、無駄な部分(ロス)を取り除く取り組みを着実に進めるしか手がない。 FIT4 e-HEVは、街乗りで30km/L近い燃費をたたき出す優れた車になった。これは素晴らしいことだ。しかし、まだまだ今後、省エネの開発が続くだろう! |
2020年3月24日(火)
FIT4 e-HEV 使って気づいたこと、満足度は?
(その3)
| 新型コロナウィールスが世界的に大流行し、日本もクルーズ船の感染者が出てから急に騒がしくなり、大相撲春場所も無観客で行われ、何とか無事に終了しました。一方で、K1試合がこの状況下で観客を動員して開催されましたが、感染者が出ないことを祈るばかりです。 東京オリンピックもこの分では100%予定どおり開催できないでしょう。延期になることは間違いないでしょうが、いつまで延期するのか、半年か、1年か、2年か。それにより選手の体調や、年齢的な体力のピークを維持できるかどうか、いろんな条件が変わりますので大変なことです。 経済活動も、第一次、第二次世界大戦後、最大の不況が来ることは明らかです。世界の正常な経済循環が完全に停滞していますので、今後どうなるか? 全く見当がつきません。 このコロナウィールスの蔓延は、ワクチンが開発され、接種することができるようになるまで収まらないような気がします。それまでは注意深く自分が罹らないように各自が注意するしかありません。出来るだけ人込みは避けることが一番ですね。 このページは車情報についてですので、本論に戻します。 新型FIT4ハイブリッドe-HEVが納車され、1か月過ぎました。昨年12月に事前予約していたので、何とか早く手に入ったのですが、コロナの影響で、部品が滞ったり、完成ラインがストップするなど納車が乱れてきているようです。トヨタ自動車ですら、国内5工場の生産を停止すると発表しています。 さて、走行距離は1か月で766kmになり、次第にこの車の特徴がつかめるようになりました。  燃費は、家の周辺のチョイノリや、買い物に行く程度なら29km~30km/L走るようです。この燃費はすごい良い値です。 昨日、和歌山の実家まで往復で267km走りました。その内、250kmほどが近畿自動車道(高速道路)で、80km~100km/hで渋滞なく走れました。その平均燃費は27km/L~28km/Lでした。 今までのFIT3ハイブリッドは、高速道が27km/Lぐらいで、近くのチョイノリでは20km/L程度でした。手放すまで約4万km走行しましたが、平均燃費は21km/Lでした。(満タン法) 新型FIT4は、高速道路より近場のチョイノリの方が燃費が良くなります。これは2モーター・シリーズハイブリッドシステムの特徴で、発進・停止を頻繁に繰り返すような街乗りの場合は、モータ駆動トルクが大きく寄与し、燃費が向上します。 高速道路では、従来のi-DCDハイブリッド方式でも、今回のe-HEV方式でも基本的には同じで、動力はエンジンが回りっぱなし状態に近いですから、エンジンの特性に起因します。どちらも同じ型式のエンジンを搭載していますので、高速燃費はほとんど変わりません。 日頃は近場でチョロチョロ走る程度ですから、街乗りの燃費が良ければ有難いことです。 しかも、モーター駆動ですから、加速は大変スムーズで、変速のショックは全くありません。今回の新型FITは実によくできた車だと太鼓判を押します。 外観も落ち着いた上品さを醸しています。これ見よがしの顔つきではなく、自分には好みでぴったりです。室内のデザインもしっとりしていて、上の写真;メータ部は、7インチカラー液晶モニターで大変見やすく、文字のフォントもしなやかで、視認性が大変良いです。表示項目は必要にして十分な事柄を表示するので、不要な項目が目に入らず煩わしさもありません。更にポイントはカラー表示しますので一層見やすくて、眼が疲れません。 表示の切り替えも、ステアリング(ハンドル)のホームボタン 騒音は前車のFIT3に比べると、1ランクか2ランク静かになりました。高速走行中も、ラジオの声がはっきり聴きとれます。会話も楽にできます。ロードノイズと言われるタイヤと地面の接地ノイズ(ザーという音)が抑えられているのだろうと思います。凸凹のつなぎ目を通過する際の突き上げられる感じも、しなやかになりました。 便利だと思った点は? ①ヘッドライト 自動で点灯・消灯、AUTOがデフォルト(通常設定)すので、ライトのON/OFF は車任せです。トンネルの出入りの際も何もせずともOKです。ヘッドランプの周囲のLEDランプは、動作状態では昼夜を問わず点灯しっぱなしです。最近のレクサスや、BMWやベンツやミニ等が一種の流行です。 ②アダプティブクルーズコントロール 停止状態から設定速度まで自動で追随しますので、高速道路で90km/hに設定すれば、前の走行車が90Km/hならそのまま車間距離を一定の車間距離を保ち追随します。前走行車が減速すれば、前車の速度に追随します。これは停止するまで追随します。前車が動き出せば、アクセルを少し踏むか、クルーズSWをプッシュ(ON)すれば、前車と車間距離を保って設定速度まで加速します。以前のFIT3は普通のクルーズコントロールしか装備していなかったので、一定の速度で走りますが、前走行車が減速すると車間距離がなくなり、ブレーキを踏まなければ追突するという危険がありました。FIT4は自動的にブレーキがかかりますので、その追突の心配は無用です。 ③オートブレーキと、オートパーキングブレーキ オートブレーキボタン; ボタンを押すと、オートブレーキ機能がセットアップされ、信号待ちで停車した際にブレーキペダルを踏みっぱなす必要がありません。ペダルから足を離しても、ブレーキが保持されます。発進時はアクセルペダルを軽く踏めば、ブレーキは解除されます。 オートパーキングブレーキ; 停車して降車時にこのボタンを引くと、ハンドブレーキのように自動的にブレーキがかかる仕組みです。この解除はスタートボタンを押して、アクセルペダルを軽く踏めば自動的に解除します。この二つも大変便利な機能です。 ④エアコン操作ボタン FIT3のエアコン操作はタッチパネル方式で、ボタンの位置とタッチ感覚が今一良くなかったのですが、今回はツマミを回してスイッチを切り替える方式に戻りました。人間工学的には、タッチスイッチは必ずしも操作性が良くないことはよく言われています。ヨーロップ車も最近は全て機械式ダイヤルスイッチに変わってきたようです。ツマミの操作のフィーリング、スイッチの切れ味まで配慮され、節度ある切替感触が得られます。これで操作性が大変良くなりました。 ⑤大画面カーナビ 今回はPanasonicストラーダ CN-X1VDという9インチ高精細度IPS液晶搭載のナビを取り付けました。これは自分で価格.comで、ドライブレコーダと共に調達しました。取り付けは工賃を払ってディーラに頼みました。このナビは本体は2DINサイズですが、モニターが本体から外れるタイプで400種の車に取付可能だということです。モニターは角度や上下に調節できるようになっています。大迫力と綺麗なフルセグ地デジテレビ放送も楽しめます。ナビの表示も、以前のホンダ純正ナビに比べて、地図やその他の表示の仕方、使い勝手、ナビの精度、動作の速さなど隔世の感があります。デジタル電子機器の5年間の技術進歩は驚嘆に値します。 ⑥ETC2 今回はETC2という進化型にしました。ETCの基本動作は同じですので、従来のETCカードを使います。いくつかのサービスが追加になりました。サービスエリアから外に出て、再度高速道に戻った際にルートを途切れることなく清算できることや、途中の交通状況の音声案内が入ってきます。今後、さらに新サービスが追加されるそうですが、あまり期待はしていません。通行料金の精算ができればそれで十分だと思います。 ⑦2本スポークのハンドル(ステアリング) 最近の車は、3本スポークが当たり前になっています。今回のFIT4は2本スポークです。ちょっと目は何か物足りない、安っぽいと思いましたが、これが実際載って運転してみると大変しっくり来て使い勝手が良いのです。3本スポークの中心のスポークは実は邪魔だったことが分かりました。さらに、ハンドルの輪っかが一様な太さではなく、手で握る部分を太く肉を盛っています。このため、握りやすくなっています。この辺の配慮も大変心地よいところです。 ⑧最後に、視界の広さは秀逸 FITの良さは、初代のFITから前方、後方の視界が広く保たれているので、運転しやすく安心でした。今回は前方がさらに広がり、視野が広くて楽ちんです。これはユーザ目線で車を造った証拠ですね。 ということで、FIT4は良いこと尽くめで、気にかかる点が見当たりません。間違いなく、このクラスのベストチョイスカーです。 一つだけ、納車時に完了していない点が、今もまだ残っています。それは、ステアリングリモコン(ボタン)で、ナビのファンクションや音量を調節するツマミが動作ししないことです。理由は車のステアリングリモコンスイッチと、Panasonicストラーダの結線ができていないためです。新車が出ると、自動車メーカとナビメーカが接続のための仕様を検討する必要がありますが、これがまだできていません。結線、端子、端子形状などこの点は、どちらのメーカがどうこう言う問題ではないのですが、ユーザに不便をかけるという点では、早く解決してほしいと思います。 ホンダとPanasonicの両社に要望済みですが、なかなか動いてくれません。早く完璧に、リモコン動作ができるように頼みますよ! せっかく、素晴らしい車と、素晴らしいナビですからね! |
2020年3月13日(金)
燃費の報告
(その2)
| 新型コロナウィールスの蔓延で大変な状況になってきました。繁華街は人が居なくなり、観光地もひっそりしていて、お店は経営がたいへんだろうなと思います。非常事態です。 そういう中で、3/9に続いて、今日は京都に行きました。 第二京阪高速道の脇道(下の一般道)を京都まで走り、東山通りを北上し、八瀬大原の里に行き、三千院、その後、鞍馬寺、貴船神社に回り、帰路も一般道を走って帰りました。 今回は、車から降りることなく、門前まで行きしばらく停車して、一休みして移動しました。できるだけ、観光客と遭わないように注意しました。 道中はいつもより車が極端に少なく、京都市内もガラっとしていて観光客も少なかったです。三千院はちらほら人がいる程度でひっそり。むしろ鞍馬寺門前周辺の方が多く感じました。それも混雑というわけではなく、寂しいなという感じでした。シーズンオフの性もあるのでしょう。 往復で100kmほど走りましたが、燃費は30.2km/Lを示しています。 今回、気づいたことは、エアコンをOFFにして、ファンだけ回してもエンジンがかかることです。ファンをOFFにすれば、エンジンがかかる頻度が極端に少なくなりました。 エアコンOFF→ONでエンジンがかかるのは理解できますが、単にファンを回すだけで、エンジンがかかるのか分かりません。温度設定は25℃にしていましたので、エンジンをかけないと暖気が出来ないからかもしれません。 もし、そうだとしたらそれぐらい通常の走行でエンジンがかからずに走っていることになります。 いずれにしても、この燃費はすごい! 前のFIT3ハイブリッドなら、多分22km/Lあたりがせいぜいだろうと思います。 |
2020年3月9日(月)
FIT4の使用レポート
| 2月23日に入庫した新型FIT4について、前回(2/25)は納車直後の感想を書いたので、今回はその後、乗って使っての感想です。 前のFIT3ハイブリッドは、薄いグレーのメタリックでしたが、今回は白にパールが入ったメタリック調で、日光にキラキラ輝いてとてもきれいです。パールホワイトにして良かったと思います。 塗料が水性塗料になり、色合いに深みが出てきました。特にマツダの赤色は出色です。特別色の塗装は普通の色に比べて、3万円、5万円、6万円高など値段も相応に高くなります。パールホワイトは3万円高でした。この程度ならOKかと思います。 納車後、300km近く走りました。先般は奈良の生駒を抜けて三郷町の道の駅を往復、今日は天理市の天理教会本部に参拝し、その後、飛鳥の里を見学しました。この記事はここをクリックしてください。 さて、FIT4ハイブリッドの感想は、一言でいえば、大変良くできた車に仕上がっています。 前の車のFIT3ハイブリッドは発売直後に購入しましたが、トラブル続きで裏切られました。5回もリコールを受けて、やっと品質が安定し、その後は特にトラブルもなく5年間乗りました。 しかし、i-DCDハイブリッドシステムの『特有の癖』は最後まで残りました。 その後、FIT3が後期型にマイナーチェンジされ、大変スムーズな車に生まれ変わり、前期型とは見違えるような車になりました。これはフルモデルチェンジ並みに大きく改善し、走りのスムーズさと、室内騒音の低減、走行時の静かさ、ハンドルのしなやかさが特に良くなりました。 燃費も良くなり、安全装置も装備されましたので、この出来栄えの車がFIT3のフルモデルチェンジとして販売されていれば、アクアやノートe-Powerと三つ巴の勝負ができたはずです。 一度、評判を落としたFIT3は残念ながら平凡な車として終わりました。 今回のFIT4ハイブリッドは、そのFIT3後期型の良さに、さらに大きく磨きをかけて改善したフルモデルチェンジ車で、新しく2モータ方式ハイブリッドシステムをコンパクトカー用に小型化したもので、愛唱も代えて、e-HEVとなりました。従来は、i-MMDと呼んでいたシリーズハイブリッド方式です。アコードに搭載後、主にホンダの高級車向けのハイブリッドシステムです。 e-HEVハイブリッドシステムは、エンジンで発電機(発電用モータと読んでいる)を回し、起こした電気をリチュウムイオンバッテリーに充電しつつ、走行用モータでタイヤを駆動するという方式です。通常走行ではエンジンが直接、タイヤにつながっていません。 走行用モータは109馬力の大容量(馬力)を持っていますので、特にスタート時の強力な加速や、ブレーキング時は(走行用モータで行います)、大きな電力を回生発電できます。この大電力をリチュウムイオンバッテリーに充電します。スタート時に消費したエネルギーを、ブレーキング時に効率よく回生(回収)できるのです。ですからエンジンが発電用モータを回す時間が少なくなり、その結果、ガソリン消費が少なくなり、燃費が良くなります。 今日は、往復109km走って、燃費は29km/リッターという表示が出ていました。日中の気温が19℃まで上がり、車内は暑かったので、帰路はエアコンを入れました。往路はエアコンOFFで走ったので、30km/リッターとなりました。往復とも一般道を走り、奈良市内は特別な渋滞もなく普段どおりでした。 新型FIT4 e-HEVシステムは期待どおりすばらしい燃費を出すことが分かりました。 カタログ燃費を見れば、トヨタ YARISはWLTCモードで36km/リッターとなっています。これに対して新型FIT4はカタログ値で29km/リッターですから、カタログ値ではYARISに負けていますが、この分では実燃費ではほとんど変わらないかもしれません。 新型FIT4は、満タン(40リッター)で1000km走れることにこだわったということですから、その程度は走るはずです。今まで、300kmほど走りましたが、燃料表示の目盛りは満タン時から2メモリ程度下がった状態です。今後、燃費実績が出ましたら、都度報告します。 今回、カーナビはPanasonic ストラーダ CN-F1XVDにしました。これは9インチIPS高精細度・高画素液晶を搭載し、フルセグメント地デジテレビが受信でき、大画面できれいな画像です。しかも画面が上下に移動、左右に角度を変えることができ、人気商品になっています。今年度モデルは10インチ大画面になっていますが、今回、取り付けたのは昨年モデルの9インチです。値段が10万円程度で買得でした。従来の8インチ画面に比べて圧倒して大きいです。 ナビ性能は日進月歩で、前車に取り付けていたHONDA純正ナビに比べて隔世の感があります。画面のクッキリ感・鮮明さ、明るさなど画質の向上が大きく改善し素晴らしいです。さらに、タッチパネルの反応の良さや、地図の正確さ、使い勝手など実に良くなっています。 最近販売されているトヨタ車には従来のナビからスマホと連携したモニターを搭載しています。スマホを使いこなせる人にはいいかもしれませんが、そうでない人は使い辛いと思います。  9インチナビと、上部にレーダ探知機が見える 今回は、『あおり運転』などに対処するため、前後2カメラドライブレコーダも取り付けました。前後の景色を運転中、常時録画します。カメラの性能が良くなり、200万画素で走行中の車のナンバープレートがはっきり読み取れます。スマホのカメラも非常に小さなレンズを使いバカチョンカメラ並みの画像が撮影できる時代ですから、ドラレコの画質も良くなって当然です。 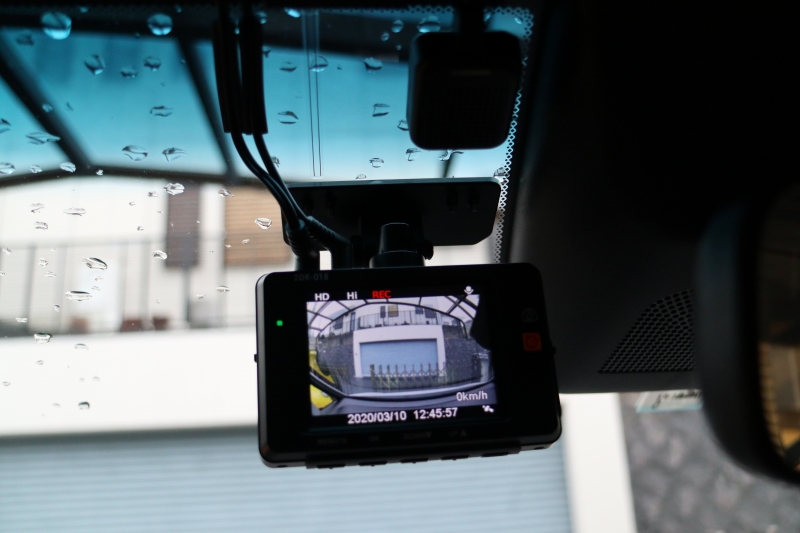 ドライブレコーダー(フロント側) さらに、レーダ探知機(取締機探知)も取り付けましたので、車内の至る所から、警報音や女性のアナウンスが聞こえてきます。出来るだけ、やかましくない程度で、必要な情報が得られる設定にしています。  ナビは2DINの本体部と9インチモニター部が分離している 運転した感じは、室内の広々感、前方の視界の広さ、後方の視界の広さ、室内の静かさ、ハンドルのしなやかな操作感、スイッチ類の操作感、ペダルの位置、椅子の座り心地などすべての面で大変満足です。問題点は今のところありません。 初めて使う電動パーキングブレーキはボタンを引くと、後輪にブレーキがかかる仕組みで、アクセルペダルを少し踏めば自動的に解除します。大変便利です。 今回はホンダがFITの起死回生をかけた入魂の車?(オーバーな表現かも)ですから、その仕上がりは素晴らしいものです。現状では久々に大満足です。 デザインは個人的には好感を持っています。ネットでは、『ダサい!』『古臭い!』という厳しい声も見られますが、多分、フロントの少々ボッテッとした感じを嫌っているのでしょう。 そういえば、近年の日本車は、(失礼ですが、小生が勝手に名付けている)マツダのジンベーザメ・デザインや、トヨタのダボハゼ・デザインなど、『これでもか!』と大口を開け、吊り上がった目のフロントデザインは小生にはとても受け入れられません。それに比べれば新型FIT4はやさしくしっとりした印象があります。ただ欲を言えば、もう少しピリッと引き締まる感じがあった方がいいのかも知れません。 その辺は、2年後?のマイナーチェンジあたりで修正をかけてきそうな気もします。 最新のベンツ(セダン)のデザインは新鮮さと緻密さが調和し、さすがに欧州デザイン、ドイツ車という印象を受けます。ただし、デザインは各人の好みですので何とも言えません。『蓼(たで)食う虫も好き好き』のことわざどおりです。 そういうことで、新型FIT4ハイブリッドは、乗り心地良し、走り良し、燃費良しの3拍子が揃った車です。 スタイルは好き好きですから、この項目から外しました。 タイミングよく、3月9日(月)から、経済対策と、高齢ドライバー安全運転支援として、『サポカー補助金制度』がスタートしました。募集期間は本年度中となっていますが、予算の都合で財源がなくなり次第打ちきりだそうです。対象は65歳以上の高齢運転者が安全装置を施した車の購入時に補助金が出ます。 さっそく、今日、申請を済ませました。 サポカーについての詳しい内容は、下記のURLにアクセスしてご覧ください。 http://www.cev-pc.or.jp/support-car/support-car.html |
| コンパクトカーの代表と言われるトヨタのVitz改めYarisと、ホンダのFIT、さらに日産のノート、マツダのデミオ改めマツダ2など、このクラスは各社が世界戦略車として位置付けていますので、力を入れて開発しています。 特に、YarisとFITは、発売が2月10日と14日ということで、まともにガチンコしています。 以前から、この2車について触れてきましたが、新型FIT4は当初11月20日頃発売予定でしたが、電動パーキングブレーキの部品トラブルで発売延期になり、2月14日に販売されました。 この電動パーキングブレーキは、欧州部品メーカ製で、ドラム方式ブレーキに対応したもの。先行して発売した新型N-WAGON(軽自動車)に搭載し、FITにも使う予定でしたが、モニターに異常表示が出るということで、N-WAGONは出荷停止になり対策を検討してきました。やっと問題が解決し、N-WAGONも販売再開されました。 その影響でFITの発売も2か月遅れ、ヨーロッパ向けの『ジャズ』と同じディスクブレーキに仕様変更し、国内販売が開始されました。 ユーザとしては、ドラムブレーキからディスクブレーキにグレードアップしたのでうれしいですが、ホンダは今までの遅れをどう取り戻すか、ホンダの真骨頂が試されていると思います。 下の写真は我が家に入庫した新型FIT4と、妻のFIT3(黄色)です。 新型フィット(白)はドアーロックしているにもかかわらずミラーが開いている状態(本文参照)  23日に入りましたので、さっそくスタンドで満タンに給油しました。 走行可能距離を見ますと、モニターに1060kmと表示されています。満タンが40リッターですから、計算上は、リッター26.5kmの燃費になります。実際どのくらい走るのかが楽しみです。 さっそく、奈良生駒三郷町の「道の駅」まで、試運転がてら往復50kmほど走りましたが、メータ表示は25km/L程度でした。なかなか燃費は良さそうです。 トヨタYarisは、カタログ燃費が36km/Lと、とんでもない数字を発表しています。WLTCモードという新しい燃費基準で測った数字です。もしこれが現実なら、まさしく世界最高でしょう。 Yarisに対し、ホンダは燃費数字競争を真っ向からしない!という方針に変えたようです。 今回のホンダの燃費に関するこだわりは、実走行で満タン(40リッター)で1000km走ることができるという点だそうです。確かに満タンにすると走行可能距離が1060kmと表示されます。 実際、1000km以上走れるかどうかは、このガソリンを空にした際にどのくらい走れたかです。 従来のように、燃費を他社よりわずかでも良くすることに競い合うのも商品戦略でしょうが、『僅かな燃費の改善にコストをかけるより、ユーザがもっと車を楽しめる部分にコストをかける方がいいのでは?』という発想もできます。自動車のユーザの成熟化に対するコンセプトです。 この発想を導入するのには決意が要ります。 なぜならば、燃費などの数字競争は誰が見ても比較が分かりやすいからです。一方で、数字で表現できない『心地よさ』等は、なかなかつかみにくい課題です。しかも、『ユーザが何を要望しているのか』をつかむことは、なかなか容易ではありません。さらに、それが受け入れられるかどうかも心配です。 そういうとりとめにくい狙いを今回の新型フィット4で挑戦したと言えるでしょう。 従来のホンダは、どちらかと言えばF1レーシングカーにチャレンジしているように、エンジン出力や、100mを何秒で走るか?というような数値競争型のメーカでした。そういう企業風土だったのです。今回の新型FIT4はそれをがらりと変えました。 燃費をよくするには、基本的に車重を軽くしなければなりませんので、騒音や振動などいろんなマイナス面が生じます。車体強度は超高張力鋼板と言われる軽い強い材料が開発されていますが、コスト面や製造上の課題があるようです。また、材料調達面での課題もあります。FITのように、世界中で製造する車は、世界中で調達できる鉄板でないと車は造れません。 車体構造(フレーム)を新設計して最新技術で軽くて丈夫な車体を造ることは、カーメーカの競争になっています。各社は競ってコンピュータを駆使し構造や強度解析をして作り上げます。 Yarisの車体重量は1090kgですから、FIT(1200Kg)に比べて110kg、大人約2人分軽いことになります。これだけ大幅な重量差があると、燃費は大きく変わります。 半面、Yarisは軽自動車に積んでいる3気筒エンジンのため騒音や振動の面で不利になります。ガソリンエンジン車は、振動を打ち消すためのバランサーを組み込んでいます。 ピストンやクランクシャフトが回転に伴い重量の偏りで発生する振動を、『バランサー』という重りを取付て回転させ、重量バランスを取り、振動を打ち消す働きをします。この『バランサー』はガソリンエンジン車のみ搭載で、ハイブリッド車には装備していないということです。 YARISの実車に乗っていないので、どの程度、騒音と振動が大きいのかは分かりません。 Yarisは車体が小さく、後席が狭く、後方視界が悪く、前席優先の構造に割り切っていますので、軽量化を図った走りに徹したコンセプトです。エンジンも3気筒で軽量化しています。 車に限らず、商品はコンセプトとバランスが大切です。車は『どういう狙いを提供するのか』というコンセプトと、性能(走りの良さ・燃費等)、ハンドリング(ハンドルの切れ味等)、コーナリング(カーブの運転感覚)、乗り心地、静かさ、安全など多項目にわたるバランスが大切です。 このバランスがユーザの志向にどうマッチングするかという点が味噌で、そこが商品企画、商品コンセプトの一番難しいところであり、やりがいがあるところです。 走りのホンダが、『心地よさ』を追求した結果が今回の新型FITだ!ということです。 確かに乗ってみて、あきらかに今までのFITと違うな!という点を感じます。 まず、ドアーの閉まり音です。薄ぺらな感じの音ではなく、厚みのあるドシッとした気密性の高い音で、ワンランク上の質感があります。椅子も座り心地が良く、やわらかくて、しかもしっかりホールドされます。座って前方を見ると、これは誰もが気づく圧倒的な広々した感があります。家内が助手席に座ってまず言ったのは、「私のFITに比べて広々していて気持ちがいい!」ということでした。 その理由は、前方のピラー(Aピラーと呼ぶ支柱)が従来のFITは太くて丈夫で安全性を確保していたのですが、今回のFITはその柱が細くて視界を妨げないのです。安全性はしっかり視野を妨げないところに太いピラーがあります。この広い視野のおかげで、前方の左右から横断する人の姿がよく見えることです。 走りだすと、モータ走行のおかげで実に静かです。しばらく走るとエンジンがかかりますが、それもよく耳を澄ませないと分からないほどです。あっという間に50~60Km/時になっています。 タイヤのロードノイズも前車(FIT3)に比べると、ずいぶん騒音対策が行き届いていることが分かります。ラジオやテレビが聞きやすいことで、騒音が低いことが分かります。 加速や減速が非常になめらかで、これは実に素晴らしいと思います。 今回のFIT4は、ホンダが『起死回生』または『捲土重来』を期したものと思われ、肝入りで開発したと言われていますので、まだちょっとしか乗っていませんが、大変すばらしい出来栄えだと思います。 皆さんに自信をもって、お勧めできる車に仕上がっています。 一つだけ、『あれー!?』と思った点があります。 それは、リモコンキーでドアーをロックをしますが、この時ミラーが閉じないのです。今時、軽自動車でもオートリトラミラーが装備されています。妻のFITはオートリトラミラーになっています。 契約時、当然だと思い、この点を確認するのを忘れていました。営業の方も気づいていなかったようです。というよりそれが当たり前だと思っていました。ここまで完成度を上げながら、なぜオートリトラミラー付きにしなかったのか? 不思議です。 但し、ドアーを閉め、車外に出て、車から1mほど離れると自動的にドアーはロックされます。 その際、ウィンカーが一回点灯し、ロック音が聞こえますので、ロック忘れの心配はありません。 最近、歳の性か、ドアーロックしたかどうか不安になります。その時、外から見てミラーが収納たたまれていれば、ちゃんとロックされているのが分かり、安心できます。 それが今回のFITでは標準装備されていないのです。 これにはがっかりしました。 オートリトラミラーはオプション設定で、追加料金が部品代1万円(税別)、工賃が1万円余り、合計で2万円ほどかかります。皆さん、契約時には、この+αが必要なことをご注意下さい。 スーパーや高速道サービスエリアなどの広い駐車場に駐車して車を離れると、不審者が巡回していて、開いているドアーミラーを見つけては、ドアーノブに触れ、車内を物色しようとする人がいるようです。ドアーのロック忘れはありませんので被害はないですが、触られることが嫌ですね。今の車はドアーロックすればミラーが閉じるのが当たり前になっているからこそ、ドアーミラーが開いている車を見つけて、不審者の物色行動につながるのではないかと懸念します。 Yarisはオートリトラミラーがきちんと装備しています。さすがにトヨタはこの辺の抜かりがありません。今は、これが気にかかる点です。さっそく、追加料金を払いオートミラーを着けました。 ちょっと騙されたような印象も受けます。多分、マイナーチェンジではちゃんと着くと思います。 以上、新車概要を速報しました。 今回のFITは、『ホンダの意地』を感じる久々の出来栄えだと実感しました。 引き続いて、後日談を報告します。 お楽しみに! |
| いよいよ、2月14日から、トヨタのYaris(ヤリス;旧 VITZ)対ホンダFIT4の対戦が始まります。 Yarisは、一足早く2月10日から発売、対してFIT4は2月14日発売でした。両社は日産ノートを加えて、日本のコンパクトカー市場で熾烈な争いになると予感します。   トヨタYarisは、Vitz(ビッツ)を改め海外市場向けブランドYarisを国内に展開したものです。 トヨタYarisは、Vitz(ビッツ)を改め海外市場向けブランドYarisを国内に展開したものです。Yarisはヨーロッパで人気の車種で、旅行中によく見かけました。 一方のFITは、これまたホンダの世界戦略車で、各国に輸出しています。 FITは今回で4回目のフルモデルチェンジを行った車で、前のFITは7速ダイレクトクラッチを初めて最小したユニークなアイデアを生かした1モータハイブリッド車でした。着想は素晴らしかったのですが、モータ・エンジン・変速機の制御プログラムの熟成が十分でなく、発売直後から5回もリコールを連発し、すっかり販売が萎えてしまいました。 その後の改良により、素晴らしい車に仕上がりましたが、一度、ケチが着いた車は思うように販売が伸びず現在に至りました。 それまで乗っていたマイルドハイブリッド方式のFIT2から、このFIT3ハイブリッドの発売と同時に乗り換えました。5回のリコールを経験しましたが、その後は正常に使用できました。 FIT3は満タン法で測定した実燃費は、手放すまでの平均燃費は21.4km/Lで、これは決して悪い数字ではなく十分満足できる値でした。 しかし、燃費ではトヨタのハイブリッド車が一歩先行してきました。 プリウスやアクアの燃費が常に上位ランキングに顔を出していました。多分、ホンダは地団駄踏んでいたことと思います。 ホンダには上級車のアコードがあり、主にアメリカで量販している主力車で、日本では大きすぎてあまり売れていません。このアコードに搭載しているハイブリッド方式は2モータシリーズ方式です。 シリーズ方式とは、エンジンが発電用モータを回して、リチュウムイオンバッテリーに充電し、その電気で駆動モータを回し走る方式です。スタート時はモータで走り始めますので、エンジンの回転が上がらずに燃費が大きく改善します。また、ブレーキング時は走行モータが発電機となり大量の電気をバッテリーに回収します。高速道路では走行モータを介さずに、エンジンの駆動力を直接タイヤに伝えるようになっています。こうすることで、エネルギーロスを最小化し、効率を最大化しているのです。アコードは、トヨタの上級車との比較でも上回る燃費性能を出しています。 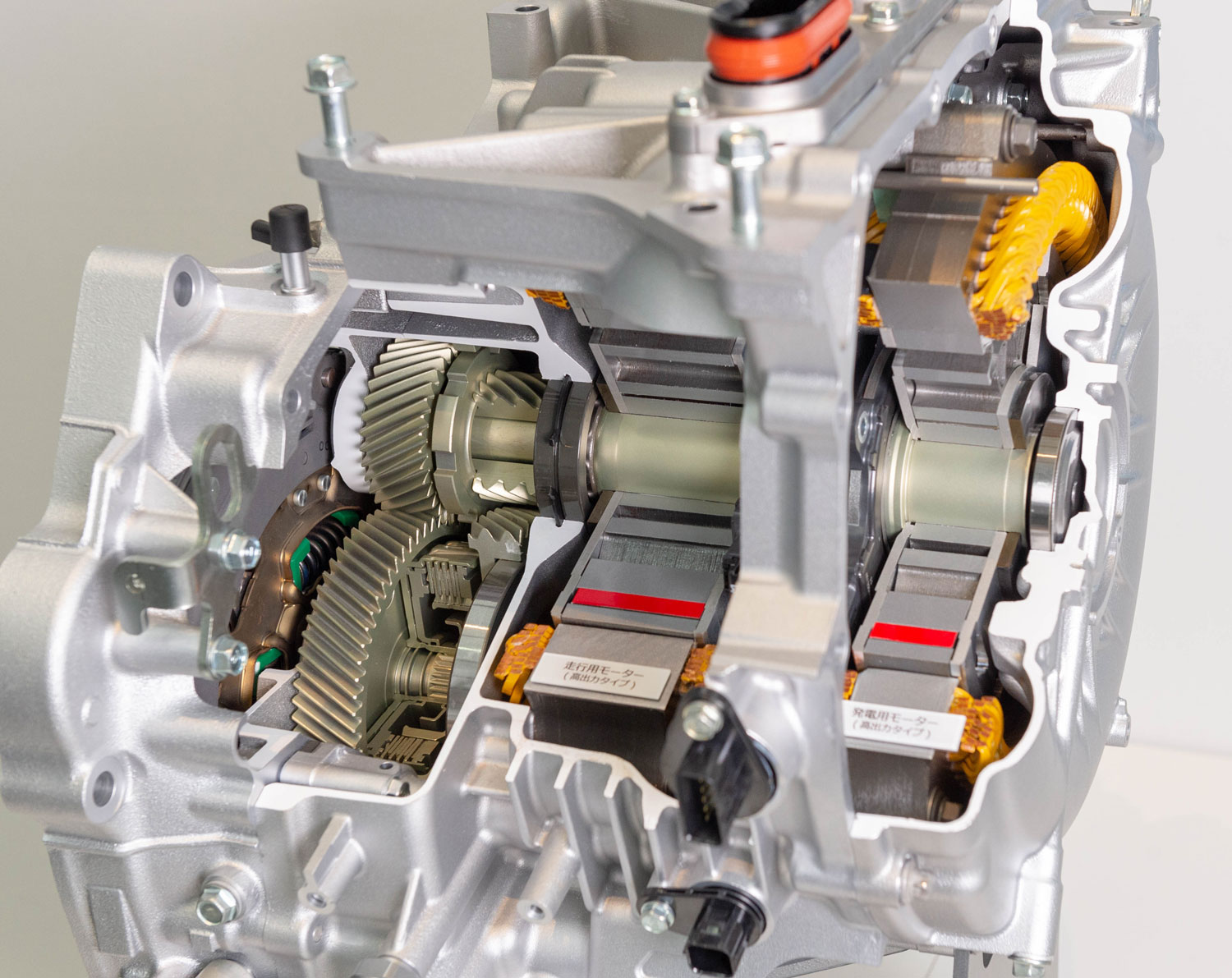 新型FIT4は、アコードの2モータ方式を素直に取り入れた優れものです。 新型FIT4は、アコードの2モータ方式を素直に取り入れた優れものです。2モータ化するにはコスト面で、コンパクトカーに載せるには厳しい課題があったようですが、日産ノートが既に商品化しベストセラーカーに仕上げていますから、ホンダもここは頑張りどころとして取り組んだはずです。 ホンダは今後、この2モータ方式を採用するとアナウンスしています。この方式をホンダはi-MMD方式と呼んできましたが、FIT4からはe-HEVと呼称を変えました。 さて、燃費の表示法が新しくなり、JC08モードからWLTCモード表示に変更されました。 これは表示をカタログ値と実用時の燃費に近づけたものにするための改訂です。 市街地走行、郊外地走行、高速道路走行の3つの走行パターンで燃費を計測し、各値と、その平均値を表示しています。今後は、このWLTCモード表示に変わります。 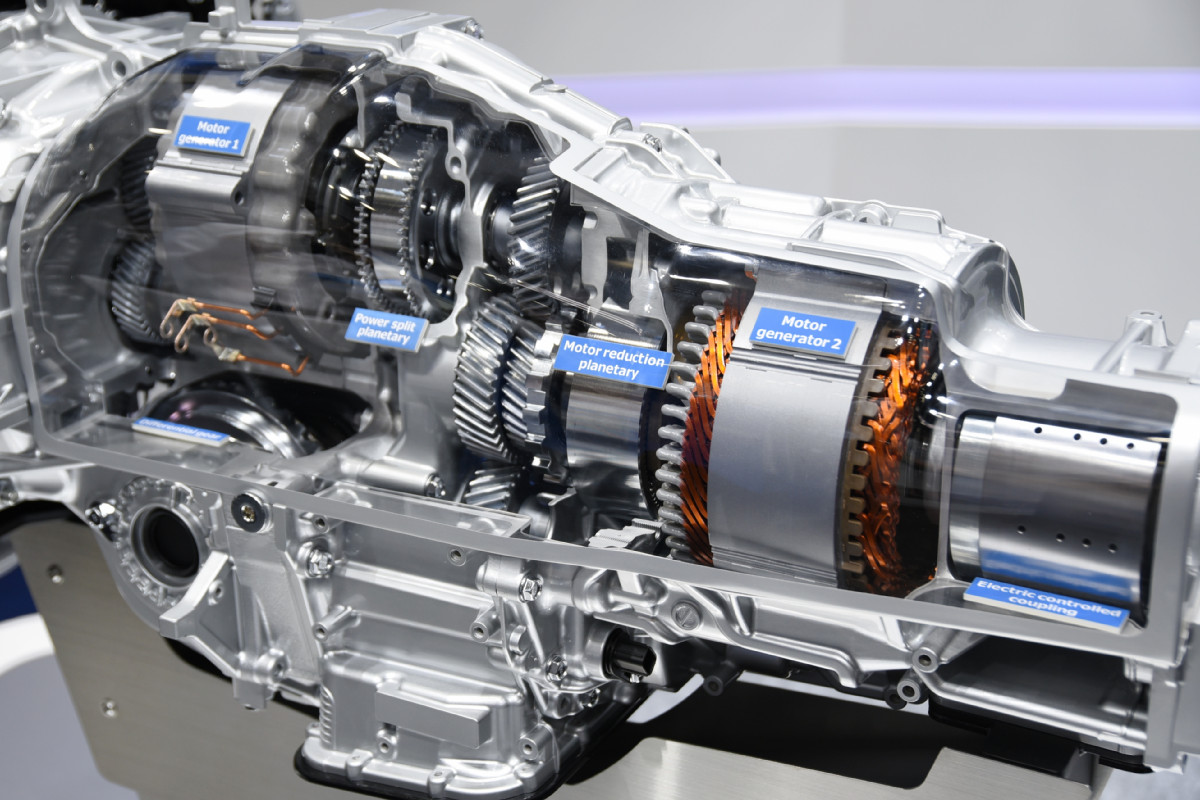 トヨタのYarisのカタログを見ると、WLTC燃費が36km/Lとなっています。この値はJC08モードでは約43km~45km/Lに相当する値です。元々すごい燃費を更に改善したと思います。 その理由は車体重量を1050kg~1090kgと軽量化していることです。加えてエンジンは、1500cc直列3気筒を新しく採用しています。 3気筒エンジンは軽自動車で使われているエンジンの形式です。 エンジン技術の進歩で、3気筒でも振動や騒音を押さえることが出来るようになりました。 BMWも小型車には3気筒エンジンを採用し始めたようです。 上の写真は、ホンダ 新型FITの構造です。 下の写真は、トヨタ Yarisの構造です。 この2枚の写真で分かるように、ホンダFIT(eHEV)の構造は、2モータ(走行用と発電用)を同じ軸上に配置し、しかもモータのコアサイズが同じです。これが大幅なコストダウンに成功した最大の肝だと思います。同じ軸上に2モータを配置することで、メカの幅が短くでき、4気筒エンジンにこのメカをつないでも車幅に収まるようになったと思われます。 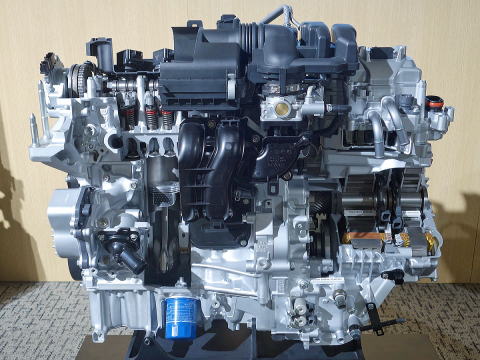 上の写真は、ホンダ 新型フィットハイブリッド(eHEV) パワートレイン 一方、トヨタハイブリッド方式も2モータ方式ですが、遊星歯車を巧に使い、複雑な制御により、エンジンとモータの特性のいいとこどりをしたシリーズ・パラレル方式で、独自の方式です。 上の2枚の写真の下のメカはトヨタYaris のハイブリッドメカニズムです。発電用モータと走行用モータが遊星歯車を介して軸を2列に並べてつながっていますので、メカニズムの幅が長くなっています。これをエンジンとつないで横に並べると、Yarisの車幅に収まらないので、エンジンを4気筒から3気筒にして、エンジンの幅を短くしたものとも考えられます。 3気筒エンジンを積んだもう一つの理由は、1気筒当たり容量が500ccとなり、エンジンのトルクや効率を上げることを狙ったのかもしれません。その反面、振動や騒音は4気筒に比べて劣るのは仕方ないことです。 従来のVitzは、4気筒エンジンでも車幅に収まっていましたが、今回、モータの馬力を相当強くしていますので、ハイブリッドメカの幅が大きくなったのかと思われます。 その他、トヨタとホンダのモータの違いは、ホンダは回転子と固定子の径を大きくしてトルクを稼いでいます。トヨタのモータ部の径は比較的小さく、高速回転に適していますが、トルクは一般的に不利です。 ここで少し理論的な話になりますが、 トルク=回転力(力)×回転子の直径 τ=F×L 馬力=トルク×回転数 P=τ×N ホンダのモータはトルク重視型、 トヨタのモータは馬力重視型とも言えそうですが、一概に この数式で言い切ることはできません。 今後、トヨタのコンパクトカー車は、3気筒エンジンが搭載されると思われます。 いずれにしても、トヨタハイブリッドは、『これに勝る方式はない!』言わば、ハイブリッドの理想形だと言われましたが、何事も記録は破られるのが世の常です。 いよいよ最量販車でホンダの2モータ方式がトヨタハイブリッド方式と真正面からガチンコする状況になりました。 下記の仕様では、やはりYarisの燃費が他を大きく上回っていますが、実使用時の燃費はどうなのか? しばらくすればいろんなデータがモータマガジンやネットで、にぎわうと思います。 しかし、YarisとFIT4はコンセプトが違うような感じを受けます。 Yarisは、ヨーロッパ市場を強く意識した小さな車で、きびきび走る個性のある印象です。 少々後席の狭さは気にしないで、走りに徹したという割り切りが入っています。イタリアのFIATなどに似た印象です。一人か二人で前席優先で乗るパーソナルカーだと思います。 一方の新型FIT4はファミリー向けで、広々とした室内で、ゆったりと静かに気持ちよく走ることを狙った車のようです。 そういう比較的明快にコンセプトが分かれていますので、正面からバッティングしないような印象も受けます。果たして、日本のユーザはどちらをチョイスするかです ??? 各社のハイブッリド車仕様 (2月16日現在の公表値)
(注) WLTC;Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure |
| 来年2月14日に、ホンダのフィットが新発売(フルモデルチェンジ)されます。 トヨタの新車種YARIS(旧名;Vitz)とFIT4(新型)と、日産ノートのガチンコ勝負になります。 FIT4とYarisはフルモデルチェンジで、この2車種は車造りの狙いが異なることが分かりました。今まで同じようなものを競い造ってきた日本のモノづくりにとって面白い勝負になるはずです。 ノートは発売して2年?経過していますので、今年か来年の夏にフルモデルチェンジを迎えますので、ここでは除外し、フィットvsヤリスについて考えます。 Yaris(ヤリス)は、パーソナル向けのようです。だから車内の広さや快適さより、一人か二人乗りを中心に考え、『走り』を追求した車のようです。少々、ヤンチャな感じの車です。 FIT(フィット)は、車内が広く、誰もが運転しやすく、快適な車でファミリー向けのようです。 東京モータショーで発表された記事を見れば、そういう両社の意図が現れています。 今回、この2車で大変興味があるのは、『ハイブリッドシステム』の違いです。 トヨタのヤリスは、トヨタが世界に誇ってきた理想的なハイブリッドシステムTHS-Ⅱを改良して搭載しました。エンジンはトヨタでは初めての3気筒で、軽自動車や日産ノートに積んだエンジンと同じです。3気筒にすることで、各部の摩擦(フリクション)を減らせるので、燃費性能改善が期待出来ますが、騒音や振動は4気筒に比べて不利になります。もちろん、3気筒はピストンやクランクシャフトが1本少なく、部品点数が減るので、コスト的に安く造れます。 3気筒は軽自動車のエンジンだと思っていましたが、日産ノートに搭載した3気筒エンジンは、1200ccでした。今回のトヨタのヤリスは1500ccのエンジンを積んでいます。 ヤリスの燃費は、新基準(WTLC基準)で36km/Lと驚く数字を発表しています。多分、間違いなく世界NO.1です。 その理由は、エンジンを3気筒にして、エンジン効率を向上したことや、ハイブリッドシステムを見直し、従来よりモーターの馬力を大きくし、バッテリーはニッケル水素電池からリチュウムイオン電池に変更したことが挙げられますが、基本的には、車体が軽く造られていることです。 車両重量は1080kgしかありません。これはホンダのフィットの現行型の車両重量に匹敵します。軽量化により大幅な燃費改善が実現しました。 車体が軽いということは、エンジンノイズや、路面の走行音(ロードノイズ)が室内に侵入しますのでやかましさという面では不利になります。さらに燃料タンクは36Lと小さく、燃費がいいからこれで十分かもしれませんが、徹底して燃費や『走り』の数値にこだわっているようです。 FIT新型は、今までのi-DCDという1モータハイブリッドシステムを放棄して、e-HEV(i-MMD)という2モータ方式を搭載しました。これは、日産のe-Powerに似ています。 i-MMD方式は、日産のe-Powerより早くアコードなどに搭載していますので、ホンダが日産の真似をしたわけではありません。(これは、ホンダの名誉のために付け加えておきます) 日産eーPowerと違う点は、フィットは、エンジンが1500cc4気筒、ハイブリッドシステムは高速走行では、モータを介さずエンジンが車軸に直結して駆動する方式ですからロスを減らし、燃費を改善している点です。 フィットの燃費などのスペックは未だ、発表していませんので分かりません。 3社のエンジンルームを覗いてみました。 写真が、トヨタのヤリス 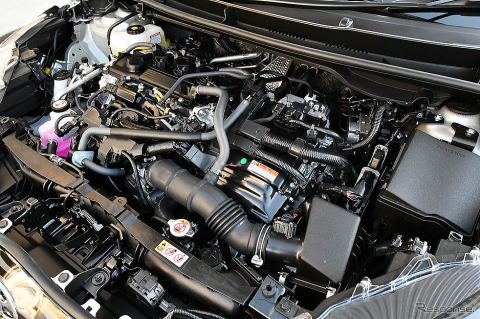 写真はホンダのフィットe:HEV 新2モーターハイブリッドシステム  写真は日産ノートe-Power  写真を見ると、最上段の写真のヤリスは、パイプやコードが交錯し複雑な感じを受ける。 その点、中断のFITはすっきりまとまっている。 最下段の日産ノートは、右の白い箱(アルミダイキャスト)が目立って大きい。この箱の中身はハイブリッドシステムを制御するPCU(パワーコントロールユニット)が入っていて、PCUはインバーター、パワー回路、制御マイコン、その他電子部品から構成されている。 上のホンダFITの白い箱もPCUが搭載されているが、フィット4はノートより小型化、高効率化されている。ヤリスは黒く見えるが、PCUはアルミダイキャストの箱に入っているはずだ。 PCUはハイブリッドシステムを制御する最も重要な部分であり、外来雑音や外来電波を遮蔽すると共に、自らの回路が発する雑音や電波を遮蔽する目的がある。更に、パワー回路が発生する熱を外部に放散するため、アルミダイキャストは放熱板の役目もはたしている。 フィット4 vs Yaris vs Note の3車種のエンジンとモータの性能比較 フィット4は未発表で不明(1/20現在)
2月14日以降の販売合戦はどこが勝利するか? |
2019年12月28日(土)
マツダの『魂動』デザインは飽きられないのか?
| 日本車のデザインの変遷に興味を抱いている。 それはデザイナーのセンスや力量などの要素が大きいが、世の中のトレンドも大きく左右する。加えて、メーカの経営戦略とも言えるデザインポリシーが大きな要因が背景にある事だ。 そういういくつかの要因で、各社の車のデザインが決まる訳だが、最近特に目立って気になるのが、マツダ車のデザインだ。  マツダは自動車メーカの中では、トヨタ、日産、ホンダ、三菱、スズキ、マツダ、スバル、ダイハツなど業界中では中堅メーカだが、最近、特にエンジンに力を入れて、ジーゼルエンジンの排気ガス規制をクリアしたり、ジーゼルエンジン特有の振動や騒音をガソリン車並みに押さえたり、ガソリンエンジンは逆にジーゼルエンジンのような太いトルク特性を持たせたりと、各自動車メーカの技術者を驚嘆させている。 マツダは広島県にあり、地方独特の粘り腰を持った技術者が多いのかもしれない。 プロ野球だって、特に有名な選手を高い報酬で獲得することができないので、素質はあるが名もない選手を採用して、徹底的に仕込んで一流選手に育て上げ、一流の球団になっている。 そういう独特の風潮があるのかもしれない。 それはそれとして、マツダの車は、高級車からデミオ(今はCX2)を見ても同じに見える。 マツダ2,3,6、 マツダCX3,5,8,など車種名も、ヨーロッパ車流に名前を数字に変えた。アテンザ、アクセラ、デミオ等の慣れ親しんだ名前が消えた。 そのグレード別の数字が、どういうグレードなのか、デザインをパッと見て、素人には全く分からない。せめて、フロントグリルの周囲に何かアクセントポイントでも付加してもらえば、差別化ができるのだが、高級車から普及車まで、相似形のデザインに統一している。 『魂動』デザインは、“Soul of Motion ”という意味らしいが、その意味するところは『生命感あふれるダイナミックで、マツダらしいエレガンス、日本の美意識を体現する』ということらしい。 そして、そのフォルムは『チータが獲物を狙って、力を溜めて、跳びかかる瞬間の動き』だそうだ。 そういうデザインコンセプトを、2010年から続けて採用してきているが、素人目には、何か陳腐化した、もう見飽きた感じで、新鮮味もなく、どれも同じに見える。 しかもフロントグリルの空気取り入れ口は、まさにジンベーザメのような印象を受ける。 これは小生だけだろうか? 大阪南港の水族館で見たジンベーザメの印象が強いく残っているためかもしれない。 車体カラーは、独自のソウルレッドメタリックを基本としている。確かにこの赤は深みがあってなかなかのものだと思う。販売当初は、素晴らしい色だと思ったが、最近は、少々見飽きてきた感じもする。 マツダは、中小メーカとして自社のプレミアムブランドの確立に躍起になっているのかもしれない。それは大した戦略だとも思う。 これに対し、巨人、トヨタは“キーンルック”と呼んでいる眉と、目が吊り上がったデザインを採用している。2012年からレクサスに"スピンドルグリル”を採用した。  『キーンルック』とは、「キリッ」とした細長いヘッドライトと、V字にきれあがった顔付きで、獲物を見つけて飛ぶ猛禽類の鋭い目と顔つきだそうです。 キーンルックの「キーン (英語: keen)」という言葉は、「感覚的に鋭い、鋭利な」という意味があります。 その意味が示すように、キーンルックのデザインは、エンブレム(メーカーや車を表す標章のこと)を中心として、V字にきれあがったグリルと、細めの鋭いヘッドライトの形が相まって、知的で、精悍な印象を与えるものとなっています。 最近のトヨタデザインは、何でもありという感じで、ドンドン進化している。よく言えばの話。 デザインのポリシーが感じられず、『これでもか!』という目立つ、際立つ表現がデザインのような印象を受ける。 しかし、トヨタがどういうダサい、違和感のある、または奇抜なデザインを採用しようが、しばらくすると、それが当たり前に定着し受け入れられる。この力がすごいところだ。 しかし、そのトヨタですら、プリウスのマイナーチェンジ前の新モデルのデザインは受け入れられなかった。すぐデザインをマイナーチェンジして、少しまっとうな形にした。それが良く売れている。 ヨーロッパの車は、ベンツはベンツのデザイン流儀があり、BMWは見れば分かるカタチであり、VWはも同様である。 しかも、従来の製品と、新製品の違いがすぐ分かる。新製品には一歩進化したな!というデザインの新鮮さが見て取れる。自社のデザインの根幹や、自社の基本ポリシーはしっかり守りながら、進化をしっかり訴えるところが、やはり日本車のデザインと一味違う洗練された感覚や、センスを持っているように感じる。これは小生だけの感想だろうか? マツダのデザインは、ヨーロッパでなかなか評判が良いと聞いている。だから全車種相似形の『魂動』デザインを続けるというのは、新しい車なのか、旧型車なのか分かりにくい。車のデザインが陳腐化し難いという面のメリットもあるが、やはり新車に乗っていると喜びは感じたい。その辺は考慮すべき点だろうと思う。 今年も、明日は大晦日、あとわずか残すのみになった。 来年の干支は、庚子(かのえね)で、物事を始めるには、良き年だそうです。 ぜひ、新しい挑戦をして、良き年になることを願っている。 来年もよろしく!! |
2019年12月22日(日)
YARIS vs NEW FITの幕開け近し
| いよいよ、来年2月にトヨタのYARISと、ホンダのNEW FIT が発売されることになった。 この2車は来年のコンパクトカー市場を占う出来事になるだろう!。ガチンコ勝負だ! 最近、若者の車離れが激しくて、軽自動車ばかりが売れている。そこへ小型車の代表車種が打って出る。  左は、ヤリス(ヴィッツ改名) 左は、ヤリス(ヴィッツ改名)ヤリスは元々、グローバルカーで、輸出のブランドだった。 YARISは、ヨーロップで以前から売られている車で、日本ではVITZと呼んでいたが、今後はビッツ改めヤリスになる。 外観はいかにも、アグレッシブで、やんちゃな走りそうなデザインになっている。 トヨタやマツダ車は、最近大きく口を開けたフロントグリルが特徴で、小生は、ジンベーザメデザインだと揶揄している。個人的には、全く好みではない。 右下は、今回、発売されるHONDA NEW FITで、今までの釣り目の睨んだデザインから変身し、大人らしく、おとなしく優しさを感じるデザインを採用した。それでいて、全体の塊感がうまく表現された飽きが来ないデザインに仕上がっていると思う。こちらの方が好みだ。  デザインは、人それぞれの好みなので、一概にどれがいいか分からない。 デザインは、人それぞれの好みなので、一概にどれがいいか分からない。だから、メーカのデザイナーは苦心する。 内装を見ると、トヨタのヤリスは従来どおりのボタンや、ツマミや、いろんなものが着いている。人によっては、この方がお得感を感じるかもしれない。 一方、NEW FITは、すっきりとした内装で、シンプルにまとめている。 必要なものは、ちゃんとついているが、まとめ方の問題だろう。 今回、言いたかったことは、日本の自動車は普及しつくして、いよいよ車もコモディティー化してきたことだ。 家電商品は既に普及率が90数%に達し、もう新規需要は考えられないところまで至っている。テレビのように、ブラウン管テレビから、薄型大画面の液晶や、有機ELテレビが生まれれば、買い替え需要が期待できる。しかし、冷蔵庫や洗濯機などは、新婚家庭は新規需要があるが、最近結婚しない人が増え、一般家庭では壊れない限り買い替え需要はほとんどない。 こういう商品を称してコモディティー商品と呼んでいる。 まさに、自動車もそういう域に達しつつある。 だから、メーカーは、『これでもか!』という強烈に目を引くデザインを採用し、次第にそれがエスカレートして、「もっともっと!」というような派手なデザインが増えてきた。 車の性能はそろそろ限界に達しつつあり、ガソリンエンジンの燃費効率は、40数%にまでなった。以前は、ガソリンエンジンは20数%、ジーゼルエンジンが35%程度と言われていた。 それが今やガソリンエンジンは50%を超えるところまで達成できる見通しの開発が進んだ。 しかも、排気ガの厳しい規制値をクリアしながらである。これは素晴らしい技術の進化だ! この技術開発の裏には、電子制御技術なしでは考えられない。半導体のCPUや、FPGAや、メモリーや、各種センサーなどの電子デバイス技術が、エンジンを精密に制御することができて初めて達成できる技術と言える。 そうなってくると、性能競争で、出力(馬力)や、トルクや、燃費競争をやっても、ユーザには響かなくなる。僅かの性能差を訴えても、ユーザは他の車を使う価値を考えて車を買うことになってきた。 車の価値は何か? という原点の問題だ! なぜ、ヨーロッパのベンツや、BMWや、VWや、ポルシェが売れるのかだ。 値段がべらぼうに高いが、性能は日本製と大きな差はない。 ヨーロッパの自動車は、長い歴史を経て、車造りの感性を磨いてきたと思う。それに対して、日本のメーカは、とにかく他車に性能やスペックで勝つ競争ばかりやってきた。 小生が松下電器のオーディオ(ステレオ)を開発していた頃を思いだす。 アンプ、チューナ、レコードプレーヤ、デッキ、CDプレーヤ、スピーカなどの各コンポーネントの開発の際に、商品企画から各社の比較表を作って設計に提示した。 それは、性能;例えば、アンプの出力、歪み、SN(ハム・ノイズ)、ダイナミックレンジなどという各項目で他社に負けないスペックを要求したものだ。そうすることが当たり前で、安心できた。 デザインは大切だが、これは好みがあるので、モノを作る側からすれば、デザインに勝負を掛けることは、非常に不安を感じた思いがある。 現在の自動車メーカの立場がそういう時期に差し掛かってきたように思う。 今回の各社の新製品を見ると、マツダやトヨタ自動車は相変わらず従来のモノづくりの延長線上のコンセプトを踏襲した開発や製造をしているように見える。これは決して間違いとは言えない。いいものをより安くは、常に正しい。 今回、思い切った開発コンセプトチェンジをしたのが、ホンダのNEW FITだと言える。 これが、受け入れられるかどうかだ。日本のユーザの商品に対する成熟度が試される。 従来の車の競争テーマの燃費、走り(100mを何秒で走るか)、パワー、トルクと言った要素から、『使い心地よさ』という開発コンセプトを掲げて、取り組んだと言われている。 これは言葉では分かるが、実際の車づくりの現場では苦労したと思われる。 その取り組みの苦労が報われるかどうか、もうしばらくすれば結果が出る! ホンダの4つの心地良さとは、 ①視界の良さ ②座り心地の良さ ③乗り心地の良さ ④使い勝手の良さ に加えて、 ・乗る人や、周囲の人に対する安全性の確保 ・つながる、コネクティングカー ・使い方による品揃え など、従来の車の車格によるランク付から、ユーザ志向の商品揃えになっている。 果たして、この新しいコンセプトのプレゼンスが受け入れられるかどうか? 日本の社会の成熟度が試される。 実車を見て、乗ってみないと何とも言えないが、東京オートショーの記事などを読むと、興味深い記事に出会う。 年末か、年明けには実車がお目見えするはずだ! |
2019年11月3日(日)
YARIS vs FIT 対決の勝負は?
| 2年に一度の「東京モーターショー」が東京の国際見本市会場『ビックサイト』で10月24日から11月4日まで開催されている。 世界の自動車市場は、ユーザの車に対する価値観が大きく変わってきたのを反映し、メーカがオートショーかける金を見直しつつあり、出展社も減ってきた。以前はアジアで開催される最大のショーであったが、今は中国に移っている。そういうことで、オートショーの性格も変わってきつつある。 車の安全運転支援機能や、自動運転や、排ガス規制や、燃費競争に注目が集まり、エンジン性能や、馬力や、100mを何秒で走るかというような車の基本性能競争から、違った次元の競争になりつつある。 地球温暖化の元凶とされてきた車の排ガスに対する規制が厳しくなり、エンジン車では規制をクリアできなくなったので、メーカはハイブリッドやEVに力を入れている。 日本ではマツダだけがガソリンやジーゼルエンジンの開発に力を入れているユニークなメーカになっている。 最大手のトヨタは従来のダイハツに加え、スズキ、マツダ、スバルの競合他社をグループの中に引き入れ大トヨタグループを形成しつつある。これに日産・三菱自動車と、ホンダの2社が対峙する様相を示してきた。 そういう自動車業界の大変革期を迎え、2019東京オートショーが開催されいる。 今日は最終日。 注目は、ホンダの新型フィットだ!フィットの4代目なので、以下、フィット4と表記する。  新型フィット4は、従来のフィット3からデザインコンセプトを変え、女性にもなじみやすく、誰でも親しみやすいデザインにまとまっている。従来のフィット3はスポーティで、少しやんちゃな感じを受けるアグレッシブなフロントデザインだった。それが新型フィット4では、全体に固まり感を強調したまろやかな曲面で構成され、やさしさを感じる。 悪く言えば、少しダサいかも! この新型フィット4は、11月発売と発表されていたが、発売が来年2月に延期になった。理由は、オートパーキングの動作に不具合が見つかったからだ。軽自動車N-WGN(N-ワゴン)も同じオートパーキングシステムを採用しているので、こちらも、ただ今販売中止状態ということだ。 もう少し詳しく説明すると、オートパーキングは後輪ブレーキ(ドラム式)で動作させているが、モデルチェンジしたN-WGNの出荷検査で不具合が見つかった。そこで、ドラム式ブレーキからコストが高いディスクブレーキに変更するそうだ。ドイツ製の部品を使うので、変更と部品調達に時間がかかり、生産や出荷ができない状態になっている。もうすぐN-WGNは販売される。 フィットはヨーロッパでは『ジャズ』という商品名を使っている。 今回の新型フィット4のオートパーキングシステムの変更は日本向けフィット4であるが、ヨーロッパ向けの『ジャズ』は、ディスクブレーキ仕様なので、それを使うだけなので、大きな設計変更はなくて済むそうだ。ただ、部品調達時間がかかるので、発売は11月から2、3か月遅れるが、ブレーキに関する不具合だから、完璧な品質を保証できる商品として販売してほしい。 今、乗っているフィット3はモデルチェンジ直後に購入したが、5回もリコールを受け、これには、正直「またか」と、あきれ返ったが、つい先日の点検で、制御プログラムをアップデートしてもらった結果、以前に増してスムーズな走りになった気がする。エンジンとモータのつながりが改善されたのだろう。現状、FIT3の完成度は大変良くなり、燃費も結構よくて、モデル末期の車として完成度は最高の状態だと思う。 さて、フルモデルチェンジされる新型フィット4はどうだろう? 今回のモデルチェンジの目玉は、なんと言ってもハイブリッドシステムの変更だ! 今までは、i-DCDという1モータ駆動のホンダらしい奇抜なアイデアを生かした7速ダイレクトチェンジというメカを採用したものだった。このダイレクトチェンジのシステムはドイツメーカのもので、初めて導入したものだったので、制御プログラムの完成度が悪く、リコールを連発をした。 今回の新型フィット4は、2モータ方式のi-MMDというホンダの高級車:アコードから採用し、既に4、5年の実績を積んだハイブリッドシステムの改良型システムなので、まず大丈夫だろうと思う。このi-MMD方式は、日産のノートeーPowerと基本的には同じ方式だが、高速道路走行時はエンジン直結で走るところが違う。 ハイブリッドシステムのi-MMDの2モータ化によって、 ・どれだけ燃費が良くなるか? ・どれだけ加速や走りが良くなるか? ・どれだけ静かな車内になるか? など大きな期待がかかる。 新型フィット4は今までトヨタのアクアやプリウスに勝てなかった燃費性能で大きく引き離せるか見ものだ。両社とも譲らぬ競争が続くだろう! 一方、トヨタはヴィッツをフルモデルチェンジして、YARIS(ヤリス)という新車名で、フィットと同じ2月に発売される。ヤリスという車名は、以前からヨーロッパで使っていて、ホンダのジャズと同様である。トヨタは今回、ヴィッツを止め、日本で『ヤリス』に改名すると発表した。 ホンダは以前どおり、日本はフィット、ヨーロッパはジャズと使い分ける。  上の写真は、『新型ヤリス』 新型ヤリスのデザインは大きく口を開いたフロントマスクで、ダボハゼがイメージとして浮かぶかもしれない。個人的には、マツダのジンべーざめを思い浮かべるデザインや、最近のトヨタ車の『これでもか!』というほど、大きく口を開いたイカツク、釣り目のデザインは好みではない。 目立ちすぎ、やりすぎの感じを受ける。 新型プリウスがデザイン不評で、思ったほど売れなくて急遽マイナーチェンジした経緯からしても、余り奇抜なデザインは目立つが、大衆受けはしないように思う。このヤリスがどう評価されるか、注目だ! ヤリスvsフィットの真っ向勝負はどちらに軍配が上がるか、大変興味深い。 ヤリスはトヨタが満を持して新開発のTNGAと呼ぶ小型車共用車体(ボディ)で、従来のヴィッツから50kgも軽量化したという。車は軽い方が燃費が良くなり、走りもよくなるが、一般的に軽くすると車体強度が落ちるので、その点は設計力でカバーして、軽くて強靭な車体を造るのがメーカの腕になる。 燃費の改良点として、ヤリスは1500ccエンジンを“3気筒”にした。1気筒当たり500ccの勘定になる。フィットは従来どおり1500cc4気筒エンジンだ。 3気筒と4気筒の差は何か? (1)3気筒は燃費が有利? 一般的に気筒数が増えるほど、振動が少なくなるので、高級車は6気筒や8気筒エンジンが採用されている。一方で、多気筒になれば、回転摩擦などが増えるので燃費が悪くなる。 4気筒と3気筒で、どれだけ燃費の差が出るか分からないが、理屈では3気筒の方が燃費の点は有利だ。しかし、4気筒でも摩擦などを軽減すれば高燃費エンジンができる。 (2)エンジンの振動が大きくなる 3気筒の不利な点は、回転時の振動が大きくなることだ。車内の騒音が増えることになる。 振動を打ち消すために『バランサー』という重りをエンジン内部に取り付ける。 ちなみに、現在の軽自動車は殆ど全て3気筒エンジンになっている。 (3)エンジンの製造コストが安くなる(部品点数が少なくなる) ヤリスのハイブリッドシステムはTHS-2の改良型を積むと思われるが、フィット4のi-MMDハイブリッドシステムと、どういう差があるか、これは実車が発売されてみないと分からない。 軽自動車では、ダントツに売れているホンダだが、登録車として久々にフィット4がトップに躍り出ることができるかどうか興味があるところだ。 YARISと、FIT4と、ノートe-Powerの三つ巴で、どういう闘いをし、どういう結果が出るか、来年2月になれば結果が分かる。 |
2019年10月14日(月)
世界の各地で開催されるオートショーに変化の兆し!
| 台風19号が関東地方・北陸・東北地方におおきな豪雨被害をもたらしました。被災地の皆さんにお見舞い申し上げます。 さて、世界各国で開催される自動車ショー(オートショー)ですが、アメリカのデトロイトや、ヨーロッパではフランクフルトなどの広大なメッセ会場で、世界の自動車メーカが新技術や新車を競って展示してきました。 そのショーの一つに、東京モーターショーがあり、10月24日からビックサイトで開催されます。 今年は、来年夏のオリンピックの準備等で、会場が一部変更になっています。 ドイツのフランクフルトメッセ会場は世界最大の広さを誇りますが、先般開催されたオートショーは例年の華やかなオートショーの姿から大きく変化したようです。 まず、出展社が従来の半分以下になったことです。 二番目は、中国メーカの台頭です。 三番目は、サプライヤー(部品など)の展示が増えたことです。サプライヤーは、アイシン、デンソー、積水化学、トヨタ紡績などの日本メーカが出展しました。 自動車メーカの出展が減り、部材メーカが増えるという様変わりです。 その要因は、自動車の変化によるメーカの対応が挙げられます。 ①インターネットやSNSなどの普及で新技術や新サービスの情報提供の場が展示会場から ネットに変わった事 メーカは自社のネットワイトやホームページで、詳しく情報が提供できるようになった。 メッセに出店するには、会場費や設営費やコンパニオンなど多額の費用が掛かる。 そのコストが出展を見合わせる要因の一つになっている。 情報発信の多様化や分散化の方向に流れている。 ②最重要市場が中国になったこと 上海モーターショーや、北京モーターショーには、今も各社出展する。 中国以外の各国のモーターショーに全て出展することを見直している。 ③自動車のライフサイクルの位置付けの変化 『CASE』と言われる[ Connected,Autonomous,Shared&Services,Electric]の流れがいよいよ 具体的な姿になってきてハードとしての自動車そのものの競争から違った内容の競争時代 に入ってきたこと。 そういう自動車の環境変化をトヨタ自動車の豊田章男社長が、「100年に一度の大変化」という表現で生き残りをかけて闘うと言っている。 トヨタですら従来の車造りを続けていれば、潰れるという警鐘を社内に発信し続けている。 そういう厳しい環境の下で、いよいよ10月24日~11月4日まで東京モーターショー2019 が開催される。 果たして、どのメーカがどういう展示をし、どのくらいの見物客が入るのか注目されている。 |
2019年8月21日(水)
トヨタ自動車がハイブリッドシステム(THS)を見直す?
| 『ハイブリッドはトヨタ』というくらい現在のハイブリッドシステム(THS)は完成度が高く、他メーカがこの20年間追いつけなかった。国内はもちろん世界中で、プリウスを筆頭にハイブリッド車はトヨタというブランドを確立してきた。 『THSはエンジンとモータの特性を最もうまく引き出す理想の方式で、これを上回ることは不可能ではないか』とまで言われてきた。 トヨタは効率化を図り、THSシステムを完成し、磨き上げ、さすがトヨタだと世界をうならせた。THSの基本システムは同じで、エンジン・2モーター(発電用モーターと走行用モーター)・遊星歯車・コンバーターの構成で、特徴は遊星歯車をうまく使った点にある。 ハイブリッドシステムを大きく分けると、シリーズ方式とパラレル方式とシリパラ方式に分けられる。THSはパラレル方式の範疇に入る。 しかし、世の中に絶対ということはない。必ず現状を上回るものが生まれてくる。 それを実証したのが、ホンダ アコードハイブリッドシステム i-MMD方式であり、その後にベストセラーになった日産 ノートe-Power である。 この二つのハイブリッド車は、今までなかったシリーズ方式を採用している。 今まで、シリーズ方式が製造されなかったのは、エンジンは発電に徹し、走行はモーターという構成のため、発電機と走行モーターと、リチュウムイオンバッテリーと大電力を制御するコンバーターが必要であり、コストが合わないという理由があった。 それをアコードとノートがクリアした。 アコードは値段が高いので、車造りにお金をかけることができる。 ノートe-Powerはコンパクトカーなので、コストが厳しいはず。どうクリアしたのか? エンジンを1000cc、3気筒にして安くし、車体は、ガソリン車のノートそのものを使い金型費や開発費を抑えた。その結果、200万円前後のコンパクトカーとして販売することに成功した。 モータで車を走らせるには、大きな馬力のモータがいる。それに見合う発電機(発電用モーター)も大きな発電量が要求される。 日産は、EV(電気自動車)のリーフを販売済みのため、モータで車を走らせるノウハウは他社より多く持っていたので、コストが見通せた。 ホンダはコストがかかる分をまず高級車、アコードから展開した。 アコードi-MMDがトヨタのカムリハイブリッドTHSより、燃費が良く、走りが良いことを実証した。 ホンダの課題は、この優れたi-MMD方式を如何に製造コストを下げ、コンパクトカークラスに商品化できるかであった。 その解はインサイトハイブリッドi-MMDだった。1500ccエンジンを積み、発電機を回し、バッテリーに充電し、走行用モータを回して走る車。 しかし、インサイトは300万円前後と高かく、アメリカ向けのため車体が大きすぎる。 そこで、さらに発電機(発電モーター)と走行モータのコストダウンを図った。 その詳しい内容は、以前の記事(8/6)を読んで頂きたい。 2年毎に東京で開催される自動車ショーは、今年10月20日から始まる。 そこで新型フィット4が発表されると聞いている。このフィット4には新ハイブリッドシステムi-MMDを搭載する。 やっと、何年もかかって、Toyota ハイブリッドシステムTHSを走りの面でも、燃費の良さも上回ったと言われている。 さて、そうなるとToyotaは安穏としていられない。 そこで、Toyotaがどう出るかを注目していたところ、日経xTECHで、下記のToyotaの記事を見つけた。 トヨタ、現行ハイブリッド以外も検討 HEV普及推進 トヨタ自動車が、ハイブリッド方式の拡大を検討していることが日経 xTECHと日経Automotiveの取材で分かった。これまで20年以上にわたり量産効果を重視して現行方式の"一本やり”と映る開発方針だったが、今後は転換する。 国や地域の需要に合わせて現行方式以外を用意して、世界でハイブリッド車(HEV)の普及を推し進める。 1997年に「プリウス」を量産して以来、主軸を担っているのが「THS(トヨタ・ハイブリッド・システム)」である。トヨタパワートレーンカンパニーPresidentの岸宏尚氏は、「(ハイブリッド方式として)THSに固執していない。スタートラインの技術と考えている」と話し、「(エンジンを発電専用に活用する)シリーズ方式や48V対応の簡易式などを含めて幅広く検討している」と明かした。 この記事の内容は、今までTHSシステムが最良方式だったが、(他社の方式がTHSを上回るようになったので)、新しい方式も開発するというアナウンスだ。 THSにこだわって、技術の変わり目を間違うと、強みが逆に弱みになり、変化に対応できなくなる。即ち、競争に負ける。 その辺のToyotaの読み、変わり身は流石である。 多分、今後、THS方式から、シリーズ方式に切り替えてくるはずだ。 あらゆる商品は性能がいいだけでは通じない。 お客さんが欲しいという要求に合わせなければならない。 それは、性能や値段がお客さんの納得いく範疇でなければ売れない。 シリーズ方式は性能は良いことが分かったが、コストがべらぼうに高かった。 そのコストを下げる取り組みに成功したということだ。 THSは今までこれを上回るシステムが現れない理想のシステムと言われてきた。 今まではそれで通用してきた。 しかし、シリーズ方式がコストダウンに成功し、THSと同じコストで生産できるようになった今、走行性能、燃費で上回るシリーズ方式に軍配が上がる。 熾烈なハイブリッド競争が今後展開される。 |
2019年8月6日(火)
Hondaはなぜ、HVシステムを一本化したのか?(改)
| 10月24日から11月4日まで東京で2年に一度、モーターショーが開催されます。 今年は、EVやハイブリッドなど目玉がたくさんあるようですが、6年ぶりにフルモデルチェンジする四代目のHonda FIT4に注目が集まっています。 新型FIT(FIT4)は、ガソリン車は、通常の1300cc車と、1500cc車と、1リッターターボエンジン車で、少容量ながらトルクが大きくて、走りがよいと言われています。しかも、省燃費で、1リッターで30kmぐらい走るようです。自動車税も、1000cc以下で登録されますので安くなります。この1000ccターボエンジンを搭載したシビックはすでに欧州で販売され好評だそうですが、日本では初めてとなります。 今乗っている車は、FIT3 HVで、発売と同時に買ったのですが、ダイレクトクラッチ(i-DCD)を初めて使ったもので、i-DCDと、モーターと、エンジンの制御プログラムの完成度が不十分で、5回もリコールを受けました。期待を裏切られた思いでした。 その後、次第に制御ソフトやi-DCDメカニズムの改良が行なわれ、現在販売されているFIT3は大変スムーズな感じに仕上がり良くなっています。発売時にこの状態であれば、FIT3HVは相当ヒットしたと思いますが、一度ケチがつくと販売が伸びないという 悪い事例の一つになりました。 さて、注目は、今後のHondaのハイブリッド戦略です。 将来のEV化やCASEなど、車の先端技術に対応できるよう、『Hondaは、全車のハイブリッドシステムをこのi-MMD方式1本化する』という発表がありました。 現在は3つの方式を採用して、車種やランクにより使い分けてきました。 ・小型車;i-DCDシステム ・中型車;i-MMDシステム ・大型車;SH-AWDシステム 一方、Toyotaは、THS方式のみで、プリウスから各車種に展開しています。 表題で、『試されるHondaの本気度!』と書いたのは、このi-MMDをどう展開するかです。i-MMDシステムは、アコードに初めて搭載し、その走行特性の良さと、省燃費性能はトヨタ カムリ HVを大きく上回りました。 トヨタのTHS方式は、2モータ方式で、駆動モータと発電モータを搭載し、『エンジンとモータの持つ特性の良いとこ取りをしたシステムで、パラレル方式で、これ以上のハイブリッドシステムを造るのは不可能』とまで言われてきました。 世界中で認められHVはToyota THSだったのです。 そこに風穴を開けたのが、アコードに採用したi-MMD方式です。 しかし、アコードはアメリカ向けが中心の車であり、大型で日本のユーザ(市場)にはあまり人気がなく、値段も高く、一部のユーザにしか売れない車でしたので、この優れた走行・燃費性能を持ちながら、今まで一部のユーザ以外には売れず、あまり評判にもなりませんでした。 その間、Hondaは、現在の1モータのi-DCDシステムを使ったHVを小型車に展開してきました。 日産ノートが、e-Powerで2モータ方式のHVを発売し、価格的にも安く、コンパクトカーで、大ヒットし、ベストセラーカーになりました。 そのわけは、トヨタハイブリッドTHSは「燃費は一番だ!」と言われてきましたが、ドライビングの楽しさに欠ける、要は加速が悪いという評判で『おっさん車』でした。 最近は改良されて、加速もよくなっています。 アコードに採用したi-MMD方式は、日産 ノートe-Powerと同様、2モーター方式で、通常走行は駆動モーターで行い、エンジンは発電に徹するシリーズ方式ハイブリッドです。 アコードと、ノートe-Powerの違いは、エンジン容量やパワーや車格が違いますが、アコードが優れている点は高速道路での燃費性能です。 以前にも書きましたが、例えば、時速100kmで高速道路を走行中はエンジン回転数は2000回転前後で、ほとんど一定です。こういう状態では、エンジンが直接、車軸を駆動する方が効率がいいのです。 ノートe-Powerは高速走行中も、エンジン⇒発電モータ⇒バッテリー⇒駆動モータというつながりで走行しますので、高速走行では燃費が悪くなります。 総合効率は各要素の効率の掛け算になるからです。 (補足) 総合効率=エンジン効率×発電モータ効率×駆動モーター効率 (例) e-Power方式の場合 0.4×0.9×0.9=0.324 アコードのiMMDの場合 0.4=0.4 e-Powerの場合、エンジン効率が下がってしまうことになります。 高速道路では、ガソリン車より燃費が悪くなるということです。 今年11月発売?の新型FIT4 HVは、アコードに搭載したi-MMD方式を小型車向けにサイズダウンした新設計のi-MMDを搭載します。(Honda 八郷社長が公表) ここで、メーカーの課題はコストアップをどう吸収するか、競争力ある価格で販売しても儲けることができるかです。 性能は良いことは分かった。しかし赤字では企業経営は成り立ちません。 Hondaのコストダウン対策は? 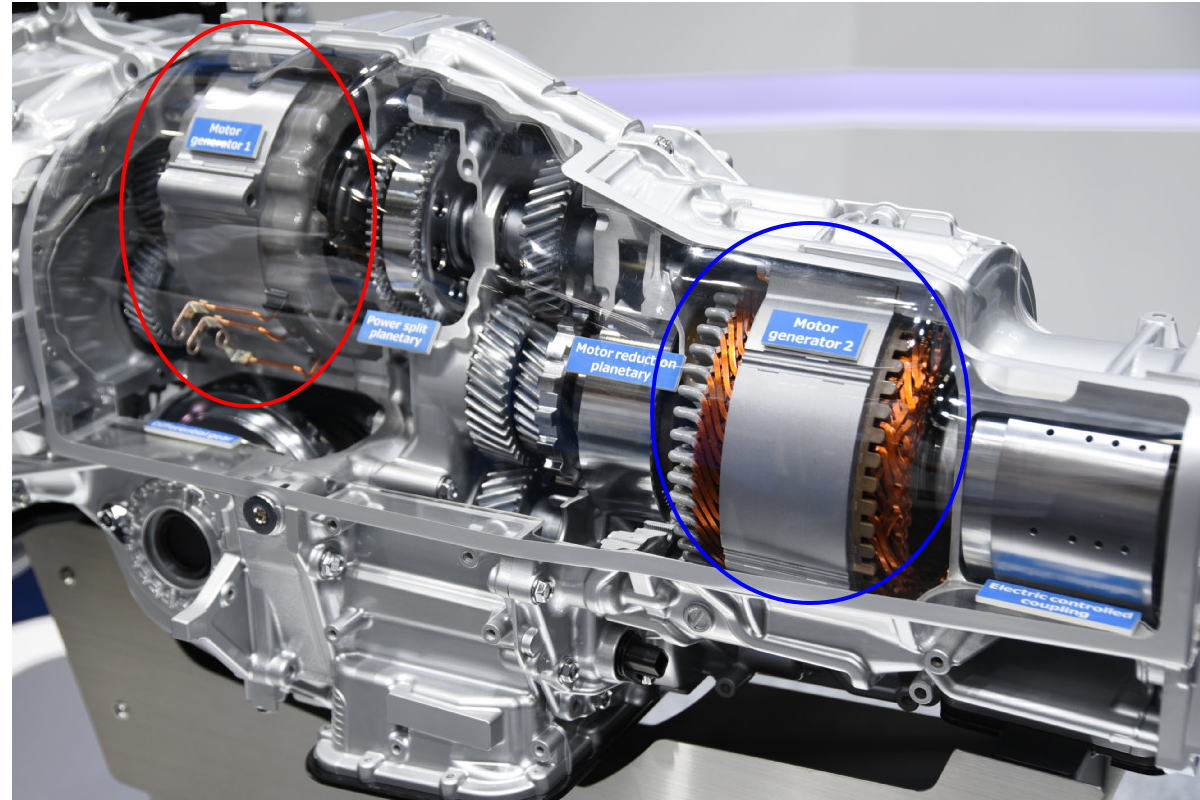 左の写真は、トヨタTHSの最新システムのカットモデルです。 左の写真は、トヨタTHSの最新システムのカットモデルです。左の赤線で囲った部分が駆動モーター。 右の青線で囲った部分が発電モーター。 見れば分かるとおり鉄芯(コア)の形状や寸法が違います。このことは、2つのモーターを量産する場合、金型が別々に必要になり、組み立ても別々になります。車種の違いでモーター出力が変わると、さらに何種類か必要になります。要は部材の共用化、共通化という点です。 ところが今回発表したHonda i-MMDは、駆動モーターと発電モーターは同じ金型で、出力の違いは鉄芯(コア)の積み厚で対応する構造です。 これなら、磁性鋼板という固い鉄板を打ち抜く金型は1つでよいことになります。 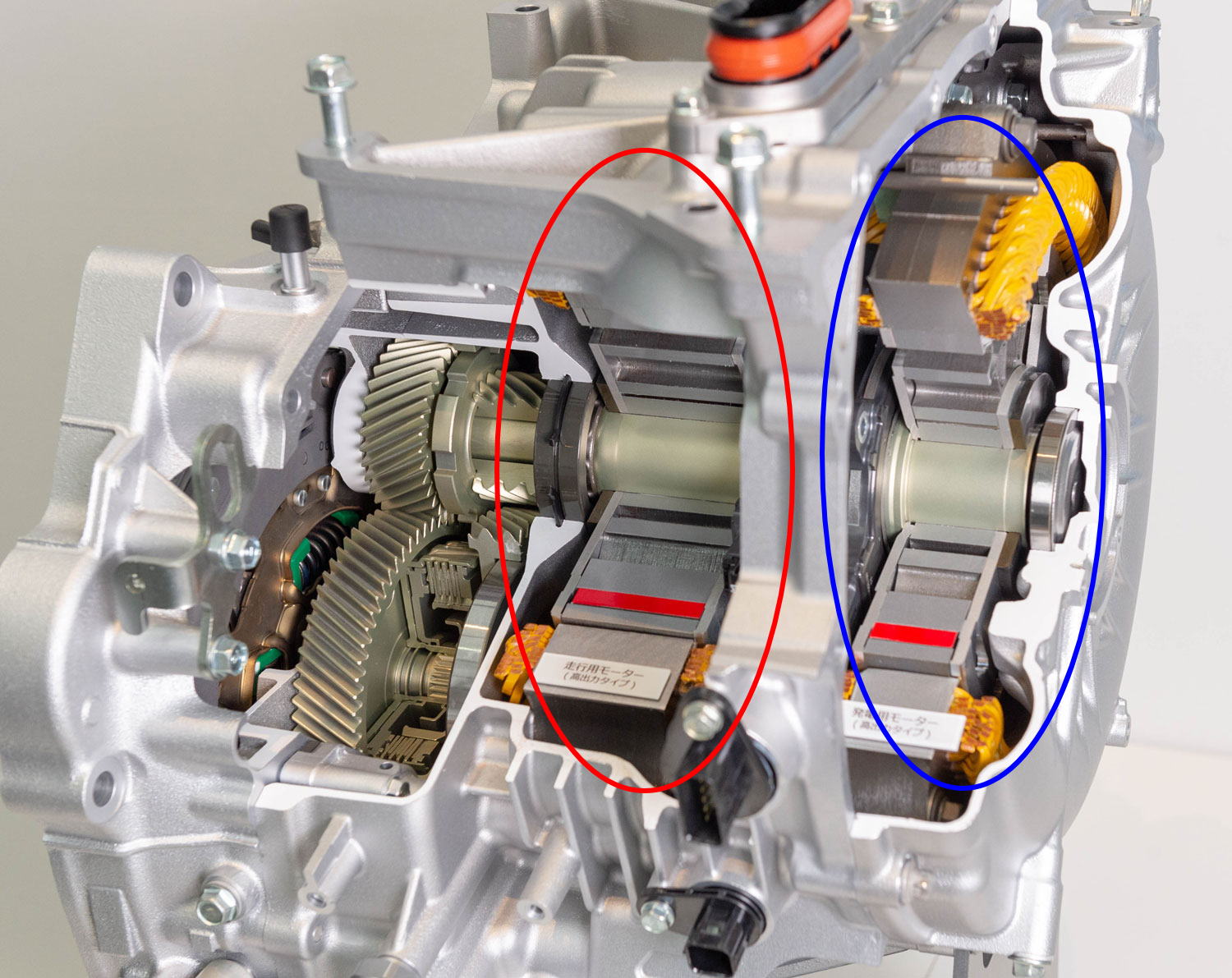 左の写真の左側の赤線部が駆動モーターで、右側の青線部が発電モーターです。 コアの外観は同じです。 出力の大きさに応じて鉄芯の積厚を変えれば対応できます。 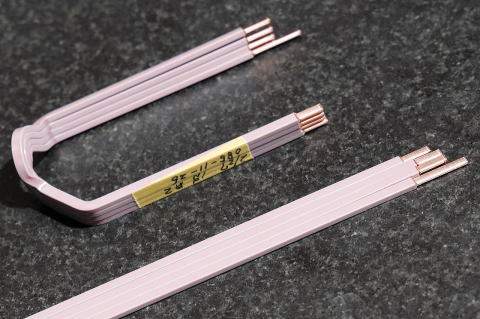 左の写真のように、今回のFIT4モーターには、アコードのモーターに使った丸銅線ではなく、断面が四角の平角導線を使います。 その巻き線の拡大写真を表示します。 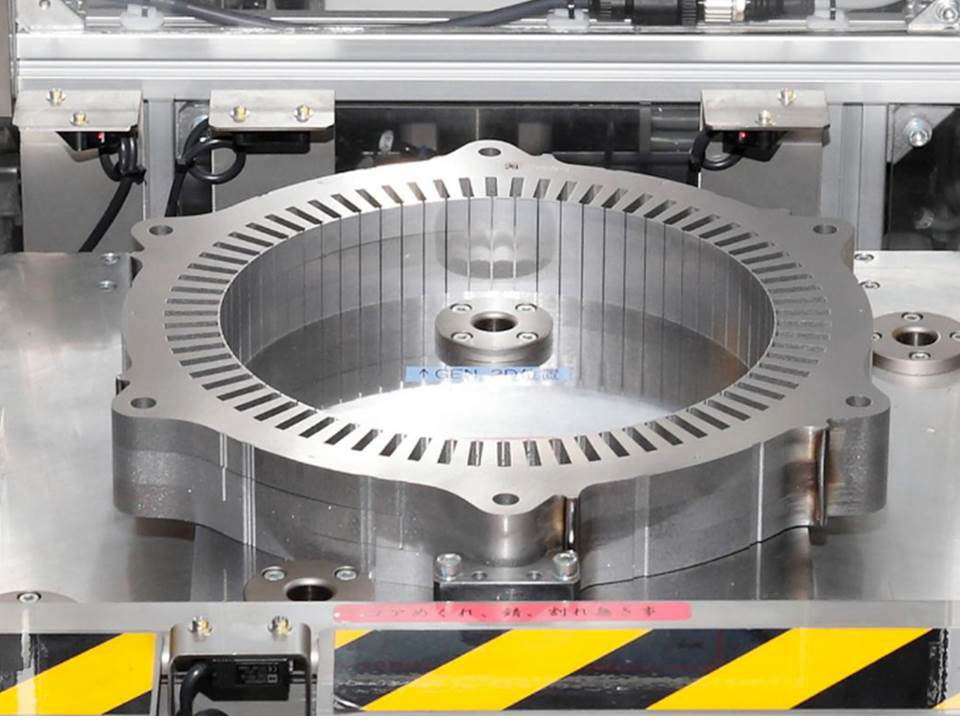 これにより、コアーのスリットに隙間なく差し込むことができるため、モータ効率が改善されます。 同じ出力なら小型化できます。  うどんのような形をした平角銅線が4本束ねてU字形にロボットで折り曲げて成形し、スリットに挿入します。 ここで難しいのは、角銅線の表面は絶縁塗料でコーティングされています ので、角銅線を曲げる際に無理をすると表面の絶縁塗装が割れたり、剥げます。 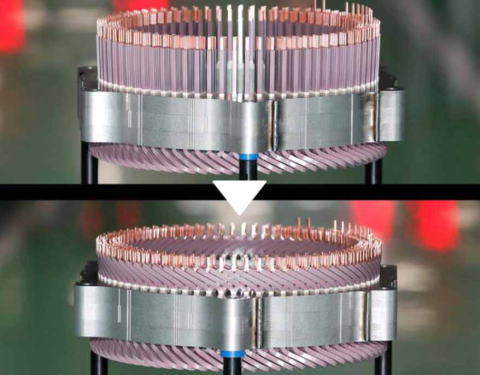 さらに、片側の角銅線の端は、機械で成形後、一本ずらして溶接します。つながったコイルになるのです。 この溶接の熱により絶縁塗料が溶けると、ショートの原因になります。 銅線の成形と溶接は微妙な作業で、その信頼性も非常に大切です。  この難しい課題を克服し、初めて量産ラインで製造ができる状況に追い込み、成功したということです。 従来のモーターの常識だったコイルの概念を覆した新モーターの出現です。 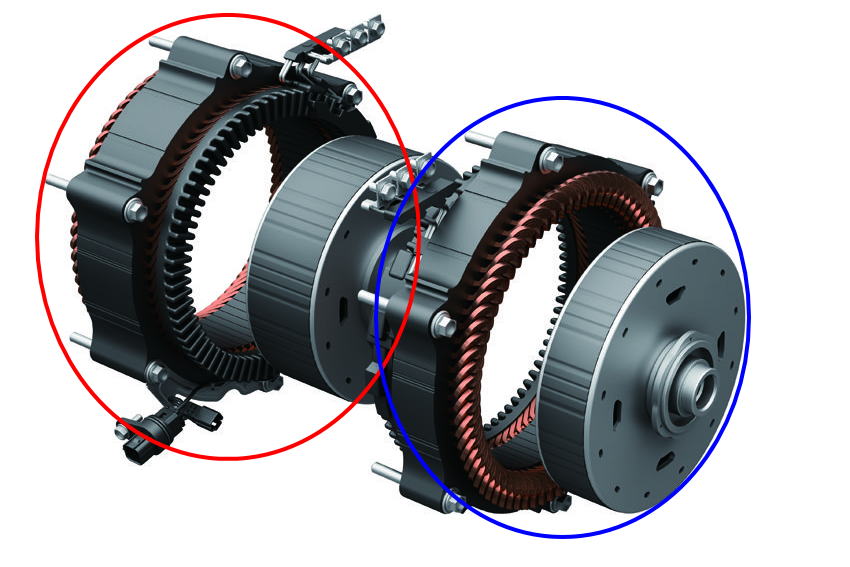 左の写真は、左側が駆動用モータの固定子と回転子、右側が発電用モータの固定子と回転子です。 駆動用モータの方がコアの積厚は厚くなっています。 コアの形状は同じです。 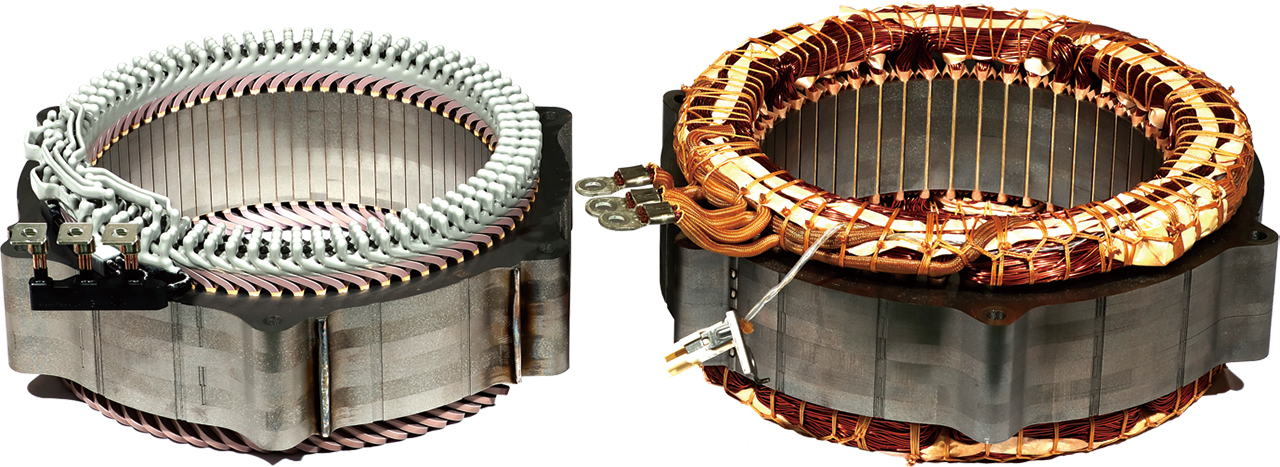 右側がアコードに搭載した従来型の丸銅線を巻いた固定子コアの状態です。丸銅線をコイルに巻き上げた状態です。 右側がアコードに搭載した従来型の丸銅線を巻いた固定子コアの状態です。丸銅線をコイルに巻き上げた状態です。これが今までのモーターでした。 左側は、今回採用の平角銅線をコアに差し込んで成形したものです。 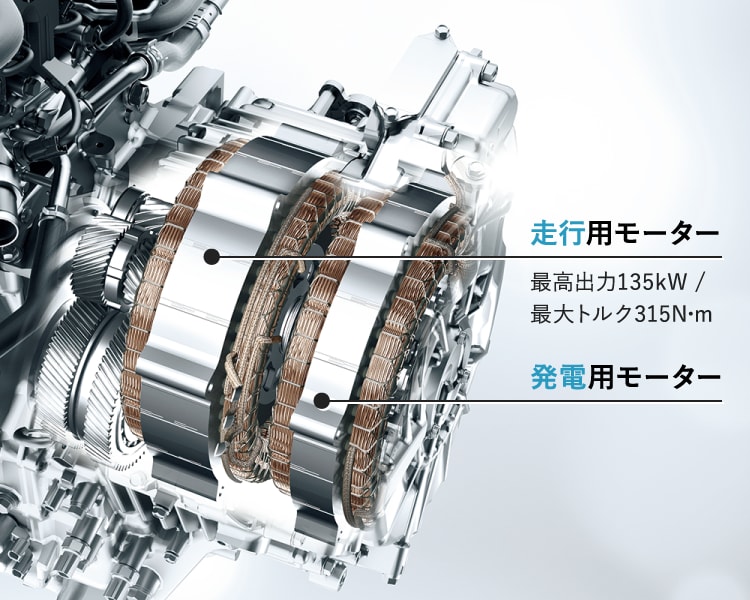 左はアコードの駆動モータと発電モータの写真です。 左はアコードの駆動モータと発電モータの写真です。上のカットモデルの写真と見比べると、新モータは非常に合理化され、量産しやすい構造に改良されていることが分かります。 こういう開発があって、コストダウンができ、量産と相まって、200万円前後の車にiMMDが搭載できるようになったのです。 この合理化された新ハイブリッドシステムi-MMDに一本化して、他の2つのHVシステムはやめるとHonda 八郷社長がアナウンスしました。 『これなら行ける。これなら戦える。これならコストもクリアできる。』と確信を得たのでしょう。 i-MMD方式は、『ちょい替え』すれば、今後のEVへの展開が容易に出来ます。 i-MMD車のエンジンと発電モーターを取り外し、駆動モーターをそのまま使い、リチュウムイオン電池の容量を大きくすればEVになります。 i-MMDは、将来のPHV(プラグインHV)やEVへすぐ対応ができるのです。 ハイブリッド ⇒ プラグインハイブリッド ⇒ EV HV、PHV、EVの搭載する駆動モーターは同じものを転用でき、非常に効率的な生産が可能になります。そのために今回の合理化されたモーターの役割が重要なのです。 そういう読みで、他の2方式のHVはやめて、i-MMDに一本化を決めたはずです。 新型のFIT4 HVは1リッターで何キロ走るでしょう? 今、乗っているFIT3 i-DCDハイブリッドは、燃費記録帳を見ると、平均燃費が21.2km/リッター(満タン-満タン法)になっています。まずまずの燃費です。  先日、和歌山の往復270km走った高速道と一般道の燃費は、最大で30.1km/リッターを示しました。(写真参照) FIT4は少なくとも、カタログ値で、40km/リッターは優に超すでしょう。 実走行では、30km~35Kmというところでしょうか! もしこれが実現できれば、すごい進化です。 低燃費&加速性能&静粛性の3拍子が揃えば、ベストセラー間違いなしです。 さて、i-MMDに対してToyota THSは、今後どのように進化するか?楽しみです。 日産ノート e-Powerの高速道路燃費の改善にどう対応するか?も見ものです。 |
2019年6月27日(金)
将来の自動車はEVになる。そのための要素技術は?
| EVは今までの自動車と同じで、自動車の動力源をエンジンからモータに置き換えただけのこと。しかし、EVは従来のエンジン自動車にはない優れた特性を持っています。 それは、エンジンの特性と、モータの特性の違いです。 モータは、発生するトルクが自動車を走らせるに必要なトルク特性によく似た特性を有するからです。 エンジンは、回転数が低い時はトルクが小さく、回転数の上昇と共にトルクが増える特性を有します。車を力強く走らせるには、大きなトルクが必要になります。 そこで、エンジンの回転数とトルクを変換する装置(変速機)が必要になります。車が走り出す際は、変速機の歯車のギヤー比を大きくしてエンジン回転数を上げ、車軸の回転数を下げることで、トルクを大きくしています。ギアーをマニュアルでチェンジする操作が必要でした。昔は運転免許を取る際に苦労した点です。 変速機をローギアに入れて、エンジンを吹かしながら、ゆっくりクラッチを操作して接続する。マニュアル車は、この変速操作が不可欠で、これが難しく、クラッチをゆっくりつながないと、急につなげばエンストを起こしました。 特に、信号待ちで信号が青色に変わった時に、慣れないドライバーは慌ててエンストし、後ろの車にクラックションを鳴らされたものでした。急ぐとエンジンがうまくかからないことがあり、一層モタモタすることがありました。そういう経験をよくしたものですが、今は全くそういう場面は見られません。 現在は、ほとんどの車が自動変速(オートマティック)に変わりました。大きく分けて2つの方式があり、ギアーを組み合わせる段数で、3速、4速、5速、さらに高級車などは7速変速など、ギアー式自動変速機があります。もう一つは金属製ベルトを二つのプーリにかけて、互いのプーリ―の径を変えることで変速するCVT方式があります。 最近の軽自動車や小型車は、CVT方式が多くなりました。CVTは連続して変速できる点が優れていますが、ベルトを強く引っ張らないと滑りますので、その分、少しロスがあります。ギヤーが少ないので小型・軽量にできるメリットがあります。 このようにエンジンを車の動力として使用するには、必ず回転数ートルク変換装置が必要です。この変速装置は歯車がたくさん必要で車重を増加させていました。 これが、EVになると、上の赤字(下線部)のように、車が走行する際に必要なトルクと、モータの発生するトルク特性が良く似ているので、トルク変換するための装置は不要になります。 EV車には、普通、3相交流同期モーターが使われています。これはモータの電力利用効率が高いからです。車を加速し速度を上げるためには、モータに加える交流電圧や周波数を制御しながらスムーズな変速を行うことができます。 (注)交流同期モーター;周波数の変化に同期して回転数が変わるモーター モータ出力は、加える交流電圧で変化する 固定子側にコイルを巻き、回転子は永久磁石を埋め込んで造ります。 トヨタのプリウス等のHV車のカタログを見ると、『電気的CVT』と表示している。 これはベルトを使った変速機ではなく、ギア比は固定で、モータの電圧と周波数を変化させることで目的を達している。これがVVVFという制御方式です。 (注)VVVF;Variable Voltage Variable Frequency(可変電圧・可変周波数制御) モータには、さらに優れている点があります。 ①トルク応答がエンジンよりも早い。 ⇒電気制御なので、即時に応答する。 ②モータを分散配置できる。⇒各車輪毎にモータを組み込める。 ③発生トルクが正確に把握できる。 ⇒モータが発生する力は、F=BiLで決まる。 ④回転による振動や騒音がエンジンに比べ極端に低い⇒車内が静か これらの優れた特性を生かせば、EVならではの付加価値を実現できる。 モータ駆動だからできる動力制御によりタイヤのスリップを抑えられる。これにより同じ運動性能を維持しながら、タイヤの幅を小さくし燃費を改善できる。 自動車の動力源が、エンジンからモータへと置き換わるのが大きな流れになる。 ただし、今のEVがそのまま普及するわけではない。 その理由の一つは、いずれ電気エネルギーの供給方法が問題になることです。 EVは、車体に搭載したリチュウムイオン2次電池にエネルギーを蓄えているわけですが、現状では充電に時間がかります。高速充電設備を利用しても30分以上かかります。しかも、電池に蓄えることができるエネルギーは限られています。ガソリン車がタンクに蓄えられるエネルギー量に比べると、EVのリチュウムイオン2次電池に蓄えられるエネルギー量は桁違いに小さいのです。だから、ドライバーは航続可能な距離を気にしながら運転しなければなりません。 将来のEVは、電車のようにインフラからエネルギー供給を受けられれば、電池切れの心配がなくなります。 信号待ちや料金ゲートなどで停車した時に充電する「ちょこちょこ充電」や、道路に設けられた充電設備から走行中に少しずつエネルギー供給を受ける「だらだら給電」などが可能になれば、ドライバーは航続距離を心配しないで走れます。 しかも、1台毎に大きなエネルギーを持ち運ばないで済むわけです。 これらが実現すると、モビリティや社会の新しい将来像が見えてきます。 そこで、インフラからエネルギーを供給する仕組みを実現する上で欠かせないのが、短時間で充電ができる「キャパシタ」の新技術、および電力系統と自動車を無線で接続する「ワイヤレス(給電)」の新技術です。 必ず、将来、そういう新技術を使った新世代のEVが開発され走り回ると思います。 |
2019年5月28日(火)
駆動トルクと、負荷と出力の関係は?(追記;6/8)
| 電車が走る状況を見ると、いくつかの走行モードがあることが分かる。 電車の先頭車両で、運転手のレバー(ノッチ)操作を眺めてみよう。 まずブレーキ・ノッチを前に倒す操作すると、空気弁が開き、『シューッ』と空気が抜ける音がする。ブレーキが解除される。 その後、駆動レバー(ノッチ)を手前に引くと、電車はゆっくり走り出す。車のアクセルを踏んだ状態と同じ。その時、運転席の計器盤の電流計を見ると、針はゼロアンペア (A)から100A~150A程度までビュンと振れる。 この電流計は車両の型式にもよるが、機械式針表示のものや、デジタル表示のものなどいろんな形式がある。学研都市線の車両は最大電流を150Aに設定している。 150A以上は振れない。環状線や東海道線では200A程度まで振れる。 電車が速度を上げるとともに、針は緩やかに下がって来る。電車が時速90Km~100Km程度でまっすぐな平坦線路を走ると、運転手はノッチを元に戻す。すると電流計はゼロに戻る。乗っていると、加速が無くなり、一瞬、体が前に揺れる。 電車は惰力で殆ど同じ速度を維持して走り続ける。これは電車は車輪とレールが鋼鉄で造られているので、摩擦が少ないからだ。だから摩擦で生じる負荷が少ない。 走行中は空気抵抗や、その他の何やかやの負荷(ロス)があるため、直線平たん線路でも、次第にスピードは落ちてくるが、自動車に比べると、電車は消費電力がゼロで惰性だけで長い間走り続ける事ができる。 カーブに差し掛かると、運転手が制限速度以下になるようにブレーキレバー(ノッチ)を操作すると、再び電流計が振れる。これはモータを発電機に動作を切り替え、電車の走行中の運動エネルギーを電力に回生発電し、電流を架線に戻している。 メータは、加速時と同じ150Aを示しても、電流の流れる方向が逆向きになっている。 即ち、電流の方向は? 加速時;トロリー線→パンタグラフ→コントローラー→モータ 減速時;モータ(発電機)→コントローラー→パンタグラフ→トロリー線 駅が近づくと、さらにブレーキを強くかけるようノッチ操作して回生発電を強くする。 走行方向と反対向きの負荷がかかる。その分、回生発電して電気を架線に戻す。 最近の電車はこのように走り出し、一定の速度に達するまでは電力を消費するが、一定速度で走行中は殆ど惰性で走り続けているので、電気は食わない。 しかも、駅が近づき停車する寸前まで回生発電して電気を架線に戻す。 運転席のメータには、大きな速度計と電流計が装備されている。それ以外に、電圧計が付いている。電圧計は、架線電圧を表示し、通常は1500V前後を示している。 走り出す際に大電流が流れるので、1500V→1400V→1300Vぐらいまで下がることもある。これは、トロリー線に大電流が流れ、電圧降下するためである。 (モータにかかる電圧)=(トロリー線電圧)ー((電流)×(トロリー線の抵抗)) トロリー線の抵抗値は一定だが、電流が大きく流れると、電圧降下が大きくなる。 逆にブレーキをかける際は、1500V→1600V→1700V近くまで上がる。電車や地下鉄は、1500Vが基準電圧だから、それを上回る時は架線に電気を戻している(回生している)ことになる。 沢山の車両が数分、十数分間隔で線路上を走るので、走ったり止まったりの動作がダイヤに従い頻繁に行われているため、架線の電流は電車に流れたり、戻されたりして平均化される。 全電車が一斉にヨーイ・ドンで走り出すとすれば、トロリー線には大電流が流れるので、トロリー線は焼き切れる。それを防ぐため、トロリー線とは別に太い撚り線をトロリー線の横に沿わして張っている。この太い電線からトロリー線に、ところどころ結線して給電している。一度、トロリー線付近を見上げて頂ければわかる。 幸い、走り出す電車があれば、ブレーキを利かして止まる電車があり、トータルでバランスが保たれる。 もちろん、電車を運行するには、変電所から電力を供給する量の方が大きいのは当然である。何十トンもある重い電車を時速何十kmと言う速さで動かすためには、大きな運動エネルギーが必要であるからだ。 しかし、回生発電する電力量も運動エネルギーが大きい分、たくさん発電できることにもなる。回生できる運動エネルギーは約40%近くあるのではないかと思われる。 昔の電車は、回生発電システムがなかったので、ブレーキをかけて運動エネルギーを熱エネルギーとして空気中に放散していた。実にもったいない状態であった。 これは電車の場合の話。 さて、自動車の場合はどうか? 電車のように架線はなく、一台・一台が独立しているので、全体で負荷(運動エネルギー)を平準化し、バランスさせる事は出来ない。 それならば、一台一台毎に加速・減速時の運動エネルギーを平均化させる方法を考えれば良い。こうして産まれたのがハイブリッド車(HV)やEVだ。 自動車が走り出すには、1トン以上もある重い車体を動かさなければならない。 人が一人で押しても動かない。二人で押してやっと少し動く程度だ。人間の力は一人当たりで言えば、1/7馬力しかない。だから2人なら2/7馬力だ。でもこの程度なら、車はやっと少し動いたという話で、ドンドン速く動かすことは不可能だ。少なくとも数十馬力の力が必要になる。たとえば20人の人が太い綱のような紐を引っ張れば速く動かすことができるが、精々駆け足程度。時速、数10kmとか100kmのような速さで引っ張り続けることは不可能だ。 だからガソリンエンジンやジーゼルエンジンの駆動力に頼って、車は動いている。 さて、ガソリンやジーゼルエンジンに注目すると、エンジンは回転数が上がると共に馬力も増える。それだけ多くのガソリンや軽油を消費する。 車が走るには馬力も大切だが、駆動トルクという車軸を回転させる力(回転力)が大きくないと動かない。エンジンは回転数が低い時は、駆動トルクが小さい欠点がある。 そこで、この欠点を補うため、変速機を積んで、走り出す際はギアー比率を大きくして、駆動トルクを増大させ、エンジン回転数を上げて車軸がゆっくり回るようにしている。 この変速機は昔はマニュアルだったが、今はオートマチックに代わっている。最近はギアー変速ではなく、金属ベルトで変速するCVTと言う方式に代わって来た。 いずれにしても、この変速機は重く、機械的なエネルギーロスがあり、車の燃費を悪くしている。 HVやEV車は駆動モータを積んでいる。 リチュウムイオンバッテリーとモータをつないで、モータを回転させ、それで車軸を駆動する。モータはエンジンと違い、回転を始める時、一番大きなトルクを発生させることができる。車の駆動用に使うには、もってこいの特性を発揮する機械である。 電車は架線から大きな電流を流せたが、車のバッテリーはリチュウムイオン電池と言えども、流せる電流の値には限界がある。電池は大電流を流せば寿命が極端に短くなる。だから取り出せる電流は電池の寿命との兼ね合いで決まる。 リチュウムイオン電池は、現在、実用化された二次電池の中で最も大きな電力容量を持ち、大電流が取り出せる優れものだが、まだまだ改善すべき点が沢山ある。 それらが解決すると、HVから全面的にEVに移行することになるだろう。 電車が回生発電で電気を架線に戻して、他の電車が発車する際の電流として使われることを前に述べたが、HVも同様に、発車時には大電流が電池から流れ出すので、電池に貯めていた電気が急速に減る。電池の蓄電量がある値以下になると、エンジンが始動し、エンジンに直結した発電機が回り、発電した電気を電池に送り貯める。 駆動用モータは大きな駆動力を発生することができるので、逆にブレーキを踏んだ際は大電力の発電機として動作し、発電した電気は電池に貯める。 このように駆動と発電を繰り返しながら、エネルギーを電池に貯め、電池にダムのような働きをさせ、車の走行時の負荷の変動を吸収して、ガソリンエンジンをできるだけ回さないで、または一番エンジンの燃料効率が良い回転数で一定に近い回転数で回し発電してトータルの燃料消費を最小にすることが車の燃費を改善する。 モータは特性上、駆動トルクが非常に大きいという話をしたが、モータの回転数が変わると、常に同じトルクが発生している訳ではない。また、回転中に、ある回転角でトルクが強い時と弱い時が交互に現れ、トルクを測定して見ると、トルクが波を打っている。これをトルクリップルと呼ぶが、モータの種類や、巻線方法や、極数や、磁石や、回転子の構造等々の諸条件により、いろいろな現れ方をする。 理想的には常に一定のトルクで平坦に発生することだが、そうはうまくゆかない。 このトルクリップルが大きく波を打つと、車に積んだ際にスムーズな走行できなかったり、モータの回転音が大きくなったりする不具合が生じる事がある。 そもそもエンジンはガソリンエンジンであれ、ジーゼルエンジンであれ、ロータリーエンジン以外は全てピストンが上下運動し、『吸入→圧縮→爆発→排気』と言う4行程をクランク軸が2回転する間に繰り返す。4サイクルエンジンとも言う。 トルクが発生するのは、爆発行程だけで、軸の1/4回転の時だけであり、3/4はトルクの発生はない。しかも、圧縮行程はピストンに負荷がかかるので、トルクは負の状態にある。だからエンジンは回転させると大きな振動が生じる。また機械的にピストンの上下運動をクランク軸で回転運動に変えるので、重い振り子のような部品が回転することになる。エンジンは元々、このような振動を生じる要素を持った機械と言える。 それを気筒数を2気筒、3気筒、4気筒、6気筒など増やしたり、水平対向させて振動をキャンセルさせたり、バランサーで振動をキャンセルさせたり、エンジンを載せるゴム台に振動吸収ダンパーを取り付ける等々、各社工夫して振動を軽減している。 さらに、エンジンの爆発工程で発生する爆発音は非常に大きな音なので、マフラーを通すことで、高い耳をつんざくような音を低減し、排気音を静かにする工夫をしている。 その点、モータは僅かなトルクリップルはあるが、回転子は円筒状で、重量バランスがよく、基本的にとても静かでなめらかで振動が少ない。 だからEVは静かで、HVもエンジンが回れば少し音がするが、EV走行中は静かな状況である。 ガソリンやジーゼル車はエンジンが毎分、数百回転のアイドリング時の低回転数から数千回転の高回転数まで広い範囲の回転をする。 トルクリップルによる振動や、クランクシャフトやピストンの上下振動や、吸排気のバルブの振動など沢山の可動エンジン部品から生じる騒音や振動を小さく抑え込むために、長い間のエンジン技術のノウハウを積み重ね、車は次第に静かで快適な状態になってきた。 (注)トルクリップル;トルクが脈を打つ現象 EVやHVになれば、それをはるかに凌駕する静かで、振動が少ない車が生まれる。 HVはエンジンが時々かかり発電するが、この充電時のエンジン回転数は車を走行させるための駆動エンジンとは違い、エンジンの回転数は一定でよい。そうすればエンジンの振動や騒音対策が大幅にやりやすくなる。 今後、車内騒音は一気に今までにない静かな車に仕上がってゆくはずだ。 (追記) モータが回る原理や、発生する力や、トルクの関係は以前に書いた。 では、モータやエンジンの出力(馬力)はどうなっているのだろうか? もう一度、それらの関係について整理する。 モータが回る原理は、『フレミングの左手の法則』による。 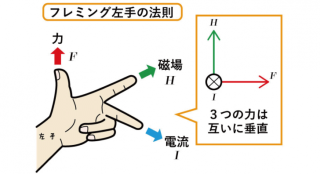 磁石を置くと、N極からS極に向かって磁力線が出ている。(もちろん、目には見えないし、そういうふうに考えるという話) 磁石を置くと、N極からS極に向かって磁力線が出ている。(もちろん、目には見えないし、そういうふうに考えるという話)人差し指の方向に磁力線が出ているとすると、中指の方向に電線(コイル)を置いて電流を流すと、親指の方向に電線(コイル)が力を受ける。これを応用したのがモータである。 逆に発電機は、『フレミングの右手の法則』による。 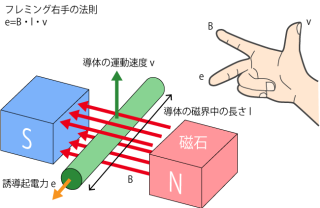 右の図は『右手の法則』を示す。 磁石のN極とS極を対向させると、N極からS極に向かい磁力線が出ている。 その間に電線(コイル)を置き、コイルを磁力線を切る方向(直角に切る方向)に動かすと、電線に起電力が生じる。 これが発電機の原理になる。 中指の電流の方向がモータと発電機では逆になっている。 電流から力を発生させるモータと、力を加えて電流を発生させる動作は、真逆の現象であることが分かる。 モータに話を戻す。 ■モータの磁界内の電線(コイル)が受ける力は、 力=(磁界の強さ;B)×(電流の大きさ;i)×(磁界を切るコイルの長さ;L) ×(コイルの巻き数;n)) F=B×i× L×n ■モータ軸の回転力(トルク)の大きさは? トルク=(コイルが受ける力;F)×(軸の中心からコイルまでの距離;半径;R) T=F×R ■モータの出力は? 出力=(トルク;T)×(回転数;N) P=T×N だから、出力;Pは、 P=BiLnRN となる。 交流同期モータの回転数は? N=120/極数×周波数 たとえば、4極のモータに60Hzの3相交流を加えると、毎分回転数は、 N=120÷4×60=1800回転/分 モータはいろんな種類があるが、基本原理は上記のとおりになる。 HVやEVに搭載する駆動モータは、数十KWという大きな出力を発生させる。 大きな出力を発生させるためには、上記の各項目の値を大きくすればいい。 P=BiLnRN の式から、 ①磁石を強くする →B を大に 形状、コスト ②電流を大きくする →i を大に 太いコイル、バッテリ ③磁界を切るコイルを長くする →L を大に 形状、コスト ④巻き数を増やす →n を大に 形状、コスト ⑤回転子の半径を大きくする →R を大に 形状、 ⑥回転数を大きくする →N を大に 形状、周波数、バッテリ・CPU と言うことになる。 しかし、HVやEVに搭載することを考えると、サイズや、電池の容量や、コスト等、それぞれ制約条件があり、設計的にどこで折れ合うかということになる。 それは設計者の腕の見せ所だ。 商品設計は全て同じことが言えるが、その商品の目的を最大限発揮するためのギリギリの選択をすることと言える。ベストな妥協と言ってもいい。 面白いことに、メーカによってモータ形状が変わっている。 トヨタのHVは、細長く、ホンダのHVは薄くて直径が大きい。 トヨタ系は、ホンダ系に比べて、モータの回転数(N)を高くして出力を稼いでいる。 そのために、PCUの電圧を700V以上まで高めている。 HVは、エンジンルームの限られた空間に、通常のエンジンと、モータと発電機とPCU(パワー制御ユニット)を納めなければならず、モータや発電機の形状を薄型で大きな直径にするか、小さな直径で胴長にするかは、各社のHVシステムの違いや、設計者の思惑による。 また、同じ軸上にモータと発電機の軸を2重にするホンダi-MMD方式や、モータと発電機を2軸にして2段積みするトヨタ方式等がある。どちらにも、一長一短があるはずだ。 モータや発電機やCPUの放熱方法や、モータと発電機の効率をいかに高めるか、さらにエンジン効率をいかに高めるか、いかに軽い車体を造るか等、最先端技術を駆使した競争は加速的に進んでいる。 特に最近は、エンジン自体の熱効率を高める競争が激しくなってきた。昔、ガソリンエンジンは25%程度、ジーゼルエンジンは30%程度と言われてきたが、今は、ガソリンエンジンが40%を超えるようになってきた。もうすぐ50%になる。 最新の火力発電所が天然ガスコンバインドサイクル発電による最大効率が45%程度と言われる値を越すところまで近づいてきた。 そうなれば、敢えて値段が高いEVを走らせるより、ガソリンエンジンで走っても大気汚染や化石燃料の消費と言う面では、同等もしくは改善するとも言える。 この考え方は、『Well to Wheel』 と言う『石油井戸から車輪まで』という燃料効率のトータルの考え方に沿えば、エンジン技術の進化は素晴らしいものがある。 特に最近、マツダは独自のエンジン開発に熱心に取り組んでいる。 トヨタですら、マツダのエンジンに一目を置き、この面でアライアンスを組み、技術の囲い込みを狙っているようだ。 トヨタは、『EV化を5年前倒しする』と昨日(6/7)発表した。トヨタが想定していたより、世界のEV化が早く進むという事らしい。今の計画では置いてきぼりを食うという事。 世の中の車がEV化すると、充電するため大量の電力を供給する大問題が生じる。 それを原子力発電に頼るとなれば、地球温暖化の炭酸ガス濃度は抑えられるが、膨大な放射性廃棄物の処理、保管場所が問題になる。 全国に電力をくまなく供給する送電線ネットワークの再構築も課題になる。 EV化の進捗に合わせて電力供給の方針も政治や政府が本気で取り組まなければ、電力会社だけに任せられない。 全国に風力発電と太陽光発電を増やして、再生エネルギー中心の電力供給を行うことを考えなければならない。 EVは大きな電気エネルギーの貯蔵ができるので、EVと太陽光や風力の不安定な自然エネルギーミックスを考えれば、将来の電力需要が平滑化される。 行き着くところは、いつもこの話になる!! |
2019年5月25日(土)
燃費基準が変わります!
| クルマの燃費表示が大きな転換点を迎えている。 基準となる測定モード(測定方法)が従来の「JC08モード」から、世界的な新たな燃費基準である「WLTCモード」へ替わり、一部車種は先行して2017年中頃から表示を開始し、すべての乗用車の新型車は2018年10月1日から表示義務化が実施。そこからすでに半年が経った。しかし、まだまだ新車が少ないこともあり、WLTCモードが浸透していない。 従来のJC08モード燃費に対して、WLTC燃費はどうなっているのか? 実燃費とも乖離(かいり)は、JC08モードからWLTCになって少なくなったのか? 新型クラウン2.5ハイブリッド2.5RSアドバンス;JC08 23.4km/L、WLTC 20.0km/L ガソリン2.0RS;JC08モード 12.8km/L、WLTCモード 12.4km/L ■2020年9月からWLTCモード燃費に完全移行! 新燃費測定法「WLTC」(Worldwide-harmonized Light vehicles TestCycle)は「乗用車等の国際統一試験法」とされ、2017年中頃から一部の車種にWLTCモードが表示。 2018年10月以降、国内で新発売される車両は、輸入車を含めてWLTCモードでの燃費表示が義務化、 2020年9月以降、JC08モードの記載はなくなり、WLTCモードで計測された燃費のみ 現状ではWLTCモード燃費を計測した車種から順次JC08モード燃費と併記 マツダが先駆けて、2017年6月 CX-3 ガソリンエンジン搭載車にWLTC公表 ■WLTCモード燃費;JC08モード燃費とどこが違うのか? WLTCモード測定試験の特徴、車種ごとに3つのモード、「市街地モード」、「郊外モード」、「高速道路モード」が設定されている。 従来の計測モードよりも実際の走行条件に近い状態で測定される、 従来の計測方法よりも実燃費を推定できる。 具体的には以下のような走行モードを想定している。 ●市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行 ●郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行 ●高速道路モード:高速道路等での走行 ところで、WLTCと合わせて「WLTP」という用語を目にするが 「WLTP」は「Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure」の略で、 「乗用車等の国際統一排ガス・燃費試験法」。 国際的に整合性の取れた標準的な試験方法を確立することで、国や地域ごとに個別に決められていた排ガスや燃費の試験方法を統一して、一度の試験で多くの国での認証に必要なデータが取得可能になるメリットがあり、「WLTC」は「WLTP」による具体的な燃費試験とその結果となる。 ■シャシーダイナモでモード燃費を計測 ここでいわゆる「モード燃費」について触れておきたい。 モード燃費、カタログ燃費はメーカーが国交省から型式認証を受ける際に承認される燃費値であり、カタログに記載が義務化されているため“カタログ燃費”とも呼ばれる。 JC08や新たに導入されたWLTCのデータは、試験機であるシャシーダイナモメーターを使用して、シャシーダイナモのローラー上で一般的な実走行を模した運転パターンで走行試験を実施することで、燃費と排ガスの量や性質を測定する。 モード試験では、常に同一条件で試験されることが大前提となる。 事前に試験車両の走行抵抗を計測し、シャシーダイナモメーターに実走行相当の抵抗や負荷を設定する。 この場合、試験室の温度と湿度、試験車の暖機状態、空気抵抗を考慮して車速に応じた送風など、環境条件を常に共通として実走行により近い条件を作り出す . JC08とWLTCの試験方法は大きく異なる。 最高速度はWLTCが97.4Km/h、JC08モードが81.6Km/h ■実燃費との乖離(かいり)はJC08モードに比べて少なくなったのか? WLTCモードは別表のように、JC08モードに比べて「最高車速が高い」「加減速が多い」「走行時間や距離が長い」特徴がある。 このほか、重要なポイントは4つある。 アイドリング時間が減少すること。アイドリング時間比率はJC08モードの29.7%から15.4%と14.3%も減少する。 クルマのエンジンが温まった状態で試験を行うホットスタートがなくなること。 JC08モードではホットスタートが75%で、エンジンが冷えた状態からスタートするコールドスタートが25%の比率で燃費を算出していたが、WLTCではコールドスタート100%。 試験車両の重量の違いについてもJC08モードとWLTCモードは大きく違う。JC08モード燃費では2名乗車による+110kgであったのに対して、WLTCモードでは1名乗車+荷物相当の100kgに、そのクルマの積載可能重量+15%にして審査を行う。そのため、WLTCモードのほうが重量の重い状態で試験をすることになる。 また、JC08モードの「等価慣性重量(燃費試験時のシャシーダイナモメーターに設定する負荷)」において、ステップ状に設定された区分(重量)に合わせて、特定グレードのみ軽量化し、軽い区分にギリギリ滑り込ませるような手法は今後できなくなる。 燃費スペシャルグレードが生み出されることへの歯止めになる JC08モードとWLTCモードの計測方法の違い 1/試験車両の重量の増加 2/平均速度が上昇 3/最高速度が上昇 4/走行時間、距離が増加 5/アイドリング時間が減少 6/コールドスタートのみ 7/加減速の増加 8/燃費スペシャルグレードがなくなる 過去に遡れば、従来のJC08モードによる測定が義務付けられたのは2011年4月(輸入車などの一部は2013年3月)と10年近く前になるのだから、ハイブリッド車の増加などを考えれば、新基準の導入は当然ともいえる。 結局、JC08モードからWLTCモードに変わると、燃費が悪化するのか? JC08モード燃費がいいクルマほど、WLTCモード燃費が悪化し、30km/L超のクルマでは、5km/L以上悪化 要因としては、WLTCモードが冷機状態から試験を開始するため、オイル粘度が増加し摩擦損失が増大するためと考えられる。 特にハイブリッド車は、低速時にEV走行するのでより暖気が遅れ、さらに触媒温度を上げるために、エンジン作動時間が増えることで悪化しやすくなる。 またアイドリングストップすることで燃費を稼いでいたクルマも、その時間が短縮されるため燃費が悪化するとのこと。アイドリングストップなどの機能を搭載しないクルマのほうが、相対的によくなることも考えられるそうだ。 ■実燃費テストでわかったWLTCモード燃費との乖離! JC08モード燃費と実燃費との乖離(かいり)は30~40%、WLTCモードは、より実燃費に近づくのだろうか、 【市街地】 交通安全環境研究所(東京都調布市)~関越道練馬IC(東京都練馬区)までの26.2km 【高速道路】 関越道練馬IC~鶴ヶ島IC(埼玉県鶴ヶ島市)までの30km 【郊外路】 鶴ヶ島IC~熊谷さくら運動公園(埼玉県熊谷市)までの27.1km これらをすべてつなげた83.3kmが今回の測定コース。 カローラスポーツ(1.2Lターボ)、 フォレスター(2.5L NA)、 クラウン(2.5ハイブリッド)。 【テスト車両WLTCモード実測燃費】 km/L
欧州で行われているリアル・ドライブ・エミッション(RDE)の走行テスト。 日本では2022年10月から乗用ディーゼル車のRDE規制が始まる ■WLTCに続くRDE燃費計測が2022年10月から始まる! この試験法では、排ガスなどの計測機器を試験車両に搭載、日常的に使用するすべての運転条件が排ガス試験の対象。 車速だけでなく減速や標高や外気温なども幅広く規定され、条件に合致した一般道を実際に走行し、排ガスを車載排ガス分析計であるPEMS(Portable Emissions Measurement System)と呼ばれる装置で計測する。 WLTCはこれまで現実の燃費に近づくことを目指したモード燃費改善の最新の努力の成果だが、ディーゼルの排ガス不正が発覚したことで、RDEの役割が大きくなった。 国土交通省は2018年3月に道路運送車両法の「保安基準の細目告示」の改正によって、乗用ディーゼル(乗車定員9人以下、車両総重量3.5トン以下)の新型車は2022年10月から、継続生産車は2024年10月からRDE試験法の適用を開始することを発表した。 国交省が先日発表した、直噴ガソリンエンジンのPM排出量の規制強化をはじめ、どうやら排ガス規制強化の流れは新たなフェーズに入ることになったようだ。 |
2019年5月18日(土)
こんな記事も見受けます!
いよいよ、面白くなったハイブリッド戦争の勝利者は?
| 5月10日の下の記事で、ホンダ 八郷社長が決算発表の席で、開発戦略に触れ、小型車に新開発の2モータハイブリッドシステム i-MMDを搭載すると正式発表した。 この話は既に流れていたので新鮮味はないが、正式にホンダとして初めての発表だ。今まで、トヨタハイブリッドTHS(トヨタハイブリッドシステム)にやられっぱなしだったので、やっと本腰を入れたかと言う感じだ。と言うか、やっと理想のハイブリッドシステムを開発できる環境が整ったと言った方が正しいかもしれない。 それは、以前にも書いた大出力・大電力制御ができる半導体や、リチュウムイオン電池や、モータの開発が整ったことにある。 今回、フィット4に搭載する2モータ i-MMD方式は、アコード等中型・大型車にすでに搭載しているので、十分ノウハウは掴んでいる。以下のような記事を見つけたので紹介する。 ホンダのi-MMDハイブリッドはハイブリッドシステムではリコールありません。 しかも同クラスのトヨタのハイブリッド(THSⅡ)ライバル車種よりも燃費がいい。. アコードハイブリッド:JC08モード:30km/L カムリハイブリッド :JC08モード:23.4km/L オデッセイハイブリッド:JC08モード:25km/L エスティマハイブリッド:JC08モード:18km/L トヨタ開発陣が言うには、「トヨタの現行THS IIで、アコードハイブリッド i-MMDを上回るのはかなり難しい。」と敗北宣言しているそうだ。 ◆焦燥の見られない豊田社長に対し、危機感漂うToyota 開発現場 豊田章男社長は「これまで500万台のハイブリッドカーを作ってきたなかで積んできた経験が我々にはある。燃費だけでなく、いろいろな面でいいクルマを作ることで頑張っていきたい」と、余裕を見せる。 だが、ハイブリッドカーを作る開発現場は、そんなアドバンテージとは裏腹に、ピリピリとした空気に包まれているという。 「ホンダさんは4年前にも『インサイト』で価格競争を仕掛けてきたが、今回はその時とプレッシャーが全然違う。いろいろな技術情報から、ライバルの中でホンダさんが最初にキャッチアップしてくるだろうとは予想していたが、本気度は想像以上でした。 気を引き締めてかからないと」 Toyotaハイブリッド技術の開発に携わるエンジニアのひとりはこのように語る。 ◆“ミスターハイブリッド”を刺激した次期型フィットの登場 研究開発部門の中でも一番エキサイトしているのは、初代プリウスの開発責任者で“ミスターハイブリッド”を自認する内山田竹志会長だ。 これまでトヨタのハイブリッドカーが世界を席巻してきた一番の原動力は、何と言っても燃費性能の高さである。 これまでもライバルがトヨタのハイブリッドを上回る燃費性能のクルマを出すことは時々あったが、すぐに圧倒的な差をつけて抜き返すことができていた。 が、今回ホンダが出してきた性能は、そのトヨタにとっても一蹴できるようなものではないという。 ◆期待される次世代ユニット開発…登場の時期は? ミドルクラスナンバーワンの座をカムリハイブリッドから奪っていったアコード 「動力性能をはじめ、トヨタのハイブリッドシステムTHS IIが勝っている部分もまだまだあるが、こと燃費性能については、今のTHS IIでアコードハイブリッドi-MMDを上回るのはかなり難しい。 もちろんエンジンの排気量が違ったりといったこともあるが、ホンダのシステムが何より優れているのは電動部分のエネルギーロスの少なさ。 本格的に対抗するには、次世代のシステムが必要かも」(トヨタのエンジニア) と言う状況らしい。 ホンダ社内では、煮え湯を今まで飲まされたトヨタハイブリッドシステムTHSⅡを上回る高効率ハイブリッドシステムが着々と準備され、量産検討されている。 いよいよ、10月発売になる。 ホンダ i-MMDハイブリッドシステムの技術解説記事は下記のURLにあります。 www.honda.co.jp/tech/auto/powertrains/immd.html |
2019年5月10日(金)
ホンダはハイブリッド競争で、トヨタに雪辱できるか?
| トヨタとホンダは、5月9日同じ日に決算報告会を開催した。トヨタは日本企業として初めて売上で30兆円を超える業績を発表した。 正確には、30兆2256億円、営業利益は2兆4675億円、純利益は1兆8828億円だ。 それに対し、ホンダは売上が15兆8886億円でトヨタの半分、営業利益は7269億円でトヨタの1/3、純利益は6103億円でトヨタの約1/3という状況だ。 追記(日産自動車の決算発表5月14日) 売上高;11兆5742億円(前年比3.2%減)、営業利益;3182億円(前年比44.6%減)、 純利益;3191億円(前年比57.3%減) 巨艦トヨタの企業収益の高さがダントツに光っている。規模が大きいだけで、必ずしも利益は出ない。むしろ変化の時代では、企業規模がマイナスに作用することも多い。 トヨタの豊田彰夫社長は大企業トヨタらしからぬ発言や、行動や、思考をして、常に社内を引き締めている。危機意識を煽っている。 その証拠に、先日の決算発表会後の質疑で、『トヨタの一人勝ちに対して、当面の課題は?』と言う記者の質問に対し、トヨタ彰夫社長は『トヨタの敵は社内にある』『慢心が一番怖い』と言ったそうだ。 トヨタは田舎侍と昔から言われてきたが、素朴さと実直さで堅実な経営を行っている。 最近はその堅実さと、変化に対するチャレンジを社長が自ら率先して取り組んでいるような気がする。 決算発表はそれくらいにして、話はハイブリッド決戦について触れてみたい。 トヨタは世界初のハイブリッド、プリウスを1997年に発売して『21世紀に間に合いました』と言うキャッチフレーズは今も強く記憶に残っている。 それから20年が過ぎ、プリウスは世界のハイブリッド車の代名詞となった。その後、いろんな車種へ展開し、トヨタらしく、抜け目なくやり遂げ、ハイブリッドのトヨタは世界で盤石な体制を構築した。 「トヨタハイブリッド(THS)方式は、理想的なシステムで、これを超えることは不可能だ」とさえ言われてきた。 トヨタのハイブリッド(THS)方式は基本的な構造(アーキテクチャ)は1種類に統一されているのに対し、ホンダは1モータのIMA方式や現在の1モータ i-DCD方式、2モータのi-MMD方式、更に3モータのSH-AWDという3つの方式を有して、車種のグレードなどで使い分けてきた。 それぞれが特徴ある方式なのだが、理想的なトヨタTHS方式に追い付けず、この20年間ハイブリッド車はトヨタの後塵を拝してきた。 しかし、世の中の環境(半導体、リチュウムイオン電池等の電子部品、製造技術、ロボット化など)が大きく進化する中で、いつまでもトヨタの後塵を拝して納まっているわけにはゆかない!というのがホンダ魂だ。 そこで、今、開発を進めている2モータ i-MMD方式を今秋、フルモデルチェンジする新型フィット4に搭載し、アクアやプリウスの牙城を崩そうと必死で取り組んでいる。 トヨタ(THS)方式と何が違うかは、下の2019年4月30日(火)以下の記事に書いたので読んで頂きたいが、もう少し説明を追加する。 5月8日、ホンダは2019年決算発表の席上で八郷(はちごう)社長が以下の発言をした。  車両の電動化では、これまでにも「2030年にグローバル4輪車販売台数の3分の2を電動車にする」と目標を明らかにしており、車両の電動化によって得られるメリットについて「燃費の向上」「ゼロエミッション」の2つがあり、燃費向上で中心になるのはハイブリッド技術である。ホンダが持っている2モータハイブリッドシステム「i-MMD(Intelligent
Multi-Mode Drive)」を、今後モデルラインアップ全体に拡大する。 i-MMDは現時点で中・大型車にラインアップされている技術だが、新たに小型車向けの「小型i-MMD」を開発した。この小型i-MMDを4代目となる新型「フィット4」に搭載し、10月に開催される「第46回東京モーターショー 2019」で世界初公開する。 今後、i-MMDは採用モデルの拡大や、グローバル展開の実施などでスケールメリットが増大することにより、2022年までにシステムコストを2018年比で25%に削減する。 車両の電動化では、これまでにも「2030年にグローバル4輪車販売台数の3分の2を電動車にする」と目標を明らかにしており、車両の電動化によって得られるメリットについて「燃費の向上」「ゼロエミッション」の2つがあり、燃費向上で中心になるのはハイブリッド技術である。ホンダが持っている2モータハイブリッドシステム「i-MMD(Intelligent
Multi-Mode Drive)」を、今後モデルラインアップ全体に拡大する。 i-MMDは現時点で中・大型車にラインアップされている技術だが、新たに小型車向けの「小型i-MMD」を開発した。この小型i-MMDを4代目となる新型「フィット4」に搭載し、10月に開催される「第46回東京モーターショー 2019」で世界初公開する。 今後、i-MMDは採用モデルの拡大や、グローバル展開の実施などでスケールメリットが増大することにより、2022年までにシステムコストを2018年比で25%に削減する。
ホンダのiMMD方式は、基本的にモータの力だけで走る車であり、モータを回すためのリチュウムイオン電池と組み合わせている。電池の容量に制約があるので、電池を充電するため、もう一つのモータ(発電機)をガソリンエンジンで回して発電し、電池に充電する仕組みである。 この方式は、ベストセラーになっている日産ノート e-Powerと同じだ。実はホンダがアコードなどの中型車で既に先行して発売してきた方式で、十分な実績を積んでいる。 この方式はEVを造るには、ガソリンエンジンと発電機(2つ目のモータ)を取り外せば簡単にできてしまう。EV車はエンジンや発電機は搭載せず不要になる。 ハイブリッド車は、エンジンや発電機を狭いエンジンスペースに納めるなど課題が多いが、エンジンや発電機を取り外すのは実に簡単にできる。 EVはエンジンと発電機を取り外し、そのスペースにリチュウムイオン電池を積めば出来上がる。 プラグインハイブリッドは、ハイブリッドの電池容量を大きくすればいい。そのためにはリチュウムイオン電池の容量を大型化する必要がある。 トヨタのプリウスやアクアは、エンジンルームがエンジンと遊星歯車などメカやモータなどを搭載しているので、取り外せば、EVが簡単にできるというものではない。別の車を作るのと同じような設計が必要になる。開発費が嵩むがトヨタならできる。 今回、ホンダが発売するi-MMD方式の新型フィット4をはじめとする新ハイブリッド車は、多分、すぐに(半年後?)兄弟車のEV車が発売されるのではないかと思われる。 もちろん、ハイブリッドとEVでは、PCUという電力制御電子回路の容量やコンピュータの制御プログラミングは相当変更しなければならないが、それはハイブリッドを造るより簡単な作業でできる。 ホンダは今後、i-MMD方式をハイブリッドの標準方式として、他車種に搭載してくる。既に、中型車のインサイトに搭載して好評を博しているが、インサイトはセダンで、今、日本ではセダンの人気は今一だから、あまり評判になっていない。 しかし、このi-MMDシステムは燃費や加速等に於いて大変評価されている。 1.4トンのインサイトに搭載したi-MMDハイブリッドと、1.2トン前後のフィットハイブリッドでは基本システムは同じでも、モータの馬力や、トルクや、バッテリー容量などは、車の重量に適したサイズダウン・パワーダウンしたものが採用される事になる。 同じ1500ccガソリンエンジンを搭載しても、軽量化し燃費が一層良くなる。 トヨタハイブリッド方式に対し、新しいホンダi-MMD車がどういう戦いができるか、その勝負は今年中に決着する。 20年来の雪辱を晴らせるか? ホンダの技術者の魂に期待したい。 多分、1リッターのガソリンで、40km以上走るはずだ! そうでないと、i-MMDの優位性が発揮できない。そうなると、低燃費NO.1になるが、低燃費だけでなく、加速や登坂力や運転の面白さが味わえる車に仕上がれば、ますます良しだろう。 もう一つ、触れておきたいことがある。 トヨタTHSに搭載しているモータと、ホンダのモータの違いは何か? ホンダのモータは回転子の直径が大きいように見える。(注;これは写真で見た感じ) トヨタのモータは回転子の直径が少し小さいので、その分、回転子の幅が長い。 一般的に、モータのトルクは回転子の直径が大きいほど大きくできる。 トルクは、 τ=F×L トルクは力(F)×腕の長さ(L) ( トルクは 力×回転子の半径) 歯医者で虫歯を治療してもらう際のエアータービンという研磨機は、回転数が毎分数十万回転もする。 キーンという耳を突き刺すようなジェット機のような音が出るが、これは直径が数cmの小さなタービンを使っているので、超高回転ができる事例だ。 トヨタのハイブリッドモータは、5万から7万回転/分するようだ。 多分、ホンダのモータはそこまで回さないはずだ。 モータの回転数を高くするには、電圧と周波数を高くする必要があり、PCUで昇圧し、VVVFで電圧と周波数を制御する。 9月頃には詳しい情報が得られるはずだが、今のところはこのくらいか! いずれにしても、ホンダ i-MMD方式はEV車にすぐ展開できるというメリットがあり、今後、中国などEVしか売れないという規制がかかった場合は、柔軟に対応ができるメリットがあることは明白だ! その辺は、トヨタも既に読み切っているはず。 だから、虎の子のハイブリッドの特許を無償公開して、自陣の優位性を保とうと狙ってやったことだろう。 いずれにしても、10月前後になれば大きな話題となることは間違いない。 トヨタ、日産、ホンダのハイブリッドの三つ巴戦が始まる!! 最終的には、モータのコストダウンと大量生産が課題になる。 それに対して、下記の記事(4月30日)または、下記のURLで紹介している。 https://web.motormagazine.co.jp/_ct/17265386 |
2019年4月30日(火)
ハイブリッド車に搭載するモータについて
| いよいよ、平成最後の日になりました。譲位が発表されてから、随分先の話だと思っていましたが、時間の経つのは早いものです。明日は『令和』に変わります。 当分は、令和とすぐに口から出るか戸惑います。言い慣れたことは、すぐに言えますが、歳と共に普段使わない言葉が口から出にくくなるのは、よく経験することです。 元号の話は、それくらいにして、本論に参りましょう。 ガソリン代が、再び上昇をしています。イランの原油輸出の制限や、円安等の影響だという話ですが、ガソリン価格は今後、安くなることは考えにくいです。 先ほど、近くのセルフで給油しましたが、137円/リッターでした。安い方だと思います。 人類は限られた石油資源を湯水のごとく使ってきました。資源の枯渇問題が表面化し議論になります。そのたびに、産油国の生産調整や、原油価格引き上げが行われます。 豊かで便利な生活に慣れた我々は、エネルギーなしでは生きてゆけなくなっています。石油・ガス・電気はそういう豊かな生活を送るための必需品です。無駄な消費を無くするよう心がけたいと思います。 そこで、最も多く原油を消費する自動車は低燃費競争が盛んです。その代表がEVであり、ハイブリッド車です。ハイブリッド車はエンジンの弱点をモータでカバーするアイデアで産まれたものです。 1トン以上もある車を動かすには大きな力が必要です。 そのような力はエンジン以外では得られないというのが以前の常識でした。 しかし、ニッケル水素電池や、リチュウムイオン電池が開発され、何十キロワット(何十馬力)という出力を出すモータを駆動できる時代になりました。 ハイブリッド車は電池の革命があったから生まれた車です。従来、車に積んでいる鉛バッテリーでは、重くて車を走らせることはできません。 ハイブリッド車について、もう少し踏み込んだ内容を紹介します。 ガソリンエンジンは回転数が低い時はトルクは小さいのです。回転数の上昇と共に、トルクと馬力が共に大きくなります。ある回転数でトルクが最大になり、それ以上の回転数ではトルクが少し下がります。 トルクとは『回転力』の事で、軸を回す力の事です。軸の中心からある距離離れたところで、どれだけの力が発生できるかということです。左図で考えますと、 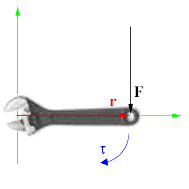 トルク=力×距離 τ=F×r トルク=力×距離 τ=F×r左図のように、モンキースパナ―で示せば、ネジを締める部分(緑)に加わるネジを締め付ける力です。その回転力は、スパナの柄の長さ(腕の長さ;赤色)(r)と、スパナの先端に加える力(黒色;F)の積だということです。 だから、Fが大きいか、rが大きければ、トルク(τ)も大きくなります。 車は走り始める際、一番大きなトルクが必要です。 走り出して加速する際にも大きなトルクが必要です。 車を走らせるのに必要なトルクと、ガソリンエンジンが発生するトルクの特性にズレがあります。下図を見れば分かりますが、赤い曲線がエンジンが発生するトルク特性です。青線がモータが発生するトルク特性です。 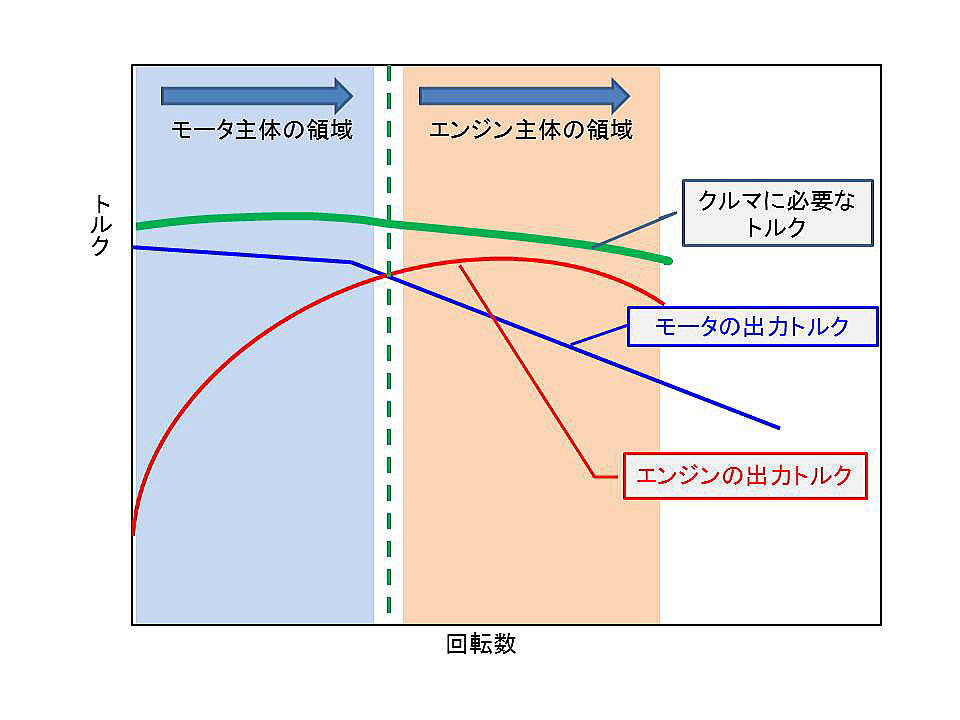 車が走るためには緑色のトルクが必要になります。 車が走るためには緑色のトルクが必要になります。モータは回転数がゼロの時(回り始める時)に一番大きなトルクを発生する特性を持っています。 モータは車が走るために必要なトルク特性とよく似た特性を持っていると言えます。 モータだけで十分車を走らせることができるのです。これがEVです。 EVを長距離走らせるには、大きな容量の電池が必要です。 現在の技術では、まだ電池の容量や寿命や充電時間やコストの問題があり、全世界の自動車メーカや電池メーカの大きな研究課題です。 そこで、エンジンと、モータの良いとこ取りをしようと考えたのがハイブリッド車です。 電車の運転席のメータを見ていると分かりますが、走り初めには大きな電流が流れます。電車は150A(アンペア)~200Aの大きな電流が流れます。電車が次第に加速すると、電流は徐々に下がります。そのままですと電流は下がりますが、電車のスピードが上がらなくなります。そこで運転手がノッチ(ハンドルレバー)を操作をすると、電流は増え電車はさらに加速します。車のアクセルを踏み込むのと同じです。 なぜ、電車の運転手がノッチ操作をする必要があるのでしょう? それは、走り始める際にモータに全電圧(電車の架線電圧は直流1500V)をかけると、非常に大きな電流が流れてモータのコイルが焼き切れてしまうからです。 走り始める際、モータにはコイルの銅線の抵抗分しか電流を制限するものはありません。モータのコイルは太い銅線を巻いていますので、電気抵抗は大変低いのです。 モータに流れる電流は、電流=電圧÷抵抗 I=E÷R ですから、架線電圧が直流1500Vですので、1Ω(オーム)にもならない低い抵抗値ですから、そのままでは数千アンペアという大電流が流れ、コイルが焼き切れてしまいます。殆ど短絡状態に近い電流が流れます。その前に保護装置(ブレーカ)が作動して回路を切り離しますが。 運転手は走り出す際、電流を規定値に押さえるためノッチの操作をするのです。 昔の電車は、床下に『抵抗箱』を積んでいました。この箱の中に抵抗器(ニクロム線)が入っていて、ノッチを操作すると、モータと直列につないだ抵抗器をスイッチで切り替えて、モータに流れる電流を制限しながら走りました。 抵抗器を通して電流を制限すると、抵抗器が発熱します。その発熱量は、 消費電力(発熱量)=電圧×電流 または 発熱量=電流×電流×抵抗 P = E×I = I2×R ですので、その発熱した抵抗器から空気中に熱が放散され電力ロスになります。 以前の電車はすべてそういう抵抗器制御方式を使っていました。 ノッチを操作することで、走り初めはモータと直列に大きな抵抗器をつなぎ、モータの回転数が上昇する(電車の速度が上がる)と、ノッチを操作して抵抗値を小さくし、モータに高い電圧を加え、回転数をさらに上げ、電車は速度をぐんぐん上げたのです。 ノッチを切り替える毎に、乗っている人はガクン・ガクンと前後に加速の変化を感じました。これは昔の電車の話です。 今でも、ローカル線に乗ると、このような体験をすることができます。それはその電車が古い車両を使っているからです。 今は、VVVF(バリアブル ボルテッジ・バリアブル フレケンシ)という半導体を使った巧妙な制御方式で、直流1500Vを架線からパンタグラフで受電し、この直流を交流に変換し、電圧と交流周波数を制御して、スムーズにモータのトルクと、回転数を可変する方式が一般的です。新幹線も同じ仕組みです。 このVVVFにより抵抗器の発熱による電力ロスを亡くし、モータをスムーズに制御するようになっています。 ここまでは前座の話です。ここからが本論に入ります。 モータには、構造的に分解すると、固定子と回転子があります。 固定子は鉄心にコイルを巻いた外側の固定した電極です。 回転子は固定子の中を回る鉄心です。 ほとんどのモータは回転子の軸から出力(駆動力;回転力)を取り出します。 回転子には、コイルを巻いたモノと、永久磁石を埋め込んだものと、単なる鉄心でできたものがあります。以上はモータの構造による分類です。 モータを接続する電気で分けると、直流モータと、交流モータがあります。 昔の電車は直流モータを使い、抵抗器で回転数を制御していました。上の説明のとおりです。この直流モータは、ブラシと整流子という部品があり、固定したブラシから回転子に取り付けた整流子を通じて、回転子に電流を供給しました。 整流子とブラシは機械的・電気的に接触しているので、軸が回転すると、火花が出て、ブラシが摩耗(消耗)します。ですから定期的にブラシを取り換えなければなりませんので、メンテナンスが大変でした。 最近の電車のモータは交流同期モータを使用しています。この交流同期モータはブラシや整流子が不要です。擦り減る部品がないのです。 固定子にコイルを巻き、回転子は永久磁石を埋め込んだものです。(回転子にコイルはありません) 新幹線は、高速電車ですから大きな馬力が必要ですので、架線電圧は交流25,000Vと非常に高い電圧を使います。直流1500Vでは、電流容量が不足しますので、電圧を上げ交流を使用しています。パンタグラフで、交流25,000Vを受電して、車体の床下にある降圧トランスで電圧を下げ、直流に変換後、VVVF回路を通して交流同期モータを駆動する方式を取っています。 ところで、モータに電圧をかけると電流が流れます。どのような種類のモータでも熱くなります。これはコイルの銅線に電流が流れる以上、コイルの抵抗分が電流で熱に変わるからです。ゼロにはできません。 発熱量は、P = I2×R ハイブリッド車に使われているモータは、交流同期モータです。 この交流同期モータは、加える交流の周波数に同期して回転数が変わります。更に、加える電圧でトルクが変わります。 自動車や電車に搭載するモータは、発進や加速により回転数が変化します。発進時は大きな電流が流れますので、発熱が大きくなり温度が上がります。 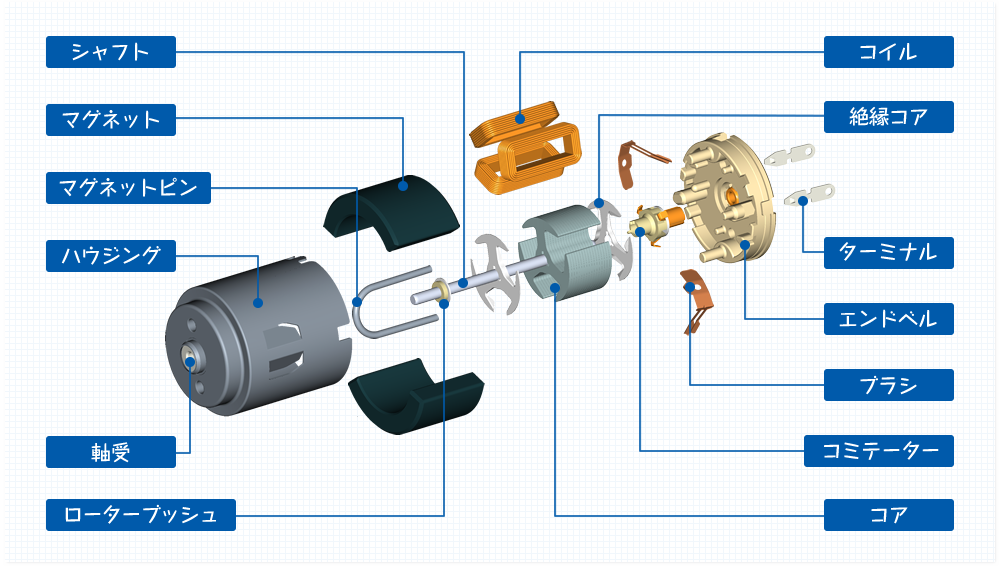 上図は、おもちゃ用の直流モータを分解した図です。 このモータの場合は、マグネットが固定子、コアに巻くコイルが回転子になります。 モータは、固定子にコイルを巻き、回転子は永久磁石を使う場合もあります。 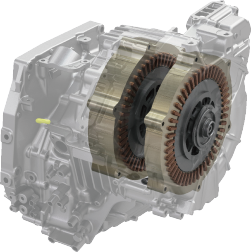 ハイブリッド車用モータは、固定子にコイルを巻いています。回転子は薄い磁性鋼板を何枚も重ねたものに永久磁石をはめ込んでいます。 ハイブリッド車用モータは、固定子にコイルを巻いています。回転子は薄い磁性鋼板を何枚も重ねたものに永久磁石をはめ込んでいます。ですから、上図のブラシや整流子(コミュテーター)はありません。 左図は、ホンダのハイブリッド i-MMD方式の2モータ の分解写真です。 左側が駆動(走行用)モータ、右側が発電用モータ コアの厚みが少し違います。 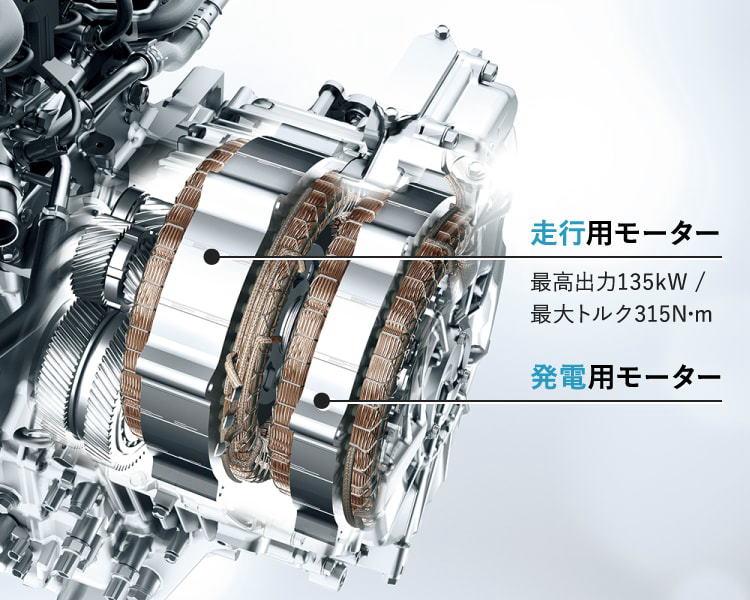 軸に固定子と殆ど隙間がない回転子が取り付けられていて、回転子に永久磁石がはめ込まれています。 問題はこの永久磁石の特性の話になります。 永久磁石にはいろんな種類のものが開発されています。 以前はKS鋼、MK鋼、フェライト磁石などがあり、日本は磁石の技術では世界NO.1でした。 近年、サマコバ(サマリュウムコバルト)磁石や、ネオジ(ネオジュウム)磁石が発明され、非常に強い磁石が得られるようになりました。 サマリュウムや、コバルトや、ネオジュウムなどは希土類と呼ばれ、世界的に産出量が少なく、埋蔵地が偏っている高価な金属材料なのです。 特に、サマコバ磁石は高価ですので価格的に安いネオジに代替されました。 サマコバの方が早く開発され、ネオジが発明されるまでは最強の磁石でした。 以前、LPレコード演奏用のピックアップのMMやMCカートリッジに極小さなサマコバが使われたことがあります。今もイヤーフォンなどにも使われています。 ネオジは現在、最強の永久磁石ですが、キューり温度が310度℃と低いことが欠点です。キューリ温度とは磁力が弱くなったり、磁石の特性を無くなる温度です。 モータの温度が上昇するに従い磁力が弱くなるのを防ぐため、キューリ温度を上げる対策としてジスプロシュウムというさらに希少な材料を混ぜる必要がありました。 このジスプロシュウムは中国でしか産出しない希少で高価な金属ですので、中国が輸出規制すれば、モータや、ハイブリッド車の生産に支障を来します。 そこで日本の各社はジスプロシュウムを使わないネオジ磁石の開発に取り組んでいます。 磁力が強いことは、モータの発生する力(出力;馬力)を大きくできます。 モータの出力は、磁束密度(磁石の強さ)×電流×磁力線と交差するコイルの長さ で、 F = B×i×L で示されます。 コイルを何回も巻けば、巻き数(n)に比例して発生する力 Fが大きくなります。 F=n×BiL トヨタ自動車はプリウスで世界中を席巻しましたので大量のモータを造っています。どこで製造しているのか知りませんが。多分、デンソーなどの系列会社? ホンダは、2モータハイブリッド i-MMD方式を今後のハイブリッド車の標準方式にすると言われています。今年の夏から秋口にかけてフルモデルチェンジするフィットハイブリッド4も、この2モータ方式を採用し燃費は1リッターで40Km以上走る車になると噂されています。この方式で、多分、トヨタの後塵を拝してきたホンダが巻き返しに出るはず。 ホンダは、今後『エンジン主体のハイブリッド方式からモータ主体に変わる』という戦略で臨んでいます。そこで、モータを自社で内製し、いかに安く高効率で高性能なモータを造るかに取り組んでいます。コスト面では、自動化と、ネオジの弱点である高価なジスプロシュウムを使わないモータを開発したと発表しました。 モータのネオジを埋め込んだ回転子を液体で冷却するようです。詳しいことは分かりません。 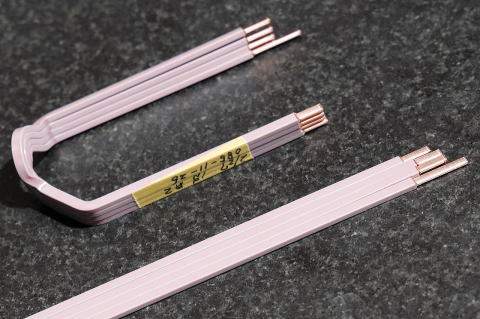 モータ固定子に巻く銅線も、丸銅線ではなく、平角銅線という断面が四角の銅線を採用しています。これにより鉄心のコイルとコイルの隙間を無くすることで、モータの効率と出力が上がります。 モータ固定子に巻く銅線も、丸銅線ではなく、平角銅線という断面が四角の銅線を採用しています。これにより鉄心のコイルとコイルの隙間を無くすることで、モータの効率と出力が上がります。モーターの定格出力から推測すると、この銅線(コイル)には、100A前後の電流が流れますから、銅線の断面積は40mm2、 電流による発生する力は、F=nBIL で示すことができます。 nは巻数です。 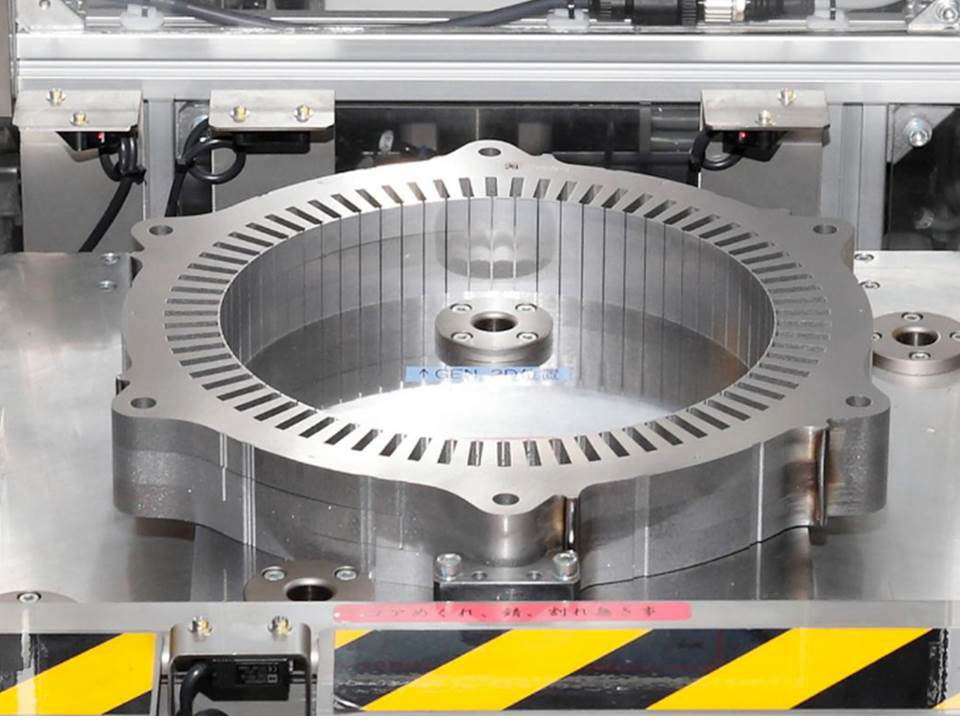 鉄心に銅線をたくさん巻けば、モーターの出力は増えますが、たくさん巻くには、モータが大型化します。 鉄心に銅線をたくさん巻けば、モーターの出力は増えますが、たくさん巻くには、モータが大型化します。鉄心の溝に沢山コイルを巻くにはコイル(銅線)を細くする必要があります。 細くすれば、銅線の電気抵抗が増え、大電流が流れると発熱して、銅線の絶縁材料が熱で耐えられません。 モータを設計する際は、馬力(出力)に見合う太さの銅線と巻数が必要だということです。 ホンダの資料によると、 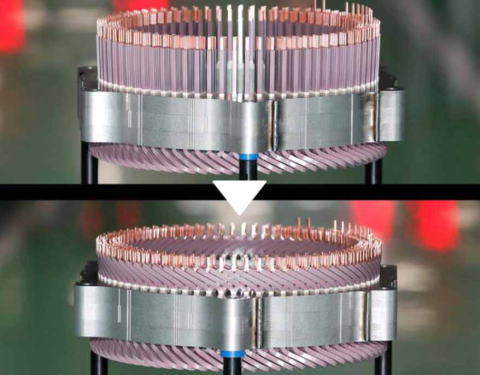 平角銅線4本を上の写真のような形にして、鉄心のスロットに刺しこみます。 そして、銅線の上部を下のように成型して銅線の先端を溶接して、コイルとして仕上げます。 平角銅線4本を上の写真のような形にして、鉄心のスロットに刺しこみます。 そして、銅線の上部を下のように成型して銅線の先端を溶接して、コイルとして仕上げます。これが新しいハイブリッド用モータの固定子です。 当初は、丸い銅線を手巻きで製造していましたが、手作業では到底、生産数が限られます。 そこで、フィットクラスの大量生産車に対応できるモータを開発しました。  一般的にコイルを巻く作業は、つながった銅線を狭いスロットに差しこんで、連続して巻く作業になりますので自動化が難しいので、成型した銅線の断片を固定子のスロット(隙間)に差し込み、成形した後、銅線を溶接でつなぎ合わせコイルにするという自動化設備を完成したと発表しています。これは間違いなく製造特許でしょう。 こういう合理化により2モータハイブリッドのフィット4が秋に発売されます。  2モータ化することで、エンジンに連結したダイレクトクラッチという複雑な変速機が不要になり、駆動メカニズムはシンプルな減速歯車だけになります。 2モータ化することで、エンジンに連結したダイレクトクラッチという複雑な変速機が不要になり、駆動メカニズムはシンプルな減速歯車だけになります。速度の可変は電子式CVTとも言えるVVVFが担当します。 その分、軽量化でき、高率化でき、コストも下がります。 次期フィットハイブリッドは、日産 ノート e-Power を上回り、特に高速道路の燃費はさらに改善され、トヨタTHSⅡに対して、シンプルなメカニズムハイブリッドシステムとなり、燃費や加速の面でもトヨタTHSⅡを凌駕するものになるはずです。 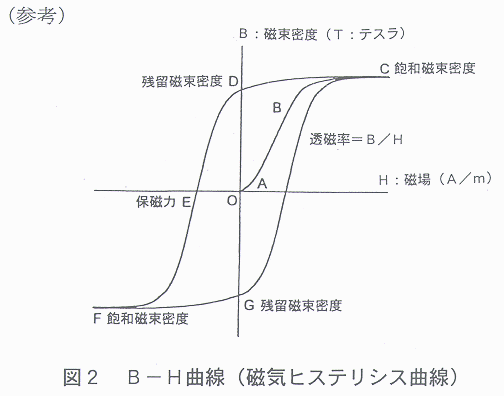 少し、専門的な話になりますが、磁石の性質をあらわすグラフとして、左図の曲線があります。 少し、専門的な話になりますが、磁石の性質をあらわすグラフとして、左図の曲線があります。これをヒステリシス曲線と呼びます。 横軸が磁場(H) 縦軸が磁束密度(B) D点が残留磁束密度 E点が保磁力 このB-H曲線の囲む面積が大きいほど、優れた磁石です。 ネオジはすばらしい磁石で、曲線が囲む面積が大きいのです。 0点から電磁石で磁界をかけてゆくと、B点を通過して、最大電流が流れた時の磁束密度がC点に達する。(飽和磁束密度;最大磁束密度)。 その後、電流を下げてゆくと電流がゼロになった時にD点になり、これが残留磁束密度になる。更に電流を逆方向に流すと、外部のNSの方向が逆転するが、磁石の保持する力が残りE点、これを保磁力という。 更に電流を逆に増やすとF点に達する、ここから電流を逆に増やすとG点を通過して磁束密度がゼロになりさらに上昇する。このループをB-H曲線(ヒステリシス曲線)と呼ぶ。 ◆電磁石の材料は、飽和磁束密度(最大磁束密度)が大きく、保磁力が小さいほど優れている。 たとえば、トランスのコア、発電機のコア、モータのコア等 ◆永久磁石は、保磁力が大きいほど良いが、更に飽和磁束密度が高ければ一層優れた磁石になる。 サマコバやネオジは保磁力も最大磁束密度も大きい材料と言える。 モータについてまだ疑問点が残っていますので、もう少し紹介します。 ハイブリッド車がモータが回転し始め、車が走り出す瞬時、一番大きな電流が流れ、トルクが最大になるという話を冒頭にしました。 ではなぜ、モータが回転を始めると、徐々にモータに流れる電流が減るのか? その訳について触れていなかったので、追記します。 モータが回り出す際(モータに電気を加えた瞬間)は、コイルの巻線の銅線の抵抗分しか電流を制限するものがないので、太い銅線を巻いたコイルの抵抗値は小さいから大きな電流が流れることは既に書いた。 モータが回転を始めると、モータの巻線(コイル)が磁石の磁力線を切ることになる。そこで、『フレミングの右手の法則』で、コイルに起電力が生じる。 この起電力の方向は、モータにつないだ電源(リチュウムイオン電池・電車の架線)の電流とは逆向きに発生する。これを逆起電力と呼んでいる。 逆起電力の大きさ eは、磁束密度(B)×コイル長(L)×コイルが磁力線と交差する速さ(v) で決まり、その値は、 逆起電力 e = B×L×v このv(磁力線をコイルが切る速さ)は即ち、モータの回転数になるから、回転数が大きくなると、逆起電力も次第に大きくなる。 たとえば、100Vの電源にモータをつないでいると考えると、 モータが回転し始める瞬間は、100Vがモータに直接加わる。モータが回転し始めると、逆起電力のために、100V-1V=99V、更に回転数が大きくなると100V-10V=90V、さらにドンドン、巻線にかかる電圧が低くなる事になる。 そうすると、コイルに流れ込む電流(i)が小さくなり、モータの発生する力(F=BiL)が小さくなるので、ある回転数で、発生する回転力と、軸にかかる負荷とバランスして、それ以上、回転数は上がらない。 更に回転数を上げるには、モータ端子にかける電圧を100V以上に高くする必要がある。交流同期モータの場合は、交流の周波数で回転数が変わるので、周波数も同時に変える。 これがVVVFという制御技術である。 プリウスやアコードなどのハイブリッド車の駆動モータには、数百ボルト(700~800Vの高い交流電圧をかけてモータの回転力を得ている。 そのために、PCU(Power Control Unit;通称パワコン)という電圧、電流、周波数制御回路を搭載して、センサーで車の走行状態をモニターして、CPU(コンピュー)でPCUに制御信号を送り、モータにかける電圧(電流)、周波数を適切に制御している。 そのPCU制御プログラムをうまく作らないと、アクセルやブレーキ操作をした際にスムーズな運転感覚が得られないことになる。 また、リチュウムイオン電池は、適切に充電・放電をさせないと、発熱したり、寿命が短くなるので、電池に対する充放電制御も重要な課題になる。 ハイブリッドが日本のお家芸で、特にトヨタTHS方式が非常に優れていると言われるのは、そういう複雑なモータ・発電機・電池の制御が巧妙に高い完成度で造られたことにある。 モータと発電機は、『フレミングの左手の法則』と『右手の法則』の関係で動いている。 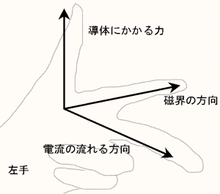 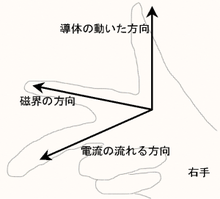 モータ 発電機 『フレミングの左手』と、『右手の法則』の違いは、上図の中指の電流の流れる方向が逆になっている。これはモータが回転することで、モータの内部で逆起電力が発生し、モータに電流を流すのを阻害する要因を示している。 車が走り始める際は、大きなトルク(力)が必要になるが、この時、モータは大きな電流を流すことができるので、大きなトルクを得ることができる。しかし、リチュウムイオン電池は、極端に大きな電流を取り出すことができないので、適当な電流になるようにPCUで制御する。 電車は、架線(トロリー線)からパンタグラフを通じて電流を取るので、架線に流せる電流以内であれば、大きな電流をモータに加えることができる。しかし、モータに流せる最大電流はモータの巻線(コイル)の太さで決まるので、電車も運転手がノッチで、最大電流を150A~200A程度以内になるように操作する。 モータと発電機は表・裏の関係にあると言える。 ■モータは、電流を流す(電圧をかける)事で、軸が回転する力を得る機械。 ■発電機は、軸に回転力を加えることで、電気を取り出す機械。 モータの軸に外部から力を加えて回転させると、発電機になる。 発電機に外部から電圧を加えると、モータになる。 こう考えると何事も、作用があれば、反作用が生じることが分かる。 電気エネルギー ⇔ 機械エネルギー |
2019年4月5日(金)
トヨタが、ハイブリッッドシステム特許を無償公開!
| 昨日の日経など各紙で、トヨタ自動車が「虎の子」のハイブリッドシステム特許を無償公開(2030年まで)したというニュースが流れた。 ハイブリッド車(HV)と言えば、トヨタ自動車が世界でNO.1の地位を占め、他の追随を許さず現在に至っている。その理由は、トヨタが世界で初めて開発したプリウスに使われているハイブリッドシステムの完成度が非常に高く、理想的とまで言われ、他社の追随を許さなかったことにある。 ハイブリッドシステムに関して、23,740件という膨大な特許を取得し、他社がこれに抵触しないで、トヨタのHVシステムを超えるHV車の開発ができなかったという裏話がある。要はHVでは、世界でトヨタに迫れる自動車会社はいなかったというのが実情だ。 その一人勝ちのトヨタがなぜ今、自社の強みで、虎の子であるHVシステム特許を2030年まで無償公開すると発表したのか? その理由はいくつか考えられる。 ハイブリッドシステムは、モータ、二次電池、PCU(パワー コントロール ユニット)から成り立っている。この3つの要素技術をシステムとしてどう組み合わせるかということに尽きる。ここで、HVの理想形とさえ言われてきたトヨタHVシステムを特許で押さえてきたので、他社がこのトヨタの特許を避けるには、大変ハードルが高く、今までホンダと日産以外は手が着けられなかった。世界の自動車会社もしかり。 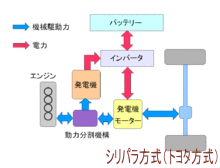 トヨタハイブリッドシステムは、開発当初から2モータを使い、遊星歯車という動力分割メカニズムで、エンジンとモータのトルク配分を最適化し、高い効率が得られるような仕組みを開発した。これがトヨタHV車が優れた燃費をたたき出す源になっている。 このシステムを支える部品は、先のモータと、電池と、PCUだが、これらの部品は値段が高く、他社はコスト的に成り立たないと諦めていた。 それをトヨタは先を読み切って、PCUは電子部品だから大幅なコストダウンが進む。電池はPanasonicと協同開発し、製造工場まで投資を行い、大幅なコストダウンに成功した。それまで、HV用電池はリチュウムイオン電池でないと、容量や重量的に無理と言われていた時代に、あえてPanasonicが製造していたニッケル水素電池を使った。 このニッケル水素電池は、品質が安定し、寿命も十分耐えられる部品で、リチュウムイオン電池に比べて大幅に安いので、今もトヨタのプリウスやアクアに使用している。 モータの改善、電池の容量アップとコストダウン、PCUの半導体のコストダウンが進み、システムコストの引き下げに成功し、プリウスやアクアがバカ売れしたこともあり、圧倒的なHVの牙城を築き上げてきた。 HVの特許をガンジガラメに押さえているので、安泰な経営ができると思われていたところ、急に今回の特許公開、しかも無償で!という記事を見てびっくりした。 トヨタは特許の無償公開の裏で新経営戦略を立てた。それはトヨタ方式のHVシステムで他社の囲い込みを急がなければならなくなったのではないか? ベンツ、BMW、アウディ、VW等、ヨーロッパの各自動車メーカは、ガソリン車よりクリーンなジーゼル車が完成したとしてて、販売してきた。 ジーゼル車はもともと、エンジン特性として、トルクが大きく力強い走りができる反面、エンジンの振動や騒音がうるさいという乗用車には大きなマイナス面を持っていた。 また、発進時に黒煙を吐き出すことも大きな欠点だったが、エンジン技術が進歩し、そういう欠点やマイナス面が殆ど改善された。 日本では、マツダだけがジーゼルエンジンに力を入れて独自の開発が進んでいる。 VW(ワーゲン)は、ヨーロッパやアメリカの厳しい排気ガス規制をクリアするジーゼル車ができたとして発売した。 ところが、車の排気ガス検査で、検査時はOKだった排気ガス値が、実走行では規制値を大幅にオーバしていることが分かり大問題になった。 VWはコンピュータプログラムを書き換えて、検査時は排ガスを規制値以下に下げるように制御し、実際、使う時はプログラムを切り替えて、排気ガスが規制をオーバーする状態になっていた。 これは規制をクリアさせるプログラムでは走行性能が悪くなり、ユーザに不満が出るので、そういう姑息な手段で対応をしたことがばれた。 この話を聞いた時、今までヨーロッパ、特にドイツのモノづくりに対する高い信頼が崩れ去った。まさか、あのドイツがそこまで追い詰められているのかと驚いた。 彼らは、トヨタHVの優秀さは知っているが、特許が壁になり手が出せない。 そこで48Vという中途半端な電圧を使ったマイルドハイブリッド方式をHVのデファクトスタンダード(標準)に定めようと動いた。 車のバッテリー電圧は世界標準で12Vになっている。 (一部、バスや大型トラックは24V仕様)。 鉛バッテリーは1セルが2Vなので、6セル直列接続して12ボルトを得ている。 48Vバッテリーは4倍の電圧だから、モータ電流は1/4になる。しかし、この程度のモータの馬力では重い自動車を動かすことができない。だから、48VHV車の場合は、車を発進する際はエンジンが主体で、モータはエンジンをアシストする補助的な位置づけで、これをマイルドハイブリッド方式(パラレル方式)と呼んでいる。 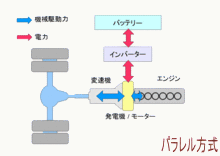 ホンダが以前、フィットやインサイトで、このマイルドハイブリッドを採用したことがある(IMAと呼んだ)が、本格的なトヨタハイブリッド方式の前にあっけなく崩れ去った。それは発進加速性能はある程度良くなるが、燃費の改善は十分できなかったからだ。 そのトヨタがなぜ、虎の子のHV特許無償公開(2030年まで)に踏み切ったのか? 公式的には、トヨタハイブリッド方式を世界のハイブリッドの標準仕様(デファクトスタンダード)にすることで、モータや電池やPCUなどの要素部品を世界の自動車メーカに供給しようとする戦略が透けて見える。 自動車メーカから、HV部材メーカへも事業拡大を狙っているのではないか? デンソーやBOSHなど世界の自動車部品メーカが力を着けてきているので、車の組立て、完成メーカから部品、部材を含めた脱皮を狙っているのかも知れない。 これが一つの見方である。 もう一つ、別の視点を紹介しましょう。 それは、日産自動車のバカ売れし出した『ノート e-Power』の存在。このe-Powerは、トヨタハイブリッド方式とは違う、トヨタのHV特許に抵触しない方式で、EVに近いHVを完成しました。別の表現をしますと、トヨタHV方式は、シリーズ・パラレル(シリパラ)方式と言い、日産ノート『e-Power』は、シリーズ方式と言われます。 マイルドHVはパラレル方式です。 ハイブリッドシステムには、この大別し3つの方式があります。 (1)パラレル方式はエンジンとモータが直結し駆動する方式で、制御は最も簡単です。 (2)シリーズ方式はエンジンは発電機(発電用モータ)に直結し、発電した電気はバッテリーに蓄えられ、駆動用モータを回し、駆動用モータは車軸に直接つながります。 モータの力だけで車を動かします。 (3)この両者を組み合わせたのがトヨタのシリーズパラレル(シリパラ)と言われる方式で、エンジンは発電用モータ(発電機)を回し、バッテリーに充電します。充電が十分されている場合はエンジンがかからず、発進時には駆動用モータで行い、走行時は駆動用モータとエンジンの両方を使い、両者の効率のいい状態で使うという複雑な制御が必要です。エンジンとモータを組み合わせ、もっとも効率がいい使い方をするため遊星歯車により動力分割機構と呼ばれるメカニズムを経由します。トヨタ方式は2モータ方式ですので、複雑なメカニズムがあります。複雑なメカニズムは摩擦などでエネルギー伝達ロスが発生します。高効率を実現するためには、各部のロスを最小限にすることです。ここに、今まで理想的とされてきたトヨタHVシステムの課題が見えてきました。 今まで、一番良い方式と考えられてきたシステムも完全無欠なものはありません。 ある条件の下では、他より良いという事であり、諸条件が変われば、一番が一番でなくなることはよくあることです。 日産は、EV(電気自動車)のリーフを早くから商品化していました。しかし、EVはモータと電池しか積んでいませんので、リチュウムイオン電池の容量と、コストの課題があり、なかなか大量販売に結びつかない状況で今まで細々販売してきました。EVの走行距離を伸ばすためには、大容量リチュウムイオン電池が必要ですが、まだコストが高く、車両価格も高止まり状態でした。 そこで、日産はリーフに、エンジンと発電機を積み、電池の容量は比較的小さくして、車両コストを引き下げ、ノートe-Powerを造ることに成功しました。 モータはその特性から走り出す際の加速感が素晴らしいのです。それはモータは停止状態から回転を始める時に最大トルクを発生するからです。回転数が上がるに従いトルクは下がります。 エンジンは逆で、回転数が低い状態ではトルクが弱く、回転数の上昇と共にトルクも馬力も上昇します。 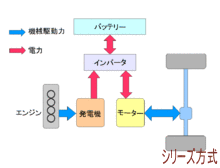 車が走るための必要なトルクは、モータの特性に良く似ているのです。だからEVは駆動特性的には理想的な方式ですが、バッテリーのコストと容量が問題でした。 車が走るための必要なトルクは、モータの特性に良く似ているのです。だからEVは駆動特性的には理想的な方式ですが、バッテリーのコストと容量が問題でした。それをエンジンとリチュウムイオン電池を積むことでシリーズハイブリッド化し、うまくEVの課題を解決し、商品化したのが、ノートe-Powerという訳です。 2018年の普通乗用車部門でベストセラーカーになり、アクアやプリウスを上回る販売を行い、一躍有名になりました。 (余談)2018年は、軽を含めれば、ホンダN-BOXがダントツですが、・・。 このシリーズ方式が構造的にシンプルで、伝達ロスが少なくトヨタの特許の壁に抵触せず、素晴らしいHVができる証明をしたのです。 HVシステムを構成するメカニズム等の部品点数も少なくて済み、トヨタ方式からシリーズハイブリッド方式に移行する時期にきたと思います。 トヨタが一人勝ちしていたHVは、新しい時代が来たとも言えます。 ホンダの技術発表資料(2013年6月)より、 「SPORT HYBRID i-MMD」は、高い環境性能と走りの楽しさを実現したハイブリッドシステムです。環境性能と走りを両立するため、駆動用と発電用の2つのモーターを搭載。さらに高効率のエンジンを組み合わせることで、状況に応じてそれぞれを自由に動かせる構造にしました。発進を含む低速走行から高速走行までの全域で、モーターがタイヤに直接駆動力を伝えるレスポンスに優れた走りを基本としています。バッテリーの充電状況などに応じて、高速クルージング時は、エンジンがタイヤを直接駆動するモードに切り換えることもあります。2つのモーターとエンジンを独立して動かせるという自由度が高いシステムによって、あらゆるシーンで高効率な走りを実現しています。 「SPORT HYBRID i-MMD」は、駆動用モーターと発電用モーターの2つのモーターを備えた2モーター・ハイブリッドです。駆動用モーターは、駆動軸と直結した構造となっており減速時には回生を行います。一方、発電用モーターは、エンジンと直結しています。特徴は、動力をミックスさせるための複雑な機構やトランスミッションが介在しない、シンプルなシステムに仕上げたこと。これにより駆動時には、複雑な機構を介したフリクションロスとは無縁の、高効率でモーターの持ち味を生かしたスムーズな駆動を実現しています。エンジンを利用して発電する際も同様で、発電用モーターをダイレクトに駆動することでロスを最小限に抑えています。
|
2019年2月3日(日)
車の顔つきの変化と好み
最近、自動車の顔つき(フロントデザイン)が大きく変わって来た。個人的には余り好きな顔がない。困ったことだ。『これ見よがしで、派手で、とにかく目立ちたい!』というメーカの意図が透けて見えるように思う。『そこまでやるか!』という顔つきが多い。 何事もやりすぎると世間の不評を買う。そういう意味で、最近、とても気になるのはトヨタ自動車のデザインだ。 何事もやりすぎると世間の不評を買う。そういう意味で、最近、とても気になるのはトヨタ自動車のデザインだ。その内でも、プリウスとクラウンが個人的には、全く好きでなく、評価に値しないと思っていた。これらの高級車を買う立場でないので、トヨタからすれば痛くもかゆくもない  話だが・・・。 話だが・・・。2018年フルモデルチェンジしたプリウスはやたらと尖った顔つきで、吊り上がった鋭い眼光の目付のヘッドライトと、シャープな直線を活かした車体のデザイン。 そしてここまでやるか!というのがクラウンのフロントグリルだ。レクサスまでクラウンのグリルデザインを踏襲している。どちらが先かは知らないが・・・・。 トヨタ自動車は豊田彰男社長が、一見おとなしそうな穏やかな顔つきの方だが、アグレッシブな人柄で、オーナー社長には珍しい改革派社長だ。  それにしても、2018年型のプリウスは一見、ペンギンの目のように吊り上がった目つきと、触ると切れそうなシャープなエッジラインを活かして、とても量産車とは思えなかった。(個人的な意見) それにしても、2018年型のプリウスは一見、ペンギンの目のように吊り上がった目つきと、触ると切れそうなシャープなエッジラインを活かして、とても量産車とは思えなかった。(個人的な意見)しかし、やはり、世の中の人も同じように考えていたようだ。 この『キーンルック』と言われる新型プリウスの売れ行きが以前より芳しくなかった。吊り目の顔はやり過ぎたようだ。 そこで、さすが財力に余裕のトヨタは、予定外のマイナーチェンジを実施。『キーンルック』の基調は変わらないがデザインを少し元に戻し親しみやすいデザインにし、昨年末から販売している。その後の売れ行きはまだ分からない。 キャッチコピーは『親しみやすい、あなたに応えた』とカタログに書いている。 目立ち過ぎるデザインが売れないとは言わないが、『デザインはユーザに共感を呼ぶものでないと、メーカの独りよがりでは、お客様はついて行かない』という教訓をトヨタは学んだのではないか。  それにしても、最近、自動車の顔は目を引く。 それにしても、最近、自動車の顔は目を引く。その理由がある。 要は人の顔と同様に、顔つきを決定するのは、目付である。 人の目に相当する車のヘッドライトのデザインの自由度が大きく広がったことにある。 電球(ハロゲンやHID放電管)がLEDに変わったことがその理由だ。 LEDは、発光部が5mm×5mmほど(上の写真の黄色の部分)と極小さく、薄く、このチップをいくつか並べて必要な明るさを得ている。 消費電力はハロゲンランプの1/10程度で、HIDに比べても1/3以下という低い消費電力で、同等の明るさが得られる。LEDは点灯中、あまり熱を出さないので、狭い場所や、ランプを薄くし取り付けるうことが可能になった。 しかし、LEDは半導体で、基本的には熱に弱いので、少しの発熱でも寿命が短くなったり破壊される。そこで、LEDから出る熱を逃がすために、上の写真のようなアルミの放熱器や、小さな冷却用ファンを取付けたり見えない部分で対策が施されている。 このようなLEDの特性を生かして、LEDをいくつか列に並べて、ヘッドライトが丸型から細長くしたり、電球では実現できなかったデザインが自由にできるようになった。 目に当たるヘッドライトが自由に配置できると、フロント部のデザインが自由にできる。そこで自動車メーカのデザイナーは従来の制約から解放され、自在なデザインができるようになった。そうなると、我も我もと奇抜なデザインが生まれるようになり、現在のような顔つきになった。 LEDは、寿命が4万時間と長く、電球の10倍ほどで、また電力消費が数ワットなので、昼間も常時点灯してもバッテリーに負担が余りかからないので、今後、エンジンをかけると点灯するデイライトが増えるはず。 北欧は昼間も薄暗い季節があるので、今までもボルボはエンジンをかけると、ヘッドライトが点灯するようになっていたが、これがLEDになれば省エネにも寄与することになる。 それにしても、ヘッドライト同様に、空気取り入れ口のグリルの部分のデザインも必要以上に大きく口をはったようなデザインが増えている。 マツダのCXシリーズや、クラウンや、ワンボックス車等は異様な気がする。 工業デザインは、機能を満たしつつ、きれいさを表現するものだと思ってきたが、最近の自動車メーカのデザインは、目立ちたがり屋さんが多いようだ。 ドイツのVWやベンツやBMWなどは、今も落ち着いた綺麗さを維持している。 |
2018年12月18日(火)
新型インサイトに試乗した感想は?
| ホンダは、12月14日、新型インサイトを発売しました。 インサイトはハイブリッド専用車で 、トヨタのプリウスと同じ位置づけの車でしたが、トヨタの2モータとガソリンエンジンを動力分割機構として遊星歯車をうまく使った最適トルク制御するハイブリッド方式にはかなわず、ついに市場から姿を消していました。 これは世界のトヨタの凄いところで、特許を抑えたこのハイブリッドシステムはどのメーカも追いつけないほど完成度の高いものです。 トヨタのプリウスは第4世代になり、『キーンルック』と呼ぶ超斬新?なデザインで販売されましたが、余りにも奇をてらったデザインは、賛否が分かれ売れ行きが伸びず、ついにフロントとリアのデザインを大幅に変更した予定外のマイナーチェンジを行い、発売されました。 新型ハイブリッドは従来のプリウスの顔つきに戻した感じがあります。 トヨタですら、こういう失敗があるのですね!。  写真はマイナーチェンジされた新型プリウス 写真はマイナーチェンジされた新型プリウスホンダは下記の4種類のハイブリッドシステムを有しています。 ・ IMA方式 ・ i-DCD方式 ・ i-MMD方式 ・ SH-AWD方式 一番シンプルなものは、IMA方式で、エンジンのクランクシャフトにモータを取り着けた構造で、これは初代フィットハイブリッド車に搭載しました。インサイトも同じIMA方式でした。現在もスバルや一部メーカで、これと同じ方式を採用している車が売られていますが、燃費はあまりよくありません。通称、マイルドハイブリッドと呼ばれています。 このIMA方式は常にモータとエンジンが一体としてつながっているので、相互に負荷がかかり、燃費は余り良くありません。 初代のインサイトは完全にプリウスに打ちのめされ生産中止になり消えました。 フィットも同じIMA方式でしたが、5年前に、7速ダイレクトクラッチというドイツ製の特殊な変速機を搭載し、第2世代のハイブリッドとしてi-DCD方式を開発しました。 これは1モータでありながら、エンジンとモータをクラッチで断続するので、燃費は格段に良くなりましたが、ダイレクトクラッチ(変速ギアー)の複雑な制御プログラムのソフトウェアに手こずり、5回もリコールを繰り返しました。 ホンダは売れ筋のフィットで味噌をつけてしまい、その後、フィット3は苦戦しました。 トヨタはプリウスの大成功をもとにして、さらに小型のアクアを発売し、ベストセラーになりました。フィットはさらに置いてきぼりを食った形で推移しました。 このフィット3は、アクア対抗馬として、発売を急ぐあまり、車の品質が十分練られていない状態で市場に出したのだと思います。私は初代のハイブリッドIMA(フィット2)からこの車(フィット3)に乗り換え、現在も乗り続けていますが、ホンダに対する信頼が薄らいだことは事実です。 5回もリコールを受け、やっと落ち着いたのですが、つい最近、走行中に『ぎくしゃくする動き』が出てきたので、ディーラで対策済みのダイレクトクラッチに載せ替えてもらいました。その後は調子よく軽快に走るようになりました。現在売られているフィット4ハイブリッドは素晴らしく改善され、良くなっています。 そういう経過で、私は、初代IMD方式から2代目i-DCD方式にフィットを乗り続けてきました。 確かにi-DCD方式の車の燃費は良くなり、高速道路走行では29km/Lという高燃費を出しますが、近くでチョイ乗りしても結構いい燃費です。全走行距離約2万kmの平均燃費は20km/L超になっています。 これらの経過について、このCar Lifeでも詳しく書いていますので、ご興味のある方は、この下に続く以前の記事を読んで下さい。 さて、12月14日、久々にインサイトが復活、販売されましたのでディーラに行き、今日(18日)、試乗させてもらいました。その感想を書きます。  まず外観は、流れるようなラインで、奇をてらわない落ち着きを持っています。 まず外観は、流れるようなラインで、奇をてらわない落ち着きを持っています。いわゆる高級車としての佇まいをしていますが、 でっかいというのが第一印象です。 インサイトはメイン市場をアメリカに置いて開発されたものですから、日本で使うには、正直デカすぎます。 プリウスより一回り大きいです。 ホンダは、真っ向からプリウス対抗車として打ち出したものではないことがよく分かります。造りも、値段も、プリウスより1ランク上級になっています。 ドアーの開閉音は、もどしっとした感じで、ピシッと閉まるという音です。ドアーの造りも気を配っていることがよく分かります。 乗り込んでみると、コクピットのように包み込まれた感じがします。これは運転席と助手席の間にあるセンターコンソールの性かも知れません。センターコンソールは幅と高さがあり、しっかり左右を分けています。 ハンドブレーキレバーや、パーキングブレーキペダルがないので、走り出す際にパーキングブレーキの解除をどうするのか? 一瞬迷いましたが、これは新型インサイトの新技術です。  よく見ると、センターボックスにいくつかのボタンが並んでいます。 よく見ると、センターボックスにいくつかのボタンが並んでいます。Pのボタンを押せば、電気式でパーキングブレーキがかかるのです。 発進はDボタンを押せば、パーキングブレーキが解除されます。 バックはRボタンを上にあげるとバックに入ります。全操作はボタンで行います  ハンドルにはたくさんの操作ボタンが左右に付いています。これに慣れるのは少々時間がかかりそうです。 ハンドルにはたくさんの操作ボタンが左右に付いています。これに慣れるのは少々時間がかかりそうです。ハンドルの輪っかに左右に適度のふくらみ(赤い○部)があり、これは走行中に指をかけるにはちょうどいい具合にハンドル操作ができます。 このふくらみは、インサイトが初めてではありません。 計器類(メータ部)は、下記のようにすっきりとした表示になっています。 いろんな情報が、ボタンで切り替えられるよう工夫されています。 ダッシュボードは、柔らかな厚みを感じるシートをミシンで縫った手の込んだ仕上げです。この辺に高級感を感じます。  さて、いよいよスタートですが、ブレーキペダルを踏んで、スタートボタンを押すとメータの針が一瞬大きく振れます。すぐに元の位置に針が戻り、車のセットアップができたことを示します。 さて、いよいよスタートですが、ブレーキペダルを踏んで、スタートボタンを押すとメータの針が一瞬大きく振れます。すぐに元の位置に針が戻り、車のセットアップができたことを示します。いよいよDボタンを押し、アクセルを軽く踏むと、音もなくスーッと発進します。エンジン音も、モータ音のヒューンという音も聞こえません。 静寂の内に車が走り出す感じです。 以前、アコードハイブリッドに試乗した時は、モータのヒューンという回転音が、いやに耳につきました。このインサイトはそのもーた音すら全く聞こえませんでした。 モータのトルクリップルを改善したのか、車体の気密性を良くしたのか、防音性能を上げたのか分かりませんが、いずれにしても実に静かです。 室内はテレビ番組の会話の声がクリアに聞こえました。最近、耳が衰えて、テレビ音声が聞き取りにくいのですが、車内でこういう明瞭なテレビの音を聞いたことがないくらいクリアーに聞こえました。大変印象に残ったことです。 エコモードで、アクセルペダルを軽く踏むと、スムーズに走り出す感じで、飛びだすような加速感ではありません。個人的にはフィットに乗っている感じからすると、もう少しアクセルに対する反応を良くした方がいいのではないかと思いました。アクセルを踏み込めば、なめらかに加速してゆきます。 この点はフィット3ハイブリドのぎくしゃくした加速感とは全く違うものです。 ブレーキを踏めば、実になめらかに減速して、スムーズなブレーキの効き方でした。 フィット3の場合は、ブレーキもアクセルも、ぎくしゃく感が残っています。 道路の凸凹面に対しても、突き上げる感じがなく自然な感じでした。フィットはコツコツした突き上げ感が残り、タイヤの上下が車内に伝わるようで衝撃吸収のレベルの違いを感じました。 高速走行はしていませんが、一般道路を30分ほど走った感じでは社内の静かさ、道路から拾うロードノイズが低く抑え込まれています。 一番安いグレードで、326万円ですから、決して安くはありませんが、それだけの価値があると思います。 このようなビッグサイズの車を乗りまわす年齢ではなくなりましたので、やはり本命は新型フィット2モータ i-MMDハイブリッドです。 来年9月頃?に、このインサイトに搭載したものと同じi-MMD方式が、フィットに搭載されます。エンジンは同じ1500CCです。 モータは車体重量が軽くなる分、小型化されるかもしれませんが、量産は同じものを造る方が品質が安定しコストダウンもできますから、全く同じエンジンと、2モータと、バッテリーを積めば、次期フィットは凄い車になることは間違いないと思います。 燃費は40km/Lを越す可能性もあります。 発売まで半年以上ありますので、インサイトでバグ出しをしっかりやって、その結果を反映したものにすれば次期フィットは安心して買えると期待しています。 ぜひ、ホンダさんに現行フィットの罪滅ぼしをしてほしいものです。 一言で言えば、インサイトはサイズは別とすれば、よくできていると思いました。 |
2018年12月2日(日)
SKYACTIVEエンジンで、マツダが超元気です!
| 今年のプロ野球、セントラルはマツダ広島が昨年に引き続き優勝しました。 以前はパッとしなかった地方球団というイメージでしたが、近年、プロ野球はセ・パを通じて、赤ヘル軍団が気を吐いています。同様に、自動車業界でも、マツダがエンジンで次々と気を吐いて、超元気です! その一端を紹介します。 ロータリーエンジンは世界で唯一、実用車に搭載し世の中をアッと言わせました。 先般、東京に行った際に、明治150年記念の日本の『千の技術博』を見てきましたが、その展示の一つにロータリーエンジンが誇らしげに置かれていました。 このロータリーエンジンは不運にも発売後、原油高になり、超高性能なエンジンでありながら燃費が悪く、次第に売れなくなり、ついに販売中止になりました。 しかし、マツダのエンジン開発に掛ける熱き心は生き続けていたようです。 最近、Skyactiveというシリーズの呼称で世界を再び驚嘆させています。 ホンダは創業者、本田総一郎氏がバイクの生産から初めて、四輪自動車に進出し、独自のエンジン開発で気を吐いていましたが、最近は少しおとなしくなっています。 そのお株を奪ったのがマツダと言えるでしょう。 決してホンダのエンジンが劣っているとは思いませんが、マツダはエンジンの基本的な課題を一つ一つ克服してきたという面で、訴求力が強く、トヨタ、ニッサン、ホンダと肩を並べる自動車会社に成長してきたと思います。今や、エンジンのマツダです。 もう少し詳しく紹介します。 2017年8月8日、次世代ガソリンエンジン「SKYACTIV-X」を公表 それは、ガソリンエンジン(SKYACTIV-G)の「高温高圧場での異常燃焼(ノッキング)の限界への挑戦」 と、ディーゼルエンジン(SKYACTIV-D) の「低温低圧場での着火性(失火)の限界への挑戦」の物語です。 エンジンは空気・燃焼ガス・燃料を圧縮し、そこに火をつけて燃焼させることで回転力を得る仕組みです。理論上は、よりたくさんの気体でより大きく圧縮して燃焼させればさせるほど、より大きな力が得られますが、それがうまくいかないのです。 ガソリンエンジンと、ジーゼルエンジンの特性が違うので、高圧縮比にすると異常燃焼が起きるガソリンエンジンと、 低圧縮比にすると失火が起きるディーゼルエンジン。 この相反とも言える課題に挑戦する中で、次世代ガソリンエンジン「SKYACTIV-X」誕生に向けて技術力が鍛えられてきたのです。 その課題とは? 一つ目は「異常燃焼しやすい」という性質を逆手にとって利用した。 SKYACTIV-Xは、たくさんの気体を強い力で 圧縮して点火プラグで火を付けると、シリンダー内で多数の火種がすばやく燃焼(圧縮着火)し、大きなエネルギーを得られる仕組みです。高圧縮状態で火種を自着火させるという穏やかな異常燃焼のような現象を利用しています。 二つ目はシリンダー内の気体と燃料(ガソリン)のバランスです。 シリンダー内では、空気と、燃焼ガスと、燃料の混じった混合気を作り、混合気における気体の割合が大きければ大きいほど燃費は良くなります。 SKYACTIV-Xは、従来のエンジンより大幅に気体の割合を大きくすることに成功 外気温度や、高度、走行状況など車の利用環境が異なる中、安定的に狙ったとおりの燃焼を実現することが大きな課題。 ガソリンは温度、圧力の条件が合えば圧縮着火で元気に燃えますが、条件が合わないと燃えない。しかも気体の量を増やして燃料の割合が少なくなるとさらに燃えにくい。 外気温度などの環境に合わせて、多くの気体を取り入れて、決められた燃料で狙い通りに燃える環境をエンジンの一回の燃焼ごとに、全運転領域で精密につくり込めることが課題だった。 この課題を追求するためコンピューターによる燃焼シュミレーション(CAE)だった。 複雑で新しい燃焼をつくり込むには、燃焼室内の様子を正確に模擬すること。 ありたいお手本の燃焼を計算により定めて、その通りに現実の世界で燃やすという 「モデルベース 開発」を行うためのものです。 従来のエンジン開発は、エンジンの試作機をたくさん造ってテストを繰り返すという時間のかかる仕事でした。 一つの条件の燃やし方でも組み合わせが何千万通りもあるこのエンジンでは、このようなテストの進め方では、全く開発が進みません。モデルベース開発を行うことで、開発の効率が飛躍的に高まりました。 さらに原理原則の基盤技術の開発はシミュレーションの精度も上げながら、ガソリンが元気に燃える火加減を実現しました。ここで得られた知見をまとめて、レシピのようなものをつくって、それをモデルにしてエンジン制御するコンピュータープログラムに実装しました。 その結果、歴代のガソリンエンジン技術者が追い求めて来た圧縮着火技術が盛り込まれたSPCCI (火花点火制御圧縮着火)をエンジンシステムとして完成させました。 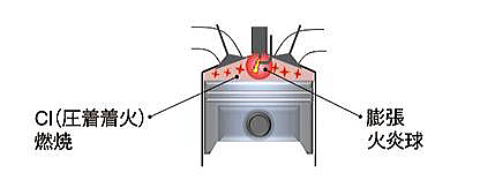 SPCCI (SPark Controlled Compression Ignition)火花点火制御圧縮着火 スパークプラグの点火による膨張火炎球が、まさに第 二のピストン(エアピストン)のように 燃焼室内の混合気を追加圧縮し、圧縮着火に必要な環境を実現しました。 このスパークプラグの点火時期を制御することで、圧縮着火領域を拡大し、完全に制御された圧縮着火を実現させることがマツダ独自の燃焼方式 SPCCI。圧縮着火燃焼を火花点火で制御した燃焼です。 この画期的なガソリンエンジンは、従来のガソリンエンジンの効率を大きく上回るそうで、燃費が2,3割改善されるということです。そうなれば、HV(ハイブリッド)車などと同様の燃費になることが予想されます。 このSKYACTIVE-Xエンジンは、マツダのヒット車であるCX-***シリーズの小型車、CX-3のモデルチェンジ車に近々搭載されるようです。エンジンの出来栄えと同時に、燃費や、車としての完成度の高さがどうか注目したいと思います。  上の写真はCX-3現モデル 下の写真はNEW Model CX-3 マツダの最近のデザインも注目を浴びている。下の写真はNEW Model CX-3で、上下のデザインを比べると、新型車は直線(平面)部が全くない、全て曲線や曲面で構成された塊り感を演出している。エンジングリルのジンベーザメ(小生の付けた字名)は個人的には好きではないが、曲面構成の柔らかさや温かみの感じは伝わってくる。  このSKYACTIVE-Xエンジンを使ったハイブリッド車を造れば、一層燃費改善ができる。さらに、ロータリーエンジンを復活させて、ハイブリッド車を造ることも視野にあるらしい。 マツダはこのことを否定せず、エンジンの高効率化はハイブリッド車にも一層寄与するという考え方。 既にトヨタ自動車と提携し、トヨタ方式ハイブリッドシステムを導入しています。 内燃機関としてのエンジンの改善は留まることを知らず日進月歩の世界です。マツダのSKYACTIVE-Xに刺激されて、他の自動車メーカもさらに素晴らしいエンジン開発を進めると思います。その一つが日産の可変圧縮エンジンです。 日本の摺合せ技術の塊と言えるエンジン開発は世界をリードし続けると思います。 |
2018年10月24日(水)
ダイソンがEVを開発中、商品化が間近?
| 羽根のない扇風機で世の中をあっと言わせたダイソンが今度はEV(電気自動車)を開発中というニュースです。 以前、『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えたか?』(経営における「アート」と「サイエンス」)という山口周氏の著書を紹介した。その中に、アップルのスティーブ・ジョブズ氏と、ダイソン氏と、ソニーの創立者、井深さんが紹介されていた。この本にホンダの本田総一郎氏や松下幸之助氏はなかったと思うが、要はモノづくりに於いて、従来の延長線の発想ではなく、『人』の心を揺さぶる、琴線に触れる何を提供できるかどうかと言う問いかけだ。  その内の一人が英国のジェームズ・ダイソン氏だ。『ダイソン』と言えば、ジャパネット高田がテレビショッピングや新聞で盛んに取り上げている掃除機や、扇風機や、ヘアドライヤーがある。創業は1993年というから、会社を立ち上げて20年余りの若々しい会社だ。 その内の一人が英国のジェームズ・ダイソン氏だ。『ダイソン』と言えば、ジャパネット高田がテレビショッピングや新聞で盛んに取り上げている掃除機や、扇風機や、ヘアドライヤーがある。創業は1993年というから、会社を立ち上げて20年余りの若々しい会社だ。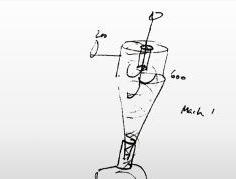 ダイソン社にはデザイナーが居ない。 ダイソン氏がイメージ・スケッチを書いて、設計者が商品デザインを完成するという手法を取っている。 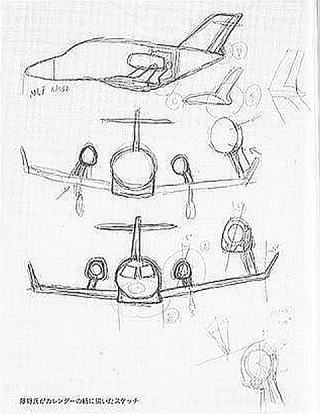  ホンダビジネスジェットの開発もこの手法でやった。 ホンダビジネスジェットは7人乗小型ジェット機であるが、ホンダのチーフエンジニアだった藤野さん(現在、ホンダエアークラフト社長)が温めていた主翼の上にエンジンを載せるという従来の航空機工学ではタブーとされてきたアイデアをスケッチし、チャレンジして大成功をおさめた。 従来のビジネスジェット機は、プロペラ機以外は以前のB727のように機体の後方に2個のジェットエンジンを取り付けていた。 ビジネスジェット機は旅客機のように主翼の下にエンジンをぶら下げる高さがないので、後部に取り付けるしか方法がなかった。 この場合、機体の主翼とエンジン取付け部の構造を強化しなければならず、機体重量がかさみ、その分、客室スペースが狭くなる。 一方、主翼上部にエンジンを取付けると、気流が乱れて安定性が悪くなくなるというのが従来の定説だった。藤野さんたちは実験を重ね、主翼上部のある一点にベストスポットがあることを発見した。これにより安定性、スピードアップ、静かさ、燃費、室内の広さ、デザインの新鮮さなど今までのビジネスジェットの概念を打ち破った。まさに技術者の執念である。 ホンダ魂、人のやらないことをやる藤野氏の勇気に敬服する。 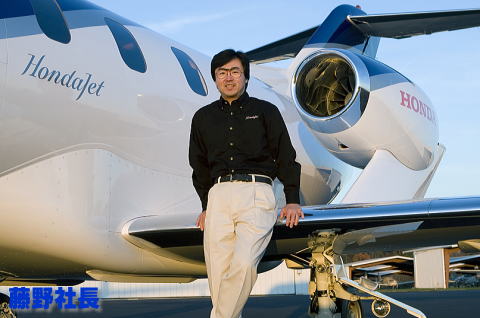 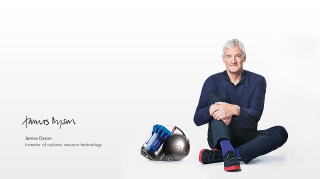 話を戻すと、ダイソンが会社の創立に至った経緯は、1978年、家庭用掃除機は使用すると、次第に吸い込み力が落ちてくるのを何とか解決したいと考えていた。このことについて、ダイソンのホームページには次のように書かれている。 1978年 ジェームズ ・ダイソンは、当時使っていた掃除機の性能が低下することに不満を持ちました。掃除機を分解してみると、紙パックがゴミで目詰まりして、吸引力の低下を起こしているのだと気付きました。この解決法を探し求めていたある日、製材工場の屋根に木くずと空気を分離するサイクロン装置を見てひらめきました。 しかし、同じ原理が掃除機にも通用するか。5年と5,127台の試作品を経て、ジェームズは世界初のサイクロン掃除機の開発に成功しました。 その後、羽根のない扇風機、これを応用したヘアードライヤー等へ進出。これらの商品は従来の家電商品と明らかに一線を隔する商品で、一目見れば違いが分かる驚きがあった。 そのダイソンが2017年9月にEV(電気自動車)に進出すると発表した。しかも電池からモーター、車体まであらゆるパーツを自前で設計・開発する方針ということだ。 自動車は約4万点の部品で構成される複雑な商品だ。だからトヨタ自動車を見れば分かるが、創立は1937年(昭和12年)で、約80年前になる。これは自動車はエンジンが主体で、機構部品の塊の商品だから、技術やノウハウの積み上げがモノを言う産業だった。一朝一夕にできる事業ではないというのが常識だ。 これはトヨタに関わらず、世界の有名な自動車メーカは同様な歴史をもつ。だから、自動車業界には今まで新規参入が少なく、急激な変化もなく、各社のノウハウを積みあげながら発展してきた。 最近になり、この自動車産業に新参者が現れた。 一つはアメリカのテスラであり、もう一つは、ダイソンと言うことになる。この2社以外にも中国やインドなどの新規参入を企てている会社が沢山現れてきている。 これは、この数年間の出来事であり、そういう新参のメーカは開発着手から、わずか数年で商品を発売すると言う考えられない速さで事業化を進めている。 なぜ、今まで何十年、いや100年近くかかって育ってきた自動車産業がわずか数年で開発し販売出来るようになったのか、その背景を見ることにする。 新参メーカが開発している車はすべてエンジンを使わないEV(電気自動車)である。 EVは車体とモータ、バッテリー、制御電子回路を組み合わせた車だ。この内、モータ、バッテリー、制御電子回路は電気・電子部品である。車体のみが構造部品と言える。 この車体は、車体(シャーシー)や、懸架装置(クッション)や制動装置(ブレーキ)や、ドアやハンドルなどの部品に分かれるが、これらの設計はエンジンを作る技術ノウハウや信頼性設計から考えると、はるかに優しい課題だ。 車の仕上がりについていえば、ハンドリングのよさや、車体の強度、静かさ、衝突安全性、乗り心地の良さ等、いろんな面の条件を満たさなければならない。 しかし、最近のコンピュータを使った設計支援ツールを使えば、従来の設計者が長年も苦労して積み上げてきた固有技術やノウハウをあっという間に習得できる。 だからCAD(コンピュータを使った設計)や、CAE(コンピュータを使った解析)やCAM (コンピュータを使った金型設計)など、コンピュータを駆使すれば、人手の数十倍の速さで、手書き図面もなくデータ処理だけで試作品を作らないで金型を彫り、量産用部品まで作ってしまう。しかもミスがない。 こういう開発手法を『デジタルモノづくり』という言い方もあるが、既存の自動車メーカはもちろん、新参入の会社もIT(コンピュータを使った幅広い技術)の導入をはかり、活用している。 ダイソンはコードレス掃除機で、高効率モーターと、充電式バッテリーと、それを制御する電子制御技術ノウハウを確立し保有しているので、EVの3つの要素を掴んでいる。だから、ダイソンは車体さえ設計出来れば、EVを作る要素技術は自前で持っていると言える。現実は車づくりはそう簡単ではないが・・・。 米国のテスラがEV車を造りつつあるが、量産をするノウハウはまだまだ未熟で、なかなか思うように製造ラインが動いていない。 ダイソンから見れば、成熟化した家電商品、しかも扇風機や掃除機で大ブレークして、今や売上が5100億円、営業利益が1180億円の企業に成長した。この実績をベースとして、潤沢な資金をEV開発に積極的に投資している。 ダイソンは、モータは高効率で高速回転(12万5千回転/毎分)のモータを新製品V10の掃除機で搭載した。さらに一度充電すると、60分間連続して使える大容量電池も開発した。EVにはそういう自前の技術を生かし、特に電池は自動車用に「全個体電池」と呼ぶ大容量で、安全性が高く長寿命の次世代型電池を開発し搭載すると言われている。 工場はシンガポールに2900億円を投資し、2020年までに建設し、テストコースは英国南部の本社近くに290億円を投じる。 果たして、この計画が奏功するかどうかが見ものだ。 さらに、ダイヘンが造るEVはまだ形が分からないが、あっという新時代のデザインを提示してくれるかもしれない。 その期待は、ホンダジェットが主翼の上にエンジンを載せたと同様に、思いもよらない姿で産まれるかもしれない。 もし、これがうまく行くなら、既存メーカは『何をやっていたのか?』と言われかねない自動車業界のアキレス腱を見る思いがする。 あと2年足らずで、その成果が見える。 |
2018年10月7日(日)
自動車産業の苦悩! 伸び率が縮む市場!
| 日経新聞 朝刊に『縮む新車市場、世界で成長率半減 保護主義を誘発』という記事が掲載されている。 トヨタ自動車は現在ある5つの販売チャンネル(お店)をレクサスを除き、1つにまとめると発表した。トヨタ店、トヨペット店、カローラ店、ビスタ店、トヨタオート店だが、ビスタとオート店が合併してネッツトヨタ店に変わっていたので、コローラ、トヨタ、トヨペット、ネッツ店が一つになる勘定だ。トヨタは40%を超える高いシェアを誇ったのも、この販売店のきめ細かなサービスが車の品質の高さと相まって、顧客に信頼されてきた。 その販売店が、全店で同じ全車種を扱えるようになる。当然、トヨタ系列の店同士の生き残りをかけた食い合いが始まる。互いに値引き競争になる場合も生じる。 しかし、その危険性を押してまで、店を統合する決意に至ったのは、余程の危機感が漂っている証拠だ。しかも現在の60車種を2020年半ばまでに半減し30車種に絞り込むそうだ。集中と選択による経営資源の効率化の取り組みになるが、それが果たして奏功するだろうか? 確かに、覚えられないほどたくさんの車種が必要かと思うほど、チョイ換えの車が沢山あったのは事実だ。『下手な鉄砲、数撃ちゃ、当たる』からの脱却。いや、トヨタは下手な鉄砲ではなく、上手な鉄砲だった。 いずれにしても世界NO.1かNO.2のトヨタですら、このようなドラスティックな販売チャンネルの見直しや統合、車種の絞り込みをしなければ生き残れないと判断したようだ。 先日、東京に行った際、杉並の娘のマンションに立ち寄った。このマンションは2、3年前に新築した建物で駐車場に、BMWやベンツやボルボなどの高級外車がずらりと並んでいた。それを見て『すごいな!どんな人が住んでいるのかな』と思っていた。 それが、先日行った時、外車と並んで、何と軽自動車が駐車していた。住民が入れ替わったそうで、軽自動車を乗る人に変わった。これは住民の所得が落ちたとは必ずしも言えないようだ。 聞いてみると入居者の内、3割ほどの家族が海外赴任等で売り払っている。その後に入ってくる人は、どういうわけか年配者が結構いるそうだ。 マンションは人に賃貸すると、帰国した際に相当多額の修理・修繕が要るらしい。 それなら、賃貸に出すより売り払って、帰国した時に新しい家を買う方がいいというのが、今時の人の考え方らしい。 マンションの話をするつもりではなく外車が軽自動車に変わったことを言いたかった。 この場所は東京23区内でも、建築の高さ規制がされているので高層マンションは全くない。静かで住環境がよく、都内でも人気が高い場所だ。 街中の一角に、BMWの大きな販売店があり、今まで何回かその店の横を歩いて通り過ぎマンションに行ったが、店内を見ると新車と並んで、BMWの中古車で、きれいな車が120万円とかで売っている。これなら買えるなという値段だ。すぐ近くにはベンツの販売店もあり、住宅街の近くに外車の店が建ち並ぶほど需要があるのだなぁ!と感心した。 しかし、東京都内でも次第に軽自動車が増えてきているような気がする。自動車の販売ランキングを見ると、1位から3位、4位あたりまで軽自動車で占められている。直接軽自動車を持たないトヨタ自動車、ニッサン自動車などはこれに危機を抱いている。 (もちろん、OEMなどで軽自動車も売ってはいるが、・・・) 一昨日、トヨタ自動車の豊田社長とソフトバンクの孫さんが自動運転車の開発で開発会社を共同で設立する発表があり、二人が仲良く握手する姿をテレビ中継していた。 今後、10年ほどで、自動車の姿が大きく変わり、自動車会社は今、大きな曲がり角に差し掛かっている。 自動運転という技術的な課題だけではなく、肝心の販売が伸びなくなってきたことが悩みだ。加えてカーシェアリングが増えてきたので、自家用車を所有するという感覚が都市部を中心に次第に変わってきた。クルマの所有はステイタスではなくなった。 さらに、世界的に、既にアメリカの自動車の販売は成熟化して伸びは期待できない。今後、中国に期待したいと思っていた矢先に、中国の販売も鈍化してきたようだ。 そうなると、パイが一定の中での食い合いが始まる。アメリカは自国の市場は高い関税をかけて保護する動きを始めている。 世界がグローバル化、ボーダレス化する中で、逆行するような動きに見える。 車は、一方でEVや自動運転に対する多額の開発コストを負担しながら、市場は成熟化し、カーシェアリングという使い方が増えると、ますます新車の販売は難しくなる。 今後、どういう展開になるのか、各社の動きに注目したい。 日経新聞の記事の一部を紹介すると、 世界の自動車市場が転機を迎える。 2018~25年までの新車販売の年平均成長率は約2%と、約4%を維持した11年以降から半減する。主な原因は2つ。 カーシェアなどデジタル化の流れと、二大市場である米中の急減速だ。 成長を前提としてきた自動車産業は不透明な時代に入る。 中国の新車市場は18~25年の年平均成長率が2.6%と、11~17年の8%から急減。 米国を抜き世界最大市場に躍り出たが、都市部の市場飽和や地方経済の停滞でブレーキがかかる。投資を抑えなければ、鉄や造船のように生産過剰を招きかねない。 中国だけではない。25年の世界販売は1億1000万台程度と、17年比で約1600万台増える見通し。18~25年の年平均成長率は2.0%。11~17年の3.7%からほぼ半減することになる。 変節の一因はデジタル化による構造変化だ。 米グーグルやアップルなど世界のIT大手が自動運転技術で攻勢をかける。その先には、車を所有せずに共有するカーシェアの普及が現実味を帯びる。 30年までに人々の移動距離の最大37%がカーシェアや自動運転車が占めるようになるという話もある。 特に先進国で影響が大きい。 日本の年率は11~17年の3.7%増から18~25年には1.5%減になると予想。北米5.3%増から0%に減速する見通しだ。 「北米自由貿易協定(NAFTA)は米国から雇用を奪ってきた」。 トランプ米大統領はNAFTAの見直しでカナダ、メキシコと新協定を結ぶなど生産の米国回帰の果実をもぎ取りつつある。 自動車産業のすそ野は広く、米国では700万人以上の雇用を創出している。何も手を打たなければ自動車産業が空洞化し、雇用減や消費の減退に陥る危機感が保護主義を誘発している。 トランプ政権は中国との貿易戦争でも矛を収める気配を見せない。米中などの関税引き上げで貿易コストが上がり、世界の国内総生産(GDP)が1.4%下がる試算もある。 自動車の成長力の落ち込みで、保護主義がほかの国に広がる恐れも否定できない。 成長率の減速は、限られたパイの奪い合いを通じ優勝劣敗をより明確にする。 自動車各社は5~10年後の競争力を分ける転換点に立っている。 自動車産業は、すそ野が広い産業分野と言われるので、自動車産業が停滞するようなことが起きれば、世界の景気は急にしぼむと考えられる。 そうなって欲しくないが、いつまでも現在の豊かな時代は続くと考えにくい面もある。 |
2018年8月12日(日)
我が家のFIT3・ハイブリッドが新メカに載せ替え!
| 先日、猛暑の昼間、枚方市内を走行中、信号待ちから発進しようとアクセルを踏むと、エンジンが吹き上がり、加速が鈍い感じがして『おかしいな?』と思いつつ、慎重に走ったが、街中の運転中に変速動作がぎくしゃくして、どうやらクラッチが滑っているような症状が現れた。 家に帰る途中に、通称『地獄坂』と呼ぶ急な坂があるが、そこでもエンジンの吹き上がる症状が出た。この症状はこの車を買った5年前に出た症状に近い感じだ。 そこで、いつも世話になっているホンダ交野(ディーラ)の営業のYさんに電話したところ、「一度、車を見せて頂きたい」という話だったので、すぐに店に向かった。その日は土曜日で、店のイベントがあり、沢山の顧客が来店するので、サービスも時間が取れないという話だった。そこで、FIT3ハイブリッドのマイナーチェンジされた最新の車を代車として貸してもらった。夜、サービスの方から電話があり、「試乗した結果、症状が確認できたので、メーカと相談して対応を決めるので少し時間が欲しい」という話だった。手元には新車の代車があるので、「急がないので、完全に直してくれ!」と頼んで電話を切った。 あくる日、営業のYさんから再び電話があり、DC(ダイレクトクラッチ)を最新のものに載せ替えるので、3日ほどかかるという話だった。このメカはフィット3ハイブリッドで初めて採用した新メカで、購入当時にリコールがかかった曰く因縁つきの部品だ。『やっぱりそうだったのか!』という気がした。 一方、マイナーチェンジされた最新の代車で、和歌山の有田の家内の実家のおばあちゃんを見舞いに出かけた。おばあちゃんが高齢になったので、月に一度、見舞いに有田に通っている。 代車のFIT3 ハイブリッド(後期型)は、まず走行音が大変静かになっている。走行中の道路の継ぎ目の音や振動が低く抑えられている。高速道路走行中にラジオを聞いているが、自分の車に比べて放送が良く聞こえる。高校野球開催中だったので、往復の走行中はずっとNHKラジオを聞きながら走った。 ロードノイズ、タイヤの音が入ってこない分、静かになったが、その分、エンジンの回転音が少々気になるほどだった。これは中途半端なマイナーチェンジでなく、フルモデルチェンジ車のような改善が施されている。 自分の車は、ロードノイズが結構大きいので、エンジン音はマスクされてあまり気にならない。それくらい、マイナーチェンジ後の新型フィット・ハイブリッドは静かな車に変わっていた。このクラスでは飛び切り静かな車になったのではないかと思う。 もう一つ、『アダプティブ・クルーズコントロール』が非常に気に入った。 これは高速道路を走行中、クルーズコントロールスイッチをONすると、動作するが、自分のFITは、一般のクルーズコントロールしか付いていないので、常に一定の速度で走ることはできるが、前の車との車間距離がなくなると、ブレーキを踏まなければならない。代車の新型FIT3は、前を走る車との車間距離が狭まると、自動的にブレーキがかかり、車間距離を確保する仕組みになっている。前の車が加速して早く走り出すと、設定した速度まで自動的に加速して、前の車に追随する。アクセルやブレーキを操作しなくても、高速道路では安全に運転ができる。追突もしない。 もちろん、衝突防止や、レーンキープや、道路標識など、その他のいろんな安全システムも付いている。今まで、そういう安全装置は必要がないと思っていたが、自分が歳を重ねるとともに、この『ホンダセンシング』と呼ぶ安全運転支援装置が非常に有効で、これからの車には絶対必要な装置だと思うようになった。 アダプティブ・クルーズ・コントロールのおかげで、有田への往復300kmほど走っても、殆ど疲れずに済んだ。しかも、満タンにしてから300km走って、11.4リッターしか減っていなかった。燃費は26km/リッターだ。猛暑の昼間走るので、オートエアコンは23度に設定してガンガン冷房した。FIT3のエアコンは、モータ式コンプレッサーを搭載しているので、エンジンがストップしてもエアコンは動作し続けるので快適だ。 当初、トラぶってリコールを繰り返したi-DCDハイブリッドシステムのダイレクトクラッチ制御動作は、マイナーチェンジの改良で完全に問題は解決された。 力強い加速、スムーズなつながり、高燃費と大変素晴らしい車に仕上がった。 しかし、燃費競争は留まるところを知らずなので、今後、走りと燃費の両立が各社の腕の見せ所になるはず。 今のところ、ニッサンのノートe-Powerが半歩先に行っている感じがする。 さて、自分のFIT3ハイブリッドは先週末に修理が終わったという連絡をもらい、さっそく代車を返しにディーラに出かけた。 購入当初から問題のダイレクトクラッチ部分(ミッションのメカ部に相当)をそっくり載せ替える大修理をして頂いた。修理後の確認をするため、昨日、奈良の天川村まで走ってきた。殆ど国道や県道で、一部、京奈和高速道路の無料区間も走った。 途中、奈良市内の24号線は渋滞に巻き込まれた。片道約100kmの距離だったが2時間半ほどかかった。昨日も猛暑だったので、エアコンは23度に設定して走った。 天川村近辺に入ると、外気温は28度ぐらいまで下がった。山の日の休日だったので、家族連れでバーベキュウやキャンプや、修験僧(山伏)姿の人とも出会った。結構沢山の人出でびっくりした。 出発時にガソリンスタンドで満タンにしてから走り始めた。今まで問題だったエンジンとモータの切り替え時のショックや、ダイレクトクラッチの変速ショックは見事に直っていた。デーラーに聞いてみると、「エンジンとメカの制御プログラムも最新のものに書き替えました」という話だった。 これで良しだ! 早速、ホンダの営業のYさんに電話して、諸々の報告をした。 燃費は、一般道の走行で24Km/リッターだった。しばらく使って様子を見たいと思っている。 歴史に『もし?』はないが、この完成度の車を新発売時に売り出していたらFITは販売でアクアといい勝負をしたはずだ。残念ながら、5回のリコールが続き味噌をつけたので、なかなか販売は回復しない。クルマは決して悪くはない。むしろ素晴らしくなった。このことは長年、メーカに勤めた経験から分かる。 現在販売中のFIT3は大変素晴らしい車に生まれ変わった。マイナーチェンジではあるが、ものすごい力の入れようで、フロントデザインも大きく変更し、車体の補強部材を追加し、室内の床のシートを厚くした効果で走行音が実に静かになり、車体の剛性感が増し、しっかりした感じがある。ハンドルも一層軽くなり、道路の段差の通過時の突き上げ感もうまく吸収している。特に言うことなしだ。 欲を言うなら、もう一歩、走行時のエンジン音を下げてほしい。自分の車では気づかないようなエンジン音が相対的に浮かび上がって聞こえる。これは人の耳の性になるが、一方の音が小さくなると、他の音が浮かび上がって聞こえるという事。 今後の期待は、先日、日経EXに掲載されていたように、2019年下期にFIT4としてフルモデルチェンジが行われる。 FIT4ハイブリッドは、『2モータ方式(i-MMD)』を採用し、一層燃費が良くなる。噂では1リッターのガソリンで40km以上走ると言われている。そうなると、実走行でも30kmは優に超えるはず。しかも、EVのようにモータで走る方式なので、静かで、スタート時の加速がすこぶるいい。ノートe-Power以上に良くなるはずだ。 次のFIT4フルモデルチェンジは、ホンダが捲土重来をかけ満を持して発売する。 絶対失敗は許されない! しかも、最激戦区のこのゾーンはライバルを大きく引き離さなければ勝てないことは十分、分かっている。 それには、性能・品質・コストが勝負だ。品質はこなれた技術、部品を使うこと。 ①エンジンは、高性能1500ccの現行改良型 ②2モータ方式(i-MMD)は、アコード等で十分実証済 ③ホンダセンシングは、FIT3マイナーチェンジで搭載し実証済 ④新しい軽量化車体は、ノウハウを蓄積済み ⑤リチュウムイオン電池はFIT3やアコードで搭載して実証済み というようなことを考えると、次期フィットフルモデルチェンジはダントツに高品質な車になる。 来年が待ちどおしい!! |
![]()
2018年7月1日(日)
フィットのフルモデルチェンジが見えてきた!
| 月日の経つのは早いもので、ついこの前、正月を迎えたと思っている内にもう、今年も半分が過ぎた。この半年の間に世の中はいろんな出来事があった。 この数日、異常な暑さが続き、関東地方は6月末に梅雨が空けたという話だ。関西もこの分では、既に梅雨明けしているいるかもしれない。多分、一両日中に梅雨明け宣言が出される可能性が大きいと思う。 地球温暖化の性か、年々、夏の気温が高くなってきたような感じがする。日本も熱帯地方のような土砂降りの雨(シャワー)や、竜巻や、巨大な台風が襲ってくることが珍しくなくなった。地球温暖化の原因は、車の排気ガス中の二酸化炭素(炭酸ガス)が真綿のように地球を包み、地球から宇宙に熱が放散されるのを防ぐ温室効果という役割を果たしていると言われているが、便利さに慣れてしまった人間が元の状態に戻るという選択肢はなかなか取れない。そこで、技術開発により排気ガス濃度や量を減らす取り組みが行われている。 電力は最も人間の生活に不可欠なモノの一つであり、排気ガスを全く出さない原子力発電が環境に優しい発電だと言われ原発が推進されてきた。 しかし、原発は東日本大震災の津波で、福島第一原発が爆発事故を起こし、大量の放射能をまき散らし、周囲の環境を汚染し、家に戻れない人々が何万人もいる。 『原発は絶対安全だ!』と言う安全神話のもとに原発を推進をしてきたが、実は何事にも『絶対』という二文字はない。だから、事故が起きた場合にどうするかを考えておかなければならない。 これは『品質』と全く同じで、モノを造ったり、作業したり、人間が仕事や活動すれば、いくら注意しても、不良は発生する。不良ゼロはありえない。それでも、不良をゼロにする取り組みを続けている。 話が横道に逸れたが、車の排気ガスをできるだけ少なくして、環境汚染に対する負荷を下げる努力が続いています。その一つが、エンジンに動力を頼ってきたが、最近、急速にEVやハイブリッド車などに代わってきた。いろんな方式が開発され、各社は競って技術開発を行っている。 NO.1のトヨタ自動車は他社に先駆けて、ハイブリッド車の代名詞になった『プリウス』を世に出した。その宣伝キャッチコピーは『21世紀に間に合いました』という凄い表現だった。この初代プリウスはそれまでのエンジン車と比べダントツの低燃費を実現したが、加速が悪く、全く運転の面白味のないつまらない車だった。その理由は電池やモータや制御回路の未熟さによるもの。それが2世代、3世代、4世代目とモデルチェンジを繰り返す毎に、ガソリン車以上に走りの良い車に生まれ変わった。その間の技術の進歩はすごいの一言。 技術は、何もしないで進化することはない。 必ずモノを造って世に問うことで、そこにいろんな課題が見えてくる。その課題を解決するため技術者が一生懸命取り組む。それが技術進化につながる。人間の知恵には限界がありませんので、改善・改良がドンドン進み、目を見張る進化を遂げる。これは今まで、世の中の商品やインフラなどあらゆるものに言えることです。 さて本題に戻りますが、このCar Lifeのページに何回も書いてきたが、この10年ほど、ホンダのフィットに乗り続けてきた。ガソリン車のフィット1世代目(FIT1)、ハイブリッドの1世代目(FIT2)、そして今乗っているフィットハイブリッドの2世代目(FIT3)です。 現在、愛用しているフィット(FIT3)ハイブリッドは、5回もリコールが行われた。 これは前代未聞のこと。ホンダとしては大変恥ずかしい思いをしたと思う。 その理由は、日本で初めて採用したドイツ製の『ダイレクトクラッチ(DC)』という特殊な変速メカニズムを搭載したこと。ホンダの技術者はダイレクトクラッチに付いてノウハウが無いまま最量販車の新型フィット(FIT3・HV)に搭載した。 ホンダは人まねをしないことで有名ですが、モータ軸とエンジン軸を使い分けて、変速ギアの奇数段にモータ軸をつなぎ、偶数段にエンジン軸をつなぎ、変速ギヤーを切り替えるという構造のもの。発想は奇抜で良かったのです。 ダイレクトクラッチはドイツのフォルクスワーゲン(VW)等にも搭載せれています。 フォルクスワーゲンは普通のエンジン車で、従来のトランスミッションの代わりに搭載しているので、特殊な使い方ではありません。 ホンダはこともあろうに、モータとエンジンを分けて駆動するという発想のもとに採用したが、この変速制御プログラムや、エンジン制御プログラムは非常に複雑で、エンジンとモータの協調制御が十分こなれないまま発売してしまった。 当初、走り出す際に変速がぎくしゃくして乗り心地が悪く、坂を登る際に急にエンジンが吹き上がるという異常も発生した。そういう異常な運転時の状況をディーラに細かく伝え、結局、次から次に制御プログラムを書き換え、ソフトウェアのバージョンアップを行い、エンジン・モータ・ダイレクトクラッチギアー制御を改善して、何とか収まった。 しかし、今も、加速時やブレーキ動作のスムーズさに違和感が残っている。 その後、マイナーチェンジが行われ、何をどう変えて修正したのか分かりませんが、新しいHV車に試乗させてもらったところ、『これが同じフィットハイブリッドか?』と疑うほど軽快でスムーズな走りと、車内の走行音が極端に良くなった。 『やればできるじゃないか』と思った。 発売当初に、このマイナーチェンジ車の出来ばえであれば、フィットはアクアに十分対抗できる車になっていたと惜しまれる。 ホンダはハイブリッドシステムに4方式を開発し採用している。 ①フィット・ハイブリッド第1世代は、IMA (1モータ;補助型HV) ②フィット・ハイブリッド第2世代は、i-DCD (1モータ;ダイレクトクラッチHV) ③アコードなど高級ハイブリッドは、i-MMD (2モータ;シリーズ・パラレルHV) ④NXSやレジェンドの最高級車は、SH-AWD (3モータ;先進HV) 初代のIMAシステムは、エンジンシャフトとモータ―が直結されたシンプルな構造で、モータ駆動時にエンジンも連れて回すことになりロスが大きい。これでは燃費が大きく改善されません。モータは補助程度に働くシステムです。ただし、電動自転車と同じですので、走行感覚は大変スムーズ。 次はi-DCDシステムで、今乗っているフィット3ハイブリッドのシステム。  先日、和歌山まで走った際の片道、高速道路110km、一般道20km、全走行で130kmの燃費計表示は、平均燃費30.1km/L。高速道路の燃費は大変良い。このフィットハイブリッドシステムは、エンジンとモータをクラッチで切り離すことができるので、ロスが少なく、燃費は大幅に良くなった。 先日、和歌山まで走った際の片道、高速道路110km、一般道20km、全走行で130kmの燃費計表示は、平均燃費30.1km/L。高速道路の燃費は大変良い。このフィットハイブリッドシステムは、エンジンとモータをクラッチで切り離すことができるので、ロスが少なく、燃費は大幅に良くなった。①②のハイブリッドシステムはモータ一個で、モータが発電機の役割も兼ねる仕組みになっている。 トヨタのハイブリッドシステムは、基本的にすべて同じ方式で、発電機とモータを別々に積んだ2モータ方式です。これはシリーズ・パラレル方式(シリパラ方式)と呼ばれる。走行中の運動エネルギーを効率よく回生発電しバッテリーに充電します。エンジンとモータのいいところ取りをした方式。HVシステムの一つの完成系と言えるもの。さすがトヨタです。 このままでは、ホンダはトヨタの後塵を拝し続けることになります。 ホンダの技術屋に火をつけたのは、ニッサンノートのe-Powerと呼ぶシリーズ方式ハイブリッドです。 ニッサンe-Powerはトヨタと同じ2モータ方式ですが、システムの仕組みが大きく異なる。ガソリンエンジンは発電機を回すことに徹し、タイヤを直接駆動しません。 発電した電気はリチュウムイオン電池に充電しながら、走行は電池から電流を受けた走行用モータで行う。 動力の流れは下のように直線的につながっているので、シリーズ方式と呼びます。 エンジン⇒ 発電機⇒ リチュウムイオン電池⇒ 走行モータ⇒ 車軸⇒ タイヤ モータのトルク特性は車の走行の負荷特性とよく似た性質を持っているので、スタートから巡航速度に至るまでスムーズに車を走らせることができます。 しかも、ブレーキをかけると、運動エネルギーを効率よく回生して電池に充電する。 (ニッサンはアクセルペダルから足を放すと、回生発電でブレーキがかかるシステムを採用しています。これは日産のEVリーフと同じです) だから、車を走らせる面白さが損なわれず気持よく走ることができる。それが大変評判になり、このクラスの小型車のベストセラーカーになった。 お客さんはいいものを出せば、正しく評価してくれるという証拠です。 このトヨタ方式も、日産方式も、よく見ると課題・問題点がある。 その課題を解決し満を持して出すのが、2019年(来年)予定されているフィット・フルモデルチェンジの新型フィット4ハイブリッドです。 この新しいハイブリッドシステムは、既にオゼッセイやアコードなどに搭載して、その高い走行性能と、低燃費性能が実証されたシステムです。 新型フィット(FIT4)HVは2モータ方式で、エンジンは従来のフィットHVに搭載の1500ccエンジンです。このエンジンは軽やかに良く回り、馬力があり、低燃費で評価が高いものです。素晴らしいエンジンです。 新型フィット4ハイブリッドに搭載するハイブリッドシステムi-MM方式は十分実証されたものなので、新型フィット4はリコールもなく、発売時から大人気になると期待しています。 燃費は、40km/Lを優に超す43km/Lとうわさされるほど良くなるはず。 高速道路の燃費はハイブリッド方式とは関係なくガソリン車でも良い値を示します。 高速道路を一定の速度で走り続けるには、常に走行負荷に対する駆動エネルギーが必要です。平坦な高速道路ではエンジンで直接、車輪を駆動するのが最も効率がいい方法です。だから高速道路ではガソリン車とハイブリッド車の燃費の差はほとんど出ないのです。一定速度で走行時に発電機を回すと余計なロスを生み燃費が落ちます。 現状のニッサンノート e-Powerはシリーズ方式を採用しているため、高速道路で弱みを持っている。常にエンジンを高速回転しないと、モータが走行する力を出せないのです。次の新製品ではこの点も改善されるでしょう。 これから、2019年にかけて、各社のハイブリッド(HV)のフルモデルチェンジが行われます。トヨタのアクア、ニッサンノート、そしてホンダのフィット、・・・・ 気持ちのいい運転を楽しみながら、燃費はどこまで下げられるか? 1リットルのガソリンで何Km走れるか、 大変興味深い話です。 ハイブリッドの次はEVになると言われますが、EVのバッテリーが大きな課題です。現状では、リチュウムイオン電池が主役ですが、大量の電力を貯めるには、数十分の充電時間がかかります。ガソリンの給油は数分で完了します。 さらに、ガソリンに代わる大量の電気を供給しなければなりません。その電気をどうして発電するか? あまり触れられませんが、今後の大きな課題です。 日本政府(通産省)は相変わらず原発をベース電源に据え、火力発電で電力を賄うという従来どおりの電力供給方針を出しました。 一方で太陽光発電量が増え、全電力量の30%を賄える時代がもうすぐきます。太陽光発電に合わせ風力発電も増えつつあり、今後有望です。 ただし、「徒然なるまま」のページでも書きましたが、自然エネルギーは不安定で電力の安定供給という面では大きな課題を含んでいます。 しかし、この課題は次第に解決の方向に進みます。ヨーロッパでは、太陽光発電の電力コストは他の方式に比べ安くなると言われています。 国際再生可能エネルギー機関(IRENA)は、2010年から現在までに太陽光発電のコストが73%、陸上の風力発電のコストが約25%下落したとの調査結果を2018年1月13日に発表した。 同機関は、太陽光発電のコストが2020年までに2017年比で半減する可能性があると見込む。 IRENAは、2019年までに陸上風力と太陽光のいずれでも、優良なプロジェクトでは発電コストがkWh当たり3セント以下となり、現在の化石燃料による発電コストを大幅に下回ると見込む。 日本政府が強引にまだ進めようとしている原発は、日立、三菱、東芝3社の思惑が強くあり、それが政府の電力関連議員を動かし、原発は需要なベースロード電源だという世界の潮流から逸脱した時代遅れの方針を固持している。 自然エネルギーを安定に供給するには、地球規模の巨大な送電線網を考えれば解決します。太陽が当たっている国(場所)で発電した電力を、夜の国(場所)に送ればよいのです。ゴビ砂漠などの乾燥地帯で雨が降らない(天気ばかりが続く)不毛な広大な土地で太陽光発電すると、地球全体の電力量を賄うことができるのです。 しかも、太陽エネルギーは無限で、コストゼロだから、設備代だけで済みます。 自然エネルギー発電の不安定さを解決するもう一つの策は、巨大な蓄電装置を設置することです。蓄電の方法はいろんなことが考えられます。 揚水発電もその一つです。 また、太陽光発電した電気で水の電気分解をし、水素と酸素を作り、タンクに収納し、夜は燃料電池で発電することも考えられます。また巨大な容量のリチュウムイオン電池に貯めることも可能です。 人知は無限に広がりますので、『原発に頼る』という考えはもう古いのです。 しかし、電機業界や自民党は原発を未だ推進したい人が未だに牛耳っています。 その中で異彩を放っているのが、元総理の小泉さん、細川さん、小沢さんなどの面々が原発ゼロを訴えています。もっと声を大きくして脱原発の流れを大きくしてもらいたい。 車がガソリン車から、ハイブリッド車に代わり、さらにEVに変わって行く姿は、大きな自動車の世界の転換点に来た証拠です。この流れはもう止めることができないところまで来ています。 これからの車は何で走るのかを見てきましたが、一方で自動運転という流れもあります。AIの進歩で、人間に代わって人工頭脳が運転する時代がもうそこまで来ています。そうなりますと車は移動手段であり、車を運転する楽しみは一部のクルマ好きの趣味となるでしょう。 いま、クルマに対する考え方が大きな転換点を迎えつつありますね。 |
2018年6月17日(日)
高齢運転者の検査・講習について
| 連日、高齢者の運転操作ミスで、痛ましい事故の報道がありますが、このニュースを見るたびに自分も運転に注意しなければと思います。 今年、11月誕生日で75歳になります。 70歳以上の高齢者は高齢者講習を受けなければならないようになりました。 75歳以上は、その講習の前に、認知機能検査を受けなければなりません。 先日、『認知機能検査』を半年以内に受けなさいと言う封書が届きましたので、近くのネヤガワドライビングスクール(寝屋川自動車学校)に電話で申込ました。 タイミングよく、空きが立たのでしょうか、2日後に試験を受けることができました。 インターネット上に、高齢者運転に関するいろんな公式サイトが開かれています。 興味のある方は、下記のサイトにアクセスしてご覧ください。 認知機能検査(試験)に関わる情報も記載されています。 高齢運転者支援サイト https://www.zensiren.or.jp/kourei/ 認知機能検査サイト https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/ninchi.html (注意) 上のサイトがうまく開かない場合は、Yahoo などの検索サイトで検索して下さい。 これを見ると、認知機能検査とはどんな試験が行われるのか、知ることができます。 試験問題を公表しているので、それを覚えてゆけばいい点数が取れると思います。 「問題を公表することは違反行為ではないか」と思いましたが、よく考えると、事前に問題を見て覚えようと努力して覚えられるということはその人は認知症ではないという事でしょう。言い代えると、覚えられないから認知症なのだということです。 だから、問題はこういうものですよ!と公表しているのだろうと思います。 認知機能検査の結果は、下のようなハガキが自宅に郵送されてきます。 検査結果は、『記憶力・判断力に心配はありません』 でした。 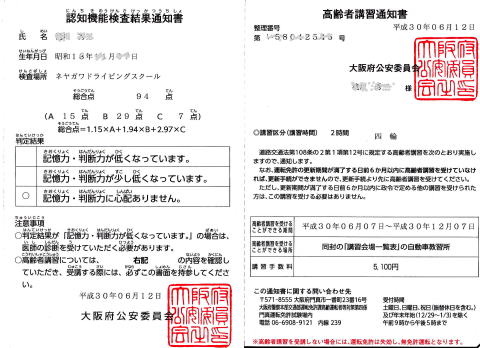 この通知書は認知機能検査結果通知書と、高齢者講習通知書がセットになっていますので、再度、自動車学校に申込連絡して、高齢者講習を受ける必要があります。 その際に、認知機能検査結果により、コースが3つに分かれます。 認知機能検査結果、判定が ①記憶力・判断力に心配はありません。 ②記憶力・判断力が少し低くなっています。 ③記憶力・判断力が低くなっています。 ①なら、高齢者講習会は2時間で、講習料は5100円 これは70歳になった時に受ける高齢者講習会と同じだと思います。 ②③なら、みっちり、3時間、講習料は7950円 ③の場合は、もっと厳しい指摘があるかもしれません。 まず第一関門をクリアしましたので、次の『高齢者講習』を受けます。 この歳になっても、車の運転は楽しくて、大好きです。 しかし、視力や聴力は歳を重ねるごとに衰えを感じます。 また、とっさの判断力や反応は遅くなっていると思いますので、それを頭に置いて、事故がないように注意したいと思っている昨今です。 |
2018年5月9日(水)
やはり、3年半ぶりの高値が報道された
| 今日の新聞によると、原油高の影響で、ガソリンが3年5か月ぶりに全国的に値上がりし145円90銭をつけた。 この分だと、もう少し値上がりするのではないか? ひょっとすると、最高値の160円に近づく可能性が大いにある。 そうなると、低燃費車の価値が上がり、自動車メーカはさらに低燃費競争に拍車がかかる。ハイブリッドや、EVは一層注目され、燃費競争が加速される。 ジーゼル車は、排ガス規制が厳しくなり、ヨーロッパ各国で人気が落ちて、新車の販売がガタ減りだと聞いている。日本の自動車メーカ(ニッサンやホンダなど)もジーゼル車の販売を今後中止するという報道もある。 中国は、アメリカを追い抜いて自動車販売台数トップに躍り出た。 35年ほど前に上海に行った時は、街中を走る車は古ぼけた、ボコボコに傷がついたスクラップ同然のおんぼろのVW(フォルクスワーゲン)が一番多く目立った。 これは、VWが早くから中国と合弁会社をつくり、中国でノックダウン(部品を運び込んで組み立てる方式)でクルマの製造を始めていたからである。 その後、数年後に行った時は、車の台数がさらに増え、道路は至る所で渋滞が起きていた。交差点にはお巡りさんが手旗信号で、交通整理をしていた。 道路を横断するのは命がけで、クルマは止まらず、その隙間を狙って渡るという神業が必要だった。 そういう中国の車社会が、20年前に再び行った時は随分、日本車が増え、新車が増え、クルマが急にきれいになったのには驚いた。 更に15年前に、娘が上海の大学に業務で語学短期留学した際に遊びに行ったが、この時はもう日本と変わらないような車社会に代わっていた。 中国の国策は、自前で自動車を製造することを掲げている。 しかし、自動車はエンジンや変速機(ギヤー)などメカニズムの塊で成り立っているので、部品や材料はもとより、設計や、製造のノウハウが物を言う。 つまり、急に造ろうとしても、ノウハウが無いので自前ではできない。 ノウハウを積み上げる時間的余裕がないので、中国政府が取った手段は、一気にEV化して、エンジンを積まない自動車づくりに舵を切った。 昨日の記事にも書いたとおり、モータと電池で走るEVは、モータのトルクと車を走らせるのに必要なトルクがほとんど同じモードを描くので、極端に言うなら、変速機が不要になる。 モータと歯車をつないで減速するだけで使用できる。ギヤーの組み合わせを変える必要がない。そうなれば、簡単なメカで自動車が製造できる。 モータは電気器具で、変圧器(トランス)と共に一番古くからある機械で、部品点数も少なくて簡単に製造できる。 中国は石炭火力発電所が多く、その排気ガスでPM2.5の濃度が非常に高くなり、連日スモッグが発生し、排気ガスで肺や喉の健康被害まで生じている。 その主原因が、石炭火力発電所の排気ガスと、クルマの排気ガスだと言われる。 そこで、この両者の排気ガスを無くそうと政府は、石炭火力発電は原子力発電や自然エネルギー発電に変える方向に舵を切っている。 一方で、クルマはガソリンやジーゼルエンジン車から、HVを認めず、一気にEV化し、クルマの排気ガスをゼロにする『ゼロエミッションプログラム』を実行しようとしている。 中国は、モータの磁石に使うマンガン、サマリュウム、コバルトなどの希少金属(レアメタル)と、リチュウムイオン電池の電極材料になるリチュウムを世界一産出している。 EVを造る2大要素部品のモータとリチュウムイオン電池の材料が自国にあるという願ってもない条件を満たしている。 そこで、ドイツやアメリカや日本のエンジン自動車の輸入を排気ガスの口実で制限し、自国のEV自動車の生産を国策として始めようと戦略的に動き出した。 リチュウムイオン電池は電池の信頼性を高めないと、粗悪品を造れば使用中に爆発する恐れがある。スマホやノートパソコン用リチュウム電池でも爆発して、火災になる事故が報じられている位、品質や信頼性を確保しなければ危ない部品である。 今まで、中国製のリチュウムイオン電池は安かろう・悪かろうと言われ、日本の自動車メーカは採用してこなかったが、最近、中国製のリチュウムイオン電池がドイツのBMWや、VWのEVに採用が決まっという話もある。もちろん、中国の国産の自動車会社はその電池を採用している。 現在、世界のEVで最も注目されているアメリカのテスラの自動車には、Panasonicとテスラが共同出資したギガファクトリーと呼ばれる超巨大なリチュウムイオン電池工場が稼働を始めている。 しかし、2025年頃には、中国のリチュウムイオン電池工場はテスラを追い越すというロードマップを描いて巨大な工場の建設を進めている。 しかも、電池の容量などは大幅に改善されて、世界でも指折りの性能になると報道されている。 何事も中国のやることは桁違いに大きい。 しかも、彼らの取り組みの速度は非常に速いので、あっという間にキャッチアップされるだろう。 中国が世界のEV自動車の工場になるのも、そう遠い将来の話ではない。 もしかすると、我々が生きている間に、トヨタやホンダや、GMや、VWやBMWをあっという間に追い越すときは来るだろう。 なぜなら、EVを造るために必要な希少材料を自国で産出し、生産を握っているから十分賄えること。 もう一つの理由は、EVはモータと電池の技術で製造できるので、長い間積み上げてきたメカニズムのノウハウがあまり要らないこと。 ここで疑問を呈しておくと、EVは車自体は全く排気ガスは出さないゼロエミッションが達成できる。これは事実だ。 しかし、EV車が走るためには、ガソリンに相当する電気エネルギーを大容量バッテリーに充電しなければならない。この電気をどうして発電するかが問題だ。 原子力発電に頼るなら、大量のウランの燃えカスが溜まり、放射性廃棄物の処理が課題になる。 石炭火力発電所はそのままでは煙突から大量の炭酸ガスを排出するので、排気ガスから炭酸ガスを取り除くためのための処理設備を開発し、設置する必要がある。 多分、中国はそういう方向に向かわないだろう。 中国は広大な国土を有しているから、そこに太陽光発電パネルを敷き詰めて、発電するという戦略を取るだろう。 太陽光発電パネルは大量生産することで、値段は劇的に下がる。それを使って発電する。そして、安い太陽光パネルを世界に輸出して儲けるという戦略を描いている。 既に、中東の広大な砂漠に太陽光パネルを敷き詰め、原発が何基にも相当する巨大な太陽光発電所の建設作業が始まっている。 EVと太陽光発電を組み合わせれば、昼間の余剰電力を一時、車に充電し、夜は車のバッテリーから家に電力を供給するという計画も浮かび上がる。それほど、EVに搭載する電池の容量は大きなものになる。 一度満充電すれば、500km以上、将来的には800kmぐらい走れることになる。 EV化を進める場合に重要なことは、“Well to Wheel” を考える事だ。 これは、油田から車の輪までの総トータルエネルギーが、どの方式が一番自然負荷が軽いかという課題である。 ガソリンエンジンか? EVか? そのWell to Wheelが最小になる方法をチョイスすることが大切な課題になる。 |
2018年5月8日(火)
電動自転車に乗ると、ペダルが軽い!
楽ちんだ!
| あまり話題にならなくなったガソリン価格が再び上昇しています。レギュラーガソリンが147円前後という看板を見て、びっくりです。 でも、うまくカードや会員になれば、5円前後は安く買えます。 ガソリンの安い時は70円台だったのが、一時、ピークで160円台になり、この時は盛んにニュースに取り上げられた。 今また、原油価格の上昇で、そのピーク時に近づいているが、特に騒いでいるような様子がない。 何故でしょう? 若い人の車離れが、こういうところにもその影響が出ているような気もする。 今は、若人は仕事には軽自動車などを使い、家族用にはワンボックスが主流になっている。しかも、ハイブリッド車を使う人が増えた。 ガソリン代が安い時は燃費を気にしなかった人も、さすがに150円に近づくと、再び車の燃費が話題になるだろう。 現在、クルマの燃費は各社がハイブリッド車を揃えて来たので、1リッターで15km~25kmぐらい走るクルマが増えた。10km/L以下のガソリンがぶ飲み車は売れないそうだ。 ハイブリッド(HV)については、このページでも何回か紹介してきたが、『なぜHVは燃費が良くなるのか? 』について分かり易く再び書いてみたい。 分かり易く言えば、車でなく、自転車に乗った時の感覚を思い出せばいい。 自転車に乗り、走り始めにはペダルが重く、こぐ力がいる。これを足に『負荷がかかる』と言うことにする。 自転車に乗る時、自分の足にかかる力、自転車のペダルをこぐ力が、クルマで言えばエンジンの力と同じと言える。 自転車をこいで、走り始め、次第にスピードを上げようとすれば、足には常に大きな負荷がかかり続ける。さらに登り坂に差し掛かると、一層大きな負荷が足にかかる。 漕ぐのが重くなる。 だから、走り始めや、登り坂ではサドルから腰を浮かせて、体重をペダルをこぐ力に伝える。 こういう状態が続くと、しんどくなって、足に力が入らなくなる。そうすると自転車は段々速度が遅くなり、登り坂の途中で止まってしてしまう。 下り坂に差し掛かると、ペダルをこがなくても勝手にスピードが速くなる。早くなり過ぎると危ないのでブレーキを利かせる。 再び平坦な道路を走る際は、あまりパダルを力強くこがなくても、スイスイ走れる。 こういう繰り返しで、私たちは自転車に乗っている。 ①クルマを止まっている(停止)状態から発車(発進)させる時、 ②速度を上げる(加速)時、 ③登り坂を登る(登坂)時、 ④下り坂を下る時、 ⑤平坦な道路を一定速度で走る(定速走行)時、 こういういろんな走る際の状態を『走行モード』と呼んでいる。 電動自転車に乗った時に感じることは、①②③で、自転車ではペダルを踏むのに力が要るが、電動自転車では⑤の状態と同じように軽くこぐだけで走れる。 この足に負荷がかからない分だけ、モータが負荷を分担してくれている。 充電した電池(最近はリチュウムイオン電池が多い)から、モータに電流を流して足でこぐペダルの負荷を助けている。だから電動アシスト自転車と呼ぶ。 坂道を登る時も、今までの自転車では足でこいで登れなかった坂をペダルをこいで登ることができる。その楽な分だけ、電池に貯めた電気エネルギーを使っている。 このことをハイブリッドカー(HV)に置き換えると、全く同じような動作をしていることが分かる。 エンジンが、足でペダルをこぐ力を出す役割 モータが、HVの走行用モータ となる。 自転車に乗った時に、自分の足に力だいるのを、電動自転車なら軽くスイスイ走れるように、HV車のエンジンも、モータのおかげでスイスイと走れることになる。 だから、ガソリンの使用量が大幅に減ることになり、燃費が良くなる。 何故、モータを使うと、エンジン(足でこぐ力)が軽くなるのか? ガソリンエンジンは回転数が低い時は車軸を回す力(正しくは回転力、トルクという)が小さく、回転数の上昇と共にトルクが大きくなり、更に回転数が高くなるトルクは下がって来るという特性を持っている。 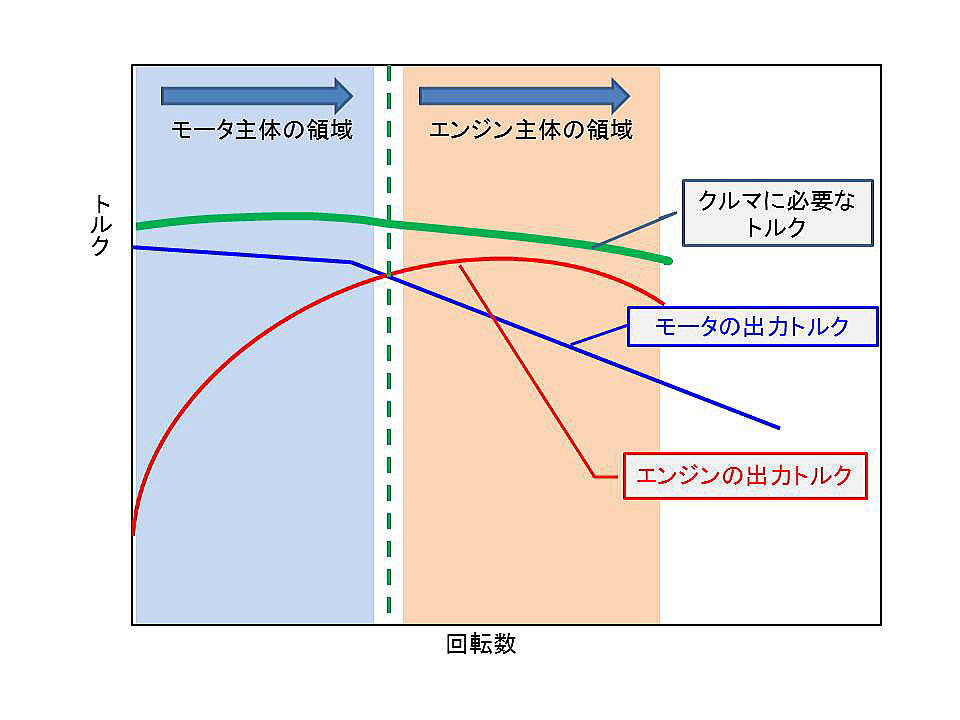 モータは回転し始めの時に一番大きなトルクを発生する特性がある。回転数が上がるにしたがって、徐々にトルクは下がって来る。 モータは回転し始めの時に一番大きなトルクを発生する特性がある。回転数が上がるにしたがって、徐々にトルクは下がって来る。要は車を走らせるいろんな『走行モード』に必要なトルクがモータが発生するトルクと同じような関係にある。これがHVやEVとしてモータが使われる最大の要因だ。 エンジンは回転数が低い時はトルクが小さいので、トランスミッションというギアーの組み合わせで、発進時からロー、セコ、サード、トップというふうにギアーの歯数を変えることで、トルクを拡大する必要がある。以前はこの変速ギアーは3速だったが、それが4速になり、5速になり、いまや6速変速というように小刻みにギアーを切り替えて、加速や燃費を良くするようになっている。 また、最近はギアーの代わりにCVTという金属ベルトを2個のプーリにかけ、両方のプーリの径を変えることで、トルクを大きくする変速装置が用いられるようになった。 これで、実用面では特に違和感なく運転できるようになったが、クルマは信号で止まったり、発進したり、坂道を上り下りしたり、いろんな走行モードの繰り返しで走る。 その際に、エンジン回転数が大きくなったり、不用な時にでもエンジンがかかっていたりという無駄がある。それを無くし、徹底して効率化しようとしたのが、HVである。 いわば、エンジンとモータのいい所取り作戦だ。 現在、トヨタのプリウスが40km/Lで一番燃費がいいというスペックを表示しているが、友人に聞いてみると、実走行では20km/L程度だという話であった。 小生のフィットハイブリッドも大体それくらいで、ほとんど差がない。 HVで燃費が一番になろうとするにはどうすればいいか? ①エンジンの熱効率をさらに改善すること、 ②モータと制御回路の効率を良くすること、 ③リチュウムイオン電池の充放電の速さを良くすること 一番大切なことは、エンジンとモータの相互のいい所取りを最適化するアルゴリズム (ソフト)にあると思う。 フィット3はモデルチェンジ後、2回のマイナーチェンジを行い、現行モデルはフィット3の最終モデルになる。 来年はフィット4がフルモデルとして発売されると聞いている。 これは、i-MM方式と呼んでいる2モータ方式に代わる。この方式はアコードやオゼッセイなどで採用され、既に実績を積んでいる。 2モータ化することで、ブレーキ時の回生エネルギー発電を最適化し、エンジンと発電機で起こした電気はリチュウム電池に充電されつつ、走行モータを駆動する電力になる。要は、クルマの走行モードのトルク負荷の山谷をできるだけ電気エネルギーで置き換えて、フラットにし、その上でモータかエンジンか、効率のいい方で駆動させる。 そういうフィットが来年発売になる。 多分、燃費は40km/L以上になることは間違いないだろう。43km/Lなどという表示ならベストセラーになる! しかし、その辺が限界かもしれない。 2018年から2019年にかけて、小型車のフルモデルチェンジがオンパレード状態になる。大変興味があるが、若者が興味を示さなければ、自動車メーカは先が思いやられる。 |
2018年3月25日(日)
フィットの魅力と、次期フルモデルチェンジに期待
| 何十年も、日産⇒トヨタ⇒ホンダ⇒トヨタ⇒ホンダと各社の車に乗り継いできた。 このところ近年はずっとホンダ車に乗り続けている。 ホンダの車には、何か他社にない魅力があるように感じ、惚れこんでいる。 運転して疲れないのが一番だ。 過去を振り返ると、若い頃は『技術の日産!』と言われ、エンジンはトヨタより良いと思い込んでいたので、初めて乗った車がブルーバード1300(中古)で、もう50年も昔の事。当初は日産党であった。 ブルーバードの後に買ったのは、初代のサニー1200(新車)だった。この車はトヨタのカローラと真っ向から競合する車で、カローラ・サニー戦争とまで言われていた。 軽くて、低燃費で大変良くできた車だった。4速マニュアル車だった。 今では考えられないことだが、冬期、氷が張るような寒い朝、出勤時、車に乗り込んで、エンジンを始動させる際、ドキドキしたものだ。チョークというボタンが付いていて、それを手前に引っ張ってから、セルをスタートさせる。 気温が零下になるような寒い朝はエンジンがかかりにくい。一発ではなかなかかからないのが普通であった。 これはバッテリーは温度が下がると電圧が下がり、セルモータを力強く回せない。こうなると、点火プラグの電圧も下がるので、プラグの火花も弱くなる。バッテリーは数回、セルモータを回すと、だんだん、電圧が下がり、ますますエンジンがかかりにくくなる。 チョークボタンを引きすぎた状態では、プラグがガソリンで湿ってしまい、こうなれば火花が飛ばないので、エンジンはかからない。適度にチョークボタンを戻すことがうまくエンジンをかけるノウハウであった。 そこで、今は当たり前になっているが、バッテリーが弱っても、プラグの放電電圧をしっかり加えることができるように、トランジスタイグナイターと呼ばれる部品を自分で取り付けて、始動しやすいように対策したことを覚えている。 この頃は、バッテリーの性能も悪く、寒いと電圧が低くなると同時に電気容量も下がる。また、バッテリーの寿命も2年間は持たないような時代であった。 最近は鉛バッテリーも良くなり、そういう不具合は無くなった。 その後、クルマはオートマチックに変わり、オートマはトヨタが他社より先行していて、当時は3速オートマチックが主流だったが、コロナ1800(4気筒)は4速オートマが出た。いわゆるオーバードライブ付オートマだった。しかも電子燃料噴射キャブレータが採用されたので、冬の始動は全く問題なくなった。 このコロナ1800は大変良くできた車で、低燃費で乗りやすい車だった。しかし、欠点は登り坂で速度が落ち、エンジンの馬力不足を感じた。 その後、このオートマチックのメカが壊れ、発進ができない故障が起きたので、ホンダのアコード2000(4気筒)に買い替えた。ホンダとお付き合いの始まりとなった。 その後、6気筒車が売れだしたので、再びトヨタのマークⅡ2500(直列6気筒)に乗り替えた。この車は大きな問題はなかったが、『運転が楽しい』という感じがなかった。 万人向きのトヨタ流モノづくりの傑作かもしれない。 そこで、再び、ホンダのインスパイア2500(V6)に買い替えた。これは静かで運転していて楽しい車だった。燃費は高速で12km、普段の街中走行では7kから10km/L。 その後、定年になったのを機会に、大きな車は燃費がかさむので、フィットに買い替えた。フィットがハイブリッド車を出したので、初期のフィットハイブリッドと呼ばれる車を買った。これはエンジンの主軸にモータを直結した構造で、常に両方がつながって回っている。この方法はメカニズムが簡単で、今もスバルや軽自動車の一部で『マイルドハイブリッド方式』と呼ばれ販売されている。 一方、トヨタはプリウスで開発した『ストロングハイブリッド方式』という2モータ方式を開発し、燃費を大幅に向上した。 2モータと言っても、一つのモータは走行用モータで、減速時には発電する。もう一つのモータは発電用モータで、エンジンとつながり発電機として働く。それを遊星歯車というメカニズムでうまくつないで、走行するというトヨタ独自の方式を開発した。 この方式でトヨタは世界一低燃費車としてハイブリッド=プリウスが代名詞になった。  さて、話を本論に戻すと、我が家には写真のように2台のフィットが並んでいる。 さて、話を本論に戻すと、我が家には写真のように2台のフィットが並んでいる。黄色のフィットは、昨年秋にマイナーチェンジされたのを機会に、13年間乗た初代のフィットから買い替えたガソリンエンジン車。 この新型フィットは『ホンダセンシング』という安全装置を搭載しているので、万一の事故を未然に防ぐ、または軽減するような安全アシスト機能が付いている。 フィットは今年6月頃に、更にマイナーチェンジされるという噂を聞いている。 ホンダセンシングをさらに改良し、バック時に後進発進衝突防止機能や、ヘッドライトのハイビームオート切替機能、アンテナを棒から今はやりのイルカのような形(ドルフィンアンテナ)に変更すると聞いている。エンジンにも手が入り、更に低燃費エンジンになるそうだ。 余談だが、ヘッドライトは通常、ハイビームで走行するのが正しいことを知った。 対向車がある時はロービームに切り替えるのが礼儀だ。 今までの車は、ランプが電球からハロゲン電球に変わり、更にハロゲン放電管(HID)に変わり、今はLEDに変わっている。 ロー・ハイビームともLEDになっている。 以前は、ロービームはLEDで、ハイビームはHIDまたはハロゲン電球になっていた。 LEDが明るく、長寿命で、安くできるようなったため、クルマのすべての照明用ランプはLEDに変わっている。これも省エネ、燃費の改善に役立っている。 写真の左のグレーの車は、以前のマイルドハイブリッドのフィットから買い換え、5回もリコールがあったフィット3のストロングハイブリッド車です。 このハイブリッドはホンダらしく、ワーゲンのゴルフやポロに搭載されているDSG(ダイレクトシフトギア)またはDCT(ダイレクトクラッチトランスミッション)とも呼ばれる変速メカニズムを搭載し、エンジンは偶数段、モータは奇数段のシャフトに接続され、複雑な制御プログラムでエンジン・モータ・ギアーの制御を行い、燃費を稼ごうというi-DCD方式である。 この複雑な制御プログラムの不具合(熟成不足)で、発売当初、走行時に異常な状態になり、リコールが立て続けてあり、フィットの期待を裏切り、販売の足を大きく引っ張ってしまった失敗作品。その後、ホンダの技術陣の頑張りで、何とか改良を重ねて今は大変すばらしいクルマになった。 我が家のフィットハイブリッドは、発売前から注文していたので、まさに、そのリコール対象車となり、今もまだ少し違和感が残る。それは走行中に、エンジンからモータ走行に切り替わった時に、ちょっと前のめりになる僅かなショックを受ける。これはモータ側のギヤーに切り替わった瞬間、ちょっと減速するためであり、逆に加速時にはあまり違和感がない。それとブレーキの効き具合が少しぎくしゃくする感じが残っている。 そういう不具合は、現在、販売されているフィットハイブリッドではほとんど感じない。 相当、改良がおこなわれたようだ。大変スムーズに運転ができる車に仕上がっている。 お勧めの車に仕上がった。 ホンダはこのハイブリッド方式をi-DCDと呼んで、フィット以外の複数モデルの小型車に搭載している。 トヨタのプリウスやアクアとの大きな違いは1モータ方式で事を済ませようというもの。 走行用モータを駆動モータと、発電機に切り替えて使うという方式だ。 以前のフィットのマイルドハイブリッド方式との違いは、エンジンの出力軸にクラッチを設けて、エンジンを切り離すことができるので、モータ走行時にエンジンを回すことがないので、その分、モータ走行距離を伸ばすことができる。燃費が良くなるという算段である。しかし、変速機の構造が複雑でコストがかかるので、どうやらこの方式は今回のマイナーチェンジで最後になるようだ。 来年の夏頃に、フィットはフルモデルチェンジが行われ、4世代目に代わる。 その新しいフィット4ハイブリッドは2モータ方式に変わると言われている。 この2モータはトヨタ方式ではなく、日産ノートe-Power(ハイブリッド)で採用しているシリーズハイブリッドと呼ばれる方式になる。この2モータ方式は既にホンダの高級車のアコードやステップワゴンで採用されている実績がある。i-MMDと呼んでいるハイブリッド方式だ。 現在、日産ノートe-Powerはプリウスやアクアを抜いて、トップを走るベストセラーカーを続けている。その理由は、スタート時の加速の良さ、加速のスムーズさ、走行の静かさにある。モータで走行するので、EVと全く同じ運転感覚になる。 これがシリーズ方式のハイブリッドの強みだ。 エンジンは発電機を回す。発電した電気はリチュウム電池に貯める。リチュウム電池から走行用モータを駆動しタイヤを回して走る。これは日産ノートe-Powerと同じ。 日産ノートe-Powerとの違いは、高速道路を走る時、ノートe-Powerはエンジンが吹き上がり発電機を最大に回して発電し、リチュウム電池と走行用モータを回さなければならない。ここで、発電機とモータがシリーズ(直列)につながることになる。 発電機やモータは効率が高い機械だが、効率は100%ではないのでロスが生じる。 例えば、発電機の効率が仮に90%、モータの効率が90%とすると、直列につながった発電機&モータの総合効率は、0.9×0.9=0.81となり、2割近くロスすることになる。 ホンダのi-MMDの2モータ方式は、普段の走行は殆ど日産ノートe-Powerと同じだが、高速道路を走る際は、エンジンが直接タイヤを回すようなクラッチを設けているので、ロスがないことになる。 詳細な動作の説明はHondaのホームページをご覧ください。 http://www.honda.co.jp/tech/auto/i-mmd/topic1/ アコードは大型車で重量がクラウン並だが、この2モータ方式を採用しているので、何と30km/Lという高燃費をたたき出している。 このi-MMD方式をフィットに採用すれば、多分40km/Lは超す思われる。しかも、このシステムは十分、アコードで実績を積んでいて、ノウハウも掴んでいるので、前回のようなリコールすることは考えられない。 フィットの1500ccのガソリンエンジンは高効率で、大変軽やかに回る実績がある。 リチュウム電池も特に問題はない。新採用するi-MMD方式ハイブリッドも十分こなれた実績がある。安全運転支援システム、ホンダセンシングはN-BOXや現行フィット等で十分実績を積んでいる。 以上を考えると、来年のフィットのフルモデルチェンジ車は大きな課題はなく、スムーズに商品化が進むと考えられる。 加えて、新型フィットのガソリンエンジン車は1000cc、3気筒ターボ車になり、燃費は30km/Lを超すのではないかと言われている。この燃費が実現できれば高価なハイブリッド車を買わなくともよいかもしれない。ターボ独特の加速感で軽快に走ることが期待されている。価格もそう高くなく販売されるはず。 来年のフィットフルモデルチェンジが待ちどおしい。 |
2017年9月16日(土)
新型フィットは高速道走行が楽ちんだ!
| 昨日、和歌山の有田まで出かけました。 第二京阪道の側道(一般道)を門真まで走り、門真ICから近畿自動車道に乗り、堺ICを通過して阪和高速道を走り、紀ノ川サービスエリアで昼食を取り、一休みして再び阪和高速を有田ICまで走り、ここで降りて金屋方面に新しい一般道路を走りました。 途中で、『ドンドン市場』に立ち寄り、買い物を済ませ目的地に着きました。2時間半。  今回は、前回に続いて家内用の黄色の新型フィットで出かけました。この車は1300ccガソリンエンジン車。紀ノ川サービスエリアの駐車場に留めても、同じ色の車がないので、一目で自分の車が見つかり、これに限るな!と言う感じ。 今回は、前回に続いて家内用の黄色の新型フィットで出かけました。この車は1300ccガソリンエンジン車。紀ノ川サービスエリアの駐車場に留めても、同じ色の車がないので、一目で自分の車が見つかり、これに限るな!と言う感じ。広い駐車場に留めると、どこに置いたのか忘れて、車を探すのに一苦労、右往左往することがある。その点、黄色の車は数少ないので、目立ってとても見つけやすい。 しかし、まさかクラウンやレクサスで黄色はおかしだろうと思うが、軽自動車やフィットクラスの小型車では、むしろ鮮やかな色の方がいいな!と言う気がする。 次回、自分の車を買い替える時は、今のダークグレーから鮮やかな青色にでもしようと余計なことを考えています。 今まで、白か、ベージュか、グレーに乗ってきた。高齢化すれば目立つ色の方が、相手に分かってもらい易く、安全、安心につながると思う。 もしかすれば、そういう意味で、今後、黄色い車が増えるのではないか?とも。  『派手な色の車は下取りが安い』とか聞いたこともあるが、そういう時代ではなかろう。 『派手な色の車は下取りが安い』とか聞いたこともあるが、そういう時代ではなかろう。ミニ(BMWが買収した)は黄色がなぜか目につく。 さて、往復で360kmほど走った。燃費は高速道路では25km/リッターで、往復の平均燃費は24km/リッターだった。ガソリンエンジン車と言えども、殆どが高速道路走行だったので、燃費はフィット・ハイブリッドとあまり変わらない高燃費でした。 理屈的に、ハイブリッド車は高速道路では、余り威力は発揮できない。一定の速度で長距離走行し多場合は、ほとんどガソリンエンジンと変わらないということになる。 新型フィット1300は高速道路を走行中も大変静かで、エンジン音は気にならない。道路ノイズ(タイヤの音)もこの新型は低く抑えられていて、自分のフィット・ハイブリッド1500より静かなような印象だった。この3年間の技術の進化なんだろう。 今回で、同じコースを2回走ることになるので、『ホンダセンシング』と名付けられた安全運転支援システムをじっくり味わってみた。 まず、高速道路を走る際に、今までとは違い格段に楽ちんだ! 疲れが少ない、疲れないという感じがする。 その理由は、ACCとLKASという『ホンダセンシング』の内の2つの機能が非常によくできているからだ。 ACC(Active Cruse Control)は、今までのオートクルーズの定速走行機能を進化させたもの。自分のフィット・ハイブリッドはオートクルーズしか着いていない。 今回の家内の新型フィットには、オートクルーズ機能にプラスして、自動減速や加速を行う機能が着いている。少し詳しく説明すると、ある速度でオートクルーズボタンを押すと設定した速度で走るが、前方を走っている車との車間距離が接近して、安全な距離より狭くなると、自動的にブレーキがかかり減速する。そして安全な車間距離を確保して走行する。前方車が速度を上げて車間距離が広くなると、自動的にエンジンを吹かして、設定した速度まで速度を上げる。前方に車がない時は、設定したオートクルーズの速度で定速走行する。 前方に車がある場合は、メータ内に車のマークが塗りつぶしで表示され、前方に車がない場合は、車のマークが線で表示される。 前方の走行車を追い越したい場合は、追い越しレーンに移ると、追い越しレーンの前方に車がなければ、直ちにエンジンを吹かして、設定した速度までスピードを上げる。 もちろん、この時、さらにアクセルを踏み込んでもよい。そして設定速度になると、定速走行する。この追い越しレーンの前方に車があって、車間距離が狭くなると、自動的にブレーキがかかり、車間距離を確保する。 今までのオートクルーズは、定速走行はできるが、前方走行車との車間距離が詰まると、自分でブレーキを踏まなければ、そのままでは追突してしまう。ブレーキを踏めばオートクルーズは解除されるので、普通の状態に戻る。 追い越す場合はアクセルを踏み込んで、加速して追い越しレーンを走り、そこで再びオートクルーズボタンを押すか、左の走行レーンに戻ってからオートクルーズボタンを押す操作が必要であった。 今回のホンダセンシングACCは、高速道路の走行中は、ブレーキとアクセルを殆ど踏むことなく運転ができるので、大変楽になる。 走行レーンだけを走るのなら、ハンドルを持っているだけで、前方車両に安全に追随して運転ができる。 もう一つ、高速道路で運転中、LKAS(Line Keep Assist System)をONにすれば、走行しているレーンを自動で追随してハンドルを切ってくれる。直線道路は勿論、コーナに差し掛かると、ハンドルが自動に動いて道路(レーン)の真ん中を走ることができる。 もちろん、自分で普通の車と同様にハンドルを操作できるので、意識的にセンターライン寄りにハンドルを切ると、ハンドルが振動して、同時にメータの表示部に警告表示が出て、警報音も鳴るようになっている。 ハンドルから完全に手を放すと、ハンドルが振動し、警告表示、警告音が出る。 その他、信号待ちしている前方の車に追突防止、歩いている人に衝突防止、前方車が発進した場合の告知音、バックで急発進して後方の衝突防止など、他社が搭載している安全対策システムは全て装備されている。 面白いのは、道路端に立っている丸い標識(速度制限等)はカメラで読み取り、メータ内の表示部に標識がカラー表示される。40とか80とか現れる。 これで2回、大阪と和歌山を往復してみたが、今回のマイナーチェンジした新型フィットは非常に完成度が高い。久々に非常によくできた車になった。 燃費良し、静か、乗り心地よし、ハンドリング良し、ガタツキなし、広さよし、視野が広い(特に後方の見通しがよい)、安全性よし、自動運転よし、と良い事尽くめだ。 しかも値段は高くない。これは売れて当たり前だと思う。 非常に良い車に仕上がっている! (追記) さらに、新型フィット・ハイブリッドは、先般、ホンダの販売店で試乗させてもらったが、マイナーチェンジを超える大幅な改良が施されたようで、一段とグレードが上がった車に仕上がっている。 自分が乗っているハイブリッド車と基本的には同じシステムだが、いろんな面で相当大きく改善されている。試乗して気づいた点は、スタートが非常にスムーズになり、静かにスーッと走り出す感じがする。もちろんエンジン音はガソリン車より一段と静かだ。変速時のショックが感じなくなり、大変なめらかに加・減速し、素晴らしい車に生まれ変わった。 これこそ、3年間余りのユーザからの苦情や情報を真剣に取り入れて、制御関連のハードやソフトを見直し改善したものと思う。 最近のこのクラスの車は静かになったが、この車はワンランク上の車のような印象を受けた。車の購入を検討している方には、ぜひ、試乗してみることをお勧めする。 |
2017年9月10日(日)
新型リーフが行続400Kmに進化した!
| このところ、乗用車のニュースはハイブリッドからEVに代わるという話題でにぎわっている。ハイブリッド車はトヨタがプリウスで先行し、ハイブリッド=プリウスと代名詞になるほど誰もが知っていて、販売のトップランナーとして走り続けている。 確かに、トヨタ・ハイブリッド方式と言うか、プリウス方式はうまくできていて、エンジンとモータの複雑なシステム制御を最も効率的に行っている。 このハイブリッド開発には、たくさんの技術者と、巨額の開発費をかけて仕上げたものだ。世界の自動車メーカでNO.1の潤沢な資金を持つトヨタにしか出来ないことだ。 未だに、この方式を上回るハイブリッド車が見当たらない。それほど完成度が高いと言える。トヨタのハイブリッド車の面白くない点は運転感覚にある。 ただ、ホンダが車の運転の楽しさを活かすようなハイブリッド車を出し始めた。 最近、世界の自動車メーカや、フランス、イギリスなど欧州各国が『ガソリン車の販売を2030年以降認めない』というような過激?な方針や計画を打ち出した。 ガソリン車の販売を認めないということは、ハイブリッド車もガソリンエンジンを積んでいるので、ハイブリッド車も販売できないことになる。要はEVしか販売できないことになる。 そこで、急速に注目され出したのがアメリカの『テスラ』で、株式総資産価値はGMを大きく上回るような勢いになっている。このテスラに電池を供給するのが、Panasonicでアメリカに強大な工場(メガファクトリー)を建設し、最近稼働を始めた。もちろんここで、自動車用リチュウムイオン電池の生産を行う。  このようなEVへの流れを、やっとつかんだのが日産自動車だ。 このようなEVへの流れを、やっとつかんだのが日産自動車だ。2010年に、『リーフ』というEV専用車を販売した。初代の『リーフ』は、注目されたが、高価なことと、一度の充電で200kmしか走れないので、近くの乗り物用としては良いが、ちょっと遠乗りしたいときは電池切れが心配で、一部の人を除いて余り売れなかった。しかし、日産自動車のゴーン社長は辛抱強くリーフを育ててきた。 2012年には228km、2015年には280kmと、次々と走行距離を伸ばし、今回のフルモデルチェンジで一気に400kmにした。 電池容量を初代の24kWh、30KWh、そして今回搭載する電池は40kWhと大容量化を果たした。一度の満充電で、400km走れるのなら、大阪から和歌山を往復できる。 途中、サービスエリアで休憩中に急速充電をすれば、40分で80%まで充電できる。ちょうど、休憩し、食事でも取る間に充電できるという訳だ。 この充電スタンドは、全国に28,500か所、既に建設されている。その内、急速充電スタンドは7,108か所になっている。 日産自動車は世界のEV車の先頭を走り続けたいと考えているようだ。 ガソリンに代わる電気代は、月2000円払えば、『使い放題プログラム』が用意されていて、何回でも充電ができる仕組みを作った。 月額定料金2000円なら、ガソリン(現在126円/リッター)なら15.9リッターだから、ガソリン車で15km/リッター走る車なら240kmぐらいに相当する距離。これなら近くのスーパなどに買い物に行く主婦が日ごろ乗る距離に相当するので、充電代としては高くない。むしろそれ以上に遠乗りすると、安くなるという仕掛けだ。 もちろん、自宅のコンセント(200V)からも充電ができる。夜間電力契約も出来る。 自宅で充電する場合は電気代がいるし、満充電するのに8時間程度かかる。 世界の車がEVに変わり、車の排気ガスゼロのゼロエミッションを目指しているが、車を走らせるには何かのエネルギーがいる。ガソリンをエンジン内で燃やすか、電気でモータを動かすかだ。 EVになると、充電するための電気はどこかで何かのエネルギーを電気に変える必要がある。 それが天然ガス、重油、石炭等の化石燃料エネルギーなら、火力発電所で発電し、それを送・配電線を通じて、各充電スタンドに配電することになる。 だから、EVに代わってもゼロエミッションにはならない。 もっとも、原子力発電なら地球温暖化の基と言われる炭酸ガスは出ないが、高レベルの厄介な放射性廃棄物が生じる。この処理方法がまだ決まっていない。 EVがゼロエミッションと言われるのは、車から出る排気ガスがゼロと言う意味で、トータルとしてゼロエミッションにはならない。 太陽光発電や風力発電など、自然エネルギーで発電すれば、話は別だが、自然エネルギーは発電量の変化が激しくて、安定しない。全国各地に自然エネルギー発電所を設けて、発電量を平準化する必要がある。 それはさておき、このEV化の流れはもう止まらないところまで来ている。 そこで、EVの大きなテーマは、電池容量、コスト、寿命、充電時間がある。これらの課題は新技術が次々に開発されて改良や改善が進んでいる。 今回の新型リーフのリチュウム電池もその一つだ。日産の発表を見ると、新型リーフに搭載されているリチュウムイオン電池は、電池寿命が大幅に向上し、劣化の速さが以前のものに比べて半分以下になったようだ。だから電池は8年または16万kmの走行距離を保証している。また、電池の容量も陽極と陰極の材料を改善し、特に正極にはNi-Co-Mn(ニッケル、コバルト、マンガン系の3元素を使い、エネルギー密度を240Wh/kgと大幅に向上改善した。以前のものは140Wh/kgだから、70%以上改善したことになる。 (注)電池のエネルギー密度とは、電極材料1kg当たり、どれだけ電気を貯められるかの指標。 その結果、初代のリーフは24KWhと言う容量だったものが、同じサイズ(大きさ)で、今回の新型リーフの電池は、40KWhと70%も大きくなった。 現在はリチュウムイオン電池がEV用電池として適しているが、今後、さらに新しい素材が開発され、さらに大容量のものや、諸課題を解決した新電池が生まれるはずだ。 EV化が進めば、自動車産業の構造が変わる。 自動車はエンジンが命だ!。 そのエンジンやトランスミッション(変速機)などの重要メカニズムは非常にたくさんの部品で構成されていて、車一台当たり4万点を超える部品が取付けられている。 それを支える各部品メーカが自動車メーカの生産ラインを支えるすそ野の広い産業構造になっている。 それがEVに代わると、半分以下の部品で車ができる。 さらに、ノウハウの塊と言われるエンジンが無くなることで、メーカにとっては大激震以外の何物でもない。 一方で、エンジンに代わるモータや、モータと電池の制御に使われる半導体や、自動運転などに使われる電子部品が多くなる。自動車産業は機械屋(メカニカル産業)からエレクトロニクス産業に代わるかもしれない。 同じ電池を積んでも、モータの効率によって走行距離が変わる。またモータの制御の仕方によっても走りや、航続距離が変わる。 坂道を下る時や、ブレーキをかけると、モータを発電機として使い、回生発電して電池に電気を戻して貯める。この回収(回生)を上手くできるかどうかでも航続距離が変わる。 これらは、電池とモータというハードと、それを制御するソフトウェア(プログラム)により、大きくEVとして性能が左右されることになる。 今後、自動車業界はパワートレインを内燃機関から電動機関へ移行することになる。自動車メーカとしては、ガソリンエンジンやジーゼルエンジンと言う内燃機関を追求し改善してきたが、EV化はこの100年に渡る歴史を一変する大変革期を迎えたと言える。 その変化がもっとゆっくりだと思っていたが、想像以上に早くなりそうな雲行きになってきた。 とは言っても、今後20年、30年はガソリン車、ハイブリッド車、EVが共存するだろう。 一時、燃料電池車が話題になったが、水素ボンベに積んで、空気中の酸素と水素を化合させることで発電し、副産物は水と言うことになる。この燃料電池車はトヨタとホンダが世界で初めて実用化し販売しているが、価格が高いこと、水素充填のスタンドが数少ないことなどの理由で、最近の動きはあまりぱっとしない。 そこで、一気に市場はEVの方向に動き出したという感じがする。 現在、自動車の販売世界NO.1は中国で、次はアメリカになっている。このEVに流れの裏には中国の国策が絡んでいるようだ。 中国は自動車の排気ガスで光化学スモッグが発生し、北京等の大都市部では昼間からガスがかかり、pm2.5の濃度が非常に高くなっている。 これは車の排気ガスだけの問題ではなく、石炭火力発電所や製鉄所の高炉の排煙の性だと言われている。 世界の自動車の最大の市場に成長した中国は、国内で造る車(国産車)を増やしたいという戦略を持っているが、複雑でノウハウの塊のエンジン開発を今からやるより、一気にEVに切り替え、中国の国内自動車会社の生産台数を増やし、EVでイニシャティブと取りたいという強い思惑が透けて見える。 中国は国内でリチュウムが取れるし、その他、モータ等に使われるレアメタルが取れる。それらの素材を原料として輸出するのではなく、電池やモータなどの製品に加工して付加価値を上げ、さらに最終製品のEVとして製造したいということだ。 その流れの中で、日産自動車は2010年から7年に渡り、先行して頑張ってきてやっと日の目を見るところまで辿り着いたな!と言う感じがする。果たして、先行者利益が守り通せるかどうかが、日産自動車の命運を決する。 『何事もやり続けることが大切だ!』 とも言えそう。 参考資料(2016年、JETRO資料より) 販売台数 生産台数
|
2017年8月3日(木)
新型フィット3ハイブリッドに試乗しました。
素晴らしい出来栄え、 『超』お勧めの車!
| 6月末にフィット3はビッグマイナーチェンジされて、発売されました。 家内の車は、下の写真の初代のFIT1300ガソリン車でした。このFITは従来のコンパクトカーになかった広い室内と、運転のしやすさや低燃費など、時代が求めるニーズを上手く取り入れてベストセラーになりました。 この車は14年間乗りましたが特にトラブルはなく、快調に走りましたが、乗ってみると、いくつか気にかかる点がありました。  ①ハンドルは電動モータのパワーアシスト方式でしたが、少々重い。 ②発進時にぎくしゃくする。これはトルクコンバーターというメカニズムを省略したためです。 ③道路の段差でゴツゴツとした振動を感じる。 が3つの欠点でした.  この前に乗っていたトヨタのヴィッツ・クラビアと比べて、室内が圧倒して広々として快適でした。ヴィッツは、助手席でも足元が狭く、脛が広げられない状態でした。後部座席の前後感覚も狭くて、小型車はこんなもんかと思って我慢して乗りましたが、初代フィットは、以前のインスパイアを思わせる室内の広さでびっくりしました。それが、ホンダの特許であるガソリンタンクの位置を運転席の真下に置くという発想『センターレイアウト』によるものだったのです。 今回、FIT3のモデルチェンジ(マイナーチェンジ)を機会に、『ホンダセンシング』と言う最新の安全運転支援システムが搭載され、業界でも最先端機能ということで、運転者(家内)が高齢化?してきましたので、思い切って入れ替えることにしました。 当初は、次に乗る車は『軽にしよう』という話をしていたのですが、万一の事故の際の身の安全を考えると、やはり普通車の方が安全と言うことで、FIT3に決めました。 色は、他の車の運転者(ドライバー)に分かりやすい黄色にしました。とてもよく目立つし、きれいな色です。この色にしてよかったと思います。スーパーや高速道路のサービスエリアの広い駐車場でもすぐに見つかります。 知り合いのセールスの方と相談し、発売前に予約注文を出していましたので、7月3日に納車されました。納車後、すぐに奈良の道の駅に30kmほど走ってみました。 その後、和歌山の有田まで、高速と一般道を往復300kmほど走りました。その際の感想は7月22日のページでご紹介しましたので、ご覧下さい。 納車後、早くも1ヶ月がたち、 家内も運転に慣れてきたようです。ハンドルは大変軽くなり、非常に滑らかと言うか、しなやかな感触で、とても気持ち良く運転ができます。車体ががっちりしている性か、以前のようなガタツキ音や振動は皆無です。 エンジン音やロードノイズも抑えられ、乗っていて『大変静かになったな!』という印象を受けます。 加えて、最新の安全運転支援システム『ホンダセンシング』が素晴らしく、高速道路を定速で走行するオートクルーズをONにしますと、前を走る車の速度に自動的に反応して、スピードをコントロールしますので、ブレーキを踏むこともほとんどありません。走っている車線を自動的にハンドルを切って走ることも出来ます。これも、以前の記事で紹介済みです。 さて、今日は1ヶ月点検にディーラに行ったので、新型FIT3ハイブリッド車に試乗させてもらいました。インターネットでいろんな記事が掲載されていますが、自分で運転しないと実感が湧きませんので、試乗車を借りて一人で、少し長い距離を走ってみました。  現在、小生が乗っているFIT3ハイブリッドはトヨタのアクア対抗と言うことで、鳴り物入りで発売されましたが、初めて採用したDCT(ダイレクト・クラッチ・トランスミッション)というドイツ製の自動変速機の動作制御ソフトと、駆動モータの協調制御がうまくゆかず、平坦道路の走行は特に異常なかったのですが、坂道などを上る際、エンジンが空吹きするという異常動作をしたので、クレームをつけました。その結果、HIT3は次々リコールを行い対策に追われました。 これをきっかけに、品質トラブルや信用問題になり、残念ながら販売は伸び悩んでしまいました。5回のリコール後、FIT3ハイブリッドは特に問題はありませんが、欲を言えば、ギヤー切替の際や、エンジンからモータに、モータからエンジンに駆動が切り替わるたびに、ショックが少し大きくて気になります。それ以外は特別に問題はなく、燃費もそこそこ伸びますので、アクアと多分どっこいどっこいの実燃費だと思います。 今日、試乗したマイナーチェンジされた新型FIT3ハイブリッドは、そういう3年前から抱える課題を全部解決したすばらしい車に仕上がっています。 今まで、たくさんの車に乗り継いできましたが、この新型FIT3ハイブリッドは掛け値なしに一番いい車になったと思います。実にすばらしいです。 良くなった点(改善された点) ①ハンドルが軽く、しなやかで、スムーズに切れる(これはガソリン車も同じ) ②エンジンの吹き上がりがよく、軽やかに回る(これはガソリン車も同じ) ③ハイブリッドシステムの見直しで、エンジンとモータのつながりが非常にスムーズ になり、変速ショックはほとんど感じなくなった。 ④モータ走行(EV走行)の範囲が広がった感じがする。 ⑤エンジン音やロードノイズが抑えられ静かになった。(ガソリン車も同じ) ⑥車体の剛性が良くなった性か、ビビり音などは皆無。(ガソリン車同じ) ⑦ハイブリッド車は1300ガソリン車と比べると、発進や加速時はモータの力強さが 実感でき、エンジン回転数が上がらず加速するので静か。 ⑧デザインは好みによるが、新型は精悍な顔つきになり、きりっと引き締まった。 個人的には好ましい顔になったと思う。(ガソリン車も同じ) ⑨ホンダセンシングが付くので、安全運転をアシストしてくれる。(ガソリン車も同じ) 今回、新型FIT3はマイナーチェンジとは思えない力の入れようだ!。 エンジンの改良、モータの改良、DCTメカニズムの改良、ギアー比の見直し、制御ソフトの改良、車体剛性の強化、サスペンション(クッション)の改良、ハンドリングの改良、騒音対策の強化とあらゆる面から手を入れたようだ。 ホンダの本気度が伝わってくる。やっと、もやもやが晴れた感じがする。 膨大な費用が掛かるシャーシや外観の金型は変えずに、バンパーなどのデザインを変更し、引き締まったデザインに生まれ変わった。 値段もリーズナブルなので、現在発売されているコンパクトカーの中では、ぬきんでた商品として、素晴らしい車に仕上がった。気になる点が全くなくなっている。それほど、完成度が高く熟成された車になった。 是非、近くのホンダ販売店で試乗されることをお勧めする。 フルモデルチェンジ車は、新鮮味は大きいが、車のような機械物は市場に出し、たくさんの人が使って初めて分かる点がある。メーカは発売するまで、性能、品質、信頼性等などを徹底して検討しているはずであるが、市場に出してみないと分からないという問題が残る。 FIT3は、初めてDCTと言う先進技術のトランスミッションを組み合わせることにより、ハイブリッドの弱点であったモタモタした加速を一掃し、ギヤーの切り替えの感触が得られることを目指して採用したものだが、それが十分、熟成されていなかった。その結果、5回のリコールになった。しかし、そこでホンダは十分反省した。 今回のマイナーチェンジは、以前の反省の下で、あらゆる課題に対して十分な改善と熟成をした結果、この新型FIT3が生まれた。 本当に素晴らしい車になった! あっぱれホンダと言いたい。 |
2017年7月30日(日)
EVが変える社会はどう変わるのか?(第2編)
| 7月27日にも同様な内容を書いたが、いよいよ本格的なEV時代が到来してきた。 アメリカのEV自動車会社『テスラ』がEVの量産『モデル3』を発売開始した。テスラと言う会社は、アメリカのビッグ3(GM、フォード、クライスラー)とは全く無関係な会社で、いわゆる新興のベンチャ企業として生まれた会社だ。その会社が先頭を切ってEVを量産し発売した。 このテスラ車向けに、Panasonicが全面的に協力し、リチュウムイオン電池の巨大な工場(メガファクトリー)を建設し、世界トップシェアをキープするところまで事業が拡大している。 ベースモデルが35,000ドルと、ロングレンジモデルが44,000ドルの2モデルがあり、違いは満充電で、どれだけの距離を走れるかである。 ベースモデルは日本円で388万円位で、354km走行できるらしい。ロングレンジモデルは499kmも走れる。 テスラはトヨタ自動車とGMが以前に共同経営していたカリフォルニア州のフリーモント工場を買い取り、EV用工場に改変したもの。この車は既に発表していて、2016年3月で予約は40万台に上っていた。今の計画は、2018年に年間50万台を製造・販売する予定。  世界の自動車市場のEVのシェアは2016年は、わずか1%だったが、2030年には少なくとも30%を超えるらしい。 世界の自動車市場のEVのシェアは2016年は、わずか1%だったが、2030年には少なくとも30%を超えるらしい。 フランスやイギリスは、2040年以降、ガソリンエンジン車の販売を認めない方針を発表した。お隣の中国でも、EV化が急速に進んでくる。 フランスやイギリスは、2040年以降、ガソリンエンジン車の販売を認めない方針を発表した。お隣の中国でも、EV化が急速に進んでくる。日本の自動車メーカは、ハイブリッド車に力を注いできたが、ここにきて一気にEV化の方向が顕著になっている。 ハイブリッドは複雑な制御が必要なので、日本メーカしか造れなかったが、EVはモータだけで動くので、制御は簡単になる。だからどのメーカでも手を出すことができる。 1トン以上ある車を長距離走らせるには大量の電力が必要となる。その電力容量を貯める二次電池は今のところ、リチュウムイオン電池しかない。 リチュウムと言う金属は、地球上では希少金属に類するので高価であり、産出国も限られる。いかに安く大量のリチュウムを入手するかが、EV化の大きな課題になる。 EV化が進んだ場合、どういう社会問題が起きるかを考えると、先般、27日にも記載したが、今まで考えられなかったような新しい課題が生じる。 車を走らせる車道(道路)の新設、整備、保守メインテナンスの財源は、世界中で各国はガソリン税で賄ってきた。EVになると、ガソリンの消費はゼロになるので、ガソリン税収入が無くなる。 これに変わる財源は、走行距離に応じて税金をかけるマイル税と言うようなことを考えているようだ。 もう一つの大問題は、EVのバッテリーに充電するための電力供給の問題である。 今までは原油生産国から運ばれた原油を石油精製所で、いろんな種類の油成分に分離し、その内、軽油はジーゼルエンジン車に、ガソリンはガソリンエンジン車に使ってきた。ジェット機はジェット燃料で飛行するが、これは軽油に近い種類である。 いずれにしても、EV化社会ではガソリンの消費は無くなる。だからガソリンスタンドはガソリンエンジン車が次第に減ってゆくので、ガソリンスタンドのニーズが無くなり、店の数は今のようにたくさん必要でなくなる。 ガソリンの需要が次第に減るのである。その代り電気の需要が次第に増えてゆく。 ガソリンはタンクローリで運ばなければならないが、電気は送電線を張れば、輸送コストは要らない。 ただし、ガソリンのエネルギーを電気エネルギーに代替するのであるから、大量の電力が必要になる。 問題はこの大量の電力を何で賄うのかである。 風力発電や、太陽光発電や、地熱発電や、水力発電などの自然エネルギーを寄せ集めて、EVの膨大な電気エネルギー需要を満たせるかと言うと大幅に不足する。 その分を原子力発電で賄うとなれば、新設の原発が必要になる。この潮流を読んで、電力会社はフォローの風が吹いてきたと思うかもしれない。 しかし、原発に頼って電力を賄うなら、未解決の放射性廃棄物の処理や、その保管が大問題となる。 自然エネルギーは、発電の電力量が不安定な電力である。 太陽光発電は昼間しか発電できないし、風力発電は風が吹かなければ発電できない。いくらたくさん太陽光発電所や風力発電所を作っても、発電できない時がある。 だから、自然エネルギーを利用して安定に電力需要を賄うには、発電した電力を大量に蓄える技術が必要になる。 例えば、 ①大電力用リチュウムイオン電池 ②揚水ダム ③水の電気分解 ④その他 もう一つの課題は、自然エネルギーは地域間で発電量が変わるので、それを大電力送電線網でネットワークを組み、平準化することが必要になる。 現状は、国内に10電力会社が各自の送電線網を有しているが、基幹送電線は国有化するなどして、全国を結ぶ送電線が必要になるだろう。 いろんな課題が今後、EV化の進展と共に生じるが技術はどんどん進化するから、そういう課題を克服しながら前進すると思われる。 いずれにしても、ガソリンやジーゼルエンジン自動車が一気にEVに変わるわけではないので、そういう周辺のインフラの対応を進めながら次第に移り変わることになる。 今まではEVは一部の特殊な車と言う印象だったが、それがいよいよ身近な普通の車として近づいてきつつある。 |
2017年7月27日(木)
EV化でインフラがどう変わるのか?
| トヨタ自動車が世界に先駆けて、「21世紀に間に合いました」というキャッチフレーズで、ハイブリッド車、プリウスを開発し大ヒットしました。 発売当時、二次電池はリチュウムイオン電池が未だ車に搭載できるほど信頼性がない時代でした。パソコンや携帯電話用リチュウムイオン電池が充電中や使用時に発火や爆発事故が相次ぎ、怪我や死者まで出したことがあり、リチュウムイオン電池は危険な電池と言われていました。 そこで、トヨタは品質の掟(おきて)として定められているとおり『OR・FO』を守り、パナソニックが長年、商品化しているニッケル水素電池を採用し搭載しました。 (注)トヨタ自動車の品質の掟: OR;オーバーラン ;必ず止まること FO;ファイアーアウト;火が出ないこと ニッケル水素電池は、ニッケルカドミュウム電池(通称;ニカド電池)の改良型と言える電池で、安全で信頼性が高く、コスト的にも安い電池です。弱点はリチュウムイオン電池と比べ、同じサイズなら充電容量が半分ぐらいしかなく、電圧は1.2ボルトと低く、リチュウムイオン電池の3Vに対して1/3しかない事でした。 要は、ニッケル水素電池は高電圧・大容量のリチュウムイオン電池に比べて、電池としての基本性能が劣るものでした。しかし、当時は使えるものでこれしかないので、初代のプリウスはニッケル水素電池を多数、直列接続し電池パックとして搭載し、その後も引き続いニッケル水素電池を採用してきました。 現行プリウスでは、カタログで高燃費を謳った一部のグレードだけ、リチュウムイオン電池を搭載し出していますが、売れ筋の車種では相変わらずニッケル水素電池を採用しています。 もう一つの違いは、リチュウムイオン電池に比べて、充電時の充填の速さが劣ることです。即充電と言う面ではリチュウムイオンに負けるのです。 ハイブリッド車やEVは電池が命ですので、リチュウムイオン電池が改良され、信頼性が高まりつつある中、各社はリチュウムイオン電池の採用を進めています。 さて、地球温暖化の最大の原因と言われている車の排ガスを如何に削減するかという課題が世界的に表面化しています。 特に中国の北京等では、光化学スモッグが頻発する状況になりました。これは車の排気ガスだけでなく、石炭を燃料とする石炭火力発電や製鉄所等から排出されるガスが主な原因ですが、急激な車社会に変わり、膨大な数の車両が走り回ることで、ますます空気中の二酸化炭素や、PM2.5に代表される微粒子が増えています。 そこで、世界の潮流として、最近、言われ出したことは、ガソリンやジーゼルエンジン車からEVに移行するという転換の話です。 昨日の新聞では、フランスやイギリスは2040年以降、ガソリンエンジンやジーゼルエンジン車は販売中止という法令を出したようです。2040年までは20数年間ありますが、いずれにしましても時間との闘いです。 日本の自動車メーカは、まずハイブリッド車を普及させ、排気ガスを削減する方向で対応してきました。 EVはスーパー電池がその内に開発されれば対応ができるという考え方でした。 世界の潮流はガソリンやジーゼルエンジンから即、EVへ移行するという方針です。 ハイブリッド車はエンジンとモータの駆動源の力を組み合わせて、燃費を削減しながら運転性能も満たした車を作ろうという考え方です。 これに対して、EVは100%モータの力で走る車ですから、大容量の電池がないと長距離を走ることができません。それを満足するのは、リチュウムイオン電池しかないのが現状です。 一度、満充電したら500km~700kmほど走れないと、安心して出かけることができませんが、現状、車として成り立つコストを考えると非常に難しい問題があります。 車体の底に大きなリチュウムイオン電池の箱を積まなければなりませんので、そのスペースと重量が大きくなるのです。その結果、車の重量が増えて、車内の空間が狭くなるなど、車を造る上でも、運転する側からもいろんな課題があります。 現在、リチュウムイオン電池は使用する材料、材質などいろんな面から開発を進められ、急速に性能の向上を図りつつあります。 どの電池も、正極(+極)と負極(-極)と、その両電極間に電解質と言われる材料が挟み込まれる構造をしています。その各材料を洗い出し、課題を一つ一つ解決しつつあるのが現状です。 EV用電池として要求される条件は、容量が大きく、軽く、小型で、急速充電ができ、繰り返し充電ができ、大電流が流せて、値段がやすく、信頼性がある、そういう電池が求められます。それに一番近いのがリチュウムイオン電池と言うことになります。 但し、リチュウムと言う金属は世界上で埋蔵量が少なく、偏った地域にしか存在しないという課題があります。中国やチリなどが産地です。 そこで、リチュウムに変わる負極材料の金属を盛んに研究しています。近い将来、新しい電池が生まれる可能性があります。 もう一つ、EVに変わるための条件があります。 これは車自体とは関係ないことですが、EVは必ず充電するということが必要です。 現在はガソリンスタンドで給油しますが、EVは充電スタンドが必要で、充電スタンドが沢山出来て、どこでも充電ができるようインフラが整備されなければ、電池切れのEVが続出します。これではEVは役に立ちません。 EVスタンドができても、そこで充電する電気をどうして供給するかという課題があります。全国、世界レベルで、化石燃料のガソリンや、軽油が車に使われなくなると、原油が余りますが、その分、膨大な電力を供給しなければなりません。 車が走るためには、相当なエネルギーが必要です。そのエネルギーとして油を使うのか、電気を使うのかです。 車はEV化で電気自動車に変わったが、走るための電気をどうして発電するのかです。自民党与党は原子力発電をベース電源として位置付ける政策を打ち出しています。車がEV化すれば、現在の発電量では全然不足しますので、大量の電力の供給を考えなければなりません。 一番良いのは、再生可能エネルギーである風力発電や太陽光発電や地熱発電や波力発電などを組み合わせて、最大限電気エネルギーを確保するようにしないと、原発と火力発電に頼るなら、放射性廃棄物はドンドン増え続け、火力発電所から出る排出ガスが増えることになります。 車はEV化でゼロエミッション(廃棄物ゼロ)は達成できますが、その代わりに他のところで、環境負荷廃棄物が増えるとなれば、何のためのEV化かと疑問が湧いてきます。 自動車のEV化による電力使用量と、その電力供給のための発電のあり方について、両面で考えなければならない課題です。 ヨーロッパ諸国は大量の風力発電所を建設して、電力を賄う計画で進んでいます。日本は原発をベース電源として、30%程度を原子力で賄う計画です。これに車を走らせるEV用の電力が上積みされます。 そういうトータルの電力需給体制を考えなければならない時代になりました。 しかし、このような話を聞いたことがありませんね。 |
2017年7月22日(土)
新型フィット3で、和歌山に出かけました
| 6月30日に発売されたマイナーチェンジモデル;フィット3(ガソリン車1300cc)が早期契約していましたので、早々に納車されました。 “どんなもんかな?”と思い、和歌山の田舎の有田に行ってきました。走行距離は往復で約300km。 ルートは第二京阪高速道の側道一般道路を寝屋川ICから門真まで走り、門真の花博近くのインターチェンジから近畿自動車道(高速道路)に入り、堺ICを直進して阪和高速道を走り、紀ノ川サービスエリアの手前の新設中の京奈和高速道路(未完成)に逸れて、少し走り『かつらぎ西IC』で高速道を降りて、一般道路に出て、『JAめっけもん広場』に立ち寄りました。この付近は桃の産地で、『あらかわの桃』で有名なところです。 JAめっけもん広場は話には聞いていたのですが、今は桃のシーズンですので、大阪近郊から買いに来る客で超満員でした。第一、第二駐車場が満杯で入れず、300mも離れた場所にある第三駐車場に留めて、歩いて市場にたどりつきました。 たくさんの人でごった返していました。特に、桃をお中元に送る人が多く宅急便受付カウンターは長い列になっていました。 市場内には、桃の箱が積み上げられ、その他スイカ、ハウスミカン、夏野菜類、花などが売られていました。市場に入ったのが正午頃でしたので、一番込んだ時間帯だったようです。 桃を一箱買い、お寿司を買って車内で軽く食事を済ませました。 その後、一般道を走り、黒沢牧場を通る山越えの狭い道路で金屋に降りました。 帰りは金屋から一般道路を走り、有田ICから阪和高速道に入り、近畿自動車道を門真まで走り、一般道路に降りて、第二京阪高速の側道を寝屋川まで走り無事に帰宅しました。  以前のフィットは初代のもので、14年間ノートラブルで走り、まだ不都合もなかったのですが、家内も歳をとってきたので、安全装置が付いた車に代えようということで入れ替えました。 以前のフィットは初代のもので、14年間ノートラブルで走り、まだ不都合もなかったのですが、家内も歳をとってきたので、安全装置が付いた車に代えようということで入れ替えました。何と彼女が選んだ色が黄色です。 よく目立つので、広い駐車場に置いた時はすぐ分かります。 運転中も他車のドライバさんに見つけてもらえるので、安全かもしれませんね。 今回のフィット3はこのクラスの業界最高レベルの安全運転支援システムが採用された車で、安全支援システム名はホンダセンシング。 詳しいことはこのページの中の、自動車のEV化は本物か? 課題は何か?を読んで頂ければ分かりますが、画像処理技術の進化に驚いています。 高速道の走行で一番楽だったのは、ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)とLKAS(ラインキープオートステアリング)です。 ACCはとても賢いオートクルーズ装置で、前を走っている車と、車間距離を適当に維持しながら追随して走行するものです。自分のフィット3ハイブリッドはオートクルーズはついていますが、設定した一定の速度で走りますので、先行車の速度が遅くなるとブレーキを踏まなければ追突します。逆に先行車が速度を上げると、アクセルまたは増速ボタンを押してやらなければ車間距離が開いてしまいます。その点、この新しいHONDAセンシングと名付けられた安全走行支援システムのACCは、車が全てやってくれますので、これは長距離高速運転の際には疲れないだろうと思いました。 もう一つすごいのは、LKASと言うシステムで、高速道で運転中は両側の白線を検出して、車線の中央付近を自動的にハンドルを切って走ることができます。極端に言えば、手放しでも左右に曲がった道路を追随して走ります。一応、ハンドルから手は離さないように!と言うことになっていますが、軽くハンドルを触る程度でいますと、自動的にハンドルが動いて曲がり角を上手に曲がることが分かります。 そのほかに衝突防止装置など8つの項目が搭載された最新システムです。 このHONDAセンシングシステムで、ホンダは業界の先端に立ったと思います。 新しいフィットは、外観や顔つきもキリッとした感じに代わり、余分な局面を削いだので精悍な顔つきになりました。 ワイド&ローとも言える感じす。 車体の剛性も強化されていますので、ビビり音や、ギクシャクした感じが無くなり、ドイツ車のような剛性感があります。 エンジンは1300ccアトキンソンサイクルエンジンと言われるタイプで、環境に優しい排ガスの少ない新しいものです。ホンダ製VTECエンジンは軽やかな音で良く回りますので、静かで気持ちよく走れます。 変速機のCVTも改良され、トルクコンバーターも食いつきが良くなったので、本当にスムーズな走りができます。この点は初代フィットと大きく改良された点の一つです。 走行距離は往復で300kmほどになりました。燃費は満タンでm平均燃費は20km/リッターとなりました。今までのフィットならせいぜい17~18kmと言うところでしたので、相当改善されました。ちなみにカタログ値は26km/Lです。 私用のもう一台のフィット3ハイブリッドは26~30km/Lぐらい走ります。 当日は気温が34~35℃ありましたのでエアコンをガンガンかけて走った燃費です。 車内の騒音は、フィット3ハイブリッドとほとんど同じか、少し静かかというレベルですが、凸凹の路面の衝撃の吸収能力は明らかに新型の方が改善されているようです。 全体として、今回の新型フィット3(マイナーチェンジモデル)は相当、ホンダの開発陣が肝いりで改良や手直しを図った力作だと思います。 新型フィット3のハイブリッド車にはまだ試乗していませんので、自分のハイブリッド車との違いは分かりませんが、ネットの試乗レポート記事等を見ますと、非常に車内の騒音が低くなり、上級車並みになったということです。 DCT自体の改良や、制御プログラミングの改良で、スムーズで加速が良くなったということです。今乗っているフィット3ハイブリッドは、その辺が未だこなれていないという印象を持っていました。やっと、DCTとモータとエンジンの組み合わせの制御が成熟して良くなったようです。 さて、次期フルモデルチェンジが2019年になるようですので楽しみです。 その時は、今のハイブリッドシステムi-DCDからi-MMDの新しいものに変更するといわれています。日産ノートe-POWERと同様なシリーズ方式ハイブリッドに近い改良型になるはずです。これは2モータ方式ですから、一般走行はモータで、エンジンは発電用として搭載されます。高速道路ではエンジン駆動で走ることになるようです。 現行のアコードが既に採用しているシステムですから、十分、技術的にはこなれたものです。 新しくi-MMDシステムを採用する理由は、モータの量産は比較的簡単にできることがあげられます。今後、EVが主流になった場合は、2モータ方式の場合はエンジンと発電機を取外し、バッテリー容量を大きくすればいいのです。 EVとハイブリッドの部材の相互利用と言う考えに立てば、2モータ方式は合理性があります。 NISSAN NOTE e-POWERが爆発的なヒットを実現したのは、モータの特徴を生かした加速の良さ(大きなトルク)にあります。 そういう新しい流れが始まっている中で、エンジン主体の車からモータ主体の車に流れが変わってゆくはずです。 車に興味がない方はどうでもよい話だと思いますが、車やカメラやハムに興味がある者にとっては、新しい技術の流れがどうなるのかを見るのが楽しみです。 今回の新型フィット3シリーズは間違いなく良くできた完成度が非常に高い商品に仕上がり、よく売れると思います。 デザイン善し、燃費善し、安全対策善し、値段もリーゾナブルです。 勿論、フィットの車内の広さは、初代のフィットからの最大の特徴です。 |
2017年7月12日(水)
自動車のEV化は本物か? 追記記事
| 昨日、同じタイトルで記事をアップしましたが、少々書き漏らした点がありますので追記しました。引き続き読んで頂ければ幸いです。 自転車(電動自転車は別の話です)に乗ると実感できるのですが、漕ぎはじめは足に大きな負担がかかります。ゆっくり走り出す場合はそうでもないのですが、早く走り出そうとすると力強くペダルをこがないと走りません。競輪選手の姿を見ているとよく分かります。走り始めは腰をサドルから浮かして、体重をペダルにかけています。 動き始めは大きな力が必要なのです。この『力』という表現は正確には正しくありません。理屈っぽくいうと、ペダルを踏むとき、ペダルの長さが短いものと、長いものがあれば長い方が軸に大きな回転力が生まれます。言い方を変えれば、ペダルの長い物の方が、軽く踏むことができます。その代り一回転するのに大きな円周を回ることになります。この力を『トルク』と呼んでいます。 トルクとは、ペダルの長さと、ペダルに直角にかかる力の積(掛け算)になります。 トルク=ペダル(一般的表現ではアーム(腕))×力 ということになり、このトルクが大きいかどうかで、走り始めの出足や加速が変わります。 自動車は小型車でも1トン前後ある重い物体です。一人の力で押して自動車を動かすことは不可能です。少なくても数人が押して、やっと少し動くという程度です。その重い自動車を静止状態から100mを10秒程度で加速して動かすのですから、エンジンにはものすごい力(正確にはトルク)が必要になります。 世界のアスリートが100mを10秒切るかどうかで競っています。彼らの体重は50~60kg程度でしょうから、人間の能力は車の1/10程度しかないとも言えます。しかもこれは瞬発力ですので、一瞬に出せる力です。 話が横道に逸れましたので戻します。 エンジンは大きく分けると、ガソリンエンジンとジーゼルエンジンがありますが、基本的には「回転数が低い時はトルクが弱い」という特性を持っています。特にガソリンエンジンはそういう傾向があります。 そこで、歯車を組み合わせて、エンジンの回転数を落としてトルクを増やすという仕組みを使います。これがミッション(変速機)です。その他に同様な働きをするCVTという方式が実用化されるようになりました。CVTは金属のベルトを使い、直径が可変のプーリを2個使い、これにベルトをかけて、歯車の組み合わせを変えるのと同じ働きをさせる方式です。いずれも、エンジン回転数が低い時に大きなトルクを発生させるのが目的です。 この変速機(トランスミッション)やCVTは重量があり、車の重さに大きく影響します。 エンジンに対して『モータ』は逆のトルク特性を持っています。モータは回転数がゼロから回り始める時に最大トルクを発生します。(その代り、回転が始まる際に非常に大きな電流が流れます。) 回転数が上がるにしたがって、トルクは下がってゆきます。その理由はモータ内部に回転による逆起電圧が発生し、それがモータにかかる電圧と逆方向ですから、モータに流れる電流が回転数の上昇と共に減ることになるのです。 モータが発生する力は、内部の磁界の強さと、磁界を切るコイルの長さと、電流の掛け算になります。 発生する力=(磁界の強さ)×(コイルの長さ)×(電流) そして、モータの発生するトルクは、回転子と呼ぶモータ内部で回転する円筒状のものの半径の大きさと、上記の発生する力の積(掛け算)になります。 ですから、モータの形状を見れば分かりますが、モータの胴体が太い形状のものはトルクが大きいモータだと言えます。逆に細い胴体のものはトルクは小さいのが一般的です。最近の電気洗濯機は大型化し、洗濯物を10kg以上まとめて洗うことができます。当然、水の量も増えますので、動かすのが重くなります。そこで、大きな直径のモータを洗濯機の底の部分に取り付けています。 また話が逸れましたので、元に戻ります。 モータのトルク特性は、実は車が走り出す際に必要なトルクとよく合致していますので、実に相性がいいのです。 それを今まで活かしきれなかったのは、モータを動かすためにはバッテリーが要りますが、従来の鉛バッテリーでは、そういう大容量のバッテリーは非常に重くなって車に積めなかったのです。鉛は比重が大きいので重い金属ですから。 充放電が可能で軽いバッテリーとして、まず実用化されたのが、ニッケル水素電池です。これはPanasonicや旧、三洋電機が得意としていました。プリウスは初代から現行車まで、この電池を搭載しています。ニッケル水素電池は化学的に安定しているので、爆発などの心配はありません。電圧が低くて一個当たり1.2V程度です。 それに対して、最近盛んに使われ出したリチュウムイオン電池は一個あたり3Vの電圧を発生します。さらに、充電できる電気量が大きく、リチュウムは軽い金属ですので電池の重量が軽くなり、車に搭載するのには打ってつけの電池です。この電池の注意点はリチュウムが非常に化学的に激しい性質を持っていますので、回路のショートや水分の混入などで爆発する危険が伴うことです。そういう危険性を克服しつつ、リチュウム電池は沢山使われるようになりました。但し、リチュウムは希少金属ですので高価です。 これらの電池の開発により、電池とモータで車が動かせる時代になったのです。 もう一つ、技術的なブレークがあります。 それは電池の電圧は、一個当たり1.2Vとか3Vしかありません。これでは何十馬力という大きな力を出すモータに使えません。そこで、この電池を直列接続して電圧を上げます。100Vから200V程度まで直列接続して高い電圧を得ます。この電圧ではまだ車を駆動するには十分ではありません。 そこでインバータと言う電子回路を通して、数百ボルトという高い電圧に昇圧します。この電圧は3相交流電圧として取り出します。同時にインバータ回路は電圧と交流周波数を自由に変えることができる回路です。 コンピュータを使い、プログラムされた制御信号でインバータは制御されます。 車が静止状態から走り出す際には、バッテリーからの直流電気を昇圧し、さらに適当な交流電圧と交流周波数に替えてモータに供給します。 モータは大きなトルクを発生しながらスムーズに回転数を上昇させ、それにより車がスムーズに加速してゆきます。 そういう複雑な一連の動作をコンピュータが制御しているのです。 もし、走り出す際に、バッテリーの充電量が少ない場合は、エンジンをかけてモータとエンジンの両方で動き出すこともあります。 この一連の動作は、ハイブリッド車であれば同じことになります。 違いは、モータの数、モータの使い方、バッテリーの容量、種類、エンジンの役割などで各社が腕を競うところです。 話は変わりますが、関西電力が原発再稼働を前に料金の値下げを発表しました。関電は国内の10電力会社の内、一番原発依存度が高い電力会社です。ですから早く原発の再稼働をしたかったのですが、原子力規制委員会の安全基準に合格するための追加工事等で時間がかかっていました。それがやっと合格になり、再稼働にこぎつけ、『原発の電気は安いのだ』と言いたいのでしょう。料金値下げをしました。 小生は月、数百円の値下げより、原発再稼働は反対の立場です。 しかし、最近、大阪ガスも電気を供給し、関電から買わずとも大阪ガス会社から電気の供給を受けることが可能になりました。しかも関電より安いのです。 なぜ、電力会社の電気料金がガス会社の電気料金より高いのか? 不思議に思いませんか? そのわけはよく分かりませんが、関電は原発依存度が高く、原発のウラン燃料は既にたくさん手持ちがあります。原発の停止状態では、手持ちのウランが宝の持ち腐れ状態です。関電は電力供給責任がありますので、停止していた古い火力発電所を稼働させてきました。古い火力発電所は熱効率が低く、石油燃料をたくさん食いますので、割高の電気料金になります。 一方、大阪ガスは原発は持っていませんので、全て自社の火力発電に頼りますが、新しい火力発電所は熱効率が高く、燃料代が安くなります。 原発は見かけ上は発電コストは安くなりますが、巨額の安全対策や、事故の際の補償や、廃棄物処理等を考えると、決して安い電力とは言えないのです。 原発の発電コストには放射性廃棄物(原発の燃えカス)処理費用が入っていません。しかも、処理の場所や処理施設や保管方法も決まらず、そのままなし崩しで進めているのが現状です。実に無責任状態です。 小泉元総理はこれを『トイレのないマンションに住むようなものだ』と看破しました。 話を車に戻しますが、『これからの車はEVが本命だ』と言われてきました。ハイブリッド車はそのつなぎの技術であると・・・。 一方でトヨタとホンダは燃料電池を積んだ車を開発し、究極の排気ガスゼロの車だと大々的に宣伝したのですが、車の値段が非常に高い点と、燃料の水素を補充するスタンドがまだ少ないなど、普及に至っていません。 『世界的にEVがこれからの車』と言う流れになってきましたが、『EVは大容量バッテリーを如何に安く、軽く、大量に製造できるか?』が最大の課題です。 しかも、EV車を走らせるには必ず『充電』は必要になります。 充電のため『ガソリンスタンド』に代わる『充電スタンド』が近所や各地に必要です。 現状ではまだ十分『充電スタンド』があるとは言えませんので、自宅のコンセントからコードをつないで、一晩かけて充電することになります。 『充電スタンド』なら大量の電流をバッテリーに一気に流し込むことができるので30分ぐらいで満充電が可能です。 いずれにしても、EVが普及すると、ガソリンに代わる大量の電気が必要になります。 その電気を何で賄うのか?です。 そういう議論を聞いたことがありません。 大量の電力が必要だから、更に次々と原発を建設し稼働させたいというのが電力会社の本音だと思います。電力会社は大きなビジネスチャンスが到来したのです。 逆に石油精製や元売り会社はEV化で、ガソリンの消費がガタ落ちになります。そこで石油精製会社は、業態を変え、火力発電所を建設して電力会社に売電することになるでしょう。 また、巨大な太陽光発電所や、風力発電所や、地熱発電所などの地球環境に優しいエネルギー利用の方向に進んでゆくことが考えられます。 大型の太陽光発電所(メガソーラ)は各地に開設されています。例えば、瀬戸内沿岸の広大な塩田跡地に太陽光発電パネルを敷き詰め20万KWと言うような大型発電所も出来てきました。このようなメガソーラが10か所できると、原発2基分の発電が可能です。ただし、メガソーラは昼間、日照がある間だけの発電になります。 EV自動車は電気を食うだけの商品ではなく、電力系統に接続することで太陽光発電や風力発電により電気が余っている時に充電し溜池のような役割をさせることも可能です。EVのバッテリーを電力の余力のある時に貯めてバッファーとして使用できれば、電力の平準化に役立ちます。 これからそういう新しい電力の融通や平準化ができる時代になると思います。 Yahooの孫さんが提案している夢のような巨大な電力構想を紹介します。 それは、モンゴルの広大な平原に太陽光発電パネルを敷き詰め、巨大な発電所を建設し、その電力を中国、韓国、日本海海底ケーブル経由で日本に送電するというものです。更に、衛星を電力伝送の基地として使い、モンゴルで発電した電力を無線で衛星に送り、日本で受電するという構想もあります。まさに夢のような話です。 何千kmと言う遠隔地から巨大な電力を送電することができるかが課題です。 費用対効果を考えると、これらアイデアは少々無理があるように思いますが、日本から離れたところに太陽光発電パネルを設置することに大きな意義もあるのです。 それは時差で日照時刻がズレルからです。一日の内で電気を一番食う時間帯は昼間から夕方までです。日本国内に太陽光発電パネルを設置すれば、電力消費が大きい時に発電量が最大になり都合がいいのですが、日本は山国ですから広大な平原はありません。その点モンゴルは土地代がただのように安いので、いくらでも太陽光パネルを敷き詰められます。 もう一つ重要な課題は、日本列島を北海道から鹿児島まで南北につなぐ電力系統の背骨になる基幹送電線網を施設する必要があります。 この基幹送電線は交流送電ではなく、直流送電がこれから新しい技術開発につながると思います。 このように、EV化は単なる『車』だけの問題ではなく、これから始まる新しい時代の幕開けにつながるはずです。 |
2017年7月11日(火)
一部改定
自動車のEV化は本物か? 課題は何か?
| トヨタ自動車が『21世紀に間に合いました!』というキャッチフレーズで世界で初めて発売したハイブリッド車、初代プリウスから4代目になった。 エンジンは当初の1500ccから1800ccにパワーアップし、Panasonicニッケル水素バッテリーをメインに、一部のグレードにはリチウムイオン電池も搭載している。 2000年5月、2003年9月、2009年5月、2015年12月と、4回のモデルチェンジを行い、燃費性能を大きく向上し、運転性能も良くなった。 ホンダもハイブリッド車でトヨタを追随しているが、まだ後塵を拝している。 注目すべきは、日産自動車が急に頭角を現してきたこと。アクアやフィットやデミオと同じクラスの『日産ノート』に、EVの『リーフ』のシステムを搭載し、これにエンジンを加えてチョイ換えして大ヒットさせた。まさに商品企画の妙だと思う。  商品がヒットするにはメーカが肝いりで全社から優秀な開発陣を集め、巨額の研究開発費や設備投資をして、今までなかった新製品を市場に出すことで生まれることが多い。 しかし、まれに『日産ノート e-POWER』のように、今まで他の車(リーフ)で使ってきた技術や部品を組み合わせることで大ヒットにつながることもある。この場合、開発投資が極端に少なくて済むので企業は儲かる。 リーフはEV専用車として開発された車だが、1回の充電で200km程度しか走らず、少し遠方に出かけるにはバッテリーの電気容量を気にしなければならず、一般の人にはあまり人気が出なかった。 しかし、モータの強烈な加速力や回転の静かさは大変魅力を感じる人が多かった。 そこで、日産はガソリン車の『日産ノート』の車体にEV『リーフ』のモータをそのまま積み、小さな1200cc直列3気筒エンジンを積み、このエンジンに発電機を直結し、発電した電気をリチュウムイオン電池に充電し、走行はリチュウムイオン電池から駆動モータに電気を送ると言うシリーズ方式で、これが『日産ノート e-POWER』だ。 『リーフ』はエンジンを積まない純粋なEVだ。だからリチュウムイオン電池の容量は非常に大きいので重い。『日産ノート e-POWER』はガソリンエンジンを積んでいるので、電池の容量が減ると、エンジンがかかり発電機を回し充電する。だから電池の容量は小さくできるので軽くなる。ガソリンさえあれば、従来のハイブリッドやガソリン車と同様どこまでも走ることができる。 『日産ノート e-POWER』には『リーフ』と同じ出力の駆動用モータを積んでいるので、リーフより軽い車体と相まって、大変力強いスタートや加速が得られる。 又、スタート時はエンジン音がしないので大変静かにスルスルと走る。しかし、急激な加速をすると大量の電気を食うので、小さな容量のバッテリーは充電してやらなければ電気が空っぽになる。そこでエンジンがかかるという仕組みだ。 しかし、その際の加速や静かさは、今までのガソリン車やハイブリッド車になかった楽しさを感じさせてくれるので、あっという間にベストセラー車になった。街中の走行では燃費も大変良いらしい。 日産自動車はこれほど『ノート e-POWER』がヒットするとは思っていなかっただろう。だが、ヒットする要件をしっかり満たしている。 トヨタ自動車が2000年に初代プリウスを発売して今年で丸17年になる。この間、ハイブリッドの代名詞になった『プリウス』だが、これは大量の開発者や開発費を注ぎ込み、いろんな課題を克服し燃費や性能を向上させてきた。努力とノウハウの積み重ねの結果だ。 『日産ノート e-POWER』は新参者として、即ベストセラーに入った。モノづくりの面白さというか、怖さを感じるほどだ。 しかし、何もないところから『ノート e-POWER』が生まれたのではなく、長年、『リーフ』を販売し、EVのノウハウを積んできた結果だと思う。 このクラスはアクアやフィットなどが圧倒してきた激戦市場だが、『ノート e-POWER』の発売で1・2・3の販売ランキングが入れ替わった。イラついているのがホンダではないかと思う。 初代フィットハイブリッドはエンジンの軸にモータを直結し、エンジントルクをモータでアシストする方式(IMAシステム;Integrate Motor Asist system)を採用した。この方式は構造が簡単で、モーターがエンジントルクを補助するので出足は良くなるが、十分なエネルギー回生電力が得られないので、燃費の面ではトヨタハイブリッド車に大きく差をつけられていた。 そこで現行のフィット3ハイブリッドは、エンジンとモータをクラッチで切り離せる構造に変更し、ブレーキをかけるとエンジンは切り離し、モータを発電機として働かせ、車の運動エネルギーの回生発電量を大きくし、モータの出力も大きくして、モータだけで車を始動させ、走行できるように改良した。 さらにフォルクスワーゲン(VW)等が採用しているDCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)と言う新しい変速機を搭載し、変速機の効率を改善した。同時に、変速時の加速の感覚が体感できるようになった。 この結果、燃費性能はアクアに匹敵するところまで迫ってきたが、今なお、追い越すところまで至っていない。熾烈な戦いを挑んでいる。そのこだわりがホンダの技術の真骨頂だ。燃費で負けられない。数値だけでなく、実燃費や運転の楽しさも同時に満たさなければならないという使命がある。 フィット3は今年6月30日にビックマイナーチェンジを実施し、ガソリン車は1300と1500ccと、ハイブリッド車の3車種を発売した。 1300ccガソリンエンジンは、燃焼効率が高いと言われる『アトキンソンサイクルエンジン』方式を採用し、ホンダ独自のVTECエンジンで大変気持ちよく軽快に吹き上がり、加速する一層磨きがかかった素晴らしい車に変身した。フィットが発売されてから16年目になり、車として熟成されてきた感じがある。 我が家には初代のフィットとフィット3ハイブリッドがあり、初代のフィットは購入後14年が経ったので、先日、このマイナーチェンジされたばかりの新型ガソリンモデル(フィット3 GK)を家内用に買い替え、先日納車されたので、早速、運転してみたが、今までの初代フィットに比べると、14年間の技術の進化が実感できる。 燃費が良くなったのは当然の話だが、エンジン音やタイヤの騒音が低く抑えられ、大変静かな車になった。ハンドルはパワーステアリングにモータ方式を採用しているが、軽くて大変なめらかになった。変速機はCVT方式だが、トルクコンバータが付加され、発進や加速がスムーズになり良くなった。 何より、今回のマイナーチェンジの目玉は、最新の安全運転支援システム(ホンダセンシング)の搭載だ。これは、前方の人や車を検知し衝突防止、ふらつき警告、高速道路での車線キープ、車間距離検知のオートクルーズシステムなど8項目の安全支援システムが作動する最新最強のシステムになった。 具体的には単眼光学カメラと、ミリ波レーダーで安全運転を可能としている。 これはカメラ画像の高精細化、画像認識・画像処理技術、ミリ波レーダー発信・受信素子、高速信号処理システムLSI、マイコン、新アルゴリズムによるソフトウェア技術等のエレクトロニクスの進化が車の安全運転支援システムを可能にしている。 このホンダセンシングは、スバルの2カメラ方式(アイサイト)と合わせ、現状では一番進んだ安全支援システムと言われている。 何ができるのかは、下記の8項目 ①歩行者対応自動ブレーキ ②歩行者衝突回避支援 ③誤発進抑制 ;アクセルとブレーキの踏み間違いで急発進することを抑制 ④先行車発進告知;信号待ちで先行車が発進したことを知らせる ⑤標識認識(表示);道路標識を認識し、ディスプレイに表示する ⑥先行車追従 ;高速道路で車間距離を保ちながらオートクルーズする ⑦車線維持支援 ;高速道路で車線を維持運転する ⑧路外逸脱抑制 ;道路外にはみ出した際に警告する カーメーカは今まで、車本来の走りや快適性等を競ってきたが、ここにきて急激に「燃費と安全運転」と言う2つの項目が加わってきた。特に安全運転は高齢者による事故が急増する中で、大きく注目されてきたからだろう。 ますます、カーメーカはエレクトロニクス技術に対応出来なければ生き残れない時代に入ってきた。逆にエレクトロニクスメーカは部品(各種センサー、モータ、半導体など)のみならず組み合わせたシステムとして提供するメインサプライヤーとして、また直接、車の製造に参入する可能性が生まれてきた。 さて、フィット3のビックマイナーチェンジが行われた直後であるが、2年後(2019年)には次のフルモデルチェンジが行われる噂がある。それについて触れて見る。 以下の内容は『当たるも八卦、当たらぬも八卦』と気軽にお読み頂きたい。 ホンダは3種類、あえて言えば4種類のハイブリッドシステムを開発し販売している。 ①3モータ方式 SH-AWD レジェンドに搭載、左・右後輪に別々のモータを組み込んだ独自のシステム。 ②2モータ方式 i-MMD アコードやオゼッセイ等。この方式はシリーズハイブリッド方式に近い。 ③1モータ方式 i-DCD 大衆車クラス;フィット、フリード等に搭載、 現行フィット(フィット3)はデュアル・クラッチ・トランスミッション(DCT)と言う変速メカニズムを搭載し、複雑な制御プログラムにより、モータとエンジン駆動をうまく切り替え、運転時の加速や走りを実現してきた。しかし、このDCTのメカニズムは複雑で部品点数が多く、制御プログラムが難しいので、量産時のコストや調達の課題もあるはず。 その証として、フィット3は発売後に前代未聞の5回リコールを実施した。そのため、優れた特徴を持っていながら、フィット3は販売が伸び悩んでしまった。 現在、愛用中のフィット3ハイブリッドはそういうトラブルも全て解決し、対策され、燃費も良く、運転時のDCTが切り替わる気持ち良さも味わえる。生来のフィットの室内の広さと、窓やルーフの広々とした解放感は群を抜いている。 さて、現行の1モータシステム(i-DCD)はガソリンエネルギーの利用効率や運動エネルギーの回収(回生)効率に限界があると見抜いたのだろう、ホンダは次期フィット4は2モータシステムになるといううわさがある。そうなると、アコード方式のハイブリッドシステム i-MMDを搭載することになる。 この2モータ方式が優れているのは、一般走行は強力な駆動モータで行う。日産ノートe-POWERと同様にシリーズ方式ハイブリッドに近い。 日産ノートe-POWERと違う点は、高速道路の走行はエンジンが車輪に直結し駆動する。これはアコードが大型車でありながら30km/Lを実現している理由である。 高速走行時だけエンジンと車軸が直結するので、変速機やCVTやDCTのような複雑な構造の可変変速機は必要がない。単に固定ギヤーのシンプルな構造になる。たとえば、100km/時で走行する場合、エンジン回転数を1800回転となるような歯車を用意すればいいことになる。それ以外の走行モードは駆動モータがある固定歯車で対応する。但し、エンジンと発電機、駆動モータと車軸にはクラッチが介在する。 日産ノート e-POWERの弱点は高速道路の走行にあるらしい。 高速道路の走行中はエンジンを回し発電機を回転させ、発電してバッテリーに充電しながら、その電気でモータを回して車輪を駆動する。完全なシリーズ方式である。 この場合、エンジン出力が100とすると、仮に発電機の効率が90%、モータ効率が90%とすると、日産ノートe-POWERの出力は、100×0.9×0.9=81となり、ガソリンエンジンで走るのに比べ19%もロスが生じてしまう。だから日産ノートe-POWERは高速道路の燃費は余り良くないというデータが出ている。 アコード方式は、一般道路の走行は日産ノートe-POWERと同様シリーズ方式でモータで走る。高速道路では、発電機、モータを介せず、エンジンが車軸と直結するから、100×1=100となり、日産ノートe-POWERの81より高くなる。 余談だが、電気部品で一番効率が良い部品はトランスで、98%前後になる。モータや発電機は多分90~95%程度になると思われる。上の話は発電機やモータの効率を90%と仮定した場合である。 アクアやプリウスは2モータ方式を初代から採用しているが、発電機はエンジン軸と常に直結している。駆動モータとエンジンは遊星歯車を介してつながり、電子式変速機と呼ばれているメカニズムを採用している。だから発電機は常にエンジンとつながっているので、高速道路では発電が不要な場合でもエンジンの負荷となる。そのため、高速道路の燃費は必ずしも良くない。一般道路の走行時は高燃費となる。 簡単に言えば、トヨタハイブリッド方式はアコード方式と日産ノートe-POWER方式の中間的な方式と言えるだろう。 次期フィット4の2モータ方式は構造的に簡単で、軽量化ができ、一番燃費が良くなる可能性がある。 各社はエンジンそのものの効率化の取り組みも強化している。特にこの分野では、マツダが熱心に研究し『スカイアクティブ』と命名し、特にジーゼルエンジンでは突出した高効率で騒音や振動が少ないエンジンの開発に成功している。 50年も前、学生の頃、エンジンの熱効率は、ガソリンエンジンで25-30%、ジーゼルエンジンで35%程度という値だった。それが最近はガソリンエンジンで50%という値を目指している。このようにエンジン自体の改善も進み、省エネ化されてきた。 シリンダー内でガソリンの燃焼が可視化できる技術が開発され、温度や空気とガスの割合とか燃焼技術が急速に進んだこと、シリンダーとピストンの摩擦、軸受けの摩擦の軽減、クランクシャフトの空芯化による軽量化など、徹底したロスの排除をして燃費を改善している。 また、車体の軽量化も年々進化している。自動車の車体は鉄板を使っているが、最近の高張力鋼板という鉄板は薄くても大変剛性が大きい優れもので、軽くてもしっかりした車体が造れる。一方では衝突安全という規制があり、薄くて軽い車体だが、万一衝突しても安全だという車体設計が進んできた。 あらゆる方面で、まさにすさまじい開発競争を行っている。 トヨタが7月10日に発売したカムリは、2500ccで33.4km/Lという優れた燃費を実現している。これはこのクラスで燃費がトップだったアコードを上回った。ホンダも黙って見ている訳ではなく、次期アコードではこれを上回ると思う。 2モータ方式の次期フィット4は、少なくとも40km/L以上を達成するはず。 車は単に燃費が良いだけではなく、運転して楽しく走る車でないと意味がない。 その点、日産ノート e-POWERは今までのハイブリッド車の常識を覆した点に大ヒットの要因がある。 矢沢栄吉の『やっちゃえ NISSAN!』が良く似合う言葉だ。 2年後のフルモデルチェンジのフィット4の2モータハイブリッドが楽しみだ! |
2017年6月14日(水)
昨日、愛車フィットが最高燃費を出しました!
| 昨日、愛車、フィットハイブリッドで和歌山の有田郡有田川町の郷里に行きました。 全走行距離は250km足らず。 その内、高速道路は片道約120kmで、往復では240km程度です。 昨日は渋滞もなく、高速道路は80km~90km/hで、殆どオートクルーズ走行をしました。家から第二京阪高速道の下の一般道路を門真まで走り、門真から近畿自動車道に乗り、阪和自動車道で有田インターまで高速道路を走り、有田川を渡って、有田インターで降り、金屋まで一般道路を走るコースです。 所要時間は約2時間足らずで、途中、紀ノ川サービスエリアで一休みし、昼食をとりました。このコースは毎月、一度走ります。 昨日の天候は晴れ、気温は26度ぐらいで、オートエアコンをかけて走りました。 出発前にガソリンを満タンにしていたのですが、250km走り、平均燃費は計器表示で、29.2km/リッターとなりました。(下の写真のとおり) 今まで、26.5km/リッターが最高でしたが、今回、非常に良い値になりました。車の全走行距離が16,000kmになり、エンジンやシャフトのなじみが良くなった性で、摩擦などが減ったためかな!と思います。 この値なら、満タン給油値で計算しても、25km/リッター以上になると思います。 今までの最高燃費となりました。(メータ表示と実際の給油値で計算すると若干の差が出る)  昨日は天気が良くて、室内は暑かったので、走行中はエアコンを25度に設定し、かけっぱなしにして、この値になりました。 昨日は天気が良くて、室内は暑かったので、走行中はエアコンを25度に設定し、かけっぱなしにして、この値になりました。普段、家の近辺を買い物に行く『チョイノリ』では、17~20km/リッターですが、高速道路を80km~90km/hの定速走行では大変良い燃費を示すことが分かりました。 さて、6月29日にこのフィットのマイナーチェンジが行われます。情報ではさらに燃費が若干、改善されるそうです。 ハイブリッド車はプリウスが先行し、ハイブリッドの代名詞になりました。その後、アクアもよく売れました。トヨタのハイブリッドシステムは、全て同じ2モータ方式で、遊星歯車を使いトランスミッションを積んでいません。そのため、なめらかな加速と高燃費が売りになっていますが、加速時のもたつきが感じられます。 ホンダのハイブリッドは、3つの方式を車格に応じて使い分けています。 低価格の小型車には、1モータ方式のスポーツハイブリッド、アコードやオゼッセイ等は2モータ方式、レジェンドなど高級車には3モータ方式を採用しています。 フィットやフリードなどはシンプルな1モータ方式を採用しています。以前のフィットハイブリッドはエンジンのクランクシャフトとモータ軸が直結されているIMA方式でしたが、この方式では燃費の改善に制限があり、現行の新型フィットはエンジンとモータ軸の間にクラッチを入れ、切り離せるようになったi-DCD(inteligent Dual-Clutch Drive)方式を採用し、燃費がトヨタハイブリッドに迫る値になりました。 近距離の『チョイノリ』ではまだ、トヨタ方式の方が若干優れているような気がします。 ホンダのハイブリッドは加速時の応答が良く、ストレスなく気持ちよく走れます。 この他に、最近発売された日産自動車ノート e-Powerのハイブリッドも大変良く売れています。この車はエンジン付きのEV車という内容で、ハイブリッド車としては、シリーズ方式で、EV独特の走りをするようですが、まだ実際に運転したことはありません。 ハイブリッド・システムは一応、いろんな方式が出尽くした感がありますが、ハイブリッド車の燃費はまだ、多少、改善の余地があるようです。 エンジン自体の熱効率の向上や、エンジンやギアーのメカ部の軸受け摩擦の低減や、インバーター回路の発熱によるロスの低減や、リチュウム電池の大容量化や、電池の充放電時の改善や、モータの高効率化など細かな改善が図れています。 フィットハイブリッドのマイナーチェンジが6月29日に発売されますが、これには安全運転支援システム(ホンダセンシング)を搭載しています。
 マイナーチェンジは、追突防止、高速道路などの安全運転支援などに加えて、燃費をアクア並、または超える値に改善したようです。詳細は未発表です。 マイナーチェンジは、追突防止、高速道路などの安全運転支援などに加えて、燃費をアクア並、または超える値に改善したようです。詳細は未発表です。各社、燃費の数値では負けられないという事のようです。コンマ何km/リッターに拘るところまで競争しています。 現役の頃、Technicsブランドのオーディオアンプやチューナなどを設計していましたが、感度や出力やひずみやSNなどの性能数値では敗けられないということで、コンマ以下の数値にもこだわったことがありました。 燃費競争もそういう状態になって来たようです。 ただ、車の燃費は、実用時の燃費と、カタログ値が3割ぐらい差が低く出ますので、カタログ値をそのまま信用することができません。多分、マイナーチェンジしたフィットは、アクア並の37.2km/リッターを上回る37.4km/リッターぐらいの表示になるのではないかと言われていますが、果たしていくらになるのか楽しみです。 ちなみに、小生が乗っている現行のフィットのカタログ値は36.4km/リッターです。 そんなことを思いながら、昨日の実走行の29.2km/リッターは大変良い実績を示しました。 来月の和歌山行きではどうなるか?楽しみです。 良い車がドンドン発売されて、楽しい時代になってきました。 |
2017年3月19日(日)
EV車には変速機が不要です!
| 『自動車がEVに代わる』という流れが世界中で本格的になって参りました。EVは電池とモータで走りますが、変速機が原理的に不要になります。 その理由と、不要になる変速機の製造メーカは今後、どうなるのでしょう? 技術の進歩や変化がもたらす産業革命とも言える潮流です。それに触れてみました。 要素技術が大きく変わる時代には、今まで長年かけて積み上げてきた自社の技術が不要になることが突然起きることがあります。 私が経験した身近な話として、50年ほど前にはラジオやテレビは真空管という部品が使われていました。今時、真空管と言っても知らない人が増えてきましたが、・・・・。 私が会社に入った頃、昭和40年代前半まで、ラジオやカラーテレビには真空管が使われていました。 入社時に新入社員研修の一環で、ショップ実習という呼び方で、街の電気屋さんに約3か月ほどお世話になりましたが、アルミケース(アルミ製のカバン)に修理道具一式を入れたカバンを自転車に積んで、カラーテレビの修理にお客様の家に出かけたことを覚えています。 そのアルミケースの中身は、当時のカラーテレビに使われている30から40種類余りの大小の真空管がぎっしりと詰まっていました。その他の部品は抵抗器やコンデンサーなど少々でした。道具は半田ごて、テスターだったと思います。そして、サービスマン用の修理マニュアルが入っていました。このサービスマン用のアルミカバンがあれば、当時のカラーテレビの故障の9割程度は修理できました。 カラーテレビの原理は難しいのですが、どこが故障しているかを見分けるのは比較的簡単にできました。画面が全く映らない、画像は出るが音が出ない、画面がカラーでなく白黒状態、画面が半分しか映らない等々、テレビは画面と音が表示されますので、それをみれば故障箇所の検討をつけられたのです。 しかも故障の7、8割は真空管の不良で、単なる部品としての不良か、長年使って劣化したための不良かが多く、ほとんどは真空管を新品に差し替えるだけで直りました。 当時は町の電気屋さんでも、見よう見まねでテレビの修理ができたのです。 そのカラーテレビが、プラズマテレビや液晶テレビに代わり、最近のテレビはほとんど故障しなくなりました。以前は、画面を映すブラウン管というガラス管で出来た大きな一種の真空管を使っていました。これは非常にデリケートな部品で、調整が狂うととんでもない画面になり、歪んだり、ボケた画面になったり、いろんな症状が出ました。 また、真空管の一種ですので、1、2年使うと劣化して、次第に暗くなり、ぼやけたり、色の鮮やかさが無くなったりしました。使用時間と共に必ず不良が起きました。 今の液晶テレビやプラズマテレビは革命的な商品で、過去のブラウン管テレビの様な不安定さが無くなり、いつまでもきれいな画面が映るようになりました。その訳は、アナログ技術からデジタル技術へ電子回路の動作原理の変化が基本にあります。 この話は難しくなるので、ここでは省略します。 一時期、プラズマテレビか、液晶テレビかの戦争は液晶に軍配が上がり、プラズマテレビを主流に据えてきたPanasonicはシャープの液晶に完全に負けました。 『なぜ負けたのか?』 ①液晶テレビの方が消費電力が少なくできた。 さらに、LEDのバックライトができるようになり、さらに長寿命化、省電力化した。 ②画面の精細度を高める技術的余地が残されていた。 画面の綺麗さの面は、プラズマテレビは自発光型ですので、液晶にない良さもあり ましたが、世の中の流れは液晶になりました。 現在は地デジ(地上波デジタルテレビ)に完全に移行して、以前のアナログ放送は電波を停波(放送を止める)しました。 そして、今、量販店の店頭には『4Kテレビ』という表示のテレビが並んでいます。今のところ、4Kテレビ放送はされていませんので、4Kテレビを買っても、映る画像は従来の2K(フルハイビジョン)の画質と同じです。 (注)普通のフルハイビジョンテレビが縦・横に約1000×2000の仕切りで、約200万個の画素(ドット)で構成されています。これを『2kテレビ』とも呼びます。 横方向の仕切りの数と考えれば分かり易いです。 これに対して、縦・横に2000×4000の仕切りで、800万画素で構成されたものが、4Kテレビです。2Kに対して4倍の細かな粒粒(ドット)で画面が構成されます。 その分、画像が高精細度化し、きれいに見えます。 さらに、4000×8000の3200万画素のテレビ放送とテレビジョン受信機が開発され、各地のイベントやショーで商品の出展や紹介がされています。 これは『8Kテレビ』と呼びます。2Kフルハイビジョンの16倍の細かさで超高精細度テレビです。 2020年の東京オリンピック開催時まで、この8Kテレビ放送が開始できるよう現在、総務省電波審議会とメーカ各社で詰めをしています。 技術的に特にクリアしなければならない難しい問題はないようですので、近々、試験放送が開始されるはずです。8Kテレビ放送の前に、4Kテレビ放送が開始されますが、4Kも8Kも地上波電波では送れませんので、BS放送かCS衛星からの電波を受信することになります。今、売っている4Kテレビは、そういう訳で、買っても映りは2Kの画面になります。4K放送が始まっても、そのままでは4Kで受信できませんので、注意が要ります。光インターネット(例えば、eonet など)回線でテレビを見ている場合は、今後、4Kの放送に対応するということになるでしょう。 話がテレビの内容になりましたが、元に戻しますと、要素技術が大きく様変わりする時に従来の技術が役に立たない、または不要になるという状況になることがあります。 その例が、真空管やブラウン管を作っていた工場では、トランジスタや、ICや、LSIや、液晶パネルが全く造れないということに相通じます。 真空管とトランジスタは、電気信号を増幅したり、スイッチしたり、検波という作用をするのは同じことですが、その動作原理が全く違うものです。 この流れは、電気メーカとしては革命的な出来事だったのです。ですから真空管を作っていた会社や工場が潰れたり、新しい半導体会社が生まれたり、老舗の会社が潰れたりしました。 社内の工場も同様で、真空管製造工場で、トランジスタは造ることができません。働く人々も今までと全く違う知識や作業を要求されました。まさに産業革命です。 こういう状況は、電気業界だけでなく、今や自動車業界にも起こりつつあります。 いよいよ、本論に入りますが、燃料のガソリン価格の高騰と排気ガス規制を受け、ガソリンエンジンそのものが高効率エンジンに代わり、ジーゼルエンジンが見直され、さらにモータを積んだハイブリッド車が今や自動車の主流になろうとしています。さらにその先にはEV(電気自動車)が大きく伸びる可能性を見せてきました。 Panasonicとアメリカのテスラが共同で世界最大のリチュウム電池工場(ギガファクトリー)の建設を進めていますが、EVの普及と、太陽光発電などの自然エネルギー電力の一次貯蔵用としてリチュウム電池を大量に製造することを目的にしています。 ここで、従来の自動車メーカが危惧していることは、このEV化の流れにうまく乗らなければ、従来積み上げてきた自動車製造技術やノウハウが不要になることです。 エンジンで動く自動車は部品点数が約2万点以上もあり、その一つ、一つの部品の製造ノウハウが蓄積され、そのノウハウの下で自動車が完成しています。一朝一夕にはできない産業なのです。 これがEVに代わると、部品点数は十分の一ほどの2000点ぐらいになります。 しかも、モータと、モータを制御する電子部品、および電池になり、その技術は通来のメカニカル部品(鋳造物、歯車、ベアリング、軸受、ばね、ネジ、などなど)と技術の世界が違います。 さらに、ガソリンエンジンやジーゼルエンジンの持つ特性と、EVに使うモータの特性の違いから、今まで自動車に欠かせなかった変速機(ミッション)が不要になります。 変速機も最近は、一部マニア車にマニュアルミッションが残っているものの、ほとんどはオートマチック変速機に代わりました。 オートマチック変速機も、省エネや排気ガス対策で、いろんなタイプのものが開発され、ギアの組み合わせで変速するタイプとベルトで変速するタイプがあります。それぞれ、 一長一短があるのですが、エンジン車には変速機が欠かせない重要部品でした。 それがEV車では、モータと車軸を一定のギアーを介してつなぐだけという簡単な構造になります。何故、そういう構造で車が走れるのかを以下に説明します。 そもそもクルマに変速機が搭載されているのは、エンジンの「回転速度-トルク特性」とクルマに求められる「駆動力特性」の間にある“溝”を埋めるためです。 エンジンは特定の回転数の時、発揮されるトルクが最大に達し、それ以外では急激にトルクが落ちます。一方、クルマは発進や加速時に大きな駆動力を必要とし、一定の速度に達すると小さな駆動力でも速度を落とさずに走行できます。 クルマに求められるこのような駆動力特性を実現するため、エンジン車は変速機が必要なのです。エンジンのトルクが出る回転域を保ちつつ、変速機で減速比を変化させることでさまざまな走行条件に対応します。 これに対してモータは、停止状態から一定の回転速度までは最大トルクを保ち、その速度以上になるとトルクが落ちます。こうしたモータの回転速度-トルク特性はクルマに求められる駆動力特性に近いので、EVはモーターに固定段の減速機を付けるだけでさまざまな走行条件に対応した走りができます。 このように変速機は、パワートレーンの電動化でその存在意義が問われる局面に差し掛かっています。それは、エンジンを搭載するハイブリッド車(HEV)でも、しかりです。 EV時代に向けてモータ主導で走行するのであればエンジンは脇役となるので、変速機の役割は少なくなるからです。 EVはモータの逆起電力などの問題があるので、変速機がないと最高速度を上げにくいといった課題があります。しかし日常利用のEVは時速百数十km程度出せれば十分なので、重い変速機をわざわざコストをかけて付ける必要はないのです。 ただ、一部ではありますが「運転の楽しさを高めるために変速機を付けたい」といった声もあります。特にスポーツ車ではこうした意見が根強くあるそうです。 例えば米BorgWarner社は、ある自動車メーカーとの共同開発で変速機能を備えるEVを2017年内に試作するそうです。どんな変速機を用いるかは分かりませんが、「EVならでは」といえる変速時のフィーリングや加速感を狙っているのかもしれません。 |
2017年1月18日(水)
マツダが超元気ですね!
| 自動車メーカのマツダは「スカイアクティブ」と名付けたエンジンをガソリンエンジンと、ジーゼルエンジンの両方に採用した。これが大変人気を得ている。 トヨタやホンダがハイブリッド車を販売し、特にトヨタはハイブリッド王国になり上がった。プリウスはハイブリッドの代名詞になり、アクアが続く。ホンダはその後を追っかけているが、フィットハイブリドの5回のリコールが足を引っ張って失速状態。車は悪くないが、今一評判が出ない。今年4月頃に起死回生のフィットハイブリッドのマイナーチェンジが行われるらしい。 これに日産自動車が最近、ノートでシリーズ方式のハイブリッドを発売した。このハイブリッドノートは日産がこだわってシリーズハイブリッドとは呼ばずにイーパワーと呼んでいる。これが大変人気になっている。日産はEVのリーフを既に販売し、リーフの販売実績をもとにして、今回ノートをハイブリッド(HV)化して発売した。モータで走る車だが、ガソリンエンジンを積み、エンジンは発電機を回すだけで、車軸とつながっていない。ガソリンエンジンと発電機、モータと車軸は完全に分離されている。つながっているのは電気配線のみ。発電機はリチュウムイオンバッテリに充電するためのもので、電池からインバータを経由してモータにつながる方式。 このモータはEVのリーフに使ったモータと同じものということなので、加速性能は良さそうだ。 未だ、試乗したことがないので、何とも言えないが。 マツダはこれらの自動車3社と違い、エンジンそのものを見つめなおし、その効率アップに力を注いで来た。その成果が、『スカイアクティブ』という名前で、新しく従来のエンジンの欠点をいくつもクリアしてきた。 従来『エンジンはホンダ』というイメージが強くあった。 アメリカの排気ガス規制のマスキー法が施行された時に一躍有名になったのはホンダのCVCCエンジンだった。見事に不可能と言われた排気ガス規制をクリアしたのだ。 しかし、今やエンジンはマツダという感じになってきた。 スカイアクティブで特に注目すべき点はジーゼルエンジンだ。ジーゼルエンジンは軽油を燃料にし、圧縮比を20:1以上に高めて、空気を断熱圧縮し高温にした状態の空間に燃料を吹き込み自然着火させて爆発させるという方式でエンジンが回る。 従来のジーゼルエンジンは圧縮比を20以上と高くするのが常識だった。このためシリンダやピストンやエンジンヘッドと言われる部品の強度が必要であり、その分、ガソリンエンジンに比べて高価で、重量がガソリンエンジンに比べて重くなる欠点があった。 また、燃料を吹き込むノズルの細かな制御を高速で行うための電子回路技術は近年急速に進化し、ノズルの燃料圧力は2000気圧という途方もない高い圧力をかけ、微細な霧のような状態で、エンジン内に吹き込むコモンレール方式という技術が開発され、これによりジーゼルエンジンの黒い煙が出るのが防げるようになり、しかもパワーが大きくなった。 しかし、ジーゼルエンジンは相変わらずアイドリング状態で、カリカリという独特の振動音が発生し、乗用車として使うにはやかましいという弱点があった。 ヨーロッパの乗用車にはジーゼルエンジンを搭載した車が多い。それは車体が大きいので、防振対策や防音対策が十分できることだ。ヨーロッパは高速道路が多く、発進停止の頻度が少ないためにあまりエンジン騒音を気にしない。 ジーゼルエンジンはガソリンエンジンと比べると、トルクが大きく出足が力強く、かつ上り坂の粘りが良いという長所がある。 マツダはこのジーゼルエンジンの欠点である音に着目し見事に解決した。それは従来ジーゼルエンジンは圧縮比を高くするという常識を破り、なんとガソリンエンジン並みに圧縮比を14ぐらいまで下げた。これによりカリカリという独特の音と振動を大幅に低減することに成功した。 逆にガソリンエンジンの開発では、圧縮比を従来の10~12ぐらいを14前後まで高めることで大幅な高効率エンジンを開発した。 この新ジーゼルと新ガソリンエンジンにスカイアクティブという名前を冠して、全車に搭載し、高い評価を得ている。最近マツダ車をよく見かけるようになったのは、このような商品力の大きな向上が基本にある。また、マツダは独特の柔らかい曲線を活かし、デザイン面でも評価が高い。そのほか、細かな点を見直し改良してスカイアクティブエンジンは大成功している。 消費者(ユーザ)は良く商品を見つめているなという感じがする。 一方、ハイブリッド車はその構造から従来のガソリンエンジン車に比べて、モータと大容量バッテリーと、大容量インバータと、プログラム制御回路という高額な電気部品が余分に必要になる。だからどうしてもハイブリッド車は値段が数十万円高くなる。 これがマツダのように、エンジンの改善だけで済むのなら低燃費を実現しながら値段はそう高くならない。 ここまでは、今までの話である。ところが、マツダはまたまた新しいことをやってのけたというニュースを出した。 これが実に素晴らしい。エンジンのマツダはまだまだ満足せず進化していた。 これがマツダの真骨頂だ。広島が熱い!! ガソリンエンジンの熱効率は元は20%台、それが次第に改良されて30%台になり、40%を狙うところまできた。まだ40%を超えたという話は聞いたことがない。トヨタのプリウスのエンジンはトヨタエンジンの新しい世代のエンジンということで40%に近いと聞いている。 ところが今回発表のマツダの新スカイアクティブエンジンは、現状のスカイアクティブエンジンをベースとして、さらに30%効率を上げたという話である。現状のスカイアクティブエンジンが、35%の熱効率ならなんと45%を超える値になる。 従来比で5%程度向上させるのなら、部品を見直して軸受の摩擦を減らすとか、可動部を軽くするとかで実現できる。これも大変な努力がいるが精々数%程度の改善レベルである。 今回のマツダの発表は何と現状のエンジンより30%効率を改善したという話だ。これは革命的な出来事だと思う。エンジンに未だそういう革新的な改善ポイントがあったのかと感心する。 これは従来のガソリンエンジンではタブーや不可能だとされていた方式や技術を導入したことに起因する。 4サイクルエンジンは、吸入→圧縮→爆発→排気を繰り返し、ピストンがシリンダー内を上下することで、クランク軸を回転させている。 この時、圧縮行程でピストンが一番上に上がった点(上死点)より少し手前で、点火プラグに電気火花を飛ばし、ガソリンと空気の混合ガスに着火し、爆発させる。その爆発力でピストンが下に押し下げられる。 ジーゼルエンジンでは、点火プラグがなくて、ピストンが上死点の直前にノズルから霧状態の燃料が吹きこまれ自然着火する。 これがガソリンエンジンとジーゼルエンジンの基本的な違いである。 マツダはスカイアクティブエンジンをガソリンとジーゼルエンジンの両方を手掛けてきたので、ガソリンエンジンをジーゼルのように点火プラグなしで着火する方式を考え出したようだ。 それが下に記述している予混合圧縮着火(HCC)と呼ぶ方式だ。 ガソリンエンジンの専門家からすると、それは不可能という答えが返ってくるはずだ。 しかしスカイアクティブを深堀していたマツダのエンジンエンジニアはその壁を乗り越えた。 これは大発明に相当する。素晴らしい技術開発だと思う。 これに類することは、技術の世界ではたくさんある。 例を挙げると、ホンダジェット機だ。主翼の上にジェットエンジンを載せている独特の姿をしている。小型ジェット機は車輪は小さく、旅客機のように主翼の下にエンジンをぶら下げられないので、今までの小型ジェットは全てボーイング727のように機体の後ろに2個のジェットエンジンを取り付けるのが常識だった。 ホンダの藤野さん(ホンダジェット社長)は、ある日、突然ひらめいて主翼の上にエンジンを載せればいろんなメリットがあることに気付いた。しかし、空力学的にこれはタブーで、やってはならないことだとされていた。そこで諦めていればホンダジェットは商品化につながらなかった。 彼は沢山の空力実験を通じて、あるポイントに取り付けると素晴らしい性能が得られることを発見した。スイートスポットを見つけ出し、その後の実験でそれを証明した。 これがホンダジェットの生まれた原点である。その結果、素晴らしいジェット機が完成し、販売を開始し、好評を博し出荷が追いつかず、待ち客が沢山あると聞いている。また、たくさんの航空機に関する賞を獲得している。 マツダの新スカイアクティブは、トヨタやホンダや日産のたくさんのエンジニアが実現できなかったタブーを見事に打ち破った。だから数%の改善でなく、30%の驚くべき画期的なエンジンが発明された。マツダに敬意を表する。 これで、マツダはハイブリッドとほとんど対等にエンジン車で戦えるかもしれないし、何と言ってもコスト的に絶対勝てるはずだ。 このエンジンをハイブリドと組み合わせると、さらに燃費は伸びるはずだ。 ホンダファンとしては、ホンダのエンジニアにもっとタブーに挑戦する意欲が欲しいと注文したい。ホンダ魂はホンダジェットで見事に開花しているが、本業の自動車では最近おとなし過ぎる。ホンダはチャレンジする会社だったはずだ。それが見えなくなると、ホンダの魅力は無くなる。逆に最近のマツダに魅力を感じている。 以下、新聞発表記事を紹介する。 *************************************************************************** マツダは燃費を従来比約3割高めた新型エンジンを2018年度末に導入する。 点火ではなく圧縮によってガソリンを燃やす技術を世界で初めて実用化し主力車に搭載する。 同社は環境規制強化に対応するため電気自動車(EV)の開発も進めているが、当面は世界の新車販売台数の大半をエンジン車が占めるとみている。エンジンの改良を続け主力分野で競争力を高める。 新型エンジンは18年度末に約5年ぶりに全面改良する主力車「アクセラ」から搭載を始め車種を順次広げる。11年に投入した環境技術「スカイアクティブ」の第2世代と位置づける。 ガソリンの燃焼方式に「予混合圧縮着火(HCCI)」と呼ぶ技術を採用する。空気と燃料を十分に混ぜた後、圧力を高めて発火させる。点火プラグを使う従来方式より燃焼効率が高く大気汚染物質の排出量が少ないといった特徴がある。 ただ燃焼させるための着火の制御などが難しく、これまで量産化したメーカーはない。 同社の新型エンジンも加速時などは点火プラグを補助的に使うとみられる。 燃費は同社の従来エンジンより3割ほど向上する。車体が異なることから比較は難しいが、現行のアクセラをもとに燃費を算出すると、ガソリン1リットルあたりの走行距離は30キロメートルに迫る。 マツダは19年までにEVを量産し、21年以降にPHVも投入する計画だ。米国や欧州を中心とした環境規制の強化に対応する狙いだが、同社は新興国も含めた世界の新車市場では少なくとも30年ごろまではエンジン車が中心とみている。 |
2016年9月7日(水)
日産自動車もHVに本格的に参入
| ゴーン社長のワンマン経営で有名な日産自動車は、今までEV戦略をとり、リーフを販売し、それなりのシェアを取ってきたが主流になれなかった。そこで、満を持して、トヨタやホンダと一味違うハイブリッド車(HV)を11月に発売する。車種はノート。 トヨタのプリウスはHVの代名詞になり、その後のアクアもダントツに売れている。 ホンダのフィットも発売当初はアクアと肩を並べる勢いだったが、5回のリコールで熱が冷めてしまった感じがある。 小生はホンダ派なので、フィットHVに乗っているが、車自体は良くできていると思う。 トヨタのHVのような出足のもたもたした感じは全くない。 フィットHVは、今現在、全走行距離が16,000km、実燃費が21km/リッターである。 さて、トヨタ、ホンダの2社が先行したHVは低燃費性を立証した。 日本の3大自動車メーカとして、日産はこの分野で出遅れていた。ゴーン社長は将来、車はHVでなく電気自動車(EV)になると言う方針だったので、トップの意思に逆らえなかったのかもしれない。また、HVの開発には多額の金がかかるので、当時の日産の財務状況では開発費が出せなかったのかもしれない。それはさておき、日産も本格的にHVに参入する。日産HVはまず、最激戦区であるコンパクトカー分野(アクアやフィットやデミオなど強豪がひしめく)で、ノートのマイナーチェンジに合わせて、ノートHVを追加し、この11月に発売するらしい。 トヨタやホンダのパラレル方式とは違い、シリーズ方式を採用してくる。 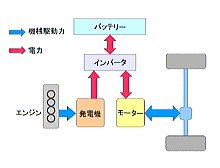 これは、上図のとおり、エンジンは発電機を回すだけで、車軸とはつながっていない。 これは、上図のとおり、エンジンは発電機を回すだけで、車軸とはつながっていない。発電した電気はインバータを介して電池(Panasonic製リチュウム電池)に蓄える。車が走行する場合、バッテリの電気をインバータを介してモータが車軸を駆動する。 このシリーズ方式のメリットは、走行時はモータのみなので静かということ。但し、電池に充電されている電気が十分ある場合。 走ると電池の電気が減るので、エンジンが自動的にかかり発電機を回し、電池に充電する。エンジンはアクセルペダルの踏み加減に関係なく、一番燃料効率が良い回転数(2000回転回転ぐらい)になるようコンピュータ制御する。 カタログ値で、40km/リッター前後の燃費になるようだ。 最新型(第4世代)のプリウスは、一番安いランクのEグレードが40km/リッター(カタログ値)を超える最高の燃費を実現している。商品企画的に逆転現象を起こしているが、世界最高の燃費を言いたかったので、最低価格車Eグレードにリチュウムイオン電池を積んで、燃費表示を改善している。これは燃費にこだわったおかしな話だ。 その上のグレードは、ニッケル水素電池を搭載しているので、燃費は37.2Km/リッタ。 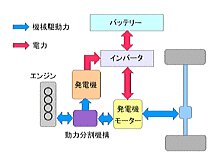 日産自動車は後で出すのだから、すでに販売している車に負けるわけにはゆかない。矢沢栄吉の『やっちゃえ!日産』のテレビコマーシャルどおりにやってくれるのか、楽しみだ。 HVにはシリーズ方式とパラレル方式には長短がある。機構や回路的にはシリーズ方式が簡単になる。今まで複雑なパラレル方式をトヨタやホンダが採用してきた理由にはモータだけで駆動力を得るには馬力不足が感じられることを危惧したためだろう。 しかし、今回、日産は今までEVのリーフを販売して、それなりの販売実績とノウハウを積み、それをベースにして、シリーズ方式でも可能だと判断したのだろう。 EVはシリーズ方式HVのエンジンと発電機を省略したものになる。 モータは回転が立ち上がる時に最大トルクを発生するので、車のスタート時の加速は問題がない。むしろ高速道路などを走る際にトルクが減って速度が出ないので、インバータで電圧を上げるとか、CVT変速機で補うような対策を取っている。 多分、今までのプリウスやアクアと違ったドライビングが楽しめるのではないか。 その上に、燃費が最高となると、これは売れるかもしれない。 ホンダフィットHVも負けてはいられないので、9月か10月にマイナーチェンジし、燃費を改善する。これも現行36.4km/リッターから40km/リッターを超えるようだ。 今後、発売される車は、40km/リッターが一つの目安になるだろう。 |
2016年8月19日(金)
(約2年ぶりに更新)
自動車の技術開発の方向性は?
トヨタ自動車がプリウスの初代を開発して早くも18年になります。 初代プリウスは1997年に発売されました。 初代プリウスは1997年に発売されました。その際のキャッチコピーは、『21世紀に間に合いました』でした。価格は215万円。 燃費は28km/Lで途中で改良を加え31km/L  2003年に第2世代になり、デザインを 変更しました。燃費は35.5Km/L。 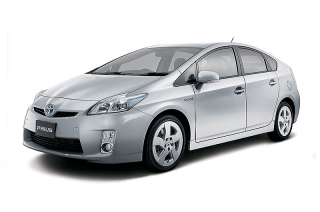 2009年には第3世代に代わり、燃費は38Km/L、エンジンは1800ccにアップ。 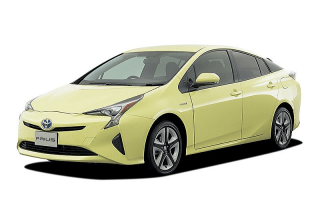 2015年に第4世代の現行車になりました。 重心を下げて、走りをよくしたそうです。 現行車両の燃費は40.8Km/L(最低価格の車両のみ)と改善されました。 プリウスに搭載している蓄電池はPanasonicのニッケル水素(NiH)電池です。世の中がリチュウムイオン電池に変わる中で、相変わらずNiH電池を使い続けています。 現行車の最低ランク車だけ、燃費40Km/L以上を表示するため、値段の高いリチュウムイオン電池を使っています。何ともおかしな戦略です。 これは、量産車として、リチュウムイオン電池の安定した調達ができないのか、トヨタとしてリチュウムイオン電池に対する信頼性が保証できないのか分かりません。 または電池の値段の点もあるかもしれません。トヨタのハイブリッド車はモータと発電機を別々に搭載する方式ですから、コスト高になっているはずです。 このプリウスのおかげで、日本のハイブリッド車は省エネの代名詞になりました。 最近の車の技術の先端を走ってきた感じを受けますが、ここにきて、車の技術開発が大きく様変わりしてきました。 車の技術開発の潮流は大きく分けると3つになると思います。 (1)省エネ化の流れ (2)環境対応の流れ (3)AI化の流れ です。 (1)の省エネ化の流れでは、 ①ハイブリッド化 ②高効率エンジン化 (2)環境対応の流れでは、 ①燃料電池車 ②EV (3)AI(人工知能)化の流れでは、 ①衝突防止 ②オートクルーズ ③自動運転 というように、今までの自動車自体の技術の競い合いと様変わりしてきました。 そうなりますと、各自動車メーカは、エンジンやメカニカル設計や車体設計など従来の機構・構造設計者以外に、エレクトロニクスやプログラミングのできるソフトウェア技術者が沢山必要になります。 体力のあるトヨタ自動車は全面対応できますが、体力に限界があるその他のメーカは何かに重点特化し、その分野でダントツの特徴を発揮するしかありません。 最近、面白いのは、マツダがスカイアクティブエンジンという名で開発を進めていますが、ガソリンエンジンと、ジーゼルエンジンそのものを徹底して見直して、エンジンの効率を高めて、ハイブリッド車に近い燃費をたたき出すことに成功しています。 ハイブリッド車は、次第に良くなってきましたが、モータとエンジンの制御のプログラムや モータとエンジンの性格の違い等で、走り方によっては違和感があることがあります。 そういう面では、エンジンだけでスムーズに吹き上がるスカイアクティブは非常によくできたエンジンです。 特にジーゼルエンジンは、騒音と排気ガスの煙が嫌がられてきましたが、この二つのデメリットを完全に克服した新しいジーゼルエンジンの開発に成功しています。 これに目を付けたトヨタやその他のメーカもエンジンそのものを再度見直そうという動きになっています。 日産は、走行状によりエンジン容量が可変できる新しいエンジンを開発することに成功したという発表をしました。ホンダは別の方法で効率化を図るようです。 現在、ガソリンエンジンは35%前後の熱効率になっています。ガソリンが持つ熱量の約1/3が運動エネルギーに変換されるという状態です。これを、数年以内に40%を超す効率に高めようと各社競いあっています。 そうしたエンジン自体の高効率化と合わせて、車体の軽量化と合わせ、電池とモータを組み合わせたハイブリッド車がさらに燃費を高めるでしょう。その内に45Km/Lか、50Km/Lという車も現れても不思議ではありません。 一方で、ガソリンやジーゼルエンジン車は燃料を燃やして運動エネルギーを発生させるわけですから、いくら効率化を図っても、排ガスがゼロにはなりません。ガソリンや軽油は炭化水素でできていますから、燃やすと必ず排気ガスとして炭酸ガスが発生します。 それに対して、EV(電気自動車)はバッテリーとモータだけですから、車自体からの排気ガスはゼロです。ただし、電池に大量に電気を貯める必要があり、その電気を充電するために発電所が必要です。発電所は原発か、火力か、水力か、太陽光か、風力かに頼ることになります。火力の場合は火力発電所の煙突から煙として炭酸ガスが出ますね。 さらに、燃料電池車の場合、トヨタのミライが既に発売されています。ホンダも近々発売するそうです。これは水素ガスをタンクに充てんして、水素ガスを燃料として空気中の酸素と化学反応を起こさせて、電気を起こします。水の電気分解と逆の反応です。起こした電気を使ってモータを回し車を動かします。 この燃料電池車の場合は、水素ガスをどうして作るかです。アルコールを分解して作る方法や、ガソリンを改質して作る方法や、水の電気分解でつくる方法など、いろいろな方法が考えられています。 いずれにしましても、車から廃棄ガスが出ないと言えども、燃料を作る段階で排気ガスが出たり、高濃度放射線物質が溜まったりすると、本当の解決策になりません。 (3)の人口頭脳化による自動・自立運転が最近注目されてきました。車の運転が楽しいという時代は終わったようです。以前は、高性能な走りの車などを運転することが楽しいという時代がありました。今もそういう人が居ますが、世の中の高齢化や、車は足代わりとなってきましたので、いかに安全に、簡単に運転できるかに重点が移ったようです。 そこで注目されているのが、渋滞時の衝突防止装置です。前の車に当たりそうになると自動的にブレーキがかかる仕組みです。また最新式のオートクルーズ装置は、高速道路で、アクセルから足を放しても一定速度で走行し、前を走る車が遅くなって車間距離がある距離以下になると、自分の車の速度を落とし、ブレーキをかけ、前の車が加速すると、自分の車も加速するという自在な運転ができる装置です。 今使っているフィットもオートクルーズが着いていますが、一定の速度で走る対応しかできていません。車間距離が狭くなると、自分でブレーキを踏みます。そうすればオートクルーズは解除されます。前の車が加速すれば、自分も加速して再度オートクルーズのボタンを押すことになります。 最新のオートクルーズはそういう煩わしい操作なしで、すべて自動で制御されるそうです。 この自動運転の延長線上に、ハンドル操作も、自動で運転できるようになりそうです。 もちろん車庫入れも、手ばなしでOKです。こうなると、運転免許証が不要になるかもしれません。 今のところ、まだ開発段階で、公道でのテストが始まったばかりですが、近未来には必ずそういう車が実現できます。 これはデジタル技術やコンピュータ技術が進化したおかげで、実現できることです。 ユーザは便利になりますが、自動車メーカ側は、新しい自動運転等の技術は、従来の自動車技術とは別なものですから、今後の流れによっては、今までの自社の強みが行かされるかどうかわかりません。 現に、アメリカのテスラはEVで先行し、今まで自動車メーカでなかった会社が急に世界に出回る時代です。 また、グーグルや、マイクロソフトや、アップルと言ったコンピュータや、ソフトウェアの会社が自動車メーカと組んで、新しい自動運転車の開発を進めています。 技術が大きく変わる時は、産業構造が変わることを意味します。そういう意味では、世界のトヨタもうかうかしていられない状態でしょう。 高齢化社会で、車を運転する場合は思わぬ事故がつきものですが、そういう世の中になっても安全な車がもうすぐそこまで近づいてきています。 |
2014年10月26日(日)
新型フィット ハイブリッドの
5回のリコールは何を意味するか?
| 我が家の新型フィットハイブリッドは4回のリコールを受けて、調子よく動いています。 家の近所に出かけるチョイ乗りの燃費は、20Km/リッター前後で安定している。 以前のインスパイア2,500cc、V6は7km/リッターで、満タンで60リッターも入る車に対して、新しいフィットはガソリンを満タンにすれば、2、3ヶ月そのままで走れる。しかも満タンで40リッターしか入らないので、ガソリンが高騰しているが、全く気にならなくなった。 一昨日、インターネットで、『フィットが5回目のリコールを申請した』というニュースを知った。 早速、ディーラに電話を入れて確認したところ、「申し訳ない」ということで、今週金曜日に点検・修理してもらうことになった。 使っていて何ら問題はないが、そのままでは故障するかもしれないという話である。 リコール内容は二点で、一つは外来ノイズによりコンピュータが誤動作するということ。 二つ目は点火プラグのコイルに問題があり、エンジンストップするということで、そのままでは、いつ不具合が生じるかわからないので対策部品と交換するということ。 新型フィットは、車の基本性能は素晴らしいと言える。今まで乗った車の内でも最高の部類に入る。このクラスの車(200万円以下)としての出来栄えは突出している。 走行時の静かさ、加速感、ハンドリング、ブレーキの効き具合、燃費などどれも素晴らしい。さすがホンダ車だと言える。 この車は全く新しい台車(シャーシ)、エンジン、変速メカニズム、リチウムイオン電池、ハイブリッドシステム、ブレーキシステムなどを採用した言ってみれば、オールニューの車として生まれた。 それだけに、発売前の自動車関係の月刊誌で非常に話題になり記事として取り上げられた。話題になるということは、それだけ先進性があるということで、いままでのIMA方式フィットハイブリッドの弱点を一新したハイブリッドシステムを開発して搭載したものだ!。 そのポテンシャルは非常に高いものだったので惚れ込んで、新型に乗り換えた。 乗ってみて、基本的には素晴らしいが、運転中に、いろんな走行状態でギクシャクした感じが有り、『これは治すべきだろう』と気づいた点はディーラに連絡した。 それが前回のリコールで、エンジン制御プログラムと、ダイレクト・クラッチギヤー制御プログラムの修正、書き換えで、大変スムーズに運転できるように改善された。 完成度が大変良くなった。 『やればできるではないか!』と思った。それなら、発売前にもう少しプログラムを熟成して完成度を上げておけば、ユーザの評価はもっと上がっただろうに!、と思いながら使っていた。 車の故障ではないので、満足ゆくようになれば、それでよかった。 今回の5回目のリコールは、以前までの熟成不足という内容とは少し違う。 車の部品の品質問題と、外来雑音(ノイズ)に対する許容値が低いという設計的な問題だ! 最近の車は、軽自動車から全てコンピュータを搭載し、コンピュータ制御で動いている。コンピュータは半導体内部の電子回路が数ボルトの低電圧で動作し、ON-OFFの組み合わせのデジタル信号で、プログラムに従い動作しているので、この回路に外部からいろんなノイズが侵入すると、本来の電気信号と判別できなくなり誤動作につながる。だからこういう誤動作が起きないように、アルミダイキャスト製の弁当箱のような密閉した箱にコンピュータシステムを収納し、ノイズを遮蔽(シールド)する。また電源回路にフィルター(ろ過器)を入れて、電源ラインから侵入するノイズをシャットアウトする対策を講じる。 車だけでなく、家電商品や、その他あらゆるコンピュータを使った電気製品にはそういう対策を施し、トラブル(誤動作)が起きないか、十分確認してから商品を出荷し販売している。 具体的な確認方法は、大きな測定室に実車を持ち込んで、車の外からノイズ発生器で強力なノイズを車にシャワーのように浴びせて、誤動作しないかどうかを確認する。 このノイズで誤動作しないレベルを数値で測定できるようになっている。 フィットもこの実験テストを行い確認して出荷したはずだが、どういうわけか、今回はノイズ対策が不十分ということで、りコールに発展している。 こんないい車を造り、評判が良いのに、こういうことでは自ら冷水を被るような状態になる。ホンダのファンとしては残念だ!! しかし、最近、この種のリコールが非常に増えたことも事実だ。 殆ど全メーカが年中、次々とリコールを発表している。 悪く言えば、『メーカがリコール慣れしてしまった』かのようだ。 よく言えば、気づいた時に、『早くリコールして事故が起きないように先手を打つ』ことはユーザにとって安心につながる。 もう一つはリコールの台数が非常に大きいこと。『何十万台が対象』と言うのが珍しくない。今回のリコールも45万台が対象だ。 今年2月に、トヨタ自動車のプリウスは全世界で190万台、日本だけで98万台というリコールをしている。これもハイブリッドシステムの制御プログラムの書き換え。その後、4月にヴィッツなど108万台のリコールを届け出ている。 このように大規模なリコールが頻発するようになった理由はいろいろある。 一つは、車がコンピュータ制御されるようになり、その制御プログラムが非常に複雑な内容になっているので、完璧に確認することが不可能になっていること。 二つ目は、部品の共用化が進んでいるので、部品不良が発生すると沢山の車種に搭載されているので、対象台数が膨大になる。 三つ目は、開発期間の短縮による確認不足。 発売時期が決まっているため、どうしても確認不足が起きる。特に制御プログラムの確認は、プログラム自体のミスがないかという確認と、実車で走ってみて不具合がないかという2面性の確認がいる。いずれにしても、車の電子化と、車の生産方式が変わってきたために発生していると言える。 そういう背景を考えると、今後もリコールは相変わらず起きると言わざる得ない。 現役の頃、トヨタ自動車の品質部門を仕事の関係で訪ねた際に、社員の方が言われたことが今もなお頭に残っている。 「トヨタ自動車が絶対起こしてはならない不良は『FO&OR』です」ということを聞いた。 FOとは、Fire out ORとは、Over run 何があっても、『火を出さない』ことと、『オーバーランしない』ことという意味です。 コンピュータ制御プログラムは、ますます複雑化し、思わぬミスが隠れている可能性があるので、今後一層安全に力を入れて欲しい。 |
2014年8月3日(日)
新型フィット ハイブリッドの燃費実力は?
大坂南港から、名門大洋フェリーで新門司港に入り、ハウステンボス、
熊本城、クマモンスクエア、阿蘇山、別府、地獄めぐりをして、帰路も
往路と同じくフェリーで帰阪しました。全走行距離は750Kmでした。

ガラケイのカメラで撮影
走行距離747.7km 平均燃費26km/リッター 燃料残量3目盛
| 満タンにして出発し、約750km走行し、帰阪後、近くのスタンドで満タンにしたところ31リッター入りました。実燃費は24.4km/L。燃費メータ表示は上の写真のとおり、26km/Lですからあまり大きな差はありませんでした。 メーカによっては、表示はいい数字になっているが、満タン法で実燃費を計算すると良くないというような記事をよく見かける。 ユーザの中には、メータの平均燃費だけ見て、省燃費だと満足している人が多いようで、そこにメーカがつけこんだ形になっている。 燃費表示は、プログラムソフトでいくらでもいい表示ができる。しかし、満タンで何km/リッター走ったかを計算すればごまかしは効かない。 まあ、これくらいの表示誤差なら許せる範囲だと思う。 九州旅行の詳細については、旅行のページ(ここをクリック)を見て下さい。3日目は、大雨の中、阿蘇山に登りましたので、相当、燃費が悪くなっていました。それまでは28km/Lと言う表示を示していました。 猛暑の中、エアコンを、25℃・Autoに設定して、乗員大人2人、子供1人、他に旅行用スーツケース2個、その他荷物をトランクに積みこんで回りました。 新型フィットハイブリッドは今までと全く違う日本で初めてダイレクト・クラッチと言うドイツ生まれの変速機を使った方式で、従来よりオートマチックやCVTに比べると、マニュアルクラッチのような感触で変速し、変速ロスが少ないというすぐれものです。 ハイブリッド方式も、以前のホンダIMA方式から進化させたもので、エンジンとモータをクラッチで切り離せるという新メカニズムを搭載したものです。 トヨタ方式のハイブリッドは駆動用モータと発電機を別々に搭載した方式で、こちらは完璧を狙ったものですが、車は軽く、シンプルに造ることが走りに大きく影響します。モータと発電機を積むトヨタ方式は理屈的にはいい方式ですが、重くなり、コストもかかります。 その点、新型フィットのハイブリッドは構造的に簡単で、軽く造れて、しかも モータとエンジンを切り離しますので、走行中のエネルギーロスもありません。 しかし、それだけエンジンのクラッチと、モータと発電機としての切り替えのタイミングや、制御プログラムが相当複雑になったため、当初、納車時に届いた 時は走りがギクシャクして、これは改良の余地がまだまだあると、素人でも分かるほどでした。やはりメーカもそれに気づいていたらしく、ホンダは新型フィットを3回もリコールしました。 3回目のリコールで、制御プログラムを新しく書き変えることで、今まで気になっていたギクシャクした車の運転時の感覚がきれいに解消されました。 一言で言えば、大変スムーズな走りができるようになり、これが新型フィットだという力強い走りの車に生まれ変わりました。 車はメカニズムの商品だという感覚から、これからの車はエレクトロニクスの商品だというぐらい、コンピュータ制御で、その車の良し悪しが大きく左右されるほどになりました。 これで『新型フィットは大変素晴らしい車に仕上がった』と思います。 もともと、新型フィットは、以前のフィットハイブリッドに比べると、静かで、特に高速道路を走る際のタイヤノイズの侵入が少なく、今まで乗ったどの車より静かだと思います。 勿論、エンジン音は聞こえないほど静かで、このクラスの車としては、クラスを超えた素晴らしい出来栄えです。 ハンドリングは大変しっとりとして、思いのままに切れますし、直進性も今までのどの車よりよくできていて、しかも軽いので疲れません。 室内空間の広々感はフィットのフィットたるゆえんで、狭苦しさは全くありませんので、長距離を走っていても圧迫感もなく、実に快適です。 以前のフィットハイブリッドが嫌になったのは、真夏に運転すると、信号待ちの度に、アイドリングストップしますが、その際にエアコンが切れることでした。 真夏の日中は、エアコンが止まるとすぐに室温が上がり、エコボタンをOFFしてアイドリングストップを切るということになります。そうすれば燃費が悪くなります。今回の新型フィットはエアコンがエンジンと切り離されたモーター駆動方式に変わりましたので、エンジンが止まっていても、エアコンは作動し続けます。当然こうあるべきです。 これは私の感覚ですが、こう少しモータのパワー(馬力)をアップして、リチュウム電池の容量も大きくすれば、燃費はもっと良くなると思います。 坂を下ったり、登ったりする際に、回生エネルギー量をもう少し増やせば、その分が燃費改善になると思います。 この辺は、車の設計時のコストと性能のバランスで決まることだろうと思いますが、多分、今後一層、燃費競争が激しくなると、コストをかけても燃費では負けないという設計思想になるのではないかと思います。 多分、これからまだまだ燃費は改善され、1リッターで40km走るという車になってゆくでしょう。 新型フィットは構造的にそれが達成できる車だと思います。 新型フィットは、超お勧めの一台になりました。 |
2014年7月16日(水)
久しぶりに、信楽(しがらき)にドライブしました
| 真夏を思わせるような気温になり、じっとしていても汗が出るような本格的な大阪の夏になってきました。 『天神祭』は7月25日ですから、年中で一番暑い季節です。 多分、この調子だと、もうすぐ梅雨明け宣言が出ると思います。  昨日、久しぶりに信楽に行ってきました。自宅から往復で、100km余りの距離です。 昨日、久しぶりに信楽に行ってきました。自宅から往復で、100km余りの距離です。12月に買った新型FIT(FIT3)は、珍しく3回目のリコールの連絡がありディーラに修理をしてもらいました。 修理と言っても、メカが壊れたのではなく、メカを制御しているプログラムを書き換えるだけです。自動車屋さんもエレクトロニクスの時代になったものです。 エンジンルームの中にある特殊な端子にプログラムを書き換える特殊なコンピュータを接続して、1時間余りかかって制御プログラムを電気的に書き換えます。多分、ファームウェアを書き換えたのだと思います。 新しいプログラムは全国のホンダディーラにホンダ本社から送られてきます。それを販売済みの車に書き替えるわけですが、車は凶器になりかねませんので、制御プログラムのミスは致命傷になります。 書き替える際に、書換えミスがあれば大変危険ですから、コンピュータに入っている新しい書換え用プログラムの内容が正しく車のコンピュータのメモリーに記録されたかどうかをチェックするベリファイと言う確認が行われます。ですから、書き換えるだけでは30分もあれば終わりますが、書き換えた後、正しく書き換えられているかどうかを照合する時間がかかるのです。 パソコンやスマホでも、インターネットからOSのバージョンアップや、いろんなアプリケーションソフトをダウンロードしますが、その際にも同様な作業がされています。 新型フィットは世界で初めてドイツ生まれのダイレクトクラッチ変速機を採用し、特殊なハイブリッド機構を採用した車なので制御プログラムが複雑でエンジン制御とダイレクトクラッチ制御をするコンピュータが別々に動作しているようです。 メーカは考えられる多彩な走行モードでチェックしていると思いますが、ユーザはそれ以上にいろんな扱い方・走り方をしますので簡単に言えばチェック漏れ、またはプログラムミスがいろんな不具合を生じさせます。 未経験の新製品を作る際は、今までのノウハウが全くないか、今までのノウハウが生かせませんので、そういうチェックミスが生じることがよくあります。 これは製造業で商品開発を経験した者なら容易に理解できるます。 ホンダが肝いりで開発した新型フィットは、同一車種で、前代未聞の3回目のリコールを公表しました。悪びれずによく公表しているな!と思います。 普通なら、3回もリコールがかかると、その車に乗るのがいやになると思いますが、今回は全くそういう気に全くなりません。 むしろ、使ってみて、『ちょっと変だな!』と気づいた点をホンダディーラに連絡し、その点をホンダ開発部門にフィードバックしてもらい、ソフト修正する。リコールの度に次第によくなるのが楽しみと感じています。 それほど、この新型フィット車は今までの車になかったほど、車の基本部分はよくできた車だと気に入っています。 基本部分とはエンジンの馬力・吹き上がりのスムーズさ・回転の静かさ・振動のなさ・粘り強さなどいろいろありますが、1500cc新設計のアトキンソンサイクルエンジンは素晴らしい出来栄えです。 車体は実にしっかりしていて、剛性が高く、ドアの締り音や、ハンドルの切れ味がスムーズです。高級車に匹敵する出来栄えだと思います。 以前のフィットハイブリッドは、エンジンとモータが車軸と直結し、常に両方が回っているという簡易ハイブリッドでした。 この方法は構造や制御が簡単にできるので、小型車や軽自動車にも使えるシステムだと思いますが、常にエンジンが回っているので、モータで走行する際はエンジンが負荷になりますし、ブレーキングで回生発電する際にもエンジンブレーキがかかりますので、その分、発電量が減ってしまいます。 結果としてはハイブリッド車ではありますが十分燃費の改善ができないという欠点がありました。 また、決定的な欠点はエアコンがベルトでコンプレッサーを回す従来の方式だったので、信号待ちでアイドリングストップすると猛暑中ではすぐに冷風から温風に代わりアイドリングストップをやめてエンジンをかけるということになりました。 プリウスは初代からモーター式コンプレッサーを搭載していて、そういう点ではしっかりと先を読んだ完成度の高いシステムを採用していました。 今回の新型フィットからプリウスと同様に、モータ式コンプレッサーになり、信号待ちの間もしっかり冷房が効きます。 昨日、午前中でリコール対策をやってもらい、昼から修理後の調子を確認するついでに久しぶりに信楽にドライブしました。往復で約100kmです。一般道路を走りました。 家を出る際に、走行メータをゼロにリセットしました。エアコンをかけて、往復100km走って帰宅し、燃費計を見ると、27.8km/リッターを示していました。 この車で最高の燃費が出ました。 先般、浜田、松江に行った際には25km/リッター前後だったと記憶していますので、今回はエアコンを効かせて走っても最高燃費が出たということです。 制御プログラムの入れ替えがどう燃費に貢献したのかは分かりません。 走って、気づいたことは、今まで走行中に、EVモード(モータだけで走行する)に入る直前に、ちょっと体が『前のめり』する感じを受けました。モータに切り替わる際に、少しマイナスの加速(ちょっと、ブレーキを踏んだような感じ)が生じていました。 今回の対策で、これがなくなり、全く気が付かない内にEV走行するようになりました。 それ以外にも、いろいろとプログラム修正していると思いますが、詳しい内容は分かりません。 着実に、この車は欠点が修正され、本来の良さが熟成されてきました。 ただし、もう一つ、気にかかる点が残っています。 家の駐車場からスタートする際はエンジンがかかります。ゆっくりとスタートして、20mほど走ると、急な下り坂道に差し掛かります。その際、ローギヤーでエンジンブレーキがかかり、エンジンが高回転します。 バッテリーは満充電でない状態ですから、エンジンを切り離し、モータを最大の回生発電させて充電すべき状態ですがそうなっていません。 これは、まだ改良の余地がありますので、ホンダに伝えています。 メーカとユーザは『持ちつ、持たれつ』の関係であればいいと思っています。 メーカ側からすれば、いろいろとクレームをつける人を『クレーマ』と言う呼び方があります。理不尽なことを要求するクレーマにはなりたくないですね。 新型フィットは、もう少しで素晴らしい車になります。 今のままでも結構いい車ですが、まだまだよくできる余地を残している車です。 ぜひ、ハイブリッドをお考えなら、フィットハイブリッドをお勧めしますよ! |
| 2014年4月21日 新型フィットハイブリッドの燃費は? 神の国、出雲旅行の往復の全走行距離は927.1kmだった。満タンにして出発し、帰ってから満タンにしてガソリンは37.67リッター給油しただけ。実燃費は24.6km/Lという数字になった。車の燃費計は24.5km/Lと表示していたので、燃費計の表示値と実際の燃費がぴったりだった。 これには驚いた!!。 普通、燃費計の表示が相当いい値に出ると車の雑誌には書いているが、今回の実測では奇しくも殆ど同じ値になった。 以前のフィットハイブリッド(IMA方式)は高速道路では20~22km/L、一般道路では17km/L程度が精々だった。やはり新型フィットの燃費は素晴らしいことが実証できた。 もう一つ気づいた点は、時速90~100kmで走行すると、燃費はさらに良くなり25km/Lを超す。時速が100kmを超して連続走行すると、若干燃費は悪くなり、23~24kmとなる。 国道9号線(一般道)を距離で100km余り走ったが、高速道路と変わらない値だった。 新型フィットハイブリッドはエンジンが1500cc、アトキンソンサイクルエンジンを搭載しているので、馬力に余裕があり、坂道の粘りや加速は大変力強くなった。以前のフィットは1300ccだったので、その差は大きく感じる。 特筆すべきは高速道路走行時のロードノイズで、大変良く抑えられ、これが200万円以下の車かと驚くほど静か。長距離高速道路を走っても全く疲れはない。以前のインスパイア(セイバー)V6/2500ccと比べても、新型フィットの方が良い印象である。 もちろん、以前のフィットハイブリッド1300と比べると、一段静かになっている。 運転時のハンドルのしなやかな感触、高速時の直進性の良さ、道路の継なぎ目を通過する際の突き上げの感じや振動、計器盤のレイアウト、各種レバーレイアウト、椅子の座り心地などあらゆる面で全く不満がない。 実に良くできている車だ。 おすすめの車。  我が家のフィットハイブリッド 我が家のフィットハイブリッドさらに良くなると思う改良点は? エンジンとモータ(発電機)とバッテリの充放電動作の状態をディスプレイで示している。これを見ていて気づいた点がある。 高速道路を走行中、相当きつく下り坂が長く続く場所で、時々エンジンがかかりタイヤにつながっている。この時充電をしていない。坂道を高速で下っているのだから、エンジンを回す必要はない。むしろ充電すればいい走行状態のはず。 このようにエンジンがかかり、充電しない時がある。この状況のプログラムを修正すれば不要な燃料消費がなくなり、まだ燃費の改良の余地がある。 もう一つは50~70km/hぐらいで結構急な坂を上る時に急にエンジン回転数が上がる時がある。速度が出ているのだから、ローギヤーに入れる必要がないと思う。 これも改善余地があると思える点だ。 それ以外に、特に違和感のある点はなかった。 中国道や浜田道や米子道は大変空いているので、オートクルーズで走ると楽ちんで 運転できる。 新型フィットは本当に素晴らしい車だと思う。 |
| 今日のネットを見て、目を疑った。ついこの前にトヨタはプリウスで世界中で100万台のリコールをすると発表した。今日はさらに6倍以上多い639万台という数字である。 あまりにも大量な天文学的な数字であり、ピンとこない。それだけ車がトヨタ車が世界中で売れている証拠でもある。 リコールの内容は明らかではないが、日本で約100万台、その他海外で500万台という台数だ。 つい先日、GEが500万台のリコールを発表した。その直後にさらに100万台上積みし、さらに上積みして、最終的?に1000万台近くのリコールに及んでいる。 まさか、あの信頼していたトヨタが639万台のリコールになるとは、トヨタ社内に何かが起きているのではないか?と疑うような事態だ! よもやま話のページで、豊田社長の話を書いた。最近の豊田章男社長の発言は素晴らしいと思っていた。トヨタはますます成長するだろう!と思っていた。 そのトヨタ自動車が巨大なリコールの発表である。 639万台のリコールをするための費用を考察してみよう。 一台5000円かかるとしても320億円、1万円かかれば639億円の損失となる。 トヨタは2兆円の利益を上げる会社だから、600億円は大したことがないと言えるかもしれない。 そして、リコール費用は車の原価にサービス対策費として、数千円から1万円程度組み込んでいるので、利益に直接影響しない。 しかし、恐ろしいのはブランドイメージのダウンだ。韓国の現代自動車(ヒュンダイ)は以前は品質が良くないということで、買うのは二の足を踏むユーザが多かったが最近ヒュンダイ自動車は大変良くなったという話である。 品質でブランドを確立して伸びてきたトヨタやホンダや日産など日本の自動車各社は 自らの品質不良問題でブランドイメージを潰すことになりかねない。 100万台とか600万台という天文学的なリコール台数はなぜ最近よく起きるのか?それは自動車の製造方法が以前と変わってきたからだ。 部品の共用化、共通化、標準化により一つの部品不良が出れば沢山の車種に及ぶことになる。また世界同時生産が進んだため、不良が見つかれば、あっという間に全世界で販売する車に波及する。 コスト競争のため、合理化を進めた結果の裏返しの課題が表面化していると言える。 今回のトヨタのリコールの内容を見ると、設計不良が原因とされている。設計不具合の場合は、全数が対象になる。製造不良はバラツキや作業ミスが原因だから、悪いものもあれば、いいものもある。設計不具合は大変怖い。だから新車はていねいに試験や 検査される。トヨタ自動車の絶対起こしてはならない品質の基本は、FAとORだと聞いた。FAはFire out, ORはOver runということ。絶対に火が出ない、絶対にブレーキが利かずにオーバーランしてなならない。この二つは何が起きようが絶対発生してはならないというトヨタ自動車の教訓(家訓)のようなもの。 今回の不良の内容は3つある。 (1)エアバック不具合:350万台、配線関係の不具合らしい:RAV4,マークXなど (2)走行中、座席シートがずれる:287万台:ヴィッツ、ラクティスなどの小型車 (3)エンジンスターターのモータが回りっぱなし:2万台:カローラ、オーリスなど 2004年~2013年8月までのものが対象と発表されている。 つい先日、パワーウィンドウ不具合で、14車種、743万台のリコールをやったところで、今回のリコールは2番目に多い台数になっている。 今、載っている車は、2か月待ちで、昨年12月中旬にやっと納車になったホンダの新型フィットで、このハイブリッドは出足と加速と、燃費が非常に良くて気に入っている。 ただし、一つだけ気にかかる点があり、ディーラーに連絡して修理を依頼している。 それは、20~30km/時からスピードを落とし低速(10km/時ぐらい?)にして、その後加速する時、エンジン回転数が空ぶかしのようになる。 これはエンジンのクラッチ動作が滑っているのではないか?と思い、修理を依頼中。その他は今のところ問題はなさそう。 やはり、新型フィットⅢは、今までとは違う全く新しいメカ(ダイレクトクラッチとモーター)を採用しているので、メカ部とエンジンを制御するソフトウェアの協調性があらゆる運転する場面で、最適化できていないのかもしれない。 パソコンパソコンのOSやアプリソフトは不具合があれば、ネットを通じてバージョンアップと称して常に書き換えができる。知らぬ内に書き換えられていることがある。 自動車というメカニックな商品ですら、もしソフトウェアの不具合があれば、定期点検時に制御ソフトの書き換えをすることで対応できる時代になった。メカそのものの不具合はメカ(ハード)で補修することになるが、ある程度はソフトウェアの変更で、メカニズムの動作の不具合をカバーできる。 車は今や電子技術の塊になってきた。ボンネットを開けると配線だらけ?になっている。車のディーラーも、修理やメンテナンス作業の内容が大きく変わってきた。 特殊なコネクター(接続器)で制御ボックスと接続し、デジタル信号を送って、制御ボックス内のマイコンのメモリーのソフトを書きかえる。これが今の車の修理の姿である。 そうなると、専用のプログラミングマシーンと接続器を有する計器(測定器、書換え器)を持たなければ、修理ができなくなる。 これから街の車屋さんはメーカのディーラーに入らなければ、修理もできなくなる。 独立系の中古車販売店などは、中古車のエンジンなどの点検をどうしてやっているのか?疑問が残る。 それにしても、トヨタの639万台のリコールには驚いた。 今後、まだこの数字は更新されるかもしれない!! |
| 12月に納車してもらった新型フィットは快適に動いている。しかし、ホンダから2月14日、下記のとおり、2月24日以降にリコールするという知らせが届いたが、その後連絡がないので、先日、ディーラに聞いてみたところ、14日の大雪で寄居工場に隣接するテストコースに雪が積もり、リコール対策の改良プログラムで走行確認ができなくて、対策実施がさらに伸びているということであった。 幸い、私の車は特に異常なく走っていたのであまり気にしなかったが、ホンダはこの間、生産と販売をストップしたため、新車登録が8000台ほどロスってしまったらしい。そのため2月の新車登録は新型フィットがダントツトップのはずが、6位になった。 またまた、トヨタのプリウス、アクアに1位、2位を譲り、3位、4位、5位は軽自動車、その後に新型フィットとなった。3月以降はトップに返り咲くと思うが・・・。 ソチのオリンピックを思い出した。あまりにも期待が大きすぎたので、その期待外れの度合いが大きい。対策用の新しいプログラムが準備されたので、ディーラに出向いた。 2時間ほどかかって、制御プログラムの書き換えをしてもらった。多分、制御コンピュータのファームウェアという基礎プログラムの修正をしたものと思う。これは慎重にやらないと車は危険な物体になるので、書き換えにも十分時間がかかる。 書き換えたプログラムが正しく書き換えられているか、元のプログラムと比較しながら検証するベリファイというプログラム上の確認作業が要る。 パソコンでも、DVDにビデオや写真や音楽を焼く時、焼いた後で、データが正しいかどうかをDVDの信号を読み取って、元のデータと比較する作業が入る。同じであればOKとなる。リコール対策の後、和歌山まで高速道路を走ってきた。全く問題なく順調に走ってくれている。 先週、火曜日は、五個荘の近江商人屋敷で開催されている人形展に行ってきた。 納車後、今まで2か月余りで1263km走行した。この走行距離はオドメータに表示されると同時に、インターナビを通じて、毎日、ホンダのインターナビ・サーバにデータがリンクアップされているので、走行距離と燃費の経過がよく分かる。実燃費でちょうど24Km/Lになっている。 この値は、今まで乗っていた初代フィットハイブリッドに比べると、6Km/Lほど改善している。高速道路では26Km/L~28Km/L走る。 この厳寒の季節に、1260km程度の走行で、24Km/Lは十分満足が行く燃費だと満足している。 先日、本屋でカー雑誌を立ち読みしていると、アクアとスズキのスイフトの実燃費データ比較が載っていた。アクアは燃費計表示はいい値を示すが、注油して実燃費を計算すると、表示とのかい離が大きすぎると書いていた。『トヨタさん、この点は改善してほしい』という記事があった。その点、スズキのスイフトは良心的な表示値でかい離が少ないようだ。もちろん、アクアの方が燃費の絶対値はスイフトよりい値になっている。 その本によると、新型フィットはアクアより実燃費はいい値を示したという記事になっていた。最近、アクアとフィット、クラウンとアコードという互いに直接的な一対一の燃費比較記事をあまり見ない。アクアとスイフト、フィットとデミオというように真っ向勝負の車の比較をしない。これはトヨタから雑誌社に圧力がかかっているのかもしれない。 こういうことは一位メーカがよくやることだ。雑誌社を巻き込んで、自社に都合のいいことはどんどん書かせるが、都合の悪いことは記事を抑える、または控えめな表現にする。一番手メーカだからこそできる手立てである。 本当に燃費や性能などが一番なら、『堂々と比較試験をしてくれ!』と雑誌に逆にけしかけるはずだ。 それを敢てしないのは、実燃費ではアクアよりフィットが勝っているのではないか?。 実際運転してみて、燃費のバラツキがあまりなく、安定した値を示している。現在、燃料タンクの燃料計が半分を示しているが、走行距離は560Kmになっている。満タンで40リッターだから、実燃費の25km/Lともよくあっている。今までの車なら、約その半分の走行しかできなかった。 しばらく、給油の際に、きちっと給油量と走行距離を記録してみるつもり。 家の周囲の買い物などの『チョイ乗り』でも18~20km/Lぐらいになる。すこし、距離を乗れば20km/Lはオーバする。これから気温が上がり、ウォーミングアップの時間が短くなれば、もっと燃費は良くなるだろう。 それにしても、家内の初代フィットは『チョイ乗り』で10km/L程度である。昨年暮れまで乗っていた初代フィットハイブリッドは『チョイ乗り』で14~16Km/Lであった。それに比べると、新型フィットは格段に良くなっている。 リコールでギアの制御プログラムを書き換えた性か、走りはスムーズになったような気がする。多分、また半年後ぐらいに、さらに改善したプログラム更新をするのではないかという気がする。これはリコールではなくバージョンアップということになるかも知れない。半年点検時に、点検という名目でバージョンアップすることができる。車の世界も大きく変わってきた。 リコール作業は、制御コンピュータのメモリーのデータを読み出せば、ギアーの異常があれば、データで分かるらしい。異常のデータが表示されれば、ギアーの駆動部の部品を交換することになるらしい。その作業は大変な時間がかかりそう。 小生の車は幸いその『データ異常はなかった』ということで、プログラムの書き換えだけでことが済んだ。 いずれにしても、全く『新』の商品には品質上の課題が着きまとう。これはある程度仕方ないことだ。危険な動作が生じては絶対駄目であるが、色んな使い方やいろんな場面が起こり得るので、メーカが十分チェックしていても、想定外のことは起きる。その場合にどう対処できるかだ。メーカはそれをのりこえて、磨きをかけることで、素晴らしい商品に育て上げる。 新型フィットがそういう素晴らしい商品に育ってほしい。 しかし、原発だけは、『想定外』という言葉で、絶対に逃れられない。 |
2014年2月14日(金)
新型FITハイブリッドのリコールについて
| 10月に注文した新型FITは、爆発的なヒットで、生産が追い付かず12月下旬に2か月半待ちでやっと納入された。この新型FITハイブリッドは特に問題なく調子よく動いてくれている。 すでに、淡路島へドライブし、正月には孫を連れて鈴鹿サーキットに行き、長距離走行の燃費はピーク値で30km/L、平均で25km/Lを確認した。なかなか燃費は良さそう。 そして、ハイブリッド車の発進時のもたつき感は全く感じない。 今のところ、特に気になることがないが、ディーラーから1ヶ月点検のはがきが届いたので、ホンダ販売店に出向いた。 その直前に日経新聞で3回目のリコールを実施という記事が出ていたのを見て、ホンダのHPを覗いてみた。 今回の新型FITは、エンジンとモーターを切り離すクラッチがあり、さらに変速は7段のダイレクトクラッチ(DTC)というドイツ製のものを使っている。ギアーが完全にかみ合うので動力伝達ロスがない、さらにシフトアップがマニュアル車のようにギヤーの切り替えの感覚が分かるというのが売り文句だが、この方式はVWのポロが採用し、ハイブリッド車としてはホンダが初めて採用したもので、ダイレクトクラッチ、ギヤーの切り替えのプログラムに、まだノウハウが不足していたようだ。 そういえば、坂道を登って、左にカーブする際に速度を落とすが、その時に異常にエンジン回転数が上がり、おかしいなと思っていた。 また家から坂道を下り降りる際にもエンジン回転数が大きくなる。 マニュアル車のローギヤーに入れたような感じ。運転感覚としては、セカンドポジションぐらいで十分だと思う。しかいs、これは正常な動作かもしれないが・・・。 今回のリコールは、内容を見ると、『発進時に時間を要するとか、発進ができなくなる』ということらしい。そういう事態になったことはないが、車によってはそういう現象が出る場合があるようだ。 発進時のもたつきや、発進できなくなるクレームは、すでに10月と12月にも、プログラム修正という形で対応している。 そう言えば、納車後、ホイールをアルミに替えてもらうため、ディーラに立ち寄った時に『プログラムバージョンアップをしておきました』という話を聞いた。その時は『あッ、そうですか』だけの返事をしました。 自動車のリコール対策も最近、大きく変ってきた。 以前、リコールというと、何か(機械)部品を取り換えて対策するのが普通だった。今は、コンピュータ制御プログラムを書き換えることで対応することが多い。 制御プログラムは非常に重要な働きをする車の頭脳なので、簡単に書き換えては大変危険である。だから、これからのリコールは正規ディーラーでしかできない。 制御プログラム書き換え用のコンピュータが必要である。 また特殊なコネクターで、車と書き換え用コンピュータを接続して、プログラムのバージョンアップを行う。多分、基本のプログラム部分であるファームウェアという部分を書き換えていると思う。これは機能、動作を制御するプログラムで、非常に重要なプログラムだ。 トヨタのお化け商品、プリウスも、昨日、新聞でリコールを発表した。こちらは現行商品である3世代目のプリウス全数がリコール対象ということで、日本だけで100万台、世界中では200万台という気が遠くなる台数が対象になっている。 プリウスのリコールの原因は、ニッケル水素電池の電圧をインバーターという電気回路で600Vから700Vの高電圧に昇圧して、駆動用モータに高電圧をかけるようになっているが、その際、インバーターの半導体素子が非常に高温になり破壊することが起こる可能性があるらしい。 アクセルを踏み込んで加速すると、大電流が流れ発熱する。普通に運転する人はそういう過酷な加速はしないが、急発進などをすれば起きる可能性があるということだ。 このリコールの対策内容も、大電流で発熱が大きくなるとプログラムで電流を制御して発熱を抑えるようにするらしい。ということは、加速が悪くなるということになる。 本来なら、半導体素子を取り替えて、容量の大きい熱に強いものに替えれば、加速性能はそのままで問題がなくなるが、電子部品の取り換えは大変な作業になるので、簡単に対応できるプログラムの変更で対処するということだ。 製造メーカは自動車メーカにかかわらず、製品の品質不良対策費として、製造原価に何%か上乗せして現金を積み立てている。 だから世界中で200万台のリコールをしてもトヨタの業績には影響しない。今回のホンダのリコールも同じこと。 新型FITは全く新しい技術を盛り込んだ意欲的で、画期的な車だと思っているので、まだまだ改良の余地がありそう。 次のマイナーチェンジぐらいになれば、今までのノウハウを生かしてさらに素晴らしい車に仕上がるはずだ。 今度の3回目のリコールは慎重を期しているのか、対策に苦慮しているのか分からないが、リコール作業開始が2月21日以降になる。 それまで、製造ラインも止めているらしい。もちろん店頭販売もストップしている。あまり長くなると、せっかく人気が上昇中の新型FITに傷がつく。 また、不具合の度合いや、その対策に苦慮しているとなると、全く新しい技術を組み込んだ商品を買うことは、やはりリスクが大きいということになる。 でも、問題点は把握できているので、これを機に完全に対応するために念には念を入れて調べているというように理解すれば、よくなるのだから様子を見ようということになる。 なんと、ホンダにやさしいことか! 現役時代に、ステレオ(Technics)商品の企画、開発、設計、製造を担当し、モノづくりの経験をしてきた者にとって、品質の重要性はいやというほど身に染みている。 今回は、新型FIT、8万台のリコールに出くわしたが、プリウスの200万台のリコールは天文学的な台数である。 これらのリコールを通じて分かることは、最近の自動車がソフトウェア(プログラム)で動いているという証になったと言える。 リコールの対策後、運転感覚に変化があれば再度レポートします。 |
2014年1月13日(月)
新型FIT3のエンジンルームは?

| 新型FIT3のボンネットを開けて、エンジンルームを撮影した。狭いエンジン ルームに見事にいろんな部品が詰め込まれている。 一目見て分かることは、このエンジンはベルトを使っていないこと。普通の車にはVベルトや歯付平ベルトが使われている。 ベルトはエアコンのコンプレッサーの駆動、ウォータポンプの駆動、発電機の駆動などに使うためベルトが張られている。新型FIT3には一本のベルトもない。これらの電装品の駆動はモータに代わっている。 ベルトを使うと、張力によるロスが生じ、燃費が悪くなる。 新型FIT3はエアコンのコンプレッサーがモータ駆動になったので、真夏の暑い時に、信号待ちでエンジンストップしても、エアコンはモータ駆動なので働き続ける。これが以前のFIT2ハイブリッドが欠点だった。 信号待ちでエンジンストップするのは結構であるが、真夏にエアコンが止まってしまうのは頂けない。すぐに室温が上昇してしまう。 スズキの軽自動車はエンジンストップしても、ある程度冷風が出るように、エアコンが働いている時に冷媒(氷嚢みたいなもの)を冷やしておいて、エンジンストップしコンプレッサーが止まった時に、ファンで空気を冷媒に当てて空気を冷やすという手を考えて採用している。しかし、これは十分な策ではない。『ないよりある方がまし』というぐらいのこと。 やはり、エアコンはコンプレッサーを回さなければ冷えない。 もう一つ、コンプレッサーをモータで回すと、冷やし具合に応じてモータの回転数をコントロールできるので、付加が軽い時は電気をあまり消費しないで済む。その分が燃費改善になる。 エンジンの冷却水を循環するウォータポンプも従来はすべてベルト駆動になっていたが、FIT3ではモータ駆動に変わっている。モータ駆動することで、エンジンの温まり方に対して、循環水量を最適にコントロールできるので、エネルギーの無駄遣いがなくなる。その分、燃費が良くなる。 車両駆動用の電池はリチュウム電池で、後部座席とトランクの間に収納されていて、見ることができない。電圧が173ボルトもあるので触れると危険である。 エンジンルーム内には通常の12ボルトの鉛バッテリーが積載されている。これは、コンピュータシステム、AV、カーナビ、ワイパー、ヘッドランプなどの照明などの電装品用の電源である。 ヘッドランプは、ハロゲンランプから、HIDディスチャージランプになり、大変明るくなったが、このFIT3には、さらに進化したLEDランプが使われている。 消費電力がさらに低減でき、ON-OFFを繰り返しても全く問題はない。 明るさも十分で照明の色合いも大変見やすく仕上がっている。 今、一番気に入っているのはドアの仕上がりである。ドシっと重くて、分厚さを感じる。締り音も大変いい音で、高級車並みの開閉音である。 このクラスの車とは思えない高級感があり、以前に乗っていたインスパイアよりも良いと感じている。 |
2013年12月23日(月)
やっと、FIT3ハイブリッドが納車になった
 やっと納車されたFIT3(左側の車) 前のFIT 2はホワイトだったが、今回はシルバー調で、少し暗めか? 右の車は家内のFIT 1(初代のフィット)(パステル調のスカイブルー) |
|
 |
 |
| サイドはフロントドアーから後部ドアーにかけて、深くて太いラインが伸びている。 FIT3ハイブリッドは、少しやんちゃな顔つきと、彫の深いライン構成が特徴的だ。 このデザインは、好みがはっきり分かれると思う。トヨタのアクアは曲面を生かした 優しくかわいいデザインで女性好みなスタイルに対して、FIT3は男性的・個性的。 プレスドアーと防振材の採用で、ドアーの開閉音は高級車のどしっとした音。 |
|
| 9月16日に正式契約したFIT3(3世代目のフィット)ハイブリッドが、やっと 12月15日に納車になった。 3か月待ちでした。ディーラの話では売れに売れているようで、特にハイブリッド車は「今、注文しても3月末までに入らない」という状況のようです。 理由は分かりませんが、製造が追いつかないという話です。 今回のFIT3ハイブリッドは、アコードと同じブルーエナジー社(GS・ユアサバッテリーとホンダの合弁会社)のリチュウムイオン電池を使っています。 どうやら、この新しい電池の生産能力がネックになっているのではないか?と思います。 さっそくドライブがしたくなり、明石大橋を渡り淡路島の洲本温泉、淡路インターナショナルホテルに『フグ』を食べに行きました。 当初は島根の玉造温泉に「カニ食い」に行く予定で、ホテルの予約まで取っていたのですが、納車が延び延びになり、やっと12月中旬になりました。 山陰地方はこの時期になると雪が降る季節となり、予報では大雪警報まで出ましたので、急きょ、行き先を変更しました。 淡路島ならすぐ近くで、往復で350kmほどです。納車まで15kmほど積算されていましたので、累積走行は365km。 燃費は、何と25km/Lと良い数字が出ました。高速道路は30km/Lを示しましたが、帰り道の湾岸道路、阪神高速が大渋滞でしたので、それでも平均で25km/Lです。これはメータの表示値です。 22日に、スタンドでガソリンを満タンにしました。なんと13.8Lしか入りません。ほとんどメータの指示値どおりの燃費でした。 この車は渋滞時にモータでチョロチョロ発進できますので、エンジンがその都度かかりません。その分、燃費が良いようです。ただし、電池の容量が下がると、さすがにエンジンがかかりリチュウム電池に充電を開始します。 家の周りのチョイ乗りでも、20km~21km/Lでしたので燃費は良さそうです。 前のFIT2ハイブリッドは家の周りのチョイ乗り(買い物など)では14~15km/Lでした。FIT3ハイブリッドは大幅な改善です。期待どおりです。 プリウスやアクアは発進時に出足が悪く「もたつき」ますが、この車はもたつき感は全く感じません。スーッと出ますので大満足です。 走行時の騒音も大変静かで、高速運転時も、ロードノイズが低く、前の車と比較にならないぐらいです。以前、アメリカ製のセイバー(インスパイア)2500CC(V6エンジン)に11年間乗りましたが、セイバーより静かなように思います。 ハンドリングや車体の剛性感も高く、とてもしっかりした造りの車です。特にドアーの開閉音はドシっとした高級車並みです。 さらに、カーナビは8インチの大画面、純正品(Panasonic製)にしました。少々高いのですが、これがとても正解でした。老眼でも画面が大きいので、はっきり地図が見えますので、運転中も楽でした。 このカーナビはホンダが開発したInter Navi Systemを搭載していますので、いろんな情報が受信され見ることができます。 実走行距離など車からホンダのサーバに送信さられますので、累積何km走ったかが、インターネット経由で家のパソコンで見ることもできます。ガソリンの給油も何月何日に何リッター入れたかをパソコンで入力すると、インターネットでサーバに蓄積され、累積の燃費や走行距離など情報が蓄積されます。 たぶん、個々の車の走行ルートや、平均時速や渋滞情報や運転の仕方や癖まで、ありとあらゆるデータがサーバに蓄積されます。 これからメーカとして顧客サービスの一環として考えられているビッグデータの 収集と活用に生かされるのでしょう。 先日、Panasonicも家電商品でそういうビッグデータの活用により、ユーザの商品の使用実態を把握し、商品開発に生かす記事が掲載されていました。 ホンダはすでにビッグデータを生かそうとしているようです。 FIT3は大ヒット中で、販売実績No.1になっている車です。今なら、たくさん造れば、いくらでも売れるかもしれません。やはりいい車は売れますね。 この車は、今までのこのクラスの車より、1ランクではなく、2ランク上のクラスの車に出来上がっているように思います。 また、気づいた点は引き続いてアップします。 |
2013年11月4日(月)
『エネルギー保存の法則』に行きつきます。
| 11月2日の記事は、くどくどと書きましたが、要は『エネルギー保存の法則』に行き着くということです。誰もこの法則から逃れることはできません。 車でも電車でも、止まった状態は運動のエネルギーはゼロです。走り出すためにはガソリンや電気を使ってエンジンやモータを回して運動エネルギーに代えます。そこでエネルギーの変換がされるのですが、変換時の効率のよし悪しで、燃料や電気の食い方が変わってきます。 モータは変換効率が高く70~80%以上になりますが、ガソリンエンジンは精々30%台です。ガソリンが持っている本来のエネルギーの1/3しか有効に働いていません。(ジーゼルエンジンは40%台まで進んでいます。) そういう意味で、電車で通勤したり旅行するのは車通勤やバス旅行に比べて省エネになります。 さて、動き出した電車や車は一定速度になると惰力で走りますので、大きなエネルギーは必要はありません。レールや道路が登り坂になると、速度が落ちますので、アクセルを踏まなければなりません。登り坂では重力に逆らって動くわけですから、その分エネルギーが必要になります。 歩く場合でも平坦道路は平気ですが、階段を登る、山を登る際は急に心臓に負担がかかりますね。これと同じことです。 電車が駅にさしかかってブレーキをかけスピードを落とす、又は車が止まる時はブレーキペダルを踏みますが、今まではディスクブレーキなどで、摩擦で電車や車の運動エネルギーを熱に代えて空気中に放散していました。これはもったいないことです。 加速するために使った運動エネルギーをすべて熱として逃がしていたのです。 このエネルギーの無駄をなくし、できるだけ有効利用しようという技術開発が進められて来ました。その具体例が11月2日書いた電車とハイブリッド車の取組みです。 車の場合は、ガソリンエンジンの特性と、モータの特性がちょうどXの字のように互いに反対の特性を示します。 モータは停止から回転し始める時に回転力(トルク)が最大になります。 ガソリンエンジンはある程度回転数が上がらなければトルクが増えません。 ガソリンエンジンは最大トルクは3000回転/分ぐらいの所にありますので、車のスタート時はギヤーで減速してトルクを稼いでいました。 昔はシフトレバー操作、今はオートマで自動化されました。 スタート時にモータを使い、走り出したらガソリンエンジンを使うというハイブリッド車はエネルギー効率化の面では理にかなっています。 もう一つは停まる際の運動エネルギーをブレーキで100%摩擦熱にして捨てていましたが、車が走行中の運動エネルギーを電気エネルギーとして回収し、バッテリーに溜めて、発車時にモータを駆動させるために使うという考えです。 この二つの方法でハイブリッド車は省エネ・低燃費に成功しています。 今までも理屈は分かっていましたが、実現が困難でした。 一つは、モータを回すための電池が今まで車に積んでいた鉛電池では電気容量的に非常に重くなり、車としては成り立ちませんでした。 最近、ニッケル水素電池や、リチュウムイオン電池という素晴らしい大容量・軽量電池が開発され、ハイブリッド車が日の目を見るようになりました。 もう一つの要因は、インバーターという電気回路で使われるマイコンや電力半導体素子が非常に高性能で効率のいいものができるようになったことです。 今後さらに電力用半導体は改良され、さらにロスを少なくできます。 リチュウム電池もますます小型大容量の優れたものが開発されます。 1リッターのガソリンで、快適なドライブをしながら何km走れるようになるか? これからさらに改善が進むと思います。 もうすぐ40km/リッターの時代に入るでしょう。 |
| 電車の先頭車両に乗り、運転手がレバーを動かして電車を発車させ、停車させる運転操作を見ていると、歳を忘れてしまう。 運転席には架線の電圧(直流1,500V、新幹線は交流15,000V)、モータの電流、エアーブレーキ用の空気圧、などの計器が並んでいる。 運転レバーはモータに流す電流を制御するレバー(車で言えばアクセルに相当する)と、ブレーキレバーの二つ。 地下鉄などでは、一つのレバーでニュートラルのポジションから手前に引くと発車し、逆にニュートラルから前に倒すとブレーキがかかり止まるという簡単なワンレバー方式を採用したものもある。理屈では一つのレバーで電車を操作できる。 それでは本論に入ります。 電車が発車する時、運転手がモータ制御レバーを手前に引く。(どういう訳か、日本人は動作させる場合は手前に引く癖があるらしい。ノコギリも日本製は手前に引くと切れる。アメリカのノコギリは押すと切れるので逆になる。 ジェット機の操縦桿も離陸する際にスロットルレバー(自動車のアクセルペダルに相当する)を向こうに押すとエンジンが全開し離陸する。 電車の運転手がレバーを引くと、電流計の針がピーンと跳ね上がり、指示は一気に100A(アンペア)から150A程度を示し、電車が動き出し次第に加速してスピードを上げる。 この時、モータの出力は最大になり、1500V×100A=150KW(約200馬力) 6両編成の電車には、3両にモータが付いているので、600馬力となる。 スピードが上がるにつれて、レバーをさらに引くとドンドン加速する。 その間、電流計は100A前後を維持している。時速が70kmから100Kmぐらいの運行スピードになると、運転手はレバーを中立の位置に戻す。 電流計はゼロに戻る。 電車はレールの上を走るので、車と違って走行時の『ころがり抵抗』が非常に少ないので、平坦な場所を走る時はあまり速度が落ちずに長い間走り続ける。この状態の時は電気を全く消費せず、惰力で走っている。しかし、空気抵抗やその他の摩擦抵抗などにより、少しずつ速度が落ちてくる。 カーブや駅に近づくと、決められた制限速度に落とすため、運転手はブレーキレバーを手前に引く。そうすると電流計はまた100Aぐらいを示し、電車はスピードを落としてゆく。この時の100Aはモータが発電機として働き、発電した電気を架線に戻している電流を示している。電流の流れが、発車する時と逆になっている。 さらにブレーキをかける場合はブレーキレバーをさらに手前に引く。その時にエアーブレーキのシリンダーの空気圧が大きくなり、機械式ブレーキも同時に働き、電車は停まる。 最近の電車はこのようにモータを発電機に切り替えて、動き出す時はモータとして、止まる時は発電機として動作するようになっている。 このモータは、同期交流モータという種類で、架線から受けた1500V(ボルト)の直流電圧をVVVF(Variable Voltage -Variable Frequency)という直流を交流に変換し、交流電圧と周波数を自由に可変できる電子回路と通して、モータに交流電気を加えるようになっている。 同期交流モータは、周波数に比例して回転数が変わるので、発車時にはモータに低い周波数で低い電圧をかけると、モータはゆっくり回転し始め、次第に周波数と電圧をあげるとモータは回転数を上げて電車を加速する。 その切り替えを電子回路で連続的にスムーズに行うので、最近の電車は加速する際にギクシャク前後に揺れることが少ない。 この同期交流モータは回路を切り替えることで発電機として使える。 発電するということは、電車が走行している時に持っている運動エネルギーを発電機を回すことで電気エネルギーに変える回生発電を行っている。 この方式は電車が発車し加速する際に使った電気エネルギーを止まる時に回収するので、最近の電車は余り電気を食わなくなっている。 トロリー線(架線)を張っているので、電車はパンタグラフから受電したり、パンタグラフから架線に送電したりすることが自由にできる。 都市部の電車は朝夕のラッシュアワーは数分間隔で運転され、ダイヤが過密状態になっている。一本の架線から受電して走る電車は大きな電流が流れ、架線の電流容量をオーバーする可能性もあるが、このように発車時に電気を食うが、止まる際に電気を戻すので、たくさんの電車が一本の架線につながっていると、架線の電流は平準化される。 もちろん、適当な間隔で変電所から架線に電気は給電している。 昔の電車は運転手が発車する際、モータに流れる電流を制御するためコントローラと呼ぶレバーを回して機械式スイッチを直接切り替えていた。いろいろな値の抵抗器を何個もスイッチにつなぎ、モータに電流が流れ過ぎないように速度に応じて手動で切り替えていた。 モータに流れる電流は回転し始める際に一番大きな電流が流れる。回転数が大きくなるに従い、電流は減少する。発車時に直接、全電圧を加えると、モータも架線も電流オーバになるので、抵抗器を使い電流を制限していた。回転数が上がるにしたがって抵抗値を小さくし、最高速度付近で直接電源につなぐ。 このスイッチの切り替えの度に、モータにかかる電圧が段階的に変わるので、前後にギクシャク揺れを感じた。今でも田舎を走るローカル線の古い電車にみられる。 このモータは直流モータで、モータとしてしか働かない。ブレーキは機械式のエアーブレーキで停止するようになっているので、ブレーキをかけると電車の持っている運動エネルギーはすべて熱として空気中に放散され電気を回収できなかった。電気を食う、無駄遣いの大きい電車であった。 もう一つは、直流モータは整流子とブラシという部品があり、整流子をブラシが常にこすっている(接触している)状態なので、ブラシが摩耗し、一定期間使うとブラシの交換が必要であった。ブラシは炭素棒や特殊な銅合金を使った。 現在のように過密ダイヤで電車を運行するためには、車両のメンテナンスが少ないほど都合がいい。そういう意味でもVVVFを使った同期交流モータはブラシや整流子がなく、非接触式なので摩耗する部分がないので、メンテナンスフリーとなっている。 さて、大人気のハイブリッド車ではどうなっているのか? 車はトロリー線(架線)がないので、その代わりにバッテリーを積んでいる。 プリウスやアクアと新型フィットを比べると、スペック上は大きな違いがある。《スペック比較は、7月11日の記事に掲載している≫ トヨタのハイブリッド車はモータ馬力が大きくアクアが61馬力、プリウスが 82馬力となっている。一方、新型フィットは30馬力である。これはスペック上の数字で、実際この馬力が出せるのかどうかは分からない。 ガソリンエンジンの場合は一応、スペックの馬力が出せると考えられる。 エンジンの出力はアクアが74馬力、プリウスが99馬力、新型フィットが110馬力となっている。ホンダの車はエンジン主体の考え方だ。 モータの出力(馬力)は電流が十分流せるという前提の数値である。 そうすると、搭載している電池がその電流を流せるか?ということになる。 トヨタのハイブリッド車の電池は、トヨタとPanasonicの合弁会社で造っていたニッケル水素電池を搭載している。 現在は、トヨタがこの会社を買い取った形になっている。 このニッケル水素電池は信頼性では高い実績があるが、電池1個当たりの電圧が低く1.2Vで、リチュウムイオン電池の3.6Vの1/3である。 トヨタはニッケル水素電池1.2Vを5個直列にしたものを一つのセル(単位)として1セルが6ボルト、これをプリウスは28本、アクアは24本直列につないで使用している。 電圧はプリウスが168V、アクアが144Vになる。 これに対して新型フィットは、1個3.6Vのリチュウムイオン電池を48個直列につなぎ173Vを得ている。新型アコードハイブリッドは72個つないで259Vという高電圧を得ている。 以上は電圧に関することであるが、電池には容量という問題もある。 容量とはどれだけの電力を溜められるかで、電流と電圧の積になる。 リチュウムイオン電池は、ニッケル水素電池に比べると、同じ大きさの電池なら、約2倍以上の容量があると言われている。 できるだけ車体を軽くしたいハイブリッド車の電池は今後、リチュウムイオン電池になる。だがリチュウムイオン電池はまだ歴史が浅く、製造ノウハウもこれからで、新材料開発がさらに進んでいるので、今後急速にその性能を改善すると考えられる。課題はリチュウムはレアメタルで非常に高価なこと。 今後、リチュウムイオン電池はコスト的にも、信頼性的にも、容量もさらなる大きな改善が進む。一方、ニッケル水素電池は今まで積み上げた実績の上に立っているので、これ以上の大きな改善はあまり望めない。 ここで重要なことは電池の性能は電圧や容量だけではないことだ! 電池には『内部抵抗』という電流を流すと、電池内部で熱に代わる電気抵抗分が存在する。この内部抵抗がゼロであれば理想の電池だが、そういう電池は存在しない。だから内部抵抗は小さいほど良い。 リチュウム電池は内部抵抗がニッケル水素電池に比べて小さいので、大きな電流が取り出せる。 もう一つ重要な要素に、車は加速したり減速したり繰り返すが、それに応じ瞬時に放電したり充電したりすることができる電池が理想的だ。 しかも、充放電回数による電池の劣化が少ないほど長寿命になる。そういう意味でもリチュウムイオン電池が優れている。 このように考えると、スペック上ではアクアが新型フィットのモータの約2倍の出力を持っているが、電池を含めたトータルシステムで、どういう出力特性を発生するのか、データが公表されていないので分からない。 車が動き出す時は軸を回転させる力、即ちトルク特性が重要になる。 スペックを比較すると、アクアが17.2に対して、新型フィットは16.3となっている。この値も、モータに十分電流を流した場合の値であり、電池の内部抵抗が大きくなると、この値は出ない。 モータ出力(馬力)は、モータに流す電流の大きさと、コイルの巻き数に比例する。 モータ出力 ∝ (モータの電流)×(コイルの巻き数) モータ電流を大きくするには太い(抵抗が少ない)電線をコイルに使うか、高い電圧をかければ電流が増える。 太い電線を巻くと形状が大きくなり重くなる。そこで適当な太さの電線にしなければならない。電圧をあげるには電池の端子電圧をインバータ回路を用いて高い電圧に変換してモータに加える方法がある。 プリウスの場合は168Vを最大650Vまで昇圧してモータに加えている。 新型フィットはいくらにしているか手元にデータがないので分からない。 高い電圧にするにはインバータが必要になるのと、昇圧回路でも発熱するので熱損失が発生する。 インバータに電流を供給できなければ負荷がかかった状態で十分な電圧が得られない。 モータ出力を強くする方法として、もう一つの要素であるコイルの巻き数を増やす方法はコイルの太さを細くして巻き数を増やせばいい。しかし細い線をたくさん巻くことはコイルの電気抵抗が増えて、電流が十分流れない。抵抗が増えるとコイルの発熱が増えるので、熱損失が増える。太い線で巻くとモータが大きくなり、重くなる。 このように、一方を良くすれば、一方が悪化するというトレードオフの関係になる。各メーカは一番バランスの良い点を求めて仕様を決めている。 ハイブリッド車はガソリンエンジンというメカニズムと、電気部品(モータとバッテリーとインバータ回路)の総合的な最良のバランスの上に立って、初めて高燃費(省エネ)が実現できる。開発には多額の資金がかかる。 車は重量を軽くすれば燃費や加速性能が良くなることは分かっている。 車体を軽くしながら衝突時の安全性や、運転性能、ハンドリングに優れる車を造ることは並大抵ではない。 世の中は、一方を立てれば、一方が悪くなるというトレードオフの関係になることが多い。むしろそういう関係でバランスが取れているようにも思える。 これから先の燃費は大発明がない限り、一気に大きく前進することが少なくなると思う。 しかし、少しずつ改善はまだまだ続く。 1リッターでどこまで走れるか? 今後の改善が楽しみだ! しかし、燃費はいいが、走りが悪い車はおもしろくない。 車は楽しく走れること!。 “Fan to drive” |
2013年7月21日(日)
新型フィットハイブリッドはアクアを越えた?
| フィット(ハイブリッド)はなかなかよくできた車だったが、燃費で、プリウスやアクアに大きく差をつけられ、トヨタの一人勝ちが続いてきた。 毎月の登録車ランキングはプリウスか、最近はアクアがトップを取っていた。 日本のユーザは『厳しく燃費を見ている!』ということが分かる。 ホンダは地団駄を踏んでいたに違いない!。 これが品質や性能にこだわる日本の市場である。 日本人の厳しいこだわりである。 スペックは0.1km/Lだって負けは負けだ。これがアメリカならどうだろうか? もっとおおらかであるが、彼らは車の大きさや値段には厳しい。 ホンダは苦節2年半、いよいよ『アクア』にリベンジする武器、新型フィットが発売される。新型フィットはフィット3というらしい。 発売前の新車情報は極秘で、なかなか手に入らなかった。 しかし、最近、車の雑誌や新聞やインターネットで新車情報が流れてくる。 予告宣伝という手法で、メーカが意識してルートに情報を小出しして流す。 事前の新車情報は下手をすれば現行品の販売の足を引っ張ることになる。 だからメーカは現行品の在庫管理をうまくやりくりしないと、在庫処分に多額の金が要る。その辺の管理が最近、コンピュータで日々の販売情報が把握できるので心配なくなったのだろう。 さて、最新情報によると、フィット3ハイブリッドは、1モーター、軽量コンパクトハイブリッドシステム「SPORT HYBRID Intelligent Dual Clutch Drive(i-DCD)」を新開発し搭載した。 このシステムは、同社の新世代パワートレイン技術「EARTH DREAMS TECHNOLOGY」の1つであり、1モーターでありながらエンジンとモーターを切り離して走ることができ、モーターのみのEV走行を実現している。 走行状況に応じて、モーターのみの「EVドライブ」、エンジンとモーターの「ハイブリッドドライブ」、エンジンのみの「エンジンドライブ」という3つの走行モードを自動的に選択する。 新開発エンジンは、直列4気筒1.5Lの燃費に優れたアトキンソンサイクル (高膨張比サイクル)エンジンを採用し、高出力モーター内蔵・7速DCTとリチウムイオンバッテリーを内蔵したIPU(インテリジェントパワーユニット)を組み合わせている。 さらに、電力回生効率を高める電動サーボブレーキシステムと、エンジン負荷を低減するフル電動コンプレッサーなどを採用し、従来のIMAハイブリッドシステムと比べて35%以上の燃費性能向上を達成した。 各車の比較表
フィット3の燃費は、36.4km/リッター。 アクアが35.4km/リッター、アクアを1km上回った。 このレベルになると、技術的に飽和してくるので、今後、大幅な改善はむずかしくなるが、40km/L当たりが限界か? それ以上改善するには、現在のエンジンと違った燃費効率のいい新しいエンジンが生まれなければ難しいのではないか?。 燃費性能と走りの楽しさの両立ができないと単なる低燃費車になる。 モタモタした走りでは、おもしろくない。 問題はスペック数値と実燃費(実際使用した時の燃費)の差が大きくかい離することがあり、最近の燃費競争で問題になっている。 従来の10モード燃費は、実燃費とのかい離が大きすぎたので、JC08燃費モードが新しく制定された。これでもまだ実燃費より悪い。 理由はいろいろあるが、スペック上の燃費は、エアコンやその他の電装品などを使わないで、平坦な道を走った場合の値で、実際は道路の起伏や、エアコンをつけ、カーナビやカーオーディオを付け、ランプを点灯するので、その分、ガソリン消費されることになる。 メーカによって、スペック燃費と実燃費の比率がまちまちで、ホンダの場合はスペックの70%~75%ぐらいだそうだ。 現在使っているフィットハイブリッドは、街中だけの走行は16km/L位で、高速道路を走ると21km/L位になる。 燃費計では19~20km/Lを示している。 さて、フィット3はアクアを追い越した。 アクアも負けていられないので次期アクアは新型フィットを上回るスペックを出すだろう。トヨタのハイブリッドシステムは2モータ方式で、電池はニッケル水素を積んでいる。間違いなく次期のアクアはリチュウムイオン電池にするはずだ。 リチュウムイオン電池は、ニッケル水素電池に比べると、充電、放電する際に 電流を流れにくくする電池の内部抵抗が小さいので、大きな電流を流せる。 電池の内部抵抗が小さいと、充放電する際の発熱が減り、発進する際にモータに大きな電流が流せるので、モータのトルク(力)が強くなり加速が良くなる。 また、ブレーキング時に回生発電した電気を電池に大量に流し込めるので、充電効率が良くなる。 今後はハイブリッド車の電池はリチュムイオン電池に変わる。 ホンダは自前でリチュウムイオン電池の生産を行っている。ユアサバッテリーと共同出資した『ブルーエナジー社』で生産を始めている。 しかし、燃費の改善という意味では、今後、一気に3km、5kmという差がつかなくなるはずだ。0.1kmでも上回ればトップ燃費という宣伝ができる。そうなると、実燃費が重要になる。果してフィット3の実燃費はいくらになるか?   発表されている新型フィット3、なかなか精悍な顔つきとスポーティなボディだ。 9月に発売されるこの車は間違いなく売れる。 なぜなら、いままでフィットがアクアやプリウスに負い目にしていた点を完全に払しょくしたから。 フィットは室内の広さや、頭上の空間等は今までも他を圧倒していた。走り自体も悪くない。アクアやプリウスに負けていたのは燃費。 それと、エアコンがアイドリングストップした際に停まること。これは真夏に信号待ちしていると、エンジンストップする度にエアコンが止まってしまう。 エンジンにベルトをかけてエアコンのコンプレッサーを回していたのだから仕方ない。長い信号待ちでは室内の気温が上がり、いやな思いをしていた。 アイドルストップを強制的に止める(エンジンを止めない)には、信号待ちの度にシフトレバーをLレンジに入れなければならない。これは実にどぐさい! この点、プリウスやアクアは電動式で、コンプレッサーをモータで回したので、アイドルストップしてもエアコンは通常どおり働いている。 そういう点でもトヨタの技術力は先進的だった! だから売れたのだ!。 新型フィットは、この二つの負けていた点を解決しクリアし、さらに上回った。 プリウス(先代の1500CC)に乗ってみたが、発進時はモタモタとして、『これがハイブリッド車の走りか?』 と思った。スーッと気持ちよく走り出さない。 その点、先般試乗した新型アコードハイブリッドの走りは、今までどの車でも経験したことがない素晴らしい静かさと加速であった。 新型フィットがどれだけアコードに近づけているか? そういう爽快な走りができるなら、プリウスやアクアを凌駕できると思う。 |
2013年6月29日(土)
ホンダのHV戦略、次の矢は何か?
本命は、新型フィット!
| ホンダは『Sport HYBRIDシステム』という名で、3種類のHVシステムを開発済み。 ①3モータ搭載;SH-AWD 大型、高級車用、 レジェンドなど ②2モータ搭載;i-MMD アッパーミドル車用、新型アコードなど ③1モータ搭載;i-DCR 小型、量販車用、新型フィットなど この3つのHVシステムを車体に合わせて搭載し、商品展開する。 トヨタのHVシステム(THS)を上回る低燃費と加速の良さを実現する。 9月に、新型フィット発売。これはアクアをしのぐ燃費になる。 |
| 最近、自動車業界は、変調をきたしている。 軽自動車が思ったより良く売れ出した。自動車の販売ランキング10の中に半分以上、軽自動車になっている。今や車の中核的な存在になってきた。 売れる車と、そうでない車が極端に大きな差になってきた。 自動車会社は『軽』を看過できない状態になっている。 軽自動車と言えば、辺ぴな田舎の生活を支える移動手段、足として使われてきた。それが性能が向上し、小さいことが街中でチョイ乗りに便利ということで、東京都内でも良く売れるようになっている。さらに燃費も良くなり、価格的にも、維持費も極端に安いので、手に入れやすい。 長距離の移動には、相変わらずつらい面はあるが、以前の『軽』とは全く違った車になってきた。 普通車も一皮、二皮剥かないと、『軽』に食い荒らされるだろう! 軽自動車は日本だけの特例の規格車であり、いろんな面で優遇されている。 特に、税金、保険が普通車に比べて大幅に安いので、維持費が助かる。 日本がデフレで、経済が縮小する中で、価格が安く、維持費が安い『軽』が伸びるのは当然だが、自動車会社は厳しいコスト競争を余儀なくされる。 軽自動車のトップはダイハツとスズキ。これにホンダが急激に伸びてきた。 三菱、日産も共同で新型の『軽』を開発し、本格的に参入を図った。ますます激しい競争に入る。 もう一つの悩みは、若者の車離れ。これは大変深刻な問題である。 スマホやi-Padなどに小遣いを叩いているので、なかなか車を買うまで金が回らないのかもしれない。 イヤ、お金の問題ではないという意見もある。草食化した男性は車を使って、彼女をものにするという発想がないのかもしれない。そういえば、最近、やたらと飛ばして走る車や、ガンガン音楽を鳴らして走る車を余り見なくなった。 今もなお、極くわずか、マフラーを替えて排気音を大きくした車があるが、その数は以前に比べると、極端に少なくなった。 そういうところにも、若者の車離れが現れているような気がする。 話が逸れたが、これから新しい車がドンドン出てくるようなので、車好きにとっては目が離せない。 |
2013年6月28日(金)
新型アコードと、プリウスの違いは何か?
  新型アコード カムリ 新型アコードに試乗した感想は、下記ページを見て下さい。 ここではハイブリッドカーの代名詞となった『プリウス』とそれに挑戦? した新型アコードについて、触れてみる。 プリウスは、200万円+αの庶民向けの車であり、新型アコードは360万円以上のハイミドル(中高級)クラスに入る車なので、その造りは大きく違う。 ここではハイブリッドシステムの違いについて述べる。 新型アコードは、トヨタのカムリが競合車種になる。 車はガソリンと言う化石燃料が持つ「熱」エネルギーを「力」エネルギーに変換し駆動力を得て走る。この時のエネルギー変換効率をどうして高めるか?が課題であり競争である。 今までは吸気弁や排気弁のタイミングを変えて最適化したり、燃料噴射をキャブレターから電子燃料噴射装置に替えたり、軸受けやピストンリングの摩擦など減らしてロスを削減したりエンジンを工夫し、燃費効率向上を図ってきた。 単なる効率化なら比較的造りやすいが、車はドライバーが『気持ちよく運転できた』と言う感じを持つことが大切なので、加速のスムーズさや、運転のしやすさなど、いろんな項目を同時に満たす必要がある。 一時、ロータリーエンジンで気を吐いたマツダは、エンジンそのものに着目し、エンジンの改良を徹底して行い、従来のエンジンのままで低燃費や排ガスの低減や高出力を実現することに成功した。 エンジンはまだまだ改良の余地があるというのがマツダの考え方だ。 この新しいエンジンをマツダは『スカイアクティブテクノロジー』と名付けて、ガソリンエンジンとジーゼルエンジンの二種を開発した。素晴らしいこと。 特に、ジーゼルエンジンは発想を転換し、圧縮比を従来の20以上から14~15に大幅に下げることで、振動、排ガス、低燃費を両立させた。 すごいの一言。世界が注目している。 ガソリンエンジンについては、逆に圧縮比を10前後から14ぐらいまで高めて、高出力、低燃費を実現することに成功した。 一方、ガソリンエンジンの特性を生かしながら、モータをうまく組み合わせることで、ガソリンエンジンの不得手の部分をカバーしようと考えたのが、HV(ハイブリッドシステム)と言える。 HVは蓄電池を積むことで、今までブレーキをかけた際に摩擦熱として逃がしていた運動エネルギーを電気エネルギーとして回収し電池に蓄え、これを発進や走行時に使うもの。その分、ガソリンの使用が削減でき、低燃費と排ガスを減らせる。 HVはエンジンとモータと蓄電池と、それらを最適にコントロールする制御回路システムが必要になる。 モータとエンジンはその特性を生かし最適状態で使用することで、低燃費や排ガス規制を満たしつつ、運転の楽しさを体感できるようになってきた。 日産自動車は、これらの開発に少し遅れた。現状でこれだ!と言う新しい技術は発表されていない。 スバルはホンダのフィットHVと同様なHVシステムを搭載した車を発売したが、この方式は電動自転車と同じ理屈で、ペダルをこぐ力が軽くなることで、エンジンの負荷を下げて、ガソリン消費を減らすというものだ。 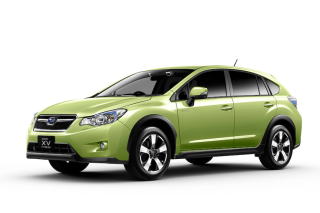 スバル XVハイブリッド スバル XVハイブリッドこの方式のHVシステムは比較的簡単に実現できるが、徹底した低燃費は実現できない。クランクシャフトにモータ(発電機)を直結させ、発進時にモータでエンジンをアシストする。ブレーキ時はモータが発電機になり、電池に充電する。この時もエンジンは回るので、ロスが大きく回生発電量が減ることになる。また、モータのパワーも小さく、モータだけで発進はできない。 スバルは2000ccのエンジンに、このHVシステムを搭載した。 しかし、小型エンジンの場合はもともと低燃費なので、フィットHVのように15km/L~20Km/L程度の燃費性能は可能になる。 究極の低燃費を得るには、HVの代名詞となったプリウス方式を使わざるを得ないのか? 2つのモータとエンジンで構成し複雑な制御をしながら、エンジンとモータを最適制御する。その上で、機械的ロスを最小にすることが必要になる。 車の駆動部はエンジン、モータ、歯車(ギヤー)、動力分割機構、クラッチ、軸受けなど多数の部品で複雑な構成となっている。 モータやエンジンで発生したトルク(回転力)をロスなくタイヤに伝え、タイヤの運動エネルギーをロスなく発電機に伝え、効率よく電気エネルギーに変換することが低燃費を実現する上で条件になる。 さらに、車両の軽量化、空気抵抗の低減など、車体全体のロスを削減することで究極の低燃費が実現できる。
新型アコードは、発進、走行は強力なモータで行い、リチュウム電池の充電量が無くなってくればエンジンがかかり、発電用モータ(発電機)が回り、リチュウムイオン電池に充電しながら、エンジン⇒発電機⇒電池⇒モータという直列的(シリーズ)な関係になる。ここが大きく違う点である。大きな加速を要する時はエンジンがかかり、モータとエンジンの両方で駆動する。 簡単に言えば、アコードは走行用モータで走る。走行用モータは馬力が強い。一種のEV車である。 プラグインハイブリッド車はアコードの電池容量を大きくして、電池での走行距離を長くしたもの。 電池容量が足りなくなればエンジンがかかり、発電機を回し、その電気で走行用モータを回す。エンジンは発電機を回すためにある一方、高速道路を一定の速度で走る時は、エンジンだけで走る。 プリウスのような複雑な動力分割機構は持っていない。 高速道路で運転する場合、プリウスはエンジン、モータの協調制御でうまく切り替える。新型アコードは、一定速度で高速運転する場合は基本的にはエンジン直結で動作する。モータはお休みとなる。 トランスミッションやCVTは使っていない。ここの考え方も大きく違う。 高速道路で減速したり、加速したりする場合は、両車ともエンジンとモータの協調制御が行われる。 減速、ブレーキング時の動作は、両車とも走行用モータが発電機になり回生電気をバッテリーに充電する。 新型アコードはブレーキペダルを踏むと、その踏込量を電気信号に変換し、その信号がHV制御回路につながり、回生発電により電池に充電することでブレーキがかかるが、停止直前は油圧ブレーキで停車する。 ブレーキペダルから油圧管が無くなり、電気配線で制御回路を通じて、ブレーキ用モータにつながっている。これにより、ブレーキ時の回生電気量を高めて充電を多くすることに成功した。 こう見てくると、さすが巨人であるトヨタはプリウスをいち早く完成させ、複雑なHVシステムで多数の特許を取得したことが分かる。しかし、その特許は期限切れになる。各社は新しいHVシステムを開発中と思われるが、その基本になっているのはやはり、プリウスだった。 プリウスがHV車の代名詞となったことがよく分かる。 一方で、プリウスは超低燃費に成功したが、『HV車の走りはこういうものだ』という感覚を植え付けてしまった。プリウスによって、車を走らせる面白さを無くしたことも事実である。そういう人は、ドイツ車などに乗っている。 その点を突いて、車の操る楽しみを目指したのが新型アコードだと思う。 これからドンドン新しいHV車が発売されるが、低燃費はそろそろ卒業して、 Fan to Drive! にふさわしいHV車が登場することを期待している。 |